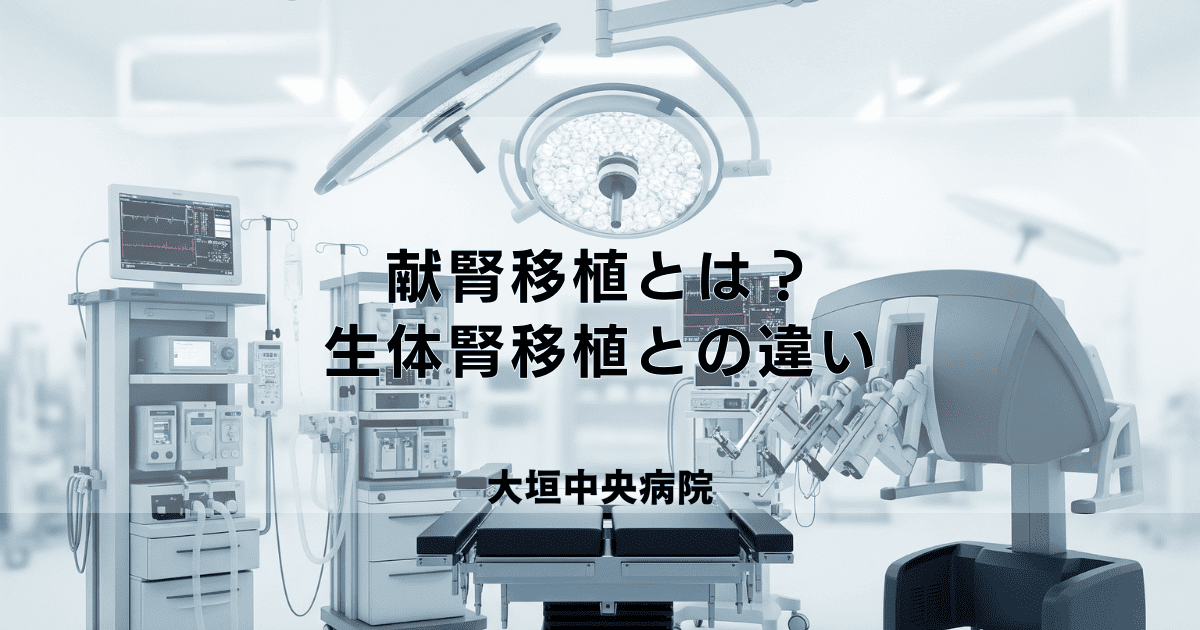腎不全と向き合う日々の中で、腎臓移植は大きな希望となり得ます。選択肢の一つである献腎移植は、亡くなった方の尊い意思によって成り立つ医療ですが、詳細については、まだ広く知られてません。
この記事では、献腎移植の基本的な知識から、生体腎移植との違い、長い待機期間の現実、そしてドナー登録の仕組みに至るまで、皆さまが抱えるであろう疑問や不安に、一つひとつお答えしていきます。
献腎移植の基本的な知識
腎臓移植という言葉を聞いたことがあっても、献腎移植がどのようなものかご存じの方は少ないかもしれません。まずは、この移植医療の根本的な部分から理解を深めていきましょう。
献腎移植の概要
献腎移植とは、亡くなった方(ドナー)から提供された腎臓を、慢性腎不全の患者さんに移植する治療法です。
日本では、臓器の移植に関する法律に基づき、ご本人が生前に臓器提供の意思を示している場合、またはご家族が提供を承諾した場合に限り、移植が行われます。
提供される腎臓は、日本臓器移植ネットワーク(JOTNW)を通じて、待機リストに登録されている患者さんの中から、医学的な適合性や緊急度などを基に公平に選ばれた方に移植されます。
この方法は、自分では腎臓を提供してくれる家族(ドナー)がいない患者さんにとって、唯一の腎臓移植の道です。
腎臓の主な働き
- 老廃物の排泄
- 体内の水分量調整
- 血圧のコントロール
- ホルモンの産生
腎臓移植が必要になる背景
私たちの体にある腎臓は、血液をろ過して老廃物や余分な水分を尿として排泄する、生命維持に欠かせない臓器です。しかし、糖尿病や高血圧、慢性腎炎などの病気が原因で腎臓の機能が著しく低下すると、末期腎不全という状態に陥ります。
自分の腎臓だけでは生命を維持できなくなり、透析療法か腎臓移植のどちらかの腎代替療法を選択する必要が出てきます。
透析療法は、機械を使って血液を浄化する方法ですが、時間的な制約や食事制限など、生活に大きな影響を及ぼすことがあります。一方、腎臓移植が成功すれば、透析から離脱し、より自由度の高い生活を送ることが期待できます。
献腎移植は、このような状況にある患者さんにとって、生活の質を大きく向上させる可能性を秘めた治療法なのです。
献腎移植の歴史と現状
日本の腎臓移植は1964年に始まりましたが、献腎移植が本格的に行われるようになったのは、1997年に臓器移植法が施行されてからです。この法律により、脳死状態からの臓器提供が可能になりました。
しかし、海外と比較すると、日本の臓器提供数は依然として少ないのが現状です。このため、献腎移植を希望して日本臓器移植ネットワークに登録してから、実際に移植を受けられるまでの待機期間は非常に長くなっています。
近年、少しずつ臓器提供への理解は広まりつつありますが、多くの患者さんが移植を待ち望んでいるという現実があります。長い待機期間が、献腎移植における大きな課題の一つです。
日本の腎臓移植の現状
| 項目 | 説明 | 近年の傾向 |
|---|---|---|
| 年間移植数 | 生体腎移植が献腎移植を大きく上回る | 微増傾向 |
| 待機者数 | 約14,000人以上が待機リストに登録 | 増加傾向 |
| 平均待機期間 | 約15年以上 | 長期化傾向 |
生体腎移植との根本的な違い
腎臓移植には、献腎移植のほかに生体腎移植があります。どちらも腎機能を回復させるための治療法ですが、背景や手順には大きな違いがあります。
ドナー(腎臓提供者)の相違点
最も根本的な違いは、腎臓を提供するドナーが誰かという点です。生体腎移植では、健康な親族(配偶者、6親等以内の血族、3親等以内の姻族)から、2つある腎臓のうちの1つを提供してもらいます。
ドナーは手術後腎臓が1つになりますが、健康状態に問題がなければ、日常生活に大きな支障はありません。
献腎移植のドナーは亡くなった方です。生体腎移植はドナーとなってくれる家族がいることが前提ですが、献腎移植はドナーがいない方でも移植の機会を得られるという点が大きく異なります。
ドナーの比較
| 移植の種類 | ドナー | ドナーの条件 |
|---|---|---|
| 生体腎移植 | 健康な親族 | 原則65歳未満、医学的・倫理的な審査を通過 |
| 献腎移植 | 亡くなった方 | 本人の意思表示または家族の承諾 |
手術計画の立てやすさ
生体腎移植は、ドナーと患者さん(レシピエント)双方の体調が良い時期を選んで、計画的に手術日を設定でき、手術に向けた心身の準備を十分に行うことが可能です。仕事の調整や家族のサポート体制なども、事前に整えやすいでしょう。
対して、献腎移植は、いつドナーが現れるか予測ができません。日本臓器移植ネットワークから連絡が来た場合、患者さんは速やかに入院し、手術を受ける必要があります。
深夜や早朝に連絡が来ることも珍しくなく、常に準備を整えておく心構えが大事になり、この計画性の違いは、患者さんやご家族の生活にも影響を与える点です。
移植腎の生着率と待機期間
生着率とは、移植された腎臓が機能し続けている割合を示す指標です。一般的に、生体腎移植の方が献腎移植よりも生着率はやや高い傾向にあります。
生体腎移植ではドナーと患者さんの適合性を事前に詳しく調べられることや、腎臓を摘出してから移植するまでの時間が短いことなどが理由として挙げられますが、近年の医療技術の進歩により、献腎移植の生着率も大きく向上しています。
待機期間については、生体腎移植はドナーが見つかれば比較的早期に手術が可能ですが、献腎移植は平均で15年以上という非常に長い待機が必要です。
移植方法による主な違いのまとめ
| 項目 | 生体腎移植 | 献腎移植 |
|---|---|---|
| 計画性 | 計画的に手術日を設定可能 | ドナー発生時に緊急で行う |
| 待機期間 | 比較的短い | 非常に長い(平均15年以上) |
| 生着率 | 献腎移植よりやや高い傾向 | 向上しているが、生体腎移植に及ばない場合がある |
献腎移植のドナーについて
献腎移植は、ドナーとなる方の尊い意思がなければ成り立ちません。ここでは、どのような方がドナーになれるのか、そしてドナーの意思がどのように尊重されるのかについて詳しく見ていきます。
どのような方がドナーになれるのか
臓器提供ができるのは、厳しい医学的な基準を満たした方に限られます。
提供できる年齢に上限はありませんが、がんや全身性の感染症など、移植を受ける患者さんに影響を及ぼす可能性のある病気を持っている場合は、提供が難しいことがあります。
提供される臓器が正常に機能しているかどうかが、最も重要な判断基準です。最終的には、専門の医師が医学的な検査結果を基に、一つひとつの臓器が移植に適しているかを慎重に判断します。
脳死と心停止後での違い
献腎移植のドナーは、脳死と判定された方と、心臓が停止した後に亡くなった方の2通りに分けられます。
脳死とは、脳全体の機能が失われ、回復不能な状態のことで、人工呼吸器などによって心臓は動いていますが、自力で呼吸することはできません。
脳死ドナーからは、心臓が動いている状態で臓器を摘出するため、腎臓を含む複数の臓器提供が可能です。一方、心停止後の提供では、心臓が止まってから臓器を摘出します。
この場合、血流が途絶えるため、提供できる臓器は腎臓や膵臓、眼球などに限られます。日本の献腎移植では、心停止後のドナーからの提供が比較的多い状況です。
脳死ドナーと心停止後ドナーの比較
| 項目 | 脳死ドナー | 心停止後ドナー |
|---|---|---|
| 定義 | 脳全体の機能が回復不能な停止状態 | 心臓が停止した後の死亡 |
| 提供可能な主な臓器 | 心臓、肺、肝臓、腎臓など多数 | 腎臓、膵臓、眼球など |
| 腎臓の状態 | 血流が保たれているため良好 | 血流停止による影響を受ける可能性 |
ドナーの意思表示の重要性
臓器提供は、本人の意思が最も尊重され、臓器を提供する意思があるかどうかを示す方法はいくつかあります。
健康保険証や運転免許証、マイナンバーカードの裏面にある意思表示欄への記入や、インターネットによる意思登録、臓器提供意思表示カード(ドナーカード)への記入です。本人の意思が不明な場合でも、家族の承諾があれば臓器提供はできます。
しかし、残された家族が突然、重い決断を迫られることは大きな負担となるため、生前から臓器提供について考え、家族と話し合い、自分の意思を何らかの形で示しておくことがとても大切です。
意思表示の方法
- 健康保険証の意思表示欄
- 運転免許証の意思表示欄
- マイナンバーカードの意思表示欄
- 臓器提供意思登録サイト
- 臓器提供意思表示カード
献腎移植の待機登録
献腎移植を受けるためには、日本臓器移植ネットワーク(JOTNW)の待機リストに登録することが第一歩です。ここでは、登録の手順や必要な条件について、解説します。
待機リストへの登録手順
献腎移植を希望する場合、まずは現在治療を受けている病院の主治医に相談します。その後、移植医療を行っている病院(移植施設)を紹介してもらい、詳しい説明と検査を受けます。
移植が医学的に可能であると判断されると、移植施設を通じて日本臓器移植ネットワークに新規登録の申請を行います。申請が受理されると、正式に待機リストに登録され、献腎移植を待つことになります。
登録後は、年に1回、登録を継続するための更新手続きが必要です。
待機登録の主な流れ
| 手順 | 内容 | 場所 |
|---|---|---|
| 相談 | 主治医に献腎移植希望の意思を伝える | かかりつけの病院 |
| 受診・検査 | 移植の適応を判断するための精密検査 | 移植施設 |
| 申請・登録 | 移植施設を通じてJOTNWへ申請 | 移植施設・JOTNW |
登録に必要な条件と検査
待機リストに登録するためには、いくつかの条件を満たす必要があります。まず、透析療法を受けているか、近い将来に透析導入が見込まれる末期腎不全の患者さんであることが前提です。
また、全身状態が移植手術に耐えられること、悪性腫瘍や活動性の感染症がないことなども重要な条件となります。
登録前には、条件を満たしているかを確認するために、血液検査、尿検査、胸部X線、心電図、腹部超音波検査など、全身にわたる詳細な検査が行われます。
登録施設の選び方
献腎移植の待機登録は、全国にある移植施設の中から1か所を選んで行います。自宅からの距離や交通の便、施設の移植実績などを考慮して選ぶことが一般的です。
ドナー発生の連絡は突然入るため、すぐに駆けつけられる範囲の施設を選ぶことが望ましいでしょう。
また、施設によって移植に対する考え方や方針が異なる場合もあるため、事前に説明会に参加したり、資料を取り寄せたりして、納得のいく施設を選ぶことが大切です。登録する施設は後から変更することも可能ですが、手続きが必要になります。
登録内容の更新について
待機リストへの登録は、一度行えば終わりではありません。年に1回、登録を継続するための更新手続きが求められ、更新時には、現在の健康状態を確認するための検査結果などを移植施設に提出します。
また、住所や連絡先が変わった場合や、体の状態に大きな変化があった場合は、その都度、速やかに移植施設に連絡を入れることが大事です。正確な情報が登録されていることが、いざという時にスムーズに連絡を受けるための鍵となります。
長い待機期間と過ごし方
献腎移植を希望する上で、避けては通れないのが長い待機期間です。この期間をどのように過ごすかは、心身の健康を維持し、万全の状態で移植に臨むために非常に重要です。
日本における平均待機期間
日本における献腎移植の平均待機期間は、約15年(2023年時点)と非常に長いのが現状です。これは、献腎移植を希望する待機者の数に対して、臓器提供(ドネーション)の数が圧倒的に少ないために起こります。
血液型や組織適合性(HLA)のタイプによっては、さらに長い期間を要することもあります。
待機期間中の健康管理
いつドナー発生の連絡が来ても良いように、待機期間中は透析治療をきちんと受け、最良の健康状態を維持することが何よりも大切です。食事療法や水分管理、適度な運動を心がけ、体重をコントロールすることも求められます。
特に、感染症や心血管系の合併症を予防することは重要です。定期的に移植施設で検査を受け、良好な健康状態を保つことが、移植のチャンスを最大限に活かし、手術の成功率を高めることにつながります。
待機中の健康管理のポイント
| 項目 | 具体的な内容 | 目的 |
|---|---|---|
| 透析療法 | 指示通りにきちんと受ける | 体内の老廃物除去、体液バランスの維持 |
| 食事・水分管理 | 塩分、カリウム、リンなどの制限を守る | 合併症の予防、体重コントロール |
| 自己管理 | 禁煙、節酒、定期的な運動 | 心血管系疾患のリスク低減 |
待機中の精神的なサポート
いつ終わるとも知れない長い待機期間は、患者さんにとって精神的に大きな負担となることがあります。希望と不安の間で気持ちが揺れ動くこともあるでしょう。
このような時は、一人で抱え込まず、家族や友人、主治医、移植コーディネーターなどに気持ちを打ち明けることが大切です。
また、同じように移植を待つ患者さんたちの会に参加し、情報交換をしたり、悩みを共有したりすることも、大きな支えになります。
待機期間を左右する要因
献腎移植のドナーが現れた際、誰に移植されるかは、医学的な基準に基づいて公平に選ばれます。主な要因は、血液型(ABO式)と組織適合性抗原(HLA)の適合度、待機期間の長さ、レシピエントとドナーの地理的な距離などです。
HLAの適合度が高いほど、移植後の拒絶反応のリスクが低くなるため、優先順位が高くなり、また、待機期間が長いほどポイントが加算される仕組みになっています。
移植の優先順位を決める主な要因
- 血液型の一致
- 組織適合性(HLA)の適合度
- 待機日数
- 地理的条件(距離)
献腎移植の手術と術後
長い待機期間を経て、ついに移植の機会が訪れた時、どのような流れで手術が行われ、術後はどのような生活が待っているのでしょうか。ここでは、手術当日から退院後までの道のりについて解説します。
ドナー発生から移植手術までの流れ
移植施設からドナー発生の連絡が入ったら、指定された時間までに病院へ向かいます。病院に到着後、移植手術が可能かどうかを最終的に判断するための検査が行われます。並行して、ドナーから摘出された腎臓が移植施設へ搬送されます。
すべての準備が整い、医学的に問題がないと判断されたら、移植手術が開始されます。この一連の流れは非常に迅速に進められるため、事前の準備と心構えが重要です。
移植手術当日のタイムライン(一例)
| 時間 | 内容 | 場所 |
|---|---|---|
| 連絡時 | 移植施設から電話連絡、来院指示 | 自宅など |
| 来院後 | 最終的な適合性検査、術前準備 | 移植施設 |
| 手術開始 | 全身麻酔下で移植手術を行う | 手術室 |
移植手術の具体的な内容
移植手術は全身麻酔をかけて行われ、通常3時間から5時間程度です。手術では、下腹部の右か左を大きく切開し、提供された腎臓を骨盤内に配置します。
新しい腎臓の動脈と静脈を、患者さんの足へ向かう血管(腸骨動脈・静脈)につなぎ、血流を再開させ、その後、新しい腎臓の尿管を膀胱につなぎます。
多くの場合、機能しなくなった自分自身の腎臓は、特に問題がなければ摘出せずにそのまま残しておきます。血流が再開されると、新しい腎臓はすぐに尿を作り始めます。
入院期間と術後の生活
手術後の入院期間は、経過が順調であれば約1か月から2か月程度です。入院中は、拒絶反応や感染症などの合併症が起こらないか、注意深く経過を観察します。
また、生涯にわたって服用が必要な免疫抑制剤の調整や、自己管理の方法について指導を受けます。退院後は、定期的な通院が必要ですが、透析治療からは解放され、食事や水分の制限も大幅に緩和されます。
多くの方が、学業や仕事に復帰し、旅行やスポーツを楽しむなど、活動的な生活を取り戻しています。
術後の主な注意点
- 免疫抑制剤の確実な服用
- 感染症の予防(手洗い、うがい、人混みを避ける)
- 定期的な通院と検査
- 血圧や体重の管理
免疫抑制剤との付き合い方
移植された腎臓は、自分のものではないため、体の免疫機能が異物とみなして攻撃しようとします。これが拒絶反応です。拒絶反応を防ぐために、免疫の働きを抑える免疫抑制剤を毎日服用する必要があり、生涯にわたって飲み続けます。
飲み忘れたり、自己判断で量を減らしたりすると、急性の拒絶反応が起こり、せっかく移植した腎臓を失うことにもなりかねません。
免疫抑制剤には、感染症にかかりやすくなるなどの副作用もありますが、医師の指示に従って正しく服用し、体調管理を行うことで、リスクを最小限に抑えることが可能です。
献腎移植に関するよくある質問
最後に、献腎移植に関して多くの方が抱く疑問について、Q&A形式でお答えします。ここに記載されていること以外にも、不安や疑問があれば、主治医や移植コーディネーターに相談してください。
- 費用はどのくらいかかりますか
-
腎臓移植の手術や入院にかかる医療費は非常に高額ですが、大部分は公的医療保険でカバーされます。
さらに、特定疾病療養受療制度や自立支援医療(更生医療)などの公的な助成制度を利用することで、自己負担額を大幅に軽減できます。
ただし、制度の利用には申請が必要なため、事前に病院のソーシャルワーカーや市区町村の担当窓口に相談しておくことが大切です。
- 誰でもドナー登録できますか
-
献腎移植を受けるための待機登録には、医学的な適応基準があります。基本的には、末期腎不全で、全身状態が移植手術に耐えられると判断された方が対象です。
年齢の上限は明確には定められていませんが、一般的には65歳くらいまでが望ましいとされています。
ただし、年齢だけでなく、心臓や肺などの機能、合併症の有無などを総合的に評価して、一人ひとり個別に登録の可否が判断されます。
- 移植後、食事制限はありますか
-
移植が成功し、腎機能が安定すれば、透析中に行っていた厳しい食事制限(カリウム、リン、塩分、水分など)は大幅に緩和されます。基本的には、健康な人と同じような食事を楽しむことができます。
ただし、免疫抑制剤の副作用で高血圧や糖尿病、脂質異常症などが起こりやすくなるため、塩分や糖分、脂肪分の摂りすぎには注意が必要です。
また、グレープフルーツなど、一部の免疫抑制剤の効果に影響を与える食品は避ける必要があります。栄養士の指導を受けながら、バランスの取れた食生活を心がけることが大切です。
- 献腎移植と生体腎移植、どちらが良いですか
-
これは非常に難しい問題であり、一概にどちらが良いと言えるものではありません。
生体腎移植は、計画的に手術ができ、生着率も高いという利点がありますが、健康な家族の体にメスを入れるという倫理的な課題や、ドナーへの身体的・精神的負担が伴います。
献腎移植は、家族に負担をかけずに済みますが、いつ受けられるか分からない長い待機期間という大きな壁があります。
それぞれのメリットとデメリットをよく理解した上で、ご自身の価値観やご家族の状況などを総合的に考慮し、主治医や家族と十分に話し合って決めることが重要です。
以上
参考文献
Aikawa A. Current status and future aspects of kidney transplantation in Japan. Renal Replacement Therapy. 2018 Nov 28;4(1):50.
Aida N, Ito T, Kurihara K, Naka Mieno M, Nakagawa Y, Kenmochi T. Analysis of risk factors for donation after circulatory death kidney transplantation in Japan. Clinical and Experimental Nephrology. 2022 Jan;26(1):86-94.
Yagisawa T, Mieno M, Ichimaru N, Morita K, Nakamura M, Hotta K, Kenmochi T, Yuzawa K. Trends of kidney transplantation in Japan in 2018: data from the kidney transplant registry. Renal Replacement Therapy. 2019 Dec;5(1):1-4.
Egawa H, Tanabe K, Fukushima N, Date H, Sugitani A, Haga H. Current status of organ transplantation in Japan. American journal of transplantation. 2012 Mar 1;12(3):523-30.
Okamoto M, Akioka K, Nobori S, Ushigome H, Kozaki K, Kaihara S, Yoshimura N. Short-and long-term donor outcomes after kidney donation: analysis of 601 cases over a 35-year period at Japanese single center. Transplantation. 2009 Feb 15;87(3):419-23.
Imamura R, Nakazawa S, Yamanaka K, Kakuta Y, Tsutahara K, Taniguchi A, Kawamura M, Kato T, Abe T, Uemura M, Takao T. Cumulative cancer incidence and mortality after kidney transplantation in Japan: a long‐term multicenter cohort study. Cancer Medicine. 2021 Apr;10(7):2205-15.
Okumi M, Unagami K, Kakuta Y, Ochi A, Takagi T, Ishida H, Tanabe K, Japan Academic Consortium of Kidney Transplantation (JACK), Inui M, Toki D, Toma H. Elderly living donor kidney transplantation allows worthwhile outcomes: the Japan Academic Consortium of Kidney Transplantation study. International Journal of Urology. 2017 Dec;24(12):833-40.
Takahashi K, Saito K, Takahara S, Okuyama A, Tanabe K, Toma H, Uchida K, Hasegawa A, Yoshimura N, Kamiryo Y. Excellent long-term outcome of ABO-incompatible living donor kidney transplantation in Japan. American journal of transplantation. 2004 Jul 1;4(7):1089-96.
Teraoka S, Nomoto K, Kikuchi K, Hirano T, Satomi S, Hasegawa A, Uchida K, Akiyama T, Tanaka S, Babazona T, Shindo K. Outcomes of kidney transplants from non-heart-beating deceased donors as reported to the Japan Organ Transplant Network from April 1995-December 2003: a multi-center report. Clinical transplants. 2004 Jan 1:91-102.
Nakagawa Y, Ikeda M, Ando T, Tasaki M, Saito K, Takahashi K, Aikawa A, Kikuchi M, Akazawa K, Tomita Y. Re-evaluating cut-off points for the expansion of deceased donor criteria for kidney transplantation in Japan. InTransplantation Proceedings 2017 Jan 1 (Vol. 49, No. 1, pp. 10-15). Elsevier.