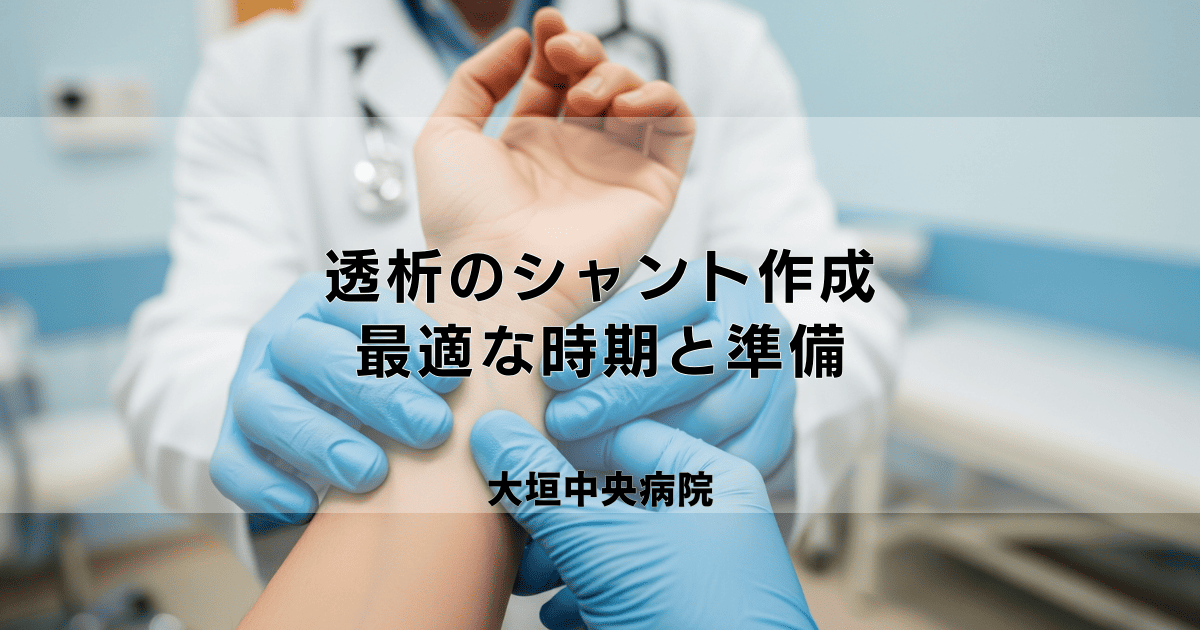腎臓の機能が低下し、医師から将来的に透析治療が必要になるかもしれないと告げられたとき、多くの方が大きな不安を感じるでしょう。
バスキュラーアクセスやシャント作成手術という言葉を初めて聞くと、何をするのか、いつ手術を受けるべきなのか、さまざまな疑問が心に浮かぶはずです。
この記事では、血液透析治療に欠かせないバスキュラーアクセス、その中でも代表的な自己血管内シャント作成手術について、役割から手術の適切な時期、手術に向けた心と体の準備まで、解説します。
バスキュラーアクセスとは?透析治療における役割
血液透析を始めるにあたり、まず理解しておきたいのがバスキュラーアクセスの存在です。
これは、透析治療のたびに、体の血液をダイアライザーと呼ばれる人工の腎臓へ送り、きれいになった血液を再び体内に戻すための、いわば血液の「出入り口」を指します。
なぜバスキュラーアクセスが必要なのか
血液透析では、1分間に約200mlという、コップ1杯分もの大量の血液を体外へ取り出し、浄化して体内に戻す必要があります。
しかし、私たちの腕などにある通常の静脈は、皮膚の表面近くにあって穿刺しやすいものの、血流が緩やかで壁も薄いため、この力強い血流に耐えることができません。
また、週に3回、毎回の透析で針を刺すという負担にも耐えられず、すぐに血管が硬くなったり詰まったりしてしまいます。
この根本的な問題を解決するために、手術によって透析に適した太く丈夫な血流の豊富な血管、つまりバスキュラーアクセスを作成することが必要です。
バスキュラーアクセスの種類と特徴
バスキュラーアクセスには、主に3つの種類があります。
それぞれに長所と短所があり、患者さんの血管の状態(太さや走行)、全身の状態(心臓の機能や糖尿病の有無など)、そして生活スタイルなどを総合的に判断して、どの種類を選択するかを決めます。
ご自身の体に関わることですので、それぞれの特徴を理解しておくことが大事です。
バスキュラーアクセスの主な種類
| 種類 | 作成方法 | 特徴 |
|---|---|---|
| 自己血管内シャント(AVF) | 自身の動脈と静脈を手術でつなぎ合わせる | 長期間使用できる可能性が高く、感染症のリスクが低い。シャントが成熟するまで時間が必要。 |
| 人工血管内シャント(AVG) | 人工の管(グラフト)を使い、動脈と静脈をつなぐ | 自己血管が細い場合でも作成可能。AVFより閉塞や感染のリスクがやや高い。比較的早く使用開始できる。 |
| 長期留置カテーテル | 首や胸、足の付け根の太い静脈にカテーテルを留置する | 手術後すぐに使用できるが、感染症や血栓のリスクが最も高い。入浴などに制限がある。 |
自己血管内シャント(AVF)が第一選択となる理由
多くの医療機関では特別な理由がない限り、自己血管内シャント(Autogenous Venous Fistula、略してAVF)をバスキュラーアクセスの第一選択としています。
これは、ご自身の血管を使用するため、人工物であるグラフトやカテーテルに比べて、体へのなじみが良く、拒絶反応の心配がないからです。なじみの良さが、長期的なメリットにつながります。
感染症を起こすリスクが他の方法に比べて格段に低く、また一度安定して使えるようになると、人工血管よりも長持ちする(開存率が高い)傾向があります。
シャントが成熟し、透析に使えるようになるまでには数週間から数ヶ月かかりますが、長期的な視点で見ると、患者さんにとって最も安全で負担の少ない方法であると考えられるため、可能な限りAVFの作成を目指します。
シャント作成手術の概要と流れ
シャント作成手術そのものは局所麻酔で行うことが多く、入院期間も数日から1週間程度と、比較的体への負担が少ない手術の一つです。ここでは、手術の具体的な進め方から、術後の過ごし方までを解説します。
手術はどのように進むのか
シャント作成手術は、通常、利き腕とは反対の腕の、手首に近い部分から検討します。手術台に横になり、腕を消毒した後、手術する範囲に清潔な布をかけ、手術する腕に局所麻酔の注射をします。
手術中に意識はあり、医師や看護師と会話することも可能です。麻酔が効いたことを確認した後、皮膚を数センチ切開し、顕微鏡などを使って慎重に動脈と静脈を露出させます。
そして、この2つの血管の壁を小さく開き、髪の毛よりも細い糸でつなぎ合わせ、つなぎ終えると、動脈から静脈側へ「ザーザー」という血流音が聞こえ、振動(スリル)が触れるようになります。
血流を確認し、皮膚を縫合して手術は終了で、手術時間はおおよそ1時間から2時間程度です。
手術前の検査内容
安全に手術を行い、長持ちする良好なシャントを作成するためには、事前の詳細な検査が重要です。手術に適した血管があるか、また全身の状態が手術に耐えられるかを確認します。
検査結果は、いわば手術の設計図となり、医師はどの血管を使って、どのようにシャントを作成するかを具体的に計画します。
シャント手術前に一般的に行われる検査
| 検査の種類 | 目的 | 内容 |
|---|---|---|
| 血液検査 | 全身状態と手術への適合性の把握 | 貧血や腎機能の現状、肝機能、感染症の有無、血液の固まりやすさなどを調べます。 |
| 血管超音波(エコー)検査 | 血管の「地図」作成と状態評価 | 腕の動脈と静脈の太さ、深さ、走行、石灰化の有無などを詳しく調べ、手術に最適な血管を選びます。 |
| 心電図・胸部X線検査 | 心臓や肺への負担の評価 | シャント作成による血流の変化に心臓や肺が耐えられるか、手術に影響を与える病気がないかを確認します。 |
手術後の注意点と回復期間
手術が終わった直後は、麻酔の影響や手術による痛みを感じることがあります。痛み止めで対応できますので、我慢せずにスタッフに伝えてください。
手術した腕は、感染を防ぐために清潔に保ち、心臓より少し高く上げておくことで腫れを軽減します。数日間は重いものを持ったり、腕に強い力を入れたりしないようにしてください。
シャントが実際に透析で使えるようになるまでには、通常2週間から1ヶ月、人によってはそれ以上の時間が必要です。この期間は、動脈血が流れ込むことで静脈の壁が厚く、太く成長する、いわゆる「シャントを育てる」大切な時期です。
医師や看護師の指示に従い、焦らずにシャントの成熟を待ちます。
シャント作成手術の時期
透析導入が避けられない状況になったとき、多くの人が悩むのがシャント作成手術のタイミングです。
早すぎても実際に使わない期間が長くなりますし、逆に遅すぎると、尿毒症の症状が悪化して緊急透析が必要になるなど、心身ともに大きな負担がかかります。
腎機能の低下と手術時期の目安
一般的に、腎機能の指標であるeGFR(推算糸球体濾過量)の値が、透析導入の時期を検討する一つの目安です。
多くの場合は、eGFRが15ml/min/1.73m²未満になったあたりで、透析の専門医とシャント作成について具体的な相談を始めることが推奨されます。重要なのは、ある一点の数値だけでなく、腎機能が低下していく「速度」です。
eGFRの低下スピードが速い場合は、早めに準備を始める必要があります。シャントは作成後、成熟して安定的に使えるようになるまで数週間から数ヶ月かかるため、透析が必要になる時期から逆算して、余裕を持った計画を立てることが重要です。
eGFR値とシャント手術を検討する時期の一般的な目安
| eGFR値 (ml/min/1.73m²) | 腎機能の状態 | 推奨される行動 |
|---|---|---|
| 30以上 | 軽度〜中等度低下 | 腎臓専門医による定期的な診察と生活習慣の管理を継続。 |
| 15~29 | 高度低下 | 透析に関する情報収集を開始。シャント作成の利点・欠点について説明を受け、相談を始める時期。 |
| 15未満 | 末期腎不全 | シャント作成手術を具体的に計画し、実施を検討する。尿毒症症状があれば速やかに準備を進める。 |
糖尿病や血管の動脈硬化が進行している場合、シャントの成熟に時間がかかることが予想されるため、より早い段階で手術を検討することもあります。主治医とよく相談することが大切です。
計画的な手術と緊急透析の違い
シャント手術を計画的に行うか、それとも緊急的に透析を開始するかは、その後の治療生活に大きな違いをもたらします。計画的に準備を進めることの重要性を理解するために、両者を比較してみましょう。
計画的導入と緊急導入の比較
| 項目 | 計画的導入(シャント作成後) | 緊急導入(カテーテル使用) |
|---|---|---|
| アクセスの種類 | 自己血管内シャント(AVF) | 長期留置カテーテル |
| 安全性 | 感染や閉塞のリスクが低い | 感染症や血栓のリスクが高い |
| 身体的・精神的負担 | 心身ともに準備期間があり、負担が少ない | 突然の入院や処置で負担が大きい |
| 生活の質(QOL) | 入浴などの制限がなく、日常生活を送りやすい | カテーテル刺入部の管理が必要で、入浴などに制限がある |
手術時期を検討する上での判断材料
最終的な手術時期は、eGFRの値だけでなく、尿毒症の症状(食欲不振、吐き気、だるさ、かゆみなど)、体のむくみや体重増加、血圧の管理状態、そしてご自身の仕事や家庭の事情などを総合的に考慮して決定します。
手術時期を決定する際の考慮点
- 血清クレアチニン値やeGFRの推移(低下の速度)
- 尿毒症症状の有無と程度
- 水分管理の状態(むくみ、体重増加、心臓への負担)
- 降圧薬でもコントロール困難な高血圧
- 患者本人の生活や仕事のスケジュール、価値観
手術に向けた準備
手術の日程が決まったら、次はその日に向けて心と体の準備を整えていく段階です。シャント手術は、その後の生活に直結するため、日々の少しの心がけが、手術の成功やシャントの寿命に影響を与えることもあります。
精神的な準備と情報収集
手術に対する不安は誰にでもある自然な感情です。不安を和らげるためには、まず正しい情報を得ることが助けになります。
医師や看護師、臨床工学技士などから、手術の方法、起こりうる合併症、術後の経過について、納得できるまで説明を受けましょう。家族にも同席してもらい、一緒に話を聞くことも理解を深める上で有効です。
腕の血管を守るための日常生活の工夫
シャントを作成する腕の血管は、手術の成功率を左右する大切な資源です。将来シャントを作成する可能性のある腕(通常は利き腕でない方)の血管は、日頃から大切に扱う必要があります。
シャント作成予定の腕の血管を保護する方法
| 行動 | 理由 | 具体的な注意点 |
|---|---|---|
| 採血・点滴を避ける | 繰り返し針を刺すと血管が硬くなり、使いにくくなるため | 健康診断などでは、必ず反対側の腕で採血・点滴をしてもらうよう伝える。 |
| 血圧測定を避ける | カフによる強い圧迫が血管に負担をかけるため | 血圧測定も反対側の腕で行う。両腕とも難しい場合は足で測定することもある。 |
| きつい衣服や装飾品を避ける | 腕の血流を妨げないようにするため | 腕時計やブレスレットは反対の腕につけ、袖口のきつい服は避ける。 |
食事や運動に関する注意点
手術前は、体力を維持し、万全の体調で臨むことが重要です。腎機能の段階に応じた食事療法(塩分、タンパク質、カリウム、リンなどの制限)を継続し、体重や血圧を適切に管理します。
また、適度な運動は血行を良くし、血管の状態を良好に保つのに役立ちます。ゴムボールなどを繰り返し握ったり開いたりする簡単な運動(グーパー運動)は、腕の静脈を発達させ、太く丈夫なシャントを作成する助けになることがあります。
運動により、静脈が発達し、手術がしやすくなるだけでなく、シャントの成熟も早まる効果が期待できます。ただし、どのような運動が良いかは個人の状態によりますので、必ず主治医に相談してから行ってください。
シャント作成後の管理と長期的な維持
無事にシャント作成手術が終わり、透析が開始された後も、シャントを一日でも長く大切に使っていくための自己管理が始まります。シャントは非常にデリケートなもので、日々の少しの注意が、寿命を大きく延ばすことにつながります。
日常的なシャントの観察方法
シャントの管理で最も基本となるのは、毎日シャントの状態をご自身で確認する習慣をつけることです。見る(視診)、聞く(聴診)、触れる(触診)という3つの方法で、シャントが正常に機能しているかをチェックします。
毎日のシャント自己観察ポイント
| 観察方法 | チェック項目 | 正常な状態 |
|---|---|---|
| 見る(視診) | 皮膚の発赤、腫れ、傷、出血、こぶ(瘤)の有無 | 皮膚の色に異常がなく、極端な腫れや傷もない。 |
| 聞く(聴診) | シャント血管の血流音(直接耳を当てるか聴診器で) | 「ザーザー」「ゴーゴー」という連続した柔らかい低い音が聞こえる。 |
| 触れる(触診) | シャント血管の振動(スリル) | 血流による柔らかく細かい振動(スリル)を指先で感じる。 |
音が弱くなったり、高くなったり、振動が感じられなくなったりした場合は、シャントが狭くなったり詰まったりしているサインかもしれません。すぐ病院に連絡してください。
シャントを長持ちさせるためのポイント
日々の観察に加えて、日常生活でのいくつかの注意点を守ることが、シャントの保護につながります。シャントのある腕に過度な負担をかけないことが基本です。
シャントのある腕で避けるべきこと
- 腕時計やきつい袖の衣服の着用
- 重い荷物を持つこと(買い物袋など)
- シャント部分を圧迫するような姿勢(腕枕、正座で腕を敷くなど)
- 血圧測定や採血、点滴
- シャント部分を掻いたり、叩いたり、強くこすったりすること
また、透析後は穿刺部からの出血が完全に止まったことを確認し、絆創膏は翌日には剥がして皮膚を清潔に保ちます。シャント部分の皮膚を保湿クリームなどでケアし、柔らかく保つことも、穿刺しやすく、トラブルを防ぐ上で重要です。
トラブルの兆候と早期発見の重要性
毎日シャントを観察していると、いつもと違う変化に気づくことがあります。
閉塞(詰まること)や感染、狭窄(狭くなること)などの問題は、早期に発見し対処すれば、カテーテル治療(VAIVT)など体への負担が少ない方法で修復できることが多いです。
ただし、発見が遅れると、シャントを再建するための大きな手術が必要になったり、シャントが完全に使用できなくなったりすることもあります。
ささいな変化でも、「これくらい大丈夫だろう」と自己判断せず、ためらわずに病院のスタッフに相談することが、ご自身のシャントを守る上で最も大切なことです。
手術に伴うリスクと合併症
どのような手術にも、残念ながらリスクや合併症の可能性はゼロではありません。事前にどのようなことが起こりうるのかを理解しておくことで、万が一の際にも冷静に対処できますし、予防のために何ができるかを考えることにもつながります。
手術直後に起こりうる合併症
手術が終わって間もない時期に注意したい合併症がいくつかあり、手術手技や患者さん個人の血管の状態に関連して起こることがあります。多くの場合は、早期に適切な処置を行うことで改善します。
手術直後の主な合併症
| 合併症 | 症状と対処 |
|---|---|
| 出血・血腫 | 手術創から血がにじむ、あるいは皮下に出血し腫れる。多くは圧迫することで止まりますが、大きい場合は再手術で血腫を取り除くこともあります。 |
| 感染 | 創部が赤く腫れ、熱を持ち、痛む。抗生物質の投与で治療しますが、重症の場合は切開して膿を出す必要があります。 |
| 神経障害 | 指先のしびれや痛み、動かしにくさ。多くは手術操作による一時的なもので、時間とともに軽快しますが、回復に時間がかかることもあります。 |
長期的に注意すべき合併症
シャントを長年使用していると、さまざまな理由でトラブルが発生することがあります。透析効率の低下やシャントの寿命に直結する問題であり、定期的な検査と日々の自己管理によって早期発見に努めることが重要です。
長期的な使用に伴う主な合併症
- シャント閉塞・狭窄: 最も多いトラブル。血管の内側が厚くなり狭くなる。
- 感染症: 穿刺部からの細菌侵入が原因。
- 静脈高血圧症: シャントの血流が末梢に逆流し、腕や手が腫れ、皮膚の色が悪くなる。
- シャント瘤(りゅう): 血管の一部がこぶ状に膨らむ。破裂のリスクがある場合は手術が必要。
- スチール症候群: シャントに血液が盗まれ(steal)、指先の血流が不足し、冷感や痛み、しびれが出る。
合併症を予防するためにできること
合併症を完全に防ぐことは難しいかもしれませんが、リスクを減らすためにできることはあります。
まず、シャントを清潔に保ち、感染予防を徹底すること、シャントのある腕に負担をかけない生活を心がけること、そして、毎日の自己観察を怠らず、異常を感じたらすぐに報告することです。
また、血圧や血糖、体重の管理、禁煙といった全身状態を良好に保つことも、血管の動脈硬化を防ぎ、シャントを長持ちさせることにつながります。
よくある質問(Q&A)
最後に、シャント作成手術に関して、患者さんからよく寄せられる質問と回答をまとめました。
- 手術の痛みはどのくらいですか?
-
手術は局所麻酔で行うため、手術中に強い痛みを感じることはほとんどありません。麻酔の注射の際にチクッとした痛みがある程度です。
手術後は、麻酔が切れるとズキズキとした痛みが出ることがありますが、痛み止めの薬で十分にコントロールできます。
- シャントを作った腕は見た目が変わりますか?
-
シャントを作成すると、動脈の血が静脈に流れ込むため、静脈は時間とともに太く浮き出てきます。人によっては、血管がこぶのように膨らむ(シャント瘤)こともあります。
これはシャントがしっかり機能している証拠でもありますが、見た目が気になる方もいるかもしれません。
- シャントが使えなくなったらどうなりますか?
-
シャントが閉塞などのトラブルで使えなくなった場合でも、治療法はあります。風船のついたカテーテルで狭くなった部分を広げる治療(VAIVT)や、血栓を溶かしたり取り除いたりする治療で、多くは修復が可能です。
もし修復が困難な場合でも、同じ腕のより心臓に近い場所にシャントを作り直したり、反対側の腕に作成したり、人工血管を用いたりするなど、次の手段があります。
一つのシャントが使えなくなっても、それで透析ができなくなるわけではありませんので、過度に心配する必要はありません。
- 手術費用はどのくらいかかりますか?
-
シャント作成手術は、公的医療保険が適用されます。また、慢性腎不全の透析治療は、特定疾病療養受療制度の対象となり、申請することで自己負担限度額が原則として月額1万円(上位所得者は2万円)です。
この他にも、重度心身障害者医療費助成制度や自立支援医療(更生医療)など、さまざまな医療費助成制度を利用できます。
以上
透析センター(人工透析) | 大垣中央病院(医療法人社団豊正会 )
参考文献
Ozeki T, Shimizu H, Fujita Y, Inaguma D, Maruyama S, Ohyama Y, Minatoguchi S, Murai Y, Terashita M, Tagaya T. The type of vascular access and the incidence of mortality in Japanese dialysis patients. Internal Medicine. 2017 Mar 1;56(5):481-5.
Murakami M, Fujii N, Kanda E, Kikuchi K, Wada A, Hamano T, Masakane I. Association between timing of vascular access creation and mortality in patients initiating hemodialysis: a nationwide cohort study in Japan. American Journal of Nephrology. 2024 Dec 16;55(6):647-56.
Yamauchi T, Yamamoto H, Miyata H, Kobayashi J, Masai T, Motomura N. Surgical Aortic Valve Replacement for Aortic Stenosis in Dialysis Patients―Analysis of Japan Cardiovascular Surgery Database―. Circulation Journal. 2020 Jul 22;84(8):1271-6.
Furukawa H. Surgical management of vascular access related aneurysms to salvage dialysis access: case report and a systematic review of the literature. The journal of vascular access. 2015 Mar;16(2):120-5.
Tsuchida K, Nagai K, Minakuchi J, Kawashima S. Vascular access for long-term hemodialysis/hemodiafiltration patients in Japan. Contrib Nephrol. 2015 Jan 1;185:132-7.
Ethier J, Mendelssohn DC, Elder SJ, Hasegawa T, Akizawa T, Akiba T, Canaud BJ, Pisoni RL. Vascular access use and outcomes: an international perspective from the Dialysis Outcomes and Practice Patterns Study. Nephrology Dialysis Transplantation. 2008 Oct 1;23(10):3219-26.
Nakata J, Io H, Watanabe T, Sasaki Y, Makita Y, Aoki T, Yanagawa H, Kanda R, Tomino Y. Impact of preoperative ultrasonography findings on the patency rate of vascular access in Japanese hemodialysis patients. Springerplus. 2016 Apr 14;5(1):462.
Miyamoto K, Sato T, Momohara K, Ono S, Yamaguchi M, Katsuno T, Sakurai H, Imai H, Ito Y. Analysis of factors for post–percutaneous transluminal angioplasty primary patency rate in hemodialysis vascular access. The Journal of Vascular Access. 2020 Nov;21(6):892-9.
Yoshida M, Doi S, Nakashima A, Kyuden Y, Kawai T, Kawaoka K, Takahashi S, Ueno T, Nishizawa Y, Masaki T. Different risk factors are associated with vascular access patency after construction and percutaneous transluminal angioplasty in patients starting hemodialysis. The Journal of Vascular Access. 2021 Sep;22(5):707-15.
Kambayashi Y, Iseri K, Morikawa T, Yao A, Yokochi A, Honda H. Risk factors for blood vessel rupture during vascular access intervention therapy for hemodialysis patients. PLoS One. 2023 Mar 31;18(3):e0283844.