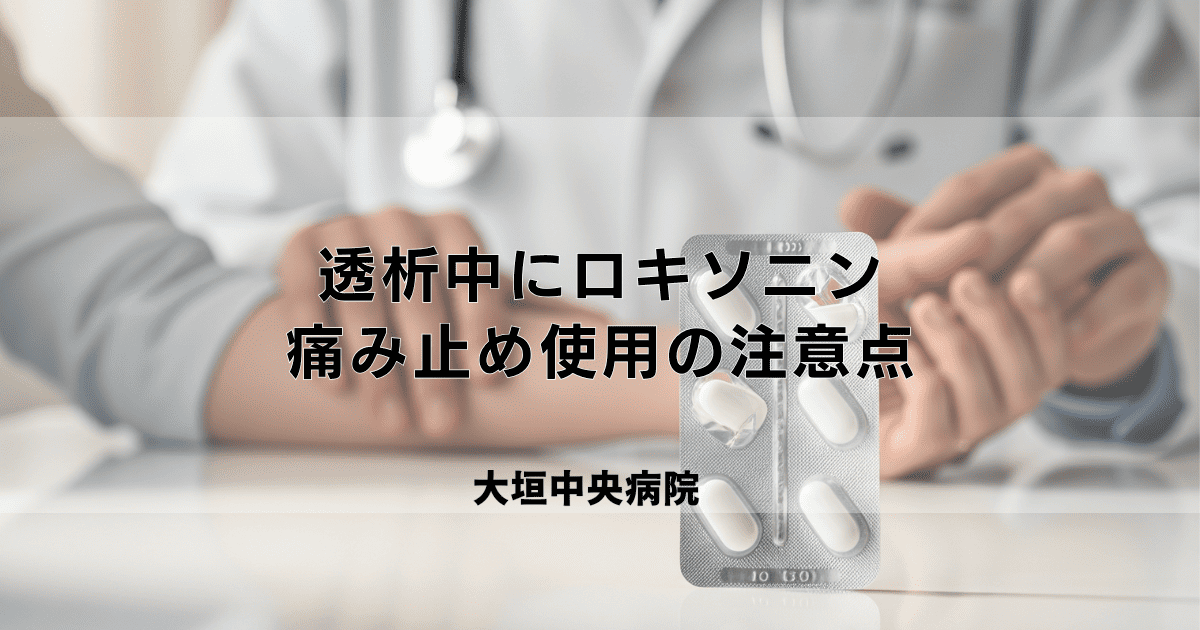透析治療を受けている中で、頭痛や関節痛、シャントの痛みなど、さまざまな痛みを感じる場面は少なくありません。
そんな時、手軽に手に入る市販の痛み止め、特に有名なロキソニンに頼りたくなりますが、透析を受けている方の体は、薬の影響を非常に受けやすい状態にあります。
この記事では、透析治療中の方がロキソニンに代表される痛み止め(NSAIDs)を使用する際に、なぜ特別な注意が必要なのか、理由とリスク、そして安全に痛みと付き合うための方法について、分かりやすく解説します。
透析と痛み なぜ痛み止めが必要になるのか
透析治療と痛みは、切り離せない関係にある場合があり、多くの方が、治療生活の中で何らかの痛みを経験します。痛みの原因は一つではなく、透析そのものに関連するものから、長年の腎臓病が体に及ぼす影響まで、実にさまざまです。
透析患者が抱えやすい痛みの種類
透析を受けている方が経験する痛みは多岐にわたります。代表的なものは、透析を行うために必要なバスキュラーアクセス(シャントやグラフト)に関連する痛みです。
穿刺時の痛みはもちろん、シャントの血流障害(狭窄や閉塞)、感染、あるいは過剰な血流によるスチール症候群によって痛みが生じることもあります。
また、腎機能の低下に伴い骨がもろくなる腎性骨症による腰痛や関節痛、カルシウムやリンのバランス異常が原因で血管や関節周囲に石灰が沈着する異所性石灰化による痛みも深刻です。
透析関連の痛みの原因と特徴
| 痛みの種類 | 主な原因 | 痛みの特徴 |
|---|---|---|
| シャント痛 | 穿刺、狭窄、感染、スチール症候群 | 穿刺時の鋭い痛み、安静時の鈍い痛み、拍動性の痛み |
| 骨・関節痛 | 腎性骨症、透析アミロイドーシス | 体を動かした時の痛み、安静にしていても続く痛み、関節のこわばり |
| 筋肉の痛み | こむら返り、カルニチン欠乏 | 透析中や夜間に起こる突然の激しい筋肉のけいれん |
痛みが日常生活に与える影響
慢性的な痛みは単に不快なだけでなく、日常生活のあらゆる面に影を落とし、痛みのために夜十分に眠れなくなったり(睡眠障害)、食欲がなくなったりすることもあります。
また、体を動かすのが億劫になり、リハビリや社会活動への参加意欲が削がれてしまうことも少なくありません。痛みが続くことで気分が落ち込み、不安や抑うつ状態に陥るなど、精神的なストレスが増大する悪循環に陥る可能性があります。
痛みを個人的な問題として放置せず、医療チームと共に積極的に対処することが、その人らしい生活を維持するために重要です。
痛み止めを求める心理と背景
痛みを感じた時、すぐにでもその苦痛から解放されたいと思うのは自然なことです。特に、ドラッグストアなどで手軽に購入できる市販の痛み止めは、医療機関を受診する手間もなく、非常に便利な存在に感じられます。
しかし、透析を受けている方の場合、この手軽さが大きな落とし穴になることがあります。健康な人であれば問題なく使用できる薬でも、透析患者にとっては深刻な副作用を引き起こす危険性をはらんでいることを、まず知っておくことが必要です。
痛み止めの王道 ロキソニン(NSAIDs)とは
痛み止めと聞いて多くの方が思い浮かべるロキソニンは、非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs: Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs)という薬のグループに属します。
NSAIDsは、優れた鎮痛・抗炎症・解熱作用を持ち、世界中で広く使われています。
NSAIDsが痛みを抑える働き
私たちが痛みや熱を感じる時、体内ではプロスタグランジンという化学物質が作られていて、プロスタグランジンは、痛みや炎症、発熱を引き起こす原因です。
NSAIDsは、シクロオキシゲナーゼ(COX)という酵素の働きをブロックすることで、プロスタグランジンの生成を抑えます。原因物質が作られなくなるため、痛みや炎症が和らぐというわけです。
COXには、主に体の恒常性維持に関わるCOX-1と、主に炎症時に働くCOX-2の二種類があり、多くのNSAIDsは両方を阻害するため、目的の鎮痛作用と同時に、COX-1阻害による副作用も生じる可能性があります。
市販されている主なNSAIDsの種類
ドラッグストアなどで手に入る痛み止めには、さまざまな種類のNSAIDsが含まれています。成分によって効果の強さや作用時間が少しずつ異なりますが、基本的な働きや注意点は共通しています。
透析を受けている方は、これらの成分名を知っておき、薬を選ぶ際に必ず確認する習慣をつけることが大切です。
市販薬に含まれる代表的なNSAIDs
| 成分名 | 主な商品名(例) | 特徴 |
|---|---|---|
| ロキソプロフェンナトリウム | ロキソニンS | 比較的効果が速く、鎮痛作用が強い。プロドラッグ。 |
| イブプロフェン | イブ、リングルアイビー | 比較的マイルドで、解熱鎮痛薬として広く使われる。 |
| アスピリン(アセチルサリチル酸) | バファリンA | 古くからある代表的な薬。血を固まりにくくする作用も。 |
NSAIDsの一般的な副作用
NSAIDsは効果的な薬である一方、いくつかの代表的な副作用があり、最もよく知られているのが胃腸障害です。
胃の粘膜を保護するプロスタグランジン(主にCOX-1の働きによる)も抑えてしまうため、胃痛や胃もたれ、ひどい場合には胃潰瘍や十二指腸潰瘍を起こすことがあります。
また、腎臓の血管を収縮させて血流を悪くするため、腎機能障害の原因となることも知られています。その他、アスピリン喘息と呼ばれる喘息発作を誘発したり、血圧を上昇させたり、心血管系のリスクを高めたりすることもあります。
透析患者がロキソニン(NSAIDs)を使う際のリスク
なぜ、透析を受けている方はNSAIDsの使用に特に注意が必要なのでしょうか。残された腎臓の機能や心臓、消化管など、全身に及ぼすリスクについて詳しく見ていきましょう。
腎機能への影響と残存腎機能の保護
透析を導入した後でも、尿が少しでも出ている場合、それは残存腎機能がまだ残っている証拠です。
このわずかな腎機能は、体内の水分や尿毒素のコントロールに役立っており、貧血の改善や栄養状態の維持、生命予後にも良い影響を与えることが分かっているため、残存腎機能をできるだけ長く保つことは非常に重要になります。
NSAIDsは腎臓への血流を低下させる作用があるため、この大切な残存腎機能に大きなダメージを与え、完全に失わせてしまう可能性があります。尿量が減る、あるいは全く出なくなるといった事態を招きかねません。
消化管出血(胃潰瘍など)のリスク増大
透析患者さんは、尿毒素の影響で血小板の機能が低下し、血が止まりにくくなる出血傾向があります。その上、透析治療の際には回路内での血液凝固を防ぐために血液を固まりにくくする薬(抗凝固薬)を使います。
このような状況で、胃腸障害の副作用を持つNSAIDsを服用すると、相乗効果で消化管からの出血リスクが著しく高まります。健康な人であれば軽度の胃粘膜の荒れで済むところ、透析患者さんでは重篤な吐血や下血につながる危険性があります。
命に関わる事態にもなりかねない、非常に注意すべき副作用です。
NSAIDsの主な副作用と透析患者におけるリスク
| 一般的な副作用 | 透析患者における特有のリスク |
|---|---|
| 腎機能障害 | 貴重な残存腎機能の完全な喪失、無尿化 |
| 消化管障害 | 出血傾向と相まって重篤な消化管出血(吐血・下血)へ |
| 体液貯留・血圧上昇 | 心不全の悪化、ドライウェイト管理の困難化、高血圧 |
カリウム値の上昇(高カリウム血症)
カリウムは、筋肉や神経の働きに重要なミネラルですが、体内に増えすぎると心臓に重篤な影響を及ぼします。
通常、カリウムは腎臓から尿中へ排泄されますが、透析患者さんはその能力が低いため、食事制限などで体内のカリウム値を厳格にコントロールしています。
NSAIDsには、腎臓でのカリウム排泄を妨げる作用があり、血液中のカリウム濃度が異常に高くなる高カリウム血症を起こす可能性があります。
高カリウム血症は、手足のしびれや脱力感だけでなく、致死的な不整脈や心停止の原因となる、極めて危険な状態です。
体液貯留と心臓への負担
NSAIDsは、腎臓でのナトリウムと水分の排泄を抑制する働きもあり、体に水分が溜まりやすくなり、むくみ(浮腫)や体重増加、血圧の上昇を招きます。透析患者さんにとって、体液量のコントロールは心臓への負担を管理する上で生命線です。
ただでさえ水分管理が重要な中で、NSAIDsの使用によってさらに体液が貯留すると、心不全が悪化したり、ドライウェイト(透析後の目標体重)の管理が困難になったりする危険性があります。
それでも痛みがある時に どうすれば良いのか
NSAIDsのリスクを理解すると、では痛みがある時はどうすれば良いのか、と不安になるかもしれません。大切なのは、自己判断で市販薬に頼るのではなく、専門家である医療スタッフに相談し、安全な方法で痛みをコントロールすることです。
まずは主治医や透析施設のスタッフに相談する
痛みを感じたら、どんな些細な痛みでも、まずは主治医や透析室の看護師、薬剤師に相談してください。いつから、どこが、どのように痛むのか、どんな時に痛みが強くなるのかなどを具体的に伝えることが重要です。
痛みの原因を突き止め、その原因に応じた最も安全で効果的な治療法を一緒に考えてくれます。自己判断で市販薬を服用することは、絶対に避けるべきです。
医師に痛みを伝える際のポイント
- いつから痛むか(例:昨日の夜から、1週間前から)
- どこが痛むか(例:右ひざの内側、シャント全体)
- どのように痛むか(例:ズキズキ、ジンジン、締め付けられるよう)
- 痛みの強さ(例:10段階のうち7くらい、我慢できないほど)
- どんな時に痛みが変化するか(例:動くと強くなる、夜間にひどくなる)
安全に使用できる痛み止めの選択肢 アセトアミノフェン
透析患者さんが痛み止めを使用する場合の第一選択薬は、アセトアミノフェンです。アセトアミノフェンは、NSAIDsとは異なる仕組みで作用し、脳の痛みを感知する部分(中枢神経)に働きかけて鎮痛効果を発揮します。
NSAIDsのような腎血流への影響や胃腸障害、血液を固まりにくくする作用がほとんどないため、透析患者さんでも比較的安全に使用できます。
市販薬では、タイレノールAや、小児用の風邪薬などに含まれていますが、透析患者さんの場合は肝臓での代謝などを考慮して用量調整が必要な場合があるため、必ず医師や薬剤師の指示のもとで服用してください。
アセトアミノフェンの特徴
| 項目 | 特徴 | 注意点 |
|---|---|---|
| 作用機序 | 中枢神経に作用し痛みの閾値を上げる | 末梢での抗炎症作用は弱い |
| 腎臓への影響 | ほとんどないとされる | 長期連用は医師の管理下で行う |
| 主な副作用 | 胃腸障害が少ない | 過量服薬で重篤な肝障害のリスク |
痛みの種類に応じた他の薬物療法
アセトアミノフェンで効果が不十分な場合や、痛みの種類によっては他の薬が選択されます。ピリピリ、ジンジンといった神経の痛み(神経障害性疼痛)には、プレガバリンなどの神経に作用する薬が使われます。
また、非常に強い痛みに対しては、医師の厳格な管理のもとで、トラマドールなどの弱オピオイドや、さらに強力な医療用麻薬(オピオイド鎮痛薬)が使われることもあります。
これらはすべて専門的な判断が必要な薬であり、自己判断での使用はありえません。
痛み止め(NSAIDs)の安全な使い方 透析患者の視点から
これまで述べてきたように、透析患者さんにとってNSAIDsの使用は原則として避けるべきですが、例外的な状況もあります。
アセトアミノフェンでは効果がなく、痛みが非常に強く生活に大きな支障をきたしている場合などに、医師がリスクと効果を慎重に天秤にかけ、特別な管理下で処方することがあります。
医師がNSAIDsを処方する特別なケース
医師がNSAIDsの処方を検討するのは、他のすべての安全な手段を試しても痛みがコントロールできない、限定的な状況です。
例えば、手術後の強い痛みや、痛風発作、炎症が非常に強い関節炎など、短期的に強力な鎮痛・抗炎症作用が必要と判断された場合です。
この場合でも、患者さんの残存腎機能の有無、心臓の状態、消化管出血の既往歴、服用中の他の薬との相互作用などを総合的に評価し、ごく限られた患者さんにのみ、細心の注意を払いながら使用します。
使用する場合の具体的な注意点
万が一、医師の判断でNSAIDsを使用することになった場合でも、使い方は通常とは全く異なり、まず、使用は必要最小限の期間に限定します。漫然と長期間使い続けることはありません。
また、用量も可能な限り少なく設定し、胃薬(プロトンポンプ阻害薬など)を必ず併用して、消化管出血のリスクを最大限に減らします。
さらに、服用期間中は、尿量の変化やむくみ、血圧、血液検査データ(カリウム値、肝機能など)を注意深く監視し、副作用の兆候が少しでも見られれば直ちに中止します。
NSAIDsを限定的に使用する場合の条件
| 項目 | 具体的な管理方法 |
|---|---|
| 期間 | ごく短期間(数日程度)に限定する |
| 用量 | 最小有効量を使用する |
| 併用薬 | 強力な胃粘膜保護薬を必ず併用する |
| 監視 | 副作用(尿量、血圧、血液データ)の綿密なモニタリング |
自己判断による市販薬の使用は絶対に避ける
最も重要なことは、自己判断で市販のNSAIDsを購入して服用しないことです。医師が処方するのは、患者さん一人ひとりの状態を詳細に把握し、厳格な管理が可能であるという前提があります。
ドラッグストアで同じ成分の薬が売られているからといって、安易に手を出すことは極めて危険です。痛みがある場合は、必ずかかりつけの医療機関に相談するという原則を徹底してください。
湿布や塗り薬(外用薬)なら安全か
飲み薬がだめなら、貼るタイプや塗るタイプの外用薬なら大丈夫だろう、と考える方もいるでしょう。確かに外用薬は内服薬に比べて全身への影響は少ないですが、それでも全くリスクがないとは言えません。
外用薬のNSAIDsも体内に吸収される
湿布や塗り薬、テープ剤などに含まれるNSAIDs成分も、皮膚から吸収されて血液中に入り、全身を循環します。
内服薬に比べれば血中濃度ははるかに低く、全身的な副作用のリスクは格段に低くなりますが、吸収される量がゼロではない以上、リスクもゼロではありません。
広範囲に大量に使用したり、長期間にわたって使い続けたりすると、内服薬と同じような副作用(腎機能の悪化や喘息発作など)を起こす可能性が指摘されています。
透析患者さんでは薬の排泄が遅れるため、成分が体内に蓄積しやすいことも考慮に入れることが大事です。
外用薬使用時のチェックリスト
- 一度に広範囲に貼りすぎていないか(目安は2枚程度まで)
- 傷のある場所や粘膜、湿疹のある部分には使用していないか
- 長期間、漫然と自己判断で使い続けていないか
- 貼った場所に発疹、かゆみ、かぶれなどの異常はないか
- 医師や薬剤師の指示通りの使い方か
外用薬を使用する際の注意点
外用薬のNSAIDsを使用する場合でも、医師や薬剤師の指示に従うことが基本です。一度に貼る枚数や塗る量を守り、必要以上に広範囲には使わないようにしましょう。
また、皮膚に傷や湿疹がある場所に貼ると、バリア機能が低下しているため成分の吸収量が増えてしまうため避ける必要があります。
もし、外用薬の使用中に尿量が減ったり、むくみが出たりした場合は、全身への影響が出ている可能性も考えられるため、すぐに使用を中止して主治医に相談してください。
アセトアミノフェン以外の外用薬の選択肢
痛みの種類によっては、NSAIDsを含まない外用薬も選択肢になります。
温感タイプの湿布に含まれるトウガラシエキス(カプサイシン)や、冷感タイプの湿布に含まれるメントール、カンフルなどは、血行を促進したり、皮膚に刺激を与えることで痛みを和らげます。
NSAIDsとは異なる作用を持つため、腎臓への影響を心配することなく使用できます。また、局所麻酔薬であるリドカインを含んだテープ剤なども、神経性の痛みに有効な場合があります。ただし、いずれも皮膚のかぶれなどには注意が必要です。
よくある質問
最後に、透析患者さんから痛み止めに関してよく寄せられる質問についてお答えします。
- 透析の日に頭痛がします。ロキソニンを飲んでも良いですか。
-
自己判断でロキソニンを飲むのは避けてください。透析中の頭痛は、血圧の変動や体内の水分・電解質のバランス変化(不均衡症候群)、あるいはカフェインの離脱症状など、さまざまな原因で起こります。
原因に応じた対処が必要なため、まずは透析施設の医師や看護師にすぐに伝えてください。痛みが強い場合は、腎臓への影響が少ないアセトアミノフェンが処方されることが一般的です。
- 市販の風邪薬にも痛み止め成分が入っていますか。
-
多くの総合感冒薬(風邪薬)には、熱を下げたり喉の痛みを和らげたりする目的で、痛み止め成分が含まれています。
イブプロフェンなどのNSAIDsが含まれている製品もあれば、アセトアミノフェンが含まれている製品もあります。風邪をひいたからといって安易に市販の風邪薬を飲むと、知らずにNSAIDsを摂取してしまう危険があります。
風邪の症状がある場合も、必ずかかりつけの医療機関を受診し、透析中でも安全な薬を処方してもらうようにしてください。
- 歯医者で痛み止めを処方されましたが、飲んでも大丈夫ですか。
-
歯科治療を受ける際は、治療前に必ず透析中であることを歯科医師に伝えてください。この情報があれば、歯科医師は腎機能に配慮して、アセトアミノフェンなど比較的安全な痛み止めを選択してくれます。
もしNSAIDsが処方された場合でも、抜歯後の強い痛みに対して短期間のみ、といった特別な理由があるはずです。
処方された薬について不安な点があれば、歯科医師に質問するか、透析施設の主治医や薬剤師に持参して相談すると、より安心して服用できます。
- アセトアミノフェンなら、いくら飲んでも安全ですか。
-
アセトアミノフェンは腎臓への影響が少ないため、透析患者さんにとって安全性の高い薬ですが、決して無害というわけではありません。
定められた量を超えて大量に服用すると、重篤な肝機能障害を引き起こすことが知られています。これは命に関わる非常に危険な副作用です。
痛みがおさまらないからといって、自己判断で追加して飲んだりせず、必ず医師や薬剤師に指示された用法・用量を厳守することが、安全な薬物治療の大前提です。
以上
透析センター(人工透析) | 大垣中央病院(医療法人社団豊正会 )
参考文献
Katsuno T, Togo K, Ebata N, Fujii K, Yonemoto N, Abraham L, Kikuchi S. Burden of renal events associated with nonsteroidal anti-inflammatory drugs in patients with osteoarthritis and chronic low back pain: a retrospective database study. Pain and Therapy. 2021 Jun;10(1):443-55.
Imai S, Momo K, Kashiwagi H, Miyai T, Sugawara M, Takekuma Y. Nonsteroidal anti‐inflammatory drugs use in patients with chronic kidney disease are often prescribed from different clinicians than those who diagnosed them. Pharmacoepidemiology and drug safety. 2020 Aug;29(8):873-80.
Wang X, Uzu T, Isshiki K, Kanasaki M, Hirata K, Soumura M, Nakazawa J, Kashiwagi A, Takaya K, Isono M, Nishimura M. Iron Status and the Use of Non‐Steroidal Anti‐Inflammatory Drugs in Hemodialysis Patients. Therapeutic Apheresis and Dialysis. 2007 Jun;11(3):215-9.
Hayashi K, Miki K, Kajiyama H, Ikemoto T, Yukioka M. Impact of non-steroidal anti-inflammatory drug administration for 12 months on renal function. Frontiers in Pain Research. 2021 May 26;2:644391.
Kimura H, Yoshida S, Takeuchi M, Kawakami K. Impact of potentially inappropriate medications on kidney function in chronic kidney disease: retrospective cohort study. Nephron. 2023 Apr 20;147(3-4):177-84.
Ejaz P, Bhojani K, Joshi VR. NSAIDs and kidney. Japi. 2004 Aug;52(632-640):371.
Baker M, Perazella MA. NSAIDs in CKD: are they safe?. American Journal of Kidney Diseases. 2020 Oct 1;76(4):546-57.
Gooch K, Culleton BF, Manns BJ, Zhang J, Alfonso H, Tonelli M, Frank C, Klarenbach S, Hemmelgarn BR. NSAID use and progression of chronic kidney disease. The American journal of medicine. 2007 Mar 1;120(3):280-e1.
Zhan M, Peter WL, Doerfler RM, Woods CM, Blumenthal JB, Diamantidis CJ, Hsu CY, Lash JP, Lustigova E, Mahone EB, Ojo AO. Patterns of NSAIDs use and their association with other analgesic use in CKD. Clinical Journal of the American Society of Nephrology. 2017 Nov 1;12(11):1778-86.
Lee A, Cooper MG, Craig JC, Knight JF, Keneally JP. The effects of nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) on postoperative renal function: a meta-analysis. Anaesthesia and intensive care. 1999 Dec;27(6):574-80.