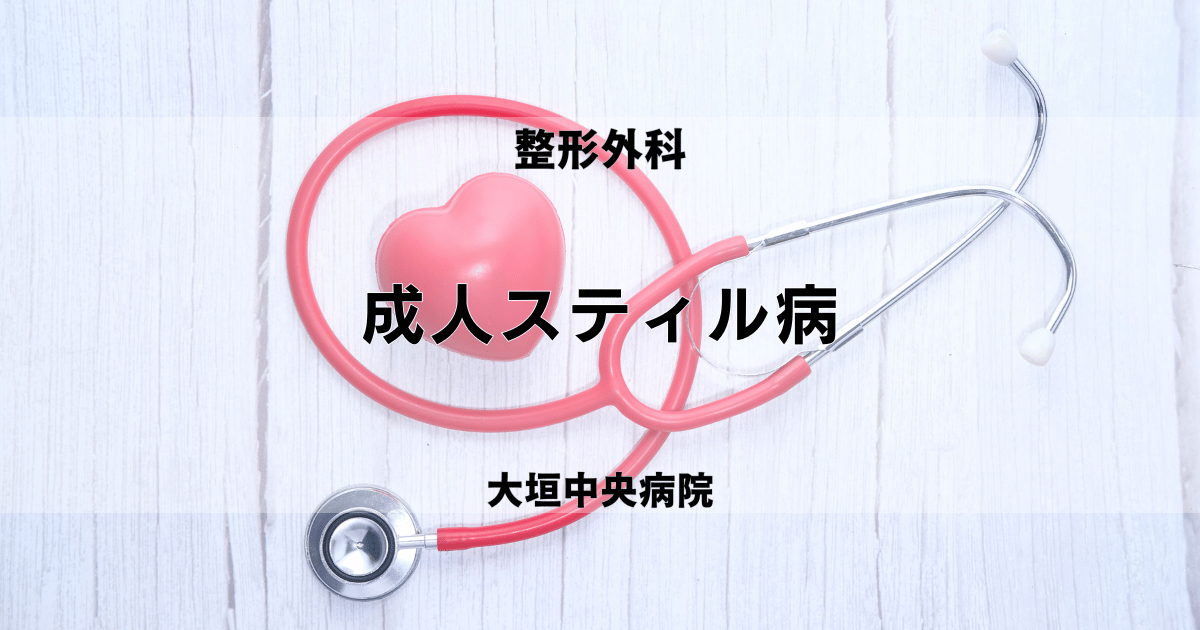成人スティル病(AOSD, Adult-onset Still’s Disease)は、高熱や関節痛、皮疹などが同時にみられる炎症性の疾患です。
若年性特発性関節炎(小児期のスティル病)とは区別され、成人期に発症する稀な病気という点が特徴です。
明確な発症メカニズムが解明されていないため、早期発見が遅れ、治療の開始が後手に回るケースもあります。
しかし、高熱や急激な関節痛などは日常生活に大きな負担となるため、正確な知識と早期の医療機関受診が重要です。
自己抗体(リウマトイド因子・抗核抗体)は陰性であるため関節リウマチなど自己免疫疾患とは異なり、「自己炎症性疾患」(オートインフラマトリー疾患)の典型と考えられています。
この記事の執筆者

臼井 大記(うすい だいき)
日本整形外科学会認定専門医
医療社団法人豊正会大垣中央病院 整形外科・麻酔科 担当医師
2009年に帝京大学医学部医学科卒業後、厚生中央病院に勤務。東京医大病院麻酔科に入局後、カンボジアSun International Clinicに従事し、ノースウェスタン大学にて学位取得(修士)。帰国後、岐阜大学附属病院、高山赤十字病院、岐阜総合医療センター、岐阜赤十字病院で整形外科医として勤務。2023年4月より大垣中央病院に入職、整形外科・麻酔科の担当医を務める。
成人スティル病(AOSD)の病型
成人スティル病はその経過により複数の病型に分類されますが、従来の分類では単周期性全身型、多周期性全身型、慢性関節型の3型が知られています。
単周期性全身型(monophasic型)
一過性に発症し、治療に良く反応して比較的短期間で寛解するタイプ(全体の30~40%)です。
再発せず治療中止も可能なケースがあります。
多周期性全身型(polycyclic型)
寛解と再燃を繰り返すタイプで、高熱や全身症状が治療減量のたびにぶり返す傾向があります(30~40%)。
減量・中止により再発しやすく、寛解維持に注意が必要です。
慢性関節型
初期の全身炎症は抑えられても関節炎が持続・進行するタイプで、関節リウマチ様の経過をとります(20~30%)。
関節破壊を来たす例もあり、関節リウマチの治療薬が有効な場合があります。
成人スティル病の2表現型
近年では2表現型への新たな分類も提唱されています。これは全身型(単周期・多周期)をまとめて「全身炎症優位型」とし、慢性関節型を「慢性関節炎型」に分ける考え方です。
全身炎症優位型は炎症反応(高熱、肝酵素・CRP上昇)が著明で、多臓器障害や血球貪食症候群(MAS)を合併しやすく、強力な抗炎症療法が必要となります。
一方、慢性関節炎型は初期に全身症状を伴っても最終的に関節病変が主体となり、関節リウマチに準じた治療戦略が奏功しうるとされています。
発症時の因子では、高熱(>39℃)や肝酵素・CRP高値は全身型を予測し、女性・多関節炎の存在・ステロイド依存は慢性関節型に関連すると報告されています。
成人スティル病(AOSD)の症状
成人スティル病の症状は、高熱、関節炎、皮疹の3つが三大症状です。
それに加え、リンパ節の腫れや肝臓・脾臓の腫大、喉の痛みなど多岐にわたります。
これらが重なるため生活に支障が出やすく、体力が著しく消耗しやすいです。早期診断と治療が重要です。
高熱
成人スティル病の代表的な症状に高熱があります。朝の体温が平熱に近くても、夕方から夜にかけて急激に上がるケースが多いです。
39℃以上のスパイク状高熱が特徴で、頻回に繰り返す発熱による疲労や脱水が深刻化するリスクがあります。
解熱剤を使用するケースが多いですが、一時的に体温を下げても炎症が続くと再び高熱になる可能性があります。
高熱による影響
| 影響 | 内容 |
|---|---|
| 脱水 | 汗や発熱による水分消耗が激しく、水分補給が重要 |
| 倦怠感 | 熱による体力消耗で日常活動の維持が難しくなる |
| 眠りの質の低下 | 就寝中に熱が上がる場合、睡眠の質が下がり疲労が続く |
| 意識障害 | 熱が極端に高い場合、思考力や判断力が低下する恐れ |
関節症状
成人スティル病では、強い関節の痛みや腫れが特徴的です。
手首や膝などの関節が痛みやすい傾向がありますが、指関節などの小さな関節も複数同時に侵される場合があります。
炎症によって関節が腫れ、熱感を伴うと日常生活動作が困難になる人もいます。
皮疹
皮膚に淡いピンク色やサーモンピンク色の発疹が出るケースがあります。全身に広がる場合もあれば、体幹部や四肢だけに限定的に出る場合もあります。
四肢近位部や体幹に出現し、発熱時に増悪し解熱とともに消退する移動性の発疹が特徴的です。
一般的にかゆみは強くありませんが、人によっては発熱時に大きく赤みが増します。
その他の症状
成人スティル病では、発熱、関節痛、皮疹の3つだけでなく、リンパ節や肝臓の腫れ、喉の痛みなどもみられます。
倦怠感や食欲不振が長引くと体重減少を招きやすく、栄養状態の悪化が回復を遅らせる可能性があります。
重篤な合併症としてマクロファージ活性化症候群(MAS:続発性血球貪食症候群)が10~15%の患者に合併しうると知られています。
- 高熱は断続的に出る場合が多い
- 関節痛の部位や強度に変動がある
- 皮疹は特徴的だが個人差が大きい
- 全身的な倦怠感を見過ごすと体力低下が進みやすい
成人スティル病(AOSD)の原因
成人スティル病の明確な原因は解明されていません。
感染症や環境要因が発症の誘因として報告されており、発症前にサイトメガロウイルスやEBウイルス、インフルエンザやマイコプラズマ、肝炎ウイルスなどの感染を契機とした例があるものの、特定の病原体との因果関係は証明されていません。
現在有力視されているのは自己炎症(オートインフラメーション)機序であり、先天的免疫系の異常な活性化が中心的役割を果たすと考えられています。
自己免疫異常
マクロファージや単球といった白血球の一部が過剰に活性化し、炎症性サイトカイン(インターロイキン(IL)-1βやIL-18など)を大量産生することで全身の強い炎症反応(高熱、関節炎など)が引き起こされていると推定されています。
IL-1β過剰産生はAOSDの病態のホールマーク(特徴的所見)とされ、IL-18とともにIL-6、IL-8、IL-17、TNFαなど多数の炎症性サイトカインカスケードを惹起して疾患を進行させます。
こうしたサイトカインの異常高値(特にIL-18の著増)は本疾患でしばしば観察されますが、現在のところ日常診療で測定可能な施設は限られており、診断補助には主にフェリチン高値などが用いられます。
自己免疫異常のメカニズム概要
| 流れ | 内容 |
|---|---|
| 1.誘因 | ウイルス・細菌感染などによる免疫系の刺激 |
| 2.自己攻撃 | 免疫細胞が自己の組織を攻撃して炎症を引き起こす |
| 3.症状発現 | 高熱や関節痛、皮疹など全身性の炎症症状 |
| 4.持続化 | 過剰に働く免疫反応が長期化し慢性的に炎症が続く |
遺伝的素因
遺伝的素因については明確ではないものの、HLA遺伝子との関連が報告されています。
例としてHLA-DRB115:01やDRB112、HLA-B17, B18, B35といった遺伝子が感受性に関与する可能性が指摘されています。
とはいえ、家族内発症は極めて稀であり、強い遺伝性疾患ではないと考えられます。
環境要因
生活環境やストレス、感染症などの外的要因が引き金となる可能性があります。
ストレスが免疫バランスを崩し、ウイルスや細菌に感染したタイミングと重なってしまうと、自己免疫の破綻が起きるという考え方です。
総じて、成人スティル病は感染誘発など環境因子が特定の遺伝的背景を有する個体で免疫システムの異常反応を引き起こし、炎症暴走(サイトカインストーム)に至る多因子疾患と推定されています。
- 自己免疫の破綻が中心的なメカニズム
- ウイルス感染や細菌感染が発症契機になる場合がある
- 遺伝要因と環境要因の相互作用が発症リスクを高める
- 根本的原因の解明は研究が続けられている
成人スティル病(AOSD)の検査・チェック方法
成人スティル病は確立した単一の検査方法がなく、複数の検査結果や臨床症状を総合して診断を行います。
感染症や他の自己免疫疾患との鑑別が必要となり、医師は血液検査や画像検査、病歴や身体所見を含めて慎重に検討します。
血液検査
炎症反応の指標であるCRPや赤沈(ESR)、肝機能異常やフェリチン値などを調べます。
成人スティル病の患者はフェリチン値が著しく上昇する傾向があり、診断の目安としてよくチェックします。
免疫系の異常を示す自己抗体が検出されない場合が多く、他の自己免疫疾患と区別する材料にもなります。
血液検査の主な項目
| 検査項目 | 特徴 |
|---|---|
| CRP | 炎症の程度を示す指標 |
| ESR(赤沈) | 炎症があると上昇しやすい |
| フェリチン | 高値になると成人スティル病の可能性あり |
| 肝機能 | ASTやALT、γ-GTPなどの値をチェック |
画像検査
関節の状態を確認するためにX線やMRIを活用します。
成人スティル病では、発症早期は関節破壊が目立たない場合がありますが、長期間炎症が続くと変形や関節隙の狭小化が進む恐れがあります。
画像検査は関節の状態を把握するほか、肺や心臓などの臓器合併症が懸念される場合にはCTやエコーなども使います。
除外診断
成人スティル病と類似の症状を示す疾患がいくつか存在します。関節リウマチやエリテマトーデス、感染症などを排除する除外診断が重要です。
なかでも感染症は見過ごすと生命に関わるケースもあるため、抗菌薬などの投薬状況や病歴も踏まえ、あらゆる可能性を検討します。
- 全身性エリテマトーデス(SLE)
- 関節リウマチ(RA)
- 感染症(敗血症など)
- 結核やサルコイドーシス
病歴と身体所見
医師は高熱の経過や関節痛の出現時期、発疹の有無など詳しい病歴を確認します。
身体診察では、リンパ節や肝臓・脾臓の腫大の有無、皮疹の状態などを総合的にチェックします。
問診と触診で得た情報を、画像検査や血液検査の結果と整合すると診断の精度が上がります。
主な診断指標とチェック項目
| チェック項目 | 内容 |
|---|---|
| 高熱のパターン | 39℃を超える高熱が定期的に出る |
| 関節痛の様子 | 複数箇所、または対称的に痛みがある |
| 皮疹の特徴 | サーモンピンク色の発疹、かゆみは少ない |
| 血液検査での所見 | フェリチン値高値、自己抗体は陰性のことが多い |
| 内臓合併症の兆候 | 肝・脾腫大、リンパ節の腫れ |
診断基準
現在広く用いられているのは山口基準(Yamaguchi基準, 1992年)およびFautrel基準 (2002年)の2つです。
山口基準は感度・特異度が高く日本でも採用されています。
山口(Yamaguchi)分類基準
発熱、関節痛、定型発疹、白血球増多を「大項目」、咽頭痛、リンパ節腫脹または脾腫、肝機能異常、RF陰性/ANA陰性を「小項目」とし、除外すべき疾患を除外した上で大項目≧2項目を含む計5項目以上を満たせばAOSDと分類します。
具体的には「①39℃以上の発熱が1週間以上持続、②関節痛(関節炎)が2週間以上持続、③定型的皮疹、④白血球1万/μL以上かつ好中球80%以上」という4つの大項目と、「①咽頭痛、②リンパ節腫脹または脾腫、③肝機能異常、④リウマトイド因子陰性かつ抗核抗体陰性」の小項目があります。
感度は約93.5%、特異度は約92%と報告されています(除外項目の精査に依存)。
Fautrel診断基準
山口基準にフェリチンの指標を加え除外項目を不要とした欧州の基準です。
主要項目に「高フェリチン血症とフェリチン糖化率≦20%」が含まれる点が特徴で、この低糖化フェリチンはAOSDで特異的に認められる所見です。
Fautrel基準では主要項目6つ(39℃以上の発熱、関節痛、定型皮疹、咽頭痛、好中球80%以上、糖化フェリチン≦20%)のうち4つ以上、または主要項目3つ+副項目2つ(リンパ節腫脹/脾腫、肝酵素上昇、白血球増多、RF陰性/ANA陰性)で診断とされます。
糖化フェリチンとは血中フェリチン中の糖鎖付加フェリチンの割合で、成人スティル病では異常に低下することが知られ、20%以下であれば本症を強く示唆します。
Fautrel基準は除外疾患の検討が不要という利点がありますが、糖化フェリチン測定が一般に普及しておらず、日本では主に山口基準が用いられています。
成人スティル病(AOSD)の治療方法と治療薬、リハビリテーション、治療期間
炎症をコントロールし、臓器障害やMASへの進展を防ぐのが成人スティル病の主な治療です。
急性期の炎症を抑えつつ、長期的な関節機能の維持と合併症の予防を図ります。ステロイド療法や免疫調整薬、リハビリテーションを組み合わせるケースが多いです。
ステロイド療法
ステロイド薬(プレドニゾロンなど)は、炎症を強力に抑える力があります。急性期の強い発熱や関節痛に対して使用するケースが多く、中等症~重症例では第一選択となります。
初期には高用量で症状を抑制し、徐々に減量していきます。症状が落ち着くと低用量で維持する場合もあり、医師の指導のもとで服用量を調整します。
| 概要 | 内容 |
|---|---|
| 使用目的 | 炎症と免疫反応のコントロール |
| 投与方法 | 経口薬が主流だが、点滴投与を行う場合もある |
| 治療期間の目安 | 数週間~数か月かけて徐々に減量 |
| 維持量 | 症状と検査結果によって異なる |
免疫調整薬・免疫抑制薬
ステロイド療法だけでは十分な効果が得られない場合や、ステロイドの副作用を抑えたい場合に、免疫調整薬(メトトレキサートなど)を併用します。
これらの薬は免疫系の過剰反応を抑える目的で使われ、慢性的な炎症を抑制する効果が期待できます。
必要に応じて生物学的製剤(インターロイキン-1阻害薬、インターロイキン-6阻害薬など)を使う場合もあります。
リハビリテーション
関節痛や炎症が強いと、身体を動かすのが難しくなり筋力が低下しやすいです。
理学療法士などの指導のもとで、痛みが少ない範囲で可動域訓練や筋力維持トレーニングに取り組むと、関節の機能維持や体力の回復につながります。
無理に負荷をかけると悪化する恐れがあるため、専門家による段階的なプログラムが望ましいです。
リハビリテーションのメリット
- 筋力低下を防ぎ、関節機能を温存しやすい
- 継続的に動かすことで血行が良くなり痛みが緩和しやすい
- ストレッチや軽い運動で可動域を維持する
- 日常生活動作をスムーズにするための工夫を学べる
治療期間の目安
急性期の炎症がおさまるまでに数週間から数か月かかる人が多いです。
その後、ステロイドを含む薬物療法を減量しながらリハビリを並行して行い、症状や検査データが落ち着いた状態を維持できるようにします。
人によっては再発を繰り返すケースもあり、長期的な通院が必要になる場合があります。
完治をめざすというよりも、症状をコントロールしながら生活の質を高める考え方が重要です。
治療期間の例
| 病期 | 機関の目安 | 目的 |
|---|---|---|
| 急性期 | 数週間~数か月 | 高熱や激しい炎症を抑える |
| 軽快期 | 数か月~1年程度 | ステロイド減量、免疫調整薬の調整 |
| 維持期(再燃予防) | 個人差あり(数年に及ぶ場合も) | リハビリ継続、低用量ステロイドや免疫調整薬で症状コントロール |
薬の副作用や治療のデメリット
治療に用いるステロイドや免疫調整薬には、さまざまな副作用やデメリットが存在します。
治療のメリットと副作用リスクを比較しながら、医師が治療計画を組み立てます。患者さんも副作用について理解し、自己判断で薬を中止せず、医療チームと相談しながら対応することが大切です。
ステロイドの副作用
ステロイド薬は炎症を抑える効果が高い一方で、副作用として体重増加やむくみ、血糖値の上昇、骨粗しょう症などが起こるときがあります。
長期使用で胃腸障害や感染症リスクが増大する可能性もあります。
急に中断するとリバウンドが発生し、症状が急激に悪化する恐れがあるため、減量は慎重に行う必要があります。
| 副作用 | 内容 |
|---|---|
| 体重増加 | 食欲増進や水分貯留の増加 |
| 骨粗しょう症 | 骨密度の低下で骨折リスクが高くなる |
| 血糖値上昇 | ステロイド誘発性糖尿病になる場合もある |
| 胃腸障害 | 胃痛や胃潰瘍などを引き起こすリスクがある |
| 免疫力の低下 | 感染症にかかりやすくなる |
免疫調整薬の副作用
メトトレキサートや生物学的製剤などは免疫系への働きかけが強力なので、感染リスクの上昇や肝機能障害、血液障害などが生じる可能性があります。
定期的に血液検査を受け、肝機能や白血球数をチェックするなどのモニタリングが重要です。
治療デメリット
強力な薬剤を使うと症状コントロールが期待できますが、長期的には副作用の蓄積や生活習慣の制限が課題になります。
ステロイドの長期投与は骨や筋肉、内分泌系への影響が大きく、医師と相談しながら投与量や投与期間を調整する必要があります。
また、高額な生物学的製剤を使う場合は経済的負担も大きくなります。
- 副作用のサインを早期に察知し、医師と相談する
- 定期的な血液検査や骨密度検査を受ける
- 生活習慣(食事、運動、禁煙)を見直し、副作用リスクを下げる
- 医師の指示なしに自己判断で薬をやめない
保険適用と治療費
以下に記載している治療費(医療費)は目安であり、実際の費用は症状や治療内容、保険適用否により大幅に上回ることがございます。当院では料金に関する以下説明の不備や相違について、一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。
成人スティル病は厚生労働省の指定難病に該当し、医療費助成の対象となる可能性があります。具体的な手続きや負担額は各自治体や所得により異なるため、主治医や役所の窓口で確認が必要です。
治療費には外来診察料や検査費用、薬剤費などが含まれます。
保険適用
成人スティル病で使用する薬剤のほとんどは健康保険(公的医療保険)の適用が受けられます。
さらに指定難病のため、特定医療費助成制度※1が活用できます。その際、医師の診断書などが必要です。
※1特定医療費助成制度:指定難病と診断されて、重症度基準を満たす人、または軽症であっても高額な医療費が継続する場合に医療費の自己負担額が軽減される。上限額は所得に応じて設定。
該当する場合は条件を確認し、早めに申請するほうが負担軽減につながります。
保険適用のポイント
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 健康保険の利用 | 通常3割負担が基本(年齢や所得で異なる場合あり) |
| 特定医療費助成制度 | 所得に応じて自己負担の上限額が決まる |
| 申請手続きに必要な書類 | 診断書、申請書、マイナンバーなど |
| 申請窓口 | 自治体の保健所または役所担当課 |
治療費の目安
薬剤費は使用する薬の種類や量、頻度によって大きく変わります。
ステロイドだけで症状をコントロールできる場合、自己負担は月あたり数千円~1万円程度になる人が多いですが、生物学的製剤を使用すると月あたりの自己負担が3万円~5万円になるケースも珍しくありません。
検査費や通院費を含めると、合計で月あたり数万円から数十万円に及ぶ場合があります。
生活面のサポート
医療費助成以外にも、障害年金や休業補償、介護保険など活用できる制度があります。
仕事を続けながら治療を行う場合は、職場の理解を得やすくするために診断書を活用し、労働条件の調整を相談すると良いです。
- 難病指定を受けると自己負担が減る場合がある
- 生物学的製剤の利用では負担額が高くなることがある
- 定期的な検査や通院費を含めて総合的に見積もる
- 社会保障制度を活用するために早めの情報収集を行う
成人スティル病(AOSD)は症状が多岐にわたり、原因が複雑である分、自己判断だけで対応するのは難しい病気です。
少しでも不調を感じたら早めに受診し、医師や専門スタッフとともに継続的な治療プランを組み立てることが大切です。
整形外科クリニックやリウマチ科の専門医と連携しながら、焦らず治療を続けましょう。
以上
参考文献
GERFAUD-VALENTIN, Mathieu, et al. Adult-onset Still’s disease. Autoimmunity reviews, 2014, 13.7: 708-722.
EFTHIMIOU, Petros; PAIK, P. K.; BIELORY, Leonard. Diagnosis and management of adult onset Still’s disease. Annals of the rheumatic diseases, 2006, 65.5: 564-572.
KÁDÁR, János; PETROVICZ, Edina. Adult-onset Still’s disease. Best Practice & Research Clinical Rheumatology, 2004, 18.5: 663-676.
CUSH, John J., et al. Adult‐onset still’s disease. Arthritis & Rheumatism: Official Journal of the American College of Rheumatology, 1987, 30.2: 186-194.
ELKON, K. B., et al. Adult‐onset still’s disease. Arthritis & Rheumatism: Official Journal of the American College of Rheumatology, 1982, 25.6: 647-654.
CAGATAY, Y., et al. Adult‐onset still’s disease. International journal of clinical practice, 2009, 63.7: 1050-1055.
VAN DE PUTTE, L. B. A.; WOUTERS, J. M. G. W. Adult-onset Still’s disease. Baillière’s clinical rheumatology, 1991, 5.2: 263-275.
CASTAÑEDA, Santos; BLANCO, Ricardo; GONZÁLEZ-GAY, Miguel A. Adult-onset Still’s disease: advances in the treatment. Best Practice & Research Clinical Rheumatology, 2016, 30.2: 222-238.
MITROVIC, Stéphane; FAUTREL, Bruno. New markers for adult-onset Still’s disease. Joint Bone Spine, 2018, 85.3: 285-293.
BAGNARI, Valentina, et al. Adult-onset Still’s disease. Rheumatology International, 2010, 30: 855-862.