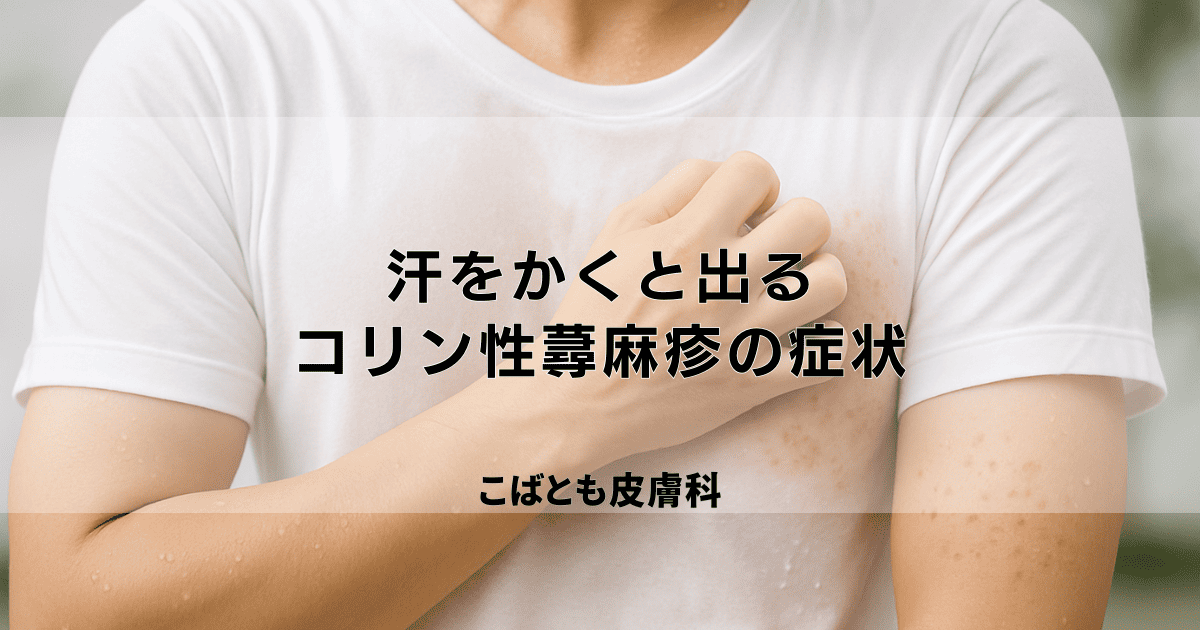運動や入浴、緊張した時など、汗をかくと同時に現れる、チクチクとしたかゆみを伴う小さなブツブツ。それは、コリン性蕁麻疹かもしれません。
コリン性蕁麻疹は、一般的な蕁麻疹とは少し異なり、特定の状況で繰り返し症状が現れるため、日常生活に大きな影響を及ぼすことがあります。
この記事では、コリン性蕁麻疹の具体的な症状から、なぜ汗で誘発されるのかという原因、皮膚科で行う治療法やご自身でできる対策まで、詳しく解説していきます。
この記事の執筆者

小林 智子(こばやし ともこ)
日本皮膚科学会認定皮膚科専門医・医学博士
こばとも皮膚科院長
2010年に日本医科大学卒業後、名古屋大学医学部皮膚科入局。同大学大学院博士課程修了後、アメリカノースウェスタン大学にて、ポストマスターフェローとして臨床研究に従事。帰国後、同志社大学生命医科学部アンチエイジングリサーチセンターにて、糖化と肌について研究を行う。専門は一般皮膚科、アレルギー、抗加齢、美容皮膚科。雑誌を中心にメディアにも多数出演。著書に『皮膚科医が実践している 極上肌のつくり方』(彩図社)など。
こばとも皮膚科関連医療機関
チクチクかゆい小さなブツブツ – コリン性蕁麻疹の典型的な症状
コリン性蕁麻疹は他の蕁麻疹とは異なる、いくつかの特徴的な症状を示します。ここでは、その典型的な症状について見ていきます。
1~4mm程度の小さな膨疹と周りの赤み
コリン性蕁麻疹の最大の特徴は、発疹の大きさです。一般的な蕁麻疹のような、地図状に広がる大きな膨らみ(膨疹)ではなく、一つひとつが1mmから4mm程度と非常に小さい、点状の膨疹が現れます。
小さな膨疹の周りが、赤く紅潮する(紅斑)ことが多く、たくさんのブツブツが密集して見えることもあります。蚊に刺された跡のような、はっきりとした膨らみとは異なり、鳥肌が立つように細かく盛り上がるのが特徴的です。
チクチクとしたかゆみやピリピリする痛み
この蕁麻疹に伴う感覚も独特です。多くの人が、通常のかゆみとは少し違う、チクチク、ピリピリとした刺激的な感覚を訴え、まるで、たくさんの細い針で刺されているような痛みを感じることもあります。
むずむずとしたかゆみを感じる人もいますが、この刺激感がコリン性蕁麻疹を疑う一つのサインです。症状が強く出ると、じっとしていられないほどの不快感を伴うことも少なくありません。
症状の主な特徴
| 項目 | コリン性蕁麻疹の特徴 | 一般的な蕁麻疹との比較 |
|---|---|---|
| 発疹の大きさ | 1~4mm程度の点状の膨疹 | 数cm以上の様々な大きさ、地図状に広がる |
| かゆみの質 | チクチク、ピリピリとした刺激感 | むずむずとした強いかゆみ |
| 持続時間 | 数分~1時間程度で消えることが多い | 数時間~24時間以内に消えることが多い |
症状が現れる部位と持続時間
発疹は、主に体幹(胸、背中、お腹)や首、腕、太ももなど、汗をかきやすい部位に現れる傾向があり、手のひらや足の裏、顔に出ることは比較的少ないとされています。
もう一つの大きな特徴が、症状の持続時間です。一度現れた発疹は、通常30分から1時間程度で、跡形もなくきれいに消えてしまいます。現れてはすぐに消えるという性質も、コリン性蕁麻疹を見分ける重要なポイントです。
全身症状を伴うケース
ほとんどの場合は皮膚症状のみですが、まれに症状が強く出た際に、全身の不調を伴うことがあります。
腹痛や下痢などの消化器症状、息苦しさやぜん鳴(ゼーゼー、ヒューヒューという呼吸音)などの呼吸器症状、頭痛などが現れることがあります。
このような症状が見られる場合は、アナフィラキシーと呼ばれる重篤なアレルギー反応の可能性も考えられるため、注意が必要です。皮膚症状以外に異変を感じた場合は、速やかに医療機関を受診してください。
なぜ汗をかくと症状が出るのか?コリン性蕁麻疹の原因
運動したり、お風呂に入ったり、緊張したり。汗をかく場面で決まって現れるコリン性蕁麻疹は、私たちの体のどのような反応によって起きるのでしょうか。
発汗を促すアセチルコリンの関与
私たちの体は、体温が上がると、汗を出すことで熱を放散し、体温を一定に保とうとします。この時、脳からの「汗を出せ」という指令を汗腺に伝えるのが、アセチルコリンという神経伝達物質です。
コリン性蕁麻疹の人はアセチルコリンに対して、皮膚にある肥満細胞(マスト細胞)が過敏に反応してしまうと考えられています。アセチルコリンの刺激を受けると、肥満細胞からヒスタミンなどの化学物質が放出されます。
ヒスタミンが、血管を広げて皮膚を赤くしたり、血管の透過性を高めて皮膚を膨らませたり(膨疹)、知覚神経を刺激してかゆみを引き起こすのです。
症状発生までの流れ
| 段階 | 体の中で起きていること |
|---|---|
| 1. 発汗刺激 | 運動、入浴、精神的緊張などで体温が上昇する。 |
| 2. 指令 | 脳が汗を出すように指令を出す。 |
| 3. 伝達物質の放出 | 神経終末からアセチルコリンが放出される。 |
| 4. 肥満細胞の反応 | アセチルコリンが肥満細胞を刺激する。 |
| 5. ヒスタミンの放出 | 肥満細胞からヒスタミンなどが放出される。 |
| 6. 症状発現 | 皮膚に膨疹、赤み、かゆみが生じる。 |
汗アレルギーとの違い
汗をかくと症状が出るため、汗そのものに対するアレルギー(汗アレルギー)と混同されることがありますが、両者は異なる状態です。
汗アレルギーは、自分自身の汗に含まれる成分が抗原(アレルゲン)となって、アレルギー反応を起こすものです。アトピー性皮膚炎の患者さんに見られることが多く、湿疹が悪化する形で現れます。
コリン性蕁麻疹は、汗の成分ではなく、発汗を促すアセチルコリンという体内の物質に反応して起こるもので、症状も一過性の蕁麻疹です。
発症しやすい年代や体質
コリン性蕁麻疹は、比較的若い世代、特に10代から30代の思春期から青年期にかけて発症することが多いです。男性にやや多く、また、アトピー性皮膚炎の素因を持つ人に発症しやすいという報告もあります。
はっきりとした遺伝性はありませんが、アレルギー体質が何らかの形で関わっている可能性も考えられています。多くの場合、年齢とともに症状が軽快していく傾向がありますが、中には長年にわたって症状に悩まされる人もいます。
コリン性蕁麻疹が出やすい状況
コリン性蕁麻疹は、発汗を伴う場面で誘発されます。どのような時に症状が出やすいのかをあらかじめ知っておくことは、症状を予測し、対策を立てる上で役立ちます。
運動や入浴による体温の上昇
最も典型的な誘因は、運動や入浴によって体温が上昇し、汗をかくことです。ランニングや筋力トレーニングなどの激しい運動はもちろん、少し早歩きをしただけでも症状が出ることがあります。
また、熱いお風呂やシャワー、サウナなども同様に症状を起こす原因となり、体の深部体温が上昇することが、発汗とアセチルコリンの放出の引き金です。
症状を誘発しやすい活動
- ランニング、ジョギング、球技などのスポーツ
- 筋力トレーニング
- 熱いお風呂への長時間の入浴、サウナ
- 暖かい布団に入った時
- 夏場の屋外での活動
精神的な緊張やストレス
人前で発表する時や、試験を受ける時、重要な会議の前など、精神的に緊張したり興奮したりする場面でも汗をかくことがあります。これは精神性発汗と呼ばれ、体温調節とは別の理由で起こる発汗です。
精神性発汗でもアセチルコリンが関与するため、コリン性蕁麻疹が誘発されることがあります。ストレスを感じた時に、急にかゆみやブツブツが現れる場合は、このパターンが考えられます。
精神的な誘因の例
| 感情 | 具体的な状況 |
|---|---|
| 緊張・不安 | 試験、面接、プレゼンテーション |
| 興奮・怒り | スポーツ観戦、口論 |
| 喜び・感動 | ライブ、映画鑑賞 |
辛いものや熱いものを食べた時
香辛料の効いた辛い料理や、熱々のラーメンなどを食べた時に、顔や頭から汗が噴き出す経験をしたことがある人は多いでしょう。これは味覚性発汗と呼ばれる反応で、これもまたコリン性蕁麻疹の引き金になり得ます。
食事中に症状が現れる場合は食べ物そのものへのアレルギーではなく、味覚性発汗が原因である可能性を疑う必要があります。
他の蕁麻疹や皮膚疾患との見分け方
皮膚に現れるブツブツやかゆみは、様々な病気の可能性があります。ここでは、似たような症状を示す他の病気との違いについて解説します。
一般的な蕁麻疹との違い
最も大きな違いは、発疹の形と大きさです。一般的な蕁麻疹(急性蕁麻疹や慢性蕁麻疹)では、数cm以上の、まるで蚊に刺された跡がくっつき合ったような、境界のはっきりした地図状の膨疹が見られます。
コリン性蕁麻疹は1~4mm程度の点状の小さな膨疹です。また、誘因が発汗という物理的な刺激にはっきりと関連している点も、原因が多岐にわたる一般的な蕁麻疹との大きな違いです。
症状による見分け方のポイント
| 項目 | コリン性蕁麻疹 | 一般的な蕁麻疹 | あせも(汗疹) |
|---|---|---|---|
| 発疹の形 | 点状の小さな膨疹 | 地図状の大きな膨疹 | 小さな水疱や赤いブツブツ |
| 持続時間 | 短時間(~1時間)で消える | 数時間~24時間で消える | 数日間続くことがある |
| 主な誘因 | 発汗(運動、入浴など) | 食物、薬剤、ストレスなど様々 | 汗の詰まり、蒸れ |
あせも(汗疹)との見分け方
汗をかくことで悪化する皮膚疾患として、あせも(汗疹)もよく知られています。あせもは、汗を排出する管(汗管)が詰まり、汗が皮膚の中に溜まってしまうことで起こる炎症です。
赤いブツブツ(紅色汗疹)や、透明な小さな水ぶくれ(水晶様汗疹)として現れます。
蕁麻疹のように数時間で消えることはなく、数日間症状が続き、また、かゆみの質も、チクチクとした刺激感よりは、むずがゆい感じが主となります。
アナフィラキシーとの関連性
非常にまれですが、コリン性蕁麻疹が、食物依存性運動誘発アナフィラキシーという重篤な状態の一症状として現れることがあります。
これは、特定の食物を食べた後に運動をすると、蕁麻疹だけでなく、呼吸困難や血圧低下などの激しい全身症状(アナフィラキシーショック)を起こすものです。
皮膚症状に加えて、息苦しさやめまい、腹痛などが現れた場合は、命に関わる危険な状態の可能性があるため、直ちに救急要請をする必要があります。
症状が出たら何科へ?皮膚科での診断と検査
コリン性蕁麻疹が疑われる症状に気づいたら、自己判断で悩まずに専門医に相談することが大切です。適切な診断を受けることで、症状の原因がはっきりし、効果的な治療へとつなげることができます。
専門は皮膚科
蕁麻疹をはじめとする皮膚の症状は、皮膚科が専門です。皮膚科医は、様々な皮膚疾患に関する深い知識と経験を持っており、問診や視診、必要な検査を通じて正確な診断を下します。
コリン性蕁麻疹は特徴的な症状や誘因から、専門医であれば比較的診断がつきやすい疾患です。
問診で重要な情報
診断において、患者さんからの情報は非常に重要で、医師は、以下のような点について詳しく質問します。
問診で伝えるべきポイント
- いつから症状が始まったか
- どのような時に症状が出るか(運動、入浴、緊張など)
- どのような発疹か(大きさ、形、色)
- どのような感覚か(かゆみ、チクチク感、痛み)
- どのくらいの時間で症状が消えるか
- 現在治療中の病気や、服用している薬はあるか
可能であれば、症状が出ている時の皮膚の写真をスマートフォンなどで撮影しておくと、医師が診断する上で参考になります。
診断を確定させるための誘発試験
問診や視診でコリン性蕁麻疹が強く疑われるものの、診断を確定させたい場合や、他の疾患との鑑別が必要な場合には、誘発試験を行うことがあります。これは、意図的に発汗を促して、実際に蕁麻疹が誘発されるかを確認する検査です。
主な誘発試験の方法
| 試験方法 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 運動負荷試験 | エアロバイクを漕ぐ、踏み台昇降運動を行うなど。 | 最も一般的な方法。 |
| 温熱負荷試験 | 40℃前後の温水に手や足を浸ける、または全身を温める。 | 運動が困難な場合などに行う。 |
| 薬剤貼付試験 | アセチルコリンに似た作用を持つ薬剤を皮膚に貼る。 | 局所的に反応を見る。 |
コリン性蕁麻疹の治療法 – 症状を抑える薬と対処
つらい症状を和らげ、快適な生活を送るために、皮膚科では様々な治療法を提案します。治療の基本は、症状を引き起こすヒスタミンの働きをブロックすることです。
治療の第一選択は抗ヒスタミン薬
コリン性蕁麻疹の治療において、中心的な役割を果たすのが抗ヒスタミン薬の飲み薬です。抗ヒスタミン薬は、肥満細胞から放出されたヒスタミンが、神経や血管に作用するのを防ぎ、かゆみや膨疹、赤みといった症状を抑えることができます。
抗ヒスタミン薬には、眠気が出やすい第一世代と、眠気が出にくい第二世代があります。現在は、日常生活への影響が少ない第二世代の抗ヒスタミン薬を主に使用します。
毎日定期的に服用することで、症状が出にくい状態を維持することを目指します。
症状が強い場合の追加治療
抗ヒスタミン薬だけでは十分に症状をコントロールできない重症の場合には、他の治療法を組み合わせることがあります。
抗ヒスタミン薬の増量や種類の変更、胃薬の一種であるH2ブロッカーの併用、発汗を抑える作用のある抗コリン薬の内服などを検討します。また、アレルギー反応を抑える別の種類の薬を追加することもあります。
ステロイドの塗り薬は、コリン性蕁麻疹にはあまり効果が期待できないことが多いです。
治療薬の選択肢
| 薬剤の種類 | 主な作用 | 備考 |
|---|---|---|
| 抗ヒスタミン薬(内服) | ヒスタミンの働きを抑える。 | 治療の基本。眠気の少ない第二世代が主流。 |
| 抗コリン薬(内服) | アセチルコリンの働きを抑え、発汗を抑制する。 | 口の渇きなどの副作用に注意が必要。 |
| 漢方薬 | 体質改善を目指す。 | 補助的な治療として用いることがある。 |
汗に慣れる脱感作療法という考え方
薬物療法と並行して、あるいは薬を減らすための試みとして、汗に体を慣らしていく方法(脱感作療法)が有効な場合があります。
これは、あえて軽い運動などで少しずつ汗をかく習慣をつけ、体が発汗の刺激に過剰に反応しないように慣れさせていくという考え方です。
ただし、自己判断で行うと強い症状を誘発する危険があるため、必ず医師の指導のもとで、症状がコントロールできている状態から慎重に始める必要があります。
急に激しい運動をするのではなく、ウォーキングなどから少しずつ負荷を上げていくのがポイントです。
日常生活でできる予防とセルフケア
薬による治療と合わせて、日々の生活の中で少し工夫をすることで、症状の発生を減らしたり、悪化を防いだりすることが可能です。自分の症状の引き金を知り、上手に対処していくことが、コリン性蕁麻疹と付き合っていく上で大切です。
発汗を上手にコントロールする
症状の引き金となる発汗を、完全に避けることは現実的ではありません。大切なのは、急激な体温上昇や大量の発汗を避ける工夫をすることです。
運動前には十分なウォーミングアップを行い、体を徐々に温め、服装は通気性や吸湿性の良い素材を選び、熱がこもらないように重ね着で調整できるようにすると良いでしょう。
入浴は、熱すぎるお湯を避け、ぬるめのお湯に短時間つかるように心がけます。
生活場面ごとの工夫
- 運動時:通気性の良いウェアを着用し、こまめに休憩をとる。
- 入浴時:ぬるめのお湯に設定し、長湯を避ける。
- 食事時:極端に辛いものや熱いものは、少し冷ましてから食べる。
- 就寝時:寝具を通気性の良いものにし、室温を快適に保つ。
ストレスとの付き合い方
精神的な緊張も大きな誘因となるため、ストレスを溜めないように心がけることも重要です。自分なりのリラックス方法を見つけ、心に余裕を持つ時間を作りましょう。
十分な睡眠をとる、趣味に没頭する、軽いストレッチや深呼吸で心身をほぐすなど、日常生活の中で実践できることはたくさんあります。
ストレスを完全になくすことは難しいですが、上手に対処する方法を身につけることで、症状の誘発を減らすことができます。
皮膚を清潔に保つことの重要性
汗をかいた後は、そのまま放置せず、できるだけ速やかにシャワーを浴びるか、濡れたタオルで優しく拭き取るようにしましょう。皮膚を清潔に保つことは、あせもなど他の皮膚トラブルの予防にもつながります。
ただし、ナイロンタオルなどでゴシゴシこすると、皮膚への刺激が新たな症状を誘発することもあるため、石鹸をよく泡立てて、手で優しく洗うようにしてください。洗浄後は、保湿剤で皮膚のバリア機能を整えることも大切です。
よくある質問
最後に、コリン性蕁麻疹について患者さんから寄せられることの多い質問にお答えします。
- コリン性蕁麻疹は治りますか?
-
コリン性蕁麻疹は、多くの場合、年齢とともに自然に症状が軽快したり、出なくなったりする傾向があります。特に、10代で発症した場合、数年から10年程度で治まることが多いです。
ただし、症状が長く続く人もいるため、一概には言えません。適切な治療で症状をコントロールしながら、気長に付き合っていくという視点も大切です。
完治を目指すというよりは、症状が出ないように上手にコントロールし、日常生活に支障がない状態を維持することが現実的な目標となります。
- 薬はいつまで飲み続ける必要がありますか?
-
薬を飲む期間は、症状の重症度や経過によって人それぞれです。
まずは症状がしっかりと抑えられる状態を数ヶ月維持し、その後、医師と相談しながら、徐々に薬の量を減らしたり、症状が出そうな時だけ服用する頓服に切り替えたりすることを検討します。
汗をかきやすい夏場だけ薬を服用し、冬場は休薬できるという人もいます。自己判断で中断せず、必ず医師の指示に従ってください。
- 子どもでも発症しますか?
-
発症のピークは10代から30代ですが、小学生くらいの子どもでも発症することはあります。部活動などで活発に運動する子どもが、運動後に体のかゆみを訴える場合、コリン性蕁麻疹の可能性があります。
子どもの場合は、自分の症状をうまく説明できないこともあるため、保護者の方がどのような時に症状が出るのかをよく観察して、皮膚科に相談することが大切です。
治療は、基本的に大人と同じく抗ヒスタミン薬の内服が中心となります。
- 食事で気をつけることはありますか?
-
コリン性蕁麻疹は、特定の食物アレルギーとは異なるため、基本的に食事制限は必要ありません。ただし、香辛料を多く使った極端に辛いものや、熱々の食べ物は、味覚性発汗を誘発して症状の引き金になることがあります。
もし、特定の食事の後に症状が出ることが多いと感じる場合は、その食事を避けるようにすると良いでしょう。
以上
参考文献
Fukunaga A, Oda Y, Imamura S, Mizuno M, Fukumoto T, Washio K. Cholinergic urticaria: subtype classification and clinical approach. American Journal of Clinical Dermatology. 2023 Jan;24(1):41-54.
Fukunaga A, Washio K, Hatakeyama M, Oda Y, Ogura K, Horikawa T, Nishigori C. Cholinergic urticaria: epidemiology, physiopathology, new categorization, and management. Clinical Autonomic Research. 2018 Feb;28(1):103-13.
Iijima S, Kojo K, Takayama N, Hiragun M, Kan T, Hide M. Case of cholinergic urticaria accompanied by anaphylaxis. The Journal of Dermatology. 2017 Nov;44(11):1291-4.
Horikawa T, Fukunaga A, Nishigori C. New concepts of hive formation in cholinergic urticaria. Current allergy and asthma reports. 2009 Jul;9(4):273-9.
Bito T, Sawada Y, Tokura Y. Pathogenesis of cholinergic urticaria in relation to sweating. Allergology International. 2012;61(4):539-44.
Nakamizo S, Egawa G, Miyachi Y, Kabashima K. Cholinergic urticaria: pathogenesis‐based categorization and its treatment options. Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology. 2012 Jan;26(1):114-6.
Nagai M, Fukumoto T, Imamura S, Oda Y, Mizuno M, Ohata M, Kubo A, Fukunaga A. Use of the Rash Appearance to Distinguish Cholinergic Urticaria Subtypes: A Retrospective Cohort Study. American Journal of Clinical Dermatology. 2025 Jul 26:1-9.
Nishino A, Adachi A, Omigawa C, Takeshita H, Sawada Y. A Case of Complication of Adrenergic Urticaria and Acquired Idiopathic Generalized Anhidrosis With Cholinergic Urticaria. The Journal of Dermatology. 2025 May 5.
Kozaru T, Fukunaga A, Taguchi K, Ogura K, Nagano T, Oka M, Horikawa T, Nishigori C. Rapid desensitization with autologous sweat in cholinergic urticaria. Allergology International. 2011 Jan 1;60(3):277-81.
Nakamizo S, Kurosawa M, Sawada Y, Tokura Y, Miyachi Y, Kabashima K. A case of cholinergic urticaria associated with acquired generalized hypohidrosis and reduced acetylcholine receptors: cause and effect?. Clinical and experimental dermatology. 2011 Jul 1;36(5):559-60.