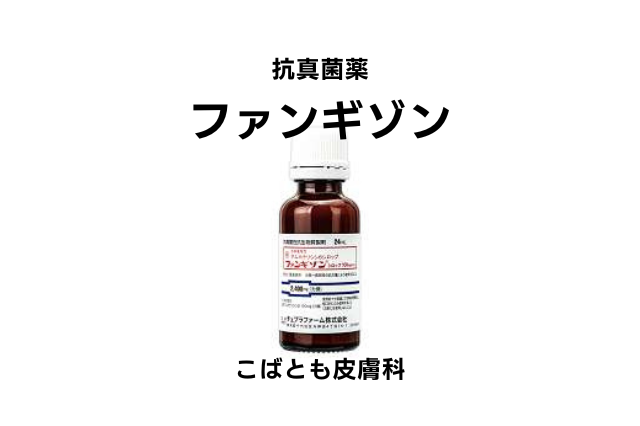アムホテリシンB(ファンギゾン)とは、お口の中に発生する真菌(カビ)の一種、カンジダ菌によって起きる口腔カンジダ症の治療に用いられる、抗真菌薬です。
口の中に白い苔のようなものが付着する、舌や粘膜が赤くなりヒリヒリと痛む、といった症状の改善に効果を発揮します。有効成分であるアムホテリシンBが、カンジダ菌の細胞膜に直接作用して破壊することで、原因菌を殺菌します。
この記事では、ファンギゾンがどのように作用するのか、効果や正しい使い方、治療期間、考えられる副作用について、詳しく解説します。
この記事の執筆者

小林 智子(こばやし ともこ)
日本皮膚科学会認定皮膚科専門医・医学博士
こばとも皮膚科院長
2010年に日本医科大学卒業後、名古屋大学医学部皮膚科入局。同大学大学院博士課程修了後、アメリカノースウェスタン大学にて、ポストマスターフェローとして臨床研究に従事。帰国後、同志社大学生命医科学部アンチエイジングリサーチセンターにて、糖化と肌について研究を行う。専門は一般皮膚科、アレルギー、抗加齢、美容皮膚科。雑誌を中心にメディアにも多数出演。著書に『皮膚科医が実践している 極上肌のつくり方』(彩図社)など。
こばとも皮膚科関連医療機関
アムホテリシンB(ファンギゾン)の有効成分と効果、作用機序
アムホテリシンB(ファンギゾン)が、なぜお口の中の不快な症状に効果を示すのか、有効成分の働きと効果の仕組みについて掘り下げていきます。
有効成分アムホテリシンBとは
アムホテリシンBは、土壌中に存在する放線菌という微生物が作り出す物質から発見された、ポリエン系というグループに分類される抗生物質です。
抗生物質という言葉から細菌感染症の薬を想像するかもしれませんが、アムホテリシンBは細菌には効果を示さず、真菌に対して選択的に強い活性を持つというユニークな特徴があります。
主な効果と適応疾患:口腔カンジダ症
ファンギゾンは、消化管カンジダ症の治療薬であり、特に口の中に発症する口腔カンジダ症に対して頻繁に処方されます。カンジダ菌は健康な人の口の中にも存在する常在菌ですが、体の抵抗力が落ちた時などに異常増殖して症状を引き起こします。
| 口腔カンジダ症の主な種類 | 特徴的な症状 |
|---|---|
| 偽膜性(ぎまくせい)カンジダ症 | 最も一般的なタイプ。頬の内側、舌、上あごなどに、こすると剥がせる白い苔のような膜(偽膜)が付着します。鵞口瘡(がこうそう)とも呼ばれます。 |
| 萎縮性(いしゅくせい)カンジダ症 | 舌の表面が赤く平らになったり、口の中の粘膜が赤くなってヒリヒリとした痛みを感じたりします。入れ歯の下に起こりやすいです。 |
| 肥厚性(ひこうせい)カンジダ症 | 白い膜が厚くなり、こすっても剥がしにくくなります。 |
| 口角炎 | 口の端(口角)が赤く切れたり、ただれたりします。カンジダ菌が原因の場合もあります。 |
作用機序
真菌の細胞膜を構成する主要な成分に、エルゴステロールという物質があり、人間の細胞膜には存在しない、真菌特有の成分です。
アムホテリシンBは、エルゴステロールに強力に結合する性質を持ち、結合すると、アムホテリシンB分子が複数集まって細胞膜に小さな穴(イオンチャネル)を形成します。
この穴から、細胞の生命維持に重要なカリウムイオンなどが細胞外へ漏れ出してしまうため、カンジダ菌は生存できなくなり死滅します。
他の口腔用抗真菌薬との違い
口腔カンジダ症の治療には、ファンギゾンの他にもいくつかの薬が用いられます。それぞれ作用の仕方が異なります。
- アゾール系(例:ミコナゾールゲル): エルゴステロールの合成を阻害することで、カンジダ菌の増殖を抑えます(静菌作用)。ゲル状の薬剤で、患部に直接塗布して使用します。
- ポリエン系(例:ファンギゾン): 既に存在するエルゴステロールに直接結合し、細胞膜を破壊します(殺菌作用)。シロップ剤で、口に含んで全体に行き渡らせてから服用します。
作用機序が異なるため、一方の薬で効果が不十分な場合に、もう一方の薬が有効であることがあります。
使用方法と注意点
薬剤の効果を最大限に引き出し、安全に治療を進めるためには、医師の指示に従って正しく使用することが何よりも重要です。ここでは、シロップ剤特有の服用方法や、使用する上での注意点について詳しく解説します。
基本的な服用方法と回数
ファンギゾンは、通常1日に2~4回毎食後に服用し、1回あたりの服用量は、年齢や症状によって医師が調整します。
大切なのは、ただ飲むのではなく、口の中全体に薬を行き渡らせることで、食後、歯磨きなどで口の中を清潔にしてから使用すると、より効果的です。
効果的な含嗽(うがい)と服用のポイント
ファンギゾンの効果を最大限に引き出すためには、以下の手順で服用することが推奨されます。
- 口に含む: 1回分のシロップを口に含みます。
- 口内に行き渡らせる: すぐに飲み込まず、頬を膨らませたり舌を動かしたりして、薬が口の中の隅々(頬の内側、舌の上、上あごなど)に行き渡るように、クチュクチュと口をすすぐようにします。
- できるだけ長く保つ: この状態を、できるだけ長く(数分間が目安)保ちます。これにより、有効成分が患部にしっかりと接触する時間を確保します。
- ゆっくり飲み込む: 口に含んだ後、ゆっくりと飲み込みます。食道にいる可能性のあるカンジダ菌にも効果を及ぼすためです。
- 服用後のうがいを避ける: 服用後30分程度は、飲食やうがいを避けてください。薬の成分が口の中に留まり、効果が持続します。
使用上の一般的な注意点
安全に治療を続けるために、以下の点を必ず守ってください。
- 指示された量を守る: 自己判断で量を増やしたり減らしたりしないでください。
- 服用前に良く振る: シロップ剤は成分が沈殿していることがあるため、毎回服用する前によく振り混ぜてから使用してください。
- 自己判断で中止しない: 症状が良くなっても、カンジダ菌が完全にいなくなったわけではありません。医師の指示があるまで服用を続けることが、再発防止のために重要です。
- 長期間使用しても改善しない場合は相談する: 指示通りに使用しても症状が改善しない、あるいは悪化する場合は、必ず医師に相談してください。
アムホテリシンB(ファンギゾン)の適応対象となる患者さん
アムホテリシンB(ファンギゾン)は、口腔カンジダ症と診断された方に処方されます。特に、どのような方がこの病気になりやすく、治療の対象となるのか、また、体の状態によって使用に配慮が必要なケースについて説明します。
口腔カンジダ症と診断された方
ファンギゾンが処方されるのは、医師が口の中を診察し、特徴的な所見から口腔カンジダ症であると診断した場合で、口の中の白い苔や粘膜の赤みは、他の病気でも見られることがあるため、専門家による診断が重要です。
確定診断のために、綿棒などで患部をこすり、それを顕微鏡で調べてカンジダ菌の存在を確認することもあります。
口腔カンジダ症になりやすい方
カンジダ菌は常在菌ですが、特定の条件下で増殖しやすくなります。以下のような方は、口腔カンジダ症のリスクが高いと考えられています。
- 乳幼児: 免疫機能が未熟なため、鵞口瘡(がこうそう)と呼ばれる口腔カンジダ症を発症しやすいです。
- 高齢者: 唾液の分泌量が減少したり、免疫力が低下したりするため、リスクが高まります。特に、入れ歯(義歯)を使用している方は、義歯の裏側でカンジダ菌が増殖しやすくなります(義歯性口内炎)。
- 薬剤を服用・使用している方: ステロイドの吸入薬を使用している方、抗菌薬(抗生物質)を長期間服用している方、免疫抑制薬を使用している方などは、口の中の菌のバランスが崩れて発症しやすくなります。
- 全身性の疾患がある方: 糖尿病や血液疾患、HIV感染症など、免疫力が低下する病気をお持ちの方は、カンジダ症を発症・再発しやすくなります。
妊娠中・授乳中の方への使用
妊娠中または授乳中の方がファンギゾンを使用する場合、その安全性は確立されていません。ファンギゾンは消化管からはほとんど吸収されないため、全身への影響は少ないと考えられていますが、リスクがゼロではありません。
治療による有益性が危険性を上回ると医師が判断した場合にのみ、慎重に使用を検討します。
アムホテリシンB(ファンギゾン)の治療期間
口腔カンジダ症の治療では、症状が消えてからも医師の指示通りに薬を使い切ることが、完全な治癒とつらい再発を防ぐために非常に重要です。
症状改善後も治療を続ける重要性
ファンギゾンを使い始めると、数日から1週間ほどで口の中の痛みやヒリヒリ感が和らぎ、白い苔が減ってくるなど、症状の改善を実感できることが多いです。
しかし、この段階で治ったと自己判断して薬をやめてしまうと、生き残っていた少数のカンジда菌が再び増殖し、症状がぶり返す原因となります。
再発を防ぐためには、目に見える症状がなくなった後も、医師から指示された期間、きちんと薬を続けることが大切です。
目安となる治療期間
治療に必要な期間は、症状の重さや患者さんの体の状態によって異なりますが、一般的な口腔カンジダ症の場合、1~2週間程度が目安となります。
| 症状の重さ | 標準的な治療期間の目安 |
|---|---|
| 軽症~中等症 | 7日~14日間 |
| 重症または免疫不全状態の方 | 14日間以上、またはそれ以上の期間が必要な場合もある |
医師は、口の中の状態を観察しながら、治療終了のタイミングを判断します。
治療終了の判断と再発予防
治療の終了は、口の中の白い苔や赤みが完全に消失し、正常な粘膜の状態に戻ったことを医師が確認してから決定し、治療が完了した後も、再発を防ぐためには日々のセルフケアが重要です。
- 口腔ケアの徹底: 毎食後と就寝前の丁寧な歯磨きを心がけ、口の中を清潔に保ちます。
- 義歯の管理: 入れ歯を使用している方は、毎日取り外して専用の洗浄剤で清潔にし、乾燥させることが重要です。就寝時は外すようにしましょう。
- うがい: 殺菌作用のあるうがい薬の使用が効果的な場合もありますが、自己判断で使わず、医師に相談してください。
- 基礎疾患の管理: 糖尿病などの持病がある方は、そのコントロールを良好に保つことが再発予防につながります。
副作用やデメリット
ファンギゾンは、消化管からほとんど吸収されないため、比較的安全性の高い薬ですが、副作用が全くないわけではありません。
主な消化器系の副作用
服用した薬が消化管を通過するため、以下のような消化器症状が現れることがあります。頻度は高くありませんが、注意が必要です。
| 主な副作用 | 症状 |
|---|---|
| 下痢・軟便 | 最も報告が多い副作用です。 |
| 腹痛 | お腹が痛くなることがあります。 |
| 悪心・嘔吐 | 吐き気や、実際に吐いてしまうことがあります。 |
| 食欲不振 | 食欲がなくなることがあります。 |
症状は多くの場合軽度ですが、症状がひどい場合や長く続く場合は、医師または薬剤師に相談してください。
口の中の局所的な副作用
まれに、薬を口に含んだ際に、舌や口の中に刺激感を感じることがあります。
副作用が起きた場合の対処法
もし、副作用と思われる症状が現れた場合は、自己判断で服用を中止する前に、まずは処方を受けた医師や薬局の薬剤師に相談してください。特に、下痢などの症状がひどい場合は、脱水症状を防ぐためにも早めの相談が重要です。
アムホテリシンB(ファンギゾン)で効果がなかった場合
医師の指示通りに毎日きちんと薬を使用しているにもかかわらず、症状が良くならない、あるいは悪化してしまうと不安になることでしょう。それにはいくつかの理由が考えられます。
考えられる原因
治療効果が見られない場合、主に以下の可能性が考えられます。
- 診断が異なる可能性: 口の中の症状が、カンジダ症ではなく、他の疾患(例えば、ウイルス性の口内炎、扁平苔癬などの粘膜疾患、アレルギーなど)による可能性があります。これらの疾患には抗真菌薬は効果がありません。
- 薬剤耐性の可能性: まれですが、原因となっているカンジダ菌がアムホテリシンBに対して抵抗性(耐性)を持ってしまい、薬が効きにくくなっている可能性があります。
- 不十分な口腔ケア: 薬を使用していても、口腔内の清掃が不十分であったり、汚れた入れ歯を使い続けたりしていると、カンジダ菌が常に供給される状態となり、治療効果が上がらないことがあります。
- 背景にある全身状態: コントロール不良の糖尿病や、未治療の免疫不全など、カンジダ症を増悪させる全身性の要因が解決されていない場合、治療が難航することがあります。
医師への相談と再評価の重要性
治療がうまくいかないと感じた際は、速やかに処方医に相談してください。医師は、再度口の中を詳しく診察し、必要であれば検査を行って診断が正しかったかを再評価します。
また、薬の使用方法や口腔ケアの状況、全身状態などを詳しく聞き取り、効果が出ない原因を探ります。
他の治療薬への変更
再評価の結果、診断は口腔カンジダ症で間違いないものの、ファンギゾンの効果が不十分と判断された場合、他の抗真菌薬への変更を検討します。
| 主な抗真菌薬の種類 | 特徴と代表的な薬剤 |
|---|---|
| アゾール系(外用ゲル) | 患部に直接塗るタイプのゲル剤。ミコナゾールゲルなど。 |
| アゾール系(内服薬) | 全身に作用する飲み薬。イトラコナゾールやフルコナゾールなど。外用薬やシロップで効果不十分な場合や重症例に用いる。 |
他の治療薬との併用禁忌
複数の薬を使用している場合、薬同士の相互作用(飲み合わせ)は常に注意が必要な点です。ファンギゾンの併用に関する注意点について解説します。
基本的に併用禁忌の薬はない理由
ファンギゾンの有効成分であるアムホテリシンBは、服用しても消化管からほとんど吸収されず、血液中に入ることがまれです。
全身に作用する他の飲み薬などとの相互作用を起こす可能性は極めて低いと考えられているため、ファンギゾンには、添付文書上、絶対に一緒に使ってはいけないとされる併用禁忌薬は定められていません。
自己判断での併用は避ける
併用禁忌薬はありませんが、だからといって自己判断で他の薬を併用するのは避けるべきです。
他の医療機関で処方された薬や、市販薬、サプリメントなどを使用している場合は、ファンギゾンを使い始める前に、必ず医師または薬剤師にその旨を伝えてください。
アムホテリシンB(ファンギゾン)の保険適用と薬価について
以下に記載している治療費(医療費)は目安であり、実際の費用は症状や治療内容、保険適用否により大幅に上回ることがございます。当院では料金に関する以下説明の不備や相違について、一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。
薬価の目安
| 薬剤名 | 規格 | 薬価(1mLあたり) |
|---|---|---|
| ファンギゾンシロップ100mg/mL | 12mL/瓶 | 24.90円 |
1回2mLを1日3回、7日間処方された場合の総量は42mLとなり、薬剤費の総額は約1,046円となります。自己負担は年齢や収入により、1~3割です。
以上
参考文献
Mitsutake K, Kohno S, Miyazaki Y, Noda T, Miyazaki H, Miyazaki T, Kaku M, Koga H, Hara K. In vitro and in vivo antifungal activities of liposomal amphotericin B, and amphotericin B lipid complex. Mycopathologia. 1994 Oct;128(1):13-7.
Umemura K, Katada Y, Nakagawa S, Hira D, Yutaka Y, Tanaka S, Ohsumi A, Nakajima D, Date H, Nagao M, Terada T. Comparison of the safety and cost-effectiveness of nebulized liposomal amphotericin B and amphotericin B deoxycholate for antifungal prophylaxis after lung transplantation. Journal of Infection and Chemotherapy. 2024 Aug 1;30(8):741-5.
Watanabe M, Hiratani T, Uchida K, Ohtsuka K, Watabe H, Inouye S, Kondo S, Takeuchi T, Yamaguchi H. The in-vitro activity of an antifungal antibiotic benanomicin A in comparison with amphotericin B. Journal of Antimicrobial Chemotherapy. 1996 Dec 1;38(6):1073-7.
Ohtsuka K, Watanabe M, Orikasa Y, Inouye S, Uchida K, Yamaguchi H, Kondo S, Takeuchi T. The in-vivo activity of an antifungal antibiotic, benanomicin A, in comparison with amphotericin B and fluconazole. The Journal of antimicrobial chemotherapy. 1997 Jan 1;39(1):71-7.
Yoshida M, Tamura K, Masaoka T, Nakajo E. A real-world prospective observational study on the efficacy and safety of liposomal amphotericin B in 426 patients with persistent neutropenia and fever. Journal of Infection and Chemotherapy. 2021 Feb 1;27(2):277-83.
Yoshida I, Saito AM, Tanaka S, Choi I, Hidaka M, Miyata Y, Inoue Y, Yamasaki S, Kagoo T, Iida H, Niimi H. Intravenous itraconazole compared with liposomal amphotericin B as empirical antifungal therapy in patients with neutropaenia and persistent fever. Mycoses. 2020 Aug;63(8):794-801.
Kohno S, Izumikawa K, Ogawa K, Kurashima A, Okimoto N, Suzuki K, Kakeya H, Niki Y, Ichihara K, Miyazaki Y. Intravenous liposomal amphotericin B versus voriconazole for chronic pulmonary aspergillosis: a multicenter trial in Japan. Acta Medica Nagasakiensia. 2018;61(4):167-76.
Noguchi S, Takahashi N, Ito M, Teshima K, Yamashita T, Michishita Y, Ohyagi H, Shida S, Nagao T, Fujishima M, Ikeda S. Safety and efficacy of low-dose liposomal amphotericin B as empirical antifungal therapy for patients with prolonged neutropenia. International journal of clinical oncology. 2013 Dec;18(6):983-7.
Nakajima R, Kitamura A, Someya K, Tanaka M, Sato K. In vitro and in vivo antifungal activities of DU-6859a, a fluoroquinolone, in combination with amphotericin B and fluconazole against pathogenic fungi. Antimicrobial agents and chemotherapy. 1995 Jul;39(7):1517-21.
URABE A, TAKAKU F, MIZOGUCHI H, NOMURA T, OGAWA T, MAEKAWA T, OMINE M, MIURA Y, HIRASHIMA K, TAKATANI O, SATO N. Prophylactic and therapeutic effects of oral administration of amphotericin B in mycosis associated with hematologic diseases. The Japanese Journal of Antibiotics. 1990 Jan 25;43(1):116-30.