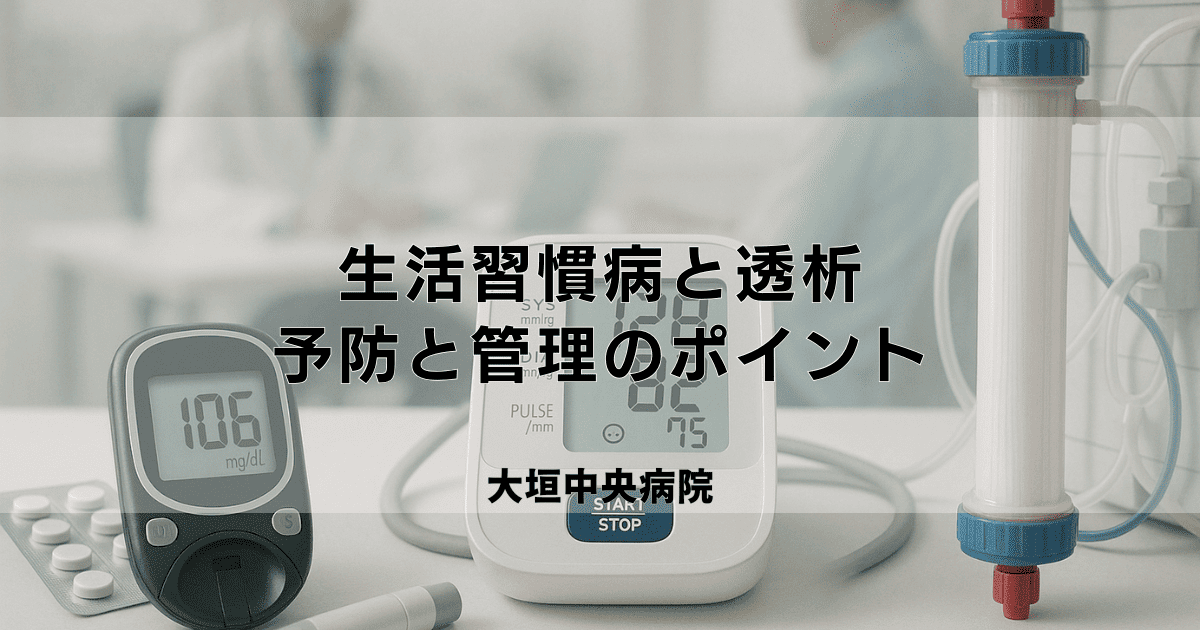糖尿病や高血圧といった生活習慣病が、日本で透析治療を始める方の原因の半数以上を占めていて、初期には自覚症状がほとんどないまま、静かに腎臓の機能をむしばんでいきます。
そして、気づいた時には腎臓の働きが大幅に低下し、透析治療を受けなければ生命を維持できない末期腎不全という状態に至ることがあります。
この記事では、なぜ生活習慣病が透析に繋がるのか、その密接な関係を詳しく解説するとともに、大切な腎臓を守り、透析を回避するための予防と管理のポイントを専門的な視点からお伝えします。
透析治療とは?腎臓の働きと生活習慣病の関係
生活習慣病と透析の関係を理解するためには、まず私たちの体の中で腎臓がどのような役割を果たしているのか、そして生活習慣病がその働きにどう影響するのかを知ることが大切です。
腎臓が担う生命維持のための重要な役割
腎臓は、腰のあたりに左右一つずつある、握りこぶしほどの大きさの臓器です。単に尿を作るだけの臓器と思われがちですが、実際には生命を維持するために、休むことなく様々な重要な働きを担っています。
その中でも特に中心的な役割は、血液をろ過して体内の老廃物や余分な水分、塩分を尿として排泄することです。この働きによって、私たちの体は常にきれいな状態に保たれています。
その他にも、血圧を調整するホルモンや、血液を作るホルモンを分泌したり、体内のミネラルバランスを整えたりと、その役割は多岐にわたります。
腎臓が担う主な働き
| 主な働き | 内容 |
|---|---|
| 老廃物の排泄 | 血液をろ過し、体内で作られた不要な老廃物を尿として捨てる |
| 水分・電解質の調整 | 体内の水分量やナトリウム、カリウムなどのバランスを一定に保つ |
| ホルモンの分泌 | 血圧を調整するホルモンや、赤血球の産生を促すホルモンを作る |
| ビタミンDの活性化 | カルシウムの吸収を助け、丈夫な骨を維持するビタミンDを活性化する |
生活習慣病が腎臓に与える静かなダメージ
腎臓の内部には、糸球体と呼ばれる毛細血管の塊が、左右合わせて約200万個も存在します。
血液のろ過は、この非常に繊細な糸球体で行われ、糖尿病による高血糖の状態や、高血圧による高い圧力が長期間続くと、糸球体の血管が少しずつダメージを受け、硬くなったり、詰まったりしていきます。
問題なのは、このダメージが非常にゆっくりと、そして自覚症状がないまま進行することです。
なぜ透析治療が必要になるのか
腎臓の機能が正常の15%以下にまで低下すると、体内の老廃物や余分な水分を十分に排泄できなくなり、尿毒症という危険な状態に陥ります。倦怠感、吐き気、食欲不振、むくみ、呼吸困難といった様々な症状が現れ、放置すれば命に関わります。
末期腎不全の状態になった時、低下した腎臓の機能の代わりをするために必要となる治療が透析治療です。透析治療は、人工的に血液を浄化することで、体内の環境を正常に近づけ、生命を維持するために行います。
日本における透析導入の現状
日本の透析患者さんの数は年々増加傾向にあり、原因疾患の第一位は糖尿病性腎症、第二位は慢性糸球体腎炎、そして第三位が腎硬化症(主に高血圧が原因)となっています。
注目すべきは、第一位の糖尿病と第三位の高血圧が、いずれも代表的な生活習慣病であるという点です。この二つを合わせると、新たに透析を始める方の半数以上を占めることになります。
日本の新規透析導入 原疾患(2022年末)
| 順位 | 原疾患 | 割合 |
|---|---|---|
| 1位 | 糖尿病性腎症 | 41.3% |
| 2位 | 慢性糸球体腎炎 | 13.8% |
| 3位 | 腎硬化症 | 12.0% |
出典:わが国の慢性透析療法の現況(2022年12月31日現在)
糖尿病が透析を引き起こす仕組み(糖尿病性腎症)
透析導入の最大の原因である糖尿病。なぜ血糖値が高い状態が続くと、腎臓の機能が失われてしまうのでしょうか。背景にある糖尿病性腎症という合併症について、詳しく見ていきましょう。
糖尿病性腎症とは何か
糖尿病性腎症は、糖尿病の三大合併症(網膜症、神経障害、腎症)の一つで、長期間にわたる高血糖が原因で腎臓の機能が徐々に低下していく病気です。
初期の段階ではほとんど自覚症状がなく、気づかないうちに進行していきますが、一度発症すると完全に元の状態に戻すことは難しく、進行すれば末期腎不全に至り、透析治療が必要となります。
高血糖が腎臓の糸球体を傷つける
血液中のブドウ糖濃度が高い状態(高血糖)が続くと、腎臓の糸球体を構成する毛細血管の壁がダメージを受け、血管の壁が厚くなったり、性質が変化したりすることで、血液をろ過するフィルター機能に異常が生じます。
初期には、フィルターの目が粗くなり、本来は尿に漏れ出ないはずのアルブミンというタンパク質が、ごく微量だけ尿中に漏れ出すようになり、この状態が、腎症の最も早いサインです。
さらに進行すると、フィルターの目が詰まっていき、老廃物をろ過する能力そのものが低下していきます。
糖尿病性腎症の進行ステージと症状
糖尿病性腎症は、進行度によっていくつかの病期に分類されます。初期の段階では自覚症状は全くありませんが、進行するにつれて、むくみや倦怠感、貧血といった症状が現れるようになります。
糖尿病性腎症の病期分類(概要)
| 病期 | 主な状態 | 自覚症状 |
|---|---|---|
| 第1期(腎症前期) | 腎症はまだ始まっていない | なし |
| 第2期(早期腎症期) | 微量のアルブミンが尿中に漏れ出す | なし |
| 第3期(顕性腎症期) | 持続的にたんぱく尿が出る。腎機能が低下し始める | むくみが出ることがある |
| 第4期(腎不全期) | 腎機能が大幅に低下する | むくみ、倦怠感、貧血、吐き気など |
| 第5期(透析療法期) | 末期腎不全の状態 | 強い尿毒症症状 |
早期発見のための重要な検査(尿中アルブミン)
自覚症状のない早期の段階で腎症を発見するために、最も重要な検査が尿検査です。通常の健康診断で行う尿たんぱく検査では検出できない、ごく微量のアルブミンの漏れを調べる尿中微量アルブミン検査が、腎症の早期発見に極めて有効です。
この段階で異常を発見し、血糖コントロールや血圧管理を徹底することで、その後の腎症の進行を大幅に遅らせることができます。
高血圧が腎臓をむしばむ仕組み(腎硬化症)
糖尿病に次いで透析導入の原因となる高血圧。血圧が高い状態が、どのようにして腎臓の機能を奪っていくのでしょうか。背景にある腎硬化症について解説します。
腎硬化症とは何か
腎硬化症とは長年にわたる高血圧が原因で、腎臓の細い動脈が動脈硬化を起こし、腎臓全体の機能が徐々に低下していく病気です。
糖尿病性腎症と同様に、初期には自覚症状がほとんどなく、健康診断などで偶然、尿たんぱくや腎機能の低下を指摘されて見つかることが少なくありません。
加齢も大きな要因の一つであり、高齢化社会の進展とともに、腎硬化症による透析導入は増加傾向にあります。
高血圧が腎臓の血管を硬くする
腎臓は、血液をろ過するために非常に多くの血液が流れ込む、血流が豊富な臓器です。血圧が高い状態が続くと、常に強い圧力にさらされる腎臓の細い動脈は、その圧力に耐えるために血管の壁を厚く硬くしていきます。
これが動脈硬化で、進行すると血管の内側が狭くなり、腎臓に流れる血液の量が減少します。血流が不足した糸球体は、栄養や酸素が足りなくなり、徐々に硬化してその機能を失っていきます。
腎硬化症の進行と自覚症状の乏しさ
腎硬化症の進行は非常にゆっくりです。多くの場合、10年、20年という長い年月をかけて腎機能が低下していきます。腎臓は予備能力が高い臓器であるため、機能が半分近くまで低下しても、自覚症状はほとんど現れません。
そのため、高血圧を指摘されても、特に症状がないからと放置してしまい、気づいた時には腎機能がかなり悪化しているというケースが多いです。
腎機能低下で現れる可能性のあるサイン
- 夜間の頻尿
- 足や顔のむくみ
- 貧血(めまい、立ちくらみ)
- 体のだるさ、疲れやすさ
家庭血圧測定の重要性
高血圧の管理において、医療機関で測定する血圧だけでなく、家庭で毎日血圧を測定する家庭血圧が非常に重要です。
診察室では緊張して血圧が高くなる白衣高血圧や、逆に診察室では正常なのに家庭では高い仮面高血圧などを見つけることができます。
朝と晩の決まった時間に測定し、記録する習慣をつけることで、日々の血圧の変動を把握し、降圧薬の効果を正確に評価できます。
透析を回避するための生活習慣病の予防と管理
糖尿病や高血圧による腎機能の低下を防ぎ、将来の透析を回避するためには、日々の生活習慣を見直し、適切に管理していくことが不可欠です。
腎臓を守るための食事療法の基本
食事は、生活習慣病の管理において最も重要な要素の一つで、腎臓を守るという観点からは、塩分の過剰摂取を避けることが基本中の基本です。塩分を摂りすぎると、体内に水分が溜まりやすくなり、血圧が上昇して腎臓に負担をかけます。
また、食べ過ぎによる肥満は、糖尿病や高血圧の引き金となります。バランスの取れた食事を、腹八分目を心がけて摂ることが大切です。腎機能が低下し始めた場合は、タンパク質やカリウム、リンなどの制限が必要になることもあります。
腎臓を守る食事の基本ポイント
| ポイント | 具体的な内容 | 理由 |
|---|---|---|
| 減塩 | 1日の塩分摂取量を6g未満に抑える | 血圧の上昇を防ぎ、腎臓への負担を軽減する |
| 適正なエネルギー摂取 | 過食を避け、肥満を予防・解消する | 糖尿病や高血圧のリスクを低減する |
| バランスの良い食事 | 主食・主菜・副菜をそろえ、様々な食品を摂る | 必要な栄養素を過不足なく摂取する |
適度な運動がもたらす効果
ウォーキングや軽いジョギング、水泳などの有酸素運動を定期的(1回30分程度を週に3日以上)に行うことは、血糖値や血圧の改善に繋がります。
運動によって、インスリンの働きが良くなったり、体重が減少したりすることで、生活習慣病の管理がしやすくなります。
ただし、すでに腎機能が低下している方や、心臓に持病のある方は、運動が体に負担となる場合もあるので、運動を始める前に、必ず主治医に相談し、どの程度の運動が適切かアドバイスを受けるようにしてください。
禁煙と節酒の重要性
喫煙は、血管を収縮させて血圧を上昇させるだけでなく、動脈硬化を直接的に促進する、腎臓にとって最大の危険因子の一つで、腎機能を守るためには、禁煙が絶対条件です。
また、アルコールの過剰摂取も、高血圧や肥満の原因となり、腎臓に悪影響を及ぼします。飲酒は、適量を守ることが大切です。
ストレス管理と十分な睡眠
精神的なストレスや睡眠不足も、血圧を上昇させたり、血糖コントロールを乱したりする原因となります。
自分なりのリラックス方法を見つけて趣味の時間を楽しんだり、十分な睡眠時間を確保したりして、心身の健康を保つことも、生活習慣病の管理には重要です。
規則正しい生活リズムを心がけ、心に余裕を持って日々を過ごすことが、結果的に腎臓を守ることにも繋がります。
糖尿病性腎症の進行を抑える治療と管理
糖尿病性腎症と診断された場合、その進行をいかに遅らせるかが治療の最大の目標となります。食事療法、薬物療法、そして定期的な検査を組み合わせた、総合的な管理が必要です。
血糖コントロールの目標(HbA1c)
腎症の進行を抑えるための基本は、良好な血糖コントロールを維持することです。血糖コントロールの指標として、過去1~2か月の平均血糖値を反映するヘモグロビンA1c(HbA1c)を用います。
合併症予防のための一般的な目標値は7.0%未満とされていますが、年齢や合併症の有無、低血糖のリスクなどを考慮して、個別に目標値を設定します。
厳格すぎるコントロールは、特に高齢者では重い低血糖を招く危険もあるため、主治医とよく相談することが大切です。
食事療法(タンパク質・塩分・カリウムの管理)
腎機能が低下し始めると、通常の糖尿病の食事療法に加えて、腎臓への負担を減らすための特別な配慮が必要で、特に、タンパク質の摂取量を制限することが重要です。
タンパク質は体内で分解される際に老廃物を生み出すため、摂取量を制限することで腎臓の仕事量を減らすことができます。また、塩分制限は血圧管理とむくみ防止のために、さらに腎機能が低下した場合はカリウムやリンの制限も必要です。
糖尿病性腎症の食事療法
| 制限項目 | 目的 |
|---|---|
| 塩分 | 血圧管理、むくみの改善 |
| タンパク質 | 腎臓への負担軽減、尿毒症症状の抑制 |
| カリウム・リン | 高カリウム血症、骨合併症の予防(腎不全期) |
薬物療法(血糖降下薬・SGLT2阻害薬など)
食事療法や運動療法で血糖コントロールが不十分な場合は、薬物療法を行います。血糖降下薬には様々な種類があり、患者さんの病態に合わせて使い分けます。
近年、SGLT2阻害薬という種類の薬が、血糖値を下げる効果に加えて、腎臓を保護する作用や心不全を改善する作用があることが分かり、糖尿病性腎症の治療において重要な役割を担うようになっています。
また、血圧の管理も極めて重要であり、ACE阻害薬やARBといった種類の降圧薬は、血圧を下げるだけでなく、腎保護作用も期待できるため、第一選択薬です。
腎硬化症の進行を抑える高血圧の治療と管理
高血圧による腎硬化症の進行を食い止めるためには、何よりもまず血圧を目標値まで下げ、維持し続けることが治療の根幹となります。
降圧目標と血圧管理の重要性
腎硬化症の進行予防において、厳格な血圧管理が最も重要です。
一般的な高血圧の降圧目標は130/80mmHg未満ですが、尿たんぱくが出ているなど、腎臓病を合併している場合は、より厳しい目標値(例えば125/75mmHg未満)が設定されることもあります。目標値は年齢や合併症によって個別に設定します。
血圧を10mmHg下げるだけでも、末期腎不全に至るリスクを大幅に低減できることが分かっています。家庭血圧を毎日測定し、目標値を達成できているかを確認する習慣が大切です。
食事療法(減塩が基本)
高血圧治療における食事療法の基本は、減塩です。日本高血圧学会では、1日の塩分摂取量を6g未満にすることを推奨しています。加工食品やインスタント食品、外食には塩分が多く含まれている傾向があるため、注意が必要です。
また、肥満は高血圧の大きな要因であるため、適正な体重を維持するためのエネルギーコントロールも同時に行います。
減塩のための工夫
- だしや香辛料、酸味を活用する
- 麺類の汁は飲まない
- 加工食品や練り製品を控える
- しょうゆやソースは「かける」より「つける」
薬物療法(降圧薬の種類と役割)
食事療法や運動療法だけでは血圧が十分に下がらない場合、降圧薬による薬物療法を開始し、降圧薬には多くの種類があり、それぞれ作用する仕組みが異なります。
腎保護作用が期待できるACE阻害薬やARBを中心に、必要に応じてカルシウム拮抗薬や利尿薬などを組み合わせて使用します。複数の薬を併用することで、より効果的で副作用の少ない血圧コントロールを目指します。
自己判断で薬をやめたり量を減らしたりすると、血圧が急上昇して危険な状態になることもあるため、必ず医師の指示通りに服用を続けてください。
高血圧治療で用いられる主な降圧薬
| 薬剤の種類 | 主な作用 |
|---|---|
| ACE阻害薬・ARB | 血管を収縮させる物質の働きを抑える(腎保護作用あり) |
| カルシウム拮抗薬 | 血管を広げて血圧を下げる |
| 利尿薬 | 体内の余分な塩分と水分を尿として排泄させる |
すでに透析を導入した方の生活習慣病管理
透析治療が始まっても、原因となった糖尿病や高血圧の管理が終わるわけではありません。心筋梗塞や脳卒中といった、より重篤な合併症を防ぎ、元気で長生きするためには、透析導入後も継続した自己管理が極めて重要になります。
透析導入後も続く血糖・血圧管理
透析を始めると血糖値や血圧は変動しやすく、透析によって体内の水分量が変わるため、血圧の管理はより難しくなります。また、血糖値も、食事の影響だけでなく、透析液に含まれるブドウ糖の影響も受けるようになります。
透析導入前とは異なる目標値や治療法が必要になるため、透析施設の医師やスタッフとよく相談しながら、適切な管理を続けることが大切です。
食事・水分管理のポイント
透析患者さんにとって、食事と水分の管理は治療そのものと言えるほど重要で、尿がほとんど出なくなるため、水分の摂取は厳しく制限されます。また、塩分、カリウム、リンの摂取も、合併症を防ぐために厳密な管理が必要です。
また、透析によって失われるタンパク質やエネルギーを補う必要もありm管理栄養士の指導のもと、決められた範囲内で栄養バランスの取れた食事を摂ることが求められます。
透析患者の食事管理のポイント
| 栄養素 | 管理のポイント |
|---|---|
| 水分・塩分 | 厳しく制限し、体重増加をコントロールする |
| カリウム | 高カリウム血症を防ぐため、生野菜や果物などに注意する |
| リン | 骨の合併症や血管の石灰化を防ぐため、加工食品などを避ける |
| エネルギー・タンパク質 | 栄養状態を維持するため、十分に摂取する |
心血管系合併症の予防
透析患者さんの生命予後に最も大きく影響するのが、心筋梗塞や脳卒中といった心血管系の合併症です。糖尿病や高血圧は、動脈硬化を進行させる大きな危険因子であり、透析患者さんは特にそのリスクが高くなります。
血圧や血糖の管理はもちろん、脂質異常症(コレステロールや中性脂肪が高い状態)の管理や、禁煙の徹底、適切な体重管理など、動脈硬化を防ぐための総合的な取り組みが重要です。
よくある質問(FAQ)
最後に、生活習慣病と腎臓、そして透析に関して、多くの方から寄せられる質問と回答をまとめました。
- 糖尿病や高血圧と診断されたら、将来必ず透析になりますか?
-
糖尿病や高血圧と診断されても、早期から食事療法や運動療法、薬物療法を適切に行い、血糖値や血圧を良好な状態にコントロールし続けることで、腎機能の低下を防ぎ、透析を回避することは十分にできます。
大切なのは、症状がないからと放置せず、真摯に治療に取り組むことです。
- 腎臓の機能は一度悪くなると元に戻らないのですか?
-
残念ながら、一度硬化して機能を失ってしまった腎臓の組織(糸球体など)を、元の状態に戻すことは現在の医療では困難です。
腎臓病の治療は、残っている腎機能をいかに守り、悪化のスピードを遅らせるかが目標となります。
- 健康診断で尿たんぱくを指摘されました。どうすれば良いですか?
-
尿にたんぱくが漏れ出ているのは、腎臓が何らかのダメージを受けているサインである可能性があります。
一度の検査では、体調などによる一時的なものである可能性もありますが、放置せずに必ず内科または腎臓内科を受診し、再検査や精密検査を受けてください。
- 透析を避けるために、今からできることは何ですか?
-
まずは、ご自身の健康状態を把握することから始めましょう。定期的に健康診断を受け、血圧や血糖値、腎機能(eGFR)の数値を確認してください。
そして、もし糖尿病や高血圧を指摘されたら、すぐに医療機関を受診し、治療を開始することです。
その上で、日々の生活においては、減塩を中心としたバランスの良い食事、適度な運動、禁煙、節酒といった、健康的な生活習慣を実践し、継続していくことが、透析を回避するための最も確実な道です。
以上
透析センター(人工透析) | 大垣中央病院(医療法人社団豊正会 )
参考文献
Fujii M, Ohno Y, Ikeda A, Godai K, Li Y, Nakamura Y, Yabe D, Tsushita K, Kashihara N, Kamide K, Kabayama M. Current status of the rapid decline in renal function due to diabetes mellitus and its associated factors: analysis using the National Database of Health Checkups in Japan. Hypertension Research. 2023 May;46(5):1075-89.
Kaneyama A, Hirata A, Hirata T, Imai Y, Kuwabara K, Funamoto M, Sugiyama D, Okamura T. Impact of hypertension and diabetes on the onset of chronic kidney disease in a general Japanese population. Hypertension Research. 2023 Feb;46(2):311-20.
Imai E, Yamagata K, Iseki K, Iso H, Horio M, Mkino H, Hishida A, Matsuo S. Kidney disease screening program in Japan: history, outcome, and perspectives. Clinical journal of the American Society of Nephrology. 2007 Nov 1;2(6):1360-6.
Wakasugi M, Narita I, Iseki K, Asahi K, Yamagata K, Fujimoto S, Moriyama T, Konta T, Tsuruya K, Kasahara M, Shibagaki Y. Healthy lifestyle and incident hypertension and diabetes in participants with and without chronic kidney disease: the Japan specific health checkups (J-SHC) study. Internal Medicine. 2022 Oct 1;61(19):2841-51.
Nakamura I, Kato S, Suda A, Kiyoshige E, Nakatsuka K, Nakaoku Y, Teramoto K, Yoshikawa Y, Takegami M, Ogata S, Hagihara A. Prevalence of diabetes mellitus and dialysis risk based on annual health checkup frequency among National Health Insurance citizens in Japan. BMC Public Health. 2025 Apr 14;25(1):1400.
Yokoyama H, Sone H, Oishi M, Kawai K, Fukumoto Y, Kobayashi M, Japan Diabetes Clinical Data Management Study Group. Prevalence of albuminuria and renal insufficiency and associated clinical factors in type 2 diabetes: the Japan Diabetes Clinical Data Management study (JDDM15). Nephrology Dialysis Transplantation. 2009 Apr 1;24(4):1212-9.
Hayashino Y, Fukuhara S, Akiba T, Akizawa T, Asano Y, Saito A, Bragg-Gresham JL, Ramirez SP, Port FK, Kurokawa K. Diabetes, glycaemic control and mortality risk in patients on haemodialysis: the Japan Dialysis Outcomes and Practice Pattern Study. Diabetologia. 2007 Jun;50(6):1170-7.
Shikata K, Kodera R, Utsunomiya K, Koya D, Nishimura R, Miyamoto S, Tajima N, JDCP study group. Prevalence of albuminuria and renal dysfunction, and related clinical factors in Japanese patients with diabetes: The Japan Diabetes Complication and its Prevention prospective study 5. Journal of Diabetes Investigation. 2020 Mar;11(2):325-32.
Osawa T, Fujihara K, Harada M, Yamamoto M, Ishizawa M, Suzuki H, Ishiguro H, Matsubayashi Y, Seida H, Yamanaka N, Tanaka S. Higher pulse pressure predicts initiation of dialysis in Japanese patients with diabetes. Diabetes/metabolism research and reviews. 2019 Mar;35(3):e3120.
Watanabe H, Anezaki H, Kazawa K, Tamaki Y, Hashimoto H, Moriyama M. Long-term effectiveness of a disease management program to prevent diabetic nephropathy: a propensity score matching analysis using administrative data in Japan. BMC Endocrine Disorders. 2022 May 20;22(1):135.