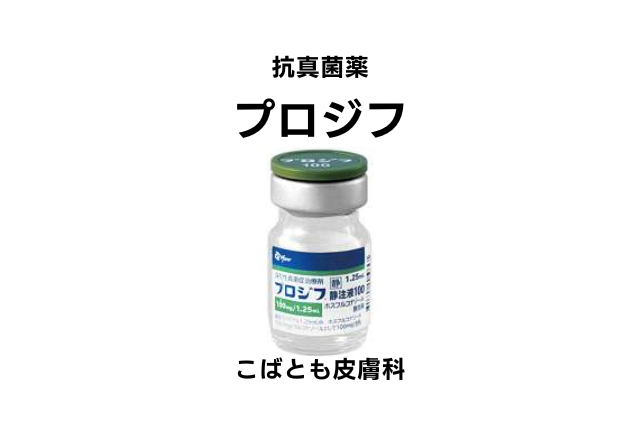ホスフルコナゾール(プロジフ)とは、真菌(カビ)によって起こる様々な感染症の治療に用いる抗真菌薬です。主に点滴で投与する静注液として、入院治療が必要な重症の真菌感染症や、経口での服薬が困難な患者さんに使用します。
体内で有効成分であるフルコナゾールに変換されることで効果を発揮するプロドラッグという特徴を持ちます。
この記事では、プロジフ静注液がどのような仕組みで真菌に作用するのか、効果や投与方法、注意すべき副作用、そして薬価に至るまで、詳しく解説します。
この記事の執筆者

小林 智子(こばやし ともこ)
日本皮膚科学会認定皮膚科専門医・医学博士
こばとも皮膚科院長
2010年に日本医科大学卒業後、名古屋大学医学部皮膚科入局。同大学大学院博士課程修了後、アメリカノースウェスタン大学にて、ポストマスターフェローとして臨床研究に従事。帰国後、同志社大学生命医科学部アンチエイジングリサーチセンターにて、糖化と肌について研究を行う。専門は一般皮膚科、アレルギー、抗加齢、美容皮膚科。雑誌を中心にメディアにも多数出演。著書に『皮膚科医が実践している 極上肌のつくり方』(彩図社)など。
こばとも皮膚科関連医療機関
ホスフルコナゾール(プロジフ)の有効成分と効果、作用機序
この薬がどのようにして真菌感染症に効果を示すのか、中心となる有効成分の働きと、体の中での作用について詳しく見ていきましょう。
静注用の「プロドラッグ」
ホスフルコナゾールは、それ自体が直接的に効果を発揮するわけではありません。点滴によって体内に投与された後、血液中などに存在する酵素の働きによって、速やかに有効成分であるフルコナゾールへと変化します。
このように、体内で代謝されることで初めて薬効を示すように設計された薬をプロドラッグと呼びます。
ホスフルコナゾールは、有効成分のフルコナゾールに比べて水に溶けやすい性質を持つため、高用量を少ない溶液量で投与できる静注液としての開発が可能になりました。
有効成分フルコナゾールの効果
体内で生成されたフルコナゾールは、アゾール系抗真菌薬に分類され、幅広い種類の真菌に対して効果を示します。
特に、カンジダ属やクリプトコッカス属といった、重篤な全身性の真菌感染症の原因となる真菌に対して、その増殖を強力に抑制します。
静脈内に直接投与するため、消化管からの吸収過程を経ずに、速やかに血中濃度が上昇し、体の隅々の組織や臓器、さらには脳脊髄液にも移行しやすいことが特徴です。
真菌の細胞膜合成を阻害する作用機序
フルコナゾールが真菌の増殖を抑える仕組みは、真菌の細胞を守る細胞膜の合成を阻害することにあります。
真菌は、細胞膜の構成成分としてエルゴステロールという物質を必要としますが、フルコナゾールは、エルゴステロールを作り出すために必要な真菌特有の酵素(14α-デメチラーゼ)の働きを選択的に妨げます。
この酵素が働かなくなると、真菌は正常な細胞膜を作れず、増殖できなくなります。
人間の細胞膜はエルゴステロールではなくコレステロールで構成されており、フルコナゾールは人間の細胞に対する影響が少ないため、比較的安全性の高い薬です。
ホスフルコナゾール(プロジフ)静注液の作用の流れ
| 段階 | 内容 | 場所 |
|---|---|---|
| 第1段階:投与 | ホスフルコナゾールとして点滴静脈内注射で投与する | 血管内 |
| 第2段階:代謝 | 血液中の酵素の働きで有効成分フルコナゾールに速やかに変換される | 血液中 |
| 第3段階:作用発現 | フルコナゾールが全身に分布し、真菌の細胞膜合成を阻害する | 全身の感染部位 |
プロジフ静注液の特徴
プロジフ静注液は、ホスフルコナゾールを有効成分とする注射剤です。経口での服薬が難しい患者さんや、重症な真菌感染症に対する初期治療として、迅速な効果発現が求められる場面で使用します。
血中濃度の立ち上がりが速く、安定した効果が期待できる点が大きな特徴です。
また、ある程度症状が改善し、経口摂取が可能になった場合には、同じ有効成分の経口薬(フルコナゾールカプセルなど)に切り替えるシークエンシャル療法への移行がスムーズに行えるという利点もあります。
使用方法と注意点
ホスフルコナゾール(プロジフ)は医師や看護師によって投与されるため、患者さん自身が使用方法を管理することはありません。しかし、どのような治療が行われるのかを知っておくことは、安心して治療を受ける上で大切です。
点滴静脈内注射による投与
ホスフルコナゾール(プロジフ)は、生理食塩液などに溶解し、点滴でゆっくりと静脈内に投与し、投与は必ず医師または看護師が行います。
投与速度が速すぎると、副作用のリスクが高まる可能性があるため、定められた時間をかけて慎重に投与し、通常、1時間あたり10mLを超えない速度で点滴します。
投与スケジュールについて
投与スケジュールは、対象となる疾患によって大きく異なります。例えば、カンジダ血症などの重症な感染症では、初日に通常量の倍量を投与し(ローディングドーズ)、翌日からは維持量を1日1回投与する方法が一般的です。
治療は、症状や検査結果を見ながら継続し、必要に応じて投与量や期間を調整していきます。
投与スケジュールの例(カンジダ症成人の場合)
| 投与日 | 投与量 | 目的 |
|---|---|---|
| 初日 | 400mgを1回 | 有効血中濃度への迅速な到達 |
| 2日目以降 | 200mgを1日1回 | 有効血中濃度の維持 |
※上記は一例です。実際の投与量は患者さんの状態により異なります。
投与中の体調変化への注意
点滴投与中は、ベッドの上で安静にしていただきます。
投与中に気分が悪くなったり、注射している腕に痛みや腫れ、赤みを感じたり、あるいは息苦しさや動悸、発疹などの異常を感じたりした場合は、我慢せずにすぐに近くの看護師に伝えてください。
このような症状は、薬による副作用やアレルギー反応のサインである可能性があり、早期の対応が重要です。特に、初めてこの薬の投与を受ける際には、アレルギー反応が起きないか慎重に観察しながら進めます。
シークエンシャル療法への移行
静注液による治療で全身状態が改善し、食事が摂れるようになるなど、経口での服薬が可能になったと医師が判断した場合には、同じ有効成分のフルコナゾールを含む内服薬(カプセル剤など)に切り替えることがあります。
これをシークエンシャル療法と呼び、静脈注射から内服薬へスムーズに移行できるため、不要な点滴を減らし、患者さんの負担を軽減するとともに、早期の退院や社会復帰にも繋がります。
ホスフルコナゾール(プロジフ)の適応対象となる患者さん
プロジフ静注液は、様々な真菌感染症の治療に用いられますが、特にどのような患者さんや病状に対して選択されるのでしょうか。
適応となる真菌感染症の種類
プロジフ静注液は、内服薬では対応が難しい、あるいは迅速な治療が必要な真菌感染症が主な対象です。
認められている適応症
- カンジダ属による真菌血症、呼吸器真菌症、消化管真菌症、尿路真菌症
- クリプトコッカス属による真菌髄膜炎、肺真菌症
- 経口抗真菌薬の投与が困難な患者における爪白癬
重症・深在性真菌症の治療
カンジダやクリプトコッカスといった真菌が血液中に入り込み、全身に広がった状態(真菌血症)や、肺、消化管、さらには脳を保護する髄膜にまで感染が及んだ状態(深在性真菌症)は、命に関わる重篤な感染症です。
このような場合、消化管からの吸収を待つ時間的猶予はなく、また吸収が不安定になるリスクも避けるため、静注薬による迅速かつ確実な治療が第一選択となります。
経口投与が困難な患者さん
意識障害がある、嚥下機能が低下している、あるいは重い吐き気や嘔吐で内服薬を服用できないなど、経口での薬剤投与が難しい患者さんに対しても、プロジフ静注液が選択されます。
また、大きな手術の前後で、感染予防や治療のために経口摂取が制限されている場合にも使用し、口から薬を飲めない状況でも、必要な抗真菌治療を継続することが可能です。
静注療法が選択される主なケース
| 状況 | 選択される理由 |
|---|---|
| 重症な全身性真菌感染症(真菌血症など) | 迅速に有効血中濃度に到達させる必要があるため |
| 真菌髄膜炎 | 有効成分が髄液へ良好に移行するため |
| 経口摂取が不可能な患者 | 嚥下困難、意識障害、消化管の問題などで内服できないため |
治療期間
治療期間は、原因となっている感染症の種類や重症度、そして患者さんの回復具合によって大きく異なります。
感染症の種類と重症度が期間を決める
治療期間に決まったものはありません。医師が、患者さんの症状の改善度や、血液検査における炎症反応の数値、そして原因菌を特定するための培養検査の結果などを総合的に評価して、治療の継続・終了を判断します。
カンジダ血症では、血液培養でカンジダが陰性化してから、さらに2週間程度の治療継続が推奨されています。クリプトコッカス髄膜炎のような難治性の感染症では、数か月にわたる長期の治療が必要です。
治療効果の判定方法
静注療法における効果判定は、以下のような複数の指標を基に行います。
- 臨床症状の改善:発熱、倦怠感、呼吸状態などの全身症状が良くなっているか。
- 検査データの改善:血液検査での白血球数やCRP(炎症反応の指標)が正常化しているか。
- 微生物学的効果:血液や尿、喀痰などの培養検査で、原因となっていた真菌が検出されなくなるか。
感染が十分にコントロールされたと判断された時点で、治療の終了や経口薬への切り替えを検討します。
経口薬への切り替え(シークエンシャル療法)のタイミング
多くのケースでは静注療法は初期治療として行い、感染が落ち着き、患者さんの全身状態が安定すれば、経口の抗真菌薬に切り替えます。
切り替えのタイミングは、患者さんが安全に食事や水分、そして薬を経口で摂取できるようになった時点が目安です。早期に経口薬へ移行することで、長期間の点滴による身体的負担や合併症のリスクを減らし、入院期間の短縮にも繋がります。
静注から経口への切り替えを検討する条件
| 項目 | 判断基準の例 |
|---|---|
| 全身状態 | 解熱し、血圧などのバイタルサインが安定している |
| 経口摂取 | 食事や水分、薬剤をむせることなく安全に経口摂取できる |
| 消化管機能 | 重篤な下痢や嘔吐がなく、薬の吸収に問題がない |
ホスフルコナゾール(プロジフ)の副作用やデメリット
どのような薬にも、効果がある一方で副作用のリスクはあります。プロジフ静注液で起こりうる副作用について正しく理解し、万が一体に異変を感じた場合に速やかに医療スタッフに伝えることが大切です。
主な副作用
比較的安全性の高い薬ですが、一部の方に副作用が現れることがあります。内服薬と同様に、吐き気や嘔吐、下痢といった消化器系の症状が見られることがあります。
また、点滴の注射部位に関連する副作用として、血管の痛みや赤み、腫れなどが起こることもあります。多くは軽度ですが、症状が強い場合や続く場合には、看護師や医師に伝えてください。
報告されている主な副作用
| 分類 | 主な症状 |
|---|---|
| 消化器症状 | 吐き気、嘔吐、下痢、腹痛 |
| 注射部位 | 血管痛、静脈炎、発赤、腫れ |
| 肝臓 | 肝機能検査値(AST, ALTなど)の上昇 |
重大な副作用の初期症状
頻度は非常に稀ですが、注意すべき重大な副作用も報告されています。特に注意が必要なのは、ショック・アナフィラキシー、肝機能障害、血液障害、そして重い皮膚症状で、早期発見・早期対応が極めて重要です。
入院・治療中に以下のような初期症状に気づいた場合は、直ちに看護師や医師に知らせてください。
- 息苦しさ、顔面蒼白、冷や汗、意識が遠のく(ショック・アナフィラキシー)
- 全身の倦怠感、食欲不振、吐き気、皮膚や白目が黄色くなる(肝機能障害)
- 突然の高熱、のどの痛み、あざができやすい(血液障害)
- 高熱、目の充血、唇や陰部のただれ、全身の発疹・水ぶくれ(重い皮膚症状)
肝機能障害への注意
ホスフルコナゾールは主に肝臓で代謝されるため、肝臓に負担をかける可能性があるため、治療中は定期的に血液検査を行い、肝機能(AST、ALT、γ-GTPなどの値)に異常がないかを注意深く監視します。
もともと肝臓に疾患のある方や、他の肝毒性のある薬を併用している場合には、より慎重なモニタリングが必要です。
副作用が起きた場合の対処法
投与中に何らかの異常を感じた場合は、すぐに医療スタッフが対応します。注射部位の痛みが強い場合は、点滴の速度を遅くしたり、温めたり冷やしたりすることで症状が和らぐことがあります。
アレルギー反応が疑われる場合は、直ちに投与を中止し、症状を抑えるための適切な処置を行います。副作用の多くは、早期に発見し対処することで、重篤化を防ぐことが可能です。
ホスフルコナゾール(プロジフ)で効果がなかった場合
適切な治療を行っても、期待したような効果が得られないケースも稀にあります。どのような原因が考えられ、次にどのような治療の選択肢があるのかを知っておきましょう。
効果不十分と判断する基準
治療効果の判定は、発熱が続く、血液検査での炎症反応が改善しない、あるいは血液培養から真菌が消失しないなど、臨床症状と検査結果に基づいて客観的に行います。
一定期間治療を継続してもこれらの改善が見られない場合に、効果が不十分である、あるいは治療に抵抗性であると判断します。
原因の考察(薬剤耐性菌など)
効果が得られない原因として、最も重要なのが薬剤耐性菌の存在です。
フルコナゾールに元々効きにくい性質を持つカンジダ・グラブラータやカンジダ・クルセイといった菌種に感染している場合や、治療中に薬剤耐性を獲得した菌が出現した場合などが考えられます。
また、体内にカテーテルなどの異物があったり、膿の塊(膿瘍)が形成されていたりすると、薬の効果が十分に及ばずに感染が持続することもあります。
他の治療薬への変更
プロジフ静注液で効果が不十分な場合、作用機序の異なる別の系統の抗真菌薬への変更を検討します。第一選択となることが多いのは、β-D-グルカン合成酵素阻害薬であるキャンディン系抗真菌薬(ミカファンギンなど)です。
また、アムホテリシンB製剤といった、より強力な抗真菌薬が使用されることもあります。
深在性真菌症に対する主な注射用抗真菌薬
| 薬剤系統 | 代表的な薬剤名 | 特徴 |
|---|---|---|
| アゾール系 | ホスフルコナゾール、ボリコナゾール | 幅広い菌種に有効、副作用のモニタリングが重要 |
| キャンディン系 | ミカファンギン、カスポファンギン | カンジダ属に強力な効果、安全性が比較的高い |
| ポリエン系 | アムホテリシンB | 最も広域だが、腎毒性などの副作用に注意が必要 |
他の治療薬との併用禁忌
ホスフルコナゾールは、他の薬の代謝に影響を与えることがあるため、一緒に服用・投与できない薬(併用禁忌薬)や、注意が必要な薬(併用注意薬)があります。
入院治療中は、医師や薬剤師が服用中の薬をすべて管理しますが、ご自身が普段飲んでいる薬があれば、必ず入院時に申し出てください。
併用が禁止されている薬剤
一緒に投与するともう一方の薬の血中濃度が著しく上昇し、重篤な副作用を起こす危険性があるため、併用が固く禁止されている薬があり、特定の睡眠導入薬や抗精神病薬、片頭痛治療薬などが含まれます。
これらの薬を服用中の方は、原則としてホスフルコナゾールによる治療を受けることができません。
主な併用禁忌薬の例
- トリアゾラム(商品名:ハルシオンなど)
- ピモジド(商品名:オーラップ)
- キニジン(硫酸キニジン)
- エルゴタミン(クリアミンなど)
- アスナプレビル(スンベプラ)
併用に注意が必要な薬剤
併用が禁止されてはいないものの、一緒に投与することで互いの作用に影響を及ぼす可能性があるため、慎重な投与が必要な薬も多数あります。該当するのは、抗凝固薬のワルファリンや、一部の糖尿病治療薬、降圧薬、免疫抑制薬などです。
併用する際には、相手の薬の効果を注意深く観察したり、血中濃度を測定したりしながら、必要に応じて用量を調整します。
主な併用注意薬の例
| 薬剤の種類 | 起こりうる影響 |
|---|---|
| ワルファリン | 抗凝固作用が増強し、出血しやすくなる可能性がある |
| 一部の糖尿病治療薬 | 血糖降下作用が増強し、低血糖を起こす可能性がある |
| 免疫抑制薬(タクロリムスなど) | 免疫抑制薬の血中濃度が上昇し、腎障害などの副作用リスクが高まる |
ホスフルコナゾール(プロジフ)の保険適用と薬価について
以下に記載している治療費(医療費)は目安であり、実際の費用は症状や治療内容、保険適用否により大幅に上回ることがございます。当院では料金に関する以下説明の不備や相違について、一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。
保険適用の範囲
プロジフ静注液は、医師が適応となる真菌感染症と診断し、治療に必要であると判断した場合、健康保険が適用されます。保険が適用されると、かかった医療費の自己負担は、年齢や所得に応じて原則1割から3割です。
薬価と医療費の目安
プロジフ静注液200mgの薬価は、1瓶あたり約3,800円で、1日1回200mgの投与を受ける場合、1日あたりの薬剤費は約3,800円となります。自己負担割合が3割の方であれば、薬剤費の自己負担額は約1,140円です。
ただし、入院治療の場合、薬剤費だけでなく、入院基本料や注射手技料、検査料など様々な費用がかかり、それらを合計したものが総医療費となります。
自己負担額の計算例(1日200mg投与の場合)
| 項目 | 金額・計算 |
|---|---|
| プロジフ静注液200mgの薬価 | 3,801円/瓶 |
| 1日の薬剤費 | 3,801円 |
| 1日の薬剤費自己負担額(3割負担の場合) | 3,801円 × 0.3 ≒ 約1,140円 |
※上記は薬剤費のみの概算です。実際の窓口負担額は、入院費やその他の費用を含めた総額で計算します。
以上
参考文献
Tanzawa A, Saito J, Shoji K, Kojo Y, Funaki T, Maruyama H, Isayama T, Ito Y, Nakamura H, Yamatani A. Fluconazole population pharmacokinetics after fosfluconazole administration and dosing optimization in extremely low-birth-weight infants. Microbiology Spectrum. 2022 Apr 27;10(2):e01952-21.
Sobue S, Sekiguchi K, Shimatani K, Tan K. Pharmacokinetics and safety of fosfluconazole after single intravenous bolus injection in healthy male Japanese volunteers. The Journal of Clinical Pharmacology. 2004 Mar;44(3):284-92.
Aoyama T, Hirata K, Hirata R, Yamazaki H, Yamamoto Y, Hayashi H, Matsumoto Y. Population pharmacokinetics of fluconazole after administration of fosfluconazole and fluconazole in critically ill patients. Journal of clinical pharmacy and therapeutics. 2012 Jun;37(3):356-63.
Takahashi D, Nakamura T, Shigematsu R, Matsui M, Araki S, Kubo K, Sato H, Shirahata A. Fosfluconazole for antifungal prophylaxis in very low birth weight infants. International Journal of Pediatrics. 2009;2009(1):274768.
Bentley A, Butters M, Green SP, Learmonth WJ, MacRae JA, Morland MC, O’Conno G, Skuse J. The discovery and process development of a commercial route to the water soluble prodrug, fosfluconazole. Organic process research & development. 2002 Mar 15;6(2):109-12.
Bell AS. Triazole antifungals: Itraconazole (Sporanox), fluconazole (Diflucan), Voriconazole (Vfend) and fosfluconazole (Prodif). The art of drug synthesis. 2007 Jul 9:72-3.
Sobue S, Tan K, Layton G, Leclerc V, Weil A. The effects of renal impairment on the pharmacokinetics and safety of fosfluconazole and fluconazole following a single intravenous bolus injection of fosfluconazole. British journal of clinical pharmacology. 2004 Jun;57(6):773-84.
Sobue S, Tan K, Haug‐Pihale G. The effects of hepatic impairment on the pharmacokinetics of fosfluconazole and fluconazole following a single intravenous bolus injection of fosfluconazole. British journal of clinical pharmacology. 2005 Feb;59(2):160-6.
Kawakami Y, Nagino K, Shinkai K, Sobue S, Abe M, Ishiko J. Nonclinical studies and clinical studies on fosfluconazole, a triazole antifungal agent (Prodif). Nihon Yakurigaku zasshi. Folia Pharmacologica Japonica. 2004 Jul 1;124(1):41-51.
Hagiya H, Kajioka H. Successful treatment of recurrent candidemia due to candidal thrombophlebitis associated with a central venous catheter using a combination of fosfluconazole and micafungin. Internal Medicine. 2013;52(18):2139-43.