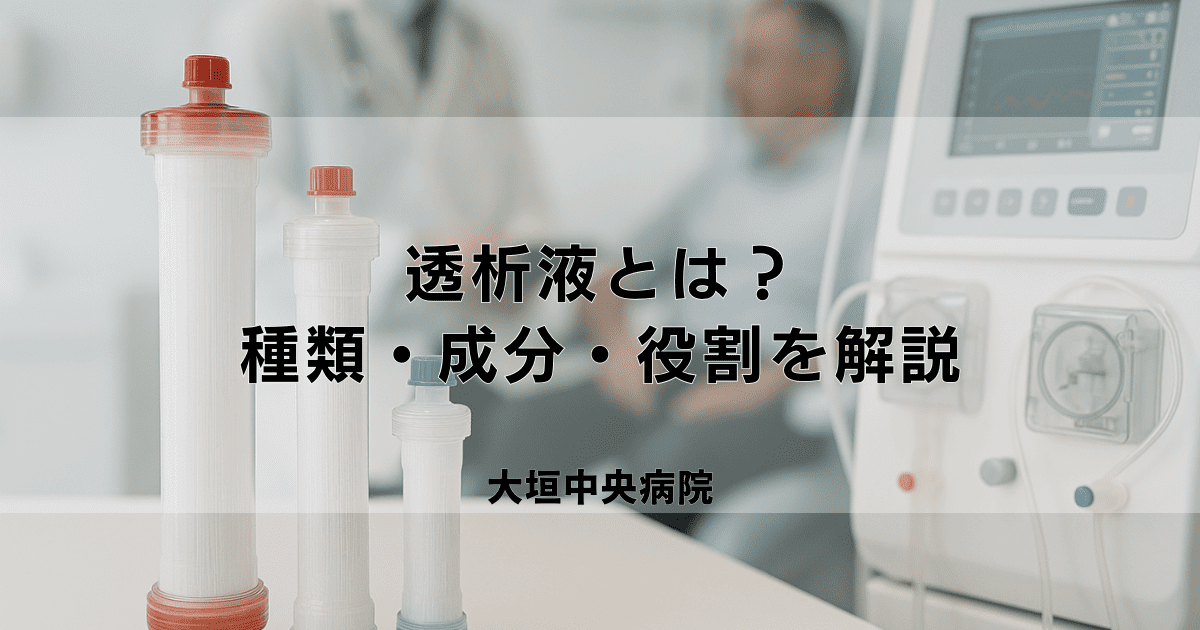血液透析治療を受ける上で、血液をきれいにするために毎回使われる筒状の医療機器が、ダイアライザーです。人工腎臓とも呼ばれるこの装置は、透析治療の成果を左右する、まさに心臓部です。
この記事では、ダイアライザーがどのような仕組みで血液を浄化するのかという基本から、性能を決める要素、様々な種類と特徴、そして治療の質を示す透析効率との深い関係性まで、解説します。
血液透析の心臓部「ダイアライザー」とは何か
血液透析治療の中心的な役割を担うダイアライザーは、腎臓の機能を代行するために開発された高度な医療機器です。
人工腎臓と呼ばれる理由
健康な腎臓は、血液中から老廃物や余分な水分をろ過して尿として排泄し、体内の環境を一定に保つ働きをしています。ダイアライザーは、腎臓の最も重要な働きである血液浄化機能を代行します。
透析装置に接続され、体から取り出した血液を内部で浄化し、きれいになった血液を再び体内に戻すという一連の流れの中心に位置することから、人工腎臓という名で呼ばれています。
ダイアライザーの基本的な構造
ダイアライザーは、一見すると単純な筒のように見えますが、内部には極めて精巧な構造が隠されています。外側のケースはハウジングと呼ばれ、中には1万本以上もの非常に細いストロー状の糸、中空糸が束ねられています。
中空糸一本一本が、血液を浄化するためのフィルターとしての役割を果たし、血液は中空糸の内側を通り、外側を透析液が流れる構造です。
ダイアライザーの主要な構成部分
| 構成部分 | 役割 | 特徴 |
|---|---|---|
| ハウジング | 外側の容器 | 中空糸膜を保護し、血液と透析液の流路を形成する |
| 中空糸膜 | 血液を浄化するフィルター | 目に見えない微細な孔が無数に開いている半透膜 |
| ポッティング材 | 中空糸の束を固定する樹脂 | 血液と透析液が混ざらないように完全に分離する |
中空糸膜の役割と血液浄化の仕組み
ダイアライザーの性能を決定づける最も重要な部分が、中空糸の壁を形成する半透膜です。膜には、目には見えないほどの微細な孔(ポア)が無数に開いていて、血液が中空糸の内部を流れる間に、この孔を通じて物質の移動が行われます。
尿素やクレアチニンといった小さな老廃物や余分な水分は、孔を通り抜けて透析液側へ除去され、赤血球やタンパク質といった体に必要な大きな成分は、孔を通り抜けることができないため、血液中に留まります。
この選択的な物質透過性によって、血液の浄化が実現するのです。
なぜ一人ひとりに合った選択が重要なのか
人の体格や年齢、食事内容、合併症の有無が一人ひとり違うように、除去すべき老廃物の量や種類も患者さんによって異なり、また、体質によっては、特定の膜素材に対してアレルギーのような反応を示す方もいます。
画一的なダイアライザーを使うのではなく、個々の患者さんの体の状態や治療目標に合わせて、膜の面積や素材、性能が異なる数多くの種類の中から、最も適したものを選ぶことが大事です。
ダイアライザーの性能を決める3つの重要要素
ダイアライザーの性能は、主に以下の3つの要素によって総合的に決まります。
- 膜面積(サイズ)
- 膜素材(生体適合性)
- 分画特性(孔のサイズ)
物質除去の基本原理「拡散」と「ろ過」
ダイアライザーでの物質除去は、主に拡散とろ過という二つの物理現象を利用しています。
拡散は、濃度の高い方から低い方へ物質が自然に移動する現象です。透析液には老廃物が含まれていないため、濃度差によって血液中の小さな老廃物が透析液側へ引き寄せられます。
ろ過は、圧力差を利用して水分とそれに溶けている物質を膜の向こう側へ押し出す現象で、コーヒーを淹れる際にフィルターで水分をこし出すイメージです。
拡散とろ過の働き方の違い
| 原理 | 主な除去対象 | 仕組み |
|---|---|---|
| 拡散 | 尿素、クレアチニンなど(小分子物質) | 濃度差による自然な移動 |
| ろ過 | 水分、中分子物質 | 圧力差による強制的な移動 |
膜面積(サイズ)と物質除去能力
ダイアライザーの性能を左右する最も分かりやすい要素が、内部の中空糸膜の総面積です。
膜面積が大きければ大きいほど、血液が膜と接する面積が広くなるため、単位時間あたりに除去できる老廃物や水分の量が増加し、透析効率が高まります。
ダイアライザーのサイズは、この膜面積によってS、M、Lのように区分され、一般的に体格の大きい患者さんには膜面積の大きいダイアライザーを使用します。
製品には1.5、1.8、2.1といった数字が記載されていることが多く、これは膜面積(㎡)のことです。
膜素材の種類と生体適合性
中空糸膜に使われる素材も、ダイアライザーの性能を大きく左右します。かつては植物由来のセルロース系の膜が主流でしたが、現在ではほとんどがポリスルホンなどの合成高分子膜に置き換わっています。
膜素材を選ぶ上で重要なのが、生体適合性という考え方です。これは、膜が血液と接触した際に、体が異物として認識して引き起こすアレルギー反応や炎症反応の起こりにくさを示します。
生体適合性の高い膜を使用することで、透析中の不快な症状を軽減し、体への負担を減らすことができます。
除去できる物質の大きさを決める「分画特性」
分画特性とは、半透膜がどの大きさの物質まで通すかという、孔のサイズに関する性能のことです。
尿素のような小さな老廃物だけでなく、関節痛などの原因となるβ2-マイクログロブリンのような少し大きめの中分子量物質まで除去できるかどうかが、長期的な合併症予防の観点から重要視されています。
孔のサイズが大きい膜ほど、より大きな物質まで除去できますが、体に必要なアルブミンなどのタンパク質が漏れ出てしまうリスクも考慮しなくてはなりません。このバランスが、ダイアライザーの性能を特徴づける重要なポイントです。
除去対象となる尿毒素の大きさ
| 分類 | 代表的な物質 | 分子量(Da) |
|---|---|---|
| 小分子物質 | 尿素、クレアチニン | 60~113 |
| 中分子物質 | β2-マイクログロブリン | 約12,000 |
| タンパク質(保持対象) | アルブミン | 約66,000 |
【性能別】ダイアライザーの分類と種類
ダイアライザーは、その性能、特にβ2-マイクログロブリンの除去能力とアルブミンの漏出量によって、いくつかの種類に分類されます。日本透析医学会の分類基準に基づいて、それぞれの特徴を見ていきましょう。
膜の性能による分類(Ⅰ型~Ⅴ型)
現在、臨床で使われるダイアライザーは、その性能に応じてⅠ型からⅤ型までの5つのカテゴリーに分類されています。
分類は、主にβ2-マイクログロブリンの除去率を示すβ2-MGクリアランスと、アルブミンの漏出のしにくさに基づいて決められていて、数字が大きくなるほどより高性能な膜です。
ダイアライザーの性能分類(2019年版)
| 分類 | β2-MGクリアランス (mL/min) | 主な特徴 |
|---|---|---|
| Ⅰa/b型 | 10未満 / 10以上20未満 | ローフラックス膜 |
| Ⅱ型 | 20以上30未満 | – |
| Ⅲ型 | 30以上50未満 | ハイフラックス膜 |
| Ⅳ型 | 50以上70未満 | ハイパフォーマンス膜 |
| Ⅴ型 | 70以上 | スーパーハイパフォーマンス膜 |
Ⅰ型(ローフラックス膜)の特徴と対象
Ⅰ型に分類されるダイアライザーは、ローフラックス膜とも呼ばれ、膜の孔が比較的小さく、主に拡散によって小分子物質を除去する能力に特化しています。
β2-マイクログロブリンのような中分子物質の除去能力は低く、アルブミンはほとんど漏出しません。透析導入期の患者さんや、全身状態が不安定な高齢の患者さんなどに用いられることがあります。
Ⅳ型・Ⅴ型(ハイパフォーマンス膜)の特徴と利点
Ⅳ型やⅤ型に分類されるダイアライザーは、ハイパフォーマンス膜と呼ばれ、現在の血液透析治療の主流です。
このような膜は孔が大きく、拡散に加えてろ過を効率的に利用することで、β2-マイクログロブリンなどの大きな老廃物までしっかりと除去する能力に優れています。
- 長期合併症(透析アミロイドーシス)の予防
- かゆみや不眠、イライラ感の改善
- 貧血の改善(EPO製剤の効果向上)
- 栄養状態の改善
なぜ高性能な膜が求められるのか
透析治療の目標は、単に生命を維持するだけでなく、透析を受けながらも健康な人と変わらない生活の質(QOL)を保つことにあります。かつては除去が難しかった中分子量領域の尿毒素が、様々な合併症の原因となることが分かってきました。
このため、中分子量領域の尿毒素を積極的に除去できる高性能なダイアライザーの開発が進められ、今では多くの施設で標準的に使用されるようになっています。
ダイアライザーの膜素材とその特徴
ダイアライザーの性能を語る上で、中空糸膜の素材は欠かせない要素です。現在、様々な特徴を持つ合成高分子膜が開発され、患者さんの状態に合わせて使い分けられています。
主流となっている合成高分子膜
現在のダイアライザー市場では、化学的に合成されたポリマーを原料とする合成高分子膜が大半を占めています。
かつて主流だったセルロース系膜に比べて生体適合性が高く、また、膜の孔の大きさや構造を精密にコントロールできるため、目的に応じた高性能なダイアライザーを設計しやすいことが利点です。
代表的な素材
- ポリスルホン(PS)膜
- ポリエーテルスルホン(PES)膜
- ポリメチルメタクリレート(PMMA)膜
- エチレンビニルアルコール共重合体(EVAL)膜
ポリスルホン(PS)膜の特徴
ポリスルホンは、現在世界で最も広く使用されている膜素材の一つです。優れた物質除去能力と高い生体適合性を両立しており、幅広い患者さんに使用されています。
また、親水化剤であるポリビニルピロリドン(PVP)を添加することで、膜表面へのタンパク質の吸着を抑え、アレルギー反応のリスクを低減します。
ポリエーテルスルホン(PES)膜の特徴
ポリエーテルスルホンも、ポリスルホンと並んで多用される代表的な膜素材です。ポリスルホンよりもさらに親水性が高く、PVPを含まない製品もあるため、PVPに対して過敏な反応を示す患者さんにも安心して使用できます。
シャープな分画特性を持ち、必要な物質は通さず、不要な物質を効率よく除去する能力に優れています。
代表的な合成高分子膜の比較
| 膜素材 | 主な特徴 | 考慮点 |
|---|---|---|
| ポリスルホン(PS) | 高い実績とバランスの取れた性能 | 親水化剤(PVP)を含む製品が多い |
| ポリエーテルスルホン(PES) | 高い親水性、シャープな分画特性 | PVPフリーの選択肢がある |
| ポリメチルメタクリレート(PMMA) | タンパク質吸着特性を持つ | 炎症性サイトカインなどを吸着除去する |
その他の膜素材(PMMA膜、EVAL膜など)
上記の他にも、特徴的な機能を持つ膜素材があります。ポリメチルメタクリレート(PMMA)膜は、膜の孔を通すだけでなく、膜自体に炎症を引き起こす物質などを吸着して除去するというユニークな特性を持っています。
また、エチレンビニルアルコール共重合体(EVAL)膜は、生体適合性が非常に高いです。
「透析効率」とは何か?評価方法
透析治療が十分に行われているかどうかを客観的に評価する指標が透析効率で、ダイアライザーの性能は、透析効率に直結する重要な要素です。
透析効率が治療の質を左右する
透析効率とは、一回の透析治療でどれだけ老廃物を除去できたかを示す指標です。透析効率が低い状態が続くと、体内に老廃物が十分に除去されずに残り、倦怠感や食欲不振、かゆみといった様々な症状の原因となります。
さらに長期的には、心血管系の合併症や栄養障害のリスクを高めることにもつながり、十分な透析効率を確保し維持することが、元気で長生きするための鍵です。
小分子尿毒素の除去効率を測る指標(クリアランス)
特定の物質をどれだけ除去できたかを示す指標として、クリアランスという値を用い、単位時間あたりに物質を完全に除去した血液量を示し、mL/minという単位で表します。
特に、尿素(Urea)のクリアランスは、透析効率を評価する上で最も基本的な指標の一つです。ダイアライザーの性能表には、様々な物質のクリアランス値が記載されており、性能を比較する際の参考になります。
β2-マイクログロブリンの除去と長期合併症予防
β2-マイクログロブリン(β2-MG)は、透析アミロイドーシスという長期合併症の原因物質で、分子量が比較大きいため、従来のダイアライザーでは十分に除去できませんでした。
しかし、ハイパフォーマンス膜の登場により、このβ2-MGを効率的に除去できるようになっています。血中のβ2-MG濃度を低く保つことが、関節痛や骨の病変を防ぎ、長期的なQOLを維持する上で非常に重要です。
透析量(Kt/V)で見る透析の充足度
一回の透析で得られた治療の量を総合的に評価する指標として、Kt/V(ケーティーオーバーブイ)が国際的に広く用いられています。
Kはダイアライザーの尿素クリアランス、tは透析時間、Vは患者さんの体液量を表し、Kt/Vはダイアライザーの性能、透析時間、そして患者さんの体格を考慮した、透析の充足度を示す指標です。
日本の透析医学会では、週3回透析の場合、Kt/Vが1.2以上であることを目標としています。
Kt/Vを構成する要素
| 記号 | 意味 | 透析効率への影響 |
|---|---|---|
| K | ダイアライザーの性能(クリアランス) | 高性能なほどKは高くなる |
| t | 時間(Time) | 長いほどtは大きくなる |
| V | 患者の体液量(Volume) | 体格が大きいほどVは大きくなる |
より良い透析効率を目指すために
高い透析効率を得るためには、高性能なダイアライザーを選ぶことだけが全てではありません。治療条件や体の状態など、他の要素も大きく関わってきます。
ダイアライザー選択以外の重要因子
透析効率は、ダイアライザーの性能(K)と透析時間(t)の積で決まります。いくら高性能なダイアライザーを使っても、十分な透析時間が確保されていなければ、目標とする透析量(Kt/V)には達しません。
また、ダイアライザーに十分な量の血液を送り込むための血流量も、効率に大きく影響します。透析効率を高めるには、以下の要素を総合的に考える必要があります。
- ダイアライザーの性能
- 十分な透析時間
- 十分な血流量(シャントの状態)
血流量(ブラッドアクセス)の重要性
ダイアライザーがその性能を最大限に発揮するためには、十分な速さで血液を送り込む必要があり、血流量は、シャントやグラフトといったブラッドアクセスの状態に大きく左右されます。
シャントの状態が良く、十分な血流量が確保できれば、ダイアライザーの除去能力を最大限に引き出すことができます。シャントの自己管理も、透析効率を高める上で大切な要素です。
透析時間と治療効果の関係
透析時間もまた、透析効率を決定する重要な因子です。同じダイアライザー、同じ血流量であっても、透析時間を長くすればするほど、より多くの老廃物を除去でき、Kt/Vは向上します。
日本の多くの施設では1回4時間の透析が標準的ですが、患者さんの状態によっては、より長い時間の透析を行うことで、血圧の安定や体調の改善が見られることがあります。
オンラインHDFという選択肢
より高い透析効率を目指す治療法として、オンライン血液透析ろ過(オンラインHDF)があり、これは、高性能なダイアライザーを使用し、ろ過を積極的に行うことで中分子物質の除去をさらに高める治療法です。
除去した水分と同じ量の清浄な補充液を体内に戻しながら行うため、循環動態が安定しやすいという利点もあります。関節痛やかゆみ、貧血の改善など、様々な臨床効果が報告されています。
血液透析(HD)とオンラインHDFの比較
| 項目 | 血液透析(HD) | オンラインHDF |
|---|---|---|
| 主な除去原理 | 拡散 | 拡散 + 大量のろ過 |
| 中分子物質除去 | 比較的良好 | 非常に良好 |
| 利点 | 標準的な治療法 | 合併症改善効果、血圧安定などが期待できる |
ダイアライザーに関するよくある質問(FAQ)
最後に、患者さんから寄せられることの多い、ダイアライザーに関する質問と回答をまとめました。
- 自分に合わないダイアライザーを使うとどうなりますか?
-
ダイアライザーが体に合わない場合、いくつかの問題が起こる可能性があります。
- 膜素材に対するアレルギー反応(透析中の胸痛、かゆみ、血圧低下など)
- 性能不足による老廃物の蓄積(倦怠感、食欲不振など)
- 長期的な合併症(心血管疾患、透析アミロイドーシスなど)のリスク増大
- ダイアライザーは再利用するのですか?
-
かつては、医療費削減の観点からダイアライザーを洗浄・消毒して再利用(リユース)することがありましたが、現在では感染症のリスクや性能低下の懸念から、ほとんどの施設で毎回新しいダイアライザーを使用する単回使用(シングルユース)が原則です。
- ダイアライザーの種類を変更してもらうことはできますか?
-
ダイアライザーの選択は、医師が患者さんの体格、血液データ、合併症の有無、透析中の状態などを総合的に判断して決定します。
もし、現在の治療で体調に不安があったり、より良い治療を目指したいという希望があったりする場合には、その旨を医師に伝えることが重要です。
相談の上で、よりご自身の状態に適した種類のダイアライザーへの変更を検討することは可能です。
- 治療中にダイアライザーが詰まることはありますか?
-
非常に稀ですが、血液が固まりやすくなっているなどの理由で、ダイアライザーの中空糸が部分的に詰まること(残血)があります。残血が多くなると、有効な膜面積が減少し、透析効率が低下する原因になります。
透析中には抗凝固薬を使用して血液が固まるのを防いでいますが、残血の状態は毎回スタッフが確認し、必要に応じて抗凝固薬の量を調整したり、ダイアライザーの種類を見直したりします。
以上
参考文献
Abe M, Hamano T, Wada A, Nakai S, Masakane I, Renal Data Registry Committee, Japanese Society for Dialysis Therapy. Effect of dialyzer membrane materials on survival in chronic hemodialysis patients: results from the annual survey of the Japanese Nationwide Dialysis Registry. PLoS One. 2017 Sep 14;12(9):e0184424.
Abe M, Kikuchi K, Wada A, Nakai S, Kanda E, Hanafusa N. Current dialyzer classification in Japan and mortality risk in patients undergoing hemodialysis. Scientific reports. 2024 May 4;14(1):10272.
Abe M, Masakane I, Wada A, Nakai S, Nitta K, Nakamoto H. Dialyzer classification and mortality in hemodialysis patients: a 3-year nationwide cohort study. Frontiers in Medicine. 2021 Aug 27;8:740461.
Mineshima M, Ishimori I, Ishida K, Hoshino T, Kaneko I, Sato Y, Agishi T, Tamamura N, Sakurai H, Masuda T, Hattori H. Effects of internal filtration on the solute removal efficiency of a dialyzer. ASAIO journal. 2000 Jul 1;46(4):456-60.
Abe M, Masakane I, Wada A, Nakai S, Nitta K, Nakamoto H. Super high-flux membrane dialyzers improve mortality in patients on hemodialysis: a 3-year nationwide cohort study. Clinical Kidney Journal. 2022 Mar;15(3):473-83.
Fujimura T, Uchi Y, Fukuda M, Miyazaki M, Uezumi S, Hiyoshi T. Development of a dialyzer with enhanced internal filtration to increase the clearance of low molecular weight proteins. Journal of Artificial Organs. 2004 Sep;7(3):149-54.
Abe M, Hamano T, Wada A, Nakai S, Masakane I. High-performance membrane dialyzers and mortality in hemodialysis patients: a 2-year cohort study from the annual survey of the Japanese renal data registry. American Journal of Nephrology. 2017 Jul 4;46(1):82-92.
Yamamoto KI, Matsukawa H, Yakushiji T, Fukuda M, Hiyoshi T, Sakai K. Technical evaluation of dialysate flow in a newly designed dialyzer. ASAIO Journal. 2007 Jan 1;53(1):36-40.
Kashiwagi T, Sato K, Kawakami S, Kiyomoto M, Enomoto M, Suzuki T, Genei H, Nakada H, Iino Y, Katayama Y. Effects of reduced dialysis fluid flow in hemodialysis. Journal of Nippon Medical School. 2013;80(2):119-30.
Yamamoto KI, Hiwatari M, Kohori F, Sakai K, Fukuda M, Hiyoshi T. Membrane fouling and dialysate flow pattern in an internal filtration-enhancing dialyzer. Journal of Artificial Organs. 2005 Sep;8(3):198-205.