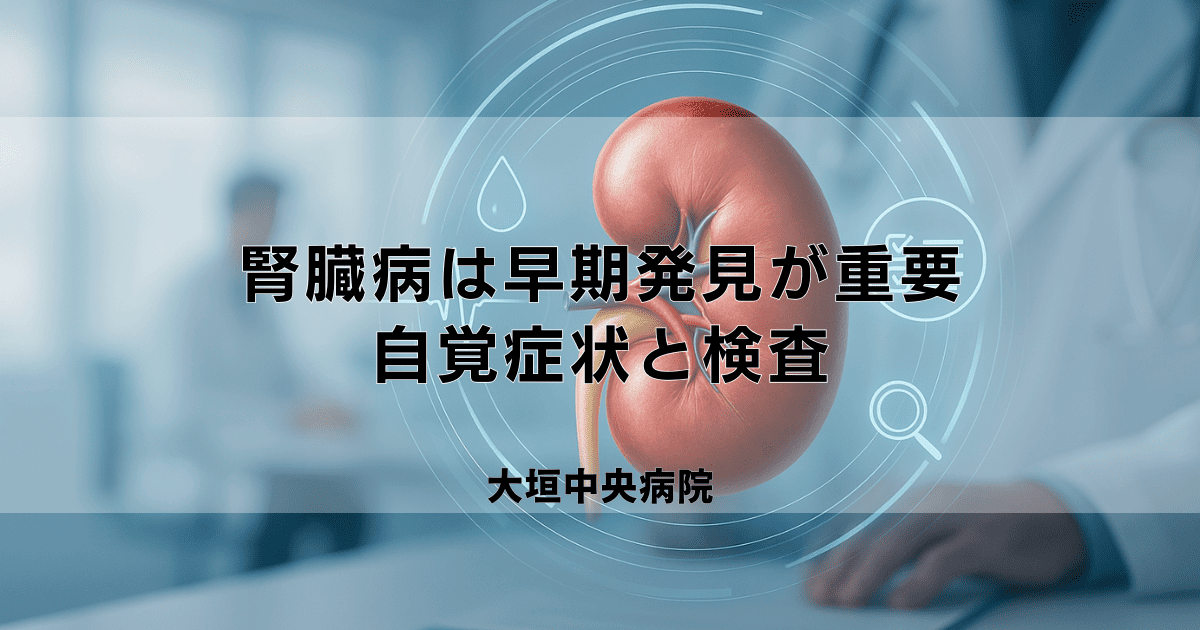私たちの体の中で、黙々と働き続ける臓器である腎臓の重要性について、普段意識することは少ないかもしれませんが、腎臓は生命維持に欠かせない多くの役割を担っています。
そして、腎臓病は自覚症状がないまま静かに進行する、いわゆる沈黙の病気です。気づいたときには機能が大幅に低下していた、ということも少なくありません。だからこそ、腎臓の病気は早期発見と早期の対策が何よりも重要です。
この記事では、腎臓の働きから、見逃したくないサイン、早期発見のための検査、そして大切な腎臓を守るための予防的な生活習慣まで、詳しく解説します。
沈黙の臓器腎臓の役割と腎臓病の怖さ
腎臓病の対策を考える前に、まずは私たちの体にとって腎臓がいかに大切な存在であるか、そして腎臓病がなぜ怖いのかを理解することが大切です。
腎臓は体の中のスーパーフィルター
腎臓は、腰のあたりに左右一対ある、握りこぶしほどの大きさの臓器です。
最も重要な働きは、血液をろ過して老廃物や余分な塩分・水分を尿として体外に排出することで、フィルター機能は非常に精密で、体に必要なタンパク質などは再吸収し、不要なものだけを選んで捨てています。
しかし、腎臓の働きはそれだけではありません。血圧を調整するホルモンや、赤血球を作るのを助けるホルモンを分泌したり、ビタミンDを活性化させて骨を丈夫に保ったりと、多彩な役割を担っています。
腎臓が担う主な役割
| 役割 | 具体的な働き |
|---|---|
| 老廃物の排出 | 血液をろ過し、体内のゴミを尿として捨てる。 |
| 体液・電解質の調整 | 体内の水分量やミネラルバランスを一定に保つ。 |
| 血圧の調整 | 血圧をコントロールするホルモンを分泌する。 |
腎臓病とはどのような状態か
腎臓病とは、何らかの原因で腎臓の働きが低下したり、腎臓の組織に異常が生じたりする状態の総称です。
腎臓のフィルター機能を持つ糸球体や、尿を作る尿細管などがダメージを受けると、老廃物を十分に排出できなくなったり、本来は体内に留めておくべきタンパク質が尿に漏れ出したりします。
この状態が長く続くと、体内に毒素が溜まったり、むくみや高血圧を引き起こしたりと、全身にさまざまな悪影響が及びます。
なぜ腎臓病は気づきにくいのか
腎臓は非常に我慢強く、予備能力の高い臓器です。腎機能が半分くらいまで低下しても、ほとんど自覚症状が現れません。
残った正常な部分が、機能が低下した部分の働きを補おうと懸命に頑張るため、多くの人が体調の異変を感じて医療機関を受診したときには、すでに腎機能がかなり悪化しているケースが少なくないのです。
だからこそ、症状がないうちからの腎臓の検査が重要になります。
慢性腎臓病(CKD)という考え方
現在、腎臓病の対策では、慢性腎臓病(CKD:Chronic Kidney Disease)という考え方が世界的に広まっています。CKDとは、一つの病名ではなく、腎臓の障害や機能低下が慢性的に続いている状態を指す包括的な概念です。
尿たんぱくなどの腎障害を示す所見、あるいは腎機能の指標であるeGFRが60ml/分/1.73m²未満の状態が、3ヶ月以上続く場合に診断されます。
CKDは、進行すると末期腎不全に至り、透析や腎移植が必要になるだけでなく、心筋梗塞や脳卒中といった心血管疾患の大きなリスク因子となることが分かっています。
CKDを早期に発見し、進行を食い止めることが、健康寿命を延ばす上で非常に大切です。
腎臓が出す危険信号見逃したくない自覚症状
腎臓は沈黙の臓器ですが、機能の低下がある程度進むと、体はさまざまなサインを発し始めます。他の病気や単なる疲れと間違えやすいものも多いため、注意深く観察することが腎臓病の早期発見につながります。
初期にはほとんど症状がない
腎臓病の初期段階では自覚できる症状はほぼなく、健康診断で尿たんぱくや血尿を指摘されても、痛みやかゆみがないため、そのまま放置してしまう人が後を絶ちません。
しかし、無症状の時期こそが、治療によって腎機能の低下を食い止められる最も重要なタイミングです。健康診断の結果は、腎臓からの最初のメッセージと捉え、決して軽視しないようにしましょう。
尿の変化に気づく(泡立ち、色、頻度)
腎臓の働きが低下してくると、尿に変化が現れることがあり、比較的早期から見られるサインの一つです。腎臓のフィルター機能が壊れ、本来は体内に留まるはずのタンパク質が尿に漏れ出すと、尿の表面張力が変化して泡立ちやすくなります。
特に、しばらくたっても消えないきめ細かい泡は要注意です。また、夜間に何度もトイレに起きるようになる(夜間頻尿)のも、腎臓が尿を濃縮する能力が落ちているサインかもしれません。
注意すべき尿の変化
| 変化の種類 | 考えられる腎臓の状態 |
|---|---|
| 尿の泡立ちが消えない | 尿中にタンパク質が漏れ出している(タンパク尿)。 |
| 夜間のトイレの回数が増える | 腎臓の尿濃縮機能が低下している。 |
| 尿の色が濃い(コーラ色など) | 血液が混じっている(血尿)。急性腎炎などの可能性。 |
体の変化に気づく(むくみ、だるさ、貧血)
腎機能の低下がさらに進むと、全身に症状が現れ始め、余分な塩分や水分を排出できなくなることで、足のすねや甲、まぶたなどがむくむようになります。
また、赤血球を作るホルモン(エリスロポエチン)の分泌が減るため、貧血(腎性貧血)になり、階段を上っただけで息切れがしたり、体がだるく感じたりします。
老廃物が体に溜まることで、食欲不振や吐き気、皮膚のかゆみなどが起こることもあります。
- 足や顔のむくみ
- 貧血による動悸、息切れ、倦怠感
- 食欲不振、吐き気
- 皮膚のかゆみ
高血圧との密接な関係
腎臓病と高血圧は、互いに悪影響を及ぼしあう、非常に密接な関係にあり、高血圧が続くと、腎臓の細い血管がダメージを受けて腎機能が低下します。
腎機能が低下すると、塩分や水分の排出がうまくいかなくなったり、血圧を上げるホルモンが過剰に分泌されたりして、血圧が上昇します。血圧が高いと指摘されている方は、腎臓の機能にも注意が必要です。
腎臓病の早期発見に繋がる重要な検査
自覚症状に乏しい腎臓病を早期に発見するためには、定期的な健康診断などによる検査が極めて重要尿検査と血液で、検査は、腎臓の状態を知るための二大看板です。
健康診断の結果を見直す(尿検査)
尿検査は、体に負担なく行える、非常に有用な腎臓の検査で、特に重要なのが、尿たんぱくと尿潜血の二つの項目です。尿たんぱくは、腎臓のフィルターが傷ついていることを示します。
健康な人でもごく微量のタンパク質は尿に出ることがありますが、持続的に陽性となる場合は注意が必要です。尿潜血は、尿に血液が混じっている状態を示し、腎臓や尿管、膀胱など、尿の通り道のどこかに出血がある可能性を示唆します。
尿検査の主な項目とその意味
| 検査項目 | 基準値 | 陽性の場合に考えられること |
|---|---|---|
| 尿たんぱく | (-) | 腎臓のフィルター機能の障害(糸球体腎炎、糖尿病腎症など)。 |
| 尿潜血 | (-) | 腎臓や尿路からの出血(腎炎、結石、がんなど)。 |
| 尿糖 | (-) | 血糖値が高い状態(糖尿病)。 |
血液検査でわかること(クレアチニンとeGFR)
血液検査では、血清クレアチニン(Cr)という項目を測定します。
クレアチニンは、筋肉でエネルギーが使われた後に出る老廃物で、通常は腎臓でろ過されて尿中に排出されますが、腎機能が低下すると、クレアチニンを十分に排泄できなくなり、血液中の濃度が上昇します。
血清クレアチニンの値と、年齢、性別から計算で算出されるのが、eGFR(推算糸球体ろ過量)です。eGFRは、腎臓が1分間にどれくらいの血液をろ過できるかを示す指標で、現在の腎機能が正常の何パーセント程度であるかを客観的に評価できます。
尿検査と血液検査の組み合わせが大事
腎臓病の早期発見と正確な状態把握のためには、尿検査と血液検査の両方の結果を組み合わせて見ることが大切です。
eGFRの値が正常範囲内でも、尿たんぱくが陽性であれば、腎臓に何らかの障害が始まっているサインであり、CKDと診断され、尿たんぱくが陰性でもeGFRが低下していれば、やはりCKDです。
両方の検査を受けることで、腎臓の状態をより多角的に評価することが可能になります。
より詳しく調べるための画像検査
尿検査や血液検査で異常が見つかり、さらに詳しい情報が必要な場合には、画像検査を行います。腹部超音波(エコー)検査は、体に負担なく腎臓の大きさや形、結石やのう胞、腫瘍の有無などを調べることができます。
腎臓が萎縮していないかを見ることは、慢性的な経過を判断する上で重要です。その他、必要に応じてCT検査やMRI検査を行い、腎臓の血管の状態や、より詳細な内部構造を評価することもあります。
慢性腎臓病(CKD)のステージとその意味
慢性腎臓病(CKD)は、その重症度によっていくつかのステージに分類され、ステージは、主にeGFRの値に基づいて決まります。
eGFRでわかる腎臓の働き具合
eGFR(推算糸球体ろ過量)は、健康な人の腎機能を100%とした場合に、現在の腎機能がどの程度残っているかを示す指標と考えることができます。
eGFRが50ml/分/1.73m²であれば、腎機能が健康な人の約50%に低下している、というおおよその目安になり、数値が低いほど、腎機能が悪いことを意味します。健康診断の結果にeGFRの値が記載されている場合は、必ず確認しましょう。
CKDの重症度分類(ステージ分類)
CKDは、eGFRの値によってG1からG5までの5つのステージに分類されます。G1とG2は腎機能自体は比較的保たれていますが、尿たんぱくなどの腎障害がある状態です。
G3からは腎機能の低下が明確になり、G4、G5と進むにつれて、末期腎不全のリスクが高まり、G5は末期腎不全の状態であり、透析療法や腎移植が必要となる段階です。
eGFR値とCKDステージ
| ステージ | eGFR値 (ml/分/1.73m²) | 腎機能の状態 |
|---|---|---|
| G1 | 90以上 | 正常または高値(ただし腎障害あり) |
| G2 | 60~89 | 軽度低下(ただし腎障害あり) |
| G3a | 45~59 | 軽度~中等度低下 |
| G3b | 30~44 | 中等度~高度低下 |
| G4 | 15~29 | 高度低下 |
| G5 | 15未満 | 末期腎不全(ESKD) |
ステージごとに異なる目標と対策
G1やG2の早期の段階では、腎機能低下の原因となっている疾患(糖尿病や高血圧など)の治療を徹底し、生活習慣を改善することで、腎機能の低下速度を緩やかにすることが最大の目標です。
G3以降は、腎機能低下そのものに対する治療に加え、貧血やミネラル異常といったCKDに伴う合併症の管理が重要になります。そしてG4、G5と進行した場合には、将来的な腎代替療法(透析、腎移植)の準備を始めることも視野に入ってきます。
腎臓病のリスクを高める要因
腎臓病は誰にでも起こりうる病気ですが、なりやすい人がいることも事実です。どのような要因が腎臓に負担をかけ、病気のリスクを高めるのかを知ることは、効果的な予防に繋がります。
最大のリスク因子生活習慣病(糖尿病・高血圧)
現在、日本で新たに透析を導入する患者さんの原因疾患として、最も多いのが糖尿病性腎症、次いで高血圧などが原因の腎硬化症です。糖尿病では、高血糖の状態が続くことで腎臓の糸球体の血管が傷つき、フィルター機能が損なわれます。
高血圧では、高い圧力がかかることで腎臓の血管が硬化し、血流が悪くなって腎機能が低下します。生活習慣病をお持ちの方は、腎臓病の最もハイリスクなグループであり、定期的な腎臓の検査が絶対に必要です。
腎臓病の主な原因疾患(透析導入患者)
| 順位 | 原因疾患 | 特徴 |
|---|---|---|
| 1位 | 糖尿病性腎症 | 高血糖による腎臓の血管障害。 |
| 2位 | 腎硬化症 | 高血圧や加齢による腎臓の動脈硬化。 |
| 3位 | 慢性糸球体腎炎 | 免疫の異常などによる糸球体の炎症。 |
加齢と腎機能の自然な低下
年齢を重ねると、体の他の機能と同じように、腎機能も自然に少しずつ低下していきます。高血圧や糖尿病といった他のリスク因子がなくても、加齢そのものが腎臓病のリスクを高めます。
高齢化社会の進展に伴い、加齢による腎硬化症などが原因のCKD患者さんは増加傾向にあり、高齢の方は脱水や薬剤による腎障害を起こしやすいため、注意が必要です。
遺伝や家族歴も関係する
腎臓病の中には、遺伝的な要因が関与するものもあり、多発性のう胞腎は代表的な遺伝性の腎疾患です。
また、特定の病名がなくても、血縁関係のある家族に腎臓病や透析を受けている方がいる場合は、体質的に腎臓病になりやすい可能性があります。
ご家族に腎臓の悪い方がいる場合は、ご自身も若いうちから定期的に腎臓の検査を受けることをお勧めします。
喫煙と腎臓への悪影響
喫煙は、肺がんだけでなく、腎臓病のリスクも高めることが分かっています。タバコに含まれる有害物質は、血管を収縮させて血圧を上昇させたり、血管の内壁を傷つけて動脈硬化を促進したりします。
このことは、腎臓の細い血管にも悪影響を及ぼし、腎機能の低下を早める原因となり、また、喫煙は尿たんぱくを増やすことも報告されています。腎臓を守るためにも、禁煙は非常に重要です。
今日から始める腎臓を守るための予防的生活習慣
腎臓病の進行を抑え、大切な腎臓を長く健康に保つためには、日々の生活習慣を見直すことが最も効果的な予防策です。特別なことではなく、毎日の少しの心がけが、将来の腎臓を守ることに繋がります。
食生活で気をつけること(減塩が基本)
腎臓を守る食事の基本は、なんといっても減塩です。塩分の摂りすぎは、血圧を上昇させ、腎臓に直接的な負担をかけ、また、体内に余分な水分を溜め込み、むくみの原因にもなります。
日本人の食事は塩分が多い傾向にあるため、意識して減塩に取り組むことが大切です。まずは、1日の塩分摂取量を6g未満にすることを目指しましょう。
今日からできる減塩の工夫
| 工夫のポイント | 具体的な方法 |
|---|---|
| 香辛料や酸味を活用する | こしょう、カレー粉、唐辛子、酢、レモン汁などで味にアクセントをつける。 |
| だしや素材の味を活かす | 昆布やかつお節でしっかりだしを取り、食材本来の味を楽しむ。 |
| 加工食品を控える | ハム、ソーセージ、練り物、漬物などの摂取を減らす。 |
適度な運動で血圧と血糖をコントロール
ウォーキングや軽いジョギング、水泳などの有酸素運動を習慣にすることは、腎臓病の大きなリスクである高血圧や糖尿病の予防・改善に繋がります。運動によって、血圧が下がり、血糖値が安定し、肥満も解消できます。
無理に激しい運動をする必要はなく、少し汗ばむくらいの運動を、1日30分程度、週に3〜5日行うのが目標です。
まずは、一駅手前で降りて歩く、エレベーターではなく階段を使うなど、日常生活の中で体を動かす機会を増やすことから始めましょう。
水分補給の正しい考え方
適切な水分補給は、脱水を防ぎ、腎臓への血流を保つ上で重要です。特に夏場や運動時など、汗を多くかくときは、こまめに水分を摂るように心がけましょう。
ただし、腎機能が著しく低下している方や、むくみがある方は、水分の摂りすぎが心臓への負担になることもあり、医師から水分摂取量の指示が出ることがあります。
自己判断で極端に水分を制限したり、過剰に摂取したりせず、不安な場合は医師に相談してください。
薬との付き合い方(鎮痛薬など)
薬の中で特に注意が必要なのが、市販もされている非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)と呼ばれるタイプの痛み止めや解熱剤です。長期間、大量に服用すると、腎臓の血流が低下し、腎機能障害を起こすことがあります。
頭痛や関節痛などで日常的に痛み止めを服用している方は、一度かかりつけ医に相談することが望ましいです。また、他の病気で医療機関にかかる際は、腎臓が悪いことを必ず伝えましょう。
腎臓病に関するよくある質問(Q&A)
最後に、腎臓病に関して患者さんからよく寄せられる質問と回答をまとめました。
- 一度悪くなった腎臓は元に戻りますか
-
残念ながら、慢性腎臓病(CKD)によって一度失われた腎機能は、基本的には元に戻ることはありません。腎臓の組織が硬く変化(線維化)してしまうためです。
だからこそ、腎機能がそれ以上悪くならないように、進行を食い止めることが治療の最大の目標となります。
ただし、急激に腎機能が悪化する急性腎障害の場合は、原因を速やかに取り除くことで、機能が回復する可能性もあります。
- たんぱく質は制限した方が良いですか
-
タンパク質を摂りすぎると、その老廃物を排泄するために腎臓に負担がかかるため、腎機能が低下した場合には、タンパク質の摂取量を制限する食事療法(タンパク質制限食)が必要です。
ただし、タンパク質は体を作る上で重要な栄養素であり、過度な制限は栄養失調を招く恐れもあります。タンパク質制限を開始するタイミングや量は、CKDのステージや年齢、体格などによって異なります。
必ず、医師や管理栄養士の専門的な指導のもとで行うことが大切です。
- サプリメントを飲んでも大丈夫ですか
-
健康のためにサプリメントを利用している方も多いですが、腎機能が低下している場合は注意が必要です。
サプリメントに含まれる特定のビタミンやミネラルが、腎臓に負担をかけたり、体内に蓄積して悪影響を及ぼしたりすることがあります。
特に、カリウムやリンを多く含むものや、海外製の成分不明なサプリメントは避けるべきです。サプリメントを利用したい場合は、必ず事前に主治医や薬剤師に相談してください。
- どのような時に専門医に相談すべきですか
-
健康診断で尿たんぱくや尿潜血が陽性(特に2年連続など持続する場合)、あるいはeGFRの値が60未満であった場合は、症状がなくても一度、腎臓内科などの専門医に相談することをお勧めします。
また、足や顔のむくみが続く、尿の泡立ちが気になる、理由なく体がだるいといった自覚症状がある場合も、受診を検討すべきサインです。
参考文献
Imai E, Yamagata K, Iseki K, Iso H, Horio M, Mkino H, Hishida A, Matsuo S. Kidney disease screening program in Japan: history, outcome, and perspectives. Clinical journal of the American Society of Nephrology. 2007 Nov 1;2(6):1360-6.
Yamagata K, Iseki K, Nitta K, Imai H, Iino Y, Matsuo S, Makino H, Hishida A. Chronic kidney disease perspectives in Japan and the importance of urinalysis screening. Clinical and experimental nephrology. 2008 Feb;12:1-8.
Chen NA, HSU CC, Yamagata K, Langham R. Challenging chronic kidney disease: experience from chronic kidney disease prevention programs in Shanghai, Japan, Taiwan and Australia. Nephrology. 2010 Jun;15:31-6.
Iseki K. Chronic kidney disease in Japan from early predictions to current facts. Nephron Clinical Practice. 2008 Nov 10;110(4):c268-72.
Takahashi S, Okada K, Yanai M. The Kidney Early Evaluation Program (KEEP) of Japan: results from the initial screening period. Kidney international. 2010 Mar 1;77:S17-23.
Mihara S, Kuroda K, Yoshioka R, Koyama W. Early detection of renal cell carcinoma by ultrasonographic screening—based on the results of 13 years screening in Japan. Ultrasound in medicine & biology. 1999 Sep 1;25(7):1033-9.
Iseki K, Oshiro S, Tozawa M, Iseki C, Ikemiya Y, Takishita S. Significance of hyperuricemia on the early detection of renal failure in a cohort of screened subjects. Hypertension Research. 2001;24(6):691-7.
Kondo M, Yamagata K, Hoshi SL, Saito C, Asahi K, Moriyama T, Tsuruya K, Yoshida H, Iseki K, Watanabe T. Cost-effectiveness of chronic kidney disease mass screening test in Japan. Clinical and experimental nephrology. 2012 Apr;16:279-91.
Yoshida Y, Kashiwabara K, Hirakawa Y, Tanaka T, Noso S, Ikegami H, Ohsugi M, Ueki K, Mita T, Watada H, Koya D. Conditions, pathogenesis, and progression of diabetic kidney disease and early decliner in Japan. BMJ open diabetes research & care. 2020 Mar 22;8(1).
Uchida HA, Wada J, Nagao Y, Ihara K. First-time diagnosis and referral practices for individuals with CKD by primary care physicians: a study of electronic medical records across multiple clinics in Japan. Clinical and Experimental Nephrology. 2025 May 16:1-2.