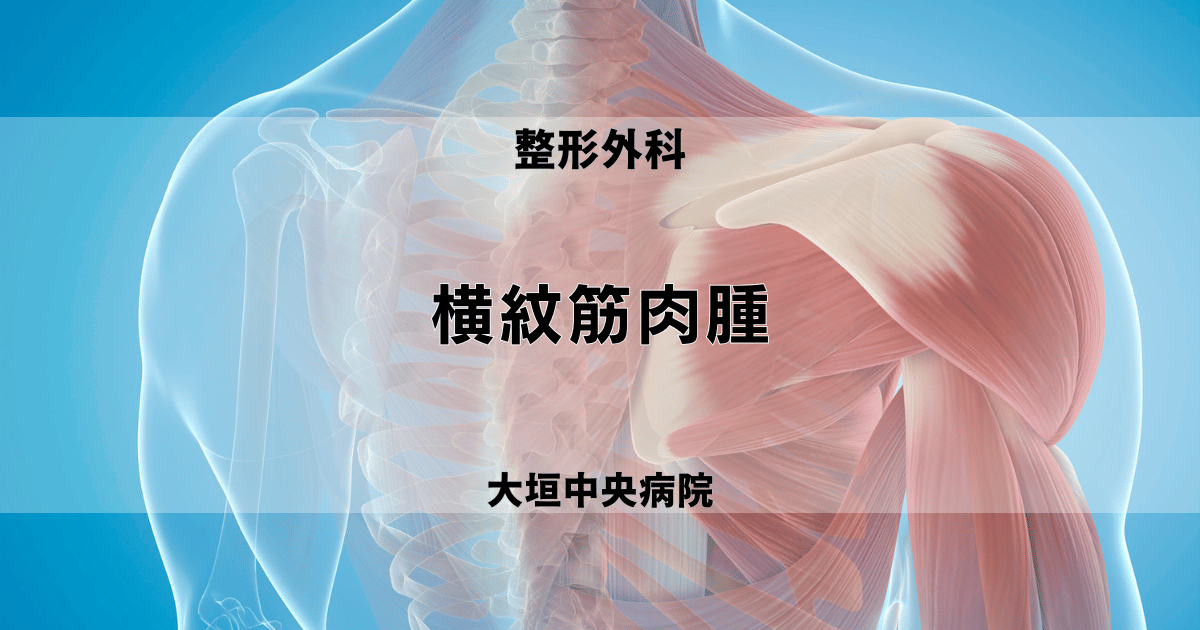横紋筋肉腫(Rhabdomyosarcoma, RMS)とは、骨格筋(横紋筋)に由来する悪性腫瘍の一種で、乳幼児から小児期に多くみられる病気です。
しかし成人にも発症し、全身のさまざまな部位に腫瘤や痛みを生じる可能性があります。
比較的まれな腫瘍であるため、名前を耳にする機会は多くないかもしれません。
横紋筋肉腫の治療成績は1970年代以降の集学的治療により大きく向上し、小児の5年生存率は1970年代の約50%から、近年では70%以上に改善しています。
この記事の執筆者

臼井 大記(うすい だいき)
日本整形外科学会認定専門医
医療社団法人豊正会大垣中央病院 整形外科・麻酔科 担当医師
2009年に帝京大学医学部医学科卒業後、厚生中央病院に勤務。東京医大病院麻酔科に入局後、カンボジアSun International Clinicに従事し、ノースウェスタン大学にて学位取得(修士)。帰国後、岐阜大学附属病院、高山赤十字病院、岐阜総合医療センター、岐阜赤十字病院で整形外科医として勤務。2023年4月より大垣中央病院に入職、整形外科・麻酔科の担当医を務める。
横紋筋肉腫の病型
横紋筋肉腫は、病理組織学的特徴により病型(サブタイプ)を分類します。世界保健機関(WHO)の軟部腫瘍分類第5版(2020年)では、4つに大別しています。
組織型により発生年齢・部位・遺伝学的特徴・予後が異なります。
診断時には病理組織検査に加え、融合遺伝子の有無など分子病理学的検査を行ってサブタイプ分類と予後予測に役立てています。
胚細胞型(Embryonal RMS)
小児例の約70~75%を占める最も一般的な病型です。5歳以下の幼児に好発し、頭頸部(眼窩周囲、鼻咽腔)、泌尿生殖器(膀胱、前立腺、膣)などに発生しやすい傾向があります。
組織学的には、未熟な横紋筋芽細胞が密度の低い間質中に散在する像を示します。
分子学的特徴として、第11番染色体短腕(11p15)のヘテロ接合性の消失(LOH)が約80%の症例で認められ、IGF2遺伝子の異常発現を伴います。
また、Li-Fraumeni症候群(TP53変異)や神経線維腫症1型(NF1)など遺伝性腫瘍症候群に合併するケースもあります。
以前は肉眼的にブドウ房状に増殖するボトリオイド型や紡錘細胞型などの亜型に細分類されていましたが、近年のWHO分類ではこれらも胚細胞型に包含されています。
胞巣型(Alveolar RMS)
小児例の約20~25%を占める病型で、学童期~青年期に好発し、四肢や体幹の筋組織、また頭頸部では副鼻腔・下眼瞼などに発生しやすいとされています。
組織学的には腫瘍細胞が隔壁によって区画化され、肺胞状の配列を示すのが特徴です。
分子学的には約80%の症例に特異的な融合遺伝子が認められ、代表的なものは第2番染色体PAX3遺伝子と第13番染色体FOXO1遺伝子の転座によるPAX3-FOXO1融合遺伝子、または第1番染色体PAX7とFOXO1のPAX7-FOXO1融合遺伝子です。
これら融合遺伝子陽性(FOXO1陽性)の胞巣型は予後不良因子であり、融合遺伝子を持たない胞巣型(FOXO1陰性)の方が臨床経過は良好で胚細胞型に近い予後を示します。
疫学的には男女差はなく、0~19歳で均等に発生し、100万人あたり1例程度の発症率と報告されています。
紡錘細胞/硬化型(Spindle cell/Sclerosing RMS)
比較的新しく独立分類された病型で、線維芽細胞様の紡錘形細胞からなる組織像を示します。
小児から成人まで発生し、小児の一部の症例ではVGLL2遺伝子やNCOA2遺伝子の転座融合(VGLL2-NCOA2など)が認められるのに対し、年長児~成人の症例ではMYOD1遺伝子変異(p.L122Rなど)を高頻度に伴うのが特徴です。
発生部位は頭頸部や四肢など様々ですが頻度は稀で、全RMS中の数%以下と推定されます。
小児の融合遺伝子陽性の例では予後良好な報告もありますが、特にMYOD1変異を有するタイプは治療抵抗性で不良とされます。
多形型(Pleomorphic RMS)
主に中高年の成人(40~60歳代)に発生する病型で、かつては成人横紋筋肉腫とも呼ばれていました。
四肢帯や臀部などの深部軟部組織に好発し、組織学的には多様な形態の異型細胞からなる高悪性度腫瘍で、免疫組織染色で骨格筋分化(デスミンや筋特異的マーカー陽性)を確認して診断します。
多形型RMSは他の成人肉腫(未分化多形肉腫など)との鑑別が難しく、複雑な染色体異常を伴うケースが多いとされています。
一般に小児型(胚細胞・胞巣型)より治療反応性が低く予後不良であり、専門の肉腫治療施設で集中的治療が行われます。
横紋筋肉腫の症状
横紋筋肉腫は、発生部位や病型によって症状が異なります。初期症状がはっきりしない場合もあるため、腫瘤や痛みに気づいたときにはある程度進行しているケースも珍しくありません。
初期の微妙な変化
- 皮下に小さなしこりを触れる
- 軽度の痛みや違和感を覚える
- 運動時に張りを感じることがある
- 発熱や体重減少は少ない
初期には特徴的な症状が少ない場合が多いです。触ってわかるような腫瘤が出るまでに時間がかかるケースや、筋肉痛や打撲と勘違いしやすい軽い痛みしか感じない人がいます。
また、場所によっては腫瘤が皮下に表れにくい場合もあり、症状を見逃しがちです。
初期症状を見極めるポイント
| 症状 | 注意すべき点 |
|---|---|
| しこり・腫瘤 | 大きくなるスピードや触った時の硬さ |
| 軽度の痛み | 痛みの原因不明で長引く場合 |
| 違和感や麻痺感 | 神経や血管への圧迫が起きている可能性 |
| 表面の赤みや腫れ | 炎症との鑑別が必要 |
全身的な症状(発熱、体重減少、夜間の発汗など)は典型的ではありません。
進行期の症状と合併症
- 腫瘍部位が腫れあがり、周辺組織に強い痛みをもたらす
- 感覚神経の障害によるしびれや麻痺
- 体幹や頭頸部の腫瘍による内臓機能への影響
- 転移先の臓器に応じた症状(肺転移による呼吸困難など)
腫瘍が大きくなると周囲の組織や臓器を圧迫・浸潤するため、より明確な症状が現れます。
四肢の場合は腫瘤の存在や痛み、可動域の制限などが出現しやすいです。頭頸部に発生した場合は呼吸困難や視力障害、鼻づまりなどが起こるときもあります。
また、症状が進行すると局所だけでなく転移によって全身状態が悪化する場合もあり、患者さんの生活の質に大きく影響します。
好発部位ごとの特徴
| 好発部位 | 症状 | 備考 |
|---|---|---|
| 頭頸部 | 視力障害、呼吸障害、鼻づまり、眼球突出、難聴など | 小児によくみられる |
| 泌尿生殖器 | 排尿困難、血尿、下腹部の腫れ | 胎児型の頻度が比較的高い |
| 四肢 | 皮下のしこり、痛み、運動障害 | 成人に比較的多い |
| 体幹(胸壁・腹壁) | しこり、深部痛、臓器圧迫症状 | 病型によっては発見が遅れる |
横紋筋肉腫はどの部位の骨格筋にも発生する可能性がありますが、特に好発しやすい部位には傾向があります。
小児では頭頸部や泌尿生殖器に多く、成人では四肢や体幹深部に腫瘍がみられるケースが比較的多いです。
症状の緩和策
- 鎮痛薬や消炎鎮痛薬の使用
- 術前・術後のリハビリテーションで患部への負担をコントロール
- 必要に応じて装具や車椅子を活用
- 心理的サポートや家族の協力体制を整える
横紋筋肉腫の進行による痛みや日常生活の障害を軽減するために、緩和策を取ります。
主な方法としては、痛み止め(鎮痛薬)の使用や神経ブロック注射の検討、腫瘍による圧迫を軽減するための装具の利用などがあります。
治療と並行してこうした対策を行うと、身体的・精神的な負担をやわらげる効果が期待できます。
横紋筋肉腫の原因
横紋筋肉腫の発生原因は明確には解明されていません。
環境要因(例えば放射線被曝や化学物質暴露)との関連は一部で研究されていますが、現時点で明らかなリスク因子とは認められておらず、大部分(90%以上)の症例は偶発的(孤発性)に発生しています。
喫煙や飲酒など生活習慣との関連も特に知られていません。
遺伝的素因に関する報告
一方で、遺伝的素因が関与する例が一部に存在します。
以下のような遺伝性腫瘍症候群・先天異常と横紋筋肉腫の関連が報告されています。
- Li-Fraumeni症候群(TP53遺伝子の生殖細胞変異)– 横紋筋肉腫を含む様々ながんのリスクが高まる。
- DICER1症候群(胚細胞性腫瘍や甲状腺腫瘍のリスクを伴う) – 横紋筋肉腫(特に胚細胞型)の発症が報告あり。
- 神経線維腫症1型 (NF1)– 神経系腫瘍に加え横紋筋肉腫の合併がみられることがある。
- Costello症候群(HRAS遺伝子変異)– 心臓疾患や発達遅滞に加え横紋筋肉腫の発症リスク増加が報告。
- Beckwith-Wiedemann症候群(生まれつきの過成長症候群) – 腎芽腫などとともに胚細胞型RMSの発症がまれにみられる。
- Noonan症候群 – 発達障害や心奇形を伴う症候群で、横紋筋肉腫の報告例がある。
- 高出生体重・巨大児 – 生まれたときの体重が大きいことが胚細胞型RMSの発症と関連するとの疫学研究がある。
しかし、これら遺伝要因に該当する患者さんは全体のごく一部であり、多くの横紋筋肉腫患者には明らかな遺伝的素因は認められません。
偶然起こる細胞の遺伝子変異の蓄積
実際、大規模な小児RMS患者コホート(615例)での検討では、7.3%にがん関連の生殖細胞変異が検出されたに留まり、それ以外は特定の遺伝的リスク因子を持たない孤発例でした。
要約すると、横紋筋肉腫の原因は不明であり、偶然起こる細胞の遺伝子変異の蓄積により発生する散発性の小児がんであると考えられています。
一部の患者さんでは遺伝的背景が寄与し得るものの、予防可能な環境因子は特定されていないのが現状です。
横紋筋肉腫の検査・チェック方法
横紋筋肉腫が疑われる場合、早期の的確な検査が重要です。
腫瘍の存在を確認し、その性質や広がりを見極めるために画像検査や血液検査、組織検査など複数の方法を組み合わせて診断と病期(ステージ)の確定を行います。
身体所見と初期診断の流れ
- 触診で腫瘤の硬さや可動範囲を確認
- 病歴から発症時期や痛みの変遷を把握
- 血液検査で炎症や貧血の有無をチェック
- 腫瘤の急速な拡大が疑われたら精密検査に進む
初期診断では、患者さんから詳しく症状や経過を聞き取り、同時に視診や触診を行います。
腫瘤の大きさや硬さ、移動性や痛みの有無などから、大まかに良性か悪性かを判断する手がかりを得ます。
さらに、必要に応じて血液検査を行い、腫瘍マーカーの動向を確認します。横紋筋肉腫の場合、特異的なマーカーはないケースが多いですが、LDH(乳酸脱水素酵素)などの上昇がみられる場合があります。
画像検査の種類と役割
| 検査名 | 特徴 | 目的 |
|---|---|---|
| MRI | 軟部組織や関節の描出が詳細 | 腫瘍の広がりや境界確認 |
| CT | 骨や肺などのチェックに有用 | 転移の確認 |
| PET-CT | 代謝の高い部位を画像化 | 全身的な病巣検索 |
| エコー | 小児や浅い部位の腫瘤確認に向く | 表在性腫瘤の評価 |
横紋筋肉腫の部位や進行度を把握するには、画像検査が欠かせません。代表的な検査方法としてMRI、CT、PET-CTなどが挙げられます。
MRIは軟部組織の描出が得意であり、腫瘍の広がりを詳細に評価するのに有用です。CTでは肺やリンパ節などへの転移を確認しやすくなります。さらにPET-CTはがん細胞の代謝活性を画像化でき、転移の有無を全身レベルでチェックします。
ただ、他の軟部腫瘍との鑑別は困難であるため画像のみで確定診断はできません。
生検と病理組織検査
| 生検方法 | 侵襲度 | 得られる情報の精度 | メリット |
|---|---|---|---|
| 針生検 | 低い | 細胞レベルの情報が得られる | 患者負担が小さい |
| 切開生検 | 中程度 | より広い組織断片を評価可能 | 診断の確度が高まる |
| 穿刺吸引細胞診 | 低い | 主に細胞単位の情報のみ | 外来でも対応が比較的容易 |
腫瘍の性質を正確に判断するためには、最終的に組織を採取して調べる生検が必要です。
生検では、針を刺して細胞や組織片を採取するコアニードル生検や、部分的に腫瘍組織を切り取る切開生検などの方法があります。
得られた組織を病理医が顕微鏡で観察し、横紋筋肉腫に特有の細胞形態や遺伝子異常の有無を確認します。
- 針生検は侵襲が比較的少ない
- 切開生検はより大きな組織を採取でき、正確性が高い
- 病理組織検査によって病型(胎児型、胞巣型、多形型など)を判別
転移の評価とステージング
横紋筋肉腫は、転移を起こすと治療方針や予後に大きく影響します。そのため、画像検査などを用いて全身のリンパ節や肺、骨、脳などへの転移の有無を詳細に調べます。
ステージングとは腫瘍の大きさ、リンパ節転移、遠隔転移の有無などを総合的に評価し、病期を決定する作業です。
正しいステージの把握は治療戦略を立てるうえで非常に重要になります。
- ステージIからIVまでに分類される
- リンパ節転移や遠隔転移を認める場合は進行期の可能性が高い
- 病理検査と画像検査を組み合わせて最終的な病期を決定
横紋筋肉腫の治療方法と治療薬、リハビリテーション、治療期間
横紋筋肉腫の治療は、外科手術、化学療法、放射線療法の3本柱で構成されます。
腫瘍の部位やサイズ、病期によって組み合わせや順番を調整し、効率的にがん細胞を抑え込む戦略を立案します。
外科手術の役割と注意点
- 切除範囲と機能温存のバランスが重要
- 四肢では筋肉や神経の温存を慎重に検討
- 頭頸部や骨盤内の腫瘍では高度な再建手術が必要な場合がある
外科手術は腫瘍を直接切除し、がん細胞を減らすうえで大きな役割を果たします。できるだけ腫瘍を取り切ることが大切ですが、切除範囲が広くなるほど術後の機能障害リスクが高まります。
そのため、手術前に化学療法や放射線療法を行い、腫瘍を縮小させてから切除する方法を採用するケースも多いです。
しかし、横紋筋肉腫は幼児の頭頸部や膀胱前立腺など、重要臓器に隣接して発生する場合も多いため、機能温存の観点から無理な拡大手術は避け、一部残存(R1/R2切除)となる例でも化学療法・放射線療法で補完する戦略がとられるときもあります。
外科的治療におけるメリット・デメリット
| 項目 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 腫瘍切除 | 腫瘍量を直接減らす | 切除範囲が広いと機能障害や後遺症を伴いやすい |
| 腫瘍縮小手術 | 化学療法や放射線との併用で効果を高めやすい | 周辺組織との境界が不明瞭だと取り残しが発生しやすい |
化学療法と代表的な治療薬
横紋筋肉腫の治療で重要な柱の1つが化学療法(抗がん剤)です。腫瘍を縮小させたり、転移を抑えたりする効果が期待できます。
代表的な薬剤としては、ビンクリスチン、アクチノマイシンD、シクロホスファミドなどが用いられます。
- ビンクリスチンは細胞分裂を阻害する機能を持つ
- アクチノマイシンDはDNA合成を妨げてがん細胞の増殖を抑える
- シクロホスファミドはDNAを損傷させるアルキル化剤
これらを組み合わせたレジメン※1を、患者さんの年齢や病期、全身状態に合わせて調整します。
※1レジメン:がん化学療法における抗がん剤や輸液、支持療法を組み合わせた時系列的な治療計画。
主な化学療法レジメンの例
| レジメン名 | 使用薬剤 | 投与スケジュール |
|---|---|---|
| VACレジメン | ビンクリスチン、アクチノマイシンD、シクロホスファミド | 3〜4週間ごとに数サイクル |
| VDC/IEレジメン | ビンクリスチン、ダクトマイシン、シクロホスファミド/イリノテカン、エトポシドなど | 病期や年齢に応じて調整 |
放射線療法の位置づけ
化学療法と同様、放射線療法も横紋筋肉腫の治療では欠かせない存在です。外科的切除が難しい部位で腫瘍を縮小させる、手術後の再発を防ぐ、といった目的で行います。
ただし、小児期の放射線照射は成長障害や二次がんのリスクがあるため、慎重に検討します。
成人の場合も、副作用に注意しながら照射範囲や線量を決定します。
横紋筋肉腫は放射線感受性が高いため、手術で腫瘍を完全に取り切れなかった場合や、初発時から肉眼的残存が想定される部位(頭蓋底など)では放射線治療が標準的に追加されます。
- 腫瘍局所に放射線を集中してがん細胞を死滅させる
- 外科的切除と化学療法の効果を補完する役割を担う
- 照射部位によっては皮膚障害や骨髄抑制が発生しやすい
リハビリテーションの重要性
横紋筋肉腫の治療では、手術や化学療法、放射線療法による副作用や後遺症が発生する可能性があります。
四肢や体幹に腫瘍があるときは、術後の可動域制限や筋力低下がみられる場合があるので、理学療法や作業療法を取り入れて機能回復を図ります。
また、心理的ケアの一環として、カウンセリングや音楽療法などを組み合わせて患者さんのQOL向上を目指します。
- 術後の運動指導による関節可動域の確保
- 筋力トレーニングやストレッチで再発を防ぎながら体力を維持
- 生活動作の訓練で職場復帰や学業復帰をサポート
- カウンセリングやサポートグループでメンタル面をケア
治療期間の目安
横紋筋肉腫の治療期間は、腫瘍の病期や治療方針によって大きく異なります。
小児では化学療法を数カ月から1年以上にわたって行うケースもありますし、成人でも複数サイクルの抗がん剤治療や放射線照射を計画する場合があります。
手術から治療終了まで、半年から1年程度かかるケースが比較的多いです。
- 化学療法は2〜6週間単位のサイクルを複数回実施
- 手術前の導入化学療法を行う場合は数カ月延びる可能性がある
- 合併症や副作用による治療スケジュールの変更もあり得る
薬の副作用や治療のデメリット
横紋筋肉腫の治療では、副作用や合併症、機能障害などのデメリットが生じるリスクがあります。
患者さんや家族はあらかじめこれらを理解し、主治医や医療スタッフとの連携のなかで対策を講じておきましょう。
化学療法による副作用
- 吐き気・嘔吐、食欲不振
- 脱毛や爪の変色
- 白血球や血小板の減少による感染や出血のリスク
- 神経障害や倦怠感
化学療法で使う薬剤は、がん細胞だけでなく正常な細胞にも影響を与えるため、多様な副作用が起こる可能性があります。
吐き気や脱毛、骨髄抑制による感染リスクの上昇などが代表的です。
副作用の種類や強度は個人差が大きいため、医師や看護師が症状をこまめにチェックし、必要に応じて支持療法(制吐剤や成長因子製剤など)を用いて対処します。
よくみられる副作用と対処法
| 副作用 | 症状 | 対処策 |
|---|---|---|
| 吐き気・嘔吐 | 食欲不振、脱水症状のリスク | 制吐剤の使用、水分補給、分割食 |
| 脱毛 | 頭髪の脱毛、眉毛・まつ毛の抜けなど | ウィッグや帽子の活用、頭皮ケア |
| 感染症のリスク | 発熱、咳、のどの痛み、下痢など | 手洗い・うがい、マスク着用、免疫力のサポート |
| 神経障害 | しびれや感覚鈍麻、筋力低下 | ビタミンB12などのサプリメント、運動療法 |
放射線療法による副作用
- 皮膚の赤みやかゆみ、潰瘍化
- 粘膜のただれや痛み
- 骨の成長障害や変形(小児)
- 放射線肺炎や放射線性腸炎
放射線療法では照射範囲の組織に炎症や損傷が起きるため、照射部位に応じた副作用が発生する場合があります。
皮膚炎や粘膜炎、倦怠感などが一般的で、小児期に照射した際は発育への影響も考慮が必要です。
外科手術後の機能障害
- 可動域の制限や筋力低下
- 神経麻痺による感覚や運動機能の低下
- 日常生活動作や仕事への影響
- 生活の質(QOL)の低下と心理的負担
- 整容面での問題
腫瘍切除範囲によっては、筋肉や神経、血管などがダメージを受け、身体の機能障害を残す可能性があります。
四肢の切除や大きな再建手術を行った場合は、術後のリハビリテーションを通して生活機能の回復を図る必要があります。
治療に伴う精神的ストレス
- 長期入院や外来通院への不安
- 副作用や後遺症に対する恐怖や落胆
- 学業や仕事、家事などの日常生活の制限
- 経済的負担や将来設計への懸念
体への負担だけでなく、治療期間が長引くために生活リズムが乱れたり、周囲に気を使わせてしまう心配が続いたりすると、精神的ストレスも大きくなります。
家族や医療スタッフとのコミュニケーションを密に行い、必要に応じてカウンセリングや心理療法を活用すると、心理的負担を軽減するうえで役立ちます。
保険適用と治療費
以下に記載している治療費(医療費)は目安であり、実際の費用は症状や治療内容、保険適用否により大幅に上回ることがございます。当院では料金に関する以下説明の不備や相違について、一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。
横紋筋肉腫の治療には、手術や化学療法、放射線療法など多彩な方法が必要になり、それぞれに費用が発生します。
日本では公的医療保険(健康保険)が適用されるため、自己負担額は実際にかかる総額より軽減されますが、負担がゼロになるわけではありません。
公的医療保険の適用範囲
手術や入院費、放射線療法や化学療法、リハビリテーションや検査費用など、横紋筋肉腫の治療に必要な多くの医療行為が健康保険の対象に含まれます。
自己負担割合は通常は3割ですが、年齢や所得に応じて1割〜2割になるケースもあります。高額療養費制度※2の対象となれば、一定の自己負担額を超えた分は払い戻しを受けられます。
※2高額療養費制度:1ヶ月当たりの医療費の上限が決められており、超過分が払い戻しされる制度。上限額は年齢や収入により決定される。手続きは市町村の役所や協会けんぽ支部、各健康保険組合や共済組合など、加入している医療保険により異なる。
- 高額療養費制度を利用すると月ごとの負担額を抑えられる
- 小児医療助成制度※3や小児慢性特定疾病医療費助成制度※4の活用が可能な場合もある
- 障害者手帳の取得によって医療費負担軽減が図れるケースもある
※3小児医療助成制度:各自治体が子どもの医療費を一部または全額助成する制度。自治体によって対象年齢や所得制限が異なるため、詳細はお住まいの市町村の役所に要確認。
※4小児慢性特定疾病医療費助成制度:医療費の自己負担割合が2割になり、月ごとの自己負担上限額が設定される。所得に応じて上限が異なる。国が定める小児慢性特定疾病にかかっている18歳未満のお子さんが対象。保健所や市町村の役所などで申請。
治療内容別の費用目安
費用目安は治療計画や入院日数、患者さんの状態によって大きく上下します。高額療養費制度を活用すると、実質的な自己負担がさらに低減される可能性があります。
加えて、小児の場合は自治体独自の医療助成制度の対象となる場合もあるため、各自治体の情報を調べるとよいでしょう。
| 治療項目 | 想定総額(自費の場合) | 保険適用後の目安(3割負担) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 手術費用(入院10日前後) | 100〜150万円程度 | 30〜45万円程度 | 切除範囲や再建手術の有無で変動 |
| 化学療法(1サイクル) | 15〜30万円程度 | 4.5〜9万円程度 | 複数サイクルを実施 |
| 放射線療法(合計30回程度) | 40〜80万円程度 | 12〜24万円程度 | 照射範囲や使用機器で差がある |
| 検査費用(MRI等) | 3〜5万円程度/回 | 9千〜1.5万円程度 | 検査回数により変動 |
| リハビリテーション | 5千〜1万円程度/日 | 1,500〜3千円程度/日 | 入院・外来リハビリで異なる |
入院と通院の費用
横紋筋肉腫の治療では、化学療法や放射線療法を通院で実施するケースもあります。
入院中は宿泊費(ベッド代)や食事代が追加でかかりますが、通院での化学療法を行った場合は交通費や付添いの家族の負担が増えやすいです。
患者さんの体力や治療計画を総合的に考慮し、入院か通院かを医療チームと相談しましょう。
- 外来治療なら入院費を抑えられるが、移動や生活負担が増す
- 入院治療なら医療スタッフの手厚いケアを受けやすい
- 仕事や家庭の事情を考慮して治療計画を決定する
以上
参考文献
SKAPEK, Stephen X., et al. Rhabdomyosarcoma. Nature reviews disease primers, 2019, 5.1: 1.
DASGUPTA, Roshni; FUCHS, Jörg; RODEBERG, David. Rhabdomyosarcoma. In: Seminars in pediatric surgery. WB Saunders, 2016. p. 276-283.
DAGHER, Ramzi; HELMAN, Lee. Rhabdomyosarcoma: an overview. The oncologist, 1999, 4.1: 34-44.
SHIELDS, Jerry A.; SHIELDS, Carol L. Rhabdomyosarcoma: review for the ophthalmologist. Survey of ophthalmology, 2003, 48.1: 39-57.
HETTMER, Simone; WAGERS, Amy J. Muscling in: Uncovering the origins of rhabdomyosarcoma. Nature medicine, 2010, 16.2: 171-173.
DASGUPTA, Roshni; RODEBERG, David A. Update on rhabdomyosarcoma. In: Seminars in pediatric surgery. WB Saunders, 2012. p. 68-78.
PARHAM, David M.; BARR, Frederic G. Classification of rhabdomyosarcoma and its molecular basis. Advances in anatomic pathology, 2013, 20.6: 387-397.
BREITFELD, Philip P.; MEYER, William H. Rhabdomyosarcoma: new windows of opportunity. The oncologist, 2005, 10.7: 518-527.
PAPPO, Alberto S.; SHAPIRO, David N.; CRIST, William M. Rhabdomyosarcoma: biology and treatment. Pediatric Clinics of North America, 1997, 44.4: 953-972.
XIA, Shujuan J.; PRESSEY, Joseph G.; BARR, Frederic G. Molecular pathogenesis of rhabdomyosarcoma. Cancer biology & therapy, 2002, 1.2: 97-104.