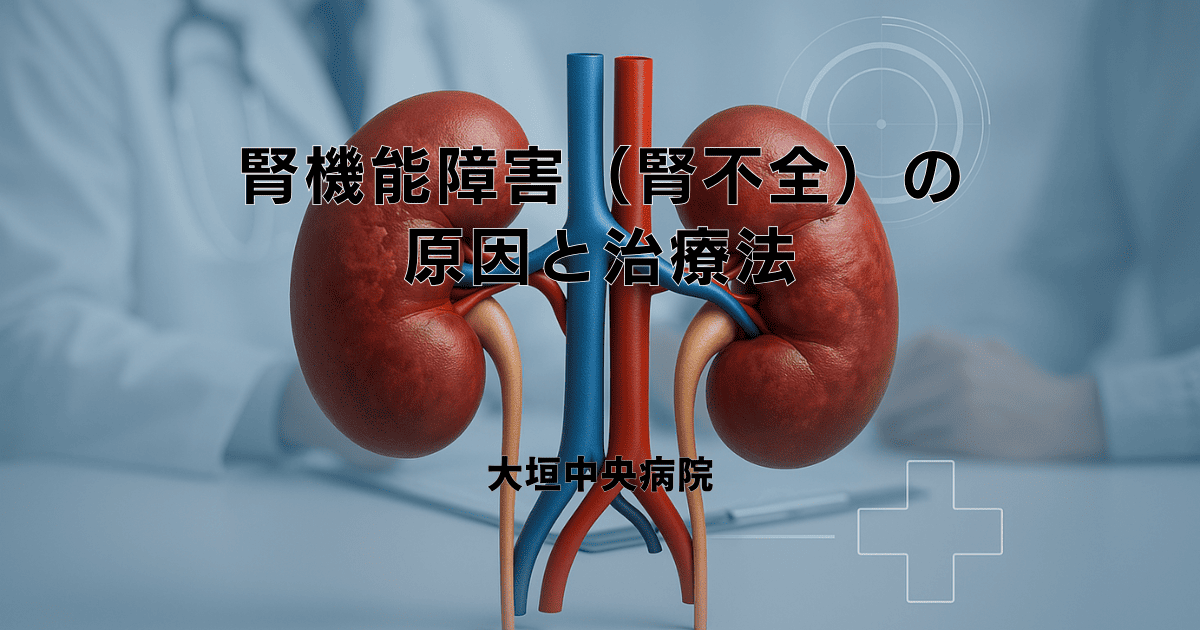腎臓は私たちの体を健康に保つために、休むことなく働き続ける重要な臓器です。しかし、様々な原因によってその機能が低下してしまうことがあります。これが腎機能障害(腎不全)です。
初期段階では自覚症状がほとんどなく、静かに進行するため「沈黙の臓器」とも呼ばれます。
この記事では、腎機能障害の原因や症状、進行度を示すステージごとの考え方、そして重要な治療法について、網羅的に解説します。
腎機能障害(腎不全)とは?知っておきたい腎臓の働き
腎機能障害について理解を深めるためには、まず健康な腎臓がどのような役割を担っているかを知ることが大切です。腎臓の働きは多岐にわたり、生命維持に重要な役割を果たしています。
腎臓の重要な役割
腎臓は、腰のあたりに左右一対ある、そら豆のような形をした臓器です。主な働きは、血液をろ過して老廃物や余分な水分を尿として体外に排出することです。
この働き以外にも、私たちの体が正常に機能するための多くの役割を担っています。
- 血液を浄化し尿を作る
- 体内の水分量と電解質のバランスを調整する
- 血圧をコントロールするホルモンを分泌する
- 血液を作るホルモン(エリスロポエチン)を分泌する
- 骨を丈夫にするビタミンDを活性化させる
腎機能障害(腎不全)が起こる状態
腎機能障害とは、何らかの原因でこれらの腎臓の働きが、健康な時の60%以下に低下した状態を指します。
腎機能障害は、急激に機能が低下する「急性腎障害」と、数か月から数年かけてゆっくりと機能が低下していく「慢性腎臓病(CKD)」の2つに大別できます。
特に慢性腎臓病は、初期には自覚症状がほとんど現れないため、健康診断などで異常を指摘されて初めて気づくケースが少なくありません。
なぜ腎機能の低下が問題になるのか
腎機能が低下すると、体にとって様々な不都合が生じます。老廃物が体内に蓄積して尿毒症を引き起こしたり、水分や塩分の排出がうまくいかず高血圧やむくみの原因になったりします。
また、ホルモンの分泌異常から貧血や骨がもろくなるなどの症状も現れます。さらに、腎機能障害は心筋梗塞や脳卒中といった、命に関わる心血管疾患の重大なリスク因子となることがわかっています。
腎機能障害の主な原因
腎機能障害を引き起こす原因は一つではありません。生活習慣病が大きく関わる場合や、腎臓そのものの病気が原因となる場合など様々です。ここでは、腎機能障害の主な原因を解説します。
生活習慣病との深い関わり
現代の日本では、生活習慣病が原因で慢性腎臓病を発症し、透析治療が必要になる患者さんが最も多くなっています。特に糖尿病と高血圧は、腎機能障害の二大原因です。
糖尿病性腎症
長期間にわたる高血糖の状態が続くと、腎臓のフィルター機能を担う非常に細い血管(糸球体)が傷つきます。その結果、本来は体内に留まるべきたんぱく質が尿に漏れ出し、次第に腎臓のろ過機能が低下していきます。
腎硬化症
高血圧が長く続くと、腎臓の血管に常に高い圧力がかかり、動脈硬化が進みます。血管が硬く、狭くなることで腎臓に流れる血液の量が減少し、腎臓全体が硬化して機能が低下します。これが腎硬化症です。
生活習慣病と腎機能の関係
| 生活習慣病 | 腎臓への影響 | 腎臓病名 |
|---|---|---|
| 糖尿病 | 高血糖により糸球体の血管が傷つく | 糖尿病性腎症 |
| 高血圧 | 高圧により腎臓の血管の動脈硬化が進む | 腎硬化症 |
| 脂質異常症 | 動脈硬化を促進し、腎機能低下を助長する | – |
腎臓自体の病気
生活習慣病以外にも、腎臓そのものに起こる病気が原因で腎機能障害に至ることもあります。
慢性糸球体腎炎
糸球体に炎症が起こる病気の総称です。免疫の異常が関与していると考えられており、IgA腎症などが代表的です。血尿やたんぱく尿がみられ、徐々に腎機能が低下していきます。
多発性のう胞腎
遺伝性の病気で、腎臓に「のう胞」と呼ばれる液体が溜まった袋が多数でき、それらが徐々に大きくなることで正常な腎臓の組織を圧迫し、腎機能が低下します。
その他の原因
上記のほかにも、鎮痛薬などの薬剤による腎障害、加齢に伴う自然な腎機能の低下、膠原病や痛風といった全身性の病気に伴う腎障害など、原因は多岐にわたります。
腎機能障害の進行とステージ分類
慢性腎臓病(CKD)は、その進行度によっていくつかのステージに分けられます。ステージを正しく把握することは、適切な治療方針を決定する上で非常に重要です。
eGFR(推算糸球体濾過量)とは
腎臓が1分間にどれくらいの血液をろ過して尿を作れるかを示す値が「GFR(糸球体濾過量)」です。
このGFRを、血液検査で測定する「血清クレアチニン値」と年齢、性別から計算式で推算したものが「eGFR(推算糸球体濾過量)」です。健康診断の結果などでも見ることができ、現在の腎臓の働きを知るための重要な指標となります。
CKD(慢性腎臓病)のステージ分類
慢性腎臓病は、eGFRの値に基づいてステージG1からG5までの5段階に分類します。ステージが進むほど、腎機能が低下していることを意味します。
CKDステージ分類の概要
| ステージ | eGFR (mL/min/1.73m²) | 腎機能の状態 |
|---|---|---|
| G1 | 90以上 | 正常または高値(ただし、たんぱく尿など腎障害を示す所見がある) |
| G2 | 60~89 | 正常または軽度低下 |
| G3a | 45~59 | 軽度~中等度低下 |
| G3b | 30~44 | 中等度~高度低下 |
| G4 | 15~29 | 高度低下 |
| G5 | 15未満 | 末期腎不全(透析や移植が必要な段階) |
ステージごとの主な症状
腎機能障害の症状は、ステージによって現れ方が異なります。初期段階では自覚症状はほとんどなく、進行するにつれて様々なサインが現れます。
初期(G1~G2)
この段階では、自覚症状を感じることはほとんどありません。健康診断でたんぱく尿や血尿を指摘されることが、発見のきっかけになることが多いです。
中期(G3)
腎機能の低下が中等度まで進むと、むくみ(特に足)、貧血による動悸や息切れ、体がだるいといった倦怠感などの症状が現れ始めます。夜間に何度もトイレに起きる(夜間頻尿)こともあります。
後期(G4~G5)
高度に機能が低下すると、体に老廃物が溜まることで尿毒症の症状(吐き気、食欲不振、皮膚のかゆみなど)が現れます。さらに進行すると、呼吸困難や意識障害など、生命に危険が及ぶ状態になることもあります。
進行度別の自覚症状の目安
| ステージ | 主な自覚症状 |
|---|---|
| G1~G2 | ほとんどない。夜間尿が増えることがある。 |
| G3 | むくみ、貧血、倦怠感、息切れ、食欲不振。 |
| G4~G5 | 吐き気、嘔吐、強いかゆみ、呼吸困難、けいれん。 |
腎機能障害の検査と診断
腎機能障害の診断は、主に尿検査と血液検査によって行います。これらの検査で腎臓の状態を評価し、必要に応じてさらに詳しい検査を追加します。
診断に用いられる主な検査
健康診断でも行われる尿検査と血液検査は、腎臓の異常を早期に発見するための基本の検査です。これらに加え、腎臓の形や大きさを調べる画像検査なども行います。
- 尿検査
- 血液検査
- 画像検査(腹部超音波検査、CT検査など)
尿検査でわかること
尿は腎臓の状態を反映する鏡のようなものです。尿中のたんぱく質や血液の有無を調べることで、腎臓のフィルター機能に異常がないかを確認します。
尿検査の主な項目と評価
| 検査項目 | 基準値の目安 | 異常時に考えられること |
|---|---|---|
| 尿たんぱく | (-)または(±) | 糸球体の障害、尿細管の障害 |
| 尿潜血 | (-) | 腎炎、尿路結石、膀胱炎、腫瘍など |
| 尿比重 | 1.010~1.030 | 腎機能低下(低値で固定する) |
血液検査でわかること
血液検査では、本来尿として排出されるべき老廃物が血液中にどのくらい残っているかを調べます。代表的な項目が血清クレアチニン(Cr)で、この値が高いほど腎機能が低下していることを示します。
この血清クレアチニン値などを用いてeGFRを算出し、腎機能のステージを判断します。
確定診断のための追加検査
尿検査や血液検査で異常が見つかり、さらに原因を詳しく調べる必要がある場合には、腎生検を行うことがあります。これは、背中から細い針を刺して腎臓の組織を直接採取し、顕微鏡で調べる検査です。
病気の活動性や進行度を正確に把握でき、治療方針の決定に非常に役立ちます。
腎機能障害の治療法|進行を遅らせるために
一度低下してしまった慢性腎臓病の腎機能を完全に元に戻すことは、現在の医療では困難です。そのため、治療の目標は、残っている腎機能をできるだけ長く維持し、病気の進行を遅らせることに置かれます。
治療の基本的な考え方
腎機能障害の治療は、原因となっている病気(糖尿病や高血圧など)の治療を基本としながら、「食事療法」「薬物療法」を両輪として進めていきます。
これらに加え、禁煙や適度な運動といった「生活習慣の改善」も、腎臓を守るためにはとても大切です。
食事療法
食事療法は、腎臓への負担を軽減し、病状の悪化を防ぐための重要な治療法です。ただし、内容は病気のステージや個人の状態によって異なるため、必ず医師や管理栄養士の指導のもとで行う必要があります。
食事療法の基本原則
| 栄養素 | 制限の主な目的 | 注意点 |
|---|---|---|
| 塩分 | 高血圧やむくみの改善、心臓への負担軽減 | 1日6g未満が目標。だしや香辛料をうまく使う。 |
| たんぱく質 | 老廃物の産生を抑え、腎臓への負担を軽くする | ステージに応じて制限量が決まる。良質なたんぱく質を適量摂る。 |
| カリウム | 高カリウム血症の予防(不整脈などのリスク回避) | 生野菜や果物、いも類に多い。茹でこぼしや水にさらす工夫をする。 |
これらの制限と同時に、必要なエネルギー(カロリー)をしっかり確保することも重要です。エネルギーが不足すると、体内のたんぱく質が分解されてしまい、かえって腎臓に負担をかけることになります。
薬物療法
食事療法と並行して、薬物による治療も行います。血圧をコントロールする薬や、腎機能障害に伴う合併症を改善する薬を使用します。
腎機能保護作用が期待できる主な降圧薬
| 薬剤の種類 | 主な作用 |
|---|---|
| ACE阻害薬・ARB | 腎臓の血圧を下げ、たんぱく尿を減らして腎臓を保護する |
| SGLT2阻害薬 | 尿中に糖を排出することで糸球体への負担を軽くする |
| ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬 | 炎症や線維化を抑え、腎機能低下を抑制する |
このほか、尿量を増やしてむくみを改善する「利尿薬」、貧血を改善する「エリスロポエチン製剤」、体内のリンやカリウムの濃度を調整する薬など、個々の症状に合わせて様々な薬を使い分けます。
生活習慣の改善
薬や食事だけでなく、日々の生活習慣を見直すことも腎臓を守る上で重要です。特に禁煙は、腎臓の動脈硬化を防ぐために強く推奨します。
また、肥満の解消や、無理のない範囲での有酸素運動は、血圧や血糖のコントロールに役立ちます。
ステージG4〜G5(末期腎不全)の治療法
腎機能の低下がさらに進行し、末期腎不全(eGFRが15未満)の状態になると、自身の腎臓だけでは生命を維持することが困難になります。この段階では、失われた腎臓の機能を代替する「腎代替療法」が必要となります。
腎代替療法とは
腎代替療法には、大きく分けて「血液透析」「腹膜透析」「腎移植」の3つの選択肢があります。
どの治療法を選択するかは、医学的な状態はもちろんのこと、ご自身のライフスタイルや価値観、家族の協力体制などを総合的に考慮して、医師や医療スタッフと十分に話し合って決定します。
血液透析(HD)
血液透析は、腕の血管に作った「シャント」から血液を体外に取り出し、「ダイアライザー」という人工のフィルターを通して老廃物や余分な水分を除去し、きれいになった血液を体内に戻す治療法です。
血液透析の概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 場所 | 病院やクリニックなどの医療機関 |
| 頻度・時間 | 通常、週に3回通院し、1回あたり4~5時間行う |
| 特徴 | 治療は医療スタッフが行う。厳格な食事・水分管理が必要。 |
腹膜透析(PD)
腹膜透析は、お腹の中にカテーテルという管を埋め込み、そこから透析液を注入します。
自分自身の「腹膜」をフィルターとして利用し、時間をかけて血液中の老廃物を透析液に移動させ、その透析液を交換することで血液を浄化します。
腹膜透析の概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 場所 | 自宅や職場など、清潔な環境があればどこでも可能 |
| 頻度・時間 | 日中に数回バッグ交換を行うか、夜間に機械を使って自動的に行う |
| 特徴 | 通院は月1~2回程度。時間的な制約が少なく、社会復帰しやすい。 |
腎移植
腎移植は、健康な腎臓を他者(ドナー)から提供してもらい、移植する外科手術です。腎臓の機能を根本的に取り戻すことができる唯一の治療法です。
親族などから提供を受ける「生体腎移植」と、亡くなった方から提供を受ける「献腎移植」があります。
日常生活で気をつけること
腎機能の低下を指摘されたら、病気と上手く付き合いながら生活の質を保つために、日々の自己管理が重要になります。
食生活の見直し
食事療法は治療の基本です。特に塩分は、加工食品やインスタント食品、外食に多く含まれているため注意が必要です。また、医師や管理栄養士から水分摂取量について指示がある場合は、それを守るようにしましょう。
体調管理のポイント
毎日の血圧測定と体重測定は、体調の変化を知るための重要なバロメーターです。記録をつけておくことで、診察時に医師が体の状態を正確に把握する助けになります。
また、腎機能が低下すると免疫力も落ちやすくなるため、手洗いやうがいを徹底し、感染症にかからないように注意しましょう。
市販の風邪薬や痛み止め、サプリメントの中には腎臓に負担をかけるものがあるため、服用する前には必ず主治医や薬剤師に相談してください。
腎臓リハビリテーション
腎臓病の患者さんが、病状に合わせて行う運動療法や食事療法、学習などを含めた活動を「腎臓リハビリテーション」と呼びます。
適度な運動は、筋力の維持や心血管疾患の予防につながり、生活の質の向上に役立つことがわかっています。ウォーキングなどの軽い運動から、無理のない範囲で継続することが大切です。
よくある質問(FAQ)
- 腎機能は一度悪くなると元に戻らないのですか?
-
急激に腎機能が悪化する急性腎障害の場合は、適切な治療によって機能が回復する可能性があります。
しかし、数か月以上かけてゆっくりと進行する慢性腎臓病(CKD)によって一度失われた腎機能は、残念ながら基本的には回復しません。
そのため、治療の目標は、残っている腎機能をできるだけ長く大切に維持し、病気の進行を緩やかにすることに置かれます。
- 食事制限はいつから始めるべきですか?
-
食事制限を開始する時期やその内容は、腎機能のステージ、原因となっている病気、年齢、合併症の有無など、患者さん一人ひとりの状態によって大きく異なります。
自己判断で極端な制限を始めてしまうと、必要な栄養が不足し、かえって体調を崩してしまう危険性があります。必ず主治医や管理栄養士といった専門家に相談し、個別の指導に基づいて正しく行ってください。
- 透析を始めると、もう旅行や仕事はできなくなりますか?
-
いいえ、そのようなことはありません。透析治療を受けながらでも、仕事や旅行を楽しむことは十分に可能です。血液透析の場合、旅行先の施設で「臨時透析」を受けることができます。
腹膜透析は、透析液などの物品を旅行先に配送することで、国内はもちろん海外旅行も可能です。仕事と治療を両立させている方も大勢いますので、ライフスタイルに合った治療法を選択することが大切です。
- 腎臓に良い食べ物や飲み物はありますか?
-
特定の食品を食べれば腎臓が良くなる、というような魔法の食べ物や飲み物は存在しません。
「腎臓に良い」と宣伝されている健康食品などの中には、カリウムやリンを多く含み、腎機能が低下している方にとってはかえって害になるものもあります。
大切なのは、特定の食品に頼るのではなく、ご自身の病状に合わせて減塩やたんぱく質制限などを守り、バランスの取れた食事を心がけることです。
以上
参考文献
ZHONG, Jianyong; YANG, Hai-Chun; FOGO, Agnes B. A perspective on chronic kidney disease progression. American Journal of Physiology-Renal Physiology, 2017, 312.3: F375-F384.
INKER, Lesley A.; LEVEY, Andrew S. Staging and management of chronic kidney disease. In: National Kidney Foundation’s Primer on Kidney Diseases. Elsevier, 2018. p. 476-483. e1.
ROSANSKY, Steven J. Renal function trajectory is more important than chronic kidney disease stage for managing patients with chronic kidney disease. American journal of nephrology, 2012, 36.1: 1-10.
CARAVACA-FONTÁN, Fernando, et al. Patterns of progression of chronic kidney disease at later stages. Clinical kidney journal, 2018, 11.2: 246-253.
LEVEY, Andrew S.; CORESH, Josef. Chronic kidney disease. The lancet, 2012, 379.9811: 165-180.
AGARWAL, Anil K.; HADDAD, Nabil; HEBERT, Lee A. Progression of kidney disease: diagnosis and management. Evidence‐based nephrology, 2008, 309-322.
CHEN, Teresa K.; KNICELY, Daphne H.; GRAMS, Morgan E. Chronic kidney disease diagnosis and management: a review. Jama, 2019, 322.13: 1294-1304.
KALANTAR-ZADEH, Kamyar, et al. Chronic kidney disease. The lancet, 2021, 398.10302: 786-802.
TANGRI, Navdeep, et al. A predictive model for progression of chronic kidney disease to kidney failure. Jama, 2011, 305.15: 1553-1559.
ROMAGNANI, Paola, et al. Chronic kidney disease. Nature reviews Disease primers, 2017, 3.1: 1-24.