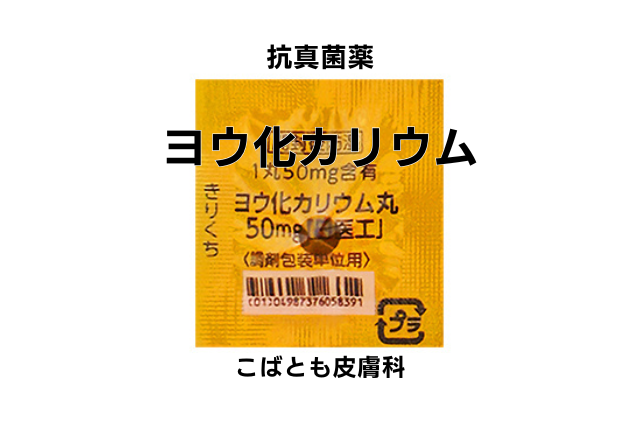ヨウ化カリウムとは、カリウムイオンとヨウ化物イオンから成る化合物で、皮膚科領域でも特定の症状に対して処方されることがある医薬品です。
一般的な抗菌薬や抗真菌薬で十分な効果が得られない症例に対して追加の選択肢となることがあり、皮膚の深部まで及ぶ真菌感染症をはじめとした難治性の病変に対して注目されています。
服用による甲状腺機能への影響や、投与中の体調管理など気をつける点もありますが、正しい用法と注意点を守れば有用な治療手段となる可能性があります。
この記事の執筆者

小林 智子(こばやし ともこ)
日本皮膚科学会認定皮膚科専門医・医学博士
こばとも皮膚科院長
2010年に日本医科大学卒業後、名古屋大学医学部皮膚科入局。同大学大学院博士課程修了後、アメリカノースウェスタン大学にて、ポストマスターフェローとして臨床研究に従事。帰国後、同志社大学生命医科学部アンチエイジングリサーチセンターにて、糖化と肌について研究を行う。専門は一般皮膚科、アレルギー、抗加齢、美容皮膚科。雑誌を中心にメディアにも多数出演。著書に『皮膚科医が実践している 極上肌のつくり方』(彩図社)など。
こばとも皮膚科関連医療機関
ヨウ化カリウムの有効成分と効果、作用機序
皮膚科でヨウ化カリウムを用いる理由には、真菌や一部の菌による感染症を抑制する作用を期待する面が挙げられます。
ヨウ化カリウムの基本的な成分
ヨウ化カリウムはカリウム(K⁺)とヨウ化物(I⁻)によって構成され、両イオンは体内で次のような特徴を持ちます。
- ヨウ化物イオン(I⁻)は甲状腺ホルモンの原料となるヨウ素の形態の1つで、甲状腺機能に関与する
- カリウムイオン(K⁺)は体液バランスや筋肉の興奮伝導などに関わる重要な電解質
成分の組み合わせによって、単なるミネラル補給とは異なる生理作用を生み出します。
ヨウ化カリウムの成分概要
| 成分名 | 概要 | 特徴 |
|---|---|---|
| カリウムイオン | 体の電解質バランスや神経伝達をサポート | 欠乏すると筋力低下や心拍リズム異常を起こしやすい |
| ヨウ化物イオン | 甲状腺ホルモン生成や抗真菌効果を助ける可能性 | 過剰摂取や長期摂取で甲状腺機能への影響に注意 |
ヨウ化カリウムはこれら2つのイオンが組み合わさった形で体内へ吸収され、特定の病原菌や真菌の増殖を抑制する効果を持つと考えられています。
真菌感染症に対する作用のポイント
ヨウ化カリウムは主に深在性の真菌感染症に対する治療で知られていて、とくにスポロトリコーシスと呼ばれる深部真菌症で古くから使われています。
真菌は皮膚の深い層やリンパ管にまで及ぶと、通常の外用薬では対応が難しくなることがあり、ヨウ化カリウムの内服によって体全体に有効成分が行き渡るため、深部の真菌にも作用が及ぶびます。
また、ヨウ化物が線維芽細胞やマクロファージなどに何らかの影響を与え、炎症反応や真菌の定着を抑える効果があるともいわれます。ただし、はっきりとした詳細な作用機序については解明が進行中の段階です。
免疫機能への関与
ヨウ化カリウムは免疫系に対する刺激作用を持つ可能性があり、体が本来備えている免疫機能を活性化することで、異物や病原菌への応答を強めます。
さらに抗真菌作用だけでなく、傷の治りを促すような二次的効果にも期待が寄せられています。
- ヨウ化物の免疫刺激作用
- 体内の酸化還元バランスへの影響
- 局所の炎症の鎮静化
ただし、免疫反応の活性化は場合によっては自己免疫的な反応を高めるリスクも伴うため、十分な観察が必要です。
甲状腺ホルモンとの関連
ヨウ化カリウムに含まれるヨウ化物は、甲状腺ホルモン合成の材料となり、甲状腺機能に異常のある人や、甲状腺疾患の家族歴がある人は注意深く使用することが大切です。
医師が甲状腺機能検査を行うことも多いため、投与前後の血液検査を行い、甲状腺ホルモン値などを確認してから治療を継続するケースもあります。
甲状腺機能に配慮したい人
- 既にバセドウ病や橋本病などの甲状腺疾患を抱えている
- 一度でも甲状腺ホルモンの値が不安定だったことがある
- 甲状腺機能異常の家族歴がある
- 甲状腺治療薬を服用している
ヨウ化カリウムの使用方法と注意点
ヨウ化カリウムの服用は、医師が病状や患者さんの年齢、体調に応じて判断し、皮膚科領域で真菌感染症に対して使用する場合は、外用薬や他の抗真菌薬で効果が不十分なときに選択することが多いです。
服用量と服用回数
ヨウ化カリウムの一般的な用量は、病状や体重などによって変動し、大人の場合、1日あたり500〜1500mg程度を数回に分けて服用しますが、より軽症な場合や小児の場合は、さらに減量して処方します。
服用のタイミングとしては、食後が推奨される傾向があり、これは胃腸への刺激を緩和し、吸収も安定させるためです。
ヨウ化カリウムの服用目安
| 患者区分 | 1日あたりの目安量(mg) | 服用回数の例 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 成人(標準体型) | 500〜1500 | 2〜3回 | 症状により調整 |
| 成人(体重が軽い) | 300〜800 | 2〜3回 | 消化器症状が出やすい場合は注意 |
| 小児 | 体重1kgあたり10〜15mg | 2〜3回 | 医師の指示で慎重に用量を決定 |
| 高齢者 | 300〜600 | 2〜3回 | 甲状腺や腎機能の状態を考慮する |
胃腸への刺激を抑えるコツ
ヨウ化カリウムは胃を刺激しやすい性質があるため、胃もたれや吐き気を訴える患者さんが少なくありません。水またはぬるま湯と一緒に十分量を飲むと、消化器への刺激をある程度抑えられます。
また、食後に服用と胃酸分泌が食物によって緩和され、薬の吸収がマイルドです。
- 服用時はコップ1杯以上の水分を一緒に摂る
- 空腹時の服用は避ける
- 胃腸障害が強いときは主治医に相談する
甲状腺機能への注意
ヨウ化カリウムの長期使用で甲状腺機能が影響を受けることがあり、甲状腺が過剰に刺激されてしまうと、甲状腺ホルモンが増加し、動悸や発汗過多、体重減少などが生じることがあります。
逆に機能低下を引き起こすと、疲労感や体重増加、むくみなどが目立つ場合があり、投与中は定期的に血液検査を行い、甲状腺機能を評価することが大切です。
甲状腺機能異常のサイン
| 機能亢進のサイン | 機能低下のサイン |
|---|---|
| 動悸が続く | 強い倦怠感や疲労感 |
| 発汗やほてり感が増す | 体重増加やむくみ |
| 頻脈や心拍数の上昇 | 心拍数が遅くなる |
| 落ち着きがなくイライラ | 皮膚の乾燥や抜け毛が増える |
妊娠・授乳中の注意点
妊娠・授乳中のヨウ化カリウム使用は、胎児や乳児の甲状腺機能に影響を及ぼすリスクがあるため慎重に検討する必要があり、必ず産科主治医や皮膚科医と相談し、必要性やメリット・デメリットを十分に考慮したうえで服用を決定してください。
妊娠初期や授乳期間であっても、治療上重要な場合は厳重な管理のもとで処方されることがあります。
妊娠・授乳期に考慮されること
- 胎児・乳児の甲状腺機能への影響
- 投与量を最低限に抑えるかどうか
- 他の治療方法や外用薬との併用
適応対象となる患者さん
ヨウ化カリウムはあらゆる真菌感染や皮膚疾患に対して使われるわけではなく、特定の病態に対して効果が期待される治療薬です。
深在性真菌感染症
深在性真菌感染症とは、皮膚の奥深くやリンパ管、あるいは全身臓器に及ぶタイプの真菌感染です。
スポロトリコーシス、クロモブラストミコーシスなど、外用薬だけでは十分に対応しきれない感染症に対して、ヨウ化カリウムを内服薬として追加することがあります。
とくにスポロトリコーシスの場合、昔からヨウ化カリウムが一つの標準的な治療法として使われてきた経緯があります。
深在性真菌感染症
| 感染症名 | 特徴 |
|---|---|
| スポロトリコーシス | バラ病とも呼ばれる。園芸作業で刺傷が原因になることが多い。皮膚やリンパ管に病変が及ぶ |
| クロモブラストミコーシス | 皮膚が暗色の結節や斑点を形成する。足や下腿に発症が多い |
| ストロングイロイデス症 | 回虫の一種が引き起こす寄生虫感染であるが、真菌感染との複合も注意が必要 |
深部まで到達した真菌を制御するには内服薬で全身的にアプローチする必要があるため、ヨウ化カリウムの処方を検討することがあります。
通常の抗真菌薬で効果不十分な患者
イミダゾール系やトリアゾール系の抗真菌薬による治療で十分な効果が得られない場合、追加としてヨウ化カリウムを組み合わせることも選択肢です。
真菌の種類によっては既存薬に耐性を示すケースもあり、そのような場合にヨウ化カリウムが有効に働く可能性があります。
- 多剤耐性を疑う真菌株
- 長期治療が必要にもかかわらず改善が乏しい症例
- 外科的治療を回避したい状況
体力や免疫力に課題のある患者
長期にわたるステロイド治療や免疫抑制剤使用などで、感染に対する抵抗力が低下している患者さんでも、ヨウ化カリウムを検討する場合があります。
一般的な抗真菌薬の使用が難しいケースでも、ヨウ化カリウムが一部の真菌に対して有用になる可能性がありますが、甲状腺機能や副作用のリスクも総合的に考慮することが必要です。
特異的な炎症反応を示す患者
ヨウ化カリウムは、少し特殊な炎症性疾患に対しても応用される場合があり、膿疱が繰り返し出現するような症状を抑えるために投与した症例報告があります。
ただし、深在性真菌感染の治療目的が主であるため、基本的には感染症治療が主軸になり、特殊な病態でヨウ化カリウムを使う場合は、専門の皮膚科医とよく相談することが大切です。
医師と相談したいケース
- ステロイドを長期使用している
- 免疫抑制剤を服用している
- 皮膚に原因不明の膿疱や結節が反復している
- 外用薬を長期使用しても改善がみられない
ヨウ化カリウムの治療期間
ヨウ化カリウムを服用する場合、どのくらいの期間飲み続ければいいのかが気になる方も多いでしょう。症状が軽快しても、短期間で服用を中止すると再発が起こる可能性もあります。ここでは一般的な治療期間の考え方を解説します。
短期〜中期(数週間〜数か月)の服用
真菌感染症の治療では、最低でも数週間から数か月単位の服用が必要になることがあります。深在性真菌感染症は、一見症状が軽快してきてもまだ菌が体内に残っていることがあるため、ある程度の期間は継続することが必要です。
治療期間の目安
| 感染症タイプ | 目安の治療期間 | 備考 |
|---|---|---|
| 表在性の真菌感染症 | 2〜4週間程度 | 軽症の場合はさらに短縮する場合もある |
| 深在性の真菌感染症 | 4〜12週間以上 | スポロトリコーシスは3〜6か月以上のこともある |
| 多剤耐性が疑われる場合 | 6か月以上 | 定期検査を行いながら判断 |
実際の期間は病状や効果の出方によって大きく異なり、医師の判断に左右されます。
定期検査を実施する意義
ヨウ化カリウムの長期服用に対しては甲状腺機能検査や肝機能、腎機能などのチェックが欠かせません。
特にスポロトリコーシスのように長期にわたる服用が想定される疾患では、定期的に血液検査や体調の聞き取りを行って投与量や期間の調整を行います。
- 血液検査(甲状腺ホルモン、肝機能、腎機能など)
- 自覚症状の変化(吐き気、むくみ、だるさなど)
- 皮膚病変の状態観察(大きさ、炎症具合、痛み)
症状の消失後も継続する意味
真菌感染症の場合、症状がほとんど消えていても、完全に真菌が排除できていない可能性があり、症状の再発や奥深く潜んでいる真菌の再増殖を防ぐため、症状消失後も数週間から数か月間、ヨウ化カリウムの服用を継続することが多いです。
ここで早期に中断すると、再発リスクが高まるケースがあるので注意してください。
中止時期の見極め
症状が改善したタイミングで、医師が検査結果や視診によって安全に中止できると判断した場合、徐々に投与量を減らしていきます。
一気に中断するとリバウンドのような形で感染が再燃する恐れがあるため、医師の指示に従い、少しずつ薬の量を調整するのが理想です。自己判断で服用を中止すると副作用以前に再発リスクが上がるため、必ず医師と相談しましょう。
治療終了時のポイント
- 症状の完全消失後でも一定期間の服用継続を考える
- 医師の指示のもと、減薬のタイミングを決める
- 再発防止のため、終了後もしばらく皮膚の状態に注意を払う
ヨウ化カリウムの副作用やデメリット
ヨウ化カリウムは深在性真菌感染症などに対して有用な一方で、さまざまな副作用やデメリットがあります。
甲状腺機能異常
前述のとおり、ヨウ化カリウムによって甲状腺ホルモンが過剰または不足するリスクがあり、甲状腺機能異常は放置すると全身状態に影響を及ぼすため、以下のような症状には注意が必要です。
- 甲状腺機能亢進症:動悸、発汗、体重減少、イライラ感
- 甲状腺機能低下症:倦怠感、むくみ、体重増加、寒がり
長期服用中にこれらの症状が現れた場合、医師に早めに相談し、血液検査などで状態を確認することが大切になります。
甲状腺機能異常発生時の対処
| 症状 | 対処法 |
|---|---|
| 動悸や発汗過多が強い | 甲状腺機能亢進を疑い、専門医受診 |
| 疲労感や体重増加が顕著 | 甲状腺機能低下を疑い、薬の量を調整 |
| 急激な心拍数変動 | 速やかに内科か皮膚科で相談 |
| その他、検査値の急変 | 服用を一時停止し、医師に報告 |
胃腸障害
ヨウ化カリウムは胃腸への刺激が強めで、吐き気や食欲不振、腹痛が起こるケースがあり、食事のタイミングや食物の種類によって症状の出方が変わるため、服用時は以下のような対策をとりましょう。
- 食後に服用する
- 多めの水分とともに飲む
- 刺激の少ない食事を心がける
胃腸障害があまりにも強い場合は、医師に相談して服用方法の変更や胃腸薬の併用を検討します。
金属アレルギーや発疹
ヨウ化カリウムに限ったことではありませんが、体質によってはアレルギー反応が出る可能性があり、皮膚発疹やかゆみ、唇やまぶたのむくみなどが見られた場合は、薬の影響を疑うべきかもしれません。
特にヨウ素アレルギーの既往がある方は気を付けてください。
アレルギー症状チェックリスト
- 皮膚のかゆみやじんましん
- 唇やまぶたの腫れ
- 呼吸困難や喉の違和感
- 目の充血や涙目
症状が急激に強まった場合はアナフィラキシーのリスクを考慮し、すぐに医療機関を受診することが必要です。
長期服用による蓄積リスク
ヨウ化カリウムは体内に蓄積しやすいわけではありませんが、長期にわたり大量に摂取すると特定の臓器に負担がかかる可能性があります。
とくに甲状腺や腎臓、肝臓に持病を抱えている患者さんは、定期検査で状態を観察しながら投与量を調整することが重要です。
長期服用で注意したい臓器
| 臓器 | 具体的リスク |
|---|---|
| 甲状腺 | 過剰刺激または機能低下 |
| 腎臓 | 代謝物の排泄障害 |
| 肝臓 | 薬物代謝過程への負担 |
ヨウ化カリウムで効果がなかった場合
ヨウ化カリウムを使用しても期待した効果が得られない、または改善が見られないケースがあり、そのような場合は、真菌の種類や体質、投与方法など複数の要因を再評価します。
真菌の種類の再評価
真菌感染症と一口にいっても、さまざまな種類があり、ヨウ化カリウムはスポロトリコーシスなど特定の真菌に対して用いる機会が多いものの、他の真菌種には効果が弱いこともあります。
培養検査や迅速診断テストで原因となる真菌を特定し、ヨウ化カリウムが適切な選択かどうかを見直すことが大切です。
再評価すべき項目
- 真菌の種類(培養検査結果)
- 薬剤感受性(耐性の有無)
- 他の病原微生物の同時感染
もし対象外の真菌感染症だった場合は、別の抗真菌薬に切り替えることが考えられます。
他の内服薬との併用状況
ヨウ化カリウムの効果が思ったほど得られない場合、併用している別の薬剤が影響している可能性も考慮し、一部の薬剤は甲状腺機能や免疫応答に影響を与えるため、併用により効果が減弱することもあります。
服用中の薬をすべて医師に伝え、相互作用の有無を確認すると対処の糸口が見えてきます。
服用期間や用量の不十分
真菌感染症は時間をかけて治療を進めるので、途中で用量が不十分になったり、服用期間を短縮してしまうと再発や不十分な効果に終わることがあります。体調が良くなったと感じても、医師の指示した期間はきちんと服用を続けることが大切です。
効果不十分の原因例と対策
| 原因 | 対策 |
|---|---|
| 真菌の種類がヨウ化カリウムと合わない | 別の抗真菌薬へ切り替え |
| 用量・期間が短すぎる | 医師の指示に従い十分な期間服用する |
| 併用薬による相互作用 | 他の薬剤の見直しや投与タイミング調整 |
| 耐性や複合感染 | 培養検査や追加検査を実施し、方針再検討 |
他の治療法への切り替え
ヨウ化カリウムで効果が得られない場合、他の経口抗真菌薬に切り替える、あるいは外科的なデブリードマン(感染部位の外科的処置)を行うなど、より直接的な対処を検討することがあります。
深在性真菌感染症の中には外科的処置と併用して初めて改善が見込めるケースもあるため、医師と相談しながら別のアプローチを検討することが大事です。
他の治療薬との併用禁忌
ヨウ化カリウムは複数の薬剤と併用しても問題ない場合が多いですが、一部には注意が必要な組み合わせがあります。ここでは特に気をつけるべき薬剤や相互作用について取り上げます。
甲状腺ホルモン製剤
甲状腺機能の低下を補うためのレボチロキシンなどの甲状腺ホルモン製剤を服用している場合、ヨウ化カリウムの併用で甲状腺機能が過度に変動する恐れがあります。
高齢者や心疾患を抱える患者さんでは注意深くモニタリングを行い、投与量を調整しなければならないことがあります。
相互作用が懸念される薬剤例
| 薬剤名(分類) | 相互作用のリスク |
|---|---|
| 甲状腺ホルモン製剤 | 甲状腺ホルモン値が変動して過不足が出る |
| 抗不整脈薬(アミオダロンなど) | ヨウ素含有成分が含まれる場合、甲状腺機能に影響 |
| 利尿剤(ループ利尿薬など) | カリウムバランスが乱れ、高カリウム血症を誘発 |
抗不整脈薬
アミオダロンなどの抗不整脈薬にはヨウ素が含まれているケースがあり、これとヨウ化カリウムを同時に使用すると甲状腺機能が不安定になりやすいとされます。
また、カリウムのバランスが崩れると不整脈自体を悪化させるリスクもあるため、併用の際は定期的な心電図検査や血液検査を実施しながら慎重に治療を進めることが必要です。
利尿剤との併用
カリウムの排泄を促すタイプの利尿剤(ループ利尿薬やサイアザイド系利尿薬)を使っている場合は、ヨウ化カリウムの服用でカリウムバランスが変動し、高カリウム血症や低カリウム血症を引き起こす危険があります。
カリウム濃度の変化によって、心臓や筋肉の機能に影響が及ぶため、併用中は血中電解質の測定を受けながら管理することが望ましいです。
併用時の対策
- 血液検査で電解質バランスを定期チェック
- 心電図などで心臓機能をモニタリング
- 甲状腺機能も定期的に評価
ヨウ化カリウムの保険適用と薬価について
以下に記載している治療費(医療費)は目安であり、実際の費用は症状や治療内容、保険適用否により大幅に上回ることがございます。当院では料金に関する以下説明の不備や相違について、一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。
保険適用の範囲
ヨウ化カリウムは、皮膚真菌症など特定の病名で処方される場合、健康保険の適用対象に含まれることが一般的です。
| 病名・症状 | 保険適用の可否 |
|---|---|
| スポロトリコーシス | 保険適用になることが多い |
| クロモブラストミコーシス | 症例に応じて保険適用が認められる |
| 根拠が乏しい美容目的 | 保険適用外 |
薬価の目安
| 製品名 | 規格 | 1錠・1gあたりの薬価(円) |
|---|---|---|
| ヨウ化カリウム丸50mg | 50mg/1錠 | 4.00 |
| ヨウ化カリウム丸100mg | 100mg/1錠 | 4.80 |
実際に処方される製品によって薬価が若干異なる場合があるため、詳細は医師・薬剤師にお問い合わせください。
以上
参考文献
Costa RO, Macedo PM, Carvalhal A, Bernardes-Engemann AR. Use of potassium iodide in dermatology: updates on an old drug. Anais brasileiros de dermatologia. 2013 Jun;88(3):396-402.
Sterling JB, Heymann WR. Potassium iodide in dermatology: a 19th century drug for the 21st century—uses, pharmacology, adverse effects, and contraindications. Journal of the American Academy of Dermatology. 2000 Oct 1;43(4):691-7.
Hassan I, Keen A. Potassium iodide in dermatology. Indian Journal of Dermatology, Venereology and Leprology. 2012 May 1;78:390.
Anzengruber F, Mergenthaler C, Murer C, Dummer R. Potassium iodide for cutaneous inflammatory disorders: a monocentric, retrospective study. Dermatology. 2019 Feb 21;235(2):137-43.
Goel N, Doshi BR. Potassium Iodide in Dermatology-Recent Advances in Mechanism of Action, Preparation, Uses and Adverse Effects. Indian Journal of Dermatology. 2025 May 1;70(3):169.
Heymann WR. Potassium iodide and the Wolff-Chaikoff effect: Relevance for the dermatologist. Journal of the American Academy of Dermatology. 2000 Mar 1;42(3):490-2.
Hayashi S, Ishikawa S, Ishii E, Koike M, Kaminaga T, Hamasaki Y, Sairenchi T, Kobashi G, Igawa K. Anti-inflammatory effects of potassium iodide on SDS-induced murine skin inflammation. Journal of Investigative Dermatology. 2020 Oct 1;140(10):2001-8.
Macedo PM, Lopes‐Bezerra LM, Bernardes‐Engemann AR, Orofino‐Costa R. New posology of potassium iodide for the treatment of cutaneous sporotrichosis: study of efficacy and safety in 102 patients. Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology. 2015 Apr;29(4):719-24.
Zone JJ. Potassium iodide and vasculitis. Archives of Dermatology. 1981 Dec 1;117(12):758-.
Nalini P, Vellaisamy SG, Manickam N, Gopalan K. Potassium iodide: A prodigy in the treatment of subcutaneous zygomycosis. Indian Journal of Drugs in Dermatology. 2019 Jan 1;5(1):59-62.