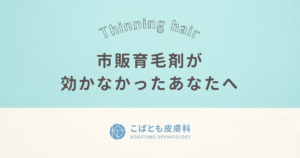禿髪性毛包炎は、頭皮の毛包に炎症が起こり、進行すると抜け毛や瘢痕につながるつらい疾患です。特に女性にとっては、薄毛の悩みは深刻です。
 Dr.小林智子
Dr.小林智子この記事では、皮膚科クリニックで行う禿髪性毛包炎の治療法と、再発を防ぐための予防策について詳しく解説します。
諦めないで!禿髪性毛包炎 治療への確かなステップ
禿髪性毛包炎は、時に治らないと感じるほど長引くことがありますが、適切な治療を根気強く続けることで改善を目指せます。初期の段階で治療を開始することが、悪化を防ぎ、瘢痕の形成を最小限に抑える鍵となります。
医師と二人三脚で、治療計画に沿って一歩ずつ進んでいきましょう。

早期発見と診断の重要性
頭皮に赤み、かゆみ、膿疱(膿のたまった水ぶくれ)、または小さな硬いしこりを見つけたら、自己判断せずに速やかに皮膚科専門医の診察を受けてください。これらの症状は、禿髪性毛包炎のサインかもしれません。
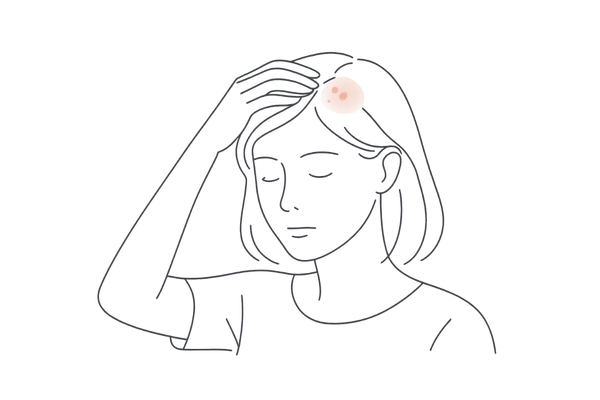
放置すると症状が悪化し、抜け毛が広範囲に及んだり、治療が困難な瘢痕性脱毛に至る可能性があります。早期診断は、より効果的な治療への第一歩です。
頭皮の初期サインを見逃さない
初期には軽いかゆみや、ニキビのような小さな赤みとして現れることがあります。これらが繰り返す場合や、徐々に数が増える場合は注意が必要です。特に、抜け毛を伴う場合は、単なる頭皮トラブルではない可能性を考えましょう。
専門医による治療計画の策定
皮膚科専門医は、症状の程度、範囲、患者さんの体質や生活習慣などを総合的に評価し、個別の治療計画を立てます。治療法には内服薬、外用薬、そして生活習慣の改善などが含まれます。
長引く炎症や繰り返す症状に対して、医師は根気強く治療法を調整していきます。
治療目標の共有
治療を始めるにあたり、医師と患者さんが治療の目標を共有することが大切です。炎症を抑えること、抜け毛を減らすこと、そして最終的には瘢痕の形成を防ぎ、可能な限り毛髪の再生を促すことなど、具体的な目標を設定します。
主な治療法の選択肢
| 治療法 | 主な目的 | 期待される効果 |
|---|---|---|
| 内服薬 | 全身的な炎症抑制、細菌感染の制御 | 広範囲の炎症、膿の軽減 |
| 外用薬 | 局所的な炎症抑制、殺菌 | 赤み、かゆみ、小さな膿疱の改善 |
| 生活習慣指導 | 頭皮環境の改善、再発予防 | 全体的な症状の安定化 |
身体の内側からアプローチ 内服薬による治療の考え方

禿髪性毛包炎(とくはつせいもうほうえん)の治療において、内服薬は炎症を内側から抑え、感染をコントロールするために重要な役割を果たします。特に症状が広範囲に及ぶ場合や、外用薬だけでは改善が見られない場合に検討します。
医師の指示に従い、正しく服用することが完治への道筋となります。
抗生物質による細菌コントロール
禿髪性毛包炎の原因の一つとして細菌感染が関与していると考えられています。そのため、テトラサイクリン系やマクロライド系などの抗生物質を内服し、細菌の増殖を抑え、炎症を鎮めます。
長期間の服用が必要になることもありますが、自己判断で中断すると症状が再発、悪化する可能性があるため、必ず医師の指示に従ってください。
抗生物質の種類と服用期間
使用する抗生物質の種類や服用期間は、症状の重症度や細菌検査の結果に基づいて医師が判断します。漫然と長期間使用するのではなく、効果を見ながら調整を行います。
副作用として、胃腸症状や光線過敏症などが現れることがあるため、気になる症状があればすぐに医師に相談しましょう。
薬剤耐性菌への配慮
抗生物質を長期間使用する場合、薬剤耐性菌の出現に注意が必要です。医師は、適切な薬剤選択と使用期間の設定により、耐性菌のリスクを最小限に抑えるよう努めます。
そのためにも、処方された量を守り、途中で服用をやめないことが重要です。
炎症を抑えるための内服薬
強い炎症や痛みを伴う場合には、非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)や、場合によっては短期間のステロイド内服を検討することもあります。
ステロイド内服は効果が高い反面、副作用のリスクもあるため、医師が慎重に判断し、必要最小限の期間と量で使用します。
ステロイド内服の考え方
ステロイド内服は、急速に進行する炎症や、他の治療法で効果が見られない重症例に限定して用いられることが多いです。症状の改善が見られたら、徐々に減量し中止します。
自己判断での急な中止は、症状の再燃(リバウンド)を引き起こす可能性があるため危険です。
その他の内服薬の可能性
上記以外にも、症状や体質に応じて、ビタミン剤や漢方薬などが補助的に用いられることがあります。これらは直接的な治療効果というよりは、体質改善や免疫力のサポートを目的とします。
内服薬治療の注意点
| 注意点 | 具体的な内容 | 対応 |
|---|---|---|
| 副作用 | 胃腸障害、アレルギー反応など | 異常を感じたら医師に相談 |
| 飲み合わせ | 他の常用薬との相互作用 | 必ず医師や薬剤師に申告 |
| 服用期間 | 自己判断での中断・増減は避ける | 医師の指示を厳守 |
気になる部分へダイレクトに 外用薬を用いた治療法と注意点
外用薬は、禿髪性毛包炎の患部に直接作用し、炎症や細菌感染を抑える治療法です。赤み、かゆみ、小さな膿疱といった局所的な症状の改善に効果を発揮します。
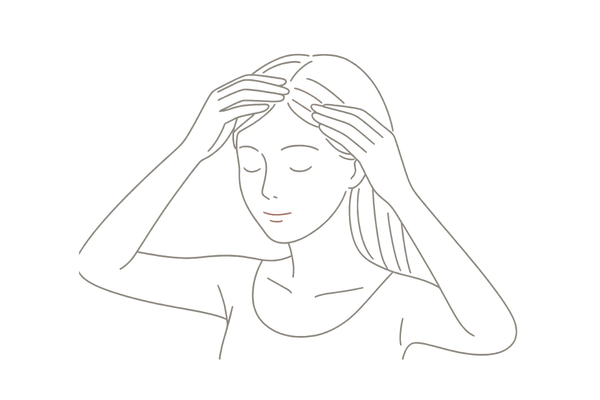
内服薬と併用することで、より効果的な治療が期待できますが、正しい使い方を守ることが大切です。
ステロイド外用薬による炎症抑制
炎症を強力に抑えるために、ステロイド外用薬を使用します。症状の強さや部位に応じて、適切な強さのステロイドを選択します。
長期間の使用や誤った使い方は副作用のリスクを高めるため、医師の指示通りに使用量を守り、塗布範囲や期間を遵守することが重要です。特に顔に近い頭皮など、皮膚の薄い部分への使用は慎重に行います。
ステロイド外用薬のランクと使い方
ステロイド外用薬には強さのランクがあり、症状に応じて使い分けます。強いランクのものを漫然と使い続けると、皮膚が薄くなる、血管が浮き出るなどの副作用が出ることがあります。
医師は症状の改善とともに、徐々に弱いランクの薬剤に変更したり、使用回数を減らしたりします。
- ベリーストロング
- ストロング
- ミディアム
- ウィーク
抗菌外用薬による感染対策
細菌感染が疑われる場合や、膿疱が目立つ場合には、抗菌成分を含む外用薬を使用します。これにより、毛包内の細菌を減らし、炎症の悪化を防ぎます。ステロイド外用薬と混合された配合剤が用いられることもあります。
抗菌外用薬の種類
ナジフロキサシンクリーム・ローションや、ゲンタマイシン硫酸塩軟膏などが代表的です。これらの薬剤も、耐性菌の問題を避けるため、医師の指示した期間を守って使用します。
外用薬の正しい塗布方法
| ポイント | 説明 | 理由 |
|---|---|---|
| 清潔な手で | 塗布前に手を洗い、患部も清潔にする | 二次感染の予防 |
| 適量を守る | 医師の指示通りの量を薄く延ばす | 副作用リスクの低減、効果の最大化 |
| 擦り込まない | 優しく乗せるように塗布する | 患部への刺激を避けるため |
お薬だけではない選択肢 頭皮環境を整えるための補助的アプローチ
禿髪性毛包炎の治療は、薬物療法が中心となりますが、頭皮環境を整えるための補助的なアプローチも、症状の改善や再発予防に役立ちます。
これらは医師の治療を補完するものであり、自己判断で行わず、専門家のアドバイスを受けながら取り入れることが大切です。
薬用シャンプーや低刺激性シャンプーの活用
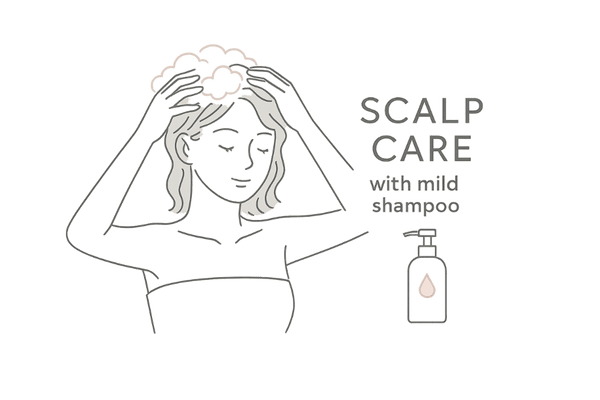
頭皮の清潔を保つことは基本ですが、洗浄力の強すぎるシャンプーはかえって頭皮を乾燥させ、バリア機能を低下させる可能性があります。
抗菌成分配合の薬用シャンプーや、アミノ酸系などの低刺激性シャンプーを選び、優しく洗髪することを心がけましょう。かゆみや赤みが強い場合は、シャンプーが刺激になることもあるため、医師に相談してください。
シャンプー選びのポイント
| 成分 | 期待される効果 | 注意点 |
|---|---|---|
| 抗真菌成分(ミコナゾールなど) | マラセチア菌の増殖抑制 | 医師の指示がある場合に使用 |
| 抗炎症成分(グリチルリチン酸など) | 炎症を和らげる | 効果は穏やか |
| 保湿成分(セラミド、ヒアルロン酸など) | 頭皮の乾燥を防ぐ | 油分が多すぎないものを選ぶ |
光線療法(ナローバンドUVBなど)の可能性
一部の難治性の炎症性皮膚疾患に対して、ナローバンドUVBなどの光線療法が有効な場合があります。
禿髪性毛包炎に対する効果はまだ確立されていませんが、他の治療法で効果が得られない場合に、医師が選択肢の一つとして検討することがあります。
この治療は、特定の波長の紫外線を患部に照射することで、免疫反応を調整し炎症を抑えることを目的とします。
生活習慣の見直しとストレス管理
不規則な生活、睡眠不足、栄養バランスの偏った食事、過度なストレスは、免疫機能を低下させ、頭皮環境の悪化や炎症の増悪につながることがあります。
規則正しい生活を送り、十分な睡眠時間を確保し、バランスの取れた食事を心がけることが、治療効果を高め、再発しにくい身体を作る上で重要です。ストレスを溜め込まないよう、適度な運動や趣味などで上手に発散しましょう。
長引く薄毛の悩みは、それ自体が大きなストレスとなり、症状を悪化させる悪循環に陥ることもあります。
生活習慣改善のヒント
- 十分な睡眠(6-8時間目安)
- バランスの取れた食事(野菜、タンパク質を意識)
- 適度な運動(ウォーキングなど)
- 禁煙、節度ある飲酒
焦らずじっくりと 治療期間の目安
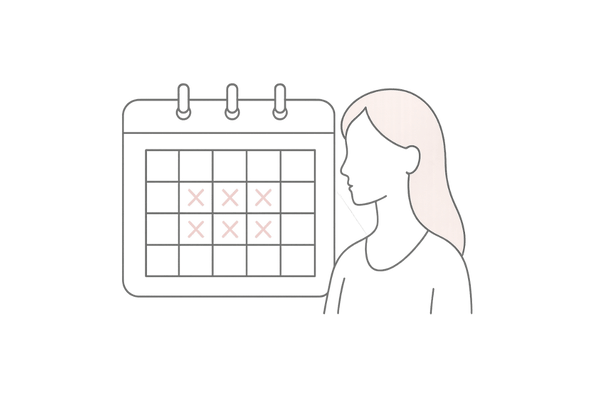
禿髪性毛包炎の治療は、残念ながらすぐに結果が出るものではありません。症状が改善し、抜け毛が減り、新しい髪が生えてくるまでには、数ヶ月から年単位の期間を要することが一般的です。
長引く治療に不安を感じることもあるかもしれませんが、焦らず、根気強く治療を続けることが完治への道です。医師は、患者さんの状態に合わせて治療法を調整し、サポートします。
治療期間の一般的な目安
軽症であれば数ヶ月で炎症が落ち着くこともありますが、中等症以上や、長期間放置されていたケースでは、1年以上の治療期間が必要となることも珍しくありません。
特に、一度破壊された毛包が再生し、しっかりとした髪が生えてくるまでには時間がかかります。治療効果には個人差があり、途中で症状が良くなったり悪くなったりを繰り返すこともあります。
治療効果判定のタイミング
通常、治療開始から1~3ヶ月程度で、炎症の軽減(赤み、腫れ、膿の減少)やかゆみの改善が見られるか評価します。抜け毛の減少や発毛の実感には、さらに時間が必要です。
医師は定期的に頭皮の状態を観察し、写真撮影などで記録しながら治療効果を判定します。
治療中の心の持ち方
治療が長引くと、精神的に落ち込んだり、本当に治るのかと不安になったりすることもあるでしょう。しかし、悲観的になる必要はありません。
現代の医学では、多くの治療選択肢があり、症状をコントロールし、QOL(生活の質)を改善することが可能です。治療の過程で生じる疑問や不安は、遠慮なく医師に相談しましょう。
信頼できる医師との良好な関係は、治療を続ける上で大きな支えとなります。
精神的サポートの重要性
薄毛や頭皮のトラブルは、他人に相談しにくいデリケートな問題です。家族や友人の理解とサポートも大切ですが、時には専門のカウンセラーや同じ悩みを持つ患者さんの会などが心の支えとなることもあります。
一人で抱え込まず、適切なサポートを求めることも考えましょう。
治療効果の指標
| 評価項目 | 改善の目安 | 時期の目安 |
|---|---|---|
| 炎症(赤み、腫れ、膿) | 明らかに軽減する | 1~3ヶ月 |
| かゆみ、痛み | 気にならない程度になる | 1~3ヶ月 |
| 抜け毛 | シャンプー時や枕元の抜け毛が減る | 3~6ヶ月 |
| 発毛 | うぶ毛や短い毛が見られる | 6ヶ月~1年以上 |
上記の期間はあくまで目安であり、個人差が大きいことをご理解ください。医師の指示に従い、根気強く治療を続けることが最も重要です。
もう繰り返さないために 今日から始められる再発予防の秘訣
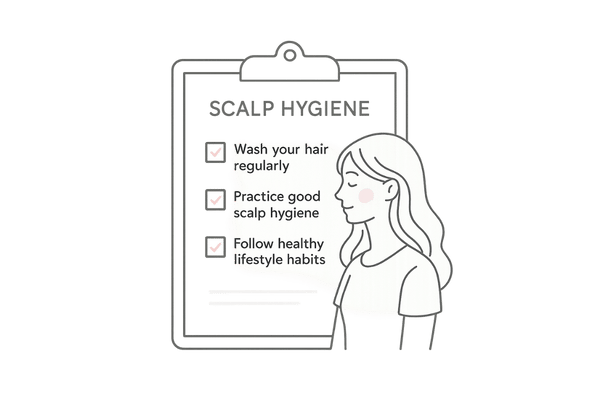
禿髪性毛包炎は、一度症状が改善しても、残念ながら再発しやすい疾患の一つです。治療によって炎症が治まっても、根本的な原因が残っている場合や、頭皮環境が悪化すると、再び症状が現れることがあります。
そのため、治療後も油断せず、日々の生活の中で再発予防を意識することが極めて重要です。繰り返すかゆみや抜け毛に悩まされないために、今日からできることを始めましょう。
頭皮を清潔に保つ正しいヘアケア
頭皮の清潔は基本ですが、洗いすぎや間違った洗い方は逆効果です。1日1回、低刺激性のシャンプーを使い、指の腹で優しくマッサージするように洗いましょう。すすぎ残しは毛穴詰まりや炎症の原因になるため、時間をかけて丁寧に洗い流します。
洗髪後は、ドライヤーで頭皮までしっかり乾かすことが大切です。濡れたまま放置すると雑菌が繁殖しやすくなり、再発のリスクを高めます。
正しいシャンプーの手順
- 洗髪前にブラッシングで髪のもつれを解き、汚れを浮かす。
- ぬるま湯で髪と頭皮を十分に予洗いする。
- シャンプーを手のひらで泡立ててから髪につけ、指の腹で頭皮をマッサージするように洗う。
- すすぎ残しがないよう、時間をかけて丁寧に洗い流す。
- タオルドライ後、ドライヤーで頭皮から乾かす。
食生活の改善と栄養バランス
健やかな頭皮と髪を育むためには、バランスの取れた食事が欠かせません。特に、髪の主成分であるタンパク質、皮膚の新陳代謝を促すビタミンB群、抗酸化作用のあるビタミンC・E、そしてミネラル(特に亜鉛)などを積極的に摂取しましょう。
脂っこい食事や糖分の多い食事、刺激物は、皮脂の過剰分泌や炎症を悪化させる可能性があるため、控えめにすることが望ましいです。
頭皮と髪に良い栄養素
| 栄養素 | 多く含む食品 | 期待される働き |
|---|---|---|
| タンパク質 | 肉、魚、卵、大豆製品 | 髪の主成分 |
| ビタミンB群 | レバー、緑黄色野菜、穀物 | 皮膚・粘膜の健康維持、代謝促進 |
| 亜鉛 | 牡蠣、牛肉、ナッツ類 | 細胞分裂の正常化、免疫力向上 |
十分な睡眠とストレスコントロール
睡眠不足やストレスは、ホルモンバランスの乱れや免疫力の低下を引き起こし、頭皮環境を悪化させ、禿髪性毛包炎の再発を招く大きな要因となります。毎日同じ時間に寝起きするなど、質の高い睡眠を十分にとるよう心がけましょう。
また、自分なりのストレス解消法を見つけ、心身ともにリラックスできる時間を作ることも大切です。長引く症状や繰り返す薄毛への不安がストレスとなり、悪循環に陥らないように注意が必要です。
健やかな髪を育む 治療後の状態を維持するためのセルフケア習慣
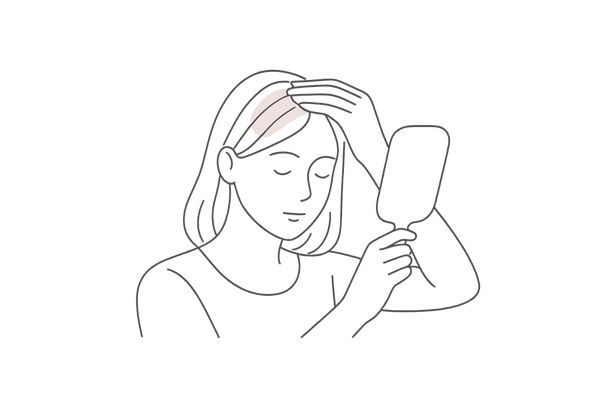
禿髪性毛包炎(とくはつせいもうほうえん)の治療が一段落し、症状が改善した後も、その良好な状態を維持し、健やかな髪を育むためには日々のセルフケアが非常に重要です。
治療で取り戻した頭皮の健康を、今度はご自身の力で守り育てていく意識を持ちましょう。
瘢痕が残ってしまった部分があっても、周囲の毛髪を健康に保つことで、全体の印象は大きく変わります。
定期的な頭皮チェックの習慣化
治療が終わったからといって安心せず、定期的にご自身の頭皮の状態をチェックする習慣をつけましょう。鏡を使ったり、家族に見てもらったりして、赤み、かゆみ、小さなブツブツ、抜け毛の増加など、再発の兆候がないか確認します。
もし何か異常を感じたら、自己判断で放置せず、早めに皮膚科専門医に相談することが、悪化を防ぐ鍵です。
セルフチェックのポイント
- 頭皮の色(赤みがないか)
- フケやかさつきの有無
- 毛穴の状態(詰まりや炎症がないか)
- 抜け毛の量(以前と比較してどうか)
頭皮マッサージによる血行促進
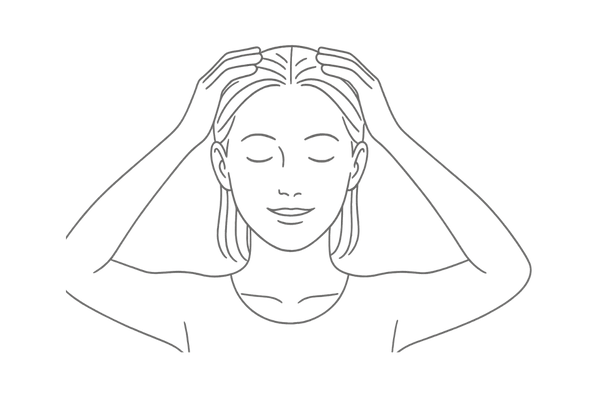
頭皮マッサージは、血行を促進し、毛根に栄養を届けやすくする効果が期待できます。指の腹を使って、優しく頭皮全体を揉みほぐしましょう。ただし、炎症が残っている時期や、強く擦りすぎることは逆効果になるため注意が必要です。
医師に相談の上、適切な方法で行うようにしてください。爪を立てたり、力を入れすぎたりすると、頭皮を傷つけ、かえって炎症や抜け毛を悪化させる可能性があります。
頭皮マッサージの注意点
| 行うタイミング | 方法 | 避けるべきこと |
|---|---|---|
| シャンプー時やリラックス時 | 指の腹で優しく揉む | 爪を立てる、強く擦る |
| 血行が良い入浴後など | 頭皮全体をゆっくり動かすように | 炎症や痛みがある時は行わない |
紫外線対策の徹底
紫外線は頭皮にダメージを与え、乾燥や炎症を引き起こす原因となります。特に治療後のデリケートな頭皮は、紫外線の影響を受けやすいため、外出時には帽子や日傘を使用するなど、紫外線対策を徹底しましょう。
頭皮用の日焼け止めスプレーなども有効ですが、使用後は丁寧に洗い流すことが大切です。長時間の屋外活動では、こまめに日陰で休憩することも心がけてください。
自信に満ちた笑顔のために 治療のゴール
禿髪性毛包炎(とくはつせいもうほうえん)の治療は、単に炎症を抑え、抜け毛を減らすことだけがゴールではありません。
治療を通じて頭皮の悩みが解消され、髪への自信を取り戻し、心から笑顔になれること。それが真のゴールと言えるでしょう。
長引く症状や繰り返す薄毛は、精神的にも大きな負担となりますが、諦めずに治療を続けることで必ず道は開けます。完治が難しいとされる瘢痕性の脱毛であっても、進行を止め、残った毛髪を大切に育むことでQOLの向上は十分に可能です。
治療後のQOL(生活の質)の向上
頭皮の状態が改善し、抜け毛の心配が減ることで、これまで避けていたヘアスタイルに挑戦できたり、人と会うことが楽しくなったりと、日常生活における精神的な負担が大きく軽減されます。
自信を取り戻すことは日々の生活の質を高め、より前向きな気持ちで過ごすための大きな力となります。薄毛の悩みが解消されることで、仕事や趣味にも積極的に取り組めるようになるでしょう。
定期的なメンテナンスと医師との連携
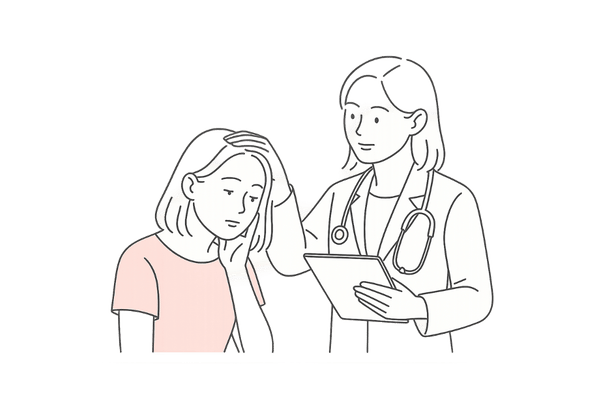
症状が安定した後も定期的に皮膚科専門医の診察を受け、頭皮の状態をチェックしてもらうことをお勧めします。万が一再発の兆候が見られた場合でも、早期に対処することが可能になります。
また、季節の変わり目や体調の変化など頭皮環境に影響を与えやすい時期には、特に注意深くセルフケアを行い、必要であれば医師に相談しましょう。
医師との良好な関係を維持し、長期的な視点で頭皮の健康管理を行うことが大切です。
医師との連携で目指すもの
| 目標 | 具体的な行動 |
|---|---|
| 症状の安定化 | 定期的な診察、指示されたケアの継続 |
| 早期発見・早期対処 | 頭皮のセルフチェック、異常時の即時相談 |
| QOLの維持・向上 | 不安や疑問の解消、前向きな生活 |
よくある質問
- 治療を開始してからどれくらいで効果を実感できますか?
-
効果を実感できるまでの期間には個人差が大きいですが、一般的に炎症(赤み、膿、かゆみなど)の改善は治療開始から1~3ヶ月程度で感じられることが多いです。
抜け毛の減少や新しい髪の毛が生えてくるのを実感するには、さらに時間がかかり、3ヶ月~半年、あるいはそれ以上かかることもあります。焦らず、医師の指示に従って根気強く治療を続けることが大切です。
- 治療薬に副作用はありますか?
-
どのような薬にも副作用の可能性はあります。内服薬では、抗生物質による胃腸症状やアレルギー反応、ステロイドによる免疫力低下やむくみなどが考えられます。
外用薬では、ステロイドによる皮膚の菲薄化や毛細血管拡張、かぶれなどが起こることがあります。ただし、医師はこれらの副作用を最小限に抑えるよう、薬の種類や量、使用期間を慎重に調整します。
気になる症状が現れた場合は、自己判断せず速やかに医師にご相談ください。
- 治療中に気をつけるべき生活習慣はありますか?
-
バランスの取れた食事、十分な睡眠、ストレスを溜めない生活を心がけることが重要です。特に、頭皮の清潔を保つための正しい洗髪方法を実践し、洗髪後はしっかり乾かしてください。
また、喫煙や過度な飲酒は血行を悪化させ、頭皮環境に良くない影響を与える可能性があるため控えることをお勧めします。紫外線も頭皮にダメージを与えるため、外出時には帽子などで保護しましょう。
- 治った後、再発することはありますか?
-
残念ながら、禿髪性毛包炎は再発しやすい疾患の一つです。治療によって症状が改善しても、頭皮環境が悪化したり、何らかの誘因が加わったりすると再発する可能性があります。
そのため、治療後も医師の指示に従い、適切なセルフケアを継続し、定期的な頭皮チェックを行うことが再発予防には重要です。再発の兆候が見られたら、早めに受診してください。
- 瘢痕が残ってしまった場合、髪はもう生えてきませんか?
-
禿髪性毛包炎が進行し、毛包が完全に破壊されて瘢痕組織に置き換わってしまうと、その部分からの発毛は困難になることが多いです。
しかし、治療の目的は、炎症を抑えてさらなる瘢痕化を防ぎ、残っている毛包を保護し、可能な限り毛髪の再生を促すことです。瘢痕の範囲や程度にもよりますが、周囲の健康な毛髪を育てることで、見た目の印象を改善することは可能です。
植毛などの外科的治療が選択肢となる場合もありますので、医師にご相談ください。
参考文献
WALKER, S. L., et al. Improvement of folliculitis decalvans following shaving of the scalp. British Journal of Dermatology, 2000, 142.6: 1245-1246.
MIGUEL-GÓMEZ, Laura, et al. Folliculitis decalvans: effectiveness of therapies and prognostic factors in a multicenter series of 60 patients with long-term follow-up. Journal of the American Academy of Dermatology, 2018, 79.5: 878-883.
WAŚKIEL‐BURNAT, Anna, et al. Management of folliculitis decalvans: The EADV task force on hair diseases position statement. Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology, 2025.
MASSON, Rahul, et al. Treatments for dissecting cellulitis of the scalp: a systematic review and treatment algorithm. Dermatology and Therapy, 2023, 13.11: 2487-2526.
EKPUDU, VIOLET IDONNI. Pattern of alopecia and the effect of alopecia on the quality of life of patients. NPMCN (dissertation). National Postgraduate Medical College of Nigeria, 2008.
KUTLU, Ömer; WOLLINA, Uwe. Management of Hair Loss. In: Textbook of Cosmetic Dermatology. CRC Press, 2024. p. 274-285.
PEREZ, Sofia M., et al. Botulinum Toxin in the Treatment of Hair and Scalp Disorders: Current Evidence and Clinical Applications. Toxins, 2025, 17.4: 163.
ALHAMEEDY, Meshal M.; ALSANTALI, Adel M. Therapy-recalcitrant folliculitis decalvans controlled successfully with adalimumab. International Journal of Trichology, 2019, 11.6: 241-243.
ARAVAMUTHAN, Ramesh, et al. An overview of scalp dermatoses in a tertiary care institute. Int J Res Dermatol, 2020, 6.3: 304-12.
TRÜEB, Ralph M., et al. Bacterial diseases. In: Hair in infectious disease: recognition, treatment, and prevention. Cham: Springer International Publishing, 2023. p. 35-127.
来院予約
当院(こばとも皮膚科:愛知県名古屋市栄)では、禿髪性毛包炎の治療を行っております。
以下のページで現地住所(アクセス)や診療時間および来院予約をいただけます。院長は女医(皮膚科専門医)ですのでご安心して治療いただけると思います。
遠隔治療のご案内
当院(こばとも皮膚科:愛知県名古屋市栄)にお越しいただくのが難しい方に、当院で処方している遺伝子検査付き育毛剤の通販を案内いたします。
遺伝子検査キットをご自宅に郵送し、あなたの遺伝子に適したオーダーメイド育毛剤をご自宅に届けます。以下で詳しく解説しておりますのでご覧ください。