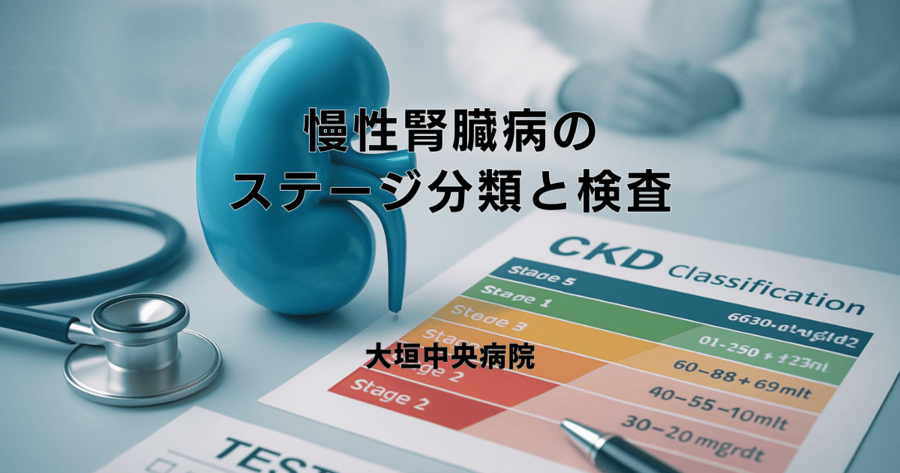腎臓は私たちの体にとって重要な臓器の一つですが、その機能が静かに低下していく「腎臓病」は、初期には自覚症状が乏しいことが多い疾患です。
この記事では、腎臓病の診断基準、特にCKD(慢性腎臓病)のステージ分類や、どのような検査が行われるのかについて、分かりやすく解説します。腎臓の健康状態を把握し、早期発見・早期対応につなげるための一助となれば幸いです。
腎臓の基本的な役割と機能低下の影響
私たちの体には、生命維持に欠かせない様々な臓器があります。その中でも腎臓は、体内の環境を一定に保つために、日夜休むことなく働いている重要なフィルターのような存在です。
ここでは、腎臓が持つ基本的な役割と、その機能が低下した場合に体にどのような影響が現れるのかを解説します。
腎臓の主な働き
腎臓は、腰のやや上に左右一つずつある、そら豆のような形をした臓器です。小さいながらも、その働きは多岐にわたります。
主な腎機能
| 機能 | 説明 |
|---|---|
| 老廃物の排泄 | 血液をろ過し、体内で不要になった老廃物や余分な水分を尿として体外へ排出します。 |
| 体液のバランス調整 | 体内の水分量やナトリウム、カリウムなどの電解質の濃度を一定に保ちます。 |
| ホルモンの産生 | 血圧を調整するホルモン(レニン)、赤血球の産生を促すホルモン(エリスロポエチン)、骨を強くするビタミンDの活性化などに関わるホルモンを産生します。 |
これらの機能を通じて、腎臓は体内の環境を整え、私たちの健康を支えています。
腎機能が低下するとどうなるか
腎臓の機能が低下すると、上記のような働きが十分にできなくなります。初期の段階では自覚症状がほとんどないことが多いですが、進行すると様々な症状が現れます。
例えば、老廃物が体内に蓄積すると、だるさや食欲不振、吐き気などの症状が出ることがあります。水分や電解質のバランスが崩れると、むくみや高血圧、不整脈などを引き起こす可能性があります。
また、ホルモンの産生が滞ると、貧血や骨がもろくなるなどの問題も生じます。これらの症状は、腎機能低下のサインである可能性があるため、注意が必要です。
腎臓病の主な種類
腎臓病と一言で言っても、その原因や病態は様々です。
代表的なものには、生活習慣病である糖尿病や高血圧が原因で起こる「糖尿病性腎症」や「腎硬化症」、免疫の異常が関与する「慢性糸球体腎炎(IgA腎症など)」、遺伝性の「多発性のう胞腎」などがあります。
これらの疾患は、進行すると腎機能が徐々に低下し、慢性腎臓病(CKD)に至ることがあります。
それぞれの腎臓病には特徴があり、治療法も異なります。そのため、正確な診断を受け、適切な対応をすることが重要です。
腎臓病のサインを見逃さないために
腎臓病は「沈黙の臓器」とも呼ばれるように、初期には自覚症状が現れにくい特徴があります。しかし、以下のような変化に気づいたら、腎臓病の可能性も考慮し、医療機関を受診することをお勧めします。
- 尿の変化(泡立ちが続く、色が濃い、血が混じるなど)
- むくみ(顔、手足など)
- だるさ、疲れやすさ
- 食欲不振、吐き気
- 高血圧
これらのサインは他の病気でも見られることがありますが、腎臓からのSOSである可能性も否定できません。定期的な健康診断を受けることも、腎臓病の早期発見には大切です。
CKD(慢性腎臓病)とは何か?定義と重要性
CKD(Chronic Kidney Disease:慢性腎臓病)という言葉を耳にしたことがあるでしょうか。
CKDは、特定の病名ではなく、腎臓の働きが慢性的に低下している状態、または尿検査などで腎臓の障害を示す所見が持続している状態を指す包括的な概念です。ここでは、CKDの定義や、なぜ早期発見と対応が重要なのかについて解説します。
CKDの定義
CKDは、以下のいずれか、または両方が3ヶ月以上持続する場合に診断されます。
- 尿検査や画像診断、血液検査、病理所見などで、腎障害を示唆する所見(例:タンパク尿、血尿など)がある。
- GFR(糸球体濾過量)が60mL/分/1.73m²未満である。
GFRとは、腎臓が1分間にどれくらいの血液をろ過できるかを示す値で、腎機能の重要な指標となります。この値が低いほど、腎機能が低下していることを意味します。
CKDの診断基準は、腎臓の障害が一時的なものではなく、慢性的に続いていることを重視しています。
なぜCKDは早期発見が重要なのか
CKDは、進行すると末期腎不全に至り、透析療法や腎移植が必要になる場合があります。また、CKDは心血管疾患(心筋梗塞や脳卒中など)の重要な危険因子でもあります。腎機能が低下すると、動脈硬化が進行しやすくなり、心血管イベントのリスクが高まることが知られています。
しかし、CKDは早期に発見し、適切な治療や生活習慣の改善を行うことで、進行を遅らせたり、心血管疾患のリスクを軽減したりすることが可能です。
自覚症状が出にくい初期の段階でCKDを発見し、対策を始めることが、将来の健康を守る上で非常に重要です。
CKDの進行リスク
| リスク因子 | CKDへの影響 |
|---|---|
| 高血圧 | 腎臓の血管に負担をかけ、腎機能低下を促進します。 |
| 糖尿病 | 高血糖が腎臓の細い血管を傷つけ、腎機能が悪化します。 |
| 脂質異常症 | 動脈硬化を進行させ、腎機能に悪影響を与えます。 |
CKDの原因となる主な疾患
CKDを引き起こす原因は多岐にわたりますが、日本では生活習慣病に関連するものが多くを占めています。
- 糖尿病性腎症
- 腎硬化症(高血圧や加齢によるもの)
- 慢性糸球体腎炎(IgA腎症など)
- 多発性のう胞腎
- その他(薬剤性腎障害、膠原病に伴う腎障害など)
これらの原因疾患を特定し、その治療を行うこともCKDの進行を抑えるためには大切です。原因がはっきりしない場合や、複数の要因が絡み合っていることもあります。
CKDの進行と合併症のリスク
CKDが進行すると、腎機能の低下に伴い様々な合併症が現れるリスクが高まります。例えば、体液の貯留によるむくみや心不全、電解質異常(カリウム値の上昇など)、貧血、骨がもろくなる腎性骨症(ミネラル・骨代謝異常)などです。
これらの合併症は、生活の質(QOL)を低下させるだけでなく、生命に関わることもあります。
CKDのステージが進むほど、これらの合併症のリスクは高まります。そのため、定期的な検査を受け、合併症の早期発見と管理を行うことが、CKD治療の重要な柱となります。
腎臓病の診断基準の概要
腎臓病の診断は、単一の検査結果だけで行われるものではなく、様々な情報を総合的に評価して行われます。
問診、身体診察、尿検査、血液検査、画像検査などを組み合わせて、腎臓の状態や機能、そして原因となっている可能性のある疾患を探っていきます。ここでは、腎臓病の診断基準の基本的な考え方について説明します。
診断に使われる主な指標
腎臓病の診断においては、いくつかの重要な指標が用いられます。これらは、腎臓がどの程度障害されているか、また、その原因は何かを推定する手がかりとなります。
主要な診断指標
| 指標 | 検査方法 | 評価内容 |
|---|---|---|
| タンパク尿 | 尿検査 | 腎臓のフィルター機能の障害の有無 |
| 血尿 | 尿検査 | 腎臓や尿路からの出血の有無 |
| eGFR(推算糸球体濾過量) | 血液検査(血清クレアチニン値などから計算) | 腎臓のろ過能力の程度 |
これらの指標に異常が見られた場合、さらに詳しい検査を行い、診断を確定していきます。特に、タンパク尿の持続やeGFRの低下は、CKD(慢性腎臓病)の診断において中心的な役割を果たします。
診断プロセスの流れ
腎臓病が疑われる場合、一般的には以下のような流れで診断が進められます。
- 問診 症状、既往歴、家族歴、服用中の薬剤などを詳しく聞きます。
- 身体診察 血圧測定、むくみの確認などを行います。
- 尿検査 タンパク尿、血尿、尿糖、尿沈渣などを調べます。
- 血液検査 血清クレアチニン、eGFR、BUN(尿素窒素)、電解質、貧血の有無などを調べます。
- 画像検査 腎臓の形や大きさ、結石や腫瘍の有無などを超音波検査やCT検査で確認します。
- 腎生検(必要な場合) 腎臓の組織を一部採取し、顕微鏡で詳しく調べることで、より正確な診断や治療方針の決定に役立てます。
全ての患者さんにこれらの検査が全て行われるわけではなく、個々の状態に応じて必要な検査を選択します。
早期診断のメリット
腎臓病、特にCKDは、早期に発見し適切な対応を始めることで、その進行を遅らせることが期待できます。早期診断には以下のようなメリットがあります。
- 腎機能低下の進行抑制
- 末期腎不全への移行リスクの低減
- 心血管疾患(心筋梗塞、脳卒中など)の発症リスクの低減
- 原因疾患の治療による腎機能改善の可能性
- 生活習慣の改善指導によるQOLの維持・向上
自覚症状がない段階でも、健康診断などで尿検査や血液検査の異常を指摘された場合は、放置せずに医療機関を受診し、詳しい検査を受けることが大切です。
診断における注意点
腎臓病の診断は、時に複雑で、専門的な知識と経験を要します。一時的な体調不良や薬剤の影響で検査値が変動することもあるため、一度の検査結果だけで判断せず、複数回の検査や経過観察が必要な場合もあります。
また、腎臓病の種類によっては、診断を確定するために腎生検のような専門的な検査が求められることもあります。
診断結果や治療方針については、医師から十分な説明を受け、理解を深めることが重要です。疑問や不安な点があれば、遠慮なく質問し、納得のいく医療を受けるようにしましょう。
CKD(慢性腎臓病)のステージ分類
CKD(慢性腎臓病)は、その進行度合いを客観的に評価するために、いくつかのステージに分類されます。このステージ分類は、主にGFR(糸球体濾過量)の値と、尿中アルブミンまたはタンパク尿の量に基づいて行われます。
ステージを把握することは、現在の腎臓の状態を理解し、今後の治療方針を立てる上で非常に重要です。
GFR(糸球体濾過量)によるステージ分類
GFRは、腎臓が老廃物をろ過する能力を示す指標で、この値が低いほど腎機能が低下していることを意味します。CKDのステージは、このGFRの値によってG1からG5までの5段階(G3はG3aとG3bに細分化)に分けられます。
CKDステージ分類(GFRに基づく)
| ステージ | GFR (mL/分/1.73m²) | 腎機能の状態 |
|---|---|---|
| G1 | 90以上 | 正常または高値(ただし腎障害を示唆する所見がある場合) |
| G2 | 60~89 | 軽度低下 |
| G3a | 45~59 | 軽度~中等度低下 |
| G3b | 30~44 | 中等度~高度低下 |
| G4 | 15~29 | 高度低下 |
| G5 | 15未満 | 末期腎不全(透析や腎移植が必要な段階) |
ステージG1やG2であっても、タンパク尿などの腎障害を示す所見があればCKDと診断されます。GFRの値が正常範囲内であっても、腎臓に何らかの異常が起きている可能性があるため、注意が必要です。
アルブミン尿による分類(A分類)
GFRによるステージ分類に加えて、尿中のアルブミン(タンパク質の一種)の量による分類(A分類)も重要です。
アルブミン尿は、腎臓のフィルター機能が障害されていることを示す早期のサインであり、CKDの進行や心血管疾患のリスクとも関連しています。
アルブミン尿・タンパク尿による分類(A分類)
| 区分 | 尿アルブミン定量 (mg/gCr) または 尿タンパク定量 (g/gCr) | 評価 |
|---|---|---|
| A1 | 30未満 (アルブミン) または 0.15未満 (タンパク) | 正常または微量 |
| A2 | 30~299 (アルブミン) または 0.15~0.49 (タンパク) | 中等量アルブミン尿 (微量アルブミン尿) |
| A3 | 300以上 (アルブミン) または 0.50以上 (タンパク) | 高度アルブミン尿 (顕性アルブミン尿) |
同じGFRのステージであっても、アルブミン尿が多いほど、腎機能低下の進行速度が速く、心血管疾患のリスクも高いことが知られています。そのため、GFRとアルブミン尿の両方を評価することが、より正確なリスク評価につながります。
CKDステージ分類の意義と活用
CKDのステージ分類は、単に腎機能の状態を示すだけでなく、治療目標の設定や管理計画の策定に役立ちます。
例えば、ステージが進むにつれて、食事療法(タンパク質や塩分の制限など)の重要性が増したり、合併症(貧血、骨代謝異常、高カリウム血症など)の管理がより専門的になったりします。
また、ステージG4以降では、腎代替療法(透析や腎移植)の準備について、患者さんやご家族と話し合いを始める時期の目安にもなります。
自身のCKDステージを正確に把握し、医師と協力して適切な対策を講じることが、腎臓病の進行を遅らせ、より良い生活を送るために大切です。
腎臓病の検査方法 詳細解説
腎臓病の診断や進行度の評価、治療効果の判定には、様々な検査が行われます。これらの検査は、腎臓の機能や形態、そして病気の原因を明らかにするために重要です。ここでは、代表的な検査方法について、それぞれ詳しく解説します。
尿検査
尿検査は、腎臓病のスクリーニング(ふるい分け)や診断、経過観察において、最も基本的で重要な検査の一つです。体に負担が少なく、多くの情報を得ることができます。
尿タンパク検査
健康な人の尿には、タンパク質はごく微量しか含まれません。しかし、腎臓のフィルター機能が障害されると、血液中のタンパク質(主にアルブミン)が尿中に漏れ出てきます。これをタンパク尿と呼びます。
タンパク尿の有無や程度は、腎障害の重要な指標となります。持続的なタンパク尿は、CKDの診断基準の一つであり、腎機能低下の進行や心血管疾患のリスクとも関連しています。
尿潜血検査
尿潜血検査は、尿中に血液が混じっているかどうかを調べる検査です。陽性の場合、腎臓や尿路(尿管、膀胱、尿道)からの出血が疑われます。腎炎、結石、腫瘍、感染症など、様々な原因が考えられます。
ただし、激しい運動後や月経時など、病気でなくても一時的に陽性になることもあります。
尿沈渣検査
尿沈渣検査は、尿を遠心分離機にかけ、沈殿した成分(赤血球、白血球、細菌、細胞、結晶など)を顕微鏡で観察する検査です。
これにより、血尿の種類(糸球体性か非糸球体性か)、感染の有無、腎臓の炎症の程度などをより詳しく評価することができます。腎臓病の種類を特定する上で、重要な手がかりとなることがあります。
血液検査
血液検査は、腎臓のろ過機能や、腎臓病に伴う合併症の状態を評価するために行われます。
血清クレアチニン値(Cr)とeGFR
クレアチニンは、筋肉運動の老廃物で、腎臓から尿中に排泄されます。腎機能が低下すると、クレアチニンを十分に排泄できなくなり、血液中のクレアチニン値が上昇します。
この血清クレアチニン値と年齢、性別から計算されるのがeGFR(推算糸球体濾過量)です。eGFRは、現在の腎機能をおおよそ把握するための重要な指標で、CKDのステージ分類にも用いられます。
血中尿素窒素(BUN)
尿素窒素は、タンパク質が体内で分解された後にできる老廃物で、主に腎臓から排泄されます。腎機能が低下すると、BUNの値も上昇する傾向があります。
ただし、BUNは食事内容(タンパク質の摂取量)や脱水、消化管出血など、腎機能以外の要因でも変動するため、クレアチニン値やeGFRと合わせて総合的に評価します。
その他の血液検査項目
腎臓病の評価や合併症の管理のために、上記以外にも様々な血液検査が行われます。
腎機能関連の血液検査項目例
| 検査項目 | 評価する内容 |
|---|---|
| 電解質(ナトリウム、カリウム、クロールなど) | 体液のバランス、腎臓の再吸収・排泄機能 |
| 貧血検査(ヘモグロビン、赤血球数など) | 腎性貧血の有無(腎臓からのエリスロポエチン産生低下) |
| 骨代謝マーカー(カルシウム、リン、PTHなど) | 腎性骨症(ミネラル・骨代謝異常)の評価 |
| 血糖値、HbA1c | 糖尿病のコントロール状態(糖尿病性腎症のリスク評価) |
| 脂質(コレステロール、中性脂肪など) | 脂質異常症の有無(心血管疾患リスク評価) |
画像検査
画像検査は、腎臓の大きさや形、構造、血流などを視覚的に評価するために行われます。これにより、腫瘍や結石、のう胞、水腎症(尿路の閉塞による腎臓の腫れ)などの異常を発見することができます。
超音波検査(エコー検査)
超音波検査は、体に超音波を当て、その反響を画像化する検査です。痛みや放射線被ばくの心配がなく、簡便に行えるため、腎臓のスクリーニング検査としてよく用いられます。
腎臓の大きさや形態、結石やのう胞の有無、水腎症の評価などに有用です。
CT検査・MRI検査
CT(コンピュータ断層撮影)検査やMRI(磁気共鳴画像)検査は、超音波検査よりも詳細な情報を得ることができる画像検査です。腎臓の腫瘍性病変の精密検査、腎血管の評価、複雑なのう胞性疾患の診断などに用いられます。
造影剤を使用することもあり、その場合はアレルギー歴や腎機能に注意が必要です。
腎生検
腎生検は、腎臓の組織の一部を細い針で採取し、顕微鏡で詳しく調べる検査です。他の検査だけでは診断が難しい場合や、治療方針を決定するために、より正確な病理組織学的情報が必要な場合に行われます。
腎生検の目的と適応
腎生検の主な目的は、腎臓病の種類(病名)を確定診断すること、病気の活動性や進行度を評価すること、そして治療法の選択や予後の予測に役立てることです。
持続するタンパク尿や血尿、原因不明の急性または急速進行性の腎機能低下、腎移植後の拒絶反応の診断などが、腎生検の主な適応となります。
腎生検を行うかどうかは、日本腎臓学会が作成している「腎生検ガイドライン」などを参考に、患者さんの状態や検査の利益とリスクを総合的に考慮して判断します。
腎生検の実際と注意点
腎生検は、通常、入院して行われます。局所麻酔下で、超音波で腎臓の位置を確認しながら、背中から細い針を刺して腎臓の組織を採取します。検査後は、出血などの合併症を防ぐために数時間の安静が必要です。
合併症としては、出血(血尿、腎周囲血腫)、痛み、感染などがありますが、頻度は高くありません。検査前には、医師から検査の必要性、方法、合併症のリスクなどについて十分な説明を受け、同意することが大切です。
腎臓疾患の一覧とそれぞれの特徴
腎臓に影響を与える疾患は数多く存在します。ここでは、比較的よく見られる代表的な腎臓疾患と、その他の腎臓疾患について、それぞれの特徴や注意点を解説します。
これらの疾患は、進行するとCKD(慢性腎臓病)の原因となることがあります。
代表的な腎臓疾患
日本においてCKDの主な原因となっている疾患や、比較的頻度の高い腎臓疾患を紹介します。
糖尿病性腎症
糖尿病の三大合併症の一つで、長期間の高血糖状態が続くことで腎臓の細い血管(糸球体)が障害される病気です。初期には自覚症状が乏しく、尿中アルブミン検査で早期に発見することが重要です。
進行すると多量のタンパク尿が出て、ネフローゼ症候群を呈したり、腎機能が低下して末期腎不全に至り、透析導入の原因として最も多い疾患です。血糖コントロール、血圧管理、脂質管理、生活習慣の改善が治療の基本となります。
慢性糸球体腎炎(IgA腎症など)
糸球体に免疫複合体が沈着し、炎症が起こる疾患の総称です。IgA腎症は日本で最も多い慢性糸球体腎炎で、血尿(特に顕微鏡的血尿)やタンパク尿が主な所見です。
風邪などをきっかけに肉眼的血尿(目で見てわかる血尿)が出現することもあります。診断には腎生検が必要となることが多く、治療はステロイドや免疫抑制薬、扁桃摘出術などが病型や進行度に応じて選択されます。
早期発見と適切な治療により、腎機能の悪化を抑制することが期待できます。
腎硬化症
主に高血圧や加齢によって腎臓の動脈が硬化し、腎機能が徐々に低下する病気です。良性腎硬化症と悪性腎硬化症があり、多くは良性でゆっくりと進行します。
厳格な血圧管理が最も重要で、生活習慣の改善(減塩など)や降圧薬による治療が行われます。高齢化に伴い増加傾向にあります。
多発性のう胞腎
腎臓に多数の「のう胞」(液体がたまった袋)ができ、それらが徐々に大きくなることで腎機能が低下する遺伝性の疾患です。
常染色体優性多発性のう胞腎(ADPKD)が最も一般的です。高血圧、血尿、腹部膨満感、腎感染などの症状が現れることがあります。
近年、のう胞の増大を抑制する治療薬も登場していますが、根本的な治療法はまだ確立されていません。定期的な画像検査や血圧管理、合併症対策が重要です。
代表的な腎臓疾患の特徴
| 疾患名 | 主な原因・特徴 | 主な症状・所見 |
|---|---|---|
| 糖尿病性腎症 | 糖尿病による高血糖 | 初期は無症状、進行するとタンパク尿、むくみ、腎機能低下 |
| IgA腎症 | 免疫グロブリンAの沈着 | 血尿(顕微鏡的・肉眼的)、タンパク尿 |
| 腎硬化症 | 高血圧、加齢による動脈硬化 | 初期は無症状、進行すると腎機能低下、タンパク尿 |
| 多発性のう胞腎 | 遺伝的要因 | 多数の腎のう胞、高血圧、血尿、腹部膨満感 |
その他の腎臓疾患
上記以外にも、様々な原因で腎臓が障害されることがあります。
- 急性腎障害(AKI) 急激に腎機能が悪化する状態で、脱水、薬剤、重症感染症など様々な原因で起こります。原因を除去すれば回復することもありますが、一部はCKDに移行することがあります。
- ネフローゼ症候群 高度のタンパク尿と低アルブミン血症を特徴とし、強いむくみが出現します。様々な腎疾患(微小変化型ネフローゼ症候群、膜性腎症など)が原因となります。
- ループス腎炎 全身性エリテマトーデス(SLE)という膠原病に伴う腎障害です。
- 薬剤性腎障害 薬剤の副作用として腎機能が障害されるものです。痛み止め(NSAIDs)、抗菌薬、造影剤などが原因となることがあります。
- 間質性腎炎 腎臓の尿細管や間質に炎症が起こる疾患で、薬剤アレルギーや自己免疫疾患などが原因となります。
- 腎盂腎炎 腎臓の感染症で、発熱、腰痛、排尿時痛などの症状が出ます。
疾患ごとの一般的な経過と注意点
それぞれの腎臓疾患は、その種類や重症度、治療への反応性などによって経過が異なります。一般的に、タンパク尿が多いほど、また腎機能(GFR)が低いほど、腎機能は低下しやすい傾向にあります。
早期に診断を受け、原因疾患の治療や腎保護療法(血圧管理、食事療法など)を適切に行うことが、腎機能の維持にとって重要です。
また、腎臓病は心血管疾患のリスクを高めるため、血圧、血糖、脂質の管理も同時に行う必要があります。定期的な検査を受け、医師の指示に従い、根気強く治療を続けることが大切です。
自己判断で治療を中断したり、民間療法に頼ったりすることは避け、必ず専門医に相談しましょう。
腎臓病の治療と生活上の注意点
腎臓病の治療は、原因となっている疾患の治療と、残された腎機能をできるだけ長持ちさせるための腎保護療法が中心となります。また、日常生活における注意点を守ることも、腎臓への負担を軽減し、病気の進行を遅らせるために重要です。
ここでは、一般的な治療法と生活上の注意点について解説します。
原因疾患に対する治療
腎臓病の原因が特定されている場合、その原因疾患に対する治療が最優先されます。
例えば、糖尿病性腎症であれば血糖コントロール、高血圧が原因の腎硬化症であれば厳格な降圧治療、IgA腎症などの慢性糸球体腎炎であればステロイド療法や免疫抑制療法などが検討されます。
原因疾患を適切に治療することで、腎機能の悪化を食い止めたり、遅らせたりすることが期待できます。
原因疾患の治療は、腎臓専門医だけでなく、糖尿病専門医や循環器専門医など、他の専門分野の医師と連携して行われることもあります。
腎保護のための治療(保存療法)
原因疾患の治療と並行して、腎臓そのものを保護し、機能低下の進行を抑えるための治療(保存療法)が行われます。これには、食事療法、薬物療法、生活習慣の改善などが含まれます。
主な腎保護療法
| 治療法 | 主な内容 | 目的 |
|---|---|---|
| 食事療法 | 塩分制限、タンパク質制限(ステージによる)、カリウム制限(必要な場合) | 腎臓への負担軽減、高血圧・むくみの改善、電解質異常の予防 |
| 薬物療法 | 降圧薬(ACE阻害薬、ARBなど)、SGLT2阻害薬、利尿薬、脂質異常症治療薬、貧血治療薬(ESA製剤)、高カリウム血症治療薬など | 血圧管理、タンパク尿減少、血糖改善、合併症の治療・予防 |
| 生活習慣の改善 | 禁煙、適度な運動、体重管理、十分な睡眠、ストレス管理 | 腎機能低下のリスク因子軽減、全身状態の改善 |
これらの治療は、CKDのステージや患者さん個々の状態に合わせて調整されます。特に食事療法は、専門の管理栄養士による指導を受けることが望ましいです。
日常生活で気をつけること
腎臓病の進行を抑え、合併症を予防するためには、日常生活での自己管理が非常に重要です。
- 塩分を控える 塩分の摂りすぎは高血圧やむくみの原因となり、腎臓に負担をかけます。1日の塩分摂取目標量を守りましょう。
- 適切な水分摂取 脱水は腎機能に悪影響を与えます。ただし、心不全やむくみが強い場合は水分制限が必要なこともありますので、医師の指示に従いましょう。
- 禁煙 喫煙は腎機能低下を促進し、心血管疾患のリスクも高めます。禁煙は必須です。
- 薬剤の服用に注意 腎機能が低下している場合、薬剤の排泄が遅れ、副作用が出やすくなることがあります。市販薬やサプリメントも含め、服用している薬剤は必ず医師や薬剤師に伝え、指示に従いましょう。特に痛み止め(NSAIDs)の長期連用は避けるべきです。
- 感染症の予防 感染症は腎機能悪化の引き金になることがあります。手洗いやうがいを励行し、予防接種も検討しましょう。
- 定期的な受診と検査 医師の指示通りに定期的に受診し、必要な検査を受けることで、腎機能の状態や合併症の有無を把握し、適切な対策を講じることができます。
これらの注意点を守り、医師や医療スタッフと協力しながら治療に取り組むことが、腎臓を守り、より良い生活を送るために大切です。
腎代替療法について
腎機能が著しく低下し、末期腎不全(CKDステージG5)に至った場合、腎臓の働きを代替する治療法(腎代替療法)が必要になります。主な腎代替療法には、血液透析、腹膜透析、腎移植の3つがあります。
どの治療法を選択するかは、医学的な状態だけでなく、患者さんのライフスタイルや価値観、家族のサポート体制などを総合的に考慮して、医師や医療スタッフと十分に話し合って決定します。
腎機能が低下してきた段階で、これらの治療法について情報提供を受け、事前に理解を深めておくことが望ましいです。
よくある質問 (Q&A)
腎臓病に関して、患者さんやご家族からよく寄せられる質問とその回答をまとめました。ただし、個々の状況によって異なる場合があるため、詳細については必ず主治医にご相談ください。
- 腎臓病は遺伝しますか?
-
腎臓病の中には、遺伝が関与するものがあります。代表的なものとして「多発性のう胞腎」があります。これは、特定の遺伝子の変異によって起こる病気で、親子間で遺伝する可能性があります。
また、糖尿病や高血圧など、腎臓病の原因となりやすい生活習慣病も、家族内で発症しやすい傾向(体質的な遺伝要因と生活習慣の共有)が見られることがあります。
ご家族に腎臓病の方がいる場合は、定期的な健康診断を受けるなど、ご自身の腎臓の状態にも注意を払うことが大切です。心配な場合は、医師に相談してみましょう。
- 食事療法だけで腎臓病は治りますか?
-
食事療法は、腎臓への負担を軽減し、腎機能の低下を遅らせるために非常に重要な治療法の一つですが、食事療法だけで腎臓病が完全に治癒することは難しい場合が多いです。
腎臓病の種類や進行度によっては、薬物療法や原因疾患の治療など、他の治療法と組み合わせる必要があります。特に、塩分制限やタンパク質制限は、医師や管理栄養士の指導のもとで適切に行うことが重要です。
自己判断での極端な食事制限は、栄養状態の悪化を招く可能性もあるため注意が必要です。
- 透析を避ける方法はありますか?
-
CKD(慢性腎臓病)が進行し、末期腎不全に至ると透析療法が必要になることがあります。透析を避ける、あるいは開始時期を遅らせるためには、CKDの早期発見と早期治療が最も重要です。
具体的には、原因疾患(糖尿病、高血圧など)の適切な管理、厳格な血圧コントロール、タンパク尿の抑制、食事療法(塩分・タンパク質制限など)、禁煙といった腎保護療法を根気強く続けることです。
これらの治療をしっかりと行うことで、腎機能低下のスピードを緩やかにし、透析導入を遅らせることが期待できます。ただし、病状によっては避けられない場合もあります。
- 腎生検は痛いですか?入院は必要ですか?
-
腎生検は、腎臓の組織を採取する検査で、通常は入院して行います。検査時は局所麻酔をするため、針を刺す瞬間にチクッとした痛みを感じることがありますが、強い痛みは通常ありません。
検査後、数時間はベッド上での安静が必要で、出血などの合併症がないかを確認します。合併症のリスクを考慮し、数日間の入院となることが一般的です。
検査前には医師から詳しい説明がありますので、不安な点や疑問点は遠慮なく質問してください。「腎生検ガイドライン」などに基づき、安全に配慮して行われます。
以上
参考文献
POGGIO, Emilio D., et al. Long-term kidney transplant graft survival—Making progress when most needed. American journal of transplantation, 2021, 21.8: 2824-2832.
COEMANS, Maarten, et al. Analyses of the short-and long-term graft survival after kidney transplantation in Europe between 1986 and 2015. Kidney international, 2018, 94.5: 964-973.
KASISKE, Bertram L., et al. The relationship between kidney function and long-term graft survival after kidney transplant. American Journal of Kidney Diseases, 2011, 57.3: 466-475.
OJO, Akinlolu O., et al. Long-term survival in renal transplant recipients with graft function. Kidney international, 2000, 57.1: 307-313.
GRIVA, Konstadina; DAVENPORT, Andrew; NEWMAN, Stanton P. Health-related quality of life and long-term survival and graft failure in kidney transplantation: a 12-year follow-up study. Transplantation, 2013, 95.5: 740-749.
LEVY, Adrian R., et al. Projecting long-term graft and patient survival after transplantation. Value in Health, 2014, 17.2: 254-260.
YEMINI, Renana, et al. Long-term results of kidney transplantation in the elderly: comparison between different donor settings. Journal of Clinical Medicine, 2021, 10.22: 5308.
NAROUIE, Behzad; SAATCHI, Mohammad. Short term and long term survival rate and risk factors of graft rejection after deceased donor kidney transplantation: a systematic review and meta-analysis. Translational Research in Urology, 2021, 3.3: 95-114.
STROHMAIER, Susanne, et al. Survival benefit of first single-organ deceased donor kidney transplantation compared with long-term dialysis across ages in transplant-eligible patients with kidney failure. JAMA network open, 2022, 5.10: e2234971-e2234971.
WONG, Germaine, et al. Comparative survival and economic benefits of deceased donor kidney transplantation and dialysis in people with varying ages and co-morbidities. PloS one, 2012, 7.1: e29591.