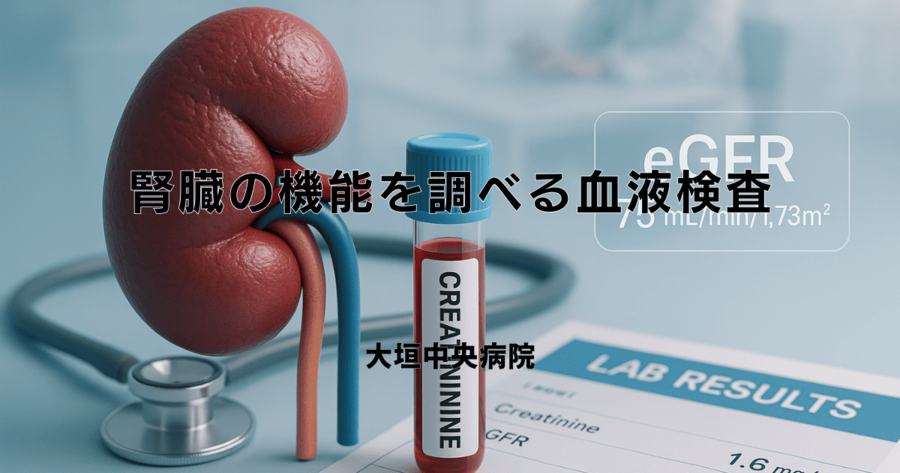腎臓は私たちの体で重要な役割を担っていますが、その機能が低下しても初期には自覚症状が現れにくい臓器です。そのため、定期的な血液検査によって腎臓の状態を把握することが、健康維持のために非常に大切です。
この記事では、腎臓の機能を調べる血液検査の主な項目であるクレアチニンやeGFRなどの数値の見方、基準値について、分かりやすく解説します。ご自身の腎臓の状態に関心を持ち、検査結果を理解する一助となれば幸いです。
腎臓の基本的な働きと血液検査の重要性
私たちの体には二つの腎臓があり、それぞれが生命維持に欠かせない多くの重要な機能を果たしています。腎臓の働きを正しく理解し、血液検査を通じてその状態を把握することは、健康管理の基本です。
腎臓の役割 体内の浄水場
腎臓の最も代表的な働きは、血液をろ過して老廃物や余分な水分を尿として体外へ排出することです。この「ろ過機能」は、体内の水分量や電解質のバランスを調整し、血液をきれいに保つために重要です。
腎臓を流れる血液の量は心臓から送り出される血液の約20%にも及び、この大量の血液の流れの中から、体に必要なものは再吸収し、不要なものだけを選り分けて排出するという高度な作業を絶えず行っています。
まさに体内の浄水場と言えるでしょう。
腎臓の主な働き
| 機能 | 概要 | 体への影響 |
|---|---|---|
| 老廃物の排出 | 血液中の不要物を尿として排出 | 体内の浄化 |
| 水分・電解質調整 | 体液量やイオンバランスを維持 | 血圧調整、むくみ防止 |
| ホルモン産生 | 血圧調整、赤血球産生、骨の健康に関わるホルモンを生成 | 全身の機能維持 |
腎機能低下が引き起こすこと
腎臓の機能が低下すると、老廃物や余分な水分が体内に蓄積しやすくなります。初期には自覚症状がほとんどありませんが、進行すると様々な不調が現れます。例えば、むくみ、貧血、高血圧、倦怠感などが挙げられます。
さらに進行すると、心血管疾患のリスクが高まることも知られています。腎臓の血液の流れが悪くなることも、機能低下の一因となります。
腎機能低下のサインかもしれない症状
- むくみ(顔、手足など)
- 尿の異常(泡立ち、血尿、夜間頻尿)
- 体がだるい、疲れやすい
- 食欲不振、吐き気
これらの症状は他の原因でも起こり得るため、気になる場合は早めに医療機関に相談することが大切です。
なぜ血液検査で腎臓の状態がわかるのか
血液検査は、腎臓が適切に機能しているかどうかを評価するための重要な手段です。腎臓が老廃物をろ過する能力が低下すると、血液中に特定の物質(クレアチニンや尿素窒素など)の濃度が上昇します。
これらの物質の血中濃度を測定することで、腎臓のろ過能力、すなわち腎機能を間接的に評価できます。腎臓の数値を見ることで、自覚症状がない段階でも腎機能の低下を発見できる可能性があります。
定期的な検査で早期発見・早期対応
腎臓病の多くは、初期には症状が現れにくいため、「サイレントキラー」とも呼ばれます。しかし、血液検査を定期的に受けることで、腎機能のわずかな変化も捉えることが可能です。
早期に腎機能の低下を発見し、適切な対策や治療を開始すれば、病気の進行を遅らせたり、重症化を防いだりすることが期待できます。健康診断などに含まれる血液検査の腎臓の値を意識して確認しましょう。
血液検査でわかる腎臓の数値とは?主要項目を解説
健康診断や医療機関での診察時に行われる血液検査には、腎臓の機能を評価するための項目が含まれています。これらの数値を正しく理解することは、ご自身の腎臓の状態を知る第一歩です。
ここでは、腎機能検査の全体像と代表的な項目について説明します。
腎機能検査の全体像
腎機能検査は、主に血液検査と尿検査によって行われます。血液検査では、腎臓のろ過機能によって排出されるべき物質が血液中にどの程度残っているかを調べます。
これにより、腎臓がどれだけ効率よく血液をきれいにしているか(腎臓の血液の流れと浄化能力)を評価します。尿検査では、尿中にタンパク質や血液が漏れ出ていないかなどを調べ、腎臓のダメージの有無を確認します。
代表的な検査項目 クレアチニン、eGFR、尿素窒素
血液検査における腎機能の主要な指標として、クレアチニン(Cr)、eGFR(推算糸球体濾過量)、尿素窒素(BUN)があります。これらの項目は、腎臓のろ過能力を異なる側面から評価するもので、総合的に判断することが重要です。
それぞれの腎臓の数値が何を意味するのかを理解しましょう。
主要な腎機能検査項目とその役割
| 検査項目 | 主な評価内容 | 数値が高い場合に考えられること |
|---|---|---|
| クレアチニン (Cr) | 筋肉で作られる老廃物の排泄状況 | 腎機能の低下 |
| eGFR | 腎臓の糸球体がどれだけ血液をろ過できているかの推定値 | 腎機能の低下(数値が低い場合) |
| 尿素窒素 (BUN) | タンパク質が分解された後の老廃物の排泄状況 | 腎機能の低下、脱水、消化管出血など |
これらの数値が示すもの
クレアチニンや尿素窒素は、本来腎臓でろ過され尿中に排出される老廃物です。これらの血中濃度が高いということは、腎臓のろ過機能が低下し、老廃物を十分に排出できていない可能性を示唆します。
eGFRは、年齢、性別、血清クレアチニン値から計算される指標で、腎臓が1分間にどれくらいの血液をろ過できるかを示します。eGFRが低いほど、腎機能が低下していると評価されます。
これらの腎臓の値を総合的に見ることで、腎機能の状態をより正確に把握できます。
検査を受ける際の注意点
腎機能の血液検査を受ける際には、いくつかの注意点があります。検査結果に影響を与える可能性があるため、事前に確認しておくと良いでしょう。
血液検査前の一般的な注意
- 食事:検査項目によっては、検査前の食事が制限される場合があります。医師の指示に従ってください。
- 運動:激しい運動はクレアチニン値に影響を与えることがあるため、検査前日は避けるのが望ましいです。
- 薬剤:服用中の薬がある場合は、事前に医師に伝えてください。薬によっては検査値に影響することがあります。
正確な腎臓の数値を得るために、これらの点に留意しましょう。
クレアチニン(Cr)値の見方と基準値
クレアチニンは、腎機能を評価する上で基本となる血液検査項目の一つです。この数値が何を意味し、どのように解釈されるのかを理解することは、ご自身の腎臓の状態を把握する上で大切です。
クレアチニンとは何か?筋肉運動との関連
クレアチニンは、筋肉でエネルギーが使われた後にできる老廃物の一種です。クレアチンという物質が代謝されてクレアチニンとなり、血液中に入り、主に腎臓の糸球体でろ過されて尿中に排出されます。
そのため、血中のクレアチニン濃度は、腎臓のろ過能力を反映する指標となります。筋肉量が多い人ほどクレアチニンの産生量が多くなる傾向があるため、同じ腎機能でも筋肉量によってクレアチニン値は変動します。
クレアチニン値が上昇する原因
血清クレアチニン値が上昇する最も一般的な原因は、腎機能の低下です。腎臓のろ過能力が落ちると、クレアチニンを十分に尿中へ排出できなくなり、血液中に蓄積するため数値が上昇します。
その他にも、脱水、特定の薬剤の影響、筋肉量の著しい増加(まれですが)などもクレアチニン値を上昇させる可能性があります。
クレアチニン値に影響を与える主な要因
| 要因 | クレアチニン値への影響 | 備考 |
|---|---|---|
| 腎機能低下 | 上昇 | 最も一般的な原因 |
| 筋肉量 | 筋肉量が多いと高め、少ないと低め | 個人差あり |
| 脱水 | 上昇 | 一時的な影響の場合もある |
クレアチニン値の基準範囲と性差・年齢差
クレアチニンの基準値は、検査施設や測定方法によって多少異なりますが、一般的には成人男性で0.6~1.1mg/dL程度、成人女性で0.4~0.8mg/dL程度とされています。
男性の方が筋肉量が多いため、女性よりも基準値がやや高めに設定されています。また、加齢とともに腎機能は徐々に低下する傾向がありますが、同時に筋肉量も減少することが多いため、高齢者では腎機能が低下していてもクレアチニン値が基準範囲内に収まることもあります。
そのため、クレアチニン値だけでなく、後述するeGFRと合わせて評価することが重要です。
基準値から外れた場合の考え方
クレアチニン値が基準値よりも高い場合は、腎機能が低下している可能性を考えます。ただし、一度の検査結果だけで判断せず、体調や他の検査結果(尿検査、eGFRなど)と合わせて総合的に評価することが必要です。
数値が高い場合は、医療機関で精密検査を受け、原因を特定し、適切な対応をとることが勧められます。低い場合は、筋肉量が少ない、栄養状態が良くないなどの可能性が考えられますが、臨床的に問題となることは少ないです。
eGFR(推算糸球体濾過量)の見方と基準値
eGFR(推算糸球体濾過量)は、現在の腎臓の働きをより正確に把握するための重要な指標です。血清クレアチニン値に加えて、年齢と性別を考慮して計算され、腎臓がどれだけ効率よく老廃物をろ過できているかを示します。
eGFRとは何か?腎臓のろ過能力を評価
eGFRは「estimated Glomerular Filtration Rate」の略で、日本語では「推算糸球体濾過量」といいます。これは、腎臓の中にある糸球体というフィルターが、1分間にどれだけの血液をろ過できるかを示した値(mL/分/1.73m²)です。
この数値が低いほど、腎臓のろ過能力が低下していることを意味します。eGFRは、慢性腎臓病(CKD)の診断や重症度分類にも用いられる重要な腎臓の数値です。
eGFRの計算方法と意義
eGFRは、主に以下の情報から計算式を用いて算出されます。
- 血清クレアチニン値
- 年齢
- 性別
この計算式を用いることで、筋肉量の影響を受けやすいクレアチニン値単独よりも、より実態に近い腎機能を評価できます。
特に、高齢者や筋肉量の少ない人では、クレアチニン値が基準範囲内でもeGFRが低下していることがあるため、eGFRの確認は非常に重要です。
eGFRのステージ分類と慢性腎臓病(CKD)
eGFRの値は、慢性腎臓病(CKD)の進行度を示すステージ分類に用いられます。CKDは、腎障害を示す所見(尿異常、画像異常、病理所見など)か、eGFRが60mL/分/1.73m²未満の状態が3ヶ月以上続く場合に診断されます。
早期発見と適切な管理が進行を遅らせる鍵となります。
eGFRによるCKD重症度分類(日本腎臓学会編 CKD診療ガイドライン2012より一部改変)
| GFR区分 (mL/分/1.73m²) | ステージ | 腎機能の評価 |
|---|---|---|
| 90以上 | G1 | 正常または高値 |
| 60~89 | G2 | 正常または軽度低下 |
| 45~59 | G3a | 軽度~中等度低下 |
| 30~44 | G3b | 中等度~高度低下 |
| 15~29 | G4 | 高度低下 |
| 15未満 | G5 | 末期腎不全 (ESKD) |
※ステージG1、G2であっても、タンパク尿などの腎障害がある場合はCKDと診断されます。
eGFR低下のサインと注意点
eGFRが低下し始めても、初期には自覚症状がないことがほとんどです。しかし、eGFRが60mL/分/1.73m²を下回る状態が続くと、腎機能が正常の60%未満に低下していることを意味し、注意が必要です。
eGFRがさらに低下すると、夜間尿、貧血、倦怠感、むくみなどの症状が現れやすくなります。eGFRの値を定期的に確認し、低下傾向が見られる場合は、生活習慣の改善や専門医への相談を検討しましょう。
腎臓の血液の流れを良く保つことも、eGFR維持には大切です。
尿素窒素(BUN)の見方と基準値
尿素窒素(BUN:Blood Urea Nitrogen)も、腎機能を評価するための血液検査項目の一つです。クレアチニンと同様に、腎臓から排出される老廃物であり、その血中濃度は腎機能の指標となります。
ただし、尿素窒素は腎機能以外の要因でも変動するため、解釈には注意が必要です。
尿素窒素とは何か?タンパク質代謝との関連
尿素窒素は、体内でタンパク質が利用された後に生じる最終産物である尿素に含まれる窒素成分のことです。食事から摂取したタンパク質や体内のタンパク質が分解されるとアンモニアが生じ、これは肝臓で毒性の低い尿素に変換されます。
この尿素は血液によって腎臓に運ばれ、糸球体でろ過されて尿中に排出されます。したがって、血中の尿素窒素濃度は、腎臓の排泄機能とタンパク質の代謝状態を反映します。
尿素窒素値が変動する要因
尿素窒素値は、腎機能の低下によって上昇するほか、以下のような要因でも変動します。
- 食事中のタンパク質摂取量(多いと上昇)
- 消化管出血(血液中のタンパク質が吸収され上昇)
- 脱水(血液が濃縮され上昇)
- 甲状腺機能亢進症(タンパク異化が進み上昇)
- 肝機能障害(尿素合成が低下し減少)
- 極端なタンパク質摂取不足(減少)
このように多くの要因で変動するため、尿素窒素の値だけで腎機能を判断するのは難しく、他の検査結果と合わせて評価することが大切です。
尿素窒素(BUN)の基準値の目安
| 項目 | 一般的な基準値 (mg/dL) | 備考 |
|---|---|---|
| 尿素窒素 (BUN) | 8~20 | 検査施設により多少異なる |
この基準値はあくまで目安であり、個々の状態によって解釈が異なります。
尿素窒素の基準範囲
尿素窒素の基準値は、一般的に8~20mg/dL程度とされていますが、検査施設によって多少異なります。この範囲から外れている場合、腎機能の問題だけでなく、上記のような様々な要因が関わっている可能性があります。
特に、腎機能が低下している場合は、クレアチニン値も同時に上昇することが多いです。
クレアチニン値との比較でわかること
尿素窒素(BUN)とクレアチニン(Cr)の比率(BUN/Cr比)も、病態を推測する上で参考になります。通常、この比率は10~20程度です。
例えば、脱水や消化管出血、タンパク質の過剰摂取など、腎前性の要因でBUNが上昇する場合は、Crの上昇よりもBUNの上昇が顕著となり、BUN/Cr比が高くなることがあります。
一方、腎機能自体が悪化している場合は、BUNとCrがともに上昇する傾向があります。ただし、これもあくまで目安であり、総合的な判断が必要です。
その他の腎機能関連検査項目
クレアチニン、eGFR、尿素窒素の他にも、腎臓の健康状態を評価するために用いられる検査項目がいくつかあります。これらを組み合わせることで、より多角的に腎臓の状態を把握できます。
尿酸(UA)
尿酸は、プリン体という物質が体内で分解されてできる老廃物です。主に腎臓から尿中に排泄されます。
血中の尿酸値が高い状態を高尿酸血症といい、痛風発作の原因となるほか、長期間続くと腎臓にも負担をかけ、腎機能障害(痛風腎)を引き起こすことがあります。
また、腎機能が低下すると尿酸の排泄が悪くなり、尿酸値が上昇することもあります。
尿酸値の基準範囲の目安
| 性別 | 基準値 (mg/dL) | 目標値(高尿酸血症治療ガイドライン) |
|---|---|---|
| 男性 | 3.8~7.0 | 6.0以下 |
| 女性 | 2.5~6.0 |
基準値は検査施設により異なる場合があります。
電解質(ナトリウム、カリウム、クロール)
腎臓は体内の水分量や電解質(ナトリウム、カリウム、クロールなど)のバランスを調整する重要な役割を担っています。腎機能が低下すると、これらの電解質のバランスが崩れることがあります。
特にカリウムは、腎機能が著しく低下すると排泄されにくくなり、血中濃度が上昇(高カリウム血症)することがあります。高カリウム血症は不整脈などの原因となるため注意が必要です。
主な電解質の基準値例
| 電解質 | 一般的な基準値 | 単位 |
|---|---|---|
| ナトリウム (Na) | 138~145 | mEq/L |
| カリウム (K) | 3.6~4.8 | mEq/L |
| クロール (Cl) | 99~109 | mEq/L |
これらの値も、個人の状態や検査施設によって基準が異なります。
シスタチンC
シスタチンCは、体内のほぼ全ての有核細胞で産生されるタンパク質で、腎臓の糸球体でろ過された後、近位尿細管で再吸収・分解されます。血清シスタチンC値は、クレアチニンと同様に腎機能の指標として用いられます。特に、筋肉量の影響を受けにくいため、高齢者や栄養状態が不安定な患者さんの腎機能評価に有用とされることがあります。eGFRの計算にも、クレアチニンの代わりにシスタチンCを用いる方法(eGFRcys)があります。
尿検査との併用
血液検査と合わせて尿検査を行うことで、腎臓の状態をより詳しく評価できます。尿検査では、尿中のタンパク質(タンパク尿)、血液(血尿)、糖などを調べます。タンパク尿や血尿は、腎臓に何らかの障害があるサインである可能性があります。
特にタンパク尿は、CKDの診断基準や進行予測において重要な指標となります。血液検査で腎臓の数値に異常がなくても、尿検査で異常が見つかることもありますので、両方の検査結果を総合的に見ることが大切です。
検査結果を受け取ったらどうすれば良いか
健康診断や病院で腎機能の血液検査を受けた後、結果を受け取った際にどのように対応すれば良いか、不安に思う方もいるかもしれません。ここでは、検査結果の基本的な見方と、その後の対応について説明します。
まずは落ち着いて結果を確認
検査結果の数値が基準範囲から外れていたとしても、すぐに深刻な状態であるとは限りません。体調や検査前の状況(食事、運動など)によって一時的に変動することもあります。
まずは落ち着いて、検査報告書に記載されている基準値とご自身の数値を比較し、どの項目がどの程度基準から外れているのかを確認しましょう。
基準値との比較だけでなく前回値との比較も重要
検査結果を見るときは、基準値との比較だけでなく、可能であれば過去の検査結果(前回値)と比較することが非常に重要です。
腎機能は徐々に変化することが多いため、前回値からの変化の傾向を見ることで、腎機能が安定しているのか、低下傾向にあるのかを把握できます。もし前回値よりも明らかに腎臓の数値が悪化している場合は、注意が必要です。
検査結果の一般的な解釈のポイント
| 確認ポイント | 注目すべき点 | 対応のヒント |
|---|---|---|
| 基準値との比較 | どの項目が基準範囲外か | 一喜一憂せず、他の情報と併せて判断 |
| 前回値との比較 | 数値の変動傾向(改善、横ばい、悪化) | 悪化傾向なら医療機関へ相談 |
| 関連する他の検査項目 | クレアチニンとeGFR、尿検査の結果など | 総合的に腎臓の状態を評価 |
異常値が見られた場合の医療機関受診の目安
血液検査で腎機能に関する数値(クレアチニン、eGFR、尿素窒素など)に異常が見られた場合や、尿検査でタンパク尿や血尿が指摘された場合は、医療機関を受診することを検討しましょう。
特に、eGFRが60mL/分/1.73m²未満の場合や、前回値から明らかに数値が悪化している場合は、腎臓専門医のいる医療機関への相談が勧められます。
医師は、他の検査結果や症状、既往歴などを総合的に判断し、必要な追加検査や治療方針を決定します。
生活習慣の見直しでできること
腎機能の維持・改善のためには、生活習慣の見直しが重要です。検査結果で軽度の異常を指摘された場合や、将来の腎臓病を予防したい場合には、以下のような点に注意してみましょう。
腎臓のために生活習慣で見直せるポイント
- 塩分摂取を控える(高血圧予防)
- タンパク質の過剰摂取を避ける(腎臓への負担軽減)
- 適度な運動を心がける
- 禁煙する
- 適切な水分摂取(医師の指示がある場合はそれに従う)
ただし、すでに腎機能が低下している場合は、食事療法(特にタンパク質、塩分、カリウム制限など)について医師や管理栄養士の専門的な指導が必要です。
自己判断での極端な食事制限は避け、必ず医療機関に相談してください。
よくある質問
腎臓の血液検査や腎機能に関して、患者さんからよく寄せられる質問とその回答をまとめました。
- 腎臓の数値(クレアチニンやeGFR)が悪くても自覚症状がないのはなぜですか?
-
腎臓は予備能力が高い臓器であり、機能がある程度低下するまでは自覚症状が現れにくいという特徴があります。
クレアチニン値が少し高い、あるいはeGFRが少し低いといった初期の段階では、多くの場合、体感できる症状はありません。症状が出始めたときには、腎機能がかなり低下していることも少なくありません。
だからこそ、症状がなくても定期的な血液検査で腎臓の数値をチェックし、腎臓の血液の流れやろ過機能を把握することが早期発見・早期対応のために重要です。
- 血液検査で腎臓の機能が悪いと指摘されました。生活習慣の改善だけで腎臓の機能は元に戻りますか?
-
腎機能低下の原因や程度によります。例えば、脱水や薬剤の影響など一時的な原因で腎機能が悪化した場合、その原因を取り除くことで数値が改善することはあります。
また、高血圧や糖尿病などが原因で腎機能が低下し始めた初期の段階であれば、適切な治療と生活習慣の改善(減塩、血糖コントロール、血圧管理など)によって、進行を遅らせたり、ある程度機能を維持したりすることが期待できます。
しかし、一度障害を受けてしまった腎組織が完全に元通りになるのは難しい場合が多いです。大切なのは、さらなる悪化を防ぎ、残っている腎機能をできるだけ長く保つことです。必ず医師の指示に従い、適切な治療と管理を行ってください。
- 腎臓をいたわるために、食事で特に気をつけるべきことは何ですか?(塩分、タンパク質など)
-
腎臓をいたわる食事の基本は、まず塩分の摂りすぎに注意することです。塩分の過剰摂取は高血圧を引き起こし、腎臓に負担をかけます。
1日の塩分摂取目標量は、一般的には男性7.5g未満、女性6.5g未満とされていますが、高血圧や腎臓病のある方はさらに厳しい制限(例えば6g未満)が必要な場合があります。
また、腎機能が低下している場合は、タンパク質の摂取量を制限することが勧められることがあります。タンパク質は体に必要な栄養素ですが、摂りすぎると老廃物が増え、腎臓への負担が増加します。
ただし、タンパク質制限の程度は腎機能の状態によって異なり、自己判断で行うと栄養不足になる危険性もあるため、必ず医師や管理栄養士の指導を受けてください。カリウムやリンの制限が必要になることもあります。
- 腎臓の血液検査は、どのくらいの頻度で受けるのが望ましいですか?
-
検査を受ける頻度は、個人の年齢、健康状態、腎臓病のリスク(高血圧、糖尿病、家族歴などがあるか)、現在の腎機能の状態によって異なります。
健康な成人であれば、年に1回の健康診断でチェックするのが一般的です。
高血圧や糖尿病などの持病がある方、すでに腎機能の低下を指摘されている方、あるいはeGFRが低い方は、より頻繁な検査(例えば3ヶ月~半年に1回など)が必要になることがあります。
かかりつけ医と相談し、ご自身にとって適切な検査頻度を確認してください。定期的な腎臓の値の確認が、健康維持につながります。
以上
参考文献
ARICI, Mustafa. Clinical assessment of a patient with chronic kidney disease. In: Management of Chronic Kidney Disease: A Clinician’s Guide. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2014. p. 15-28.
MULA-ABED, Waad-Allah S.; AL RASADI, Khalid; AL-RIYAMI, Dawood. Estimated glomerular filtration rate (eGFR): A serum creatinine-based test for the detection of chronic kidney disease and its impact on clinical practice. Oman medical journal, 2012, 27.2: 108.
GOUNDEN, Verena; BHATT, Harshil; JIALAL, Ishwarlal. Renal function tests. In: StatPearls [Internet]. StatPearls Publishing, 2024.
FERGUSON, Michael A.; WAIKAR, Sushrut S. Established and emerging markers of kidney function. Clinical chemistry, 2012, 58.4: 680-689.
LOPEZ-GIACOMAN, Salvador; MADERO, Magdalena. Biomarkers in chronic kidney disease, from kidney function to kidney damage. World journal of nephrology, 2015, 4.1: 57.
EBERT, Natalie, et al. Assessment of kidney function: clinical indications for measured GFR. Clinical kidney journal, 2021, 14.8: 1861-1870.
WASUNG, Michael E.; CHAWLA, Lakhmir S.; MADERO, Magdalena. Biomarkers of renal function, which and when?. Clinica chimica acta, 2015, 438: 350-357.
RADIŠIĆ BILJAK, Vanja, et al. The role of laboratory testing in detection and classification of chronic kidney disease: national recommendations. Biochemia medica, 2017, 27.1: 153-176.
CHAN, Ming-Jen, et al. Breath ammonia is a useful biomarker predicting kidney function in chronic kidney disease patients. Biomedicines, 2020, 8.11: 468.
KAMAL, Azra. Estimation of blood urea (BUN) and serum creatinine level in patients of renal disorder. Indian J Fundam Appl Life Sci, 2014, 4.4: 199-202.