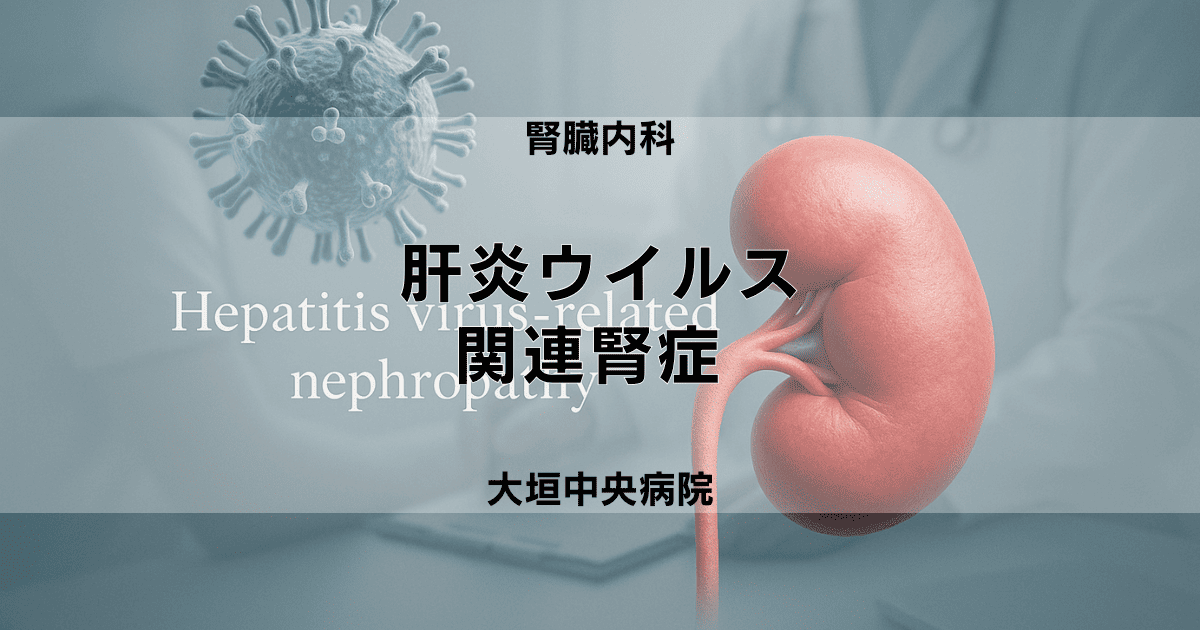肝炎ウイルス関連腎症とは、B型肝炎ウイルスやC型肝炎ウイルスなどの感染によって腎臓の機能が損なわれ、さまざまな症状や合併症が起こされる状態で、肝炎の既往歴やウイルスの持続的な感染が背景にある場合に発症しやすいです。
腎臓は老廃物の排泄や体内の水分・電解質バランスの調整などを担う重要な臓器であり、肝炎ウイルスの影響で腎臓が傷害を受けると、高血圧やむくみなどが進行する危険があります。
肝臓と腎臓は互いに関連しながら全身の代謝や排泄を支えるため、治療ではウイルス学的な対応や腎機能の保護が大切です。
肝炎ウイルス関連腎症の病型
肝炎ウイルス関連腎症の病型は複数に分類され、それぞれウイルスの種類や病理学的特徴が異なり、ウイルスが腎臓に与える影響によって、生じる病変のパターンが変化し、経過や予後にも違いがみられます。
メサンギウム増殖性腎炎
B型肝炎ウイルス感染の長期化などが原因で起こる場合が多く、糸球体のメサンギウム領域が増殖することが特徴です。
メサンギウム領域における免疫複合体の沈着などが引き金となり、尿に血液やタンパクが混ざる血尿や蛋白尿がみられることがあります。比較的軽度から中等度の腎機能異常を示す場合が多いものの、慢性化しやすいため経過観察が重要です。
膜性腎症
C型肝炎ウイルスに関連した病型として知られ、糸球体基底膜に免疫複合体が沈着することが特徴です。
初期には目立った自覚症状が少ないものの、進行すると多量のタンパク尿を伴うネフローゼ症候群を発症して、むくみや血圧上昇が起こることがあります。
治療にはウイルスに対する抗ウイルス療法や、腎炎自体に対する免疫抑制薬の使用を検討します。
クリオグロブリン血症関連腎炎
C型肝炎ウイルス感染後にクリオグロブリン血症(低温下で血清中の免疫グロブリンが沈殿する状態)が生じ、血管炎や糸球体への沈着が起こる場合があり、血管壁への障害が進むと、腎不全を含むさまざまな臓器障害が生じる恐れがあります。
皮膚の紫斑や関節痛など全身症状を呈することもあるため、慎重な診断が必要です。
IgA腎症との合併
B型やC型肝炎ウイルス感染者では、IgA腎症を合併する報告があり、病態の複雑化が懸念され、IgA腎症は、糸球体にIgAが沈着する疾患であり、慢性的な血尿や蛋白尿を呈することが多いです。
肝炎ウイルス関連腎症とIgA腎症の区別が難しい場合もあり、腎生検による病理診断が治療方針の決定に役立ちます。
主な病型
| 病型 | 主なウイルス | 病理学的特徴 | 主症状 |
|---|---|---|---|
| メサンギウム増殖性腎炎 | B型 | メサンギウム領域の増殖 | 血尿、蛋白尿 |
| 膜性腎症 | C型 | 糸球体基底膜への免疫複合体沈着 | ネフローゼ症候群、むくみ |
| クリオグロブリン血症関連腎炎 | C型 | クリオグロブリン血症による血管炎 | 紫斑、関節痛、腎不全 |
| IgA腎症との合併 | B/C型 | IgA沈着+他の病型が重なる場合あり | 血尿、蛋白尿 |
肝炎ウイルス関連腎症の症状
肝炎ウイルス関連腎症では、初期段階では症状が乏しいことも珍しくなく、自覚症状がないまま、定期健診の尿検査で蛋白尿や血尿が見つかったことをきっかけに診断されるケースがみられます。
症状が進行すると、全身のむくみや倦怠感などが目立ってくる場合があり、生活の質に影響が及ぶ恐れが生じます。
蛋白尿と血尿
糸球体の障害によって、尿中にタンパクが多量に排出されることを蛋白尿と呼び、また、血尿も起こる場合があり、目で見てわかるほど色がつく顕血尿と、検査でのみ検出される潜血に分類されます。
蛋白尿や血尿は、腎機能が低下しているサインとされ、肝炎ウイルス感染者には定期的な尿検査が重要です。
むくみや体重増加
ネフローゼ症候群のように大量の蛋白尿が出ると、血液中のアルブミン濃度が低下して、血管内の水分バランスが崩れ、全身の組織に水分が溜まりやすくなり、顔や足などに浮腫が生じ、朝起きたときにまぶたが腫れるなどの症状が表面化します。
むくみが急激に進行すると体重が増加し、動悸や息切れが気になることもあります。
高血圧や倦怠感
腎臓が傷害を受けると、水分やナトリウムの排泄が適切に行われず、血圧が上昇しやすくなり、高血圧は動脈硬化を進行させやすいため、心臓や脳への負担が増える可能性があります。
また、老廃物が排泄されにくくなるため、疲れやすさ、だるさなどの全身倦怠感が続くこともあります。
腎不全の兆候
病状が進むと、慢性腎不全へ移行する可能性があり、腎不全では、尿量の減少や血液中のクレアチニン上昇、貧血、骨密度の低下など、多彩な症状が現れてきます。
頭痛や吐き気などの尿毒症症状が進む場合もあり、日常生活に深刻な支障をきたすため、早期の対応が大切です。
肝炎ウイルス関連腎症の症状は非特異的で、他の腎疾患との鑑別が必要な場合もあるので、些細な体調の変化でも放置せず、定期検査や専門医の受診を検討することで、早期発見と治療につなげやすくなります。
| 主要症状 | 具体的な現れ方 | 影響される病態 |
|---|---|---|
| 蛋白尿・血尿 | 尿検査で指摘 | 糸球体の損傷 |
| むくみ(浮腫) | まぶたや下肢の腫れ | 低アルブミン血症 |
| 高血圧 | 血圧測定値の上昇 | 水・塩分排泄障害 |
| 倦怠感・だるさ | 持続的な疲労感 | 老廃物の排泄低下 |
| 腎不全の兆候 | 尿量減少、吐き気 | 重篤な腎機能低下 |
原因
肝炎ウイルス関連腎症はウイルス感染が原因となる腎障害であり、B型肝炎ウイルスやC型肝炎ウイルスなどが代表的な要因として挙げられます。
B型肝炎ウイルスの特徴
B型肝炎ウイルス感染は、血液や体液を介して伝播し、慢性化すると、肝臓のみならず腎臓を含む他の臓器にも影響が及ぶ可能性があります。
メサンギウム増殖性腎炎のほか、IgA腎症との合併が見られるケースもあり、ウイルスそのものが免疫系に与える刺激や、慢性的な炎症が腎組織を傷つけると考えられています。
C型肝炎ウイルスの特徴
C型肝炎ウイルス感染は、輸血や注射器の使い回しなどの経路によって広がり、近年は新規感染の減少が報告されていますが、慢性化が起こりやすく、気づかないまま長期感染状態に陥る場合が多いです。
クリオグロブリン血症関連腎炎や膜性腎症などを誘発するメカニズムが解明されつつありますが、個人差が大きく、一部の患者さんだけが腎障害を発症することが課題として認識されています。
免疫複合体と腎障害の関連
肝炎ウイルスに対する免疫反応が引き金となり、体内にウイルス抗原と抗体が結合した免疫複合体が作られ、血液を介して糸球体に沈着し、炎症を起こして腎組織を傷害します。
免疫複合体の形成量や体内の排泄能力、炎症制御機構などは個人差が大きいため、同じウイルス感染でも腎症の発症にばらつきがあります。
生活習慣や基礎疾患の影響
肥満や糖尿病、高血圧などの基礎疾患があると、腎臓にかかる負担が増加し、肝炎ウイルス感染が加わると、免疫・代謝機能の破綻が複合的に進行し、腎症発症のリスクが高くなると考えられます。
さらにアルコールの過剰摂取や喫煙なども、肝臓と腎臓の機能低下を促す要因の一つです。
肝炎ウイルス関連腎症の原因にはウイルス感染が中心にあるものの、そこに免疫反応の過剰や基礎疾患、生活習慣などが相乗的に作用すると捉えられています。
肝炎ウイルス感染による腎障害が起こりやすい背景として、以下のようなリスク因子が取り上げられることが多いです。
- 長期間のウイルスキャリア状態
- 高血圧や糖尿病などの持病
- 不規則な食事や過剰なアルコール摂取
- 肥満や喫煙習慣
- ストレスや睡眠不足
肝炎ウイルス関連腎症の主な原因
| 原因・要因 | 具体的な内容 | 関連する病態 |
|---|---|---|
| B型肝炎ウイルス感染 | 血液や体液から感染し慢性化しやすい | メサンギウム増殖性腎炎、IgA腎症との合併 |
| C型肝炎ウイルス感染 | 主に血液を介して感染、慢性化しやすい | クリオグロブリン血症関連腎炎、膜性腎症 |
| 免疫複合体の沈着 | ウイルス抗原と抗体が結合して糸球体へ沈着 | 炎症・組織傷害 |
| 生活習慣の乱れ | アルコール過剰、喫煙、肥満など | 腎機能の悪化が加速 |
| 高血圧・糖尿病などの基礎疾患 | 血管や代謝系に負担がかかる | 腎障害が重複しやすい |
肝炎ウイルス関連腎症の検査・チェック方法
肝炎ウイルス関連腎症を疑う場合、肝機能と腎機能の両面から検査を行い、総合的に病態を把握する必要があり、血液検査や尿検査をはじめ、超音波検査や腎生検など、さまざまな検査を組み合わせることで正確な診断に近づきます。
血液検査
血中のB型肝炎ウイルスマーカー(HBs抗原、HBe抗原など)やC型肝炎ウイルスマーカー(HCV抗体、HCV-RNAなど)を調べることで、肝炎ウイルス感染の有無や活動性を判別します。
さらに腎機能の指標として、血中クレアチニンや尿素窒素(BUN)の値、推定GFR(eGFR)を測定し、腎機能の程度を確認し、炎症や免疫反応の程度を把握するために、CRPなどの炎症マーカーも参考になります。
尿検査
蛋白尿や血尿があるかどうかは、最も手軽に確認できる指標です。
定性検査で糖や潜血の有無を調べるだけでなく、定量検査で尿たんぱく定量や尿アルブミン排泄量を測定し、腎障害の程度を推測します。
場合によっては尿沈渣を顕微鏡で観察し、円柱(タンパクが固まったもの)や赤血球の形態などを詳細に確認することもあります。
画像検査
腹部エコー(超音波検査)では、肝臓や腎臓の大きさや形態、腫瘤の有無などを確認し、肝炎ウイルスによって肝臓に慢性的なダメージがある場合、肝硬変へ進行している可能性も考慮して、肝臓表面の状態や脾臓の肥大などもチェックします。
腎臓に結石や腫瘍などの異常がないかどうかを見極めるうえでも、超音波検査は大切です。
腎生検
尿や血液の検査結果から腎症の原因やタイプを判断できない場合、あるいは治療方針を確定するために腎生検を行うことがあり、腰の部分から細い針を刺して腎臓の組織を採取し、顕微鏡で病理学的に評価します。
どのような免疫複合体が沈着しているか、炎症の程度はどのくらいかなど、正確な診断に欠かせない情報を得られますが、侵襲的な検査であるため、患者さんの全身状態や感染リスクを考慮しながら実施するかどうかを判断することが重要です。
| 検査種類 | 主な目的・測定項目 | 得られる情報 |
|---|---|---|
| 血液検査 | HBs抗原/HCV抗体、クレアチニン、BUN等 | ウイルス感染の有無・腎機能障害の程度 |
| 尿検査 | 尿蛋白、尿潜血、尿沈渣 | 尿異常(蛋白尿・血尿)・円柱の有無 |
| 画像検査 | 腹部エコーなど | 肝臓・腎臓の形態、肝硬変や腫瘍の有無など |
| 腎生検 | 腎組織の病理検査 | 病型の確定、免疫複合体や炎症の程度 |
肝炎ウイルス関連腎症の治療方法と治療薬について
肝炎ウイルス関連腎症の治療は、ウイルスそのものに対する治療と、腎障害に対する治療の二つの軸があります。
抗ウイルス療法
B型肝炎ウイルスに対しては、エンテカビルやテノホビルなどの経口薬を用いてウイルス量を抑制し、肝臓と腎臓への負担を和らげることが目的です。
C型肝炎ウイルスには、直接作用型抗ウイルス薬(DAA)と呼ばれる経口薬を組み合わせて投与し、ウイルスの複製を抑えることで肝炎の進行や腎症の悪化を防ぎ、抗ウイルス療法の効果が出れば、腎機能の改善や病状の安定が期待できます。
免疫抑制療法
クリオグロブリン血症関連腎炎や、重症の膜性腎症など、免疫機構が強く関与する病態には、ステロイド(プレドニゾロン)や免疫抑制薬(シクロホスファミド、シクロスポリンなど)を使用する場合があります。
免疫反応を抑えて腎臓への自己免疫性ダメージを軽減し、蛋白尿や炎症を抑制する狙いがありますが、免疫抑制薬を使うことでウイルスが再活性化する可能性があり、肝炎悪化のリスクに注意しながらの投与が必要です。
血漿交換療法
クリオグロブリン血症で重症の血管炎や腎機能障害が進行しているケースでは、血漿交換療法が検討され、血液から病的なたんぱく質や免疫複合体を取り除く目的で行い、腎障害だけでなく全身症状の緩和にも役立ちます。
一方で、侵襲的な治療であり、頻回の実施が必要になる場合もあるため、患者の全身状態や合併症の有無を踏まえて検討することが多いです。
生活習慣の改善と対症療法
適切な食事管理や塩分制限、適度な運動などは、腎臓にかかる負担を減らし、血圧や血糖値を安定させるうえで大切です。
利尿薬を用いてむくみを改善したり、降圧薬を使用して高血圧をコントロールしたりするなど、対症療法も組み合わせて行います。
肝炎ウイルス関連腎症は長期戦になる場合が多いため、日常生活の中でも継続的に治療効果を高める取り組みが重要です。
肝炎ウイルス関連腎症では、ウイルス治療と腎機能保護の両方を意識しながら治療を進める必要があり、薬剤選択と生活改善を組み合わせ、悪化を防ぎながら腎臓と肝臓の状態を観察していきます。
| 治療法・薬剤 | 対象とする病態 | 主な効果 |
|---|---|---|
| 抗ウイルス療法(エンテカビル、DAAなど) | B型・C型肝炎ウイルスの持続感染 | ウイルス増殖の抑制 |
| 免疫抑制療法(ステロイドなど) | クリオグロブリン血症関連腎炎、膜性腎症など | 自己免疫反応の抑制 |
| 血漿交換療法 | クリオグロブリン血症で重症化した血管炎や腎障害 | 病的たんぱく質の除去 |
| 対症療法(降圧薬、利尿薬など) | 高血圧、むくみ、タンパク尿など | 血圧コントロール、浮腫改善 |
肝炎ウイルス関連腎症の治療期間
肝炎ウイルス関連腎症の治療期間は、ウイルスの活動性や腎障害の重症度、患者さんの背景因子などによって大きく異なります。慢性肝炎を合併している場合は、長期にわたる治療や定期的なフォローアップが必要となるケースが多いです。
抗ウイルス療法の期間
B型肝炎ウイルスに対しては、エンテカビルやテノホビルなどを数年にわたって服用し、ウイルス量を持続的に抑制するアプローチが一般的です。
C型肝炎ウイルスでは、直接作用型抗ウイルス薬(DAA)の投与期間は通常8~12週間程度が目安になる場合が多いですが、腎機能や肝硬度の程度に合わせて変更する可能性があります。
ウイルスが陰性化した後も、再燃を防ぐために一定期間の経過観察を要することがあります。
免疫抑制療法の期間
ステロイドや免疫抑制薬を使った治療は、腎炎の炎症が治まり、蛋白尿などの臨床症状が落ち着くまで継続することが必要です。
期間は数カ月から1年以上に及ぶことがあり、減量のタイミングや中止の可否を判断するには、定期的な検査データと患者さんの状態を照合し、急に中止すると再燃のリスクがあるため、慎重に減量していきます。
慢性腎臓病としての管理期間
肝炎ウイルス関連腎症が慢性化した場合、慢性腎臓病(CKD)としての管理が続くことになり、定期的な血液検査や尿検査で腎機能をモニタリングし、進行を食い止めるために生活習慣の見直しや薬物療法を続けることが重要です。
腎機能がある程度保たれている場合でも、ウイルスの再活性化や別の合併症を起こさないよう、中長期的なフォローが必要になります。
個人差と予後
治療期間は個人差が大きく、生活習慣や年齢、合併症の有無などで大きく左右されます。
腎機能がすでに大きく低下している患者さんでは、腎代替療法(透析)の適応を検討する段階に至ることもありますが、早期発見による治療介入ができれば、比較的長期にわたり腎機能を保つ可能性が高まります。
肝炎ウイルス関連腎症は、治療期間が長期化することが珍しくなく、ウイルス治療と腎機能の保護を両立するうえで、定期的な通院と検査を欠かさず行うことが、良好な経過を目指すうえで大切です。
治療期間に関する注意点
- 治療に対する反応を確認するため、数週間から数カ月ごとに血液や尿の検査を受ける
- ステロイドなどの薬剤は主治医の指示に従って段階的に減らす
- ウイルスマーカーが陰性化しても、しばらくは再燃防止のためのモニタリングが必要
治療の期間と観察の目安
| 治療プロセス | 目安となる期間 | 留意点 |
|---|---|---|
| 抗ウイルス療法(B型) | 数年スパンで継続服用 | ウイルス量を抑えながら腎機能を守る |
| 抗ウイルス療法(C型) | 8~12週間程度が主流 | 腎機能や肝硬度によって期間を延長する場合有 |
| 免疫抑制療法 | 数カ月~1年以上 | 漸減しながら再燃リスクを低減する |
| 慢性腎臓病としての管理 | 長期(数年~継続的) | CKDの進行予防、肝炎の再燃チェック |
副作用や治療のデメリットについて
肝炎ウイルス関連腎症の治療では、肝炎ウイルスを抑制する抗ウイルス薬や、免疫反応を制御する免疫抑制薬などが使用されるため、それぞれの薬剤に特有の副作用やデメリットを理解しておく必要があります。
抗ウイルス薬の副作用
B型肝炎ウイルスに対するエンテカビルやテノホビル、C型肝炎ウイルスに対する直接作用型抗ウイルス薬(DAA)などは、多くの患者に有効とされていますが、消化器症状や頭痛、倦怠感などの副作用が生じる可能性があります。
まれに重篤な肝機能障害やアレルギー反応を起こす報告もあるため、投与開始後は血液検査などで副作用の有無を丁寧にチェックすることが必要です。
免疫抑制薬の副作用
ステロイド(プレドニゾロン)やシクロホスファミド、シクロスポリンなどの免疫抑制薬は、自己免疫性の炎症を抑えるうえで役立ちますが、感染症にかかりやすくなったり、血糖値の上昇や骨粗鬆症などが進行したりするデメリットがあります。
ステロイドは長期使用により満月様顔貌(ムーンフェイス)や体重増加、精神的な不安定などが起こるケースもあり、注意が必要です。
| 薬剤 | 主な副作用・注意点 | 補足 |
|---|---|---|
| 抗ウイルス薬(エンテカビルなど) | 消化器症状、頭痛、倦怠感、肝機能障害 | 定期的な血液検査で早期発見が重要 |
| 免疫抑制薬(ステロイドなど) | 易感染性、骨粗鬆症、糖尿病悪化、精神面の不安定化 | 用量調整と副作用モニタリングが重要 |
| 降圧薬・利尿薬など | 血圧変動、電解質異常、脱水 | 血圧と血液検査の定期評価が必要 |
肝炎ウイルス関連腎症の保険適用と治療費
以下に記載している治療費(医療費)は目安であり、実際の費用は症状や治療内容、保険適用否により大幅に上回ることがございます。当院では料金に関する以下説明の不備や相違について、一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。
抗ウイルス療法の費用目安
エンテカビル1カ月分の自己負担額の目安は3,000円~5,000円程度になるケースが多いです。
C型肝炎ウイルスに対する直接作用型抗ウイルス薬(DAA)は薬価が比較的高額ですが、多くの場合は保険適用対象であり、1カ月分の自己負担はおおむね1万円前後から2万円程度になります。
免疫抑制療法の費用目安
ステロイドは比較的安価ですが、シクロスポリンやタクロリムスなどの免疫抑制薬はやや高額になる場合があります。
それでも保険適用後の自己負担額は数千円から1万円程度になるケースが多いです。
検査費用
診察時には、血液検査や尿検査、画像検査などを組み合わせて行うため、1回の外来受診で数千円から1万円程度の費用がかかる場合があります。
腎生検を行う場合は入院や検査費用がかさみ、保険適用でも10万円以上の請求が発生することがあります。
主な治療内容と自己負担の目安
| 治療内容 | 自己負担の目安(3割負担) | コメント |
|---|---|---|
| 抗ウイルス療法(B型) | 月3,000円~5,000円前後 | エンテカビルなどの経口投薬 |
| 抗ウイルス療法(C型) | 月1万円~2万円程度 | DAAが中心で薬価が高め |
| 免疫抑制療法(ステロイドなど) | 数千円~1万円程度/月 | 薬剤の種類・用量で変動 |
| 検査費用(外来) | 1回あたり数千円~1万円程度 | 血液・尿・画像検査の組み合わせで変動 |
| 腎生検(入院) | 10万円以上になることもある | 病院や個室の利用状況で差が出る |
以上
参考文献
Kusakabe A, Tanaka Y, Kurbanov F, Goto K, Tajiri H, Murakami J, Okuse C, Yotsuyanagi H, Joh T, Mizokami M. Virological features of hepatitis B virus‐associated nephropathy in Japan. Journal of medical virology. 2007 Sep;79(9):1305-11.
Ogawa E, Furusyo N, Azuma K, Nakamuta M, Nomura H, Dohmen K, Satoh T, Kawano A, Koyanagi T, Ooho A, Takahashi K. Elbasvir plus grazoprevir for patients with chronic hepatitis C genotype 1: a multicenter, real-world cohort study focusing on chronic kidney disease. Antiviral Research. 2018 Nov 1;159:143-52.
Lai AS, Lai KN. Viral nephropathy. Nature Clinical Practice Nephrology. 2006 May 1;2(5):254-62.
Masset C, Le Turnier P, Bressollette-Bodin C, Renaudin K, Raffi F, Dantal J. Virus-associated nephropathies: a narrative review. International Journal of Molecular Sciences. 2022 Oct 10;23(19):12014.
Lai KN. Hepatitis-related renal disease. Future Virology. 2011 Nov 1;6(11):1361-76.
Sansonno D, Gesualdo L, Manno C, Schena FP, Dammacco F. Hepatitis C virus‐related proteins in kidney tissue from hepatitis C virus‐infected patients with cryoglobulinemic membranoproliferative glomerulonephritis. Hepatology. 1997 May;25(5):1237-44.
Mac-Moune Lai F, To KF, Wang AY, Choi PC, Szeto CC, Li PK, Leung CB, Lai KN. Hepatitis B virus–related nephropathy and lupus nephritis: morphologic similarities of two clinical entities. Modern Pathology. 2000 Feb;13(2):166-72.
Kamar N, Rostaing L, Alric L. Treatment of hepatitis C-virus-related glomerulonephritis. Kidney international. 2006 Feb 1;69(3):436-9.
Khedmat H, TAHERI S. Hepatitis B Virus-associated Nephropathy An International Data Analysis.
Fabrizi F, Martin P, Cacoub P, Messa P, Donato FM. Treatment of hepatitis C-related kidney disease. Expert opinion on pharmacotherapy. 2015 Aug 13;16(12):1815-27.