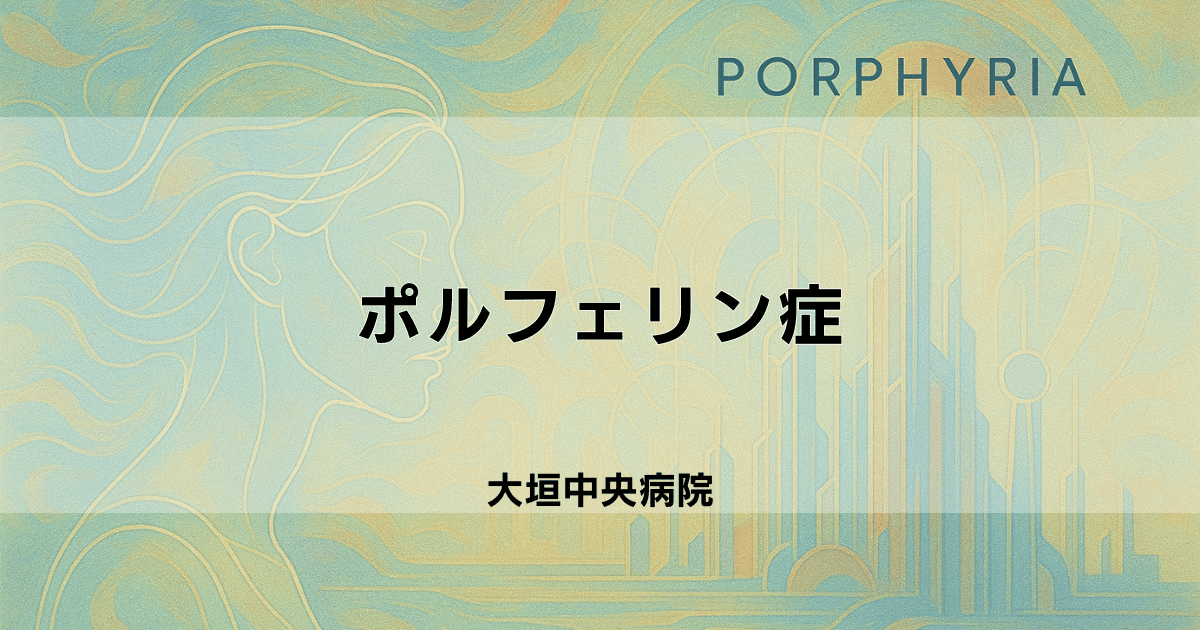ポルフェリン症とは、赤血球のヘモグロビン合成に深く関与するポルフェリン代謝の異常によって起こる疾患の総称であり、腹痛や神経症状、皮膚症状など多岐にわたる症状がみられることが特徴です。
原因には遺伝的要因と後天的要因があり、なぜ起こるのかを知ることで予防や適切な治療につなげられます。
検査や治療法もさまざまで、状態に応じて投薬や生活習慣の改善などを組み合わせ、症状を軽減していきます。
ポルフェリン症の病型
さまざまな病型が存在するポルフェリン症は、主に肝臓でのポルフェリン代謝が関わる「肝性ポルフェリン症」と、骨髄での異常が主な要因となる「赤芽球性ポルフェリン症(骨髄性ポルフェリン症)」に大きく分けられます。
肝性ポルフェリン症とは
肝性ポルフェリン症は、主に肝臓での酵素の異常によってポルフィリンやその前駆体が過剰に産生され、神経系や消化器系、皮膚などにさまざまな症状があらわれるタイプです。
なかでも急性発作を特徴とする「急性間欠性ポルフィリン症」や「バリアゲートポルフィリン症」、皮膚症状が顕著な「晩発性皮膚ポルフィリン症」などが知られます。
医師は、どの酵素がどの程度障害を受けているかを正確に把握するために詳しい血液検査や尿検査を行いながら、適切な治療に導きます。
骨髄性ポルフェリン症(赤芽球性ポルフェリン症)とは
骨髄性ポルフェリン症は、骨髄での造血過程に関わる酵素が正常に働かず、ヘモグロビン合成の途中段階でポルフェリンが蓄積することで症状が進むものです。
「先天性赤芽球性ポルフィリン症(Erythropoietic Protoporphyria:EPP)」が代表的で、皮膚が光に過敏になり、わずかな日光でも痛みや発赤が生じます。
幼児期から光過敏症状に悩まされるケースがあり、日常生活では屋外活動に制約が出ることも少なくありません。
病型と主な症状のまとめ
ポルフェリン症には大きく肝性と骨髄性があり、それぞれに代表的な病型が複数あります。
| 病型 | 代表的な種類 | 主な症状例 |
|---|---|---|
| 肝性ポルフェリン症 | 急性間欠性ポルフィリン症(AIP) | 突然の腹痛、神経障害、吐き気 |
| バリアゲートポルフィリン症(VP) | 光線過敏、皮膚水疱、神経症状 | |
| 晩発性皮膚ポルフィリン症(PCT) | 光線過敏、皮膚のびらん、色素沈着 | |
| 骨髄性ポルフェリン症(赤芽球性) | 先天性赤芽球性ポルフィリン症 | 光線過敏、皮膚の腫れや痛み、血液の障害など |
ポルフェリン症の症状
ポルフェリン症の症状は、神経系、消化器系、皮膚など多岐にわたって現れます。
ポルフェリンやその前駆体が特定の組織に蓄積したり、あるいは酵素異常による毒性物質が産生されたりすることで体のいろいろな機能に影響を及ぼすためです。
神経症状
急性間欠性ポルフィリン症などの肝性ポルフェリン症では、神経症状が中心に現れることが多く、症状は、四肢や体幹部の筋力低下、しびれや痛みを感じる末梢神経障害、時には意識障害などです。
また、自律神経系が影響を受けると、血圧の変動や頻脈、不整脈などが生じたり、尿閉や便秘などの排泄障害が起こったりします。
神経症状の例
・手足の脱力感や麻痺感
・しびれや感覚異常
・めまい、ふらつき
・便秘、排尿障害、頻脈など
腹痛や吐き気
急性型の肝性ポルフェリン症では、激しい腹痛を起こしやすい傾向にあり、腹痛は急に始まり、差し込むような痛みが長時間続くことも珍しくありません。
吐き気や嘔吐を伴うことも多く、食事が摂れないほど苦痛を感じ、入院を検討する場面も出てきます。
皮膚症状
皮膚症状は骨髄性ポルフェリン症でも肝性ポルフェリン症でも起こりうる症状ですが、病型によって症状の程度やあらわれ方が異なります。
とくに晩発性皮膚ポルフィリン症や先天性赤芽球性ポルフィリン症では、日光や人工的な紫外線への過敏反応によって皮膚に痛みや水疱、びらんなどが出現しやすいです。
小さな摩擦や軽度の日焼けでも大きな炎症へ発展する例があるため、日常生活では日傘や日焼け止めなどの紫外線対策が重要になります。
| 皮膚症状の主な特徴 | 内容 |
|---|---|
| 光線過敏 | 日光や紫外線での痛み、赤み、水疱、腫れ |
| 皮膚の色素沈着 | 慢性的な炎症による色素沈着、シミ様の変化 |
| 皮膚のびらん | 水疱が破れたあとにかさぶたや潰瘍ができる |
| 爪や毛髪の異常 | 重度になると爪の変形や毛髪の抜け毛などがみられる場合もある |
疲労感や全身倦怠感
ポルフェリン症は慢性的に体調不良を起こす場合があり、疲労感や全身倦怠感につながり、神経症状や腹痛、皮膚障害などのストレスが重なると、さらに症状が増悪する恐れが出てきます。
特に急性発作型で激しい腹痛や吐き気を経験した後は、体力の消耗が激しいため、しばらくは脱力感が続くことがあります。
原因
ポルフェリン症は、一部の遺伝的要因と、後天的要因が組み合わさって発症すると考えられています。
遺伝的要因
多くのポルフェリン症は、常染色体優性遺伝または劣性遺伝の形をとることがあります。
家族の中に同じ病型の患者がいる場合、遺伝的リスクを考える必要がありますが、発症には個人差が大きいため、遺伝子異常を持っていても症状が出にくい場合もあります。
遺伝子変異がある可能性が高い場合
・家系内に同じ病名の人物がいる
・若年期から光線過敏や激しい腹痛などの特徴的症状を訴えている
・原因不明の神経症状を呈する家族がいる
後天的要因
後天的要因としては、肝機能への負担となるアルコール多飲やホルモン剤の使用、経口避妊薬などが発症を誘発する引き金になることがあると指摘されています。
さらに、喫煙やストレス過多、過度の鉄分摂取(サプリメントなど)も負荷となって、病型によっては発作が起こりやすくなります。
薬剤によってはポルフィリン合成経路に影響するものがあり、自己判断での服用や中止は避けることが望ましいです。
| 後天的要因 | 具体的な例 | 影響の仕組み |
|---|---|---|
| アルコール | 多量の飲酒 | 肝負荷の増大、酵素活性への抑制 |
| ホルモン | 経口避妊薬、ステロイドホルモンなど | ホルモン変動が酵素活性に干渉 |
| 薬剤 | バルビツール酸系薬、抗てんかん薬など | ポルフェリン合成経路を刺激または阻害 |
| 鉄分 | 過度なサプリ摂取 | ポルフェリンの合成増進、蓄積のリスク上昇 |
| ストレス | 過労、精神的負荷など | 自律神経やホルモンバランスの乱れが酵素活性に影響 |
後天的要因は生活習慣や薬の選択である程度コントロールできる場合もあるため、医師は問診や検査結果を踏まえながら、日常の注意点を伝えます。
酵素異常とポルフェリン蓄積のメカニズム
ポルフェリン症では、ヘム合成経路における特定の酵素活性が低下したり、部分的に失われたりし、ポルフィリンやその前駆体が体内に蓄積しやすくなり、ときに毒性を持った物質が体を循環して様々な臓器にダメージを与えます。
肝性ポルフェリン症は肝臓の酵素異常が主体となり、骨髄性ポルフェリン症は骨髄内での酵素障害が主体となりますが、いずれの場合も、どの段階の酵素が異常なのかが病型や症状を決める鍵です。
ヘム合成経路の簡単な流れ
- グリシンとサクシニルCoAからアミノレブリン酸(ALA)生成
- ALAが合体してポルフォビリノーゲン(PBG)生成
- PBGが連結し種々の変換を経てポルフェリン体となる
- ポルフェリンに鉄が組み込まれてヘムとなる
ステップのどこかで異常が起きると、前駆体が蓄積して神経毒性や光過敏などの原因となります。
予防や再発防止の観点
遺伝的要因は変えられませんが、後天的要因をできる限り避けることは再発を防ぐうえで大切です。
アルコールや特定の薬の使用を控える、過度なストレスを避ける、ホルモンバランスへの配慮をするなど、日常的な管理を行うことで症状の頻度や重症度を下げることが期待できます。
生活習慣の改善は大きな負担に感じるかもしれませんが、発作のリスクを抑えるためには有効な手段の1つです。
ポルフェリン症の検査・チェック方法
ポルフェリン症と診断するためには、血液や尿、便などに含まれるポルフェリン類やその前駆体であるアミノレブリン酸(ALA)、ポルフォビリノーゲン(PBG)の濃度を調べることが基本です。
また、遺伝性が疑われる場合は遺伝子検査、骨髄性ポルフェリン症を疑う場合は骨髄検査など、発症の背景や症状に応じた検査が追加で行われることもあります。
尿検査と血液検査
ポルフェリン症の疑いがある場合、まず尿検査と血液検査が実施されます。尿検査では主にPBGやALAの量を測定し、血液検査ではポルフェリンや肝機能の状態などを確認します。
急性発作時や症状が強いときは、これらの値が大きく変動することが多いため、診断の大きな目安です。
また、尿の色や光に当てた際の変化(光で赤紫色に変化する場合があるかなど)も観察することで、ポルフェリン症特有の特徴を掴めます。
| 検査項目 | 意義 |
|---|---|
| 尿中PBG | 急性発作時には著しく上昇 |
| 尿中ALA | PBG同様、急性発作の指標となる |
| 血液中ポルフェリン | 病型によって種類や濃度が異なり、病型特定のヒントになる |
| 肝機能検査 | 肝性ポルフェリン症の有無を判断する際に活用 |
遺伝子検査
家族内発症や特有の症状から強く遺伝性が疑われる場合、遺伝子検査によって特定の酵素遺伝子の変異を調べることがあります。
遺伝子検査によって異常が確認できた場合は、本人や家族への遺伝カウンセリングを行い、発症の予防策や今後の管理についてアドバイスします。
ただし、遺伝子検査には高額な費用がかかる場合があるため、まずは血液や尿の検査で臨床症状と合致するかどうかを調べ、それでも判断が難しい場合に検討されることが多いです。
遺伝子検査を行うメリット
・病型特定の精度が上がる
・将来の発症リスク把握に役立つ
・家族内ケアの参考になる
便中ポルフェリン検査
便に含まれるポルフェリン量を測定することも、特定のポルフェリン症の診断に有効で、肝性ポルフェリン症の中には、便中に特定のポルフェリンが増加するタイプがあり、それが病型の診断につながる場合があります。
血液や尿の検査だけでは十分に判別できない際、便検査を追加して診断の補助を行います。
この検査は症状が落ち着いているときよりも、発作時や症状が強まっている時期のほうが異常値が検出されやすい傾向があるため、複数回にわたって検査することが大切です。
骨髄検査
骨髄性ポルフェリン症が疑われる場合は、骨髄検査によって造血過程を直接調べることがあり、骨髄検査では骨髄液の細胞を採取し、顕微鏡レベルで形態や酵素活性を調べることで、赤芽球性ポルフェリン症の有無や重症度を推定します。
この検査は負担が大きいため、まずは非侵襲的な血液・尿・便検査で総合的に判断し、必要性が高いと判断されたときに医師が実施を提案します。
治療方法と治療薬について
ポルフェリン症の治療は、急性発作の有無や症状の種類、病型などを考慮して、さまざまな選択肢から組み合わせるアプローチを取ります。急性期における発作時の治療から、日常生活での再発予防までを視野に入れることが必要です。
急性発作時の対症療法
急性発作(特に急性間欠性ポルフィリン症やバリアゲートポルフィリン症など)では、激しい腹痛や神経症状が出現するため、まず痛みや吐き気などを抑えることが優先課題です。
医師は鎮痛薬や制吐薬などを使用して症状を和らげ、必要に応じて点滴によるブドウ糖の補給や電解質のバランス調整を行います。
また、発作を長引かせる原因になる恐れがある薬剤は使用を避け、バルビツール酸系などは、ポルフェリン合成を刺激して症状を悪化させる可能性があるため、代替薬の選択が検討されます。
急性発作時に用いられることのある対症療法
・ブドウ糖の点滴
・鎮痛薬や制吐薬の投与
・水分と電解質の補給
・安静と十分な休息
ヘミン製剤による治療
急性肝性ポルフェリン症に対しては、静脈注射によるヘミン製剤の投与が代表的で、ヘミンはヘム合成経路のフィードバックを抑制する働きがあり、体内でのポルフィリンやALAなどの過剰生成を抑えることが目標です。
発作時には早期にヘミンを投与し、急性期の神経症状や腹痛の進行を抑えることが期待できます。
医師は患者の状態を見ながら投与回数や投与速度を調整し、過剰な鉄過負荷に注意しながら治療を進め、ヘミンは効果が高い反面、静脈注射での投与が必要であり、通院や入院が伴う場合があります。
| ヘミン製剤治療のポイント | 内容 |
|---|---|
| 投与経路 | 主に静脈点滴 |
| 投与のタイミング | 発作症状が現れたとき、または重症化の予防 |
| 注意点 | 鉄過剰を招く恐れ、血管痛に配慮が必要 |
| 期待される効果 | ポルフィリンやALAの産生を抑え、症状を緩和する |
生活習慣指導と光線対策
皮膚症状が主体となる場合や、再発を予防したい場合には、生活習慣の改善と光線対策が不可欠です。
光線過敏による皮膚障害が生じるタイプでは、外出時の紫外線対策を徹底し、日傘や帽子、衣服などで肌を覆うことや、日焼け止めクリームの使用を日常的に行います。
また、アルコール摂取や特定の薬剤の使用を控え、ストレスをうまくコントロールするなど、発作や症状の引き金になりそうな要因を少しずつ減らしていくことが大切です。
皮膚症状対策のチェックリスト
・日焼け止めや日傘、帽子などの活用
・屋外活動の時間帯を見直す(直射日光の強い時間を避ける)
・肌を擦れやすい衣類は避ける
・保湿やスキンケアで皮膚のバリアを維持
他の治療薬や補助療法
急性発作時に有効なヘミン製剤以外にも、症状や病型に応じて補助的に利用される薬剤があり、骨髄性ポルフェリン症ではビタミンDやβ-カロテンなどが光過敏症の軽減を目的に用いられるケースがあります。
また、貧血を合併する場合には鉄剤が使われることがありますが、肝性ポルフェリン症では鉄分が発作を誘発することもあるため、使用の可否を十分に検討することが重要です。
ポルフェリン症の治療期間
ポルフェリン症の治療期間は、病型や症状の重症度、発作の頻度によって違います。
急性発作型では発作期と無症状期の繰り返しが特徴的であるため、発作期には入院治療が必要となるケースもありますし、症状が落ち着いている間は通院でのフォローアップにとどめることもあります。
皮膚症状が中心の病型では長期的な紫外線対策や生活習慣の管理が必要で、完治を目指すというよりは症状のコントロールを続けるイメージを持つとよいでしょう。
急性期治療の期間
急性間欠性ポルフィリン症などで発作を起こした場合、状態によっては入院を数日から1~2週間ほど行い、点滴やヘミン製剤を使用した集中的な対症療法を行います。
激しい腹痛や神経症状があるときは、鎮痛薬や制吐薬などで症状を抑えながら、血中の毒性物質濃度が落ち着くまで経過を観察することが大切です。
発作が治まっても、急に投薬を中止すると再度悪化する恐れがあるため、医師は徐々に薬を減らすタイミングを見極めながら治療の継続を指示します。
| 急性期治療のステップ | 期間の目安 |
|---|---|
| 入院による集中治療 | 数日~1週間以上の場合もある |
| 痛みや嘔吐への対症療法 | 症状の改善に合わせて逐次調整 |
| ヘミン製剤投与 | 発作の程度に応じて数日~1週間 |
| 退院後のフォローアップ | 外来診察や検査を定期的に実施 |
再発予防のための期間
急性発作型の場合、発作を一度経験すると、その後再発を繰り返すリスクを抱えることになり、再発を防ぐためには、アルコールや薬剤の使用制限、ストレスコントロールなどの生活習慣指導を長期的に守ることが望ましいです。
再発を認めずに一定期間(たとえば数か月~半年)を過ごしたとしても、再発リスクは完全には消えないため、自己管理を継続しつつ定期的に医療機関で検査を受ける流れとなります。
再発予防の主な取り組み
・引き金となる薬剤の使用を避ける
・アルコール摂取を控える
・ホルモンバランスへの配慮(場合によっては内分泌科との連携)
・ストレスや疲労の蓄積を軽減する
・医師による定期的な血液・尿検査
皮膚症状中心の病型の管理期間
晩発性皮膚ポルフィリン症や先天性赤芽球性ポルフィリン症など、皮膚症状が中心となる病型では、光線過敏対策を含めた生活習慣の管理が欠かせないため、基本的には長期管理が必要です。
特に先天性のタイプでは幼少期から症状が出る場合もあり、紫外線対策を一生の課題として考えるケースがあります。
長期的なフォローアップ
ポルフェリン症は完治が難しいケースが多い反面、適切な管理や治療を続けることで日常生活を維持できる可能性が十分にあります。
そのため、一定期間症状が落ち着いていても、定期受診を行い、血中や尿中のポルフェリン量や肝機能、体調の変化などを総合的に評価することが大切です。
発作の兆候を早めにキャッチし、ヘミン製剤や対症療法を適切に導入できれば、重症化を防げる可能性が高まります。
ポルフェリン症薬の副作用や治療のデメリットについて
ポルフェリン症の治療に用いられるヘミン製剤や、症状をコントロールするための補助薬には、副作用やデメリットもあります。
ヘミン製剤の副作用
ヘミン製剤は急性肝性ポルフェリン症の発作時に効果的ですが、いくつかの注意点があり、ヘミンには鉄分が含まれ、過剰な投与が続くと体内の鉄過多(ヘモクロマトーシスのリスク)につながる可能性が指摘されています。
また、点滴静脈注射を行う際に血管痛が生じることがあり、投与速度や希釈方法の調整が必要です。
さらに、一部の患者さんでは一過性の肝機能障害や頭痛、発疹などがみられる場合もありますので、治療中は定期的に血液検査を実施して副作用や合併症の兆候を確認します。
| ヘミン製剤の主な副作用 | 内容 |
|---|---|
| 鉄過剰リスク | 長期投与や高用量投与で注意が必要 |
| 血管痛 | 点滴速度に注意し、希釈を工夫 |
| 肝機能障害 | 定期検査で早期発見に努める |
| 発疹、頭痛など | 軽度であれば経過観察 |
その他の薬剤によるリスク
骨髄性ポルフェリン症で使われることがあるβ-カロテンやビタミンDサプリメントなどは比較的安全性が高いとされますが、過剰摂取すれば肝機能や脂質代謝に影響が出る可能性があります。
貧血対策で鉄剤を投与する場合も、肝性ポルフェリン症と併発している場合には症状の悪化リスクがあるため、医師の指示に従って用量を厳守することが大切です。
また、神経症状を抑えるために処方される鎮痛薬や抗不安薬なども、依存性や眠気といった副作用が懸念されるため、長期使用には注意が必要です。
薬剤が与える影響の例
・抗不安薬による眠気、集中力低下
・鎮痛薬による便秘、依存リスク
・サプリメント過剰摂取による肝負荷増大
ポルフェリン症の保険適用と治療費
以下に記載している治療費(医療費)は目安であり、実際の費用は症状や治療内容、保険適用否により大幅に上回ることがございます。当院では料金に関する以下説明の不備や相違について、一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。
保険適用される主な検査
ポルフェリン症を診断するうえで基本となる血液検査、尿検査、便検査などは公的医療保険の対象に含まれます。
尿中PBGやALA測定、血中ポルフェリン測定など、特殊検査に分類されるものでも、医師が必要と判断すれば保険適用を受けられます。
遺伝子検査に関しては、保険で受けられる条件が限られている場合もあるため、必要性を医師と相談しながら検討することになります。
一般的に、血液検査や尿検査の費用は数千円から1万円前後で済むことが多いですが、特殊な検査項目が増えると追加費用がかかる場合があります。
保険適用が想定される検査
・血液一般検査、肝機能検査
・尿中ポルフォビリノーゲン(PBG)・アミノレブリン酸(ALA)検査
・便中ポルフェリン検査
治療薬の費用
急性期に用いられるヘミン製剤は比較的高額な薬剤ですが、多くの場合は公的医療保険の対象となるため、自己負担額は3割程度(または収入によってはさらに軽減)となります。
ヘミン製剤を数日間使用した場合、薬剤だけで数万円以上かかる可能性がありますが、保険を利用すれば実費負担は3割程度となる場合が多いです。
| 治療薬 | 保険適用の有無 | 自己負担額の目安(3割負担時) |
|---|---|---|
| ヘミン製剤 | あり | 薬価が高めだが保険で3割負担 |
| 鎮痛薬・制吐薬など | あり | 数百円~数千円程度 |
| β-カロテン、ビタミンD等 | ありの場合有 | 処方薬なら3割負担、サプリは保険外 |
入院治療時の費用
急性発作が起きて入院し期間が数日から1~2週間になることもあり、その間に行われる検査や治療薬の投与などを含めると総額は数十万円になることもあります。
ただし、公的医療保険の対象となるため、多くの場合はその3割前後が自己負担です。
長期管理にかかる費用
皮膚症状中心の病型では、外来フォローアップと生活習慣の管理がメインとなるため、月1回程度の通院(血液検査や医師の診察)で数千円~1万円程度の自己負担が想定されます。
治療薬の処方費用も含めて、年間を通して考えると数万円~十数万円におよぶことがあります。
以上
参考文献
Kondo M, Yano Y, Shirataka M, Urata G, Sassa S. Porphyrias in Japan: compilation of all cases reported through 2002. International journal of hematology. 2004 Jun;79:448-56.
Horie Y, Yasuoka Y, Adachi T. Clinical features of acute attacks, chronic symptoms, and long-term complications among patients with acute hepatic porphyria in Japan: a real-world claims database study. Orphanet Journal of Rare Diseases. 2023 Dec 8;18(1):384.
Horie Y, Yasuoka Y, Adachi T. Clinical features of Japanese patients with acute hepatic porphyria. JIMD reports. 2023 Jan;64(1):71-8.
Kondo M, Yano Y, Urata G. Porphyrias in Japan: Compilation of all cases reported through 2010. ALA-Porphyrin Sci. 2012;2:73-82.
Puy H, Gouya L, Deybach JC. Porphyrias. The Lancet. 2010 Mar 13;375(9718):924-37.
Thadani H, Deacon A, Peters T. Diagnosis and management of porphyria. Bmj. 2000 Jun 17;320(7250):1647-51.
Bissell DM, Anderson KE, Bonkovsky HL. Porphyria. New England Journal of Medicine. 2017 Aug 31;377(9):862-72.
Ramanujam VM, Anderson KE. Porphyria diagnostics—part 1: a brief overview of the porphyrias. Current protocols in human genetics. 2015 Jul;86(1):17-20.
Pischik E, Kauppinen R. An update of clinical management of acute intermittent porphyria. The application of clinical genetics. 2015 Sep 1:201-14.
Herrick AL, McColl KE. Acute intermittent porphyria. Best practice & research Clinical gastroenterology. 2005 Apr 1;19(2):235-49.