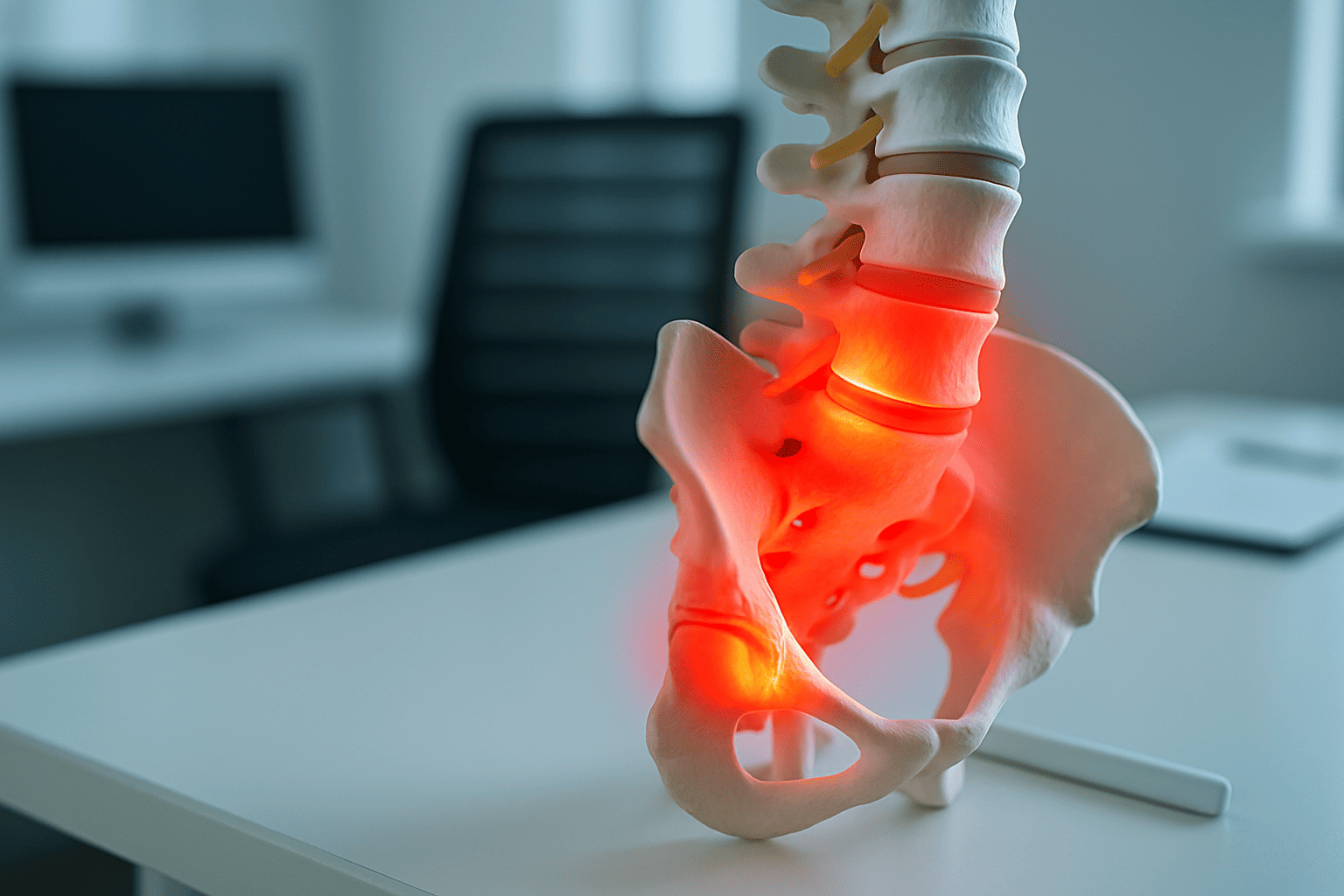「電気が走るような痛み」「焼けるような、ヒリヒリする感じ」「ジンジン、ビリビリとしびれる」…このような、言葉で表現しにくい不快な痛みに悩んでいませんか?それはもしかしたら「神経障害性疼痛」かもしれません。
この痛みは、神経そのものが傷ついたり、機能異常を起こしたりすることで生じます。
ここでは、神経障害性疼痛の基本的な知識から、原因、症状、そして整形外科での診断や治療アプローチについて詳しく解説します。ご自身の症状を理解し、適切な対処法を見つけるための一助となれば幸いです。
この記事の執筆者

臼井 大記(うすい だいき)
日本整形外科学会認定専門医
医療社団法人豊正会大垣中央病院 整形外科・麻酔科 担当医師
2009年に帝京大学医学部医学科卒業後、厚生中央病院に勤務。東京医大病院麻酔科に入局後、カンボジアSun International Clinicに従事し、ノースウェスタン大学にて学位取得(修士)。帰国後、岐阜大学附属病院、高山赤十字病院、岐阜総合医療センター、岐阜赤十字病院で整形外科医として勤務。2023年4月より大垣中央病院に入職、整形外科・麻酔科の担当医を務める。
神経障害性疼痛とは?基本的な知識
神経障害性疼痛は、一般的な「痛み」とは少し異なる性質を持っています。まずは、その基本的な特徴を理解しましょう。
痛みの種類と神経障害性疼痛の位置づけ
痛みは、その原因や性質によっていくつかの種類に分けられます。神経障害性疼痛は、その中でも特殊な位置づけにあります。
怪我や炎症によって組織が傷つき、その信号が神経を伝わって脳に痛みとして認識されるのが「侵害受容性疼痛」です。打撲や切り傷の痛みがこれにあたります。
一方、神経障害性疼痛は、神経系そのものの損傷や機能異常が直接的な原因となって生じる痛みです。
痛みの主な分類
| 痛みの種類 | 主な原因 | 痛みの例 |
|---|---|---|
| 侵害受容性疼痛 | 組織の損傷(怪我、炎症など) | 打撲、切り傷、やけど、関節炎 |
| 神経障害性疼痛 | 神経系の損傷や機能異常 | 帯状疱疹後神経痛、糖尿病性神経障害、坐骨神経痛 |
| 心因性疼痛 | 心理的・社会的な要因 | 身体表現性障害に伴う痛み |
なぜ神経が痛みを引き起こすのか
通常、神経は体の各部からの情報を脳に伝える役割を担っています。しかし、神経が損傷したり、何らかの原因で過敏になったりすると、情報伝達にエラーが生じます。
例えば、触覚のような弱い刺激を痛みとして感じてしまったり(アロディニア)、何もないのに痛みを感じてしまったり(自発痛)することがあります。
これは、神経が誤った「痛み信号」を脳に送り続けてしまうために起こります。
侵害受容性疼痛との違い
侵害受容性疼痛は、原因となる組織の損傷が治れば痛みも和らぐことが多いです。しかし、神経障害性疼痛は、元の原因が解消しても神経の異常が残ってしまうと痛みが続くことがあります。
また、痛みの質も異なり、「ビリビリ」「ジンジン」「焼けるような」といった表現がよく使われます。
痛みの原因が神経自体にあるため、一般的な痛み止め(非ステロイド性抗炎症薬など)が効きにくい場合があるのも特徴です。
こんな症状、ありませんか?神経障害性疼痛のサイン
神経障害性疼痛は、多彩な症状を引き起こします。ご自身の症状と照らし合わせてみましょう。
特徴的な痛みの表現
神経障害性疼痛を経験する方は、痛みを独特な言葉で表現することがあります。これらの表現は、診断の手がかりとなることがあります。
- 電気が走るような痛み
- 焼けるような、ヒリヒリする痛み
- ジンジン、ビリビリとしびれるような痛み
- 締め付けられるような、圧迫されるような痛み
痛みの現れ方
痛みの現れ方も人それぞれです。常に痛みを感じる場合もあれば、特定の動作や時間帯に強くなる場合もあります。また、天気や気温の変化によって痛みが変動すると感じる方もいます。
痛みのパターン例
| パターン | 特徴 |
|---|---|
| 持続性の痛み | 常に一定の痛みがある |
| 突発性の痛み | 急に強い痛みが襲ってくる |
| 誘発性の痛み | 特定の刺激(触れる、動かすなど)で痛みが起こる |
感覚の変化
痛みだけでなく、感覚そのものに変化が現れることも神経障害性疼痛の特徴です。
触れた感覚が鈍くなったり(感覚鈍麻)、逆にわずかな刺激で強い痛みを感じたり(アロディニア)、痛みを通常より強く感じたり(痛覚過敏)することがあります。
日常生活への影響
持続的な痛みや不快な感覚は、睡眠を妨げたり、集中力を低下させたり、気分を落ち込ませたりすることがあります。
痛みのために仕事や家事、趣味などが制限され、生活の質(QOL)が大きく低下してしまうことも少なくありません。
神経障害性疼痛を引き起こす主な原因
神経障害性疼痛は、さまざまな原因によって引き起こされます。代表的な原因を知っておきましょう。
病気によるもの
特定の病気が神経にダメージを与え、神経障害性疼痛を引き起こすことがあります。代表的なものとしては、糖尿病による「糖尿病性神経障害」、帯状疱疹の後に痛みが残る「帯状疱疹後神経痛」などがあります。
その他、多発性硬化症や脊髄損傷なども原因となりえます。
神経障害性疼痛の原因となる主な疾患
| 疾患名 | 概要 |
|---|---|
| 糖尿病性神経障害 | 高血糖により末梢神経が障害される |
| 帯状疱疹後神経痛 | 帯状疱疹ウイルスにより神経が損傷する |
| 脳卒中後疼痛 | 脳卒中により脳の感覚経路が損傷する |
怪我や手術によるもの
事故による怪我や手術の際に神経が直接損傷したり、周囲の組織の瘢痕(はんこん)によって神経が圧迫されたりすることで痛みが引き起こされることがあります。
手足の切断後に、ないはずの場所に痛みを感じる「幻肢痛」も神経障害性疼痛の一種と考えられています。
神経の圧迫によるもの
整形外科でよく見られる原因として、神経が物理的に圧迫されることによるものがあります。
代表的なのは、背骨(脊椎)の問題です。椎間板ヘルニアや脊柱管狭窄症などにより、脊髄から枝分かれする神経根(しんけいこん)が圧迫されると、お尻から足にかけて痛みやしびれが生じる「坐骨神経痛」などが起こります。
また、手首で神経が圧迫される「手根管症候群」などもこれにあたります。
その他の原因
上記以外にも、がんそのものや、がん治療(化学療法、放射線療法)の副作用として神経障害性疼痛が起こることがあります。また、明確な原因が特定できない場合もあります。
整形外科で診る神経障害性疼痛
整形外科では、骨、関節、筋肉、そしてそれらに関連する神経系の病気や怪我を専門としています。そのため、神経の圧迫などが原因となる神経障害性疼痛の診断と治療において、重要な役割を担います。
脊椎疾患と神経痛
腰椎椎間板ヘルニアや腰部脊柱管狭窄症は、腰や足の神経障害性疼痛(坐骨神経痛など)を引き起こす代表的な整形外科疾患です。
同様に、頚椎(首の骨)の変形やヘルニアは、首、肩、腕、手指の痛みやしびれの原因となります。これらの疾患では、神経の圧迫を取り除くための治療や、痛みを管理するための治療を行います。
整形外科で扱う主な脊椎関連の神経痛
| 疾患名 | 主な症状部位 |
|---|---|
| 腰椎椎間板ヘルニア | 腰、臀部、太もも、ふくらはぎ、足 |
| 腰部脊柱管狭窄症 | 腰、臀部、太もも、ふくらはぎ、足(特に歩行時) |
| 頚椎症性神経根症 | 首、肩、腕、手指 |
末梢神経の圧迫
脊椎だけでなく、手足の末梢神経が特定の場所で圧迫されて痛みやしびれを引き起こすこともあります。
手首の「手根管症候群」、肘の「肘部管症候群」、足首の「足根管症候群」などが代表的です。整形外科ではこれらの神経圧迫の状態を評価し、治療を行います。
外傷後の神経痛
骨折や脱臼、打撲などの怪我の後に、神経が損傷したり、治癒の過程で神経が巻き込まれたりして、神経障害性疼痛が残ることがあります。
整形外科では、怪我の治療と並行して、または治療後に残った神経痛に対するアプローチを行います。
整形外科での検査方法
整形外科では、神経障害性疼痛の原因を特定するために、問診や身体診察に加えて、レントゲン(X線)検査、MRI検査、CT検査などの画像検査を行います。
これらの検査により、骨の変形や椎間板の状態、神経の圧迫の有無などを評価します。必要に応じて、神経伝導速度検査などの特殊な検査を行うこともあります。
痛みの裏にあるもの – 見過ごされがちな心と体のつながり
神経障害性疼痛は、単に身体的な問題だけでなく、心理的な側面も深く関わっています。痛みが長引くと、どうしても気分が落ち込んだり、不安になったりしがちです。
痛みが長引く心理的要因
痛みが続くと、「いつ治るのだろうか」「悪化するのではないか」といった不安や、「痛みのせいで何もできない」という無力感を感じやすくなります。
このようなネガティブな感情は、痛みをさらに強く感じさせてしまうことがあります。また、痛みにばかり意識が集中してしまうことも痛みを長引かせる一因となることがあります。
ストレスと痛みの悪循環
痛みはそれ自体が大きなストレス源です。そして、ストレスを感じると、体は痛みを抑制する能力が低下したり、筋肉が緊張して血行が悪くなったりして、痛みを悪化させることがあります。
つまり、「痛み→ストレス→痛みの悪化→さらなるストレス」という悪循環に陥ってしまうことがあるのです。
ストレスが痛みに与える影響
| 影響 | 内容 |
|---|---|
| 痛みの抑制機能低下 | 脳内で痛みを抑える物質の分泌が減る |
| 筋肉の緊張 | 血行が悪くなり、痛みを増強させる物質が溜まりやすくなる |
| 交感神経の亢進 | 血管が収縮し、神経が過敏になることがある |
睡眠不足が痛みに与える影響
痛みがあると、夜ぐっすり眠れないことがあります。しかし、睡眠不足は体の回復を妨げるだけでなく、痛みをより強く感じやすくさせることもわかっています。
質の高い睡眠をとることは、痛みの管理においても非常に重要です。
痛みを抱えながら前向きに過ごすヒント
痛みを完全になくすことが難しい場合でも、痛みとの付き合い方を工夫することで生活の質を向上させることは可能です。
痛みにばかりとらわれず、できる範囲で気分転換になるような活動を取り入れたり、リラックスできる時間を持ったりすることが大切です。
また、痛みのつらさを一人で抱え込まず、家族や友人、医療従事者などに相談することも助けになります。
「痛いけれど、できることもある」という視点を持つことが、前向きな気持ちを保つ鍵となるでしょう。
神経障害性疼痛の診断の流れ
神経障害性疼痛の診断は、患者さんのお話を詳しく聞くことから始まります。正確な診断のために、以下の点を意識して医師に伝えましょう。
問診で伝えるべきこと
医師は、痛みの性質や始まった時期、きっかけ、どのような時に痛みが強くなるかなどを詳しく尋ねます。以下の点を整理しておくと、スムーズに伝えることができます。
- いつから、どのようなきっかけで痛みが始まったか
- 痛みの場所、広がり
- 痛みの性質(ビリビリ、ジンジン、焼けるようなど)
- 痛みの強さ(数字で表現するなど)
- 痛みが強くなる・和らぐ状況
- 痛み以外の症状(しびれ、感覚の鈍さ、脱力感など)
- これまでに行った治療とその効果
- 現在治療中の病気や服用中の薬
身体診察と神経学的検査
医師は、痛む場所やその周辺を実際に見て、触って、状態を確認します。また、ハンマーのような道具で腱反射を調べたり、感覚(触覚、痛覚、温度覚など)が正常かを確認したりする神経学的検査を行います。
これにより、どの神経に問題があるのかを推定します。
画像検査の役割
レントゲン検査では骨の異常を、MRI検査やCT検査では椎間板や神経、脊髄の状態を詳しく見ることができます。特に、神経の圧迫が疑われる場合には、MRI検査が有用です。
これらの画像検査は、神経障害性疼痛の原因となっている可能性のある構造的な異常を確認するために行います。
主な画像検査とその目的
| 検査名 | 主な目的 |
|---|---|
| レントゲン(X線)検査 | 骨の変形、骨折、関節の状態を確認 |
| MRI検査 | 椎間板、神経、脊髄、筋肉などの軟部組織の状態を詳しく確認 |
| CT検査 | 骨の詳細な構造や、レントゲンでは分かりにくい骨病変を確認 |
補助的な検査
診断を確定したり、他の病気との区別をしたりするために補助的な検査を行うことがあります。
神経伝導速度検査や筋電図検査は神経の信号がどのくらいの速さで伝わっているか、筋肉が正常に機能しているかを調べる検査で、末梢神経の障害の程度を評価するのに役立ちます。
血液検査は、糖尿病など、痛みの原因となる全身性の病気がないかを確認するために行われることがあります。
整形外科での神経障害性疼痛へのアプローチ
整形外科では、神経障害性疼痛の原因や症状の程度に応じて、様々な治療法を組み合わせてアプローチします。
薬物療法
神経障害性疼痛には、一般的な痛み止め(非ステロイド性抗炎症薬など)が効きにくいことがあります。そのため、神経の過剰な興奮を抑える薬や、痛みを伝える神経伝達物質のバランスを整える薬を使用します。
具体的には、抗うつ薬の一部(三環系抗うつ薬、SNRIなど)や、抗てんかん薬の一部(プレガバリン、ミロガバリン、ガバペンチンなど)が用いられます。
これらの薬は、医師の指示に従って少量から開始し、効果や副作用を確認しながら慎重に量を調整します。
神経障害性疼痛に用いられる主な薬の種類
| 薬の種類 | 主な作用 |
|---|---|
| 抗うつ薬(一部) | 痛みを抑制する神経伝達物質の働きを高める |
| 抗てんかん薬(一部) | 過剰に興奮した神経を鎮める |
| オピオイド鎮痛薬 | 強い痛みを抑える(使用は慎重に判断) |
| 外用薬(貼り薬、塗り薬) | 局所の痛みを和らげる |
神経ブロック療法
痛みの原因となっている神経やその周辺に局所麻酔薬やステロイド薬を注射することで、痛みの伝達を一時的に遮断(ブロック)する治療法です。
痛みを軽減させるだけでなく、血行を改善したり、痛みの悪循環を断ち切ったりする効果も期待できます。
整形外科では、レントゲン透視や超音波(エコー)を用いて、正確な場所に注射を行います。
リハビリテーション
理学療法士や作業療法士によるリハビリテーションも重要な治療法の一つです。
運動療法(ストレッチや筋力トレーニングなど)により、体の柔軟性を高め、筋力を維持・向上させることで、痛みの軽減や機能改善を目指します。
また、物理療法(温熱療法、電気刺激療法など)で痛みを和らげたり、日常生活での正しい体の使い方を指導したりします。
生活習慣の改善指導
肥満は腰や膝への負担を増やし、痛みを悪化させることがあります。適度な運動やバランスの取れた食事による体重管理は、痛みの軽減につながります。
また、喫煙は血行を悪化させ、神経への酸素供給を妨げる可能性があるため禁煙が推奨されます。十分な睡眠をとることも、痛みの管理には重要です。
神経障害性疼痛との付き合い方
神経障害性疼痛は、完全に治癒することが難しい場合もあります。しかし、適切な治療と工夫によって、痛みと上手に付き合いながら、より快適な生活を送ることは可能です。
痛みを管理するためのセルフケア
医師から処方された薬を正しく服用することに加え、自分でできるセルフケアも大切です。痛む部分を温めたり冷やしたりすることで、痛みが和らぐことがあります(どちらが効果的かは個人差があります)。
軽いストレッチや散歩などの無理のない範囲での運動は血行を促進し、気分転換にもなります。リラクゼーション法(深呼吸、瞑想など)を取り入れるのも良いでしょう。
日常生活での注意点
痛みを悪化させる可能性のある動作や姿勢を避けるように心がけましょう。例えば、重いものを持つときは腰に負担がかからないように注意する、長時間同じ姿勢を続けないようにする、などが挙げられます。
また、靴選びも重要です。クッション性の良い、足に合った靴を選ぶことで歩行時の衝撃を和らげることができます。
周囲の理解とサポートの重要性
神経障害性疼痛は、外見からは分かりにくいため、周囲の人に痛みのつらさを理解してもらいにくいことがあります。
自分の状態について、家族や職場の人などに説明し理解と協力を得ることも大切です。痛みを一人で抱え込まず、信頼できる人に相談したり、必要であれば心理的なサポートを受けたりすることも考えましょう。
よくある質問
神経障害性疼痛に関して、患者さんからよく寄せられる質問にお答えします。
参考文献
COLLOCA, Luana, et al. Neuropathic pain. Nature reviews Disease primers, 2017, 3.1: 1-19.
ZILLIOX, Lindsay A. Neuropathic pain. CONTINUUM: Lifelong Learning in Neurology, 2017, 23.2: 512-532.
GIERTHMÜHLEN, Janne; BARON, Ralf. Neuropathic pain. In: Seminars in Neurology. Thieme Medical Publishers, 2016. p. 462-468.
CAMPBELL, James N.; MEYER, Richard A. Mechanisms of neuropathic pain. Neuron, 2006, 52.1: 77-92.
BRIDGES, D.; THOMPSON, S. W. N.; RICE, A. S. C. Mechanisms of neuropathic pain. British journal of anaesthesia, 2001, 87.1: 12-26.
FINNERUP, Nanna Brix; KUNER, Rohini; JENSEN, Troels Staehelin. Neuropathic pain: from mechanisms to treatment. Physiological reviews, 2020.
BACKONJA, Misha-Miroslav. Defining neuropathic pain. Anesthesia & Analgesia, 2003, 97.3: 785-790.
HAANPÄÄ, Maija, et al. NeuPSIG guidelines on neuropathic pain assessment. PAIN®, 2011, 152.1: 14-27.
COHEN, Steven P.; MAO, Jianren. Neuropathic pain: mechanisms and their clinical implications. Bmj, 2014, 348.
BARON, Ralf; BINDER, Andreas; WASNER, Gunnar. Neuropathic pain: diagnosis, pathophysiological mechanisms, and treatment. The Lancet Neurology, 2010, 9.8: 807-819.