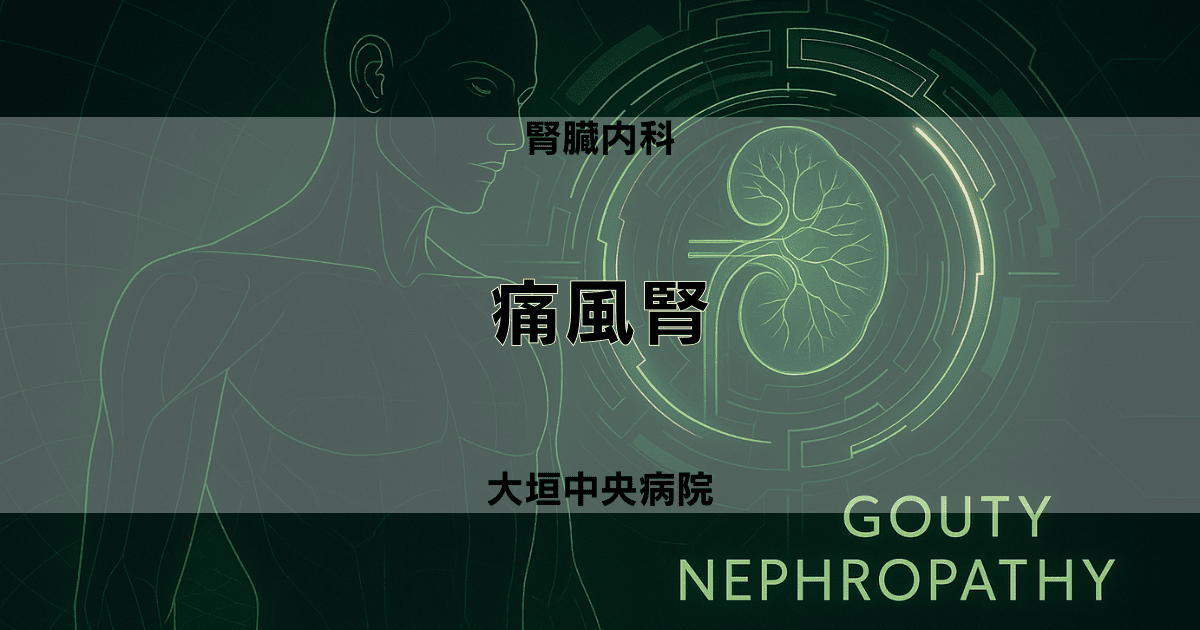痛風腎とは、高尿酸血症によって腎臓の組織や機能に影響が及び、糸球体や尿細管などに変化が生じる疾患です。
尿酸の結晶が腎臓内で蓄積したり、慢性的な炎症を起こすことで徐々に腎機能が低下していくことが特徴とされます。
痛風自体は、足の親指などの関節が赤く腫れ、激しい痛みを伴う発作で知られていますが、その原因となる高尿酸血症が進むと、腎臓にダメージが蓄積して将来的に深刻な障害を招くリスクがあります。
病型
痛風腎は、尿酸値が高い状態が続いて腎臓に負荷がかかり、さまざまな組織学的変化が起こる病気ですが、その経過や病型は単に「高尿酸血症だから腎臓が悪い」という単純なものではありません。
腎臓内でどのように尿酸が蓄積し、どの組織が影響を受けるかによって、多様な病態が見られます。
急性尿酸性腎症
急性期に尿酸が過剰に排泄される状況が生じた場合、腎臓の尿細管が尿酸結晶によって詰まり、一気に腎機能が落ち込む状態です。
激しい痛風発作のあとや悪性腫瘍の治療などで急激に細胞が壊れたときに起こることが多く、短期間のうちに血中尿酸値が急騰することで腎臓への負担が増大します。
急性尿酸性腎症が発生しやすい状況
| 状況 | 具体例 | メカニズム |
|---|---|---|
| 急性痛風発作後 | 痛風発作で炎症が強まる | 血中尿酸値が上昇し、腎臓へ結晶が蓄積しやすい |
| 悪性腫瘍の治療による腫瘍崩壊症候群 | 化学療法などで腫瘍細胞が大量に壊れる | 細胞内のプリン体が分解され尿酸が急上昇 |
| 脱水や極端な水分制限 | 水分が不足し、尿量が減る | 尿酸濃度が上がり、結晶化しやすくなる |
慢性尿酸性腎症
高尿酸血症が長期にわたって続くことにより、徐々に腎臓組織が障害される病態で、糸球体や尿細管だけでなく、腎間質にも慢性的な炎症が生じ、腎機能が少しずつ落ちていくのが特徴です。
痛風の関節症状は落ち着いていても、尿酸値が管理できていないケースで、この慢性型が進行することがあります。
腎実質への結晶沈着
痛風腎では、腎臓内部の組織に尿酸塩結晶が蓄積する場合があり、痛風結節が関節だけでなく腎臓にまで影響する形で、腎機能が障害されるため、重症化すると人工透析が必要になる危険が出てきます。
痛風歴が長い方や、尿酸値が非常に高い状態が持続している方には注意が必要です。
痛風発作と腎障害の同時進行
痛風発作が頻繁に起こる方は、高い尿酸値が慢性的に維持されていることが多く、発作時の炎症反応が全身に及ぶと、血管の機能や血流にも影響が及び、こうした反復的なダメージが腎臓にも波及し、病型がより複雑化するケースがあります。
痛風と腎機能低下が重なっている場合、双方に配慮した総合的な治療が大切です。
痛風腎の主な病型
| 病型 | 経過 | 主な特徴 |
|---|---|---|
| 急性尿酸性腎症 | 急性期に急激に発症 | 尿酸結晶が尿細管を詰まらせる |
| 慢性尿酸性腎症 | 徐々に進行 | 高尿酸血症が長期化し腎実質が損傷 |
| 腎実質への沈着型 | 痛風結節の腎沈着 | 関節同様に腎臓内部に結晶が蓄積 |
| 痛風発作との関連 | 発作と腎障害が連動 | 全身性炎症が腎に影響しやすい |
痛風腎の病型は単純ではなく、症例ごとにいくつもの経路を経て腎機能が損なわれる可能性があり、そのため、主治医との相談を通じて、どの病型に該当しそうかを早期に把握することが重要です。
痛風腎の症状
痛風腎の症状は、腎臓の機能が低下する過程であまり目立った自覚症状を示さない場合も多く、気付いたときには腎機能がかなり低下していたというケースが少なくありません。
痛風の関節痛と比べて派手さがないため、見過ごされがちな特徴があります。
だるさや疲労感
腎機能が衰えていくと、老廃物の排出が十分に行えなくなり、血液中に尿素やクレアチニンなどの有害物質が蓄積しやすくなり、全身の倦怠感や疲労感が生じやすくなることがあります。
特に、初期段階では「なんとなく体が重い」という程度の違和感に留まることも多いため、見逃されがちです。
痛風腎の初期によくある訴え
- 朝起きたときに疲れが残っている
- 体を動かすとすぐに疲れる
- 軽い頭痛や集中力の低下を感じる
- 以前より食欲が減っているように思う
こうした感覚的な不調がある場合、他の原因と合わせて腎機能の低下を疑う必要があります。
むくみや血圧の上昇
腎臓が水分や塩分を上手に排泄できなくなると、足や顔などにむくみが出ることがあり、さらに、体内の水分量や塩分量が増えると血圧が上昇しやすくなり、高血圧症を併発するリスクも高いです。
この状態が続くと、心臓や血管にも負担がかかり、循環器疾患の合併が進む恐れが出てきます。
尿に関する異常
腎臓の状態が変化すると、尿の色や量、においに変化が生じることがあり、淡い色だったり、泡立ちが強くなったりするのはタンパク質の漏出などが原因の可能性があります。
ただし、痛風腎の場合は必ずしも早期から尿の異常が顕著に出るわけではなく、症状が進行してから蛋白尿や血尿が確認されることも少なくありません。
痛風腎の主な症状と関連する臓器の変化
| 症状 | 具体的な状態 | 主な関連メカニズム |
|---|---|---|
| 全身倦怠感 | 疲れやすい、集中力の低下 | 尿毒素の蓄積 |
| むくみ | 顔や手足に浮腫が出る | 水分や塩分の排泄低下 |
| 血圧上昇 | 動悸や息切れを感じる場合も | 体液量の増加とレニン系の過剰活性 |
| 尿の変化 | 尿量の減少、泡立ち、色の変化 | 尿細管の障害やタンパク漏出 |
高尿酸血症による関節痛との関係
痛風腎であるということは、高尿酸血症が背景にあるケースが多く、関節に痛風発作を起こしているかどうかもチェックポイントになります。
激しい関節痛の後に腎機能の検査をすると、すでに慢性的なダメージが進んでいることが判明することもあるため、痛風発作歴がある方は特に注意が必要です。
痛風腎の原因
痛風腎の発症には、高尿酸血症が大きな要因として挙げられますが、食生活や遺伝要因、肥満、メタボリックシンドロームなども複雑に絡み合いながら、腎臓に負荷がかかっていきます。
痛風発作はあくまで氷山の一角であり、発作がなくても尿酸値が高い状態が続けば、腎臓への影響は着実に進行する可能性があります。
高尿酸血症との直接的な関連
血中尿酸値が7.0mg/dLを超えると高尿酸血症と定義されますが、痛風腎はこれを上回る状態が持続すると、腎臓内の尿細管や糸球体に尿酸塩の結晶が蓄積していき、局所的な炎症や硬化を引き起こすことが考えられます。
このメカニズムが長期にわたって作用し続けると、緩やかに腎機能が低下し、やがて症状が顕在化します。
尿酸値が上昇する主な要因
- プリン体を多く含む食品やアルコールの過剰摂取
- 糖分の多い飲み物や炭水化物の偏った食事
- 運動不足による肥満
- 遺伝的要因や代謝異常
食生活や嗜好品
プリン体を多く含む肉類や魚介類を過剰に摂取する食生活は、尿酸の生成を増やす要因となり得ます。
加えて、アルコールが尿酸の排泄を阻害し、さらに血中尿酸値を上昇させる効果があるため、過度の飲酒は痛風と痛風腎の両面から大きなリスク要因で、糖分の多い飲料や菓子類も腎臓への負担に直結する可能性があり、注意が必要です。
食生活や嗜好品が痛風腎に与える影響
| 要素 | 具体例 | 病態への影響 |
|---|---|---|
| プリン体 | レバー、白子、エビなど | 尿酸生成量が増え、高尿酸血症を助長 |
| アルコール | ビール、日本酒、ワインなど | 尿酸排泄を阻害、尿酸値を上昇させる |
| 糖分 | 清涼飲料水、甘い菓子、果糖の多いジュース | インスリン抵抗性を高め、尿酸の排泄低下 |
| 高塩分 | 塩辛い食品全般 | 血圧の上昇や腎負担、脱水のリスクも増大 |
遺伝的要素
痛風や高尿酸血症が家族内で多発している場合、遺伝子レベルでプリン体の代謝や尿酸の排泄に異常がある可能性があります。
必ずしも発症が確定するわけではありませんが、他のリスク要因が加わると痛風腎に進行するリスクが上昇するため、家族歴がある方は定期的な尿酸値チェックが大切です。
メタボリックシンドロームとの関連
肥満、高血圧、脂質異常症などが重なったメタボリックシンドロームの状態になると、インスリン抵抗性が高まり尿酸排泄が阻害されることが指摘されていて、高尿酸血症と腎機能の低下が悪循環を形成しやすくなります。
したがって、痛風腎を予防・改善するためにはメタボリックシンドロームの治療や管理も欠かせません。
メタボリックシンドロームが痛風腎に及ぼす主な影響
- インスリン抵抗性の向上で尿酸の排泄が滞る
- 血圧が上昇し、腎臓の血管に負担がかかる
- 脂質異常が動脈硬化を助長し、腎血流が減少
- 肥満による体重増加が全身の代謝バランスを乱す
痛風腎の検査・チェック方法
痛風腎が疑われる場合、早期に専門的な検査を受けて腎臓の状態を確認し、適切な治療方針を立てることが重要です。
痛風腎の検査は、血液検査や尿検査をはじめ、画像検査や腎機能評価など多角的に行われることが一般的であり、各種の検査結果を総合的に判断して診断が下されます。
血液検査
痛風腎の初期評価として最も基本的なのが血液検査です。
| 検査項目 | 主な目的 | 痛風腎との関連 |
|---|---|---|
| 尿酸 | 痛風の基礎的指標になる | 高値であれば腎機能への負担増を疑う |
| クレアチニン | 腎機能の評価(eGFR算出の基準) | 値が上昇していると腎障害の可能性がある |
| BUN (尿素窒素) | 老廃物排出能力の指標 | 腎臓のろ過機能低下で高値になりやすい |
| 電解質 (Na/K等) | 体内バランス・血圧管理の指標 | 腎機能障害が進むと異常を生じやすい |
これらの値を総合して、腎臓がどの程度ダメージを受けているかを把握し、また、血糖値や脂質プロファイルなども痛風腎のリスク要因を探るうえで確認されることが多いです。
尿検査
痛風腎では、尿に含まれる尿酸量、タンパク質や潜血などの有無が重要な情報になります。慢性腎臓病の指標となるアルブミン尿が出ていないか、結晶や沈渣がないかなどを詳しく調べることで、腎障害の進行度をおおまかにつかむことが可能です。
尿検査でチェックされる代表的な項目
- 尿酸排泄量:高尿酸血症でも排泄が十分かどうかを判定
- 尿蛋白:腎機能障害の進行度を示すサイン
- 尿潜血:血尿の有無や程度を把握
- 尿比重やpH:濃縮機能や酸塩基バランスを評価
画像検査
腎臓の大きさや形状、内部構造を把握する目的でエコー(超音波)検査やCTスキャンなどの画像診断が行われる場合があります。
痛風腎による組織変化は必ずしも画像上に明確に出るとは限りませんが、結石の有無や腎臓の形態異常などが確認できるため、必要に応じて選択されます。
腎生検
痛風腎の確定診断や、他の腎疾患との鑑別が難しい場合は腎生検が検討されることがあり、これは腎臓の組織を一部採取し、顕微鏡で観察する検査です。
尿酸結晶の沈着や炎症所見、線維化の程度を直接確認できるため、最も正確に病態を把握できる方法ですが、侵襲的で合併症のリスクもあるため、慎重に実施の要否が判断されます。
痛風腎が疑われる際に用いられる主な検査方法
| 検査方法 | 特徴 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
| 血液検査 | 尿酸やクレアチニンなどを測定 | 簡単に実施可能でスクリーニングに有用 | 単独では病態の細部把握が難しい |
| 尿検査 | 尿酸排泄量やタンパク、血液などを確認 | 腎機能の異常サインを感知しやすい | 状態によっては結果が変動しやすい |
| 画像検査 | 超音波やCTで形態変化や結石を把握 | 非侵襲的で追加情報が得やすい | 軟部組織の微細変化には不向きな場合あり |
| 腎生検 | 腎組織を直接観察 | 確定診断に役立つ | 侵襲的で合併症リスクがある |
治療方法と治療薬について
痛風腎の治療は、高尿酸血症の是正と腎機能低下の進行を遅らせることが大きな目標になり、生活習慣の改善や食事療法と合わせて、薬物治療が行われることが多く、腎機能の状態や合併症の有無などに応じて治療方針が変わってきます。
生活習慣と食事療法
薬物治療に取りかかる前に、あるいは併用しながら、食事や運動などの生活習慣を見直すことが大切です。
プリン体を多く含む食品やアルコールを控えめにし、水分をしっかり摂取して尿量を増やす工夫を行うことで、尿酸排泄を促しやすくなる傾向があります。
痛風腎治療における生活習慣のポイント
- 塩分の摂取を控え、高血圧を予防
- 動物性たんぱく質の摂取量を適度に抑える
- 十分な水分を補給し、尿量を確保
- 適度な運動と体重管理
こうした対策を行うことで、薬の効果を引き出しやすくし、腎機能の負担を軽減できます。
尿酸降下薬
痛風腎における薬物療法の中心は、血中尿酸値を下げる薬の使用で、代表的な薬剤としては、尿酸の産生を抑えるアロプリノールやフェブキソスタット、排泄を促すベンズブロマロンなどが挙げられます。
どちらを選ぶかは、腎機能の状態や合併症の有無などを考慮して決定されます。
尿酸降下薬の代表的な種類と特徴
| 薬剤名 | 主な作用 | 注意点 |
|---|---|---|
| アロプリノール | 尿酸産生を抑制 | 腎機能低下時は投与量調整が必要 |
| フェブキソスタット | 尿酸合成酵素の働きを阻害 | 比較的新しい薬で、肝機能にも留意が必要 |
| ベンズブロマロン | 尿酸の排泄を促進 | 尿路結石リスクに注意しながら投与 |
いずれの薬剤も、開始初期には痛風発作を誘発する可能性があるため、低用量から徐々に増量することが多く、同時にコルヒチンやNSAIDsなどを併用して発作を予防する場合もあります。
血圧コントロールや利尿薬の活用
痛風腎では、高血圧を合併する方が多いため、血圧をコントロールする薬(ACE阻害薬やARBなど)が処方されることがあり、腎保護効果が期待できるため、痛風腎の進行を遅らせる上で重要な位置付けとなります。
利尿薬の種類によっては尿酸値を上げる作用を持つ場合があり、選択には注意が必要です。
透析療法
腎機能が極端に低下し、通常の薬物療法や食事療法では対応できない段階に至った場合、血液透析や腹膜透析などの透析療法が検討されます。
ただし、透析に移行すると日常生活の制限が大きくなるため、できる限り腎機能を温存することが望まれ、痛風腎の重症化を防ぐためにも、早期から適切な治療を行うことが大切です。
痛風腎の治療法全般
| 治療法 | 目的・特徴 | 注意点 |
|---|---|---|
| 生活習慣・食事療法 | 尿酸生成を抑え、腎負担を軽くする | 効果が出るまでに時間がかかる |
| 尿酸降下薬 | 血中尿酸値を管理し、腎機能を守る | 初期発作誘発リスク、腎機能に応じた調整必須 |
| 血圧管理 | 高血圧合併例で腎保護を図る | 薬剤選択によって尿酸値に影響することあり |
| 透析療法 | 重度腎不全の場合の最終的な手段 | 生活の制限が増大し、経済的負担も大きい |
治療期間
痛風腎の治療は長期にわたって続く場合が多く、短期間で完治するイメージとはかけ離れたものがあります。腎機能は一度損なわれると完全に元に戻るのが難しいため、進行を食い止めたり症状を緩和したりすることが主な治療目的です。
尿酸値コントロールの長期化
尿酸降下薬を用いて血中尿酸値をコントロールするには、数か月から数年単位の継続が必要です。
多くの患者さんは、目標尿酸値を6.0mg/dL以下などに設定し、それに達するまで投薬を続けたうえで、達成後も再発を防ぐために低用量で維持することがあります。
痛風腎の場合は、腎機能を考慮しながら慎重に薬を調整する必要があるため、さらに期間が延びる可能性があります。
尿酸値コントロールに関してよく見られる推移
| 時期 | 尿酸値の目標 | 治療の進め方 |
|---|---|---|
| 初期~中期 | 7.0mg/dL以下を目指す | 低用量から薬を開始し発作予防に配慮 |
| 安定期 | 6.0mg/dL以下を維持 | 維持量を続け、定期的に血液検査を実施 |
| 長期継続期 | 5.0mg/dL台を目標にする場合も | 生活習慣管理を徹底し、発作防止に努める |
腎機能改善の度合い
痛風腎がある程度進行した状態から治療を開始しても、劇的に腎機能が回復する例は多くはなく、適切な治療と生活習慣の改善によって、進行が遅くなる、あるいは安定する場合は十分にあり得ます。
数か月から1年単位で少しずつ腎機能指標が改善することを目指し、こまめなフォローアップが不可欠です。
ライフスタイルの継続的見直し
治療期間が長引くほど、生活習慣の管理が負担と感じられることもあるかもしれませんが、腎臓は体の老廃物を除去する大事な役割を担っており、一度機能が損なわれると生活の質が大幅に落ちる可能性があります。
そのため、無理のない範囲で食習慣や運動習慣を継続し、ストレスを軽減しながら治療に取り組むことが望ましいです。
定期的な検査と調整
痛風腎の患者さんは、一定の間隔で腎機能や血中尿酸値、血圧などをチェックし、薬の種類や用量を調整することが必要です。
何年にもわたって通院しながら値をモニタリングし、悪化の兆候があればすぐに対応策を検討することで、大きな合併症を防ぎ、日常生活の質を維持しやすくなります。
治療期間に関して意識したいポイント
- 短期間での完治は期待しにくい
- 尿酸値が安定しても投薬を継続するケースが多い
- 腎機能の変化を半年から1年ごとに評価する
- 生活習慣の改善を途中で中断しない
痛風腎の治療は長くなるほど経過が見通しにくくなりますが、継続的なフォローによって悪化を防ぎ、一定のレベルで生活を維持できる可能性が高いです。
副作用や治療のデメリットについて
痛風腎の治療薬を使用することで、高尿酸血症をコントロールし、腎臓への負担を軽減するメリットが得られますが、副作用や治療上のデメリットもあります。
尿酸降下薬による副作用
アロプリノールやフェブキソスタットなどの尿酸合成阻害薬では、発疹や肝機能障害、消化器症状などが報告されています。
特にアロプリノールは、まれに重篤な過敏症候群を起こす可能性が指摘されており、投与開始からしばらくは体調に注意を払う必要があります。
ベンズブロマロンなど尿酸排泄を促す薬では、尿路結石ができるリスクがあるため、水分摂取を十分に行うことが重要です。
尿酸降下薬における主な副作用
| 薬剤 | 主な副作用 | 注意すべき点 |
|---|---|---|
| アロプリノール | 発疹、肝機能障害、過敏症 | 肝臓値の定期チェックが必要 |
| フェブキソスタット | 頭痛、肝機能異常、めまい | 使用初期に発作誘発に注意 |
| ベンズブロマロン | 下痢、発疹、尿路結石 | 水分補給を |
痛風発作の誘発
尿酸値を急激に下げると、血中の尿酸が動揺し、すでに関節に蓄積している尿酸結晶が移動して痛風発作を誘発しやすくなる現象があります。
そのため、治療初期には痛風発作を抑えるための薬(コルヒチンやNSAIDsなど)を併用する場合があるものの、発作のリスクを完全にゼロにすることは難しいです。
腎機能への影響
痛風腎の患者さんは、すでに腎機能が弱っているケースが多いため、薬の投与量や選択に制限が出る場合があり、腎障害が進んでいると、アロプリノールなどの薬物が体内に蓄積しやすくなり、副作用のリスクが高まる可能性があります。
定期的な血液検査やクレアチニンの測定を行い、状況に合わせた用量調整が重要です。
痛風腎治療で懸念されるデメリット
- 尿酸降下薬によるアレルギーや肝機能障害のリスク
- 治療初期に痛風発作が起こる可能性
- 腎機能低下がある場合、薬の使い分けが難しい
- 長期的な服薬が必要で経済的負担も増す
痛風腎の保険適用と治療費
以下に記載している治療費(医療費)は目安であり、実際の費用は症状や治療内容、保険適用否により大幅に上回ることがございます。当院では料金に関する以下説明の不備や相違について、一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。
検査にかかる費用
血液検査や尿検査など基本的な検査は保険診療の対象となり、自己負担額は数百円から数千円程度で済むことが多いです。CTやMRIなど高度な画像検査が必要な場合は、1回あたり数千円~1万円程度かかることもあります。
腎生検は侵襲的な検査であり、入院を伴う場合もあるため、数万円程度の自己負担となる可能性があります。
| 検査内容 | 概算費用(保険適用後) | 特記事項 |
|---|---|---|
| 血液検査(尿酸、クレアチニン等) | 1,000~3,000円程度 | 項目数が増えるほどやや高額になる傾向 |
| 尿検査(一般、尿沈渣、定量など) | 500~2,000円程度 | 複数回の検査が必要な場合がある |
| 画像検査(エコー、CTなど) | 1,500~10,000円程度 | 装置や撮影範囲で変動する |
| 腎生検 | 30,000円前後以上 | 入院や局所麻酔などが必要になる場合がある |
薬物療法の費用
尿酸降下薬や血圧降下薬などは、基本的に保険適用される薬剤が多いため、1か月あたりの薬代は数千円程度に収まることが一般的です。
| 薬剤カテゴリ | 例 | 月あたりの自己負担目安 |
|---|---|---|
| 尿酸降下薬 | アロプリノール、フェブキソスタット、ベンズブロマロンなど | 1,000~3,000円程度 |
| 高血圧治療薬 | ACE阻害薬、ARBなど | 1,000~2,000円程度 |
| 発作予防薬(痛風) | コルヒチンなど | 数百~1,000円程度 |
| 補助薬(利尿薬など) | フロセミド等 | 用量や併用により変動 |
入院や外科的処置の費用
急性期の腎障害が重症化し、入院加療が必要となるケースでは、入院費や点滴治療、人工透析などが必要になる場合があり、その費用は1日数千円~1万円程度が上乗せされます。
外科的処置として、腎生検以外に何らかの合併症が発生した場合にも費用がかさむことが予想されるため、早期の段階で治療を開始し、重症化を防ぐことが費用面でも望ましいといえます。
痛風腎治療に伴う主な費用
| 項目 | 費用の目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 外来通院費 | 1回あたり数百~数千円 | 診察、検査、処方箋料など |
| 入院費 | 1日あたり数千~1万円程度 | 病室の種類や地域により差がある |
| 人工透析 | 週3回程度行う場合が多い | 保険適用であっても自己負担は生じる |
| 自費治療 | 場合によって大きく変動 | 新しい薬や特殊な手技など保険外の場合 |
以上
参考文献
Mei Y, Dong B, Geng Z, Xu L. Excess uric acid induces gouty nephropathy through crystal formation: a review of recent insights. Frontiers in endocrinology. 2022 Jul 14;13:911968.
Wang L, Zhang X, Shen J, Wei Y, Zhao T, Xiao N, Lv X, Qin D, Xu Y, Zhou Y, Xie J. Models of gouty nephropathy: exploring disease mechanisms and identifying potential therapeutic targets. Frontiers in Medicine. 2024 Feb 29;11:1305431.
Lusco MA, Fogo AB, Najafian B, Alpers CE. AJKD atlas of renal pathology: gouty nephropathy. American Journal of Kidney Diseases. 2017 Jan 1;69(1):e5-6.
Batuman V. Lead nephropathy, gout, and hypertension. The American journal of the medical sciences. 1993 Apr 1;305(4):241-7.
Fineberg SK, Altschul A. The nephropathy of gout. Annals of Internal Medicine. 1956 Jun 1;44(6):1182-94.
Puig JG, Miranda ME, Mateos FA, Picazo ML, Jiménez ML, Calvin TS, Gil AA. Hereditary nephropathy associated with hyperuricemia and gout. Archives of internal medicine. 1993 Feb 8;153(3):357-65.
Mirzayeva GF, Jabbarov OO, Tursunova LD, Buvamukhamedova NT. GOUTY NEPHROPATHY: DIAGNOSIS, TREATMENT APPROACHES. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. 2021;1(11):503-9.
Reif MC, Constantiner A, Levitt MF. Chronic gouty nephropathy: a vanishing syndrome?. New England Journal of Medicine. 1981 Feb 26;304(9):535-6.
Batuman, V., Maesaka, J.K., Haddad, B., Tepper, E., Landy, E. and Wedeen, R.P., 1981. The role of lead in gout nephropathy.
Zhang YZ, Sui XL, Xu YP, Gu FJ, Zhang AS, Chen JH. NLRP3 inflammasome and lipid metabolism analysis based on UPLC-Q-TOF-MS in gouty nephropathy. International journal of molecular medicine. 2019 Jul;44(1):172-84.