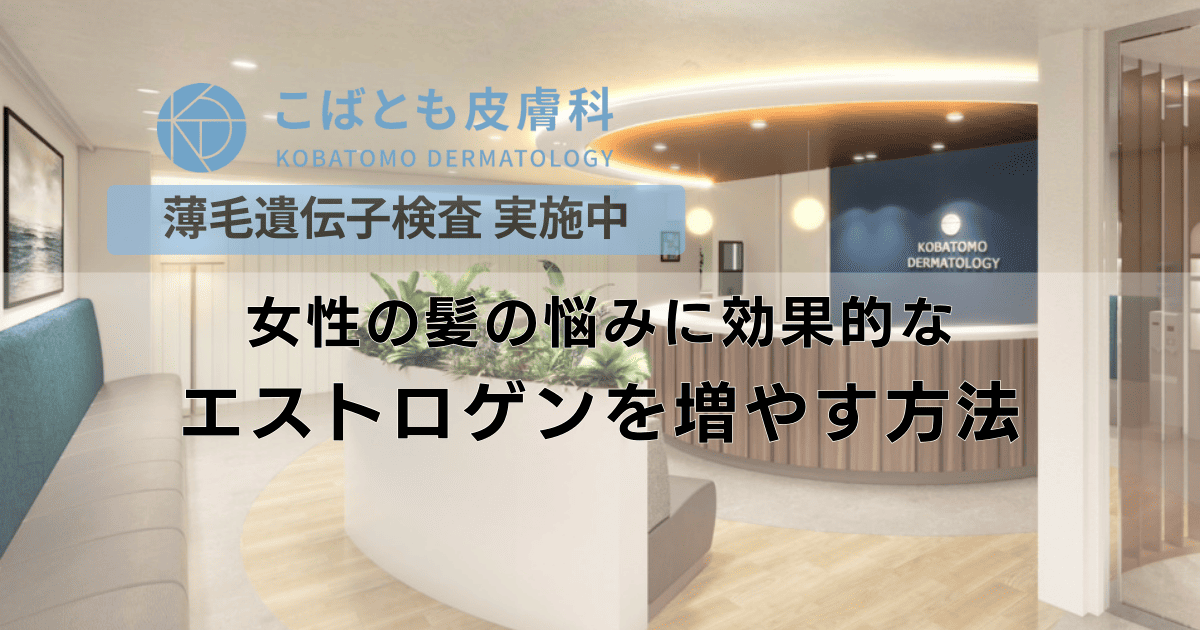髪のボリュームが減ってきた、抜け毛が増えた気がした、といった髪の悩みで来院される方が年々増えています。
女性の髪の健康には、女性ホルモンの一つであるエストロゲンが深く関わっています。エストロゲンは髪の成長を促してハリやコシを保つ働きをしますが、加齢や生活習慣の乱れによって減少する場合があります。
この記事では、エストロゲンの役割や減少の原因、そして健やかな髪を育むために日常生活で実践できるエストロゲンを増やす方法、特に食事に焦点を当てて詳しく解説します。
この記事の執筆者

小林 智子(こばやし ともこ)
日本皮膚科学会認定皮膚科専門医・医学博士
こばとも皮膚科院長
2010年に日本医科大学卒業後、名古屋大学医学部皮膚科入局。同大学大学院博士課程修了後、アメリカノースウェスタン大学にて、ポストマスターフェローとして臨床研究に従事。帰国後、同志社大学生命医科学部アンチエイジングリサーチセンターにて、糖化と肌について研究を行う。専門は一般皮膚科、アレルギー、抗加齢、美容皮膚科。雑誌を中心にメディアにも多数出演。著書に『皮膚科医が実践している 極上肌のつくり方』(彩図社)など。
こばとも皮膚科関連医療機関
エストロゲンとは?女性の健康と髪への影響
エストロゲンは女性らしさを作るホルモンとして知られ、女性の生涯を通じて心身の健康に多大な影響を与えます。特に髪の健康維持には重要な役割を果たしています。
エストロゲンの基本的な役割
エストロゲンは、主に卵巣で作られる女性ホルモンです。
第二次性徴の発現や丸みのある体つきの形成、妊娠・出産に関わるだけでなく、自律神経の安定や骨密度の維持、コレステロール値の調整、皮膚や粘膜の潤いを保つなど全身の健康維持に貢献します。
エストロゲンと女性ホルモンのバランス
女性ホルモンには、エストロゲン(卵胞ホルモン)とプロゲステロン(黄体ホルモン)の2種類があります。
これらは互いに影響し合いながら、月経周期や妊娠・出産などをコントロールしています。
このバランスが崩れると、月経不順や更年期症状、そして髪のトラブルなど様々な不調が現れる場合があります。
女性ホルモンの主な種類と役割
| ホルモン名 | 主な分泌場所 | 主な役割 |
|---|---|---|
| エストロゲン | 卵巣 | 女性らしい体つき、妊娠準備、髪の成長促進、肌のハリ維持など |
| プロゲステロン | 卵巣(黄体) | 妊娠の維持、体温上昇、皮脂分泌促進など |
髪の成長サイクルとエストロゲンの関わり
髪の毛は「成長期」「退行期」「休止期」というサイクルを繰り返しています。エストロゲンは「成長期」を長く維持する働きがあり、髪が太く長く成長するのを助けます。
また、髪の色素細胞(メラノサイト)の働きを活発にし、ツヤのある黒髪を保つことにも関与します。
エストロゲン減少が引き起こす髪の変化
エストロゲンが減少すると髪の成長期が短くなり、休止期にとどまる毛髪の割合が増加します。
これにより、髪が十分に成長する前に抜け落ちてしまい、全体的に髪が細くなったり薄毛(びまん性脱毛症など)が進行したりする原因となります。
また、髪のハリやコシ、ツヤが失われるケースもあります。
なぜエストロゲンは減少するのか?主な原因
エストロゲンの分泌量は一生を通じて変動しますが、特定の要因によって通常よりも早く、または大きく減少することがあります。
加齢による自然な変化
女性のエストロゲン分泌量は20代後半から30代前半をピークに、その後徐々に減少し始めます。特に40代半ば以降の更年期と呼ばれる時期には、卵巣機能の低下に伴い分泌量が急激に減少します。
これは自然な生理現象ですが、髪への影響が現れやすくなる時期でもあります。
ストレスとホルモンバランスの乱れ
精神的、身体的なストレスは、ホルモン分泌をコントロールする脳の視床下部や下垂体に影響を与えます。
過度なストレスが続くと自律神経やホルモンバランスが乱れ、卵巣機能が低下してエストロゲンの分泌量が減少しやすいです。
睡眠不足の影響
睡眠中は、体の修復やホルモン分泌の調整が行われる重要な時間です。
睡眠不足が続くと自律神経のバランスが崩れ、ホルモン分泌にも悪影響を及ぼします。結果として、エストロゲンの分泌が抑制される可能性があります。
睡眠とホルモンへの影響
| 要因 | 影響 | 対策例 |
|---|---|---|
| 睡眠不足 | 自律神経の乱れ、ホルモン分泌の抑制 | 毎日同じ時間に寝起きする、寝る前のスマホ操作を控える |
| 不規則な睡眠 | 体内時計の乱れ、ホルモンバランスの悪化 | 休日も平日と同じリズムを心がける |
過度なダイエットや栄養不足
極端な食事制限によるダイエットは体に必要な栄養素が不足するだけでなく、ホルモンバランスを大きく乱す原因となります。
なかでもコレステロールはエストロゲンを含む性ホルモンの材料となるため、不足するとエストロゲンの生成が滞る可能性があります。また、栄養バランスの偏りも同様に影響します。
エストロゲンを増やすための基本的な考え方
エストロゲンの減少は避けられない部分もありますが、日々の生活を見直すと、バランスを整えて健やかな状態を維持できます。
ここでは、エストロゲンを増やすための基本的な方法をみていきましょう。
ホルモンバランスを整える重要性
エストロゲンだけを増やそうとするのではなく、プロゲステロンとのバランスを含めた女性ホルモン全体のバランスを整えることが重要です。
体は非常に繊細なバランスの上に成り立っており、特定のホルモンだけを過剰にしようとすると、かえって不調を招く場合もあります。
生活習慣の見直しから始める
ホルモンバランスを整えるためには、食事や睡眠、運動やストレス管理といった基本的な生活習慣の見直しが土台となります。
規則正しい生活を送り、心身の健康を維持することが、ホルモンバランスの安定につながります。
食事改善による取り組み
毎日の食事は体を作る基本であり、ホルモンバランスにも大きな影響を与えます。
エストロゲン様作用を持つ食品や、ホルモンの生成・調節に必要な栄養素の意識的な摂取が、エストロゲンを増やす方法の一つとして考えられます。
食事改善のポイント
- バランスの取れた栄養摂取
- エストロゲン様作用のある食品の活用
- ホルモン生成に必要な栄養素の確保
専門家への相談も視野に
セルフケアで改善が見られない場合や、急激な変化を感じる場合は、自己判断せずに婦人科医や専門医に相談することが大切です。
ホルモン補充療法(HRT)など、医学的な取り組みが必要な場合もあります。
食事でエストロゲンを増やす方法としてのエストロゲン様作用を持つ食品
特定の食品には体内でエストロゲンと似た働きをする成分が含まれており、これらの摂取がエストロゲンを補う一つの方法として注目されています。
バランスの良い食事を基本としながら、エストロゲンに似た働きをする成分を含んだ食品を上手に取り入れましょう。
大豆製品とその効果
大豆に含まれる「大豆イソフラボン」は化学構造がエストロゲンと似ており、体内でエストロゲン様作用を発揮します。
エストロゲンが不足している場合はその働きを補い、逆に過剰な場合はその作用を抑制する方向に働くとも言われています。
豆腐や納豆、味噌や豆乳などを日常的に摂取することをおすすめします。
主な大豆製品とイソフラボン含有量の目安(食品100gあたり)
| 食品名 | イソフラボンアグリコン換算値(mg) | 手軽な摂取方法 |
|---|---|---|
| 納豆(1パック約45g) | 約33mg | ご飯にかける、そのまま食べる |
| 豆腐(木綿1/3丁約100g) | 約20mg | 冷奴、味噌汁の具 |
| 豆乳(コップ1杯約200ml) | 約50mg | そのまま飲む、料理に使う |
※含有量は目安であり、製品によって異なります。
イソフラボンを多く含むその他の食品
大豆以外にも、イソフラボンを含む食品はあります。例えば、葛(くず)の根に含まれるプエラリンもイソフラボンの一種です。
ただし、含有量や吸収率は大豆製品に比べて低い場合が多いです。
ナッツ類や種子類の活用
アーモンドやくるみ、カシューナッツなどのナッツ類、亜麻仁(フラックスシード)、ごまなどの種子類には「リグナン」という成分が含まれています。
リグナンも植物性エストロゲンの一種であり、腸内細菌によってエストロゲン様作用を持つ物質に変換されます。
ナッツ類や種子類は、おやつや料理のトッピングとして取り入れやすいでしょう。
リグナンを含む食品
| 食品カテゴリ | 具体例 | 取り入れ方のヒント |
|---|---|---|
| ナッツ類 | アーモンド、くるみ | 間食、サラダのトッピング |
| 種子類 | 亜麻仁、ごま | スムージー、ヨーグルト、和え物 |
バランスの取れた食事の基本
特定の食品に偏るのではなく、主食・主菜・副菜を揃えて多様な食品から栄養を摂取する工夫が最も重要です。
エストロゲン様作用のある食品も、あくまでバランスの取れた食事の一部として考えるようにしましょう。
エストロゲンを増やすために意識したい栄養素
エストロゲンの生成や代謝、ホルモンバランスの調整には、様々な栄養素が関与しています。
特定の食品だけでなく、これらの栄養素を意識的に摂取することも、健やかな髪と体を保つ上で大切です。
ビタミン類の役割(ビタミンB群、C、Eなど)
ビタミンB群(特にB6)は、エストロゲンの代謝に関与し、ホルモンバランスを整える働きがあります。
ビタミンCはストレス対抗ホルモンの生成を助け、ストレスによるホルモンバランスの乱れを緩和します。
ビタミンEは、血行を促進し、ホルモン分泌を調整する脳下垂体や卵巣の働きをサポートします。抗酸化作用も持ち合わせていて、細胞の老化を防ぐ効果も期待できます。
ホルモンバランスに関わるビタミン
| ビタミン | 主な働き | 多く含む食品例 |
|---|---|---|
| ビタミンB6 | エストロゲンの代謝、神経伝達物質の合成 | カツオ、マグロ、鶏肉、バナナ |
| ビタミンC | 抗ストレス作用、抗酸化作用、コラーゲン生成 | パプリカ、ブロッコリー、キウイ、イチゴ |
| ビタミンE | 抗酸化作用、血行促進、ホルモン分泌調整 | アーモンド、かぼちゃ、アボカド、植物油 |
ミネラル類の重要性(亜鉛、鉄など)
亜鉛は、細胞分裂やホルモンの合成に必要で、卵巣機能を正常に保つためにも重要なミネラルです。
鉄分は全身への酸素供給に不可欠であり、不足すると貧血を引き起こし、頭皮の血行不良や栄養不足につながる可能性があります。
良質なタンパク質の摂取
髪の主成分はケラチンというタンパク質です。また、ホルモンや酵素など、体の機能を維持するための様々な物質もタンパク質から作られます。
肉や魚、卵や大豆製品、乳製品などから良質なタンパク質を十分に摂取する工夫が、健康な髪とホルモンバランスの基礎となります。
食物繊維の働き
食物繊維は、腸内環境を整える働きがあることで有名です。
腸内環境が悪化すると、栄養素の吸収が悪くなるだけでなく、体全体の代謝やホルモンバランスにも影響を与える可能性があります。
野菜や果物、海藻やきのこ類などを積極的に摂取し、腸内環境を良好に保ちましょう。
生活習慣でエストロゲンを増やす方法
食事だけでなく、日々の生活習慣もエストロゲンの分泌やホルモンバランスに大きく影響します。健やかな髪のためにも、いちど生活全体を見直してみましょう。
質の高い睡眠を確保する
十分な睡眠時間を確保するのはもちろん、睡眠の質を高める工夫も重要です。寝る前にリラックスできる環境を作り、毎日決まった時間に寝起きするなど、規則正しい睡眠習慣を心がけましょう。
深い睡眠中に成長ホルモンなどが分泌され、体の修復やホルモンバランスの調整が行われます。
ストレスを上手に管理する
忙しい現代社会においてストレスを完全になくすのは難しいですが、自分なりのストレス解消法を見つけて溜め込まないようにすることが大切です。
趣味の時間を持つ、軽い運動をする、友人と話す、ゆっくり入浴するなど、リラックスできる時間を作りましょう。
- 軽い運動(ウォーキング、ヨガ)
- 趣味や好きなことに没頭する時間
- 十分な休息とリラックス
適度な運動を取り入れる
ウォーキングやジョギング、ヨガなどの適度な運動は血行を促進し、ストレス解消にもつながります。
血行が良くなると頭皮にも栄養が行き渡りやすくなり、髪の健康にも良い影響を与えます。また、運動は自律神経のバランスを整える効果も期待できます。
ただし、過度な運動は逆にストレスとなる可能性があるので注意が必要です。
喫煙や過度な飲酒を避ける
喫煙は血管を収縮させて血行を悪化させるだけでなく、卵巣機能を低下させ、エストロゲンの分泌を減少させる可能性があります。
また、過度な飲酒も肝臓に負担をかけ、ホルモンバランスを乱す原因となり得ます。
健やかな髪と体を維持するためには、禁煙し、飲酒は適量にとどめるほうが望ましいです。
日常のヘアケア習慣
エストロゲンを増やす直接的な方法ではありませんが、正しいヘアケアは頭皮環境を整え、髪へのダメージを減らす上で大切です。
洗浄力の強すぎるシャンプーを避けて頭皮を優しくマッサージするように洗い、ドライヤーでしっかり乾かすなど、基本的なケアを見直しましょう。
エストロゲンを増やす上での注意点
エストロゲンを増やそうと努力する際には、いくつか注意すべき点があります。正しい知識を持ち、安全に取り組むことが重要です。
サプリメント利用の考え方
大豆イソフラボンなどのサプリメントも市販されていますが、利用には注意が必要です。
食事からの摂取に加えてサプリメントを安易に利用すると、過剰摂取になる可能性があります。
利用するときは製品の注意書きをよく読み、摂取目安量を守ることが大切です。まずは食事や生活習慣の改善を優先しましょう。
過剰摂取のリスクについて
特定の成分、例えば大豆イソフラボンなどを長期にわたり過剰に摂取した場合の安全性については、まだ十分に解明されていない部分もあります。
食品安全委員会では、大豆イソフラボンの安全な一日摂取目安量の上限値を設定しています。
サプリメントなどを利用する場合は特に、この上限値を超えないように注意が必要です。
大豆イソフラボンの摂取目安量
| 対象 | 摂取目安量(上限値) | 備考 |
|---|---|---|
| 成人 | 70-75mg/日(アグリコン換算) | 通常の食事からの摂取は問題ない。特定保健用食品やサプリメントでの上乗せ摂取に注意。 |
| 妊婦・授乳婦・小児 | 長期的な安全性は不明確 | サプリメント等での習慣的な上乗せ摂取は推奨されない。 |
※出典:食品安全委員会「大豆イソフラボンに関するQ&A」等に基づき作成
自己判断せず専門家へ相談
髪の悩みや体調の変化が気になる場合は、自己判断でサプリメントなどに頼るのではなく、まずは医師に相談しましょう。
特に、婦人科系の疾患がある方や治療中の方は、エストロゲン様作用のある食品やサプリメントの摂取について必ず主治医に確認してください。
他の病気との関連性
エストロゲンの変動は、乳がんや子宮体がんなどの婦人科系疾患のリスクと関連することが知られています。
ホルモンバランスに影響を与える可能性のある食品やサプリメントの摂取については、これらのリスクも考慮して慎重に判断する必要があります。
よくある質問
さいごに、エストロゲンと髪に関する、患者さんからよく寄せられる質問にお答えします。
- 大豆イソフラボンの摂取目安は?
-
食品安全委員会は、大豆イソフラボンの安全な一日摂取目安量の上限を、アグリコン換算で70~75mgとしています。
これは、通常の食事(納豆1パック、豆腐1/3丁程度)で摂取する量に加えて、特定保健用食品やサプリメントで上乗せする場合の目安です。
日常的な食事からの摂取であれば、過剰摂取を心配する必要は低いと考えられます。
- 食事だけでエストロゲンを増やすことは可能?
-
食事だけで体内のエストロゲン量を大幅に増やすのは難しいと考えられます。
しかし、大豆イソフラボンのようにエストロゲン様作用を持つ食品や、ホルモンバランスを整える栄養素を摂取することは、エストロゲンの働きを補ったり、バランスを整えたりする上で役立ちます。
食事改善は、あくまで健康的な体づくりの一環として捉えると良いでしょう。
- エストロゲンが増えれば必ず髪は増える?
-
エストロゲンは髪の成長期を維持する上で重要な役割を果たしますが、髪の健康にはエストロゲン以外にも多くの要因が関わっています。
遺伝や他のホルモンバランス、栄養状態や血行、頭皮環境やストレスなどが複雑に影響し合っています。
そのため、エストロゲンの増加だけが、必ずしも髪が増えることに直結するわけではありません。総合的な取り組みが必要です。
- クリニックではどのような治療を行う?
-
女性の薄毛治療専門クリニックでは、まず丁寧なカウンセリングと診察により、薄毛の原因を特定します。
原因に応じて内服薬(ミノキシジル、スピロノラクトンなど)や外用薬、メソセラピー(頭皮への有効成分注入)や生活習慣指導などを組み合わせた、一人ひとりに合わせた治療計画を提案します。
エストロゲンの補充が適切な場合は、連携する婦人科医と協力して治療を進めることもあります。
参考文献
GOLUCH-KONIUSZY, Zuzanna Sabina. Nutrition of women with hair loss problem during the period of menopause. Menopause Review/Przegląd Menopauzalny, 2016, 15.1: 56-61.
CAMACHO-MARTINEZ, Francisco M. Hair loss in women. In: Seminars in cutaneous medicine and surgery. No longer published by Elsevier, 2009. p. 19-32.
HERSKOVITZ, Ingrid; TOSTI, Antonella. Female pattern hair loss. International Journal of Endocrinology and Metabolism, 2013, 11.4: e9860.
GUO, Emily L.; KATTA, Rajani. Diet and hair loss: effects of nutrient deficiency and supplement use. Dermatology practical & conceptual, 2017, 7.1: 1.
RAJPUT, Rajendrasingh. A scientific hypothesis on the role of nutritional supplements for effective management of hair loss and promoting hair regrowth. J Nutr Health Food Sci, 2018, 6.3: 1-11.
OLSEN, Elise A., et al. Evaluation and treatment of male and female pattern hair loss. Journal of the American Academy of Dermatology, 2005, 52.2: 301-311.
OHNEMUS, Ulrich, et al. The hair follicle as an estrogen target and source. Endocrine reviews, 2006, 27.6: 677-706.
SINCLAIR, Rodney; WEWERINKE, M.; JOLLEY, D. Treatment of female pattern hair loss with oral antiandrogens. British Journal of Dermatology, 2005, 152.3: 466-473.