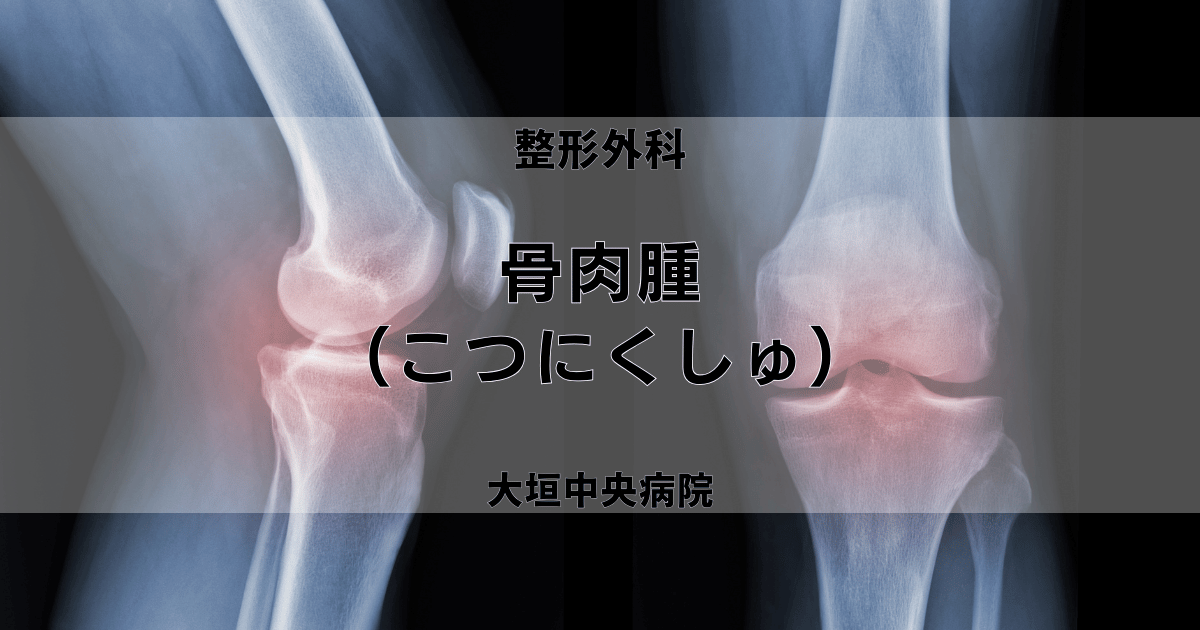骨肉腫(こつにくしゅ、Osteosarcoma)とは、主に骨を形成する細胞が悪性化して生じる骨のがんの一種で、腫瘍細胞が未成熟な骨(類骨)を産生するのが特徴です。
小児から若年層に多く発生し、大腿骨や脛骨、上腕骨などの骨端付近にできるケースが目立ちます。
痛みや腫れなどの初期症状は、成長痛やスポーツ障害と間違えやすく、見落としに注意しなければなりません。放置すると転移のリスクが高まるため、疑わしい症状を感じた場合は早めに医療機関で受診することが大切です。
治療には手術や化学療法などが用いられ、長期的な計画が求められます。
治療成績は近年向上しており、外科的切除と術後補助化学療法の導入により5年生存率は60%以上にまで改善しました。
この記事の執筆者

臼井 大記(うすい だいき)
日本整形外科学会認定専門医
医療社団法人豊正会大垣中央病院 整形外科・麻酔科 担当医師
2009年に帝京大学医学部医学科卒業後、厚生中央病院に勤務。東京医大病院麻酔科に入局後、カンボジアSun International Clinicに従事し、ノースウェスタン大学にて学位取得(修士)。帰国後、岐阜大学附属病院、高山赤十字病院、岐阜総合医療センター、岐阜赤十字病院で整形外科医として勤務。2023年4月より大垣中央病院に入職、整形外科・麻酔科の担当医を務める。
骨肉腫の病型
骨肉腫(こつにくしゅ)の病理学的分類は、発生部位(骨内か骨表面か)と悪性度に基づいてなされ、主に「中央(骨髄)発生の高悪性度骨肉腫」と「表在(骨表面)発生の骨肉腫(高~低悪性度)」のグループに分けられます。
さらに、各グループ内には「従来型骨肉腫」「特殊型骨肉腫」「表在型骨肉腫」の亜型があります。
従来型骨肉腫(中心性骨肉腫)
いわゆる「骨肉腫」の大部分(約80%)を占める代表的なタイプで、多くは骨の骨髄内から発生する高悪性度の骨肉腫です。
10~20歳代に好発し、病理組織学的には間質に骨様の組織が見られます。
従来型は細胞の形態によって骨芽細胞型・軟骨芽細胞型・線維芽細胞型などに分類されますが、これらの亜分類間で臨床経過に大きな差はありません。
長管骨の骨幹端部(特に大腿骨遠位部や脛骨近位部など膝周辺)に好発し、画像上は骨の骨融解像(骨破壊)と骨新生像が混在する所見を呈します。
特殊型骨肉腫(高悪性度)
従来型以外にも希少な高悪性度骨肉腫の亜型があります。
代表的なのは「血管拡張型骨肉腫」で、腫瘍内に血液で満たされた嚢胞状の空洞が多数見られる型です。
血管拡張型は骨肉腫全体の約4%と報告され、画像上は膨隆性の骨嚢胞様所見を呈し、類似する良性病変の動脈瘤様骨嚢腫(ABC)との鑑別が問題になります。
かつて、血管拡張型は予後不良と考えられていましたが、近年の報告では従来型との差はないともされています。
そのほか「小細胞骨肉腫」は、1~2%とさらにまれな亜型で、小円形の腫瘍細胞が増殖する点でユーイング肉腫と似ていますが、腫瘍細胞による類骨形成を認めると骨肉腫と診断されます。
「低分化型骨肉腫(低悪性度中心性骨肉腫)」も1~2%程度にみられますが、病理診断が難しく、単純切除では高悪性度に転化するおそれがあるため注意が必要です。
表在型骨肉腫
骨の表面から発生する骨肉腫で、悪性度によりさらに「傍骨性骨肉腫」「骨膜骨肉腫」「高悪性度表在骨肉腫」の3亜型に分類されます。
傍骨性骨肉腫
骨膜の外側表面から発生する低悪性度の骨肉腫で、骨肉腫全体の4~6%を占めます。
20~30歳代に好発し、特に大腿骨遠位の骨後面に生じるケースが多いタイプです。
増殖は緩徐でX線では骨皮質表面に密に石灰化した分葉状の腫瘤として描出され、髄腔内への進展は通常みられません。
骨膜骨肉腫
骨膜下に発生する中間的悪性度の骨肉腫で、傍骨性より頻度は低く、10~20歳代に発生します。
軟骨様の基質を多く含むのが特徴で、画像上は骨表面の紡錘状の骨硬化性病変と骨膜反応を呈します。
悪性度は高くはありませんが局所再発しやすいため外科的切除が推奨され、化学療法の有効性は定かでないとされています。
予後は従来型より良好ですが、傍骨性ほどは良くない中間の成績です。
高悪性度表在骨肉腫
骨表面発生のなかでは極めてまれな型で、全骨肉腫の1%未満ですが、組織学的には高悪性度であり振る舞いは従来型に類似します。
表在型でも急速に大きくなる腫瘍では、骨髄内への侵入が起こるケースもあり、従来型に準じた集学的治療が必要です。
骨肉腫の症状
骨肉腫(こつにくしゅ)の症状は、主に腫瘍が発生した骨の局所症状で、発熱や体重減少などの全身症状はほとんど現れません。
発症部位によっては、痛みがスポーツ障害や関節痛などと紛らわしく、見逃してしまうおそれがあります。
初期段階の症状
- 運動後に痛みを感じやすい
- 朝よりも夜間に痛みが強まるケースがある
- 安静にしていても鈍い痛みが続く
初期段階の痛みは軽度の場合も多く、単なる使いすぎや打撲のように見えるため、発見が遅れるおそれがあります。
間欠的で夜間に強まる場合があるのも初期の痛みの特徴です
また、痛む部位に小さな腫れや熱感が出現するケースもあります。
中期から進行段階の症状
- 激しい痛みが24時間続く
- 腫れが大きくなり、皮膚表面が突出してくる
- 関節を動かしづらくなるため、歩行困難や姿勢の不良につながる
骨肉腫が進行すると、痛みや腫れが強まるだけではなく、患部の機能障害や骨折のリスクが高まります。
特に骨端付近に発生した場合、関節をまたいで腫瘍が広がり、関節可動域が制限されやすくなります。
痛みが増して鎮痛薬が手放せなくなったら、骨肉腫の進行を疑いましょう。明らかな変形や大きな腫瘤がある場合は早急に受診してください。
部位による痛みと特徴
骨肉腫は多くの場合、大腿骨や脛骨に生じますが、上腕骨や骨盤に発生するケースも存在します。
部位ごとの痛み方や身体への影響を知っておくと、早期発見につながるでしょう。
| 部位 | 痛みの特徴 |
|---|---|
| 大腿骨 | ・歩行時や走行時に痛みが出やすい ・階段の上り下りが困難になる |
| 脛骨 | ・走る動作やジャンプ時に痛みが顕著 になる ・膝下に腫脹を感じやすい |
| 上腕骨 | ・腕を上げたり物を持ち上げる動作で痛みやすい ・肩関節周りの可動域が制限される |
| 骨盤 | ・初期は痛みがあいまいで見落としやすい ・進行すると坐骨や股関節付近に激痛が走る |
骨肉腫の原因
骨肉腫(こつにくしゅ)がなぜ発生するのかは完全には解明されていません。
しかし、遺伝的な要因や環境要因である放射線被曝、骨への外傷などがリスクを高める要因として挙げられます。
遺伝的要因
特定の遺伝子異常と骨肉腫の発症には関連があるとの報告があります。
大部分が散発例ですが、家族性のがん症候群がある場合や、親族に骨肉腫を発症した人がいる場合は、リスクがやや高まるといわれています。
放射線被曝
過去に放射線療法を受けた部位に骨肉腫が発生する二次がんのリスクがあります。
特に、小児期に放射線療法を受けた場合、成人してから骨肉腫が生じる可能性がわずかに高くなると知られています。
悪性転化
骨の良性疾患が骨肉腫に二次的に転化するケースもあります。
代表例がPaget病(高齢者にみられる変形性骨疾患)で、Paget病患者の約1%に骨肉腫などの骨肉腫瘍が発生するとされています。
特に、全身の多発性に骨病変がある重症例で悪性化のリスクが高まります。
また、多発性骨軟骨腫症(遺伝性骨端軟骨腫症)では良性の骨軟骨腫が多数できますが、一部が悪性化(軟骨肉腫が多いが骨肉腫の場合もあり)すると知られています。
線維性異形成症(骨繊維性異形成、McCune-Albright症候群など)でも、ごくまれに骨肉腫への悪性転化が報告されています。
環境要因
生活習慣については、喫煙や食事といった因子との明確な関連は示されていません(骨肉腫は小児~若年で発症するため生活習慣の影響は小さいと考えられます)。
一方で、成長に伴う要因との関連が示唆されており、骨肉腫患者は同年齢の平均より長身であるとの指摘があります。
思春期の急速な骨成長期に発症が集中するため、急激な骨の成長やホルモン環境が発症に関与している可能性もあります。
実際、骨肉腫の好発年齢は男女で差があり(女子のピークは男子よりやや早い)、これは男女の成長スパート時期の差と一致しています。
このような観点から「骨肉腫は成長期における骨形成ストレスに起因するのではないか」との仮説もありますが、詳細な機序は未解明です。
骨肉腫の検査・チェック方法
骨肉腫(こつにくしゅ)の診断には、画像検査や血液検査、病理検査などを総合的に行う必要があります。
早期に検査を受けると治療方針を定めやすくなり、治療の選択肢も広がります。
画像検査(X線、CT、MRIなど)
骨肉腫の診断では、まずX線撮影を行い、骨の変形や透亮像、骨膜反応などの特徴的な所見を確認します。
さらに、CTやMRIを実施し、腫瘍の範囲や周辺組織への浸潤状況を把握します。
- X線検査:骨の構造や病変の概略をとらえる
- 骨破壊像
- 骨膜反応によるサンバースト状陰影
- 骨膜が持ち上げられることによるCodman三角という陰影
- CT検査:骨の断面像を詳細に確認できる
- 肺へ転位しやすいため胸部CTも確認する場合が多い
- MRI検査:軟部組織や骨髄内への浸
- 骨髄内への腫瘍の広がりを確認
画像検査で確認する主なポイント
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 腫瘍の位置や大きさ | 腫瘍が骨のどの部分に、どれくらいの範囲で存在しているかを把握 |
| 周辺組織への広がり | 筋肉や関節、血管、神経への侵襲があるかどうかを調べる |
| 骨膜反応の種類 | サンバースト状、コッドマン三角など特有の骨膜反応の有無を確認 |
| 転移の兆候 | 肺やほかの骨へ転移している可能性を胸部CTなどでチェック |
血液検査と腫瘍マーカー
骨肉腫そのものを特定する特異的な腫瘍マーカーは確立されていませんが、炎症反応や組織破壊の度合いを推定する指標として、LDH(乳酸脱水素酵素)やALP(アルカリフォスファターゼ)の値を参考にするケースが多いです。
- LDH:腫瘍の活動性が高いと上昇傾向を示す
- ALP:骨形成が活発な時期や骨疾患で高値になる
- CRP:炎症や感染症の有無を示す指標
ただし、これらの値は骨肉腫特有のものではなく、他の病気でも上昇する場合があります。
病理検査
骨肉腫を確定診断するには、腫瘍組織の一部を採取して顕微鏡で調べる病理検査が必要です。
細い針で骨や腫瘍からサンプルを採取する針生検や、切開してより大きな組織を得る切開生検を行います。
- 針生検:局所麻酔下で行い、身体的負担が少ない
- 切開生検:正確な診断が可能だが、感染リスクや出血リスクがやや高まる
骨肉腫の治療方法と治療薬、リハビリテーション、治療期間
骨肉腫(こつにくしゅ)の治療は、外科的治療(手術)、化学療法、放射線療法などを組み合わせる集学的治療が一般的です。
腫瘍の大きさや悪性度、転移の有無などを考慮し、複数の診療科が連携して総合的に治療方針を決定します。
術後のリハビリテーションや治療期間の目安も含め、長期的な視点で計画を立てることが必要です。
基本的な流れとしては、術前化学療法で腫瘍を縮小させたあとに手術を行い、術後に残存腫瘍細胞を根絶する目的で化学療法を追加します。
外科的治療(手術)
- 患部切除術:腫瘍の完全な摘出を目指し、再発リスクを下げる
- 骨再建術:切除範囲が大きい場合、人工関節や骨移植で補強する
- 患肢温存手術:四肢の切断を回避するため、機能温存を重視した再建を行う
骨肉腫は局所浸潤性が強いため、周囲に一定の正常組織のマージン(数cm)を付けて切除する「広範切除」が原則となります。
患部切除後には、人工関節や自家骨移植などで機能再建を図るケースもあります。
化学療法
- 術前化学療法:腫瘍を縮小させ、手術で切除しやすくする効果を期待
- 術後化学療法:残存がん細胞や微小転移を抑える目的
- 代表的な薬剤:メソトレキセート(高用量MTX)、ドキソルビシン、シスプラチン、イホスファミド、エトポシドなど
手術の前後に化学療法を実施して、転移や再発リスクの低減を狙います。
多剤併用によって治療成績が向上してきたこともあり、高悪性度骨肉腫に対しては、効果が期待できる複数の薬剤を組み合わせる場合が多いです。
化学療法は点滴または経口薬で行いますが、点滴の場合は一定期間入院が必要となる可能性があります。
放射線療法
骨肉腫は放射線感受性が低いといわれていますが、手術が困難な部位や、高齢で手術のリスクが高い場合などには放射線療法も検討します。
放射線の照射により、腫瘍の増殖を抑え、痛みなどの症状を軽減する狙いがあります。
また、化学療法抵抗性で手術不能の患者に対し、重粒子線治療や陽子線治療を試みるケースもあります。
- 肺などへの転移がある場合、疼痛コントロールの一環として照射する場合がある
- 手術の補助療法としての活用は限定的
- 長期的にみると放射線による二次がんのリスクがわずかに高まる可能性がある
リハビリテーションと治療期間の目安
手術での切除範囲が大きいほど、筋力や可動域の回復に時間がかかるため、長期的なリハビリテーションが必要です。
化学療法や放射線療法の副作用による体力低下も考慮しながら、専門のリハビリスタッフと協力して進めていきます。
- 術後早期:痛みや腫れを管理しながら、患部の軽いストレッチやアイソメトリック運動を行う
- 中期:歩行訓練や関節可動域の拡大を目指す
- 後期:筋力トレーニングやバランス訓練を強化し、日常生活動作の回復を図る
- 維持期:定期的なリハビリを行い、再発や機能低下を防止する
リハビリテーションは術後すぐから数年単位で継続し、段階的に目標を上げていきます。
また、化学療法の期間は数カ月から1年程度に及ぶ可能性があります。
薬の副作用や治療のデメリット
骨肉腫(こつにくしゅ)の治療法である化学療法や放射線療法、外科的手術にはさまざまな副作用やデメリットがあります。
化学療法薬の副作用
化学療法で使用する薬剤は、正常な細胞にも影響を及ぼす場合があります。
- 脱毛
- 食欲不振
- 吐き気や嘔吐
- 骨髄抑制による白血球・赤血球・血小板の減少
- 口内炎や口腔内のただれ
- 腎障害
- 心筋障害(心毒性)
- 聴力障害
- 肝障害
- 成長障害や性的発達への影響
- 不妊
副作用緩和をサポートする取り組み
| 方法 | 具体例 |
|---|---|
| 制吐剤や補助療法の活用 | 吐き気止め薬の処方、心身のリラクゼーション療法など |
| 感染対策の徹底 | 手洗い、うがい、マスクの着用、人ごみを避ける |
| 栄養相談や食事指導 | 食べやすい形態の食事や高カロリーの間食を取り入れる |
| 休息と睡眠の確保 | 十分な睡眠や適度な運動により免疫力を維持 |
放射線療法のリスク
局所制御や疼痛緩和のために行う放射線療法には、皮膚トラブルや骨の変形などのリスクがあります。
- 照射部位の皮膚トラブル(やけど様症状、乾燥)
- 長期的に見た骨の変形や骨折リスクの上昇
- 放射線誘発性の二次がんリスク
比較的若い世代で骨肉腫の治療を受ける場合、将来的な影響も踏まえたうえで放射線療法を検討する必要があります。
手術による機能低下
腫瘍を確実に切除するための手術では、健康な組織も含めて大きく切除する場合があり、手術部位の機能が低下したり、外見が変わったりするおそれがあります。
- 肢温存手術でも関節可動域が一部失われることがある
- 神経や血管も再建が必要な場合、手術時間やリハビリが長期化する
- 義肢や装具の利用が必要なケースもある
- 慢性的な痛みやしびれが出るおそれがある
- 手術により外見が変化する可能性がある
保険適用と治療費
以下に記載している治療費(医療費)は目安であり、実際の費用は症状や治療内容、保険適用否により大幅に上回ることがございます。当院では料金に関する以下説明の不備や相違について、一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。
骨肉腫(こつにくしゅ)の手術、化学療法、放射線療法などは基本的に保険適用となります。
また骨肉腫を含む小児がんは小児慢性特定疾病に指定されており、公費による医療費助成を受けられます。
ただし、先進医療技術を伴う治療(特殊な人工関節など)は別途費用がかかる場合があるため、事前の確認が必要です。
治療費の目安
骨肉腫の治療費は腫瘍の進行度や治療方法によって大きく変動します。
| 治療方法 | 費用の目安(3割負担の場合) |
|---|---|
| 外科的治療(手術) | 数万円~数十万円(保険適用後の自己負担分) |
| 化学療法(入院費、薬剤費含む) | 1クールあたり数万円~十数万円 |
| 放射線療法 | 1回あたり数千円~1万円程度(照射部位や回数による) |
| 入院費 | 1日あたり数千円~1万円程度(個室利用や特別室料は別途負担) |
高額療養費制度を利用すれば、月ごとの自己負担額をさらに抑えられます。
高額療養費制度とは、一定額を超えた医療費の払い戻しを受けられる制度で、所得区分に応じて自己負担限度額が決まります。
また、転移や再発に対する追加治療によって費用が増える可能性もあるため、医療ソーシャルワーカーや保険担当者に相談しながら計画を立てましょう。
以上
参考文献
BEIRD, Hannah C., et al. Osteosarcoma. Nature reviews Disease primers, 2022, 8.1: 77.
RITTER, Jörg; BIELACK, S. S. Osteosarcoma. Annals of oncology, 2010, 21: vii320-vii325.
MESSERSCHMITT, Patrick J., et al. Osteosarcoma. JAAOS-Journal of the American Academy of Orthopaedic Surgeons, 2009, 17.8: 515-527.
LIN, Patrick P.; PATEL, Shreyaskumar. Osteosarcoma. In: Bone sarcoma. Boston, MA: Springer US, 2012. p. 75-97.
GORLICK, Richard; KHANNA, Chand. Osteosarcoma. Journal of bone and mineral research, 2010, 25.4: 683-691.
EATON, Bree R., et al. Osteosarcoma. Pediatric blood & cancer, 2021, 68: e28352.
OTTAVIANI, Giulia; JAFFE, Norman. The epidemiology of osteosarcoma. Pediatric and adolescent osteosarcoma, 2010, 3-13.
LINDSEY, Brock A.; MARKEL, Justin E.; KLEINERMAN, Eugenie S. Osteosarcoma overview. Rheumatology and therapy, 2017, 4: 25-43.
OTTAVIANI, Giulia; JAFFE, Norman. The etiology of osteosarcoma. Pediatric and adolescent osteosarcoma, 2010, 15-32.
FUCHS, Bruno; PRITCHARD, Douglas J. Etiology of osteosarcoma. Clinical Orthopaedics and Related Research®, 2002, 397: 40-52.