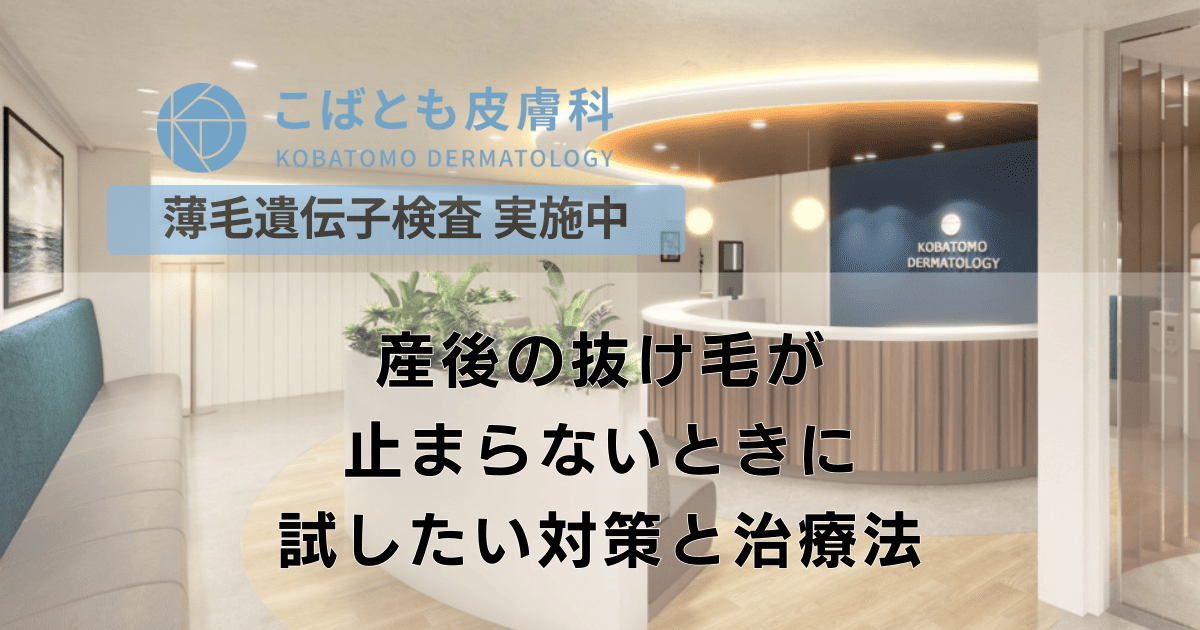産後に抜け毛が増える症状に悩む方は多く、驚きや不安を感じるケースが少なくありません。
出産を終えたばかりでホルモンバランスが大きく変化しやすい時期に生じる抜け毛は、一時的なものなのか、それとも治療を要するのか、判断に迷うこともあるでしょう。
そこで、女性専門医の視点から原因や対策、治療について詳しく解説します。
家庭でできるケアからクリニックでの治療法までを幅広く取り上げるので、自分に合った解決策を見つけるヒントにしてみてください。
この記事の執筆者

小林 智子(こばやし ともこ)
日本皮膚科学会認定皮膚科専門医・医学博士
こばとも皮膚科院長
2010年に日本医科大学卒業後、名古屋大学医学部皮膚科入局。同大学大学院博士課程修了後、アメリカノースウェスタン大学にて、ポストマスターフェローとして臨床研究に従事。帰国後、同志社大学生命医科学部アンチエイジングリサーチセンターにて、糖化と肌について研究を行う。専門は一般皮膚科、アレルギー、抗加齢、美容皮膚科。雑誌を中心にメディアにも多数出演。著書に『皮膚科医が実践している 極上肌のつくり方』(彩図社)など。
こばとも皮膚科関連医療機関
産後の抜け毛とは
産後に見られる抜け毛は、ホルモンの急激な変化や心身の負担によって起こる症状の1つです。
頭皮環境が不安定になりやすいため、一時的に抜け毛が増えたり髪が細くなったりすることがあります。
こうした状態が長く続くと、自分で対策を取るべきか、医療機関を受診すべきか迷う方が少なくありません。症状や原因を押さえておくと、必要な対策や治療の方針を見極めやすくなります。
産後における頭皮の変化
妊娠中はエストロゲンというホルモンの分泌が高まり、髪が抜けにくい状態に変化します。
しかし、出産後はエストロゲンの量が急激に減少し、本来抜けるはずだった髪が一気に抜けやすくなるのが特徴です。
さらに授乳や育児による負担、睡眠不足やストレスによって頭皮の血行が悪化し、髪の成長に影響が及ぶ場合もあります。
産後の抜け毛がひどく感じられる期間
産後の抜け毛は、産後2~4カ月をピークに感じる方が多いです。個人差はありますが、半年から1年ほどで落ち着くケースが一般的です。
ただし、抜け毛の量や期間は体質や生活環境、ストレスの有無など多くの要因に左右されます。
長期化する場合は、別の原因が隠れている可能性もあるため注意が必要です。
産後の抜け毛と薄毛の違い
産後に増える抜け毛は、一時的なホルモンバランスの乱れによる影響が大きいです。
そのため通常、抜け毛のピークが過ぎれば自然に回復していくことが多く、薄毛とは異なるものと考えられます。
しかし、体質的な要因や栄養不足、過剰なストレスなどが重なると、薄毛へ移行するリスクがあります。
育児との関係
産後のヘアトラブルは、育児と深くかかわっています。赤ちゃんのお世話に追われて睡眠不足や食生活の乱れが続くと、髪の毛のサイクルを保ちにくくなるからです。
身体を休める機会が少ない環境が長く続くと、自然回復が思うように進まずに抜け毛が長期化する可能性もあります。
産後の抜け毛と育児負担
| 負担の種類 | 内容 | 抜け毛への影響 |
|---|---|---|
| 睡眠不足 | 夜間の授乳やおむつ替えなどで断続的な睡眠になる | 成長ホルモンの分泌が乱れて髪の再生が遅れる |
| 栄養不足 | 食事をゆっくり摂る時間がとれず偏食や早食いが増える | 髪に必要な栄養素が不足して頭皮環境が悪化する |
| ストレス | 慣れない育児や子育てによる精神的負担 | 自律神経が乱れて血行不良が起こりやすくなる |
産後の抜け毛が起こる原因
産後に見られる抜け毛にはさまざまな要因が関与しています。
主にホルモンバランスの乱れによる自然な抜け毛として理解されがちですが、それだけでなく複合的に影響するものが多いです。
ホルモンバランスの乱れ
妊娠中に多量に分泌されていたエストロゲンやプロゲステロンが出産を境に急激に減少し、抜け毛が増えることがあります。
これは「分娩後脱毛症」としても知られ、一時的に髪の成長サイクルが乱れやすいのが特徴です。
急激に抜け毛が増えても、時間の経過とともにホルモンバランスが整えば自然に回復する場合があります。
ストレスと育児疲れ
産後の生活は、ホルモンの変化だけでなく育児負担や家庭環境の変化によってストレスが増大しがちです。
ストレスは自律神経を乱し、頭皮への血流を低下させる要因となります。髪に十分な栄養が届かない状態が続くと髪が弱り、抜け毛が加速するときがあります。
栄養不足
授乳中は赤ちゃんに多くの栄養を供給しなければならないため、産後の母体は栄養不足に陥りやすいです。
特にタンパク質やビタミン、ミネラルの不足は髪の成長に大きく影響します。
忙しさから食事が偏ったり、不規則な時間になったりすることが重なると抜け毛が増える傾向があります。
ヘアサイクルの乱れ
毛髪は成長期、退行期、休止期というサイクルを経て常に生え変わっています。
産後は、このサイクルが乱れやすく、一度に大量の髪が休止期に移行してしまうケースがあります。
その結果、短期間でたくさんの髪が抜け落ち、見た目にもわかる抜け毛としてあらわれます。
産後におけるヘアサイクルの変動
| サイクル | 特徴 | 産後の影響 |
|---|---|---|
| 成長期 | 髪が成長する時期 | ホルモン低下と栄養不足により短縮しやすい |
| 退行期 | 髪の成長が停止し始める時期 | 本来なら段階的に移行するが急激になる |
| 休止期 | 毛根が休止して髪が抜けやすい | 産後は休止期の髪が一斉に抜ける |
産後の抜け毛を放置するリスク
産後の抜け毛は自然に回復するケースが多いですが、放置していると長引いたり、別のトラブルを招いたりする可能性があります。
症状が落ち着かないときは適切なケアや専門的なアドバイスを受けることが重要です。
見た目への影響
短い期間で大量に髪が抜けると、生え際や分け目の地肌が目立ってくる場合があります。
生活に支障はなくても、見た目が気になって外出や人との交流を避けるようになると、精神的な負担が増えます。
頭皮のトラブル
抜け毛が増えると同時に、頭皮の脂分バランスが乱れやすくなります。
頭皮環境が悪化してフケやかゆみが増えると、さらに髪の成長を妨げる悪循環に陥ります。放置すれば抜け毛だけでなく頭皮全体の健康にも悪影響を与えます。
心理的ストレスの増加
髪は見た目を大きく左右するため、一時的に大量の抜け毛を経験すると心理的負担を抱えやすいです。
育児に対する負担に加えて抜け毛への不安が重なると、心身のバランスを崩しやすくなります。
他の薄毛症状との併発
産後の抜け毛をそのままにしていると、もともと女性に多い「びまん性脱毛症」などが併発するケースがあります。
女性ホルモンの乱れや栄養不足は複数の薄毛症状の要因になりうるため、早めに対策を講じることが大事です。
抜け毛を長期間放置した場合に考えられる影響
| 影響 | 内容 | 対応策 |
|---|---|---|
| 見た目へのコンプレックス | 生え際や分け目から地肌が透けて見える | 育毛ケアや帽子などで一時的に保護する |
| 頭皮環境の悪化 | 皮脂やフケの増加で炎症やかゆみが生じる | 洗髪方法の見直しや頭皮の保湿が必要 |
| ストレスの悪循環 | 抜け毛が増えるほど不安が増し、さらに抜け毛が加速する | ストレス解消の手段を整えてメンタルケアに注力 |
| 薄毛症状の進行 | 育児疲れやホルモン乱れ、栄養不足が慢性化し他の薄毛を併発 | 早めの専門医相談や十分な栄養補給が求められる |
自分でできる日常ケアと対策
育児期間は忙しく、なかなか自分のケアをする時間がとりづらい方が多いですが、生活の中で小さな工夫を重ねていくと抜け毛対策につなげることが可能です。
症状がひどくなる前に、できる範囲で日常ケアを取り入れてみましょう。
頭皮マッサージの重要性
頭皮マッサージは血行促進に役立ち、髪の毛の成長を助けます。
お風呂の湯船に浸かりながら指の腹で頭皮を優しくつまむようにマッサージすると、リラックス効果も高まります。力を入れすぎず、柔らかいタッチを心がけるとよいです。
頭皮マッサージで意識したいポイント
| ポイント | 理由 |
|---|---|
| 指の腹を使う | 爪を立てると頭皮を傷める可能性がある |
| 耳の上~後頭部まで | 血液やリンパ液が集まりやすい部分 |
| 小刻みに動かす | 血行を効率的に促進するため |
| 毎日続ける | 一過性で終わらず、習慣化する必要がある |
洗髪の工夫
洗髪は髪や頭皮を清潔に保つうえで大事です。ただし、過度な洗浄によって皮脂を取りすぎると逆に頭皮環境が悪化するケースもあります。
産後はホルモンバランスの変動が大きいため、低刺激のシャンプーやコンディショナーを使い、優しく洗うのが望ましいです。
- 強いメントール系は刺激が強く、頭皮が乾燥しやすい
- 爪を立てず指の腹で洗う
- シャンプー前の予洗いで汚れを落とす
- すすぎ残しがないように時間をかける
栄養バランスの見直し
育児中は思うように食事を摂れない場合もありますが、髪の成長にはタンパク質やビタミンB群、鉄分や亜鉛などが重要です。
これらを意識的に取り入れることで抜け毛予防の手助けになります。
足りない分はサプリメントに頼るのも手段の1つですが、医師に相談するなど安全性に配慮しながら行う必要があります。
生活習慣の改善
育児疲れや睡眠不足が抜け毛を助長することがあります。赤ちゃんが寝ている間に自分も睡眠を取る、家族に協力してもらい休息の時間を確保するなど、できる範囲で心身を休める工夫が大事です。
短時間でも休める機会を増やすと、ホルモンバランスの乱れを和らげられるでしょう。
日常で意識したい生活習慣
| 生活習慣 | 抜け毛への影響 | ポイント |
|---|---|---|
| 定期的な睡眠 | 成長ホルモンの分泌により髪の再生を促進 | こまめに仮眠をとる工夫 |
| ストレス解消 | 自律神経を安定させ血行を保ちやすくする | 趣味や軽い運動、深呼吸など |
| バランスの良い食事 | 栄養不足を予防し、頭皮と髪の健康を維持 | タンパク質・ビタミン・ミネラルを意識したメニュー |
| 適度な頭皮ケア | 清潔を保ち血行を促す | マッサージや保湿ケアの習慣化 |
医療機関での治療方法
産後に抜け毛がひどいと感じて、セルフケアだけでは改善が見られない場合や、ストレスが蓄積して日常生活に支障をきたす場合は、医療機関での治療を検討するのも一案です。
専門医による診断を受けると、ホルモンバランスの評価や頭皮の健康状態を総合的に見極められます。
内服薬や外用薬による治療
医療機関ではホルモンバランスや頭皮環境を改善するために、内服薬や外用薬を用いることがあります。
例えば、血行促進をサポートする成分を含む薬剤や頭皮ケア用の塗り薬などがあります。
ただし、授乳中や産後間もない時期は服用できない薬や控えるべき成分もあるため、必ず医師に相談してください。
- 血行促進成分を含む内服薬
- 頭皮環境を整える外用薬
- 栄養補給を目的としたサプリメント
- ホルモン補充療法を検討する場合もある
育毛メソセラピーなどの施術
クリニックによっては、頭皮に薬剤や有用成分を直接届ける育毛メソセラピーなどの施術を行うところもあります。
頭皮を活性化して髪の成長をサポートする狙いがありますが、施術の適応や効果は個人差があるため、カウンセリングの段階でじっくり話を聞くことが大事です。
産婦人科との連携
産後の抜け毛には産婦人科的な視点も欠かせません。
とくに授乳を続けている方はホルモンの状態が大きく変動しているため、皮膚科や美容クリニックだけでなく産婦人科で相談するとより安全に治療が進みやすいです。
授乳期に使える薬の種類や検査のスケジュールなど、産婦人科と連携しながら治療計画を立てると安心です。
カウンセリングとメンタルサポート
医療機関では、身体面だけでなく精神面のサポートも行うところが多いです。育児疲れや産後のブルーなど精神的な負担が抜け毛を助長している場合は、カウンセリングを通じてストレスケアを行うと効果的です。
専門家に相談することで、自宅でできるメンタルヘルスの対策や改善方法を学ぶ機会にもなります。
医療機関で用いられる主な治療法と特徴
| 治療法 | 特徴 | 注意点 |
|---|---|---|
| 内服薬 | 血行促進や栄養補給を狙うものが多い | 授乳中は使用できない成分があるため医師に要相談 |
| 外用薬 | 頭皮に直接塗布して成長をサポート | 続けやすさや副作用の有無を確認 |
| 育毛メソセラピー | 有用成分を注入して育毛効果を狙う | 施術には痛みやダウンタイムがある場合も |
| カウンセリング | ストレスやメンタル面から抜け毛の改善を目指す | 心理的負担が大きい場合は専門家へ相談 |
| 産婦人科との連携 | ホルモン状態や授乳状況なども考慮して多角的に治療を検討できる | 費用や受診のタイミングを医療チームと協議する |
クリニック選びのポイント
産後における抜け毛対策を医療機関に委ねる場合、自分に合ったクリニックを見つけることが大事です。
女性専門の薄毛治療を行うクリニックや、産後の体調を考慮してくれる医療機関を選ぶと安心して治療を受けられます。
女性専門の薄毛治療科を選ぶ利点
女性特有のホルモンバランスの変化を理解している医師やスタッフがいるクリニックでは、産後の身体的・精神的状況に合わせた治療を提案してくれます。
また、女性専用の空間を整えているクリニックも多く、人目を気にせず相談しやすい環境であるのも大きなメリットです。
実績や口コミのチェック
クリニックを選ぶ際は、公式サイトの情報だけでなく実際に通院した方の口コミも参考になります。
産後に見られるひどい抜け毛に対して、どのような治療方針を示しているか、症状の改善例があるかなどを確認すると信頼性が高まります。
ただし、口コミは個人の感想や体質が反映されやすい点にも留意が必要です。
通院の負担を減らす
産後は育児に加え、家事や仕事などで忙しくなる方が多いです。定期的な通院が必要な治療の場合、アクセスの良さや診療時間の融通も検討材料になります。
通院が負担になってしまうと治療が長続きしにくいため、自宅から通いやすいクリニックを選ぶと治療を継続しやすいでしょう。
カウンセリング体制
産後はホルモンバランスだけでなく精神的にも不安定になりやすい時期です。
カウンセリングに力を入れている医療機関を選ぶと、心のケアや生活改善の指導も受けられる場合があるので、抜け毛だけでなくトータルでのサポートが期待できます。
クリニック選びで考慮したい要素
| 要素 | チェックポイント | 理由 |
|---|---|---|
| 専門性 | 女性ホルモンや産後ケアに詳しい医師がいるか | 産後特有の抜け毛に対して的確な治療を受けやすい |
| カウンセリング | 初回相談が丁寧でわかりやすいか | 心理面も含めて総合的にアプローチしてもらえる |
| 通いやすさ | 自宅からのアクセスや診療時間 | 忙しい中でも無理なく通院を続けられる |
| 費用面 | 保険適用か自由診療か、治療費の目安が明確か | 出費が大きくならないように事前に把握しておく必要がある |
| 院内環境 | 女性が通いやすい空間づくりがなされているか | 周囲の目を気にせず落ち着いて受診できる |
よくある質問
産後の抜け毛は個人差が大きいため、悩みや疑問も人それぞれ異なります。ここでは、クリニックに寄せられやすい質問をまとめて解説します。
- 産後の抜け毛はどれくらいで元に戻りますか?
-
一般的には産後2~4カ月をピークに抜け毛が増え、半年から1年ほどかけて元に戻る方が多いです。
ただし、栄養状態やストレス、睡眠など生活習慣が影響するため、個人差がある点を念頭に置いてください。
あまりにも長期間抜け毛が続く場合は専門家の診察を受けると安心です。
- 授乳中でも治療は受けられますか?
-
授乳中でも治療を行うこと自体は可能ですが、薬の成分によっては母乳に移行しやすいものもあります。
治療の種類によって制限があるため、必ず産婦人科や育児中の治療に理解がある医療機関で相談してください。
安全面を配慮しつつ、代替の治療法を提案してもらえる場合もあります。
- 自宅でのセルフケアだけで改善しますか?
-
軽度の抜け毛の場合は、睡眠や栄養などの生活習慣を見直し、頭皮を清潔に保つなどのセルフケアを続けると改善が見込めることがあります。
しかし、抜け毛の量が増え続ける、頭皮に異常があるなど自分では改善しにくい状況のときは、早めに医療機関で診察を受けるのが望ましいです。
- 産後の抜け毛がひどい状態でもパーマやカラーは可能ですか?
-
産後間もない時期は髪や頭皮がデリケートになっている場合があります。
パーマやカラーに使用する薬剤の刺激が抜け毛を悪化させる懸念もあるため、無理に施術を受けず、髪や頭皮のコンディションが整ってから行うのがおすすめです。
カラー剤やパーマ液の種類によっては刺激が少ないものもあるので、美容師と相談して慎重に決めると良いでしょう。
参考文献
CAMACHO-MARTINEZ, Francisco M. Hair loss in women. In: Seminars in cutaneous medicine and surgery. No longer published by Elsevier, 2009. p. 19-32.
WOLFF, Hans; FISCHER, Tobias W.; BLUME-PEYTAVI, Ulrike. The diagnosis and treatment of hair and scalp diseases. Deutsches Ärzteblatt International, 2016, 113.21: 377.
CAMACHO-MARTINEZ, Francisco M. Hair loss in women. In: Seminars in cutaneous medicine and surgery. No longer published by Elsevier, 2009. p. 19-32.
SINCLAIR, Rodney, et al. Hair loss in women: medical and cosmetic approaches to increase scalp hair fullness. British Journal of Dermatology, 2011, 165.s3: 12-18.
JAGADEESAN, Soumya; NAYAK, Prateek. Disorders of Hair in Pregnancy and Postpartum. In: Skin and Pregnancy. CRC Press, 2025. p. 58-70.
MESINKOVSKA, Natasha Atanaskova; BERGFELD, Wilma F. Hair: What is New in Diagnosis and Management?: Female Pattern Hair Loss Update: Diagnosis and Treatment. Dermatologic clinics, 2013, 31.1: 119-127.
TOADER, Mihaela Paula, et al. Unraveling the psychological impact of telogen effluvium: Understanding hair loss beyond the scalp. Bulletin of Integrative Psychiatry, 2024, 1.
FRANÇA, Katlein, et al. Comprehensive overview and treatment update on hair loss. 2013.