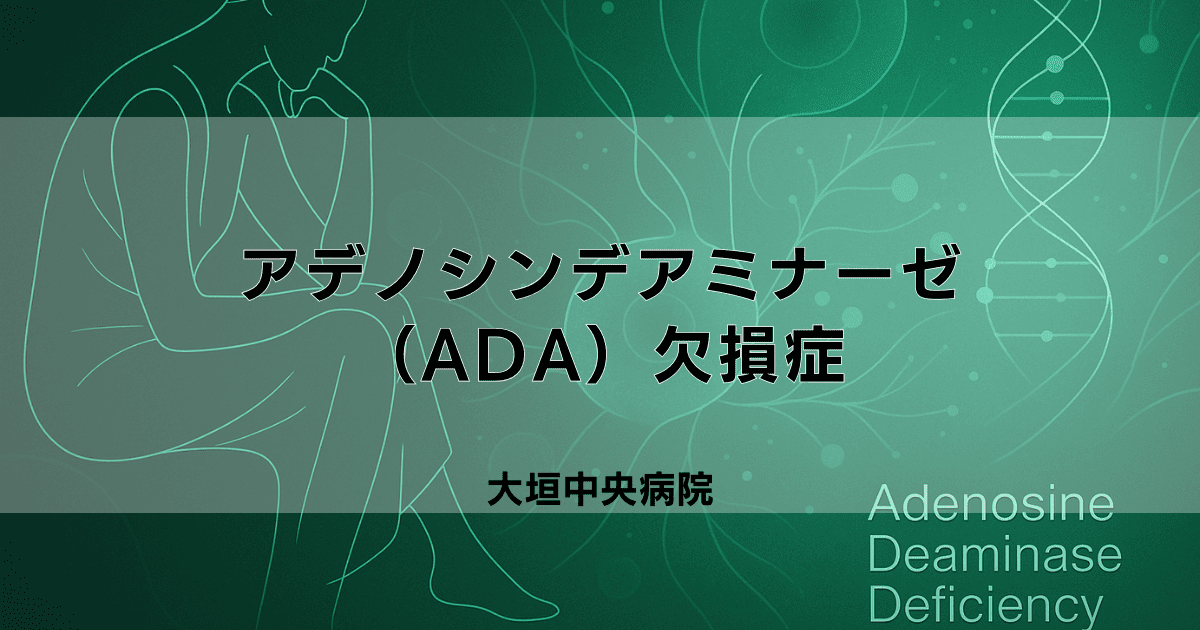アデノシンデアミナーゼ(ADA)欠損症とは、免疫システムに関わる重要な酵素であるアデノシンデアミナーゼの働きが生まれつき十分でない、または欠けていることによって起こる疾患です。
体内の老廃物や有害物質の分解がスムーズに進まず、特にリンパ球などの免疫細胞が強く影響を受けるため、さまざまな感染症を繰り返しやすくなります。
重症化するまでは気づきにくい場合もありますが、幼少期の段階で発症すると呼吸器や消化器など幅広い部位に感染が広がりやすく、成長や発達にも影響を及ぼすリスクが高まります。
病型
アデノシンデアミナーゼ(ADA)欠損症は、免疫不全を起こす代表的な先天性代謝異常の1つに数えられ、病型は重症度や発症時期の違いなどによっていくつかに分類されます。
早期発症型と遅発型
ADA欠損症は、酵素活性が極度に低いかまったくない場合、出生から間もない段階で重度の免疫不全が明らかになる場合が多く、重症複合免疫不全症(SCID)の形態をとります。
早期発症型は、生後数か月以内に肺炎や敗血症など深刻な感染症が繰り返し起こり、治療が行われないと命に関わる可能性が高いです。
一方、ADAの残存活性がある程度見込まれるケースでは、幼少期をある程度過ぎてから緩やかに症状が出現する遅発型と呼ばれる病型に分類されます。
遅発型でも体力の低下や呼吸器感染、慢性的な下痢などが続くことがあり、放置すると徐々に免疫機能が悪化します。
早期発症型と遅発型の特徴
| 分類 | 発症時期 | 主要症状 | 酵素活性の程度 |
|---|---|---|---|
| 早期発症型 | 生後数か月以内 | 重度の感染症、発育不良、SCID様 | ほぼゼロに近い |
| 遅発型 | 1歳以降~成人 | 反復する呼吸器感染、成長遅延 | 一部残存活性がある |
合併症や他疾患との関連
ADA欠損症は主に免疫系の障害として表面化しますが、合併症として中枢神経系の機能障害や肝機能の低下など、臓器やシステムに広範な影響が及ぶ場合があります。
同じ先天性の代謝異常を併発する例もあり、その場合は症状の全体像が複雑です。
ADA欠損症と関連して起こりやすい合併症
- 骨格系の奇形や骨粗しょう症傾向
- 肝臓や胆道系への負担による黄疸
- 発達障害や精神的な発達の遅れ
- 呼吸不全や肺高血圧
重症度による分類
ADA欠損症は、その重症度によって完全欠損型、部分欠損型に分けることもあり、完全欠損型は生後間もなく危険な感染症が頻発し、緊急の治療対応が不可避になるケースが多いです。
部分欠損型は、成人まで気づかれないまま経過し、突発的な合併症で診断が確定するという流れをたどることもあります。
重症度の分類
| 重症度 | 酵素活性の程度 | 臨床像 |
|---|---|---|
| 完全欠損型 | 活性がほぼ認められない | 早期発症型SCIDとして重度の症状 |
| 部分欠損型 | 一部活性が残る | 遅発型、症状が徐々に顕在化する |
アデノシンデアミナーゼ(ADA)欠損症の症状
ADA欠損症の主な症状は、免疫不全によって感染症を繰り返しやすくなるという点に集約されます。
症状の現れ方は個人差が大きく、早期発症型では重篤な感染を何度も経験する一方、遅発型では比較的軽度の症状が長期間続くケースもあります。
反復する感染症
ADA欠損症の患者は、細菌やウイルス、真菌などあらゆる病原体に対する抵抗力が低下し、通常なら軽く済むはずの風邪や胃腸炎が長引く、あるいは重症化しやすいです。
肺炎や中耳炎、敗血症などが頻繁に起こり、抗生物質や抗ウイルス薬を繰り返し使用することも珍しくありません。特に乳児期においては、下痢や口内炎などが慢性的に持続して体力が落ちると、栄養吸収不良や成長障害にもつながりやすいです。
ADA欠損症患者さんに多くみられる感染症
| 感染症の種類 | 頻度・特徴 |
|---|---|
| 肺炎 | 呼吸困難や高熱を伴いやすく重症化しがち |
| 中耳炎 | 繰り返す耳の痛みや発熱を引き起こす |
| 口腔内感染 | 口内炎や白苔が長引き、食事摂取に困難を伴う |
| 腸炎 | 慢性的な下痢や脱水、体重減少を誘発する |
成長や発達の遅れ
幼少期に重い感染症が繰り返されると、食事や睡眠が不十分になりやすく、成長や発達が平均水準より遅れることが多いです。
生後間もなく症状が現れる重症型では、栄養摂取や運動機会の不足などが重なって、身長や体重が思うように伸びないまま体力も低下してしまう例があります。
学校生活で集団行動に参加する際にも感染リスクを懸念し、保護者を含めて細心の注意を払う必要があるため、社会的活動の制限が生じやすいです。
成長や発達の遅れとして現れやすい例
- 体重増加の停滞や身長の伸び悩み
- 言葉の発達や運動能力の獲得が周囲より遅れる
- 体力が不足して疲れやすく長時間の活動ができない
自己免疫や炎症反応
ADA欠損症では、免疫機能が低下する一方で、免疫システムの異常な活性化が部分的に起こり、自己免疫反応が起こされる可能性が指摘されています。
自己免疫反応とは、本来は外部の病原体を攻撃する免疫が、自分自身の細胞や組織を誤って攻撃してしまう状態です。そのため、関節炎や皮膚炎、甲状腺機能の異常など、自己免疫疾患に類似した症状が加わる場合があります。
合併が報告される自己免疫系のトラブル
| 合併症候 | 具体的な症状や影響 |
|---|---|
| 関節炎 | 手足の関節痛、腫れ、変形など |
| 自己免疫性貧血 | 赤血球を自己抗体が破壊 |
| 甲状腺炎 | 甲状腺ホルモン分泌の乱れ |
| 皮膚炎 | 発疹や水泡、慢性的なかゆみ |
中枢神経への影響
一部の重症例では、中枢神経系に影響が及び、けいれん発作や学習障害などが見られるケースがあります。
これは、ADA欠損によって特定の代謝物質が神経細胞に毒性を及ぼすと考えられており、免疫機能だけでなく神経系の発達や維持にも重要な役割を果たしていることを示唆しています。
特に乳幼児期に発症した患者さんは、脳の発達に不可欠な時期に代謝異常と感染症の負担を抱えるため、脳機能に影響が出やすいです。
アデノシンデアミナーゼ(ADA)欠損症の原因
ADA欠損症の原因は、遺伝子レベルでの突然変異によってアデノシンデアミナーゼ酵素が正常に機能しない、あるいは全く働かない状態になる点にあります。
遺伝子変異のメカニズム
ADA酵素をコードする遺伝子は常染色体上に存在し、常染色体劣性遺伝という形式で受け継がれ、両親がそれぞれ1つずつ変異した遺伝子を持ち、その子どもが両方の変異遺伝子を受け取ったときにADA欠損症が発症するという仕組みです。
両親のどちらかが変異を保因していない限り、子どもがADA欠損症を発症するリスクはゼロに近くなりますが、保因状態は健康診断などでは判別が難しく、子どもを望む段階で初めて遺伝カウンセリングを受ける人もいます。
ADA遺伝子における変異
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 遺伝形式 | 常染色体劣性遺伝 |
| 変異部位 | ADA遺伝子(Chromosome 20などが指摘される) |
| 変異の種類 | ミスセンス変異、ナンセンス変異、挿入欠失など |
| 残存活性の差 | 変異のパターンによって酵素活性ゼロ~低下まで幅がある |
代謝経路の障害
ADA酵素は、リンパ球を中心とした細胞内でプリン代謝と深く関わっています。
アデノシンやデオキシアデノシンといった分子を分解する工程が阻害されると、細胞内にこれらの化合物が蓄積し、有毒な副産物がDNA合成を障害すると考えられています。
リンパ球はDNAの合成と再合成が活発な細胞群であるため、ADAの機能が失われるとリンパ球の成長や成熟が妨げられ、重篤な免疫不全を起こすのです。
ADA欠損時に生じる代謝障害のポイント
- アデノシンやデオキシアデノシンが正常に分解されず蓄積
- それらが細胞毒性を持つ物質に変化しやすい
- リンパ球の増殖・生存に影響し、免疫機能が破綻する
環境要因との関連
ADA欠損症は遺伝子変異が直接的な原因であるため、喫煙や食事などの生活習慣、環境汚染などが発症の根本には関わりにくいと考えられていますが、生まれた後の環境要因で症状の進行速度や合併症のリスクが変わる場合はあります。
例えば、不衛生な環境や栄養不良の状態が続くと、容易に感染症を起こしやすくなり、重症化も加速する傾向があります。
症状の悪化を招く可能性がある環境要因
| 要因 | 影響 |
|---|---|
| 栄養不良 | 体力と免疫力がさらに低下し、感染リスクが上昇 |
| 空気の汚染 | 呼吸器感染症を起こしやすく、治りにくい状態になる |
| 過度なストレス | 免疫調整機能が乱れ、感染や自己免疫反応を誘発しやすい |
検査・チェック方法
ADA欠損症を疑った場合、早期に診断を確定することで重症感染や合併症のリスクを抑えることに直結します。免疫不全の根本原因が分からないまま治療に手間取ると、患者さんの身体への負担が大きくなる可能性が高いです。
免疫学的検査
まず、リンパ球数やリンパ球サブセット(T細胞、B細胞、NK細胞など)の割合を測定し、免疫不全の程度を確認する作業が一般的です。
ADA欠損症の場合、特にT細胞が大きく減少している例が多いとされ、SCIDの一種として捉えられることもあります。
ただし、免疫グロブリン量や補体活性など、別の免疫指標とのバランスも重要なので、総合的に評価して免疫不全のパターンを明らかにすることが必要です。
免疫学的検査で着目される主な項目
- 全リンパ球数の測定
- CD3、CD4、CD8といったT細胞マーカーの解析
- 免疫グロブリン(IgG、IgA、IgM)濃度
- NK細胞数やB細胞数
ADA酵素活性測定
ADA欠損症を確定診断するための決め手として、ADA酵素活性の測定が挙げられます。
患者さんの血液やリンパ球を採取して、アデノシンをどの程度分解できるかを調べ、活性が著しく低い、もしくはほとんど認められない場合にADA欠損症と診断される可能性が高まります。
血中の赤血球やリンパ球のADA活性を測る手法が一般的で、検査そのものは特殊な機器が必要な場合もありますが、多くの大規模医療機関や専門施設で実施可能です。
ADA酵素活性測定の概要
| 検査内容 | 主な対象試料 | 測定結果の目安 |
|---|---|---|
| ADA活性測定 | 血液(赤血球、リンパ球) | 正常値の数%以下なら欠損を疑う |
| 分子レベル解析 | 遺伝子検査 | 変異の同定が可能 |
遺伝子検査
ADA欠損症の根拠となる変異遺伝子を直接確認する目的で、遺伝子検査が行われることがあります。
患者さんのDNAサンプルからADA遺伝子部分を増幅し、塩基配列を解析することで、ミスセンス変異やナンセンス変異などのタイプを特定できます。
遺伝子検査による診断プロセスで意識されるポイント
- 血液などからDNAを抽出
- ADA遺伝子領域の増幅(PCR)
- 塩基配列解析や特定変異部位をスクリーニング
- 変異型の種類を決定し、臨床像と照合
画像検査やその他の評価
ADA欠損症は主に免疫不全の検査を中心に診断されますが、合併症の評価や体内状態の把握のため、胸部X線やCT、エコー検査などが実施されることもあります。
肺炎やリンパ節の腫脹、肝臓肥大などが見られる場合は、病気の進行度合いや他の免疫疾患との鑑別を行う上で参考になり、また、中枢神経症状が疑われる場合はMRI検査を用いて脳の状態を評価することも検討されます。
ADA欠損症の鑑別や合併症を調べるために用いられる画像検査
| 画像検査 | 主な目的 |
|---|---|
| 胸部X線 | 肺の感染状況、リンパ節腫脹の有無 |
| CT(胸部・腹部) | 詳細な臓器構造やリンパ系の状態を把握 |
| MRI(脳) | 中枢神経症状の有無、構造異常の確認 |
| 超音波検査 | 肝臓や脾臓のサイズ、腹部リンパ節の評価 |
アデノシンデアミナーゼ(ADA)欠損症の治療方法と治療薬について
ADA欠損症の治療目標は、弱った免疫機能を補強し、重篤な感染症や合併症をできる限り防ぎながら患者の生活の質を向上させることにあり、治療法には酵素補充療法、造血幹細胞移植、そして薬物治療などがあります。
酵素補充療法(ERT)
ADA欠損症で認知されてきた治療手段の1つに、酵素補充療法があり、これは、遺伝子組換え技術を用いて製造されたADA酵素製剤を、定期的に筋肉や皮下に投与して体内で不足しているADA活性を補う方法です。
欠損している酵素そのものを補うため、免疫細胞の正常化が期待されます。
ただし、酵素製剤の効果は投与期間中に限られるため、継続的な治療スケジュールを守ることが要求されるほか、投与スパンが長期にわたる場合は経済的負担や治療負担が大きくなる点も考慮が必要です。
酵素補充療法の概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 投与経路 | 皮下または筋肉内投与 |
| 投与間隔 | 1~2週間に1回など、患者の状態に応じて設定 |
| 効果 | 免疫機能の改善(T細胞数増加、感染頻度減少) |
| 課題 | 長期的コスト、注射による身体的負担 |
造血幹細胞移植
重症のADA欠損症、特に幼少期に重篤な免疫不全が認められるケースでは、造血幹細胞移植(骨髄移植や臍帯血移植など)が治療の選択肢です。
健康なドナーから提供された造血幹細胞が定着すれば、ADA酵素を正常に産生できる免疫細胞が生成され、根本的に免疫不全を改善できる可能性があります。
造血幹細胞移植に関連する主なメリットと注意点
- メリット:うまくいけば長期的に免疫機能を獲得できる
- メリット:酵素補充療法のような継続投与が不要になる可能性
- 注意点:適合ドナー探しや強力な免疫抑制前処置の必要
- 注意点:移植関連合併症(拒絶反応、GVHDなど)のリスク
移植の成功率はドナーとのHLA適合度や施設の経験、患者の状態に左右されるため、十分なカウンセリングとリスク評価が欠かせません。
薬物療法と感染予防
ADA欠損症は免疫不全を伴うため、積極的な感染予防策が重要で、日常的には、免疫力が著しく低下している場合、感染症を引き起こす病原体への対策として抗生物質や抗ウイルス薬の予防投与が行われます。
また、自己免疫的な症状が強い患者さんにはステロイドや免疫調整剤を使用する場合もあり、病態に合わせたきめ細かな管理が必要です。
| 薬剤カテゴリー | 主な目的 |
|---|---|
| 予防的抗菌薬 | 細菌や真菌による感染を防ぐ |
| 抗ウイルス薬 | ウイルス感染(ヘルペス、サイトメガロなど)の予防・治療 |
| 免疫調整剤 | 自己免疫反応や炎症反応を緩和 |
| 免疫グロブリン製剤 | B細胞機能低下による抗体不足を補う |
遺伝子治療の可能性
ADA欠損症は遺伝子変異によって引き起こされる疾患のため、過去から遺伝子治療の研究が行われてきました。
患者さん自身の造血幹細胞を体外に取り出し、正常なADA遺伝子を組み込んだウイルスベクターで細胞を修復してから体内に戻すという手法が報告されています。
成功すれば長期的に正常な免疫細胞が作られる可能性がありますが、治療費や長期安全性の課題などが残っており、現実にはごく限られた施設や研究レベルでしか実施されていないのが現状です。
アデノシンデアミナーゼ(ADA)欠損症の治療期間
ADA欠損症は、乳幼児期にSCIDとして重症化しているケースでは、緊急性が高いため集中的な治療を行う一方、遅発型で症状が比較的軽い場合は、長期的な経過観察と補助療法を組み合わせる形が一般的です。
新生児期・乳児期からの治療
生後数か月以内に重度の感染症を繰り返すような早期発症型は、診断が確定次第、酵素補充療法か造血幹細胞移植を視野に入れながら、同時に感染対策や栄養サポートを強化します。
命に関わるリスクが高いため、入院期間が数か月に及ぶこともあり、治療全体は先天性免疫不全の専門施設で集中的に進めるケースが多いです。
乳児期の重症例における治療工程
- 免疫学的検査とADA酵素活性測定による確定診断
- 抗菌薬や抗ウイルス薬を用いた感染予防と治療
- 酵素補充療法の開始、もしくは造血幹細胞移植の準備
- 移植実施後の拒絶反応や感染症管理
- 成長・発達のフォローアップ
この過程で半年から1年、場合によってはそれ以上の期間にわたって集中的なケアが必要です。
遅発型の治療
遅発型の場合、症状が軽度で徐々に免疫力が落ちていく形をたどるため、通院や定期検査による経過観察が主体です。
酵素補充療法は長期的に続けることが前提となるため、1~2週間に1度のペースで酵素製剤の投与を行いながら体調を観察する場合もあります。
この場合、外来通院での治療が可能なため、社会生活をある程度維持しながら治療を続ける患者さんも少なくありません。
| 治療形式 | 期間の目安 | 留意点 |
|---|---|---|
| 酵素補充療法 | 数年間にわたる継続投与 | 定期的な効果判定と投与量の調整が必要 |
| 感染予防治療 | 状況に応じて数週間~数か月単位 | 季節や周囲の感染状況に合わせた対応 |
| 免疫調整薬 | 数か月~数年の間で検討 | 自己免疫合併症の有無で変わる |
移植後のフォローアップ
造血幹細胞移植を受けた場合、移植自体は1回の大きなイベントですが、その後の定着状況や拒絶反応の管理などが重要となり、少なくとも数年間は綿密なフォローアップが続きます。
初年度は入院・通院を繰り返しながら免疫機能の回復具合をチェックし、拒絶反応を抑える薬物療法を調整するため、治療全体の長期化は避けられません。
無事に安定期に入った後も、年単位で血液検査や感染状況をモニターしながら過ごす方が安全です。
移植後フォローアップで意識されるポイント
- 定期血液検査による免疫細胞数とADA活性の確認
- 移植片対宿主病(GVHD)などの早期発見と対処
- ワクチン再接種など免疫再構築の支援策
- 成長発達や臓器機能への影響評価
成人期の経過観察
ADA欠損症が成人期に発症したり、乳幼児期から治療を受けて成長後も症状が続く場合は、内科や免疫科での定期的な通院が中心です。酵素補充療法を受けている方は、投与頻度や量を調整しながら、感染リスクを抑える工夫を行います。
また、自己免疫や内分泌の問題を併発する方もいるため、それぞれの専門科と連携して総合的にケアする形が大切です。
副作用や治療のデメリットについて
ADA欠損症は、治療しなければ重篤な感染症や合併症を起こす恐れがあり、また、治療自体にも副作用や負担が伴います。
酵素補充療法の副作用
酵素補充療法では、定期的な注射によってADA酵素を補いますが、投与時の痛みや腫れ、皮膚のかゆみなどの局所的な反応が起こる場合があり、まれにアナフィラキシーなど重いアレルギー反応を示す例も報告されています。
投与間隔が短くなるほど注射回数も増えるため、通院や注射に伴う負担が生活の質に影響することを懸念する患者さんもいます。
酵素補充療法における副作用
| 副作用 | 具体的な症状 | 対応策 |
|---|---|---|
| 注射部位の疼痛や腫れ | 赤み、痒みを伴う場合もある | 投与部位を毎回変える、冷却など |
| 過敏症反応 | 発疹、じんましん、呼吸困難 | 投与中の厳重観察、抗ヒスタミン剤の検討 |
| 全身倦怠感 | 倦怠感や頭痛などの軽度症状 | 適度な休養と水分補給 |
造血幹細胞移植のリスク
造血幹細胞移植は根本的な治療手段として期待されますが、移植に伴うリスクも少なくありません。前処置の化学療法や放射線療法によって体力が大きく消耗しやすく、また移植後に拒絶反応や感染症が起こるリスクが高まります。
特に幼児期の患者さんは身体が弱く、臓器や骨髄へのダメージが大人より深刻化しやすいため、医療チームと患者家族が慎重に治療計画を立てることが重要です。
造血幹細胞移植におけるデメリットや注意点
- 長期入院や免疫抑制薬の使用による生活の制限
- 移植関連合併症(感染、GVHDなど)で追加治療が必要になる可能性
- 移植がうまくいっても経過観察が数年単位で求められる
薬物治療全般の副作用
ADA欠損症では、免疫調整剤や抗ウイルス薬、免疫グロブリン製剤など複数の薬が使用されることがあり、それぞれに副作用がつきものです。
長期投与が見込まれるステロイド系薬剤は、骨粗しょう症や糖代謝異常などを起こすリスクがあり、抗ウイルス薬や抗生物質も、肝臓や腎臓への負担が続くと副作用が積み重なる可能性があります。
| 薬剤分類 | 例 | 主な副作用 |
|---|---|---|
| 免疫調整剤 | ステロイド | 体重増加、高血圧、精神症状など |
| 抗ウイルス薬 | アシクロビルなど | 腎機能障害、頭痛、吐き気 |
| 抗菌薬(予防投与) | バクタ(ST合剤)など | 発疹、肝機能障害など |
| 免疫グロブリン製剤 | ヒト免疫グロブリン | 頭痛、発熱、アレルギー反応 |
アデノシンデアミナーゼ(ADA)欠損症の保険適用と治療費
以下に記載している治療費(医療費)は目安であり、実際の費用は症状や治療内容、保険適用否により大幅に上回ることがございます。当院では料金に関する以下説明の不備や相違について、一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。
酵素補充療法の費用
ADA欠損症に特化した酵素製剤は、製造工程が複雑で希少なため薬価が高くなる傾向があり、週1~2回の投与を長期的に続けると、1か月あたり数万円から十数万円の自己負担になります。
| 項目 | 自己負担の目安(3割負担の場合) |
|---|---|
| 1回の投与費用 | 約5,000~15,000円 |
| 1か月の投与費用 | 約20,000~60,000円(投与回数に依存) |
| 1年の概算費用 | 240,000~720,000円程度 |
実際には患者の体重や症状によって投与量が変わるため、詳細は担当医や医療機関での見積もりが必要です。
造血幹細胞移植の費用
造血幹細胞移植は、入院期間が長くなることや、高度な医療設備・人員が必要になるため、総額で数百万円以上の費用がかかる場合も珍しくありません。
保険適用後の自己負担でも、入院や手術費、検査費、薬剤費などを合計すると、数十万円から100万円以上になる可能性があります。
| 費用項目 | 自己負担の目安(3割負担の場合) |
|---|---|
| 手術・前処置費用 | 20~50万円程度 |
| 入院費 | 1日あたり数千円~1万円程度 |
| 抗拒絶薬費用 | 数千円~数万円/月 |
| 合計(1回の移植) | 50万円以上のケースも |
移植後も一定期間の通院治療や検査が必要になる点を踏まえ、あらかじめ費用計画を立てておくことが大切です。
薬剤費・検査費
ADA欠損症の患者さんは、酵素補充療法や移植以外でもさまざまな薬剤を使うことがあり、抗菌薬の予防投与や免疫グロブリン製剤の点滴など、各種予防措置を長期で行う場合、月あたり数千円から数万円の自己負担が発生します。
また、定期的な血液検査や画像検査の費用も積み重なると、1回につき数千円~1万円程度の自己負担になるため、合算すると年間では数万円単位になる可能性があります。
| 項目 | 自己負担の目安 |
|---|---|
| 定期血液検査 | 1回あたり数百円~数千円 |
| 画像検査(CT、MRIなど) | 1回あたり数千円~1万円程度 |
| 免疫グロブリン製剤 | 点滴1回で数千円~数万円 |
| 抗菌薬・抗ウイルス薬 | 月数千円~数万円 |
以上
参考文献
Onodera M, Ariga T, Kawamura N, Kobayashi I, Ohtsu M, Yamada M, Tame A, Furuta H, Okano M, Matsumoto S, Kotani H. Successful peripheral T-lymphocyte–directed gene transfer for a patient with severe combined immune deficiency caused by adenosine deaminase deficiency. Blood, The Journal of the American Society of Hematology. 1998 Jan 1;91(1):30-6.
Onodera M, Uchiyama T, Ariga T, Yamada M, Miyamura T, Arizono H, Morio T. Safety and efficacy of elapegademase in patients with adenosine deaminase deficiency: A multicenter, open‐label, single‐arm, phase 3, and postmarketing clinical study. Immunity, Inflammation and Disease. 2023 Jul;11(7):e917.
Otsu M, Yamada M, Nakajima S, Kida M, Maeyama Y, Hatano N, Toita N, Takezaki S, Okura Y, Kobayashi R, Matsumoto Y. Outcomes in two Japanese adenosine deaminase-deficiency patients treated by stem cell gene therapy with no cytoreductive conditioning. Journal of clinical immunology. 2015 May;35:384-98.
Miwa S, Fujii H, Matsumoto N, Nakatsuji T, Oda S, Miura Y, Asano H, Asano S. A case of red‐cell adenosine deaminase overproduction associated with hereditary hemolytic anemia found in Japan. American Journal of Hematology. 1978;5(2):107-15.
Ariga T, Oda N, Yamaguchi K, Kawamura N, Kikuta H, Taniuchi S, Kobayashi Y, Terada K, Ikeda H, Hershfield MS, Kobayashi K. T-cell lines from 2 patients with adenosine deaminase (ADA) deficiency showed the restoration of ADA activity resulted from the reversion of an inherited mutation. Blood, The Journal of the American Society of Hematology. 2001 May 1;97(9):2896-9.
Nihira H, Izawa K, Ito M, Umebayashi H, Okano T, Kajikawa S, Nanishi E, Keino D, Murakami K, Isa-Nishitani M, Shiba T. Detailed analysis of Japanese patients with adenosine deaminase 2 deficiency reveals characteristic elevation of type II interferon signature and STAT1 hyperactivation. Journal of Allergy and Clinical Immunology. 2021 Aug 1;148(2):550-62.
Ito M, Nihira H, Izawa K, Yasumi T, Nishikomori R, Iwaki-Egawa S. Enzyme activity in dried blood spot as a diagnostic tool for adenosine deaminase 2 deficiency. Analytical Biochemistry. 2021 Sep 1;628:114292.
Flinn AM, Gennery AR. Adenosine deaminase deficiency: a review. Orphanet journal of rare diseases. 2018 Dec;13:1-7.
Hirschhorn RO. Adenosine deaminase deficiency. Immunodeficiency reviews. 1990 Jan 1;2(3):175-98.
Whitmore KV, Gaspar HB. Adenosine deaminase deficiency–more than just an immunodeficiency. Frontiers in immunology. 2016 Aug 16;7:314.