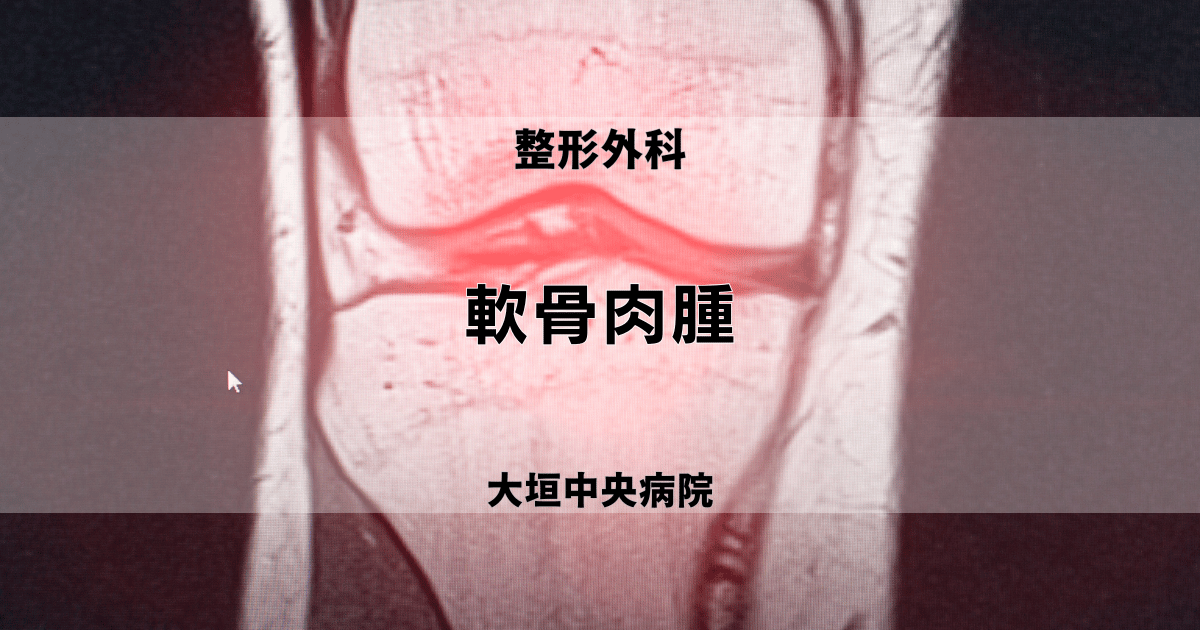軟骨肉腫(Chondrosarcoma)とは、悪性の骨腫瘍の一種で、骨の中にある軟骨組織の細胞が異常増殖を起こす病気です。
発生頻度は骨肉腫に次いで2番めに多い骨腫瘍で、骨腫瘍のなかの20~30%を占めます。
進行の程度や発生部位によって症状や治療の内容は大きく変わり、手術だけでなく薬物療法やリハビリテーションなど複数の治療法を組み合わせる必要があります。予後は腫瘍の組織学的グレードによって大きく異なります。
この記事の執筆者

臼井 大記(うすい だいき)
日本整形外科学会認定専門医
医療社団法人豊正会大垣中央病院 整形外科・麻酔科 担当医師
2009年に帝京大学医学部医学科卒業後、厚生中央病院に勤務。東京医大病院麻酔科に入局後、カンボジアSun International Clinicに従事し、ノースウェスタン大学にて学位取得(修士)。帰国後、岐阜大学附属病院、高山赤十字病院、岐阜総合医療センター、岐阜赤十字病院で整形外科医として勤務。2023年4月より大垣中央病院に入職、整形外科・麻酔科の担当医を務める。
軟骨肉腫の病型
軟骨肉腫は組織学的異型度(グレード)と発生様式の違いによって分類されます。
WHO(世界保健機構)の骨腫瘍分類(2020年改訂)では、グレード1~3の軟骨肉腫が定義されています。
グレード1
グレード1の軟骨肉腫は四肢骨※1に限り「異型軟骨腫(ACT)」と呼称され、臨床的には良性に近い振る舞いを示す境界病変と位置付けられます。
※1四肢骨:骨格のうち手や腕、足や脚を構成する骨の総称。
一方、体幹部(骨盤・肩甲骨・頭蓋底など)のグレード1病変は局所再発率が高く転移もしやすいため、引き続き「軟骨肉腫グレード1」として扱われます。
グレード2
グレード2では細胞密度や異型が増大し、中間悪性度の軟骨肉腫に相当します。
グレード3
グレード3では高度の異型性と有糸分裂像を示し、高悪性度で転移を来しやすいです。
なお、良性の内軟骨腫との鑑別は困難な場合があり、骨内への浸潤性発育パターンや粘液質基質の量などの組織学的所見から総合的に判断されます。
組織学的特徴の異なる亜型(サブタイプ)
軟骨肉腫には発生部位や組織学的特徴の異なる亜型(サブタイプ)も存在します。
大部分(約85%)を占めるのは通常型(中枢型)軟骨肉腫で、骨の髄内(中心部)に原発するタイプです。
これ以外に、続発(続発性)軟骨肉腫と称される良性軟骨性腫瘍からの二次的悪性化症例、および特殊型として脱分化型や間葉型、明細胞型や骨膜(表在)型軟骨肉腫などが挙げられます。
通常型(中枢型)
骨髄内に発生する最も一般的なタイプ(85%)。中年以降に好発し、四肢長管骨や骨盤に多い。
グレード1~3まで存在し、異型度に応じて局所再発率・転移リスクが上昇する。
続発性軟骨肉腫
良性軟骨腫瘍からの二次的悪性転化。骨内の内軟骨腫に由来する続発中枢型と、骨表面の骨軟骨腫に由来する続発末梢型がある。
多くは低グレードで組織学的所見は通常型と類似。末梢型では軟骨帽の肥厚(>2cm)や嚢胞変性がみられる。
脱分化型軟骨肉腫
通常型の低分化軟骨肉腫と、高分化肉腫(骨肉腫や未分化肉腫など)成分が突然の移行で混在する二相性腫瘍。
高齢者(60~80歳代)に多く、好発部位は大腿骨・骨盤・上腕骨など。極めて予後不良で、5年生存率0~24%と報告される。
間葉型軟骨肉腫
未分化な小円形細胞成分と軟骨分化成分からなる高悪性度腫瘍。若年者(20~30歳代)に発症し、四肢骨だけでなく軟部組織内に発生する例もある。
組織学的にはEwing肉腫様の未分化細胞と軟骨島の混在が特徴。比較的化学療法が奏効しやすいとされるが、5年生存率約50%。
明細胞型軟骨肉腫
まれな低悪性度軟骨肉腫。若年~中年成人(20~50歳)に発症し、長管骨の骨端部(大腿骨近位部や上腕骨近位部)に好発する。
組織学的には大型で淡明な細胞質をもつ腫瘍細胞がシート状に増殖し、軟骨基質をわずかに形成する。局所再発はあるものの進行は比較的緩徐で、5年生存率は62~100%と報告される。
骨膜(表在)型軟骨肉腫
骨の表面(骨膜下)に発生する軟骨肉腫。主に長管骨の骨幹端部(大腿骨・上腕骨)にみられ、20~40歳代に発症する。
多くはグレード1~2相当の低~中悪性度で、髄腔内への進展はまれ。局所切除で治癒しやすく予後良好な傾向で、5年生存率は68~93%とされる。
こうした病型ごとの違いに応じて治療戦略や予後が大きく異なるため、診断時には組織学的なグレーディングと病型の特定が重要です。
グレード1の中枢軟骨肉腫(ACT/低悪性度)と良性内軟骨腫の鑑別、および脱分化型など異型度の高いサブタイプの同定には、専門病理医を含む多職種チームでの検討が推奨されます。
軟骨肉腫の症状
軟骨肉腫の症状は、腫瘍が発生する部位や大きさによって大きく異なります。
初期段階は無症状や軽度の痛みにとどまるケースがあり、診断が遅れる場合もあります。早期発見には痛みや腫れなどのサインを見逃さない姿勢が重要です。
- 骨の傷み
- 腫れ・しこり・変形
- 運動機能の低下
- 神経症状
骨の痛みとその特徴
軟骨肉腫における代表的な症状の1つは骨の痛みです。初期は鈍い痛みで日常生活に大きな支障がない人もいますが、腫瘍が成長すると次第に強まります。
夜間にとくに痛みが増す傾向があり、睡眠障害を引き起こすケースもあります。
痛む部位に軽く触れるだけで違和感を覚える、骨を動かしたときに鋭い痛みを感じる、といった場合があります。
軟骨肉腫は一般に成長が緩徐なため、症状出現から診断まで平均10~15ヶ月を要するとの報告もあります。
- 鈍い痛みから始まる
- 夜間に痛みが増すことがある
- 日々の動作による刺すような痛み
- 定期的な鎮痛薬では改善が難しい場合もある
骨痛が続く期間の目安
| 痛みのタイプ | 持続期間の目安 | 補足 |
|---|---|---|
| 断続的な鈍痛 | 数週間〜数か月 | 進行が遅い軟骨肉腫の場合に多い |
| 強い鋭い痛み | 数週間以内に急に強まる場合がある | 進行が早い場合や腫瘍が大きいケースに多い |
| 夜間の激痛 | 数日〜数週間続くケースがある | 睡眠不足や生活の質の低下につながる |
腫れ・しこり・変形
腫瘍が大きくなると、患部の皮膚表面から触れてわかるようなしこりや腫れが見られるケースも少なくありません。
脚や腕などの四肢に発生した場合は、目で見てはっきりとわかる変形や腫脹を伴う場合があります。
また、骨盤や肩甲骨など体幹に近い骨に発生した場合でも、触診でなんとなく違和感を覚えるときがあります。
運動機能の低下
腫瘍が筋肉や神経、関節の動きに影響を及ぼすと、運動機能の低下が起こります。
具体例は、脚部に発生した場合は歩行困難や膝の曲げ伸ばしがスムーズにできなくなる、上肢に発生した場合は肩や肘の可動域が狭くなるなどの状態です。
激痛により動かすのを避けるようになり、結果的に筋力も低下する可能性が高まります。
運動機能低下の影響
- 日常動作の制限(歩行、階段昇降など)
- 自力での着替えや洗顔が難しくなる可能性
- 運動不足による筋力低下や体重増加
- 痛みをかばう姿勢から二次的な関節痛を起こす場合もある
神経症状
骨盤や脊椎など神経に近い部位で腫瘍が大きくなると、しびれや麻痺などの神経症状を伴う場合があります。
これは腫瘍による圧迫で神経伝達が障害されるために生じます。手先や足先のしびれ、体幹部の感覚異常が続くときは、軟骨肉腫の可能性を含めた検査が必要です。
軟骨肉腫の原因
軟骨肉腫の原因は明確に特定されていない部分があります。
ただし、遺伝的要因や骨にかかる長期的な負荷、既存の良性骨腫瘍の悪性化など、さまざまなリスク要因が指摘されています。
遺伝的要因
- 遺伝子変異が関係する
- 家族内に良性腫瘍が多い場合は注意が必要
- 遺伝カウンセリングを検討するケースもある
- 一部の骨の成長に異常を持つ症例では発生率が上がる
先天的に軟骨肉腫は家族性に発生しやすいケースが報告されています。
特定の遺伝子変異や家系的素因を持つ人は、骨軟骨腫や多発性内軟骨腫など良性腫瘍の段階を経て、続発性軟骨肉腫に移行するリスクが高まる場合があります。
| 要因 | 例 |
|---|---|
| 遺伝子変異 | IDH1, IDH2 などが報告されている |
| 家族性腫瘍症候群 | リー・フラウメニ症候群など |
| 良性腫瘍からの悪性化 | 骨軟骨腫、多発性内軟骨腫など |
既存の良性腫瘍の悪性化
良性の骨腫瘍として知られる骨軟骨腫や内軟骨腫は、特に大きくならない限りは無症状のまま経過する人もいます。
しかし、まれに時間をかけて悪性化し、軟骨肉腫へと移行するケースがあります。良性腫瘍の経過観察中に痛みや腫れが増大しはじめたときは、軟骨肉腫への転換を疑って医療機関の受診が必要です。
その他の可能性
放射線被ばくや免疫機能の低下、加齢による細胞修復能力の衰えなども要因の1つと考えられています。
ただし、これら単独で軟骨肉腫に直結すると断定するのは難しく、複数の要因が重なって発生リスクが高まる場合が多いと考えられています。
軟骨肉腫の検査・チェック方法
軟骨肉腫の症状が疑われる場合、専門医の診察を受け、複数の検査を組み合わせることが大切です。
画像検査や血液検査、組織検査など、それぞれの特性を活かすと正確な診断に近づきます。
画像検査
| 検査名 | 特徴 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
| X線 | 単純撮影で骨の異常を大まかに把握 | 迅速・低コスト | 軟部組織の評価は不十分 |
| CT | X線を多方向から撮影し、断層画像を作成 | 骨の細部を詳細に描出 | 放射線量がやや多い |
| MRI | 強い磁場を使って軟部組織も撮影 | 軟骨や筋肉なども鮮明に把握可能 | 機器によっては撮影時間が長い |
代表的な画像検査にはX線、CT、MRIがあります。
X線画像では骨の形状や腫瘍の有無を把握し、CTではより詳細な骨構造や腫瘍の境界を確認できます。
MRIは骨だけでなく軟部組織の状態も評価できるため、腫瘍の広がりや周囲組織との関係を立体的に把握しやすいです。
X線
- 溶骨性と造骨性が混在した病変
- 「Rings and arcs」と表現される石灰化パターン
- 骨の輪郭に沿って内部から骨皮質を侵食するようなendosteal scalloping(骨皮質内側の侵食像)がみられる
CT
- 骨破壊の程度や、石灰化の分布を評価
- 胸部CTは肺転移の検索に必須
MRI
- T2強調像で高信号を示す
- 髄腔内の範囲や軟部組織への浸潤が詳細に評価できる
血液検査
軟骨肉腫の場合、血液検査で特定の腫瘍マーカーが上昇するわけではないため、決定打にはなりにくいです。
ただし、炎症反応や全身状態を確認できるため、治療方針を立てる上で有用です。
貧血の有無や肝機能・腎機能などの状態を把握し、手術や薬物療法に耐えられる体力があるかを総合的に評価する材料になります。
生検(組織検査)
- 腫瘍の部位によって採取方法が異なる
- がん細胞の性質や増殖速度を推定しやすい
- 組織検査の結果が確定診断につながる
- 手術のリスクを見極める参考にもなる
生検は最終的な診断にとって重要です。腫瘍の一部を採取し、顕微鏡で細胞レベルの異常を確認します。
腫瘍が存在する位置によっては骨を一部削り取るようにして検体を取る必要があるため、少々侵襲的な検査です。
組織を調べてがん細胞の分化度や悪性度を判断し、治療計画を具体的に立てられます。
- 患部への局所麻酔または全身麻酔
- 腫瘍部分の骨を少量切削
- 切り出した検体を病理専門医が観察
- 数日〜数週間後に結果を報告
軟骨肉腫の治療方法と治療薬、リハビリテーション、治療期間
軟骨肉腫の治療は、外科的切除を中心に、化学療法や放射線療法を組み合わせる形が一般的です。
加えて、術後の機能回復を目指すリハビリテーションや、再発を防ぐための定期検診など、総合的な取り組みが大切になります。
外科的切除
| 手術名称 | 特徴 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
| 骨切除(広範囲切除) | 腫瘍を含む骨の一部または全部を切除 | 再発リスクを下げられる | 切除範囲が広い場合は機能低下が大きい |
| 人工関節置換 | 切除した骨や関節を人工関節で置換 | 関節機能の一定回復 | 人工物の摩耗や定期交換が必要になる |
| 骨移植(自家/人工) | 自家骨や人工骨を使って骨欠損部を補充 | 骨の連続性を維持しやすい | 移植骨の癒合不良のリスクがある |
軟骨肉腫の治療で最も重要な位置づけを持つのが外科的切除です。腫瘍を取り除く範囲や方法は、腫瘍の大きさや部位、周囲組織との関係や悪性度によって異なります。
骨を大きく切除した場合は骨移植や人工関節を使用するケースがあり、機能温存と再発リスクのバランスを考えた手術が重要です。
- 腫瘍周辺の骨を含めて切除する
- 再建方法として金属インプラントを使うケースがある
- 骨の欠損部には自家骨移植や人工骨移植を検討
- 神経や血管を可能な限り温存しながら切除する
- 四肢の低悪性度の場合、病巣部のみの掻爬術が選択されるときもある
化学療法
軟骨肉腫は、骨肉腫や他の骨腫瘍と比べて化学療法が効きにくい特性があり、標準的に推奨されるレジメン※2はありません。
※2レジメン:化学療法におけるレジメンとは、薬剤の種類や投与量、投与方法や投与スケジュールなどを示した治療計画。
これは、軟骨肉腫は増殖速度が遅く、血流が乏しいため薬剤が効きにくいのが原因です。
しかし、高悪性度のタイプや手術が難しい場合には、抗がん剤の使用を検討します。一般的に用いられる抗がん剤には、ドキソルビシンやシスプラチンなどがあり、がん細胞の増殖を抑制する役割を担います。
- 腫瘍の増殖スピードを抑える
- 転移リスクの低減を図る
- 手術前に腫瘍を縮小して切除しやすくする
- 術後の再発リスクを下げる
放射線療法
軟骨肉腫は放射線に対して感受性が低く、単独での放射線療法による根治は難しいと言われています。
ただし、手術の適応が難しい場所や、腫瘍の大きさが非常に大きいケースでは、症状緩和や腫瘍の増殖抑制のために放射線療法を併用する場合があります。
リハビリテーション
| 時期 | 目標 | トレーニング |
|---|---|---|
| 術後直後(数日以内) | 痛みのコントロール、ベッド上での活動 | 深呼吸、軽いベッド上体位変換など |
| 退院前(数週間) | 基礎的な歩行能力の回復 | 歩行器・松葉杖を使用した歩行練習 |
| 退院後(数か月以内) | 日常生活動作の自立 | 自宅での筋力強化、バランス訓練 |
| 長期(半年以降) | 社会復帰、スポーツ復帰 | ステップ運動、軽いジョギングなど |
手術後は、失われた骨や関節の機能を補いつつ、元の生活に近づけるのを目指すリハビリテーションが重要です。
理学療法士や作業療法士による専門的なリハビリテーションプログラムを実施して、関節の可動域訓練や筋力強化を行い、日常生活動作の向上を図ります。
- 歩行訓練
- 関節可動域訓練
- 筋力強化と持久力アップ
- 日常生活動作の再習得
治療期間
軟骨肉腫の治療期間は、病期や治療の組み合わせによって大きく変わります。
手術の入院期間だけでも2〜4週間程度かかるケースが多く、術後のリハビリテーションや化学療法を加えるとトータルで半年以上の治療期間になる人も珍しくありません。
再発リスクの有無も考慮して、定期的な通院と検査が数年間にわたって継続する場合があります。
薬の副作用や治療のデメリット
軟骨肉腫の治療は多角的な取り組みが必要なため、外科手術や薬物療法、放射線療法など、さまざまな副作用やデメリットが考えられます。
主治医と十分に情報共有しながら、リスクと得られる効果のバランスを考えていくのが大切です。
抗がん剤の副作用
- 吐き気や嘔吐
- 食欲不振
- 口内炎や口腔粘膜のただれ
- 脱毛
- 感染症にかかりやすくなる(白血球減少)
- 心筋障害
- 腎機能障害
- 末梢神経障害
化学療法で用いる抗がん剤には、吐き気や嘔吐をはじめとする複数の副作用がみられる場合があります。
軟骨肉腫は抗がん剤が効きにくいとされるため、大きな効果を得るためには用量や投与期間を調整する必要があり、その結果として副作用が強く出やすいです。
- 制吐剤の使用(吐き気を軽減する)
- 栄養状態を維持するための食事指導
- うがい薬や口腔ケア用品の活用
- 免疫力を保つための衛生管理
- 副作用の程度に応じた投与量やスケジュールの調整
手術による機能障害
| 合併症 | 例 | 対応方法 |
|---|---|---|
| 感染症 | 手術創部の細菌感染、深部感染など | 抗生剤投与、手術創の洗浄・再縫合 |
| 血管障害 | 出血、血栓形成など | 術中止血、弾性ストッキング、血栓予防薬の使用 |
| 神経障害 | 手足のしびれ、麻痺など | 神経回復を促すリハビリ、場合によって追加手術 |
| インプラントの不具合 | 人工関節や固定プレートのゆるみ、破損など | 定期的な画像検査、再手術による再固定や交換 |
広範囲の骨切除や人工関節の置換によって、関節の可動域や筋力が低下する場合があります。
なかでも股関節や膝関節などの体重がかかる部位の手術では、術後のリハビリテーションを長期にわたり行う必要があります。
機能回復が思うように進まないケースもあるため、焦らずに取り組む姿勢が大切です。
放射線療法のデメリット
放射線療法は軟骨肉腫に対して十分な効果が期待しにくい一方で、照射部位の皮膚炎や線維化が起きたり、倦怠感などが生じたりする可能性があります。
また、長期的には骨の脆弱化や他の部位に二次がんが発生するリスクがわずかに増加するともいわれます。
とはいえ、手術不能のケースや痛みを緩和したいケースでは放射線が選択肢になる場合があるため、デメリットを理解した上で検討します。
心理的負担
治療には長期にわたる通院や入院が必要になる場合が多く、患者さんは身体的にも精神的にも負担を抱えやすいです。
副作用や機能障害によってこれまでの生活が一変する場合もあるため、カウンセリングや家族・友人のサポート体制を確保しながらの治療が大切です。
保険適用と治療費
以下に記載している治療費(医療費)は目安であり、実際の費用は症状や治療内容、保険適用否により大幅に上回ることがございます。当院では料金に関する以下説明の不備や相違について、一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。
軟骨肉腫の治療費は、外科手術や薬物療法、リハビリテーションなど多岐にわたります。
公的医療保険が適用されるため、自己負担割合が3割(あるいは所得や年齢に応じて1割または2割)になり、治療費の大きな部分を保険でカバーできます。
ただし、高額療養費制度※3を利用する際には、適切に手続きを行う必要があります。
※3高額療養費制度:ひと月の医療費の自己負担額が、所得に応じて定められた上限額(自己負担限度額)を超えた場合に、その超えた分の金額が後から払い戻される制度。
手術費用
軟骨肉腫の手術費用は切除範囲や再建方法によって大きく変わりますが、人工関節置換を伴う大がかりな手術では、保険適用前の総額で数百万円になるケースがあります。
保険適用後は自己負担額が数十万円程度になる場合が多く、高額療養費制度の適用があれば、自己負担額がさらに低く抑えられる傾向があります。
化学療法の費用
抗がん剤の種類や投与スケジュールによって費用が上下します。1クールあたり数万円〜数十万円ほどかかるケースが多く、複数クール行う場合は累積的に大きな額になります。
ただし、これも公的医療保険や高額療養費制度の対象となるので、実際の自己負担額は軽減されます。
リハビリテーションの費用
入院中のリハビリテーションは、基本的に入院費に含まれる形になります。
退院後の外来リハビリは、1回あたり数百円〜数千円の自己負担となるケースが多いです。
頻度や期間にもよりますが、継続的なリハビリテーションが必要になる場合は、家計への負担を考慮しつつ計画を立てる必要があります。
補装具・通院関連費用
- 松葉杖や装具用の購入費用
- 病院までの交通費
- 遠方の場合の宿泊費
- 診断書や証明書の発行費
大規模な骨切除や関節再建を行った患者さんは松葉杖や装具などを購入する必要が出てくる場合がありますが、これらも保険の適用範囲になる場合があり、一部負担で済む人が多いです。
通院にかかる交通費や宿泊費は保険適用外のため、遠方からの受診や長期入院を予定している方は、事前に予算を検討するのが望ましいです。
以上
参考文献
GELDERBLOM, Hans, et al. The clinical approach towards chondrosarcoma. The oncologist, 2008, 13.3: 320-329.
WEINSCHENK, Robert C.; WANG, Wei-Lien; LEWIS, Valerae O. Chondrosarcoma. JAAOS-Journal of the American Academy of Orthopaedic Surgeons, 2021, 29.13: 553-562.
RIEDEL, Richard F., et al. The clinical management of chondrosarcoma. Current treatment options in oncology, 2009, 10: 94-106.
HEALEY, JOHN H.; LANE, JOSEPH M. Chondrosarcoma. Clinical Orthopaedics and Related Research®, 1986, 204: 119-129.
LICHTENSTEIN, Louis; JAFFE, Henry L. Chondrosarcoma of bone. The American journal of pathology, 1943, 19.4: 553.
LEE, Francis Y., et al. Chondrosarcoma of bone: an assessment of outcome. JBJS, 1999, 81.3: 326-38.
PRING, Maya E., et al. Chondrosarcoma of the pelvis: a review of sixty-four cases. JBJS, 2001, 83.11: 1630-1642.
LEDDY, Lee R.; HOLMES, Robert E. Chondrosarcoma of bone. orthopaedic oncology: primary and metastatic tumors of the skeletal system, 2014, 117-130.
GIUFFRIDA, Angela Ylenia, et al. Chondrosarcoma in the United States (1973 to 2003): an analysis of 2890 cases from the SEER database. JBJS, 2009, 91.5: 1063-1072.
GAZENDAM, Aaron, et al. Chondrosarcoma: a clinical review. Journal of Clinical Medicine, 2023, 12.7: 2506.