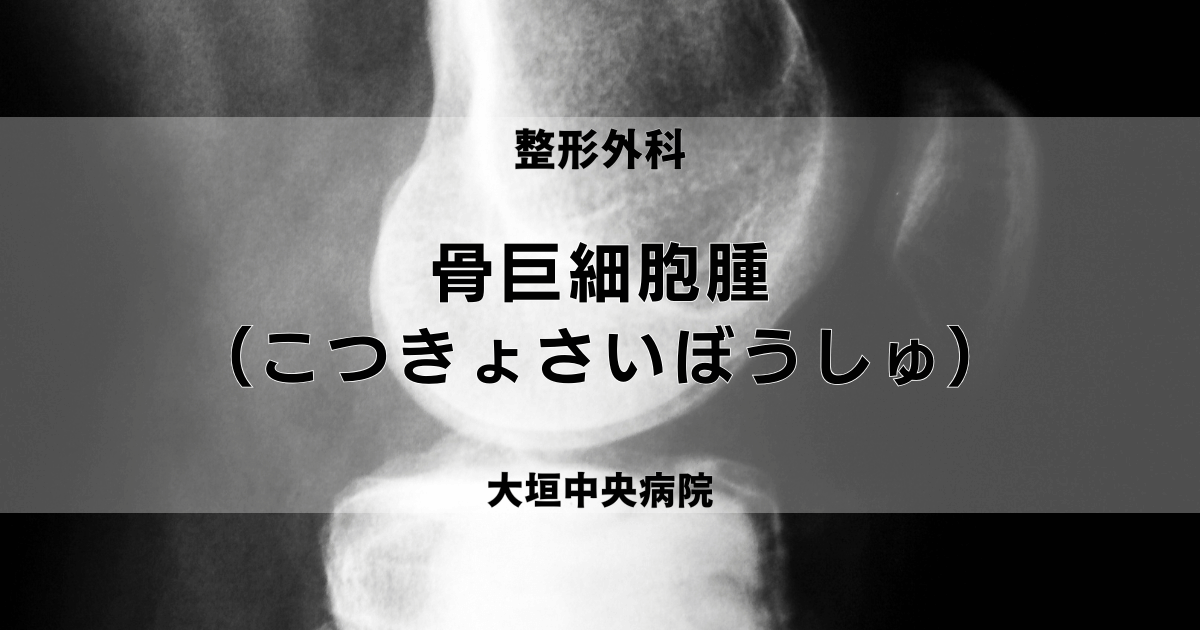骨巨細胞腫(こつきょさいぼうしゅ、Giant Cell Tumor of Bone:GCTB)とは、骨の先端生じる腫瘍の一種です。
若年から中年の方に発症しやすく、基本的には骨端線が閉じた成熟骨格の人に生じます(小児はまれ)。
良性と悪性の中間に位置付けられ、多くの場合は局所的に進行して骨を侵しますが、まれに肺などへの転移を起こします。
骨の痛みや腫れ、機能障害などにより日常生活に大きな支障を与えるおそれがあるため、早期発見と治療が大切です。
この記事の執筆者

臼井 大記(うすい だいき)
日本整形外科学会認定専門医
医療社団法人豊正会大垣中央病院 整形外科・麻酔科 担当医師
2009年に帝京大学医学部医学科卒業後、厚生中央病院に勤務。東京医大病院麻酔科に入局後、カンボジアSun International Clinicに従事し、ノースウェスタン大学にて学位取得(修士)。帰国後、岐阜大学附属病院、高山赤十字病院、岐阜総合医療センター、岐阜赤十字病院で整形外科医として勤務。2023年4月より大垣中央病院に入職、整形外科・麻酔科の担当医を務める。
骨巨細胞腫の病型
骨巨細胞腫(こつきょさいぼうしゅ)の分類としては、画像検査での腫瘍の拡がりや骨破壊の程度に基づく 「Campanacci分類」が広く用いられます。
Campanacci分類では腫瘍をGrade I~IIIの3段階に分けます。
- Grade I:骨皮質の膨隆や破壊を伴わない境界明瞭な骨透亮域
- Grade II:骨皮質が菲薄化するものの連続性は保たれ境界は比較的明瞭な病変
- Grade III:骨皮質の破壊や明らかな軟部組織への腫瘍進展を伴う病変
Gradeが上がるほど局所浸潤性が高く、再発率も高いのが一般的です。
また、外科的治療の方針にも影響し、Grade III(特に関節外へ腫瘍が進展した症例)では関節温存が困難な場合もあります。
病理学的には、骨巨細胞腫の大部分は良性像を示しますが、稀に高度異型の細胞増殖を伴う悪性型骨巨細胞腫が存在します。
悪性型は、初発から悪性所見を示す「一次性悪性骨巨細胞腫」と、良性骨巨細胞腫の既往部位に二次的に肉腫(多形性未分化肉腫など)が発生する「二次性悪性骨巨細胞腫」に分類され、後者は特に放射線照射後の発生が古くから知られています。
一方、多発性骨巨細胞腫はきわめてまれ(全症例の1%未満)ですが報告があり、Jaffe-Campanacci症候群(カフェオレ斑や軟部腫瘍を伴う)など特定の症候群との関連が指摘された例もあります。
WHO分類上、骨巨細胞腫は「中間型(局所浸潤性、稀に転移)」に位置付けられており、完全な良性と悪性腫瘍の中間の生物学的振る舞いをする腫瘍と捉えられています。
骨巨細胞腫の症状
骨巨細胞腫(こつきょさいぼうしゅ)は腫瘍が存在する骨の部位によって、症状が異なる場合があります。
初期は軽度の痛みや違和感しかなくても、腫瘍が大きくなると骨変形や可動域制限を伴う可能性が高まります。
痛みや腫れ
骨巨細胞腫の代表的な症状は、腫瘍部位の痛みと腫れです。
痛みは運動時に強まるケースが多いですが、進行すると安静時にも違和感や鈍痛が続くおそれがあります。
また、腫脹によって皮膚の上からでも患部がわかるほどに膨らむ場合があり、日常動作に支障を及ぼしかねません。
- 運動や歩行などの活動時
- 重い物を持ち上げるとき
- 連続して負荷をかける作業のとき
- 夜間や姿勢を変えたとき(進行度が高い場合)
関節の可動域制限
| 発生部位 | 可動域制限の主な影響 |
|---|---|
| 膝関節付近 | 階段の昇降や歩行が困難になる場合がある |
| 手首付近 | ペットボトルの開封や細かい作業が難しくなる |
| 肩関節付近 | 腕を上げる動作が制限され、衣服の着脱がしづらくなる |
| 足首付近 | スポーツやジョギングをしにくくなる |
多くの場合、骨巨細胞腫は関節付近に生じるため、膝や手首、肩などの可動域が低下しやすいです。
腫瘍が大きくなると骨自体が変形し、関節がスムーズに動かなくなったり、関節液が貯留して膝が腫れたりする場合があります。
こうした状態を放置すると、周辺の筋力低下や関節拘縮を引き起こすリスクが高まります。
病的骨折のリスク
骨巨細胞腫が骨の強度を著しく低下させると、外力が大きくない場面でも骨折が起こる(病的骨折)リスクが高まります。
骨折が発生すると強い痛みと機能障害が生じ、骨がくっつくまでの治療期間が長引くケースもあるため、早期発見・早期治療が重要です。
痛み以外の全身症状
骨巨細胞腫は局所症状が中心ですが、腫瘍が大きくなると周辺の神経や血管を圧迫し、しびれやむくみが生じる可能性もあります。
悪性度が高い骨巨細胞腫では、肺への転移など全身合併症を引き起こす場合もあるため、体調の変化を見逃さないように注意が必要です。
- 骨の痛みが長期間続く
- しびれやむくみが増してきた
- 発熱や倦怠感が続く(腫瘍の増大や合併症が疑われる場合)
- 過去に骨巨細胞腫の手術歴があり、再び痛みを感じる
骨巨細胞腫の原因
骨巨細胞腫(こつきょさいぼうしゅ)の発症原因は、はっきりとは解明されていません。
ただし、近年の分子遺伝学的研究により、本腫瘍の腫瘍細胞(間質細胞)に高頻度で共通して見られる遺伝子変異が報告されています。
細胞レベルの発症メカニズム
骨巨細胞腫は「多核巨細胞(破骨細胞に類似した細胞)」が増殖し、骨を吸収するように増えるのが特徴です。
正常な骨リモデリングでは骨芽細胞と破骨細胞のバランスがとれていますが、骨巨細胞腫では破骨細胞の働きが過度に活性化している可能性があります。
| 細胞名 | 役割 |
|---|---|
| 骨芽細胞 | 骨の形成を行い、骨密度を維持する |
| 破骨細胞 | 骨を吸収し、骨のリモデリングを調整する |
| 多核巨細胞 | 骨巨細胞腫で増殖し、骨を過度に破壊する場合がある |
遺伝的要因
前述のように遺伝子変異が報告されており、それはヒストンH3遺伝子(H3F3A)の変異で、特にグリシン34がトリプトファンなどに置換される点突然変異(H3.3 G34Wなど)が約90%以上の骨巨細胞腫で検出されます。
この変異は骨巨細胞腫の診断マーカーにもなっており、免疫染色でH3.3 G34W変異に特異的な抗体を用いることで腫瘍の鑑別診断に役立つとの報告もあります。
骨巨細胞腫の検査・チェック方法
骨巨細胞腫(こつきょさいぼうしゅ)の診断には、問診や視診、触診だけではなく、さまざまな画像検査や病理検査が必要です。
問診と身体診察
初診時には、症状の経過や痛みの度合い、生活習慣、家族歴などを丁寧に聞き取ります。
その後、視診や触診で患部の腫れや熱感、圧痛の有無を確認し、病的骨折の疑いがないかをチェックします。
- 痛みの始まりと持続期間
- 症状の強弱や増悪因子・軽減因子
- 既往歴や家族歴の有無
- 日常動作で困難を感じる場面
画像検査
骨巨細胞腫の診断や進行度を評価するために、X線や骨シンチグラフィなどの画像検査を行います。
- X線(レントゲン):偏心性の骨透亮像、蜂巣状構造、骨端軟骨下まで達する破壊像、骨硬化像を欠く明瞭な境界など
- 骨シンチグラフィ:骨巨細胞腫で特有なドーナツサイン(病変周囲に集積が強く、中心部は壊死のため集積が抜けて輪状に見える所見)
また、CTやMRIでは骨内部の詳細な構造や、軟部組織への浸潤の有無を調べることが可能です。
病理検査(生検)
画像検査で腫瘍が疑われる場合、病理検査のために腫瘍の一部を採取(生検)して組織学的な分析を行います。
多核巨細胞の有無や核の異型度などを観察し、骨巨細胞腫かどうかを最終的に判断します。
得られた組織で、多数の破骨細胞巨細胞と単核紡錘形細胞からなる組織像が確認されれば診断となります。
病理検査は確定診断に欠かせないステップですが、類似の疾患も多いため鑑別疾患が重要です。
血液検査
一般的な骨巨細胞腫では血液検査において大きな異常はでませんが、感染やほかの炎症性疾患との鑑別、全身状態の把握を目的として血液検査を行う場合があります。
血沈やCRPが高値の場合、炎症や感染症の合併が疑われます。
- 血球計算(白血球や赤血球、血小板の数)
- C反応性蛋白(CRP)
- 血清カルシウムやアルカリフォスファターゼなど骨代謝に関連する指標
- 肝機能や腎機能
骨巨細胞腫の治療方法と治療薬、治療期間
骨巨細胞腫(こつきょさいぼうしゅ)の主な治療法は外科的手術ですが、必要に応じて薬物療法を組み合わせるほか、術後のリハビリテーションをしっかりと行うことが重要です。
外科的治療
| 治療法 | 特徴 |
|---|---|
| 掻爬術(そうはじゅつ) | 腫瘍部分をかき出して除去し、骨移植や骨セメントで補強する |
| 広範切除術 | 腫瘍が大きい場合に患部を広く切除し、人工関節を置き換える |
| 骨移植 | 自家骨や人工骨などを用いて骨欠損部を補充し、強度を補う |
| 骨セメント充填 | 硬化性樹脂(セメント)で空洞を埋め、骨の安定性を高める |
骨巨細胞腫では、腫瘍部位を掻爬(そうは)して腫瘍を除去する手術が第一選択です。
単純に掻爬するだけでは再発率が高い(30~50%)とされており、再発リスクを下げるために高速回転バーによる掻爬面の掘削や骨セメントの重点が行われます。
骨セメント充填は単に空隙を埋める物理的支持だけではなく、固まるときの熱による腫瘍細胞の壊死効果が期待できます。
腫瘍の広がりが大きい場合は、骨の一部を切除して骨移植をしたり人工関節を置換したりする方法も考えられます。
単純な掻爬術であれば、入院期間は1~2週間程度です。
薬物療法と分子標的薬
近年では、デノスマブと呼ばれるRANKL(破骨細胞形成を促進する物質)を阻害する薬剤が骨巨細胞腫の治療に用いられるケースがあります。
デノスマブを投与すると、破骨細胞の活性を抑制し、骨破壊を食い止める効果が期待できます。
初回1か月間に4回投与(1週目、2週目、3週目、4週目に各120mg皮下注)し、以降は4週ごと(月1回)の維持投与を続けるのが通常です。
また、化学療法や放射線治療を併用するケースは少ないですが、再発例や手術が困難な症例では追加の選択肢となる場合があります。
- デノスマブ:RANKLを阻害し、腫瘍部位での骨破壊を抑制する
- 非ステロイド性抗炎症薬:痛みのコントロールに用いる
- ビスホスホネート:骨吸収を抑える作用があり、補助的に投与する場合がある
リハビリテーションの重要性
術後は、患部の骨を保護しながら関節機能や筋力を回復させるリハビリが大切です。
リハビリの開始時期や内容は手術の種類や腫瘍の広がりによって異なり、医師や理学療法士の指導のもとで、無理のない範囲から運動を始めていきます。
| 時期 | リハビリ内容 |
|---|---|
| 術後直後 | 安静を保ちつつ、痛みや腫れの観察、患部の固定 |
| 退院前 | 関節の可動域訓練や軽い筋力トレーニング |
| 退院後~数週間 | 日常生活動作の復帰に向けたリハビリ、歩行練習など |
| 数か月以降 | スポーツや負荷の高い運動を再開する場合は医師と相談が必要 |
治療期間の目安
骨巨細胞腫の治療期間は、外科的手術の有無や腫瘍の大きさ、部位によって差がありますが、手術後から社会復帰までに数か月以上かかるケースが一般的です。
また、再発を防ぐための経過観察で、数年にわたる通院が必要となるケースもあります。
- 腫瘍の大きさや進行度
- 手術の種類(掻爬術だけか、広範切除か)
- 術後のリハビリの進み具合
- 転移や再発の有無
薬の副作用や治療のデメリット
骨巨細胞腫(こつきょさいぼうしゅ)の治療には手術のリスクや投薬の副作用が伴います。
特にデノスマブなどの分子標的薬は、骨吸収を抑える効果が高い反面、長期投与によるさまざまな副作用が報告されています。
デノスマブの主な副作用
| 副作用 | 内容 |
|---|---|
| 顎骨壊死 | 顎の骨が壊死して痛みや腫れ、骨露出などが生じる |
| 低カルシウム血症 | 血液中のカルシウム濃度が低下し、筋肉けいれんなどを起こす |
| 皮膚症状 | かゆみや発疹などの皮膚トラブルが発生するおそれがある |
デノスマブは破骨細胞の働きを抑えることで骨を保護しますが、長期間の使用により顎骨壊死や低カルシウム血症などを発症するリスクがあります。
顎骨壊死を起こすと歯科治療が難しくなるおそれがあるため、服薬中は定期的な歯科検診や口腔ケアが大切です。
外科的手術のリスク
- 出血や感染症のリスク
- 人工関節置換後の摩耗やゆるみ
- 骨移植部位からの痛みや不快感
- 長期的な経過観察が必要になる
- 術後の関節拘縮
手術には全身麻酔や出血、感染症などのリスクが伴うほか、広範切除を行った場合は、関節の置換や骨移植によって患部の機能が大きく変わる可能性があります。
機能回復には時間がかかる場合があり、リハビリを続けても以前の状態に完全には戻らない危険性があります。
再発の可能性と追加治療
骨巨細胞腫は再発率が高い腫瘍のひとつです。
掻爬術で腫瘍を取り切ったと判断しても、残存した腫瘍細胞が再度増殖し、再び痛みや腫れを感じる場合があります。
再発が起こった場合は、追加の手術や薬物療法が必要です。
放射線治療の副作用
骨巨細胞腫で放射線治療を行うケースは多くありませんが、部位によっては手術が難しい場合に放射線治療を検討します。
放射線治療の副作用として、照射部位の皮膚炎や骨の劣化などが報告されています。
長期的にみると放射線照射による二次がんのリスクもわずかに存在するため、慎重な判断が必要です。
保険適用と治療費
以下に記載している治療費(医療費)は目安であり、実際の費用は症状や治療内容、保険適用否により大幅に上回ることがございます。当院では料金に関する以下説明の不備や相違について、一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。
骨巨細胞腫(こつきょさいぼうしゅ)の治療は、公的医療保険(健康保険)の適用対象となる場合が多く、手術費や入院費に加え、デノスマブなどの薬剤費用も一部負担となります。
ただし、自己負担額は治療内容や保険制度、所得などの条件によって異なります。
外科的治療の費用目安
| 手術内容 | 自己負担額の目安 |
|---|---|
| 掻爬術+骨移植(2~3週間入院) | 20万~40万円前後 |
| 広範切除+人工関節置換 | 30万~50万円前後 |
| 短期入院での軽度手術 | 10万~20万円前後 |
薬剤費用(デノスマブなど)の目安
デノスマブは保険適用がある場合でも、1回の注射で数万円以上の費用がかかる薬剤です。
初回投与から数か月ごとに継続投与を行うケースが多く、年間で10万~20万円以上の自己負担額となる場合があります。
- 高額療養費制度の利用
- 所得区分や医療費控除のチェック
- 投薬スケジュールの確立(医師と相談)
- ジェネリック医薬品の利用可否の確認
※高額療養費制度:同一月に高額な医療費の自己負担が必要となった際に、限度額を超えた分について払い戻しを受けられる制度
リハビリテーション費用の目安
リハビリは基本的に保険適用となりますが、一定の日数制限が設けられている場合があります。
また、外来リハビリを続ける際は、通院に伴う交通費も考慮しなければなりません。
理学療法士の指導下で行うリハビリテーションは、週数回の通院リハビリで1か月あたり数千円~1万円程度かかります(3割負担の場合)。
以上
参考文献
TURCOTTE, Robert E. Giant cell tumor of bone. Orthopedic Clinics, 2006, 37.1: 35-51.
ECKARDT, JEFFREY J.; GROGAN, THOMAS J. Giant cell tumor of bone. Clinical Orthopaedics and Related Research (1976-2007), 1986, 204: 45-58.
MENDENHALL, William M., et al. Giant cell tumor of bone. American journal of clinical oncology, 2006, 29.1: 96-99.
CAMPANACCI, Mario, et al. Giant-cell tumor of bone. JBJS, 1987, 69.1: 106-114.
MCDONALD, Douglas J., et al. Giant-cell tumor of bone. JBJS, 1986, 68.2: 235-242.
SOBTI, Anshul, et al. Giant cell tumor of bone-an overview. Archives of Bone and Joint Surgery, 2016, 4.1: 2.
RASKIN, Kevin A., et al. Giant cell tumor of bone. JAAOS-Journal of the American Academy of Orthopaedic Surgeons, 2013, 21.2: 118-126.
BALKE, Maurice, et al. Giant cell tumor of bone: treatment and outcome of 214 cases. Journal of cancer research and clinical oncology, 2008, 134: 969-978.
BINI, StefanoA; GILL, Kan; JOHNSTON, James O. Giant cell tumor of bone. Clinical Orthopaedics and Related Research®, 1995, 321: 245-250.
BERTONI, Franco; BACCHINI, Patrizia; STAALS, Eric L. Malignancy in giant cell tumor of bone. Cancer: Interdisciplinary International Journal of the American Cancer Society, 2003, 97.10: 2520-2529.