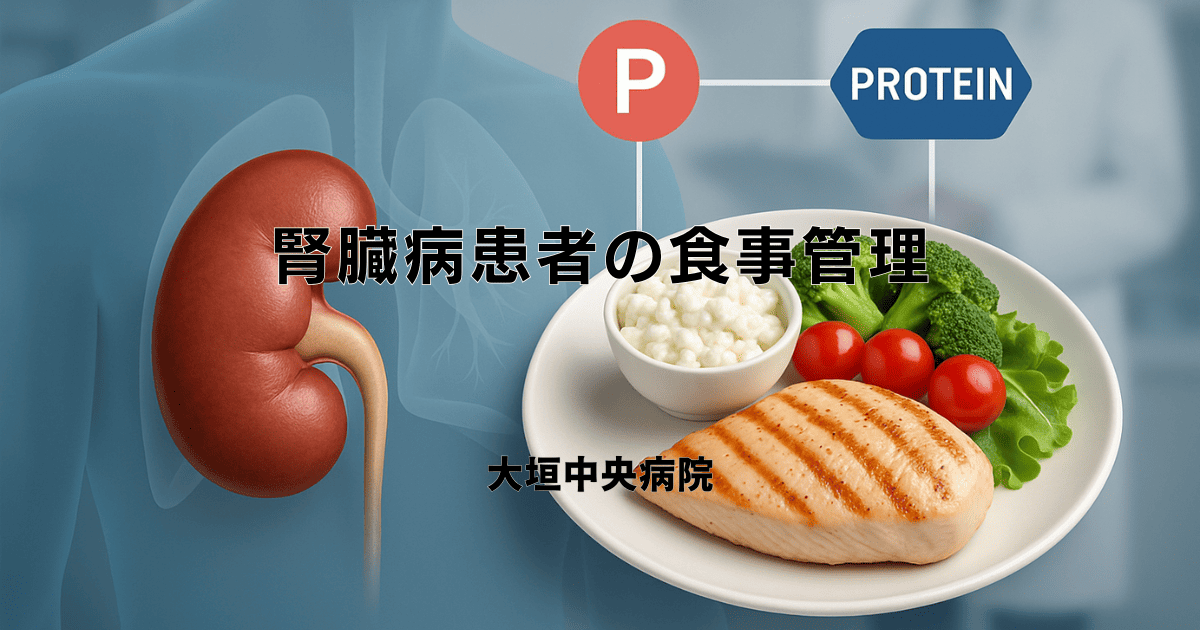慢性腎臓病や透析が必要になる可能性がある方にとって、日常の食事の管理は大切です。特にたんぱく質やリンを過剰に摂取すると腎臓への負担が増えるため、病状の進行を早めたり、透析治療の導入が近づいたりする恐れがあります。
適切な食事管理によって健康を保ちながら生活を続けるために、腎臓病たんぱく質目安や腎臓病リン摂取量を理解し、バランスのよい食事を意識することが重要です。
この記事では、腎臓病の方が気をつけたい栄養管理のポイントや具体的な工夫例、さらに日常生活での継続方法などを総合的に紹介します。
腎臓病と食事管理の重要性
腎臓病になると老廃物や余分な水分の排出機能が低下しやすくなります。その状態を放置すると生活の質が下がるだけでなく、症状が悪化すると透析を要する段階に進むこともあります。
食事管理は腎臓の負担を和らげる大きな鍵になります。
腎臓の働きと病状進行との関係
腎臓は体内の老廃物を尿として排出する働きを担います。さらに体液の量や電解質を調整し、血圧にも関与します。腎機能が低下すると老廃物の蓄積や水分調節不良が生じ、むくみや高血圧などの症状が目立ちます。
症状が進むと体内環境が乱れやすくなり、医療機関での管理が必要な段階に進行する可能性があります。
食事による影響
塩分の取りすぎやたんぱく質、リンなどの過度な摂取は腎臓に負担をかけます。特に腎臓病リン摂取量が多い食事を習慣的に続けると、血中リン濃度が上昇し骨や血管に悪影響を及ぼしやすくなります。
腎臓病たんぱく質目安を大幅に超える摂取は、老廃物の排出作業を増やして腎機能を疲れさせます。
食事制限の目的
食事制限という言葉には厳しい印象がありますが、実際には腎機能を守るための適切な栄養バランスを意識することが目的です。
単に「食べない」ではなく、体が必要とする栄養素を過不足なく摂りながら腎臓への負担を軽くする方法を探すことが大切です。
専門家との連携
腎臓病の管理には医師や管理栄養士との連携をおすすめします。血液検査の結果や病期の進み具合を踏まえて、個人の病状に応じたアドバイスを得ると、無理なく継続できる食事管理を実践しやすくなります。
食事管理における栄養素の優先度
| 栄養素 | 優先度が高い理由 |
|---|---|
| たんぱく質 | 腎臓病たんぱく質目安を超えると老廃物処理が増え、腎臓に負担がかかる |
| リン | 腎臓病リン摂取量が多いと血中リン濃度が上昇し、骨や血管に影響を及ぼしやすい |
| カリウム | 高カリウム血症のリスクが高まると不整脈などを引き起こす可能性がある |
| ナトリウム(塩分) | 血圧上昇やむくみが強まり、心臓や腎臓への負担が増える |
腎臓病とたんぱく質の関係
たんぱく質は筋肉や臓器の材料になる大切な栄養素です。一方で、その代謝により生まれる老廃物を排出する作業が腎臓には負担になります。腎機能が低下すると代謝産物をうまく排出できなくなり、体内に毒素がたまりやすくなります。
なぜたんぱく質の調整が必要か
腎臓病の方が必要とするたんぱく質量は、病期や体格によって異なります。腎臓病たんぱく質目安を無視した大量摂取は、体内に余分な窒素化合物がたまる原因になります。
逆に過度に制限すると栄養不良を招き、筋力低下や免疫力低下につながる可能性があります。
タンパク質制限の一般的な考え方
多くの場合、腎臓の働きが低下しているほどたんぱく質の制限が厳しくなる傾向があります。ただし個人差が大きいので、医師から示された数値や管理栄養士の助言を参考に調整すると安心です。
自宅ではたんぱく質の食品成分表示や調理方法に気を配ることが必要です。
高たんぱく食品と上手に付き合う方法
高たんぱく食品である肉や魚、乳製品、大豆製品などを完全に避けるのではなく、量や頻度、調理法を工夫します。赤身肉やささみ、卵などは良質なたんぱく質源ですが、腎臓の状態によっては摂取量をコントロールする必要があります。
透析導入後のたんぱく質管理
透析を行う段階に入ると、体内の老廃物を定期的に除去しやすくなります。そのため、ある程度たんぱく質摂取量の制限が緩和されるケースもあります。しかし透析患者にとっても過剰摂取は禁物です。
自己判断ではなく、定期的な血液検査の結果を見ながら専門家と相談して調整します。
高たんぱく食品の栄養量比較
| 食品 | 1食あたりの推定量 | たんぱく質量(g) | カロリー(kcal) | 注意点 |
|---|---|---|---|---|
| 鶏むね肉(皮なし) | 100g | 約22 | 約110 | 脂質が少なく扱いやすい |
| 豚ヒレ肉 | 100g | 約23 | 約115 | 赤身中心で比較的低脂質 |
| 木綿豆腐 | 100g | 約7 | 約72 | 大豆由来だがリンにも注意 |
| 卵(全卵) | 1個(約50g) | 約6 | 約76 | 黄身部分にリン含有量が多い |
たんぱく質管理の基本
たんぱく質をどの程度食事に取り入れるかは、腎機能の状態に合わせて細やかに計算する必要があります。食事を振り返る際には、主食・主菜・副菜のバランスを確認し、無理のない形でたんぱく質を管理します。
主菜選びのポイント
主菜となる肉、魚、卵、大豆製品にはたんぱく質が多く含まれます。調理時に油を使いすぎたり、味つけを濃くしすぎたりするとカロリーや塩分過多に陥りやすくなるので注意が必要です。
焼きもの、煮もの、蒸しものなど調理方法を工夫すると、同じ食材でも負担を抑えやすくなります。
副菜の活用方法
野菜やきのこ類、海藻類を取り入れるとビタミンやミネラルを補うと同時に、食物繊維が不足しないように調整できます。副菜には比較的たんぱく質が少ない食材が多いので、量を多めにとって満足感を高める方法がよく用いられます。
主食の種類を変える
白米のほかにも麦ご飯や玄米、全粒粉パンなどを活用すると、食物繊維が多くなり血糖値や体重管理に役立つ可能性があります。腎機能がある程度低下している方はカリウム含有量にも注意が必要ですが、適切な範囲で主食を選択すると多彩な味を楽しみやすくなります。
レシピづくりの工夫
味を濃くしすぎると塩分過多になりやすいため、ハーブや香辛料、酸味などを活用して風味を高めると満足度を保てます。また、食材の重さを測る習慣をつけておくと、たんぱく質量の把握が容易になります。
主菜・副菜のアレンジ例
| メニュー例 | 主菜 (たんぱく質源) | 副菜 | 塩分(推定) |
|---|---|---|---|
| 鶏むね肉の蒸し焼き | 鶏むね肉100g(皮なし) | ブロッコリー・トマトサラダ | 約1.5g(醤油少量) |
| 白身魚の煮付け | 白身魚切り身70〜80g | 大根とわかめの煮物 | 約2.0g(だし活用) |
| 豚ヒレ肉のソテー | 豚ヒレ肉80g | もやしとにんじんのナムル | 約1.8g(塩控えめ) |
| 冷奴と野菜あんかけ | 木綿豆腐1/2丁 | 小松菜と椎茸の炒めもの | 約2.0g(だし中心) |
リン管理の基本
リンはカルシウムとともに骨を形成する上で大切なミネラルですが、腎機能が低下すると過剰になりやすい栄養素です。リンの過剰は骨代謝を乱し、血管や臓器の石灰化リスクを高めます。
腎臓病リン摂取量をコントロールすることで、合併症の予防につなげることが期待できます。
リンを多く含む食品
加工食品やインスタント食品、清涼飲料水などにはリン酸塩が多く含まれる場合があります。特にファストフードに含まれる添加物はリン含有量が高い傾向があるため、チェックが必要です。
乳製品や魚介類、大豆製品にもリンが多いので、腎機能低下がある方は総摂取量に注意します。
調理によるリンの減らし方
リンは水溶性が高いので、下茹でや煮こぼしによってある程度減らすことができます。たとえば、野菜やきのこ類を茹でてから調理するとリンやカリウムを減らしやすくなります。
ただし、すべてが抜けるわけではないため、調理法と食材選びの両面から対策します。
リン制限とカルシウムの関係
リンを制限する場合でも、カルシウムを極端に制限すると骨が弱まりやすくなります。医師や管理栄養士と相談しながら、必要なカルシウムを適度に取り入れて骨の健康を維持すると安心です。リン吸着薬の服用が指示されることもあります。
リン含有量の目安比較
| 食品 | 1食あたりの推定量 | リン含有量(mg) | 注意点 |
|---|---|---|---|
| プロセスチーズ | 20g | 約120 | 添加物としてリン酸塩が含まれる場合有 |
| ヨーグルト | 100g | 約120 | カルシウムも多くバランスが大切 |
| さんま(焼き) | 1尾(約100g) | 約180 | 骨をまるごと食べると更に増える |
| 大豆(乾燥) | 30g | 約150 | たんぱく質とリン両面に配慮が必要 |
腎臓病の段階別の栄養バランス
腎臓病は段階によって症状の現れ方が異なり、食事管理の度合いも変わります。早期発見の段階では生活習慣の改善を中心に進めますが、症状が進むと専門家によるより厳密な管理が必要です。
早期(ステージ1〜2)の食事管理
腎臓の機能が軽度に低下している段階では、健康的な食習慣や生活習慣を大きく乱さないように気をつけることが重要になります。
塩分の過剰を避け、動物性脂質を控えめにし、野菜や果物をしっかりとることで腎臓への負担を和らげることにつなげます。
中期(ステージ3〜4)の食事管理
この段階では腎機能がかなり低下しているため、たんぱく質やリンの厳密な管理が必要になりやすいです。具体的には主菜の分量を測ったり、味付けを薄めにするなど、意識的に摂取量をコントロールしながらバランスを保ちます。
血清クレアチニン値や推算GFR(eGFR)などの定期的な確認も不可欠です。
末期(ステージ5)や透析導入期の食事管理
透析治療の導入が近づくと老廃物や余分な水分を身体から除去する力が著しく落ちています。リンやカリウムが過剰になりやすいため、医師の指示を守りつつ適切な範囲で日々のメニューを決める必要があります。
透析が始まるとたんぱく質の制限が少し緩和されることもありますが、リンやカリウム、ナトリウムに関しては引き続き注意が必要です。
透析中の定期検査の意義
透析治療中は血液検査や尿量の変化などで体調を把握します。食事管理が適切にできているかを確認する上でも定期検査は大切な指標になります。
透析中の方はリンコントロールが課題になりやすいため、リン吸着薬との併用や食事内容の再確認が欠かせません。
腎臓病ステージ別のおおまかな栄養管理目安
| ステージ | たんぱく質量(例) | リン摂取量(例) | 食事管理の特徴 |
|---|---|---|---|
| ステージ1〜2 | 標準的な推奨量(体重1kgあたり約0.8g〜1.0g) | 過剰にしない程度 | 生活習慣の見直しで進行予防 |
| ステージ3〜4 | 体重1kgあたり約0.6g〜0.8g | 厳密にコントロール | たんぱく質・リンともに制限度合い増 |
| ステージ5(透析前) | 体重1kgあたり約0.6g前後 | より厳密な管理が必要 | 専門家の指導のもと継続管理 |
| 透析導入期 | 個人差が大きい | 減らす工夫を続行 | 透析の頻度や状態に合わせた調整 |
日常生活での具体的な食事例
実際に毎日食べるメニューを考えるときは、食材そのものの栄養成分だけでなく、調味料や付け合わせにも配慮します。少しずつ調整しながら習慣化すると長く続けやすくなります。
朝食の例
朝は一日の始まりを支える大切な時間帯です。過度に制限しすぎるとエネルギー不足で活動に支障が出やすくなります。腎機能に合わせてたんぱく質の量を測りながら、リンが多い食材は控えめにするとバランスを取りやすくなります。
朝のメニュー構成例
| 献立 | 食品例 | たんぱく質(g)の目安 | リン(mg)の目安 | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| ご飯(150g) + 焼き魚(40g) | 白米・鮭(小さめの切り身を半分) | 約9 | 約100 | 焼き魚の量を半分にしてリンを抑えやすい |
| 味噌汁(豆腐少量) | 具は野菜中心 | 約4 | 約60 | 味噌の塩分と豆腐の量を調整 |
| 野菜サラダ | レタス、きゅうり、トマト | 約1 | 約20 | ノンオイルドレッシングで塩分控えめ |
昼食の例
昼は外出先で食べる方も多く、外食だと塩分やリン、たんぱく質量がわかりにくいです。外食の頻度が高い場合はメニューの選び方に注意し、できるだけ野菜や海藻類を一緒に摂る工夫が大切になります。
夕食の例
夕食ではエネルギーをとりすぎると寝る前に血糖値や血圧のコントロールが乱れやすくなります。主菜は量をきちんと測り、副菜を増やすことで満足感を得やすくします。
リンの多い食材や加工品は控え、家庭で作る場合はできるだけ新鮮な食材を使うのがおすすめです。
間食・おやつの考え方
腎機能が低下している方は間食を避けたほうがよいと思われがちですが、全体のカロリーが不足している場合や血糖値の上下を緩やかにする目的で間食をうまく使う手もあります。
ただし、スナック菓子や炭酸飲料はリンが多い場合があるため要注意です。
間食候補の比較
| 食品 | 1食あたり量 | たんぱく質量(g) | リン量(mg) | 塩分(推定) | おすすめ度 |
|---|---|---|---|---|---|
| プレーンヨーグルト | 100g | 約3 | 約120 | 0.1 | カルシウムも摂取可 |
| フルーツ(りんごなど) | 1個の1/4程度 | 約0.2 | 約5 | 0 | カリウムに注意 |
| ビスケット(市販) | 2〜3枚 | 約1 | 約15 | 0.2〜0.3 | ノンフライ製品推奨 |
| せんべい(塩分控えめ) | 1〜2枚 | 0に近い | 約10 | 0.3〜0.5 | 塩分表示を確認 |
食事管理を続けるための心構え
腎臓病と診断されたとき、多くの方が最初は食事制限に戸惑います。しかし、無理に禁止ばかりを意識するとストレスが大きく、長続きしにくいです。自分に合ったペースでコントロールを続けることが結果的に病状の安定につながります。
メンタル面のサポート
自己流で頑張りすぎると、効果がわかりにくいときに挫折しやすくなります。医療スタッフや家族、同じ腎臓病と向き合う仲間との情報交換が助けになることがあります。共感を得る機会が増えると、食事管理の負担を軽く感じやすくなります。
記録の活用
食事や体重、体調の変化などを手帳やアプリに記録すると現状把握が容易になります。とくに、たんぱく質やリンの摂取量を数値化しやすいツールを利用すると、つい摂りすぎてしまう食材の傾向を早めに発見できます。
食事記録時にチェックしたい項目
- 食べた時間とメニュー
- 食材の分量(gなど数値)
- 塩分量、味付けの種類
- 体重や血圧の変化
- 体調の変化や主観的な感覚
食卓でのコミュニケーション
家族と同居している場合は、同じメニューを工夫してみんなで食べられるように配慮すると、孤立感を減らすことができます。調味料を別添えにする方法や、後から塩を追加しやすい形にするなど、家庭でのひと手間が続けやすさにつながります。
適度な運動と組み合わせる
筋力や基礎代謝を維持するために、散歩や軽いストレッチなど、日常生活に適度な運動を取り入れることも大切です。
ただし、運動の種類や強度は腎臓の機能や合併症の有無を考慮し、医師やリハビリスタッフと相談して決めることをおすすめします。
運動と食事の関連ポイント
| 項目 | 留意点 |
|---|---|
| ウォーキング | 有酸素運動で血流を促し、心肺機能や血圧コントロールに役立つ |
| ストレッチ | 関節や筋肉をほぐし、日常動作をスムーズにする |
| 筋力トレーニング(軽度) | 過度にならないよう注意し、たんぱく質摂取量も調整が必要 |
| 有酸素運動全般 | 血液循環を良くし、老廃物の代謝をサポート |
よくある質問
- たんぱく質を制限すると筋肉が落ちてしまいませんか?
-
適度なたんぱく質摂取は筋肉維持にとって大切です。制限が必要な場合でも必要量は摂る意識を持ち、無理のない範囲で良質なたんぱく質源を取り入れることをおすすめします。
極端な制限は避け、医師や管理栄養士と相談すると安心です。
- リンを減らすためには製品を一切やめるべきですか?
-
乳製品にはリンだけでなくカルシウムも多く含まれ、骨の健康には大切です。完全にやめる必要はなく、摂取量や種類を工夫すると良いでしょう。
たとえばヨーグルトの量を少なくしたり、カッテージチーズを少量使ったりする方法があります。
- 減塩食品やリン低減製品は活用すべきでしょうか?
-
減塩食品やリン低減製品は活用する価値がありますが、商品によっては味や価格など差があるので、無理なく継続できる範囲で試すのが良いでしょう。
人工甘味料や添加物が多いものもあるため、成分表示を確認したうえで選ぶことを提案します。
- 透析を始めたら好きなものを食べても問題ないですか?
-
透析によって老廃物や余分なリン・カリウムを除去しますが、過度な摂取は合併症のリスクを高めます。
透析導入前よりは多少自由度が上がる場合がありますが、定期的に血液検査の結果を確認しながら、透析前と同様にバランスを意識することが大切です。
以上
参考文献
NOORI, Nazanin, et al. Organic and inorganic dietary phosphorus and its management in chronic kidney disease. Iranian Journal of Kidney Diseases, 2010, 4.2: 89-100.
GONZÁLEZ-PARRA, Emilio, et al. Phosphorus and nutrition in chronic kidney disease. International journal of nephrology, 2012, 2012.1: 597605.
KALANTAR-ZADEH, Kamyar. Patient education for phosphorus management in chronic kidney disease. Patient preference and adherence, 2013, 379-390.
ELDER, Grahame J.; MALIK, Avya; LAMBERT, Kelly. Role of dietary phosphate restriction in chronic kidney disease. Nephrology, 2018, 23.12: 1107-1115.
KIM, Sun Moon; JUNG, Ji Yong. Nutritional management in patients with chronic kidney disease. The Korean journal of internal medicine, 2020, 35.6: 1279.
KALANTAR-ZADEH, Kamyar, et al. Understanding sources of dietary phosphorus in the treatment of patients with chronic kidney disease. Clinical Journal of the American Society of Nephrology, 2010, 5.3: 519-530.
SHINABERGER, Christian S., et al. Is controlling phosphorus by decreasing dietary protein intake beneficial or harmful in persons with chronic kidney disease?. The American journal of clinical nutrition, 2008, 88.6: 1511-1518.
MASCHIO, Giuseppe, et al. Effects of dietary protein and phosphorus restriction on the progression of early renal failure. Kidney international, 1982, 22.4: 371-376.
BARSOTTI, Giuliano; CUPISTI, Adamasco. The role of dietary phosphorus restriction in the conservative management of chronic renal disease. Journal of renal nutrition, 2005, 15.1: 189-192.
GUTIÉRREZ, Orlando M.; WOLF, Myles. Dietary phosphorus restriction in advanced chronic kidney disease: merits, challenges, and emerging strategies. In: Seminars in dialysis. Oxford, UK: Blackwell Publishing Ltd, 2010. p. 401-406.