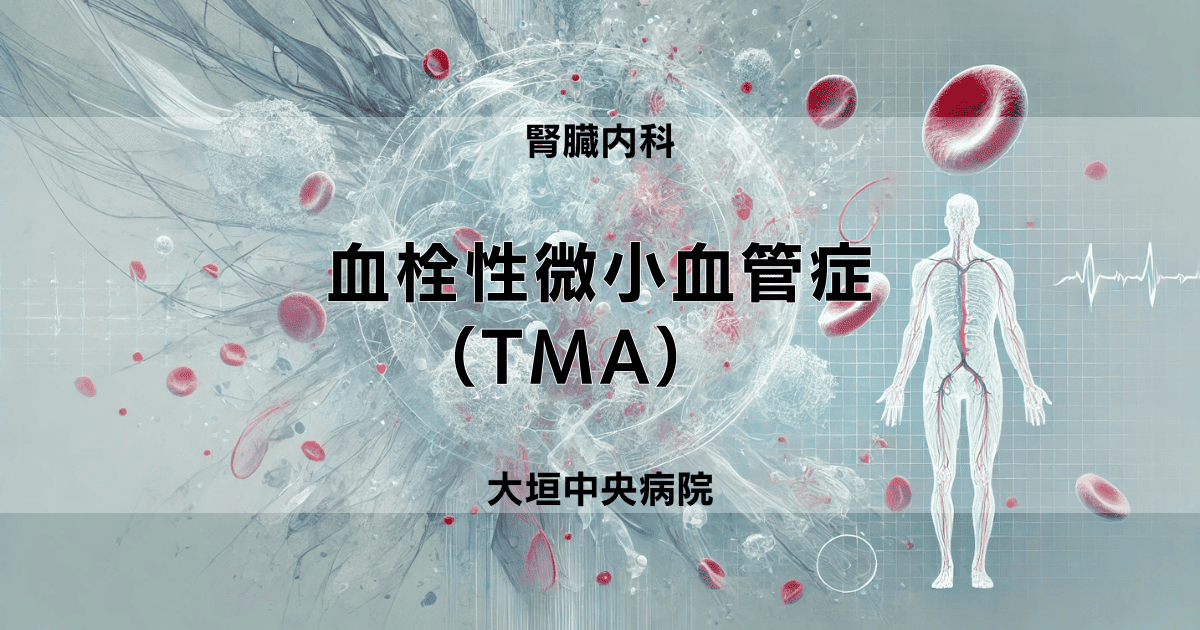血栓性微小血管症(TMA)とは、体内の小さな血管である微小血管が、何らかの要因によって血栓を形成しやすくなり、複数の臓器に障害をもたらす病気です。
微小血管に血栓が詰まると、血液が正常に循環しなくなり、臓器の機能が低下するおそれがあり、さらに、赤血球や血小板の異常が絡むことで貧血や出血傾向といった血液系トラブルが表面化し、重い合併症のリスクを高めます。
原因や病型は多彩で、一見すると別の疾患の症状と間違えられがちですが、検査や診断によって早期に対応すると、症状のコントロールや臓器障害の軽減が期待できます。
血栓性微小血管症(TMA)の病型
血栓性微小血管症(TMA)の病型には、発症の背景やメカニズムによって複数に分類され、血小板や血管内皮、凝固因子などの異常が重なり合い、微小血管に血栓ができやすくなるプロセスを幅広く含む概念でもあります。
代表的な病型と特徴
代表的な血栓性微小血管症には、大きく分けて血栓性血小板減少性紫斑病(TTP)、溶血性尿毒症症候群(HUS)、また抗リン脂質抗体症候群の一部病態や薬剤性などが挙げられます。
これらはいずれも血小板の低下や赤血球の破壊(溶血)、さまざまな臓器の血栓形成による機能障害を特徴としていますが、それぞれ発症要因や重症度、併発症状が異なります。
主な病型と特徴
| 病型 | 主な特徴 | 代表的な症状 |
|---|---|---|
| 血栓性血小板減少性紫斑病 (TTP) | ADAMTS13酵素活性の著明な低下 | 重度の血小板減少、神経症状、発熱など |
| 溶血性尿毒症症候群 (HUS) | 腎障害と溶血、血小板減少の三徴候 | 急性腎不全、貧血、浮腫、血圧上昇など |
| 薬剤性TMA | 特定の薬剤が血管内皮や血小板機能に影響 | 症状は多彩だが、投薬歴との関連が鍵 |
| 抗リン脂質抗体症候群に伴うTMA | 自己免疫による血管損傷と凝固異常 | 反復する血栓塞栓症、習慣性流産など |
原発性か二次性か
血栓性微小血管症は、原発性TMAと二次性TMAに分類され、原発性TMAでは、遺伝的な素因や特定の酵素活性不足など、疾患自体が直接的な原因です。
一方、二次性TMAでは、基礎疾患(自己免疫疾患や悪性腫瘍など)の合併や薬剤、感染などが誘因となって血栓ができやすくなる構造が形作られます。
病型を見極める意義
TMAの病型を正しく判別することは、治療効果を高めるうえで大切です。TTPでADAMTS13活性が著しく低下しているケースでは血漿交換療法が効果を発揮しやすいですが、HUSの場合は透析や溶血に対するサポートが優先されます。
また、二次性TMAの場合は基礎疾患の管理が要となり、抗リン脂質抗体症候群などの自己免疫疾患があれば免疫調整剤も検討対象です。
病型選別時に着目するポイント
| 評価項目 | 着目する意義 | 具体例 |
|---|---|---|
| 酵素活性 (ADAMTS13など) | TTPかどうかの判断材料になる | 活性が5%未満など極端に低い場合はTTPが疑わしい |
| 腎機能障害の程度 | HUSの可能性や透析導入の要否を判断 | クレアチニン上昇、尿量減少の具合など |
| 薬剤歴 | 薬剤誘発性TMAの可能性を探る | 抗がん剤や免疫抑制剤などの使用歴 |
| 自己抗体や免疫指標 | 自己免疫疾患によるTMAかどうかを推測 | 抗リン脂質抗体、抗核抗体の有無など |
病型と予後
どの病型であっても、早期に対応ができなければ臓器障害が進み、致命的になることがあるので、病型の判定に基づいてプラズマフォーレシスを行ったり、免疫調整剤や特定の生物学的製剤を使用したりすることが重要です。
病型ごとの比較
| 病型 | 治療の主軸 | 予後と注意点 |
|---|---|---|
| TTP | 血漿交換療法、免疫調整剤 | 効果的に治療すれば回復が期待しやすい |
| HUS | 透析や支持療法(輸血など) | 腎機能の回復が遅れると慢性腎不全に移行 |
| 薬剤性TMA | 原因薬剤の中止と対症療法 | 早期に薬剤中止で改善する例も |
| 二次性TMA | 基礎疾患の管理、血液浄化療法など | 基礎疾患のコントロールが重要 |
症状
血栓性微小血管症(TMA)は、血液細胞と臓器が複雑に絡むため、多様な症状を示す特徴があります。
初期の段階では軽い倦怠感やむくみ、食欲不振といった非特異的なサインが現れることがある一方で、急速に重症化して意識障害や重度の腎不全などを引き起こす可能性もあるので、早期の察知と対応が必要です。
血液検査所見に表れる徴候
TMAでは、赤血球が破壊される溶血性貧血と血小板減少という2つの特徴がしばしば同時にみられ、検査データ上でヘモグロビンが大きく下がる、LDHが上昇する、破砕赤血球が見られるなどの異常を確認しやすいです。
さらに血小板数の著しい低下は、出血しやすくなるリスクを高めるため、皮下出血や歯肉出血などの症状が起こる可能性があります。
血液検査でよくみられる異常
| 項目 | 異常の例 | 意味 |
|---|---|---|
| ヘモグロビン | 通常よりも著しく低い | 溶血性貧血による疲労感やめまいの原因 |
| LDH | 顕著に上昇 | 赤血球破壊や組織ダメージ |
| 血小板数 | 低下(例:5万/μL以下) | 出血傾向、紫斑や点状出血の原因 |
| 破砕赤血球 | 末梢血塗抹標本で多数認められる | RBC破壊が進行しているサイン |
腎障害に関連する症状
TMAの代表的症状として腎臓の機能障害があり、急速に腎不全へ進展するリスクがあり、利尿機能が低下すると、尿量が減る、全身がむくむ、高血圧が悪化するといった変化が起こりやすいです。
腎機能障害は血液検査でクレアチニンや尿素窒素などの数値を確認することが多く、上昇がみられる場合には緊急的な対応が必要なケースもあります。
- 尿量減少
- 浮腫(特に下肢や顔まわり)
- 血圧上昇
- 倦怠感・吐き気・食欲低下
神経症状
血栓が脳内の微小血管を塞ぐと、意識障害や麻痺、けいれんなどの神経症状が表面化する場合があり、特にTTPでは精神的混乱や幻覚、錯乱状態を示すことも報告されており、重症度が上がると重度の脳症へと移行していくおそれがあります。
こうした急性の神経症状が現れると、救急対応が必要になるため、周囲の人がいち早く異変に気づいて医療機関へ連絡できる体制を整えることが大切です。
神経症状
| 症状 | 原因・背景 | 対応の重要性 |
|---|---|---|
| 意識混濁 | 微小血管の血栓による脳血流の低下 | 呼吸管理や輸液、血漿交換療法による救急対応 |
| けいれん | 神経細胞の活動異常 | 抗けいれん薬の投与や集中治療室での管理が必要 |
| 局所神経麻痺 | 脳内の血管障害が特定部位を巻き込む | 早期リハビリと血栓除去の治療が予後に影響 |
出血傾向
血小板が減少することで、皮下出血や粘膜出血、歯肉出血など出血傾向が現れやすくなり、点状の赤い斑点(点状出血)が四肢や体幹に多く見られる、鼻血が止まりにくいなどの症状に注意が必要です。
病院での処置や、場合によっては血小板輸血を含む補助的なケアを検討することになりますが、あくまで対症療法で、根本的には血栓の形成を抑える治療との組み合わせが重要になります。
出血傾向が疑われる症状
| 症状 | 観察ポイント | 受診の目安 |
|---|---|---|
| 皮下出血 | 体表面の小さな斑点や大きめの青あざ | いつもよりあざが増加、日常動作で簡単に打撲跡ができる場合 |
| 歯肉出血 | ブラッシング時に大量出血 | 口の中の持続的な出血や痛みを伴う場合 |
| 鼻血 | 10分以上続く出血 | 自宅で止血が難しくなった場合 |
血栓性微小血管症(TMA)の原因
血栓性微小血管症(TMA)は、一つの原因だけではなく多因子的な要素が組み合わさって発症することが多いです。
遺伝的な素因や免疫反応、感染症、特定の薬剤、自己抗体など、さまざまな要因が血管内の凝固系や血小板の機能を乱し、微小血管での血栓形成を促進します。
免疫機構の乱れ
免疫が過剰に反応して血管を障害すると、炎症や血小板活性化が誘導されやすくなり、血栓を形成するリスクが高まります。
自己免疫疾患の中には抗リン脂質抗体症候群のように、抗体が血管内皮や凝固因子に作用して血液を固まりやすくするタイプもあり、TMAを起こす要因です。
特に膠原病やループスなどに合併するTMAは二次性TMAとして管理が必要で、基礎疾患への治療も並行して行わないと再発のリスクが残ります。
自己免疫背景
| 疾患名 | TMAとの関連 | 症状の特徴 |
|---|---|---|
| 抗リン脂質抗体症候群 | 血管内皮障害、凝固亢進 | 反復性流産、動脈血栓、静脈血栓 |
| 全身性エリテマトーデス (SLE) | 免疫複合体による血管炎 | 関節痛、腎障害、皮膚症状、貧血など |
| 強皮症 | 血管内膜の肥厚と血管攣縮 | 指先の潰瘍、肺高血圧、腎危象など |
感染症や毒素
特定の感染症は血小板や凝固因子を活性化する毒素を産生することがあり、HUSに代表されるような腎障害を合併するTMAを引き起こす可能性があります。
代表例としては腸管出血性大腸菌(O157など)のベロ毒素が挙げられ、重い下痢や腹痛のあとに腎機能障害、溶血などを発症するパターンがあります。
小児や高齢者は抵抗力が弱いため症状が重くなりやすく、対応が遅れると急性腎不全や多臓器不全に進行しやすいので注意が必要です。
薬剤性
抗がん剤や免疫抑制剤、一部の抗生物質、降圧薬などが原因でTMAを発症する薬剤性TMAのケースもあり、これらの薬剤が血管内皮細胞にダメージを与えたり、血小板の凝集を助長することで、微小血管に血栓を生じさせると考えられています。
長期投与や高用量投与を受けている患者さんは、定期的な血液検査や腎機能のチェックを行い、早期にTMAの兆候を拾うことが大切です。
注意が必要な薬剤
| 薬剤分類 | 主な適応疾患 | TMA発症リスクに関する背景 |
|---|---|---|
| 抗がん剤 | 白血病、リンパ腫など | 骨髄抑制や血管内皮傷害による血栓形成促進 |
| 免疫抑制剤 | 臓器移植、膠原病など | 免疫調整とともに血管内皮への影響が懸念される |
| 抗血小板薬 | 虚血性心疾患など | 血小板機能異常を起こし逆に微小血栓を形成する場合がある |
| 一部降圧薬 | 高血圧 | 腎血管や血管内皮にかかるストレスが増幅する可能性 |
遺伝的素因
TMAには、補体制御因子の異常など、先天的な遺伝子変異が関与する病型も認められ、こうした先天的TMAは、軽度なトリガーでも急速に病状が進行するリスクがあり、発症が幼少期や若年期に集中するケースも見受けられます。
家族歴をしっかり調べることで、同様の病態を抱える近親者がいないか確認し、早期発見につなげることが期待されます。
遺伝的要因のチェックポイント
| ポイント | 意義 | 具体的例 |
|---|---|---|
| 家族内発症の有無 | 血縁者に似た症状や病歴があるかどうかを確認 | 近親者にTTPやHUSが多い |
| 補体制御タンパク | 異常があると補体活性化が持続し微小血管に障害 | 補体因子Hの機能低下など |
検査・チェック方法
TMAを疑う兆候があれば、複数の検査を組み合わせて総合的に評価することが大切で、症状が進むと多臓器にわたる障害を招きやすいため、スピーディな検査と診断が治療効果を左右します。
血液検査
まず実施されるのは、赤血球や血小板の数値、溶血の程度を調べる血液検査です。
特にLDHの上昇や破砕赤血球の有無、ビリルビンの増加などは溶血が進んでいるサインとなり、血小板数の劇的な低下がみられる場合にはTMAの可能性を強く考えるきっかけになります。
血中のハプトグロビンが低値になるのも溶血を反映した異常所見として注目されます。
血液検査で見る主な項目
| 検査項目 | 意義 | 異常値が示す可能性 |
|---|---|---|
| 血小板数 | 出血傾向や凝固異常の有無 | 5万/μL以下だと重度の減少と判断される |
| LDH | 細胞破壊の指標 | 倍率に応じて溶血の進行度や組織障害を推測 |
| 破砕赤血球 | RBCが血管内で破砕しているかを確認 | TMAの診断に直結しやすい |
| ハプトグロビン | 赤血球破壊の指標(消費されると低下) | 溶血が活発なほど値が下がる |
腎機能検査
腎臓への影響を把握するためにクレアチニンや尿素窒素(BUN)、電解質などを測定し、GFR(糸球体ろ過量)を推定して総合的に腎機能を評価します。
尿検査ではタンパクや潜血の有無、尿沈渣で赤血球円柱が認められるかどうかなどを確認し、腎障害の進行度合いを推測します。腎エコーやCTなどの画像検査が行われるケースもあり、腎臓の形態的変化や萎縮の有無を確認することが可能です。
腎機能異常に関連する検査項目
| 項目 | 意味 | 異常が示唆する病態 |
|---|---|---|
| 血清クレアチニン | 腎機能低下があると上昇 | 急性腎不全や慢性腎障害 |
| BUN (尿素窒素) | タンパク質代謝産物で、腎での排泄がされる | 腎障害や脱水があると値が上昇 |
| 尿タンパク | 尿細管や糸球体の障害で漏出が増加 | たんぱく尿が持続すると腎障害進行の指標 |
| 尿沈渣 | 血尿、蛋白円柱、血球円柱などの有無を確認 | 顕著な血尿・円柱は糸球体障害を示唆 |
酵素活性と補体系評価
TTPを疑う場合はADAMTS13と呼ばれる酵素の活性測定が治療方針の決定に直結し、ADAMTS13は血中の超大型フォン・ウィルブランド因子を切断し、血小板の過剰凝集を防ぐ役割を担う酵素です。
活性が著しく低下している場合、血小板が塊を作りやすくなり、微小血管を塞ぐ危険が高まります。
また補体異常が疑われるケースでは、補体因子(C3やC4)や補体制御因子(因子Hなど)に関する遺伝子検査を行い、先天性または二次性の異常がないかを調べます。
画像検査・生検
神経症状が強い場合には頭部MRIやCTなどの画像検査で脳の微小出血や梗塞の有無をチェックし、重度の腎障害がある場合には腎生検で血管レベルの病理学的変化を確認することがあります。
ただし、腎生検は出血リスクを伴うため、血小板減少が著しい状況ではリスクとベネフィットを慎重に評価することが必要です。
検査の進め方におけるポイント
| 検査方法 | メリット | 注意点 |
|---|---|---|
| 頭部MRI・CT | 神経症状の原因部位や出血の有無がわかる | 造影剤使用時、腎機能が低下していると負担大 |
| 腎生検 | 病変部位を直接観察でき、確定診断に寄与 | 出血傾向が強いと実施が困難な場合がある |
| 胸腹部CT・エコー | 他の臓器障害(肝臓、脾臓、肺)を調べる | 妊娠中や造影剤アレルギーの方は手段を検討 |
血栓性微小血管症(TMA)の治療方法と治療薬について
血栓性微小血管症(TMA)の治療は、病型や重症度、合併症の有無などを踏まえて多角的に行われます。
緊急対応が必要な場合も多く、症状をコントロールするための基本的な支持療法とともに、血漿交換療法や薬物療法を組み合わせるケースが一般的です。
血漿交換療法
TTPなど、ADAMTS13活性が著しく低下しているタイプのTMAでは血漿交換療法が有力な選択肢とされています。
血漿交換療法では、患者さんの血漿を除去し、新鮮な血漿を補充することで欠損している酵素を補い、超大型フォン・ウィルブランド因子の過剰凝集を抑えるという仕組みです。
急性期には毎日のように連日交換する場合もあり、症状が安定してきたら頻度を下げていきます。
血漿交換療法の概要
| 項目 | 内容 | 期待される効果 |
|---|---|---|
| 実施場所 | 血液浄化装置のある病院 | 集中治療室や透析室で行う場合が多い |
| 交換頻度 | 初期は1日1~2回、症状軽快後は調整 | 血小板減少や神経症状の改善を狙う |
| 併用する治療 | 免疫調整剤やステロイドなど | 再発防止や抗体による酵素阻害を抑制する目的 |
免疫調整剤やステロイド
TMAの中でも自己免疫性の要因が強い場合、あるいはTTPにおけるADAMTS13阻害抗体の存在が疑われる場合に、ステロイドや免疫抑制剤を使った治療が行われます。
ステロイドは炎症反応や抗体産生を抑える作用を期待できるため、血漿交換療法と組み合わせることで治療効果を高めることがあります。
副作用として感染症リスクの上昇や血糖値のコントロール不良などがあるため、投与量や投与期間には慎重な判断が必要です。
主な免疫調整剤
| 薬剤 | 目的 | 注意点 |
|---|---|---|
| ステロイド | 炎症抑制・抗体産生抑制 | 血糖上昇、骨粗鬆症、易感染性など |
| シクロスポリン | 免疫抑制による自己抗体のコントロール | 腎毒性や血圧上昇、薬物相互作用に留意 |
| リツキシマブ | Bリンパ球を標的とし抗体産生を抑える | 打つタイミングや投与間隔を医師が管理 |
透析や支持療法
HUSなど腎機能障害が中心となるTMAでは透析療法が必須になる場合があります。
溶血による貧血が強いときは輸血を行う、血小板が著しく低下していれば血小板輸血を考慮するなど、症状の進行を抑えながら患者さんの全身状態を安定させる支持療法が重要です。
ただし、輸血を過度に行うと血管内ボリュームが増加して循環負荷が高まるリスクがあるため、輸液量や輸血量のバランス管理が欠かせません。
特定の生物学的製剤
近年、補体を制御する生物学的製剤が一部のTMAで用いられることがあり、補体が過剰に活性化している場合、それを抑える薬剤を投与すると血管内皮へのダメージが減少し、血小板や赤血球の破壊を制御する効果が期待できます。
こうした薬剤は保険適用の範囲が限られていることも多く、使用可否は病院ごとの設備や専門医の判断に左右されることがあるため、詳細は主治医とよく相談することが大切です。
使用が検討される生物学的製剤
| 製剤名 | 主な作用機序 | 投与方法 |
|---|---|---|
| エクリズマブ | 補体C5の活性を阻害し、溶血と血管内皮障害を抑える | 点滴静注で定期的に投与 |
| ラブリズマブ | エクリズマブ類似薬で長時間作用型 | 投与間隔がエクリズマブよりも長め |
血栓性微小血管症(TMA)の治療期間
血栓性微小血管症(TMA)の治療期間は、病型や重症度、患者さんの全身状態によって大きく異なります。
急性期を乗り越えたとしても、再発リスクを含めた経過観察が長期にわたって求められることがありますし、逆に早期に適切な治療を行うと数週間から数か月で状態が安定する例もあります。
急性期と慢性期
急性期には、血漿交換療法や透析、免疫調整剤などを集中的に行い、重症化を抑えることが優先され、TTPは脳症などの神経障害が合併しやすく、時間との勝負となるため、連日の治療を要するケースが少なくありません。
慢性期や回復期には治療頻度が減少し、定期的な血液検査や腎機能検査を行いながら再燃がないかを監視していきます。
治療段階による流れ
| 段階 | 主な目的 | 一般的な治療内容 |
|---|---|---|
| 急性期 | 多臓器障害や重症化の防止、死亡率の低減 | 血漿交換療法、透析、免疫調整剤、支持療法 |
| 亜急性期 | 症状の安定化と再発防止 | 治療頻度を下げながら効果を確認、投薬量の調整 |
| 慢性期 | 維持管理と生活の質の向上 | 定期検査や必要に応じたフォローアップ、合併症予防 |
再発リスク
TMAは再発の可能性も考慮しなければならない疾患で、特にTTPでは、ADAMTS13活性を抑制する自己抗体が残存していると、何かのきっかけで再度活性が低下し、血小板減少や溶血が再燃する場合があります。
そのため、一度回復しても、定期的にADAMTS13活性や血小板数をモニタリングすることが多く、HUSの場合も、感染や免疫低下が再発を誘発する可能性があるため、油断せずに体調管理を続けることが重要です。
再発に気をつけたいポイント
| 注意事項 | 具体的な理由 | 例 |
|---|---|---|
| 定期検査の継続 | 血小板減少やLDH上昇を早期に捉えて再燃を防ぐ | 月1回などの採血検査、腎機能チェック |
| 感染症対策 | 感染が補体や免疫の乱れを引き起こしやすい | マスク着用、手洗い、食中毒予防の徹底など |
| 過度のストレス回避 | 免疫バランスが崩れると抗体産生が促進される | 生活リズムを整え、疲労をためないように工夫 |
個人差の大きさ
病型や合併症の有無だけでなく、患者さんの年齢や基礎疾患、ライフスタイルなどによって、治療が必要となる期間は大きく変動します。
期間のイメージ
| パターン | 期間の目安 | 例 |
|---|---|---|
| 軽症TMA | 数週間から1~2か月程度で安定 | 血漿交換療法を短期間で終了し、経過観察へ移行 |
| 中等症~重症TMA | 1か月以上の入院治療、その後数か月のフォロー | 透析や長期免疫調整剤の投与が必要なケース |
| 慢性化・再発を繰り返す | 数年単位の長期モニタリング | 定期的に血液検査を行い、必要時に治療を再開する |
血栓性微小血管症(TMA)薬の副作用や治療のデメリットについて
血栓性微小血管症(TMA)の治療では、強力な免疫調整剤や血漿交換療法などを用いる機会が多く、一定の副作用リスクやデメリットを伴います。
血漿交換療法のリスク
血漿交換療法は、特にTTPの治療で大きな役割を果たしますが、循環血液量を操作したり外部から大量の血漿を補充したりするため、アレルギー反応や感染症リスク、血行動態の乱れなどが懸念されます。
また、治療に時間がかかる(1回の交換に数時間要する)ため、患者さんにとって身体的・精神的な負担が大きくなることが考えられます。
血漿交換療法で考えられるトラブル
| リスク | 例 | 対応策 |
|---|---|---|
| アレルギー反応 | 補充血漿中のタンパク質に対するじんましんやショック | 抗ヒスタミン薬、ステロイドの先行投与など |
| 感染症リスク | 血液製剤を介してウイルスが伝播する可能性 | 安全性試験を行った製剤を使用、厳重管理 |
| 体液量の急変 | 循環血液量減少による血圧低下、胸苦しさ | ゆるやかなペースで交換、適切な補液が大切 |
免疫調整剤やステロイドの副作用
ステロイドは炎症や免疫反応を強力に抑えますが、その反面として血糖コントロールの乱れ、骨密度の低下、易感染性、精神面での不安定など、幅広い副作用が出現する可能性があります。
シクロスポリンなどの免疫抑制剤を使用するときは、腎機能障害や高血圧、薬物相互作用などに警戒が必要で、定期的な血液検査や血圧測定でモニタリングすることが大切です。
ステロイドによる副作用
| 副作用 | メカニズム | 日常生活への影響 |
|---|---|---|
| 感染症リスク増 | 免疫反応が抑えられるため | 風邪などのウイルスや細菌感染に注意が必要 |
| 糖尿病の悪化 | 血糖値を上昇させる作用 | インスリン注射や食事制限が必要になる場合 |
| 精神症状 | 脳内ホルモンバランスの変化 | イライラ感や不安感、睡眠障害など |
透析の負担
HUSなどで腎不全が顕著な場合、週に数回の透析治療を行うケースがあり、透析は血液を体外に出して老廃物や余分な水分を取り除くため、1回につき数時間がかかり、通院やスケジュール管理が必要になります。
疲労感や血圧低下などの症状を訴える方もおり、社会生活との両立が負担になりやすい点がデメリットの一つです。
高コストの可能性
特定の生物学的製剤など、一部の薬は高額になるケースがあり、特にエクリズマブは投与を継続する場合、長期にわたる費用負担が増える懸念があります。
代表的な薬剤の価格目安
| 薬剤 | 1か月あたりの費用(保険3割負担の概算) | コメント |
|---|---|---|
| 血漿交換療法(1回) | 3万~5万円程度 | 交換回数が多いほど費用が累積する |
| ステロイド内服薬 | 数千円~1万円程度 | 用量や種類によって幅がある |
| エクリズマブ | 数万円~十数万円程度 | 投与間隔や体重により変動 |
血栓性微小血管症(TMA)の保険適用と治療費
以下に記載している治療費(医療費)は目安であり、実際の費用は症状や治療内容、保険適用否により大幅に上回ることがございます。当院では料金に関する以下説明の不備や相違について、一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。
保険診療の対象
一般的に、TMAの検査や治療は公的医療保険の適用範囲に含まれるため、血液検査や画像検査、薬物治療、血漿交換療法、透析なども3割負担で済むことが多いです。
| 治療法・検査 | 自己負担の目安(3割負担時) | コメント |
|---|---|---|
| 血漿交換療法(1回) | 3万~5万円前後 | 治療回数や使用する血漿製剤によって変動 |
| 透析(週3回) | 月あたり3万~5万円程度 | 腎不全の程度で回数や入院の要否が異なる |
| 免疫調整剤(ステロイドなど) | 月数千円~1万円程度 | 用量や投与期間次第で増減 |
| 生物学的製剤(エクリズマブなど) | 月数万円~十数万円程度 | 投与間隔・体重により変動が大きい |
外来通院と入院
TMAは重症化しやすい特徴があるため、最初は入院治療を選択することが多いです。入院期間が長いほど、ベッド代や食事代なども加わり、トータルの出費は増えます。
一方で、症状が安定すれば外来での投薬や透析(外来透析)に切り替えられるケースもあり、通院回数と内容によって費用は変化します。
以上
参考文献
Fujimura Y, Matsumoto M. Registry of 919 patients with thrombotic microangiopathies across Japan: database of Nara Medical University during 1998-2008. Internal Medicine. 2010;49(1):7-15.
Wada H, Matsumoto T, Suzuki K, Imai H, Katayama N, Iba T, Matsumoto M. Differences and similarities between disseminated intravascular coagulation and thrombotic microangiopathy. Thrombosis journal. 2018 Dec;16:1-7.
Ashida A, Matsumura H, Sawai T, Fujimaru R, Fujii Y, Shirasu A, Nakakura H, Iijima K. Clinical features in a series of 258 Japanese pediatric patients with thrombotic microangiopathy. Clinical and Experimental Nephrology. 2018 Aug;22:924-30.
Komatsu R, Mimura K, Matsuyama T, Kawanishi Y, Nakamura H, Tomimatsu T, Endo M, Kimura T. Severe hemolysis, elevated liver enzymes, and low platelet syndrome requiring differentiation of thrombotic microangiopathy: Four cases from a nationwide survey in Japan. Journal of Obstetrics and Gynaecology Research. 2024 Jul;50(7):1258-62.
Katsuno T, Ito Y, Kagami S, Kitamura H, Maruyama S, Shimizu A, Sugiyama H, Sato H, Yokoyama H, Kashihara N. A nationwide cross-sectional analysis of thrombotic microangiopathy in the Japan Renal Biopsy Registry (J-RBR). Clinical and Experimental Nephrology. 2020 Sep;24:789-97.
Hori T, Kaido T, Oike F, Ogura Y, Ogawa K, Yonekawa Y, Hata K, Kawaguchi Y, Ueda M, Mori A, Segawa H. Thrombotic microangiopathy-like disorder after living-donor liver transplantation: a single-center experience in Japan. World journal of gastroenterology: WJG. 2011 Apr 14;17(14):1848.
Nagaoka K, Kaneko K, Miyagawa E, Abe S, Kohno C, Tsurane K, Mito A, Ozawa N, Sago H, Arata N, Murashima A. Clinical features of women with thrombotic microangiopathy in pregnancy: A case series from a single Japanese tertiary perinatal care center. Journal of Obstetrics and Gynaecology Research. 2023 Dec;49(12):2804-10.
Takatsuki M, Eguchi S, Yamamoto M, Yamaue H, Takada Y, Japanese Society of Hepato‐Biliary‐Pancreatic Surgery. The outcomes of thrombotic microangiopathy after liver transplantation: A nationwide survey in Japan. Journal of Hepato‐Biliary‐Pancreatic Sciences. 2022 Feb;29(2):282-92.
Uruga H, Fujii T, Kurosaki A, Hanada S, Takaya H, Miyamoto A, Morokawa N, Homma S, Kishi K. Pulmonary tumor thrombotic microangiopathy: a clinical analysis of 30 autopsy cases. Internal Medicine. 2013;52(12):1317-23.
Fujimura Y, Matsumoto M, Yagi H. Thrombotic microangiopathy. Recent Advances in Thrombosis and Hemostasis 2008. 2008:625-39.