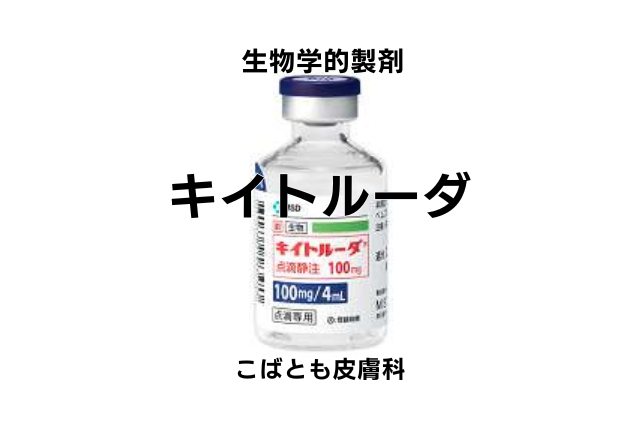ペムブロリズマブ(キイトルーダ)とは、免疫チェックポイントを標的にして皮膚がんやさまざまながん細胞を攻撃しやすくする薬です。
患者さん自身が持つ免疫の力を引き出す特徴があり、既存の化学療法とは異なるアプローチを取ります。
ここでは、のペムブロリズマブ(キイトルーダ)作用機序、投与方法、適応となる患者さん、治療期間、副作用などを詳しく解説します。
この記事の執筆者

小林 智子(こばやし ともこ)
日本皮膚科学会認定皮膚科専門医・医学博士
こばとも皮膚科院長
2010年に日本医科大学卒業後、名古屋大学医学部皮膚科入局。同大学大学院博士課程修了後、アメリカノースウェスタン大学にて、ポストマスターフェローとして臨床研究に従事。帰国後、同志社大学生命医科学部アンチエイジングリサーチセンターにて、糖化と肌について研究を行う。専門は一般皮膚科、アレルギー、抗加齢、美容皮膚科。雑誌を中心にメディアにも多数出演。著書に『皮膚科医が実践している 極上肌のつくり方』(彩図社)など。
こばとも皮膚科関連医療機関
ペムブロリズマブ(キイトルーダ)の有効成分と効果、作用機序
ペムブロリズマブは免疫チェックポイント阻害薬として分類され、免疫機能を活性化することでがん細胞を攻撃しやすくする働きを持ちます。
有効成分の概要
ペムブロリズマブはヒト化モノクローナル抗体で、PD-1(Programmed cell death-1)と結合する性質があり、PD-1は免疫細胞の表面にあり、がん細胞からの刺激を受けると免疫攻撃にブレーキがかかる仕組みを作り出します。
ペムブロリズマブを投与してPD-1をブロックすると、免疫細胞が本来の攻撃力を取り戻しやすくなるのです。
ペムブロリズマブの効果が期待できる主な皮膚がん
皮膚科の分野では、悪性黒色腫(メラノーマ)など進行が早いがんに対してペムブロリズマブを使用する機会があります。手術が難しい症例や再発が認められる患者さんで使うケースが多いです。
また、腫瘍の種類や状態によっては単独投与以外の治療法と組み合わせることも考えられます。
悪性黒色腫とペムブロリズマブの特徴的なポイント
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| がんの種類 | 悪性黒色腫(メラノーマ) |
| 使用時期の例 | 進行や再発があるとき |
| 投与形態 | 点滴静脈注射 |
| 期待される作用 | 免疫機能のブレーキ解除によるがん細胞攻撃の促進 |
作用機序の流れ
ペムブロリズマブはPD-1の機能をブロックし、がん細胞が免疫から逃れるのを阻止します。
がん細胞はPD-L1というタンパク質を出して免疫細胞にブレーキをかけますが、ペムブロリズマブがこれを解除することで、T細胞がより積極的にがんを攻撃できます。
従来の化学療法は細胞分裂を直接阻害するため正常細胞にもダメージを与えがちですが、ペムブロリズマブは免疫調節を通じて攻撃を促す点が大きな特徴です。
免疫活性化によるメリットと限界
免疫を活性化するメリットは、標的ががん細胞に限られる可能性が高まり、副作用の種類や現れ方が従来の化学療法とは異なる点です。
ただし、すべての患者さんに同様の効果が出るわけではなく、体質や腫瘍特性、病期などによって治療効果に大きく差が出る場合があります。
ペムブロリズマブの効果と限界
- 免疫に働きかけるため、効果が長く続く可能性がある
- 従来治療が効かなかった場合の新たな選択肢となるケースがある
- すべての患者さんに効果が現れるわけではない
- 免疫関連の副作用が起こるリスクがある
使用方法と注意点
ペムブロリズマブを実際に使うとき、投与スケジュールや日常生活での注意点をしっかり把握することが大切です。外来治療で行う場合もあれば、状態によっては入院下で投与する場合もあります。
投与スケジュールの一般的な流れ
ペムブロリズマブは基本的に点滴静脈注射で投与し、多くの場合、3週間ごとに1回、約30分程度かけて点滴する方法が選ばれます。
患者さんの体重や病態によって用量は変わる場合がありますが、近年は固定用量(200mgや400mgなど)を一定間隔で投与する方法が広く行われています。
投与スケジュールの目安
| 投与間隔 | 投与量の例 | 投与時間 |
|---|---|---|
| 3週間に1回 | 200mg | 約30分 |
| 6週間に1回 | 400mg | 約30分 |
| 病状による調整 | 個別に検討 | 主治医が判断 |
日常生活での注意点
免疫を活性化する薬なので、体調変化をこまめにチェックする必要があり、発熱や下痢、呼吸苦など普段と違う症状が出たら早めに主治医へ連絡してください。
3週間ごとの通院日にあわせて血液検査や画像検査を行い、治療効果や副作用の有無を確認します。
日常生活で注意したい点
- 水分と栄養をしっかり摂取する
- 疲労を溜めすぎない
- 体調の異変(発熱、下痢、倦怠感など)はすぐ報告する
- 他の薬剤やサプリメントとの併用は主治医に相談する
副作用の早期発見と対策
ペムブロリズマブでは免疫関連の副作用(皮膚炎、腸炎、肺炎、肝障害、内分泌異常など)が起こりやすく、気づかずに放置すると重症化し、治療継続が難しくなる可能性があります。
軽症のうちにステロイドなどの免疫抑制剤を適切に使うと症状を抑えやすいです。
代表的な副作用と初期症状
| 副作用名 | 初期症状例 | 対策 |
|---|---|---|
| 皮膚障害 | 発疹、かゆみ、赤み | 外用剤や抗ヒスタミン薬 |
| 腸炎 | 下痢、腹痛、血便 | 免疫抑制剤、輸液治療 |
| 肺炎 | 咳、息切れ、発熱 | ステロイド治療、酸素投与 |
| 肝障害 | 倦怠感、黄疸、尿の濃化 | ステロイド、経過観察 |
| 内分泌異常 | 倦怠感、体重減少、血圧低下 | ホルモン補充療法 |
ペムブロリズマブ(キイトルーダ)の適応対象となる患者さん
ペムブロリズマブは悪性黒色腫をはじめ、肺がんや頭頸部がんなど幅広いがん種で適応が拡大してきました。皮膚科領域でも、進行性や再発性の悪性黒色腫などに積極的に使うことがあります。
悪性黒色腫(メラノーマ)への適応
皮膚科では悪性黒色腫が代表的な対象で、以下のケースで投与を検討します。
- 手術で完全切除が難しい
- 転移や再発のリスクが高い
- 他の化学療法の効果が十分でない
悪性黒色腫は転移が早い特徴があり、進行が進むと予後が厳しくなりやすく、ペムブロリズマブで免疫を活性化させる治療が選択肢に入ると、治療の幅が広がります。
悪性黒色腫の特徴と治療戦略
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 主な発生部位 | 皮膚、爪、粘膜など |
| 進行スピード | 早いことが多い |
| 主な治療選択肢 | 手術、放射線治療、化学療法、免疫療法など |
| ペムブロリズマブの位置づけ | 免疫チェックポイント阻害薬として検討可能 |
適応を判断する検査
ペムブロリズマブの投与が適切かどうかを判断するため、PD-L1発現率の測定などの検査を行う場合があり、腫瘍内でPD-L1が高発現しているほど、免疫チェックポイント阻害薬が効果を示しやすいです。
ただしPD-L1検査結果が必須になるかどうかはがん種によって異なるため、一律ではありません。
投与前の全身状態の把握
免疫療法には体力や臓器機能にある程度の余裕が大切で、血液検査や肝機能、腎機能の評価も重要です。高齢や合併症がある方でも状況によっては投与できる可能性がありますが、主治医が総合的にリスクとメリットを評価します。
ペムブロリズマブ(キイトルーダ)の治療期間
ペムブロリズマブの治療をどのくらいの期間続けるのかは、患者さんごとに効果の現れ方や副作用の度合いが異なるので、一律の答えはありせん。
一般的な治療期間の目安
ペムブロリズマブの治療は、原則として効果があるうちは継続する方針を取る場合が多いです。
2~3か月ごとに画像検査を実施し、がんの縮小や安定を確認し、効果が認められれば治療を継続し、効果が不十分または副作用が強い場合に投与中止や別の治療に切り替える判断します。
| 治療ステージ | 投与間隔 | 評価タイミング |
|---|---|---|
| 初期~中期 | 3週間ごと | 2~3か月ごとに画像検査 |
| 病勢安定期 | 同様か延長検討 | 画像検査で状態確認 |
| 治療継続上限 | 2年程度を目安に | 副作用と効果のバランス |
悪性黒色腫における治療継続
悪性黒色腫の治療では、患者さんごとに治療効果のばらつきがあり、半年~1年継続して効果が持続する例もあれば、投与開始から数か月で効果が見られにくい例もあります。
主治医は画像検査や血液検査を総合的に判断して投与を継続するか決めます。
治療期間に影響を与える要因
- がんのステージ
- 副作用の強さと種類
- 患者さんの免疫状態
- 他の治療法との併用状況
- 画像検査と血液検査の結果
投与中断の判断
重度の副作用が出たり、明らかな進行が認められた場合は投与を中断しますが、投与を中断してもしばらく効果が続く場合もあり、免疫チェックポイント阻害薬特有の「治療終了後も一定期間効果が持続する」事例が報告されています。
治療終了後も定期的に検査を行い、再発リスクを早期に察知できるようにすることが重要です。
通院ペースと生活リズム
3週間ごとに通院する場合が多いですが、遠方の場合や家庭の事情によって通院が難しい場合は6週間ごとの投与を検討する例もあります。日常生活との調整も含めて主治医と相談しながら治療計画を立てましょう。
ペムブロリズマブ(キイトルーダ)の副作用やデメリット
ペムブロリズマブは免疫を活性化するメリットがある一方で、従来の化学療法とは異なる副作用が現れる可能性があり、特に免疫関連の副作用に注意が必要で、見逃すと重症化するリスクが高まる場合があります。
免疫関連副作用(irAE)の特徴
免疫チェックポイント阻害薬では、自己免疫反応が高まりすぎて正常な組織を攻撃する可能性があり、これを「免疫関連有害事象(irAE)」と呼び、一般的に以下の症状が代表例です。
- 皮膚症状(発疹、かゆみなど)
- 腸炎(下痢、血便、腹痛)
- 肺炎(息苦しさ、咳、発熱)
- 肝障害(黄疸、倦怠感)
- 内分泌障害(甲状腺機能異常、副腎不全など)
軽度なら外用薬や内服薬で対応できますが、進行すると入院や強力な免疫抑制治療が必要になる場合があります。
irAEの発現時期と発症率
| 副作用 | 発現時期 | 発症率(目安) |
|---|---|---|
| 皮膚症状 | 投与開始後数週間以内 | 高め(20~30%) |
| 腸炎 | 投与開始後2~3か月 | 中程度(10~15%) |
| 肺炎 | 投与開始後3~6か月 | 低め(5~10%) |
| 肝障害 | 投与開始後数か月 | 中程度(10%前後) |
| 内分泌障害 | 個人差が大きい | 中程度(10%前後) |
副作用への対処法
小さな症状でも早期に発見し、対処を行うと重症化を防ぎやすいです。
皮膚症状の場合は塗り薬を使い、早めに主治医へ報告してステロイド外用剤を追加し、下痢が続く場合は免疫抑制剤を使用して炎症を抑えるなど、症状の程度に応じて治療を行います。
効果がなかった場合
ペムブロリズマブを投与しても、すべての患者さんが良好な反応を示すわけではなく、がんの種類や個人差によって効果が得られない場合があり、その際には別の治療法に切り替える判断が必要です。
効果判定のタイミングと方法
治療を開始してから2~3か月ごとに画像検査や血液検査を行い、腫瘍の縮小や変化を確認し、進行度が変わらない、もしくは増悪が認められる場合はペムブロリズマブの効果が不十分と判断します。
偽増悪という一時的な腫瘍増大の現象もあるため、医師は複数回の検査を総合的に判断することが大切です。
偽増悪と真の増悪を判別する際のポイント
| 判別項目 | 偽増悪 | 真の増悪 |
|---|---|---|
| 時期 | 治療開始後早期に多い | ある程度継続後も進行 |
| 画像所見 | 一時的な腫瘍径の増大 | 持続的な腫瘍増大 |
| 症状の変化 | 症状がやや変化する場合あり | 症状が明らかに悪化 |
| 追加検査 | 短期間の再検査で再評価 | 追加検査でも増悪が持続 |
ほかの免疫チェックポイント阻害薬への切り替え
ペムブロリズマブと同じ免疫チェックポイント阻害薬でも、PD-L1やCTLA-4を標的とする薬剤など複数の選択肢があり、ニボルマブやイピリムマブなどが該当します。
腫瘍の特性や患者さんの副作用歴を踏まえて、別の免疫療法を試す場合もあります。
化学療法や放射線治療との併用や切り替え
免疫療法と化学療法を併用することで相乗効果を得る治療戦略も提案され、効果が認められない場合は、放射線治療や分子標的薬など別の治療へ切り替えることも検討します。
主治医ががんの性質や患者さんの状態を考慮して治療方針を柔軟に組み立てることが重要です。
効果がなかった場合の選択肢
- 別の免疫チェックポイント阻害薬へ変更
- 化学療法や分子標的薬との併用
- 放射線治療で局所的に腫瘍をコントロール
- 臨床試験(治験)への参加
他の治療薬との併用禁忌
免疫チェックポイント阻害薬であるペムブロリズマブを使う際には、他の治療薬との相互作用に注意が必要です。免疫を抑制する薬や特定の分子標的薬など、併用によって効果が減弱したり副作用が増強したりする場合があります。
免疫抑制剤との関係
ペムブロリズマブは免疫を活性化するので、大量のステロイドや免疫抑制剤を併用すると効果が下がりやすいです。
ただし、重度の副作用が出現した場合はステロイドで炎症をコントロールする必要があるため、主治医が量や期間を慎重に調整します。
免疫抑制剤を使用する際のポイント
| 免疫抑制剤例 | 注意点 | ペムブロリズマブとの関係 |
|---|---|---|
| ステロイド | 免疫抑制効果が高い | 高用量・長期使用で効果減 |
| シクロスポリン | T細胞抑制による免疫力低下 | 併用時は効果モニタリング |
| タクロリムス | T細胞活性を抑制 | 血中濃度の調整が重要 |
特定の分子標的薬との併用
一部の分子標的薬と免疫チェックポイント阻害薬を併用すると、副作用が相互に増強するリスクがあり、肝障害や腸炎が重複すると治療継続が難しくなるため、主治医が厳重に観察します。
近年は併用療法の有効性を検証する臨床試験が増えていますが、安全性の確立した組み合わせかどうかを見極めることが大切です。
ワクチン接種とペムブロリズマブ
生ワクチンの接種は免疫系への負荷が大きいため、ペムブロリズマブ投与中や直前直後の接種は注意が必要です。
インフルエンザワクチンなど不活化ワクチンは比較的安全とされていますが、主治医の指示に従って時期を検討してください。
接種を検討するときのポイント
- 生ワクチン(麻疹、風疹、ムンプスなど)は慎重に判断
- 不活化ワクチン(インフルエンザ、肺炎球菌など)は医師と相談の上で実施
- 投与タイミングとの兼ね合いを調整
自己判断で薬を増減しない
ペムブロリズマブ以外に常用している薬やサプリメントがある場合、必ず医療者に報告してください。自己判断で服用を中断したり、勝手に薬を追加すると予想外の副作用を起こすおそれがあります。
ペムブロリズマブ(キイトルーダ)の保険適用と薬価について
以下に記載している治療費(医療費)は目安であり、実際の費用は症状や治療内容、保険適用否により大幅に上回ることがございます。当院では料金に関する以下説明の不備や相違について、一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。
保険適用されるがん種
ペムブロリズマブは悪性黒色腫をはじめ、非小細胞肺がん、頭頸部がん、胃がんの一部、ホジキンリンパ腫など、複数のがん種で保険適用で、皮膚科領域では悪性黒色腫が代表的な適応です。
| 疾患名 | 保険適用状況 |
|---|---|
| 悪性黒色腫 | 適用あり |
| 非小細胞肺がん | 適用あり |
| 頭頸部がん | 適用あり |
| ホジキンリンパ腫 | 適用あり |
| 胃がんの一部 | 適用あり |
ペムブロリズマブの薬価
ペムブロリズマブは高額な薬剤で、1瓶あたりの価格が数万円から数十万円に達し、ペムブロリズマブ点滴静注100mgが1瓶あたり約58,000円前後とされ、患者さんによっては複数瓶を使うこともあります。
- 100mg1瓶を3割負担で使用した場合、約58,000円×0.3=約17,400円の自己負担
- 200mgを投与するなら2瓶相当を使用し、自己負担は約34,800円程度
- 3週間ごとの投与を複数回行うため、月単位の負担はさらに増える
高額療養費制度の活用
医療費が高額になった場合、高額療養費制度を利用すると一定額以上の負担を軽減でき、また、限度額適用認定証を事前に取得すると、医療機関の窓口で支払う段階から負担が軽減されます。
以上
参考文献
Yamazaki N, Shimizu A, Ozaki M, Hamada M, Takeuchi N, Ito Y, Maekawa S. Real‐world safety and effectiveness of pembrolizumab in Japanese patients with radically unresectable melanoma: an all‐case postmarketing surveillance in Japan. The Journal of Dermatology. 2022 Nov;49(11):1096-105.
Kijima T, Fukushima H, Kusuhara S, Tanaka H, Yoshida S, Yokoyama M, Ishioka J, Matsuoka Y, Numao N, Sakai Y, Saito K. Association between the occurrence and spectrum of immune-related adverse events and efficacy of pembrolizumab in Asian patients with advanced urothelial cancer: multicenter retrospective analyses and systematic literature review. Clinical Genitourinary Cancer. 2021 Jun 1;19(3):208-16.
Fujisawa Y, Funakoshi T, Nakamura Y, Ishii M, Asai J, Shimauchi T, Fujii K, Fujimoto M, Katoh N, Ihn H. Nation-wide survey of advanced non-melanoma skin cancers treated at dermatology departments in Japan. Journal of dermatological science. 2018 Dec 1;92(3):230-6.
Yusuke MU, Kambayashi Y, Hiroshi KA, Fukushima S, Takamichi IT, Maekawa T, Fujisawa Y, Yoshino K, Hiroshi UC, Matsushita S, Yamamoto Y. Adjuvant anti-PD-1 antibody therapy for advanced melanoma: a multicentre study of 78 Japanese cases. Acta dermato-venereologica. 2022 Aug 11;102:678.
Kwok G, Yau TC, Chiu JW, Tse E, Kwong YL. Pembrolizumab (keytruda). Human vaccines & immunotherapeutics. 2016 Nov 1;12(11):2777-89.
Hauschild A, Eichstaedt J, Möbus L, Kähler K, Weichenthal M, Schwarz T, Weidinger S. Regression of melanoma metastases and multiple non-melanoma skin cancers in xeroderma pigmentosum by the PD1-antibody pembrolizumab. European Journal of Cancer. 2017 May 1;77:84-7.
Khoja L, Butler MO, Kang SP, Ebbinghaus S, Joshua AM. Pembrolizumab. Journal for immunotherapy of cancer. 2015 Dec;3:1-3.
Ribas A, Hamid O, Daud A, Hodi FS, Wolchok JD, Kefford R, Joshua AM, Patnaik A, Hwu WJ, Weber JS, Gangadhar TC. Association of pembrolizumab with tumor response and survival among patients with advanced melanoma. Jama. 2016 Apr 19;315(15):1600-9.
Robert C, Schachter J, Long GV, Arance A, Grob JJ, Mortier L, Daud A, Carlino MS, McNeil C, Lotem M, Larkin J. Pembrolizumab versus ipilimumab in advanced melanoma. New England Journal of Medicine. 2015 Jun 25;372(26):2521-32.
Maubec E, Boubaya M, Petrow P, Beylot-Barry M, Basset-Seguin N, Deschamps L, Grob JJ, Dréno B, Scheer-Senyarich I, Bloch-Queyrat C, Leccia MT. Phase II study of pembrolizumab as first-line, single-drug therapy for patients with unresectable cutaneous squamous cell carcinomas. Journal of Clinical Oncology. 2020 Sep 10;38(26):3051-61.