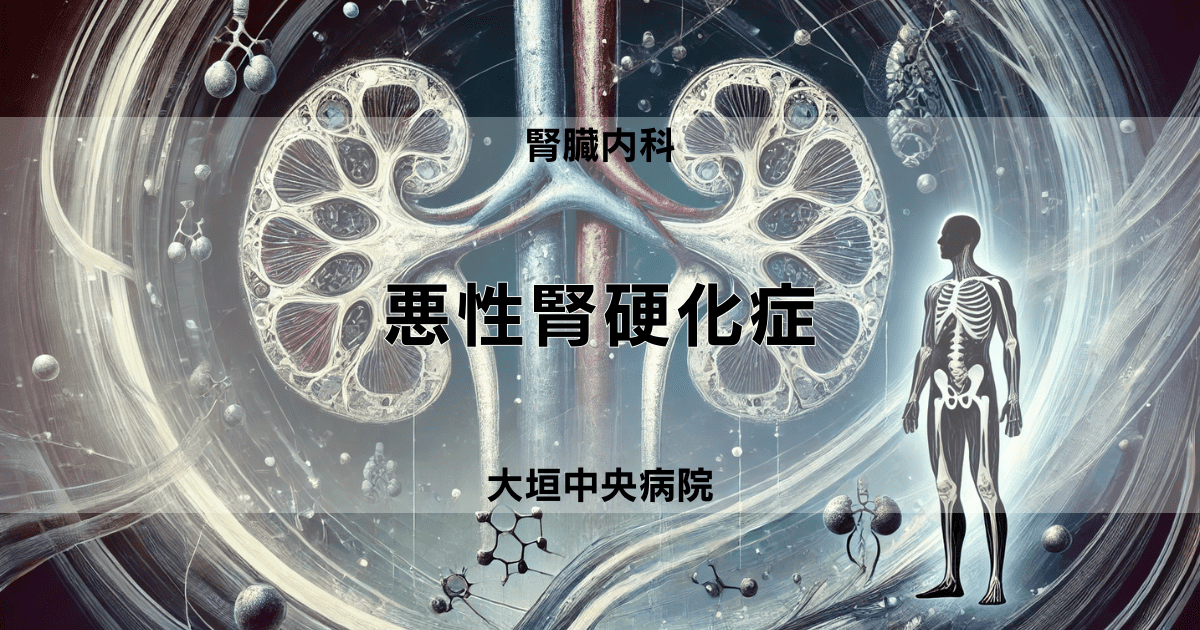悪性腎硬化症とは、非常に高い血圧の影響が腎臓の血管にも及び、急速に腎機能が障害を受ける重篤な状態です。
患者さんの中には、高血圧の治療を中断したり、血圧のコントロールを十分に行わなかったりしているうちに、突然急激な腎不全症状に陥ることもあります。
腎臓の血管が著しく狭くなることで、組織レベルでの酸素や栄養の供給が途絶えがちになり、時に全身へ深刻な影響を及ぼす懸念があるため、早期発見とケアが重要です。
治療を先送りにしていると取り返しのつかない状態に陥るおそれもあるため、少しでも思い当たる症状やリスクをお感じの方は、医師の診断を受けることを検討してください。
悪性腎硬化症の病型
高血圧が長期間にわたり腎臓を圧迫すると、血管が硬く脆くなったり、血液が円滑に流れにくくなり、こうしたダメージが過度に蓄積した結果、腎組織へ深刻な影響が及び、最終的に急激な腎機能低下を招くのが悪性腎硬化症です。
本態性高血圧との関連
悪性腎硬化症に至る方の中には、本態性高血圧と呼ばれる原因不明の高血圧がベースにあり、知らないうちに高血圧が長年続いているケースがあります。
本態性高血圧は生活習慣の影響も大きく、塩分の多い食事や肥満、喫煙などによって血管に余計な圧力がかかりやすい状況が作られます。
特に高齢の方やストレスを多く抱える方で血圧が高い状態が慢性化している場合、症状が出始める時期を見逃しがちです。
悪性型と良性型の違い
腎硬化症には良性と悪性に分類される概念があり、両者の違いは進行速度や血圧の程度などにあります。
良性の腎硬化症は高血圧が長期にわたって続き、ゆるやかに腎障害が進行し、一方で悪性腎硬化症では急激に血圧が上昇し、比較的短期間のうちに腎不全へ至るリスクが高いです。
自覚症状がないまま進行する良性型に比べ、悪性型では頭痛や視力障害、吐き気などを伴うケースが多くなります。
重症化しやすいリスク群
若い年代であっても、非常に高い血圧を日常的に示す方、糖尿病や脂質異常症を併発している方は、悪性腎硬化症へ移行するリスクが相対的に高いです。
腎臓の働きは血液ろ過と深く関係しているため、血管合併症を引き起こしやすい糖尿病などを抱えている場合は、腎臓への負荷が一層重くなります。
若年性高血圧との関連
若年性の高血圧が未治療のまま放置されると、将来的に悪性腎硬化症のリスクを高める可能性があり、家庭で血圧を測定する機会が少なく、体力がある若年層は多少の体の変化を見過ごしがちです。
血圧測定の習慣を身につけ、早期に高血圧をコントロールすることで、この病気を未然に防ぐことが期待できます。
悪性腎硬化症に関わる重症度を区別する目安
| 区分 | 血圧の傾向 | 腎機能への影響 | 進行の早さ |
|---|---|---|---|
| 良性腎硬化症 | 中程度の高血圧が長期間続く | 徐々にろ過機能が低下し、末期まで時間を要する | ゆっくりと進む傾向 |
| 悪性腎硬化症 | 非常に高い血圧が急に発症する | 急速に腎障害が進行し、腎不全に至ることがある | 比較的短期間で悪化 |
高血圧の程度や臓器障害の進展は個人差が大きいため、血圧を測る習慣があるかどうかや、多少の体調不良を見過ごさない姿勢が大切です。
悪性腎硬化症の症状
急激に血圧が上がることで、腎臓だけでなく全身にもさまざまな不調が現れ、日常生活に支障をきたす場合があります。悪性腎硬化症の典型的な症状を把握しておくと、自分や身近な人の体調変化に気づきやすくなるでしょう。
血圧上昇による頭痛と吐き気
血圧が急激に高まるため、頭痛や頭が重いような圧迫感を感じる方が多いと報告されていて、脳の血管にも大きな負担がかかっている状態であり、血圧が極めて高い水準を維持してしまうと、吐き気や嘔吐を伴うこともあります。
この頭痛は、通常の疲労や肩こりに伴う頭痛とは異なり、強い拍動感を伴うケースがしばしば見受けられます。
血圧急上昇時に感じる主な身体症状
| 主な症状 | 背景・理由 | 重症度の目安 |
|---|---|---|
| 頭痛 | 脳血管への大きな圧負荷 | 強烈な拍動性や動悸を伴う場合は要注意 |
| 吐き気 | 自律神経の乱れ、血圧急上昇による反射作用 | 頻回に嘔吐する場合、受診を検討 |
| めまい | 脳への血流不安定、体液分布の急変 | ふらつきや意識障害がある場合は重症化 |
視力障害
血圧の過度な上昇は、網膜の血管にも影響を与え、目のかすみや視野の狭まりを感じることがあり、目がチカチカしたり、視力が急激に低下したように感じたりする場合は、危険なサインの一つです。
放置すると網膜剥離や視力障害を残す恐れがあるため、専門的な検査を受けてください。
腎機能低下によるむくみ
腎臓は血液をろ過して体内の水分バランスを調整する重要な役割を担っていて、悪性腎硬化症の状態に陥ると、ろ過機能が急に弱まり、身体に余分な水分や塩分が溜まりやすくなり、むくみを感じるケースが増えます。
特に足首やふくらはぎ、まぶた周辺などの皮下組織が柔らかい部位に顕著に現れることが多いです。
腎不全に伴う疲労感と倦怠感
急性または亜急性の経過で腎臓がダメージを受けると、体内に老廃物が蓄積しやすくなるため、疲労感や倦怠感を訴える方がいます。
以前と同じ生活ペースに戻れない、些細な動作で息切れや全身のだるさを感じるといった兆候が続く場合は、悪性腎硬化症も含めた腎臓トラブルを疑って適切な検査を受けることが大切です。
体全体に現れる症状
| 項目 | 具体的な表れ方 | 腎臓との関連 |
|---|---|---|
| むくみ | ふくらはぎや足首、まぶたの腫れ、靴がきつくなる | 余分な水分や塩分が排出されにくい |
| 倦怠感 | 全身の疲れ、動くのがおっくうになる | 老廃物処理の不十分によるエネルギー低下 |
| 食欲不振 | 口の中の不快感、胃のむかつき | 代謝や消化機能への影響 |
悪性腎硬化症の原因
悪性腎硬化症は文字通り高血圧による腎臓の硬化症状が急激に進む病態ですが、背後には複数の原因や要因が複雑に絡んでいて、血圧が異常に高い状態に陥るには、生活習慣だけでなく遺伝的な要素や他の疾患との相互作用も注目されます。
遺伝的要因や家族歴
高血圧や腎疾患の家族歴がある方は、遺伝的な体質により血管の弾力性や腎臓の機能が脆弱になりやすいです。
家族や近親者に若い頃からの高血圧や慢性腎不全の経験者がいるときは、早い段階から血圧管理に取り組むことで悪性腎硬化症への進展を予防できる可能性が高まります。
食塩過多や偏った食習慣
高血圧の一因として、塩分の過剰摂取がしばしば挙げられ、味付けの濃い食品や加工食品、外食を頻繁にとる生活は、知らず知らずのうちに大幅に塩分を摂りすぎている場合があります。
過度の塩分は血液中のナトリウム濃度を上昇させ、体が水分を溜め込むことで血圧が上がりやすくなり、結果的に腎臓へ過大な負荷がかかる事態を招くのです。
食事面で注意したいポイント
- しょっぱい味付けを好む
- 加工食品やインスタント食品をよく食べる
- 外食が多く野菜摂取量が少ない
- 水分摂取よりも塩味を強く求める傾向がある
糖尿病や脂質異常症などの合併
糖尿病や脂質異常症、メタボリックシンドロームなどを併発している場合は、血管の老化や血中の脂質濃度上昇が進み、腎臓の細小血管にダメージが及びやすいです。
こうした代謝異常がある方は、たとえ薬で血圧をコントロールしていても、日頃の食事療法や運動不足の解消を怠ると、高血圧が悪化して悪性腎硬化症への道を開いてしまうリスクが高まります。
自律神経やホルモン異常
腎臓の血管収縮を制御するホルモン系や自律神経の異常がある場合、急激な血圧上昇を起こすことがあります。
特に内分泌系の疾患、例えば原発性アルドステロン症や褐色細胞腫などを患っている場合、過剰なホルモン分泌によって血管が強く収縮し、血圧が高まりやすいです。
こういったホルモン異常が未発見のまま放置されていると、悪性腎硬化症に至るリスクが増します。
主な原因と腎臓への影響度
| 要因 | 腎臓への影響 | 注意点 |
|---|---|---|
| 遺伝的要因や家族歴 | 血管や腎機能が脆弱になるケースがある | 早期発見のために定期的な健康診断や血圧測定を実施する |
| 塩分過多の食生活 | 血圧上昇を招きやすい | 1日あたりの塩分摂取量を6g未満に抑える意識を持つ |
| 糖尿病・脂質異常症の合併 | 動脈硬化の進行や微小血管障害が強まる | 運動や食事療法など総合的な生活改善が求められる |
| ホルモン・自律神経の異常 | 血管収縮や体液バランスを狂わせやすい | 内分泌系疾患の除外や適切な治療が欠かせない |
検査・チェック方法
高血圧がある程度進行してからでは、体に現れる異常が深刻化している可能性があり、早い段階で腎臓の状態をチェックし、悪性腎硬化症に至る前に的確な対処を行うことが重要です。
血圧測定の活用
自宅や職場などでこまめに血圧を測定し、自分の平均的な血圧を把握しておくことが重要で、早朝や仕事の後など、生活リズムに応じて血圧変動のパターンを掴むと、高めの数値が続いていないかどうかを客観的に確認できます。
家庭用の血圧計でも正しく使用すれば信頼性は高く、医療機関で測定する際との差が極端に大きい場合は相談してください。
尿検査によるタンパク・潜血チェック
腎臓にダメージが及ぶと、ろ過が不十分になるためタンパク質が尿中に漏れ出したり、血管の損傷で赤血球が混ざったりしやすくなります。尿検査は簡便でありながら、悪性腎硬化症のみならず腎臓の健康状態を幅広く推測する手がかりです。
タンパク尿や潜血が見られた場合は、さらに詳しい検査で腎機能を評価することが必要になります。
尿検査で注目される主な項目
| 項目 | 意味 | 悪性腎硬化症との関連 |
|---|---|---|
| 尿タンパク | 腎臓のろ過機能が低下すると漏れ出やすくなる | 重度の腎障害があると高値を示す可能性が高い |
| 尿潜血 | 血管障害や炎症で赤血球が混入している | 腎血管のダメージが深刻化しているかを推測できる |
| 尿比重 | 腎臓の水分調整能力を反映 | 腎機能が低下すると比重コントロールが乱れる |
血液検査と腎機能評価
血液検査で腎機能を評価する場合、血中尿素窒素(BUN)やクレアチニン(Cr)を測定し、糸球体濾過量(GFR)を推定する方法が広く利用されています。
悪性腎硬化症が進行すると、これらの値が正常範囲を大きく逸脱し、腎不全の兆候を示すことが多く、急にクレアチニン値が上昇している場合は、精密検査で詳しい病態を把握することが大事です。
画像診断の有用性
超音波検査やCT、MRIなどの画像診断を行うと、腎臓の大きさや血流、内部の形状などが分かり、悪性腎硬化症特有の血管病変を確認できる可能性があります。
血管造影検査などで血管の狭窄や瘤がないかを調べると、急激な高血圧の原因を特定する一助です。ただし、造影剤を使う検査では腎機能をさらに悪化させるリスクがあるため、医師とよく相談してください。
悪性腎硬化症の診断に用いられる主な検査
| 検査方法 | 主な目的 | 利点・留意点 |
|---|---|---|
| 血圧測定 | 高血圧の程度と変動パターンの把握 | 自宅でもこまめに実施でき、費用が安い |
| 尿検査 | タンパク尿・潜血・尿比重のチェック | 簡便で患者負担が少なく、早期発見に向いている |
| 血液検査 | BUNやCrなど腎機能指標の評価 | 病態を定量的に把握し、重症度を推定できる |
| 画像診断 | 腎臓や血管の状態を視覚的に確認 | 造影剤使用時のリスクや費用負担を考慮する |
治療方法と治療薬について
悪性腎硬化症は放置すると重篤な腎不全へとつながりかねないため、早期の段階で迅速かつ総合的な治療を始めることが大切で、血圧を下げるだけでなく、腎臓の機能を守るために多角的なアプローチが取られます。
降圧薬の基本的な役割
第一に血圧のコントロールが必要となるため、降圧薬の使用が中心的な治療となります。
カルシウム拮抗薬、ACE阻害薬、ARB(アンジオテンシンII受容体拮抗薬)などの薬が処方されるケースが多いですが、悪性腎硬化症の場合は単剤だけでコントロールが難しいこともあり、複数の降圧薬を組み合わせて用いる場合もあります。
血圧を急激に下げすぎると脳や心臓への血流が不足するリスクがあるため、目標値を踏まえつつ段階的に投与量を調整します。
利尿薬との併用
血液量をコントロールするために、利尿薬を併用することが検討され、特に腎臓が水分調節機能を失いつつあるときは、余分な水分を排出させることで血圧を下げつつ、むくみや肺水腫などの合併症を防ぐ狙いがあります。
併用の際は電解質バランスが乱れやすくなるため、定期的な血液検査でナトリウムやカリウムなどの値をフォローしながら調整します。
使用される主な降圧薬
| 薬の分類 | 代表的な薬剤 | 主な作用 |
|---|---|---|
| カルシウム拮抗薬 | アムロジピンなど | 血管の平滑筋を弛緩して血圧を下げる |
| ACE阻害薬 | エナラプリルなど | レニン-アンジオテンシン系をブロックする |
| ARB(受容体拮抗薬) | ロサルタンなど | 血管収縮を引き起こすホルモンの作用を阻害 |
| 利尿薬 | フロセミドなど | 余分な水分を排出し血圧を低下させる |
生活習慣の改善と指導
降圧薬による治療と並行して、塩分制限や適度な運動、体重管理など、生活習慣の見直しが欠かせません。
悪性腎硬化症の場合、短期間で血圧を急激に下げる必要がある一方で、食事内容や普段の活動量の管理を徹底しなければ再発リスクが残ります。医師や管理栄養士の指導を受けながら、着実に食事面や運動習慣を改善することが大切です。
合併症への対応
糖尿病や脂質異常症がある場合は、疾患に対する薬物療法や食事療法も同時に進め、悪性腎硬化症による腎機能の低下が著しいと、将来的に透析治療を視野に入れなければならないケースもあります。
腎不全が進みやすい状況を回避するために、合併症をなるべく早期にコントロールする努力が必要です。
多角的な治療アプローチ
| 治療手段 | 目的・狙い | 具体的な内容 |
|---|---|---|
| 薬物治療(降圧薬など) | 血圧コントロールと腎保護 | 適切な薬を選び、段階的に血圧目標を達成 |
| 食事療法 | 塩分制限やカロリー管理による血圧低下 | 毎食の塩分摂取量を把握し、野菜やタンパク質のバランスを取る |
| 運動療法 | 体重減少と血管機能の改善 | ウォーキングや軽い筋力トレーニングから始める |
| 合併症管理 | 糖尿病・脂質異常症などの進行を抑える | 血糖値コントロールや脂質管理の徹底 |
悪性腎硬化症の治療期間
急激に進行する悪性腎硬化症であっても、治療を始める時期や症状の程度、個人の体質によって必要な期間やその後の経過観察の長さは異なります。
ただし、腎臓は一度損傷を受けると回復に時間がかかったり、完全に元の状態に戻れなかったりする可能性があるため、長期的な視点で治療計画を立てることが欠かせません。
初期治療から安定化までの流れ
悪性腎硬化症と診断された段階では、血圧が非常に高くなっていることが多いため、まずは入院も視野に入れた集中的な治療が行われる場合があります。
降圧薬の点滴投与などによって一定の水準まで血圧を下げ、腎臓への圧力を軽減することが第一です。数日から数週間にわたる初期治療の後、血圧が安定すれば外来通院での管理に移行できるケースもあります。
通院と定期的検査の継続
悪性腎硬化症は一時的に血圧が落ち着いても、再度コントロール不良に陥れば短期間で腎機能が悪化するリスクをはらんでいる疾患です。
定期的に血液検査や尿検査を受け、血圧や腎機能の状態をモニタリングしながら、必要に応じて降圧薬の種類や用量を調整していきます。
治療開始から半年から1年程度は、血圧だけでなく合併症の管理や薬の副作用チェックも入念に行うことが重要です。
治療過程での主なステップと期間の目安
| 段階 | 期間の目安 | 目的や注意点 |
|---|---|---|
| 急性期(初期治療) | 数日~数週間 | 入院治療で血圧急降下を避けつつ、徐々にコントロール |
| 安定期(外来通院) | 数カ月~1年程度 | 定期検査で腎機能と血圧を評価し、薬の調整を行う |
| 長期維持期 | 1年以上 | 血圧管理と合併症対策を継続し、再発予防を図る |
回復の程度と個人差
腎機能の回復力は個人差があり、悪性腎硬化症の進行度合いによっても大きく異なり、比較的早期に発見できれば、治療と生活改善によって腎不全への移行を防ぎ、日常生活に近いレベルまで腎機能を維持できる場合があります。
一方で、既に重篤な状態に至った後では、透析が必要になるケースや、腎移植を考慮しなければならない状況に発展することもあるため、早期受診の重要性が改めて問われます。
透析が必要になる可能性
悪性腎硬化症が進行して末期腎不全へ移行すると、自力で体内の老廃物や水分を十分に排出することが難しくなり、透析治療が選択肢に含まれることがあります。
透析は週に数回病院や透析施設に通う血液透析、あるいは自宅で行う腹膜透析などの方法がありますが、いずれも患者さんの生活には大きな変化をもたらします。
透析を回避または先延ばしにするためにも、早い段階でのコントロールと長期的な維持が必要です。
腎不全に陥った場合の主な選択肢
| 方法 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 血液透析 | 病院や透析施設で専門スタッフが管理 | 週数回の通院が必要になり、自由度がやや下がる |
| 腹膜透析 | 自宅で行え、比較的生活の自由度が高い | 手技の習得が必要で、腹膜炎などの合併症リスクがある |
| 腎移植 | 移植後に腎機能が安定すれば透析が不要になる | ドナー・手術リスクや免疫抑制剤の継続服用が課題 |
副作用や治療のデメリットについて
降圧薬を中心とした治療は悪性腎硬化症の進行を抑える上で有効ですが、薬には副作用もあり、治療そのものが患者さんの生活に一定の負担を伴う可能性があります。
低血圧症状やめまい
降圧薬は意図的に血圧を下げる薬であるため、投与量や体の反応によっては過度に血圧が下がり、めまいやふらつきなどの低血圧症状が起こり得ます。
立ち上がったときにクラッとしたり、軽く息切れを感じたりするケースが見られるため、起床時や運動時は慌てずゆっくり動くよう心がけましょう。
低血圧に伴う日常的な影響
| 症状 | 背景 | 対処法・予防策 |
|---|---|---|
| めまい | 血圧低下に伴う脳血流不足 | ゆっくり動き、転倒を予防する |
| 倦怠感・疲労感 | 体全体への酸素供給量が減る | 休息を適宜取り、十分な水分補給を行う |
| 思考力低下 | 中枢神経への影響で注意力や集中力が落ちる | 勉強や仕事に一時的な配慮を取り入れる |
電解質バランスの崩れ
利尿薬を併用するとナトリウムやカリウムなどの電解質が変動しやすくなり、カリウム値が下がりすぎると筋力低下や不整脈のリスクが上がり、上がりすぎると心臓のリズム異常を起こす恐れがあります。
定期的に血液検査を受けながら、カリウムのサプリメントを利用する、あるいは利尿薬の種類を見直すなどの対策を講じることが大事です。
腎機能への影響
ACE阻害薬やARBなどは腎保護作用が期待される一方で、血圧を下げすぎると腎臓への血流が減ってむしろ腎機能を悪化させるリスクもわずかにあります。
また、降圧薬の組み合わせによっては腎臓への血管抵抗が変化し、クレアチニン値が急に上昇する可能性も否定できません。これらの副作用を防ぐためには、定期的な腎機能のチェックと必要に応じた薬剤変更が重要です。
治療のデメリットと対処
| デメリット | 具体的な例 | 対処法 |
|---|---|---|
| 低血圧リスク | めまい、意識低下、倦怠感 | 緩やかな降圧目標を設定し、生活スタイルを調整 |
| 電解質バランスの乱れ | カリウム過不足による不整脈や筋力低下など | 定期的な血液検査と食事でのミネラルバランス管理 |
| 腎機能低下の悪化可能性 | 薬の組み合わせで腎血流が下がり、Cr値が急増 | 腎機能に応じた用量調整と経過観察 |
治療に伴う生活上の制限
降圧薬や利尿薬を使用していると、飲酒や塩分摂取量を厳しく制限されることが多く、友人との食事会や日常の外食などでも気を遣わなければなりません。
ストレスが溜まると治療のモチベーションが落ちる恐れがあるため、医師や管理栄養士から指導を受け、自分なりの工夫を凝らして過度な負担を感じないようにバランスを見つけましょう。
悪性腎硬化症の保険適用と治療費
以下に記載している治療費(医療費)は目安であり、実際の費用は症状や治療内容、保険適用否により大幅に上回ることがございます。当院では料金に関する以下説明の不備や相違について、一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。
保険適用となる一般的な治療
降圧薬や利尿薬など、主に使用される薬剤は健康保険の対象に含まれ、腎機能を評価するための血液検査や尿検査、画像診断なども保険適用内で行われるケースが一般的です。
入院費や処方薬の目安
悪性腎硬化症による急性期の入院治療は、血圧コントロールのための点滴や集中モニタリングなどが中心です。
入院する病棟や部屋の種類(一般病棟か個室か)によって費用は変わることがありますが、数日から数週間程度の入院であれば自己負担分として10万円から20万円程度になるケースがあります(3割負担の場合)。
悪性腎硬化症治療にかかわる費用
| 治療・検査内容 | 保険適用の有無 | 自己負担目安(3割負担の場合) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 入院治療(急性期) | ○ | 数日~数週間で10~20万円程度 | 個室利用や検査追加で変動あり |
| 降圧薬・利尿薬などの処方 | ○ | 月々数千円~1万円程度 | 複数薬を併用するほど費用が増える傾向 |
| 定期的な血液・尿検査 | ○ | 数千円~1万円前後 | 頻度や検査項目により変動 |
| 画像診断(CT、MRIなど) | ○ | 1回あたり数千円~1万円程度 | 造影検査を追加すると加算 |
透析治療が必要となった場合
悪性腎硬化症が進行し、末期腎不全に至った際に透析治療が始まると、週に数回の継続することになります。透析は健康保険の適用となり、自己負担は3割負担の場合でも毎月数万円の出費です。
以上
参考文献
Kimmelstiel P, Wilson C. Benign and malignant hypertension and nephrosclerosis: a clinical and pathological study. The American journal of pathology. 1936 Jan;12(1):45.
Chatelain RE, DiBello PM, Ferrario CM. Experimental Benign and Malignant Nephrosclerosis. British journal of experimental pathology. 1980 Aug;61(4):401.
SHAPIRO PF. Malignant nephrosclerosis: Pathogenesis. Archives of Internal Medicine. 1931 Aug 1;48(2):199-233.
Bureau C, Jamme M, Schurder J, Bobot M, Robert T, Couturier A, Karras A, Halimi JM, Bellenfant X, Rondeau E, Mesnard L. Nephrosclerosis in young patients with malignant hypertension. Nephrology Dialysis Transplantation. 2023 Aug;38(8):1848-56.
Schwartz NH, Gross S. Unilateral malignant nephrosclerosis. The Journal of Urology. 1949 Oct;62(4):426-35.
McCormack LJ, Béland JE, Schneckloth RE, Corcoran AC. Effects of antihypertensive treatment on the evolution of the renal lesions in malignant nephrosclerosis. The American journal of pathology. 1958 Dec;34(6):1011.
Ono H, Ono Y. Nephrosclerosis and hypertension. Medical clinics of north America. 1997 Nov 1;81(6):1273-88.
Saphir O, BALLINGER J. Hypertension (Goldblatt) and unilateral malignant nephrosclerosis. Archives of Internal Medicine. 1940 Sep 1;66(3):541-60.
Zhang Y, Yang C, Zhou X, Hu R, Quan S, Zhou Y, Li Y, Xing G. Association between thrombotic microangiopathy and activated alternative complement pathway in malignant nephrosclerosis. Nephrology Dialysis Transplantation. 2021 Jul 1;36(7):1222-33.
Bidani AK, Griffin KA, Plott W, Schwartz MM. Renal ablation acutely transforms’ benign’hypertension to’malignant’nephrosclerosis in hypertensive rats. Hypertension. 1994 Sep;24(3):309-16.