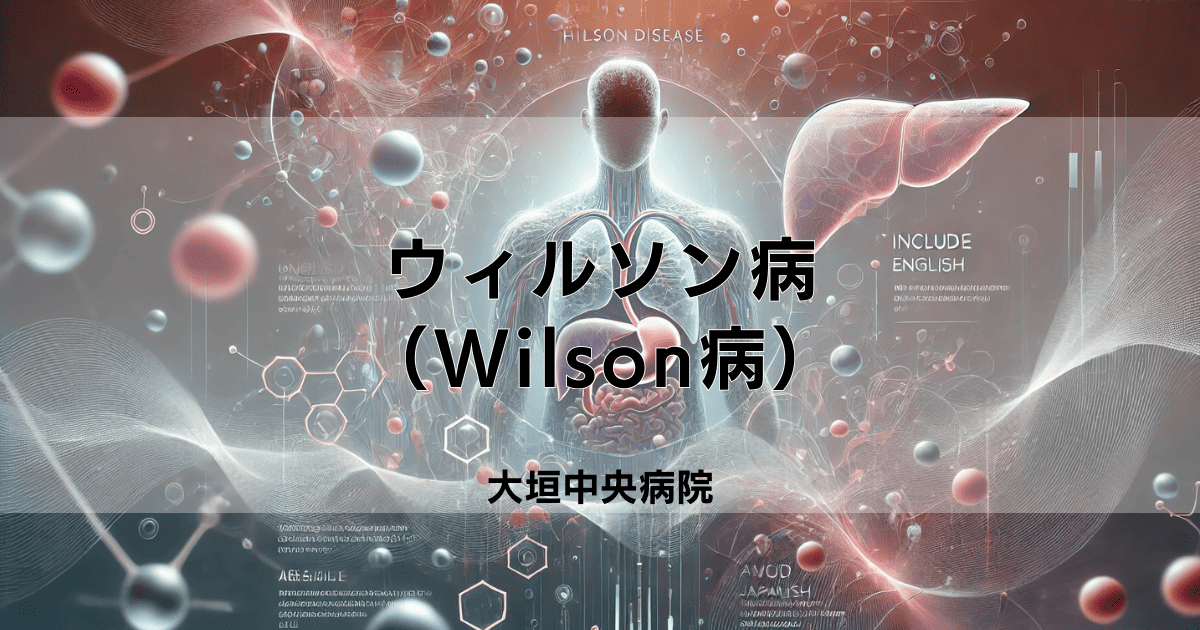ウィルソン病(Wilson病)とは、肝臓や脳を中心とした臓器に銅が過剰に蓄積する遺伝性の疾患で、幼少期から思春期、あるいは成人期にかけて多様な症状を起こします。
銅は体にとって必要な微量元素ですが、体内でうまく排泄できず過剰に溜まると、肝機能障害や神経症状、精神症状などを誘発する可能性があります。
肝臓障害から始まるタイプもあれば、神経症状や精神症状が目立つタイプもあり、発症時期や症状の現れ方は人によってさまざまです。
ウィルソン病(Wilson病)の病型
ウィルソン病には、肝機能障害を主徴とするものや中枢神経系を中心とした症状を示すものなど、いくつかの病型があります。
どのタイプが発症するかによって、医師が考慮する治療方針や注意点が異なるため、自分の病態がどの病型に当てはまりやすいのかを理解することが大切です。
肝型ウィルソン病
肝型と呼ばれるものは、主に肝機能障害を伴うウィルソン病で、幼少期や思春期などの比較的若い年齢層で発症することが多く、血液検査で肝機能を調べた際に異常が見つかるケースが少なくありません。
肝臓が銅をうまく排出できず蓄積することで、慢性肝炎や肝硬変へと進展する可能性があります。
神経型ウィルソン病
神経型ウィルソン病は、中枢神経系に銅が蓄積しやすいことから、神経症状を中心に現れる病型で、成人期に入ってから発症するケースもあり、肝型と異なり、最初は神経症状や精神症状が前面に出ることもあります。
神経型ウィルソン病は症状が多彩で、肝臓の症状が全くないわけではありませんが、神経・精神症状が強くクローズアップされるため、神経内科で検査を受けて初めてウィルソン病を疑うこともあります。
混合型ウィルソン病
肝型と神経型の両方の特徴が同時または時期をずらして生じるパターンは、混合型と呼ばれることがあります。
初期は肝臓が傷害されていても、自覚症状が乏しいまま神経症状へ移行するケースがあるため、いずれの症状が先行するかがはっきりしない場合もあります。
血液検査だけではなく、脳のMRIや神経学的検査を受けて詳しく確認すると、混合型の見出すことが可能です。
無症候性キャリア
ウィルソン病を引き起こす遺伝子に変異があっても、はっきりした臨床症状を起こさずに経過する「無症候性キャリア」の存在が指摘されています。
家族内にウィルソン病の人がいる場合は、念のため検査を受けて、遺伝子変異の有無を調べることを考慮する人もいます。
無症候性キャリアの多くは血清中のセルロプラスミン値が低かったり、銅の代謝に軽微な異常が見られたりするものの、治療を要するレベルまで病状が進行しないこともあります。
症状
ウィルソン病では、肝臓や脳などに銅が溜まるため、多岐にわたる症状が現れる可能性があり、特定の部位に症状が集中する場合や、複数の臓器に渡る症状がみられる場合など、個人差が大きいのが特徴です。
身体的な違和感だけでなく、精神的な面や行動面での変化が生じることもあり、どのような症状が出るかを把握することで、早期発見と対処につながります。
肝臓に関連した症状
肝機能の悪化に伴う症状は、ウィルソン病において最も一般的で、黄疸や倦怠感、右上腹部の痛みなどが典型的で、特に黄疸は血液中のビリルビンが高まり、皮膚や眼球が黄色っぽく変化するため目につきやすい症状です。
慢性的に肝障害が進むと腹水が溜まったり、吐血のリスクが高まったりする可能性があり、治療が遅れると肝硬変に至ることがあります。
肝障害が進む前に血液検査で異常が出るケースも多く、ASTやALT、γ-GTPなどの肝酵素値が上昇した場合にウィルソン病の可能性を調べることがあります。
肝炎ウイルスなど別の原因が除外され、血清銅やセルロプラスミンなどを調べてウィルソン病が疑われる場合は、追加検査へと進むことが一般的です。
肝臓症状に関するチェックポイント
- 黄疸があるか(皮膚・眼球の黄色味)
- 倦怠感や食欲不振
- 肝酵素値(AST、ALT、γ-GTPなど)の上昇
- 腹水や吐血などの合併症の有無
| タイミング | よく見られる症状 | 進行時のリスク |
|---|---|---|
| 初期 | 倦怠感・食欲不振などの非特異的症状 | 病気の発見が遅れる可能性 |
| 進行期 | 黄疸・肝機能検査値の異常 | 肝硬変への移行、腹水や吐血などのリスク |
| 重症化 | 腹水・意識障害・出血傾向など | 肝不全状態、生命の危険を伴う可能性 |
神経・精神症状
中枢神経系への銅蓄積が進むと、運動障害や震えなどの錐体外路症状、パーキンソン症候群のような姿勢や動作の硬さ、言語障害などが出ることがあります。
精神的な面では、注意力の低下や記憶障害、うつ傾向などが出るケースがあり、これらの症状に悩む人は単純にストレスや精神疾患が原因だと思って受診を後回しにしてしまうこともあります。
しかし、若い世代でこれらの症状が急激に進む際は、ウィルソン病の可能性も考慮が必要で、ときには攻撃的になったり、人格変化を生じたりする人もいるため、家族や周囲の理解とサポートが欠かせません。
角膜カイザー・フライシャーリング
角膜カイザー・フライシャーリングは、ウィルソン病でよくみられる特徴的なサインのひとつで、角膜の縁に銅が沈着することで茶褐色や緑褐色の輪が見える現象です。
眼科でスリットランプを用いて観察すると確認しやすく、眼が黄色く見える黄疸とは異なる見た目なので注意が必要です。
このカイザー・フライシャーリングは、特に神経型ウィルソン病や混合型の患者に多く確認され、肝機能に加え中枢神経系にも異常が生じる段階で顕著化するともいわれています。
腎臓やその他の臓器への影響
ウィルソン病は肝臓と中枢神経が代表的な影響部位ですが、銅が体内のほかの器官に蓄積すると、腎臓や骨、関節などにも症状が及ぶ可能性があります。
たとえば、尿の中にアミノ酸が漏れ出す「アミノ酸尿症」が見つかったり、関節痛や骨の変形といった骨関節系の症状が現れたりすることがあります。
さらに、赤血球が壊される溶血性貧血が起きると、倦怠感やめまいなどの貧血症状が強くなることもあります。全身性に及ぶ潜在的リスクがあるため、ウィルソン病を疑われた時点で各臓器の状態を総合的に評価することが必要です。
ウィルソン病(Wilson病)の原因
ウィルソン病は遺伝性の病気であり、特定の遺伝子(ATP7B遺伝子)の変異によって起こり、体内での銅の排出を担う働きが十分に機能しなくなることで、過剰な銅が肝臓や脳などに蓄積しやすくなります。
遺伝子変異のメカニズム
ATP7B遺伝子は肝細胞内における銅の排出や輸送を司っていて、変異が生じると、肝臓から胆汁へ銅を排泄するプロセスが妨げられ、銅が体内に過剰に留まります。
余った銅の一部は血中を巡り、最終的には脳や腎臓、角膜などに蓄積するので、症状が多面的に現れることになります。
同じ変異でも人によって症状が違ったり、まったく出なかったり、遺伝的要因と環境的要因が複雑に影響しているのです。
主な原因と影響
- ATP7B遺伝子の変異による銅排出機能の低下
- 常染色体劣性遺伝の形式をとる
- 遺伝子変異の程度により症状の出方に個人差がある
ウィルソン病の主な遺伝的特徴
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 関連遺伝子 | ATP7B遺伝子 |
| 遺伝の形式 | 常染色体劣性遺伝 |
| 銅代謝への影響 | 肝臓から胆汁への銅排泄がうまくいかず、体内に銅が過剰蓄積しやすい |
| 個人差の要因 | 遺伝子変異の種類や環境要因により発症時期や症状が多様になる |
| キャリアの存在 | 変異遺伝子を1つだけ持っている場合は無症候のケースが多い |
家族歴と発症リスク
ウィルソン病は家族内に患者がいる場合、その兄弟姉妹や子どもにも一定の発症リスクがあり、両親ともにキャリアであれば、子どもがウィルソン病を発症する確率は高まります。
ただし、家族歴が明らかでなくても突然変異の形で生じることもないわけではありません。現実には、家族内発症が確認されて初めてウィルソン病の存在を知るケースもあります。
環境要因や生活習慣との関係
ウィルソン病自体は遺伝子変異が直接の原因ですが、生活習慣や栄養状態などの環境要因によって症状の現れ方や進行速度が変わることがあります。
銅を多く含む食品を過度に摂取していると、体内に取り込む銅の量が増え、症状が顕在化しやすくなる可能性が指摘されています。
一方で、栄養状態が悪くてタンパク質が不足すると、肝臓がうまく機能しなくなることで症状が表面化しやすくなるともいわれています。
ただし、遺伝的に銅排泄機能が正常であれば、一般的な食事程度ではウィルソン病のような深刻な銅蓄積には至りません。あくまで、遺伝要因と環境要因が組み合わさって症状が顕在化する可能性が高まるという考え方が一般的です。
発症予防は可能か
遺伝子変異が存在する以上、ウィルソン病の完全な予防は難しいですが、早期に診断し、銅排泄を促す治療薬や食事療法を行うことで、重症化を防ぐことが可能です。
肝機能障害や神経症状が出現する前の段階で介入すれば、日常生活に支障をきたさない程度に症状をコントロールできる場合もあります。
家族歴がはっきりしているときは、小児期から定期的な検査を実施し、数値に異変が生じた場合は主治医が積極的に治療薬を検討します。
検査・チェック方法
ウィルソン病の診断を行うにあたっては、血液検査や尿検査、眼科検査、肝生検、画像検査など、複数のアプローチを総合的に組み合わせます。
血液検査
血液検査では、セルロプラスミンや血清銅、フェリチン、AST、ALTなど、いくつかの項目を確認し、ウィルソン病の疑いがある場合、セルロプラスミン値が低下していることが多いのが特徴です。
血清総銅量も低くなる傾向がありますが、実は血清遊離銅が増えているケースもあるため、各指標を総合的に見て判断し、セルロプラスミンが20 mg/dL未満だとウィルソン病を疑う一つの目安になります。
また、肝機能を示すASTやALTが軽度~中等度に上昇している場合は肝型ウィルソン病を念頭に、さらに詳細な検査に進むことになります。
血液検査で主にチェックする項目
- セルロプラスミン
- 血清銅
- AST、ALT(肝酵素)
- フェリチン
ウィルソン病が疑われる血液検査所見
| 検査項目 | ウィルソン病での傾向 | 主な目的 |
|---|---|---|
| セルロプラスミン | 低値になることが多い | 銅輸送タンパクの評価 |
| 血清総銅 | 低値が多いが遊離銅は高い場合がある | 体内の銅バランスの評価 |
| AST・ALT | 軽度~中等度上昇 | 肝炎や肝障害の有無を確認 |
| フェリチン | 時に高値になる場合がある | 炎症や肝障害との関連性を評価 |
24時間尿銅検査
24時間尿銅検査は、体内から排泄される銅の量を調べるもので、ウィルソン病の診断には欠かせない重要な検査の一つです。
通常は1日分の尿をすべて採取して、その中に含まれる銅の量を測定し、ウィルソン病があると、銅排泄に異常があるため、尿中銅量が増加することが多く、基準値を超える場合にウィルソン病の疑いが高まります。
また、銅排泄を促す薬を一時的に投与してから尿中銅を測定する「ペニシラミン負荷試験」も行われることがあります。
負荷試験を行うことで、体内に蓄積した銅を薬で一時的に押し出し、尿に排泄された銅の量を測定してウィルソン病かどうかを確認します。
眼科検査(スリットランプ検査)
ウィルソン病特有の角膜カイザー・フライシャーリングの有無を確認するために、眼科でスリットランプ検査を受けることがあります。
通常の視診だけでは見つけにくい茶褐色や緑褐色のリングが角膜周辺部に沈着している場合、診断の重要な手がかりで、このリングは神経型ウィルソン病で特に高頻度にみられますが、肝型の一部でも認められます。
スリットランプ検査自体は簡便に実施できて時間もかからず、大きな負担がかからない検査方法です。
画像検査・肝生検
中枢神経系症状がある場合は、MRIやCTなどの画像検査で脳内の異常集積を調べることがあります。
ウィルソン病の場合、被殻や淡蒼球、視床などに特有の異常所見がみられることがあるため、神経型や混合型の診断を後押しする情報として重要です。
また、肝臓の状態を直接評価するために肝生検を行い、肝組織中に含まれる銅の量を定量する方法もあります。
肝生検は侵襲的な検査なので、必要性を慎重に判断しつつ実施しますが、銅の蓄積量を客観的に把握できるため、診断の確定に役立ちます。
ウィルソン病(Wilson病)の治療方法と治療薬について
ウィルソン病の治療は、主に体内から過剰な銅を排泄し、臓器へのダメージを抑えることを目的とし、発症初期の段階で治療を開始すれば、生活への支障が少ない状態を維持できる可能性があります。
薬剤選択や食事指導を組み合わせながら、肝臓や神経の保護を図ることが重要です。
銅排泄を促すキレート剤
ウィルソン病の治療薬として中心的な役割を果たすのが、体内に蓄積した銅と結合して排泄を促すキレート剤です。
代表的な薬剤としてD-ペニシラミンやトリエンチンなどが挙げられ、服用することで、尿中へ銅を引き出し、血中や臓器に蓄積した銅量を減らす狙いがあります。
D-ペニシラミンは比較的歴史がある薬で、長年にわたりウィルソン病の治療に使われてきました。一方、トリエンチンは副作用の点で相対的に穏やかだとみなされることがあり、ペニシラミンが合わない人に用いられるケースが多いです。
ただし、どちらの薬でも銅以外のミネラルやビタミンへの影響が出ることがあるため、医師は慎重に用量や注意点を設定します。
主なキレート剤の特徴
| 薬剤名 | 特徴 | 主な考慮点 |
|---|---|---|
| D-ペニシラミン | 長年使用されており実績がある | アレルギー反応や副作用への注意 |
| トリエンチン | ペニシラミンより副作用が少ない場合がある | 薬価が高めのことがある |
| ジンク製剤 | 銅の吸収を抑制し、排泄促進をサポートする | 食事とのタイミングに注意が必要 |
ジンク製剤
ジンク(亜鉛)製剤を用いる方法も、ウィルソン病の治療で広く使われていて、亜鉛は、腸管での銅吸収を阻害する働きがあり、結果として体外への銅排泄をサポートするというメカニズムです。
キレート剤に比べて副作用が少ないとされる一方、十分な治療効果を得るためには毎日欠かさず服用し続けることが大切です。
神経型ウィルソン病の場合はキレート剤との併用を考慮するケースもあるため、主治医が治療方針を決めるときに判断します。
ジンク製剤は空腹時に服用するとより効果的といわれていますが、胃の不快感を訴える人もいるため、服用タイミングの調整や制酸剤の使用などが検討されます。
薬物治療と食事療法の併用
ウィルソン病の管理では、薬物治療だけでなく、銅を多く含む食品を控えるなどの食事療法を並行して行うことが大切です。
肝機能が低下している場合は、銅含有量の高い食品(レバー、牡蠣、ナッツ類、チョコレートなど)を必要以上に摂取しないよう意識する必要があります。
食事療法で注意する代表的な食品
- レバーや内臓肉
- 牡蠣、イカ、エビなどの魚介類
- ナッツ類やチョコレート、ココア
- 種実類(ヒマワリの種、カボチャの種など)
肝移植が検討される場合
ウィルソン病が重症化し、肝不全を起こすまで進行した場合は、肝移植を考慮せざるをえないケースもあり、肝臓の機能が極端に低下して、薬物治療だけでは改善が見込めない状態になったときが該当します。
肝移植を行うと、移植した肝臓が銅排泄機能を正常に機能させる可能性があるため、生体肝移植や脳死肝移植が治療オプションとして提示されることがあります。
ただし、肝移植にはドナーの問題や術後の免疫抑制など、多くの課題とリスクが伴います。
肝移植後も免疫抑制剤の服用が続くことや、拒絶反応のリスクを考慮しながら生活を送る必要があるため、医師と十分に相談し、総合的な判断を下すことが重要です。
治療期間
ウィルソン病は遺伝的要因によって引き起こされる慢性疾患なので、一度診断された場合、長期にわたって治療と管理を行うことが求められます。
薬剤を用いて体内の銅を排泄したり、吸収を阻害したりすることで臓器のダメージを防ぐ狙いがあるため、経過観察とともに治療を続ける姿勢が大切です。
治療の目標と期間の考え方
最初の目標は、過剰に蓄積した銅を減らし、症状を落ち着かせることで、肝障害が重度であったり、神経症状が急激に進行している場合は、キレート剤などを積極的に使って短期的に銅を排出することが望まれます。
この最初の段階で症状が改善しても、薬の服用をやめてしまうと再び銅が蓄積するおそれがあるので、医師の指示に従い継続して管理することが必要です。
症状が落ち着いた後も、銅の代謝異常が根本的に解消されているわけではなく、薬を中断すれば数年後に再発する可能性があるため、多くの場合は一生涯にわたって投薬と経過観察を行うことになります。
| 時期 | 治療方針 | ポイント |
|---|---|---|
| 発症初期~急性期 | キレート剤や亜鉛剤の導入、症状緩和 | 銅排泄を促してダメージを最小限に抑える |
| 症状安定期 | 投薬量の調節、定期的な検査 | 生活の質を維持しながら長期管理を続ける |
| 再発リスク管理期 | 必要に応じて薬剤変更や追加 | 軽度の変化でも対処して大きな悪化を防ぐ |
小児期発症の場合
ウィルソン病は小児期や思春期に発症することも少なくあり、子どもの場合は成長段階にあるため、薬の用量や副作用の出方に注意が必要です。
肝機能や神経症状の進展をこまめにチェックしながら、必要最小限の薬量で治療効果を得ることが望まれます。成長に伴って薬剤の調整が必要になることもあるので、主治医や専門医と連携して治療計画を見直すことが大切です。
成人期発症の場合
成人になって初めて診断されるケースもあり、その場合は仕事や家庭環境などとの両立を図りながら治療を続ける必要があります。
症状が軽いからといって自己判断で薬をやめると、数年後に再燃し、肝障害や神経症状が著しく悪化するリスクがあるため注意が必要です。
成人期発症では肝硬変などの深刻な状態に陥るまで気づかないことがあるので、定期的な血液検査やMRI検査などを継続して受けることが重要になります。
キレート剤や亜鉛剤を上手に使いながら、栄養指導を受けたり、生活習慣を見直したりすることで、長期間にわたって症状をコントロールできる可能性があります。
病状安定後のメンテナンス
一定期間治療を続けて銅の蓄積量が減り、血液検査や尿検査、眼科検査などの結果が安定したら、薬剤の用量を減らしたり、服用回数を調整したりする段階に移行することがあります。
ただし、完治ではなく、あくまで寛解状態と捉えたうえで薬を続ける必要があり、無理に薬を減量すると再び銅が蓄積し、症状の再燃につながるため、自分の判断ではなく、主治医と相談したうえで安全に減量計画を組むことが大切です。
数年にわたる治療ののち、安定した状態が続けば、少なくとも年に数回の定期検査で血中や尿中の銅、肝機能などをチェックし、異常がないかを常にモニタリングします。
ウィルソン病(Wilson病)薬の副作用や治療のデメリットについて
薬物治療はウィルソン病のコントロールにおいて欠かせない手段ですが、長期にわたる投薬には副作用リスクやデメリットを伴うことがあります。
キレート剤の副作用
代表的なキレート剤であるD-ペニシラミンは、皮膚疹や関節痛、胃腸障害などの副作用を伴う場合があり、重度になると、血球減少や腎機能障害、自己免疫性疾患を発症するリスクも否定できません。
また、服用開始後、神経型ウィルソン病を持つ人の一部では一時的に症状が悪化することがあり、医師は用量や投薬のタイミングを調節しながら経過を観察します。
トリエンチンもキレート剤として使用されますが、ペニシラミンよりは副作用が少ないと言われる一方で、胃腸障害や貧血、皮膚症状が全く起こらないわけではありません。
キレート剤で注意が必要な副作用
- 発疹、かゆみ
- 関節痛や筋肉痛
- 腎機能障害
- 血球減少(白血球や血小板)
- 消化器症状(吐き気、食欲不振など)
キレート剤の副作用と主な症状
| 副作用・症状 | 具体例 | 注意点 |
|---|---|---|
| 皮膚・アレルギー症状 | 発疹、かゆみ、アナフィラキシー様反応など | 早期に気づけば薬剤変更を検討する |
| 血液学的障害 | 白血球減少、血小板減少など | 血液検査の定期的なチェックが必要 |
| 腎機能障害 | 尿蛋白、クレアチニン上昇など | 腎機能が低下している人は用量調整に注意 |
| 消化器症状 | 吐き気、下痢、食欲不振など | 投薬時間や食事との兼ね合いを調整して対策を考える |
亜鉛製剤の副作用
亜鉛製剤は比較的副作用が少ないと言われますが、長期服用では胃腸障害(吐き気や胃もたれ)や金属臭といった不快感が生じる人もいます。
空腹時に服用することが推奨される場合が多いため、胃腸に刺激を与えやすいと感じる人は少なくありません。服用タイミングを調整したり、医師が他の薬剤と併用することで対処したりする方法があります。
また、亜鉛製剤を長期間高用量で服用すると、銅だけでなく鉄やカルシウムなどの他のミネラル吸収にも影響が及ぶ可能性があるので注意が必要です。
ビタミンやミネラルバランスを崩さないように、定期的な血液検査を実施し、必要があればサプリメントなどを調整する場合があります。
ウィルソン病(Wilson病)の保険適用と治療費
以下に記載している治療費(医療費)は目安であり、実際の費用は症状や治療内容、保険適用否により大幅に上回ることがございます。当院では料金に関する以下説明の不備や相違について、一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。
治療薬の費用目安
キレート剤のうちD-ペニシラミンは比較的古くから使用されており、薬価がやや抑えられている傾向がありますが、用量や処方日数によって1か月あたり数千円から1万円台になることが多いようです。
トリエンチンは薬価が高めのことがあり、1か月あたり1万円台から2万円近くかかるケースもみられます。亜鉛製剤に関しても、用量や処方内容によって異なりますが、1か月あたり数千円程度の負担になる場合がみられます。
検査費用の目安
血液検査や尿検査は通常、1回数千円ほどかかることが多く、MRI検査は1回数千円から1万円以上することがあります。眼科検査の場合も数百円から数千円程度の自己負担で受けられることが一般的です。
頻度としては、肝機能や銅代謝の状況を確認するために3か月から6か月ごとに検査を行うケースが多いですが、病状が安定せずこまめなモニタリングが必要なときは、もう少し短いスパンで実施することもあります。
ウィルソン病に関連した主な治療費
| 項目 | 費用の目安(3割負担の場合) | 補足事項 |
|---|---|---|
| 血液・尿検査 | 1回数千円程度 | 頻度は3~6か月に1回が多い |
| MRI検査 | 1回数千円~1万円台 | 症状や医療機関によって変動 |
| キレート剤 | 1か月数千円~2万円前後 | 薬の種類・用量・日数による |
| 亜鉛製剤 | 1か月あたり数千円程度 | 用量や処方内容次第で変動 |
| 眼科検査 | 数百円~数千円 | スリットランプ使用 |
以上
参考文献
Yamaguchi H, Nagase H, Tokumoto S, Tomioka K, Nishiyama M, Takeda H, Ninchoji T, Nagano C, Iijima K, Nozu K. Prevalence of Wilson disease based on genome databases in Japan. Pediatrics International. 2021 Aug;63(8):918-22.
Saito T. Presenting symptoms and natural history of Wilson disease. European journal of pediatrics. 1987 May;146:261-5.
Nanji MS, Van Nguyen TT, Kawasoe JH, Inui K, Endo F, Nakajima T, Anezaki T, Cox DW. Haplotype and mutation analysis in Japanese patients with Wilson disease. The American Journal of Human Genetics. 1997 Jun 1;60(6):1423-9.
Takeyama Y, Yokoyama K, Takata K, Tanaka T, Sakurai K, Matsumoto T, Iwashita H, Ueda SI, Hirano G, Hanano T, Nakane H. Clinical features of Wilson disease: Analysis of 10 cases. Hepatology Research. 2010 Dec;40(12):1204-11.
Okada T, Shiono Y, Hayashi H, Satoh H, Sawada T, Suzuki A, Takeda Y, Yano M, Michitaka K, Onji M, Mabuchi H. Mutational analysis of ATP7B and genotype–phenotype correlation in Japanese with Wilson’s disease. Human mutation. 2000 May;15(5):454-62.
Shimizu N, Nakazono H, Takeshita Y, Ikeda C, Fujii H, Watanabe A, Yamaguchi Y, Hemmi H, Shimatake H, Aoki T. Molecular analysis and diagnosis in Japanese patients with Wilson’s disease. Pediatrics International. 1999 Aug;41(4):409-13.
Sandahl TD, Ott P. Epidemiology of Wilson disease. InWilson Disease 2019 Jan 1 (pp. 85-94). Academic Press.
Eda K, Mizuochi T, Iwama I, Inui A, Etani Y, Araki M, Hara S, Kumagai H, Hagiwara SI, Murayama K, Murakami J. Zinc monotherapy for young children with presymptomatic Wilson disease: A multicenter study in Japan. Journal of gastroenterology and hepatology. 2018 Jan;33(1):264-9.
Członkowska A, Litwin T, Dusek P, Ferenci P, Lutsenko S, Medici V, Rybakowski JK, Weiss KH, Schilsky ML. Wilson disease. Nature reviews Disease primers. 2018 Sep 6;4(1):21.
Gitlin JD. Wilson disease. Gastroenterology. 2003 Dec 1;125(6):1868-77.