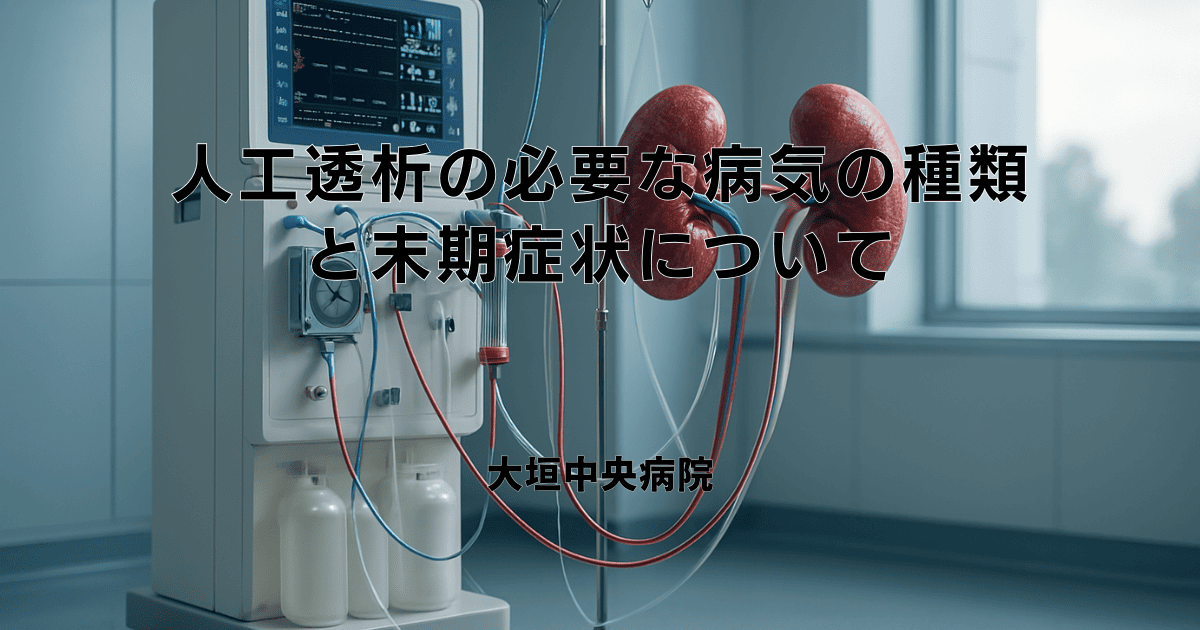腎臓は血液をろ過し、老廃物や水分バランスを調整する大変重要な器官です。腎臓の機能が低下すると、体内の老廃物排出がうまく進まず、全身にさまざまな悪影響が及びます。
特に腎機能が大幅に低下すると人工透析の必要な病気へ移行する場合があり、治療を受ける時期を判断するうえでも末期症状の特徴を知ることが大切です。
本記事では、腎機能低下の背景や主な要因、人工透析末期症状について詳しく解説し、適切な治療への第一歩を踏み出すための参考情報をご案内いたします。
腎臓の役割と腎機能低下のメカニズム
腎臓には血液から老廃物や余分な水分を取り除き、体内の水分量や電解質を調整する機能があります。これらの機能が損なわれると、体内に毒素が蓄積しやすくなり、さまざまな症状が出現します。
腎機能の低下は急激に進行する場合もあれば、長期間かけてゆっくり進む場合もあります。
腎臓が担う主な機能
腎臓は身体の恒常性を保つために、ろ過・再吸収・分泌といった複雑な働きをしています。特に血液中の老廃物排除だけでなく、ホルモンや酵素の産生にも関わり、骨の健康や血圧の調整にも寄与しています。
この臓器がうまく機能しなくなると老廃物が上手に排泄できず、むくみや血圧上昇など多彩な症状が見られます。
腎臓と老廃物の関係
| 種類 | 特徴 |
|---|---|
| 尿素 | タンパク質代謝の最終産物であり、腎臓が排泄を担う |
| クレアチニン | 筋肉由来の老廃物で、腎機能の指標として用いられる |
| 尿酸 | 核酸の代謝物で、高値になると痛風のリスクが高まる |
腎臓は上記のような老廃物を処理し、体外へ排出する役目を果たします。血液検査で尿素窒素やクレアチニンの上昇が顕著になると、腎機能の低下を疑う必要があります。
腎機能低下が起こる流れ
腎機能が落ちていく過程では、初期には自覚症状がほとんど見られない場合が多いです。腎臓は予備能と呼ばれる代償機能を持っているため、ある程度機能が損なわれても症状が目立ちません。
ただし、進行するにつれ以下のような状態が少しずつ起こります。
- むくみや疲労感が出やすくなる
- 体液バランスが崩れ血圧が上昇することがある
- 尿検査で蛋白尿や血尿が認められる場合がある
- 血液検査でクレアチニンや尿素窒素の値が上昇する
いずれも軽度の段階では見落とされやすいですが、着実に腎臓への負担が積み重なっている可能性があります。
透析導入に至る目安
慢性腎臓病の進行具合はGFR(糸球体ろ過量)などを指標にして判断します。通常、慢性腎不全の末期まで至るとGFRが15未満になることが多く、その状態では人工透析の必要な病気となる可能性が高いです。
GFR値と腎不全ステージ一覧
| ステージ | GFR値 (mL/min/1.73㎡) | 主な状態 |
|---|---|---|
| G1 | 90以上 | 腎機能正常または高め |
| G2 | 60~89 | 軽度低下 |
| G3a | 45~59 | 軽度~中等度低下 |
| G3b | 30~44 | 中等度~重度低下 |
| G4 | 15~29 | 重度低下 |
| G5 | 15未満 | 末期腎不全(人工透析を検討) |
人工透析導入の時期は症状や検査所見、全身状態を総合的に踏まえて決定します。血液検査や尿検査、身体所見などを組み合わせて評価し、適切な治療を始めることが大切です。
早期対策の重要性
腎機能低下は一度進んでしまうと完全に元の状態へ戻すことが難しいケースが多いです。したがって、できるだけ早期に異変を察知し、糖尿病や高血圧などの原疾患の管理を徹底することが必要です。
特に以下のような習慣を身につけると、腎機能を守るうえで役立ちます。
- 適度な運動を行い、血行を促す
- 塩分を控えめにし、血圧の上昇を抑える
- 定期的な血液検査や尿検査を継続する
十分な知識と意識を持って日常生活を送ると、人工透析の必要な病気への進行を遅らせる可能性が高まります。
人工透析の必要な病気の基本的な分類
腎機能が大幅に低下して人工透析の必要な病気として分類される代表例には、慢性腎臓病や糖尿病性腎症、高血圧性腎障害などが挙げられます。これらの病気にはそれぞれ進行過程に特徴があり、治療方針や予後も異なります。
慢性腎臓病と慢性腎不全
慢性腎臓病は、3か月以上にわたって腎機能障害や尿異常、画像所見などが持続した状態を指します。
その中でも、腎機能が著しく低下して末期腎不全に至ると、体内の老廃物を十分に排泄できなくなるため、人工透析を導入する必要が高まります。
慢性腎臓病の主な原因一覧
| 原因 | 具体例 |
|---|---|
| 糖尿病 | 糖尿病性腎症 |
| 高血圧 | 高血圧性腎硬化症 |
| 膠原病 | ループス腎炎など |
| 先天的障害 | 多発性嚢胞腎など |
慢性腎臓病は病期によって症状や治療法が大きく異なるため、専門医による定期的なチェックが重要となります。
糖尿病性腎症による影響
糖尿病が長年継続すると高血糖状態が続き、腎臓の微小血管が損傷を受けやすくなります。結果的にろ過機能が損なわれ、蛋白尿の増加やむくみなどの症状を引き起こしやすくなります。
さらに血糖コントロールが不十分な状態が長期化すると、慢性腎不全まで進行しやすく、人工透析の必要な病気に発展するケースも多いです。
高血圧性腎障害の特徴
高血圧が持続すると、腎臓の血管にも負担がかかります。血圧が高い状態が続くと血管壁が厚く・硬くなり、腎臓の血流が低下して機能を損ねる原因になります。
高血圧性腎障害は初期には症状がほとんど出ないため、定期的な血圧測定や検査が欠かせません。
高血圧に伴う腎ダメージの段階
| 段階 | 状況 |
|---|---|
| 1 | 血管壁のわずかな肥厚で自覚症状は乏しい |
| 2 | 尿検査で軽度の蛋白尿や血圧の持続上昇が確認される |
| 3 | 腎機能検査で明らかな低下が認められ、むくみなどが出現 |
| 4 | 人工透析を検討するレベルまで進行し、生活の質が低下 |
高血圧そのものを管理しつつ、生活習慣に着目した治療を継続することが必要です。
その他の病気
腎炎や多発性嚢胞腎、膠原病なども腎機能を低下させる原因になります。特に慢性的に炎症が続く病態は進行が徐々である反面、気づかぬうちに腎機能を蝕むことがあるため注意が必要です。
先天的な構造異常や薬剤性腎障害など、多彩な要因が腎不全を招く場合があります。
人工透析の必要な病気へのアプローチ
透析が必要になる手前で、可能なかぎり腎機能を維持・改善することが目標となります。そのためには日常生活の見直しや適切な投薬、定期検査の実施など多方面からのアプローチが欠かせません。
生活習慣の改善が果たす役割
腎機能が低下する大きな要因として、食事や運動などの生活習慣が挙げられます。特に食事制限が必要となるケースでは、管理栄養士などの専門家に相談しながら、塩分やタンパク質摂取量を見直すことが大切です。
食事と腎機能の関連
| 項目 | 意義 |
|---|---|
| 塩分 | 血圧を上昇させ腎臓に負荷を与えやすい |
| タンパク質 | 摂り過ぎると老廃物生成が増え腎臓の負担が増大 |
| カリウム | 摂取量に注意しないと高カリウム血症を起こしやすい |
| リン | 過剰摂取で血中リン濃度が上昇し、骨や血管に悪影響を及ぼす |
適切な範囲での食事管理や運動習慣の確立が、腎機能悪化の抑制に寄与すると考えられます。
投薬と管理のポイント
血圧をコントロールする薬や利尿薬、糖尿病治療薬など、原因疾患に合わせた投薬を行います。医師の指示通りに服薬を継続すると同時に、副作用や相互作用に注意しながら定期的な血液検査を受けることが大切です。
薬の調整は専門家の判断が必須となるため、自己判断で中断や変更をしないよう心がけます。
血液透析と腹膜透析の違い
腎不全が末期に達した際、人工透析を導入する方法には血液透析と腹膜透析があります。血液透析は血管にシャントと呼ばれる血液の出入り口を作り、透析装置を用いて血液をろ過する方法です。
一方、腹膜透析はお腹の中にある腹膜を用いて老廃物を除去する方法となります。
透析導入による体内の変化
| 方法 | 特徴 | 生活面への影響 |
|---|---|---|
| 血液透析 | 週に複数回通院して血液をろ過 | 通院時間がかかるが管理は医療者と連携しやすい |
| 腹膜透析 | 腹膜に透析液を注入して体内でろ過 | 自宅で行えるが管理や衛生面に注意が必要 |
いずれも長期療法として欠かせない手段であり、患者さんのライフスタイルや合併症の有無によって選択が変わります。
定期的な検査の大切さ
腎機能は長期間にわたって少しずつ低下する場合が多いため、早期発見には定期的な検査が大事です。
血液検査でのクレアチニンや尿素窒素の測定、尿検査での蛋白や潜血の確認などを定期的に行い、問題が見つかったときにはすぐに医療機関を受診することを推奨します。
透析導入を検討する段階の症状
腎不全の末期になる前から、体には少しずつ変化が見られます。症状を見過ごさずに適切な対策を始めると、透析開始時期を遅らせる可能性があります。
むくみと疲労感
腎機能が低下すると体内の水分調整がうまくいかなくなり、下肢や顔のむくみが目立ちます。それに伴って倦怠感が増し、日常生活で疲れやすくなる場合も多いです。
むくみを感じやすい部位
| 部位 | 状態 |
|---|---|
| 足首 | 靴下のゴム痕がなかなか消えない |
| ふくらはぎ | 押すとへこみがしばらく残る |
| 顔 | 朝起きたときにまぶたの腫れが強い |
疲労感は仕事や家事など、普段何気なく行っている活動に支障をきたす恐れがあります。
尿量と排泄機能の変化
腎臓がろ過する力が低下すると尿量が減少したり、逆に夜間に頻繁にトイレに行く多尿状態になることがあります。排泄機能の乱れは体内の老廃物が滞留するサインでもあるため、ふだんの尿量や色の変化に注目すると早期発見につながります。
倦怠感と貧血
腎臓は赤血球をつくるために必要なエリスロポエチンと呼ばれるホルモンを分泌しています。腎機能が低下するとこのホルモンの分泌量が減り、貧血を起こしやすくなります。
貧血が進むと全身のだるさや動悸、息切れなどが顕著になる場合があります。
腎性貧血の症状
| 症状 | 主な理由 |
|---|---|
| 動悸や息切れ | 酸素運搬能力の低下 |
| 顔色不良 | ヘモグロビン濃度の低下 |
| 疲れやすい | 全身への酸素供給不足 |
倦怠感や貧血症状が続くと体の疲労が慢性化し、栄養状態も悪化する恐れがあります。
食欲不振や吐き気
老廃物が血液中に蓄積すると消化器系にも影響が及び、食欲不振や吐き気を誘発します。食事量が減るとさらに体力低下や免疫力低下を招き、腎機能の悪化を加速させる負の連鎖に陥りやすくなります。
食欲不振が長期化すると栄養不良が進行し、体力を著しく損なう要因となります。
人工透析末期症状とは何か
腎不全が限界に近づくと老廃物や水分が十分に排出できなくなり、命を危険にさらす症状が発現することがあります。人工透析末期症状は身体の多方面に深刻な変調をもたらし、生活の質にも大きな影響を及ぼします。
末期症状の定義と背景
末期腎不全は、腎機能が著しく損なわれGFR値が15未満になった状態を指すことが多いです。この段階では血中の尿素窒素やクレアチニンの値が非常に高くなり、多くの老廃物が蓄積します。
人工透析を導入しないと、尿毒症や重度の電解質異常などにつながりやすいです。
尿毒症による合併症
腎臓が老廃物をろ過できないため、血液中に毒素が増えてさまざまな合併症を発症しやすくなります。代表的な症状には、意識障害や神経障害、皮膚のかゆみなどがあります。
高齢者や他の慢性疾患を持つ方は、免疫力低下や心不全リスクの増大などにも気を配らなければなりません。
尿毒症に伴う症状
| 症状 | 具体的な影響 |
|---|---|
| 皮膚のかゆみ | 老廃物が体内に蓄積し皮膚刺激を起こす |
| 口臭・呼気のアンモニア臭 | 血中尿素窒素が高濃度になりやすい |
| 不眠・集中力低下 | 毒素が神経系に影響しやすい |
尿毒症が進行すると意識障害に至る危険もあるため、早急な対応が求められます。
重度の電解質異常
腎臓は電解質バランスを調整する主要な臓器の1つです。特にカリウムやナトリウム、リンの調節が不十分になると、心臓や骨、神経系に深刻な影響が及びます。
高カリウム血症は不整脈や心停止のリスクを高めるため、非常に注意が必要です。
透析治療の限界点
人工透析を継続しても、血管状態や心臓の機能、合併症の進行度によっては治療そのものが困難になる場合もあります。
そうした場合でも、症状を和らげるために血液透析の回数や透析時間を再調整したり、腹膜透析を検討したりと、多角的な視点から対策を講じることが大切です。
人工透析中の注意事項とセルフケア
人工透析を導入した後も、生活習慣の見直しや体調管理が必要となります。合併症のリスクを抑えつつ、透析を受けながら安定した日常生活を維持するためにはポイントを押さえたセルフケアが重要です。
食事療法のポイント
透析中は老廃物や余分な水分を機器で除去するものの、食事内容によっては負担が大きくなる場合があります。特にタンパク質や塩分、カリウム、リンなどの摂取量には気を配り、腎臓や心臓に過度な負担をかけないよう心がけます。
食事で意識したい項目
- 塩分は1日あたり6g未満を目指す
- 高カリウム食(バナナ・メロン・芋類など)に注意
- 適度なエネルギーを確保し、栄養バランスを整える
- リン制限のために加工食品を過度に摂取しない
自分の身体状況に応じた制限内容を把握し、管理栄養士などの指導を受けると安心です。
運動のメリットと適切な方法
適度な運動は血行を促し、心肺機能を維持するうえで役立ちます。しかし、透析中や透析直後は体力が落ちていることが多いため、無理のない範囲でウォーキングや軽い体操などから始めるとよいでしょう。
激しい運動によって血圧が急激に変動する恐れもあるため、自分の体調や主治医の意見を考慮しながら実施することが望ましいです。
透析日常生活での工夫
透析は通常週に複数回行うため、通院や施設での待ち時間を含めて生活リズムに組み込む必要があります。天候不良や体調不良などで通院が難しい場合には、主治医や看護師へ早めに相談しましょう。
また、通院時に必要な持ち物をまとめておくなどの準備を整えると、急な体調変化にも対応しやすくなります。
透析生活を快適にするためのヒント
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 通院スケジュールの管理 | カレンダーやアプリを活用して忘れを防ぐ |
| 水分コントロール | 透析間の体重増加が大きくならないよう調整 |
| 体調記録 | 血圧や症状を定期的に書き留め医療者と共有 |
このような具体策を習慣化すると、透析生活に対する負担が軽減される可能性があります。
合併症予防のための受診
人工透析患者は心臓病や感染症、骨代謝異常など合併症が起こりやすいと言われています。定期的に内科や循環器科などを受診し、必要な検査を実施することでリスクを軽減できます。
医師や看護師など、医療者との連携を密にすることが早期発見・早期対応へつながるでしょう。
人工透析の必要な病気と向き合うためのサポート
重い腎不全と診断され、人工透析が必要となる事態は患者さんやそのご家族にとって心理的負担が大きいです。医療チームや社会的支援を活用しながら、長期療養に向けて現実的な対策を講じることが不可欠です。
チーム医療の大切さ
腎臓内科医や看護師、管理栄養士、薬剤師、リハビリ専門職など、複数の専門家が連携して患者さんを支える体制が求められます。各分野の専門家が情報共有を綿密に行うことで、きめ細かい治療とケアを提供できます。
患者さん自身が抱える疑問や不安を相談しやすい環境づくりも重要です。
心理面のケアと支援
長期的に透析を続けることで、孤立感や鬱状態を引き起こすケースがあります。体調だけでなく、心のケアも大切です。
医療機関によっては、臨床心理士やソーシャルワーカーが相談窓口を設け、必要に応じてカウンセリングを行う体制を整えています。本人だけで抱え込まず、専門家や家族とコミュニケーションを図ることを心がけます。
心のケアで意識したいこと
- 周囲に遠慮せずに悩みを共有する
- 趣味や楽しみを見つけ、気分転換を図る
- 自己評価を過度に下げすぎないよう意識する
心理的なサポートが得られると、治療意欲やQOL(生活の質)を維持しやすくなるでしょう。
社会保障や福祉制度の概要
透析治療は医療費が高額になりやすいため、健康保険や高額療養費制度、自立支援医療などを活用して経済的負担を軽減することが考えられます。
障害年金や生活保護などの制度が適用できる場合もあるため、ソーシャルワーカーや行政機関と連携しながら情報を収集するとよいでしょう。
自己管理と受診継続
透析が始まっても、日常生活の中で血圧や体重の管理など自己管理を徹底し、医療機関を定期的に受診する姿勢が重要です。
治療の効果や合併症の有無をチェックしながら調整を行い、体調の変化を早めに医療チームへ伝えると、重症化を防ぐ可能性が高まります。
よくある質問
腎不全が進行し、人工透析の必要な病気と診断された段階で疑問点は多岐にわたります。下記の事柄に対して、事前に理解を深めると安心して治療を受けやすくなります。
- 血液透析と腹膜透析の選択に迷う場合
-
血液透析は医療機関で専門スタッフの管理を受けながら行うため、万が一のトラブルにもすぐ対応できます。一方、腹膜透析は自宅で行えるため通院頻度を減らせる利点があります。
自分の生活リズムや家庭環境を考慮し、医師と相談して選択するとよいでしょう。
- 治療開始の時期に関する目安
-
血液検査の結果や自覚症状、全身状態から総合的に判断します。GFRが15を下回るようになると人工透析を視野に入れることが多いです。
ただし、症状の進行速度には個人差があるため、医療者と話し合いながら決めると安心です。
- 費用や保険制度について
-
透析は長期治療になりやすく、医療費が高額となるケースがよく見られます。ただし、社会保障制度や高額療養費制度、障害年金などを利用すると負担が軽減されることがあります。
主治医やソーシャルワーカーに相談して、活用可能な制度をチェックすることをおすすめします。
- 透析中に生じやすい不安
-
透析時間の長さや通院頻度、治療に伴う体調変化への不安が代表的です。また、家族や周囲への気兼ねや、仕事との両立など精神的な問題も生じやすいです。
こうした不安は医療スタッフや患者仲間と情報交換することで軽減できることがあります。治療だけでなく精神面でのサポート体制も重視してください。
以上
透析センター(人工透析) | 大垣中央病院(医療法人社団豊正会 )
参考文献
MURTAGH, Fliss EM; ADDINGTON-HALL, Julia; HIGGINSON, Irene J. The prevalence of symptoms in end-stage renal disease: a systematic review. Advances in chronic kidney disease, 2007, 14.1: 82-99.
AGARWAL, Rajiv. Defining end-stage renal disease in clinical trials: a framework for adjudication. Nephrology Dialysis Transplantation, 2016, 31.6: 864-867.
CHEN, Titi; LEE, Vincent WS; HARRIS, David C. When to initiate dialysis for end‐stage kidney disease: Evidence and challenges. Medical Journal of Australia, 2018, 209.6: 275-279.
ABBASI, Maaz Ahmed; CHERTOW, Glenn M.; HALL, Yoshio N. End-stage renal disease. BMJ clinical evidence, 2010, 2010: 2002.
WOUK, Noah. End-stage renal disease: medical management. American family physician, 2021, 104.5: 493-499.
WEBSTER, Angela C., et al. Chronic kidney disease. The lancet, 2017, 389.10075: 1238-1252.
COBO, Gabriela; LINDHOLM, Bengt; STENVINKEL, Peter. Chronic inflammation in end-stage renal disease and dialysis. Nephrology Dialysis Transplantation, 2018, 33.suppl_3: iii35-iii40.
CHEN, Teresa K.; KNICELY, Daphne H.; GRAMS, Morgan E. Chronic kidney disease diagnosis and management: a review. Jama, 2019, 322.13: 1294-1304.
AMMIRATI, Adriano Luiz. Chronic kidney disease. Revista da Associação Médica Brasileira, 2020, 66.Suppl 1: s03-s09.
PAGELS, Agneta A., et al. Health-related quality of life in different stages of chronic kidney disease and at initiation of dialysis treatment. Health and quality of life outcomes, 2012, 10: 1-11.