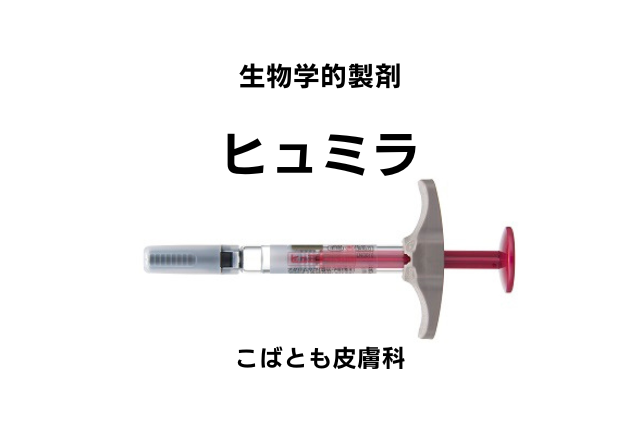アダリムマブ(ヒュミラ)とは、自己免疫が過剰に働いて炎症を起こす病気に用いる生物学的製剤で、皮膚科領域では尋常性乾癬や膿疱性乾癬などの治療に役立ち、炎症物質であるTNF-αを抑えて症状の改善を目指します。
治療効果が期待できる一方で注射による自己注射の負担や副作用の可能性もあるため、医師と相談しながら正しい使い方を理解することが重要です。
本記事では、アダリムマブ(ヒュミラ)の副作用、効果が得られなかった場合の対応、他の治療薬との組み合わせ、などを詳しく解説します。
この記事の執筆者

小林 智子(こばやし ともこ)
日本皮膚科学会認定皮膚科専門医・医学博士
こばとも皮膚科院長
2010年に日本医科大学卒業後、名古屋大学医学部皮膚科入局。同大学大学院博士課程修了後、アメリカノースウェスタン大学にて、ポストマスターフェローとして臨床研究に従事。帰国後、同志社大学生命医科学部アンチエイジングリサーチセンターにて、糖化と肌について研究を行う。専門は一般皮膚科、アレルギー、抗加齢、美容皮膚科。雑誌を中心にメディアにも多数出演。著書に『皮膚科医が実践している 極上肌のつくり方』(彩図社)など。
こばとも皮膚科関連医療機関
アダリムマブ(ヒュミラ)の有効成分と効果、作用機序
アダリムマブ(ヒュミラ)はTNF-αと呼ばれる炎症性サイトカインを抑える働きを持つヒト型モノクローナル抗体製剤です。
皮膚の赤みや腫れ、かゆみを含む様々な炎症症状を和らげる効果が期待され、慢性的な炎症トラブルを抱える患者さんにとって大切な治療選択肢の一つになっています。
アダリムマブが注目するTNF-αとは
TNF-α(Tumor Necrosis Factor-α)は、体内の炎症を引き起こす主要なサイトカインの1つです。過剰に産生されると、皮膚や関節などに強い炎症反応が起き、乾癬やリウマチといった自己免疫疾患の症状が進行しやすくなります。
TNF-αを直接ブロックすることで目指す改善
- 発疹や紅斑の広がりを抑える
- 痛みやかゆみの程度を軽減する
- 炎症が進むことで起こる皮膚の厚みや鱗屑を改善する
TNF-αは健康維持にも必要な因子ですが、過剰に活動すると慢性的な炎症を起こし、アダリムマブはこの部分をピンポイントで狙うため、従来の薬剤より選択的に炎症を抑えやすいことが特徴です。
抗体製剤の働き
アダリムマブはヒト型モノクローナル抗体製剤に分類され、これは実験室で作られたヒト抗体のコピーのようなもので、体内でTNF-αと結合して作用を抑制する仕組みです。
注射によって投与されると血液中を巡回しながらTNF-αを探し出し、結合して無力化を図ります。
- 既存の炎症反応を穏やかにする
- 新たな炎症を引き起こす連鎖反応を断ち切る
- 皮膚症状を安定させて生活の質を向上させる
抗体製剤は特異性が高い反面、投与タイミングや保管方法など細かな管理が必要です。
皮膚症状への具体的な効果
アダリムマブは尋常性乾癬や関節症性乾癬、膿疱性乾癬などの炎症性皮膚疾患に広く用いられ、特に乾癬では赤い発疹や厚い鱗屑(りんせつ)が改善するケースが多く報告され、効果の発現スピードも比較的早い傾向があります。
アダリムマブ使用後に期待できる皮膚改善
| 改善ポイント | 内容の例 |
|---|---|
| 発疹の軽減 | 赤みが減少し、鱗屑が少なくなる |
| かゆみの軽減 | 患部のかゆみが緩和し、生活の質が上がる |
| 拡大の抑制 | 新たな発疹の出現を抑え、既存の病変を小さくする |
| 関節症状の抑制 | 関節の腫れや痛みを軽減し、可動域を保ちやすくする |
継続的な治療の意義
アダリムマブは炎症を抑える強い作用を持ちますが、継続的に使わないと症状がぶり返すことがあり、治療継続の上で以下の点が大切です。
- 炎症を完治させるのではなく、できるだけ抑え込むことを目指す
- 定期的に皮膚科を受診して症状変化を確認する
- 必要に応じて投与間隔や投与量の調整を受ける
十分な効果を得るためには、決められた用量やスケジュールを守りましょう。
使用方法と注意点
アダリムマブ(ヒュミラ)は皮下注射で使用します。使用方法や保管方法に注意が必要で、治療を円滑に進めるためには正しい手順やスケジュール管理が大切です。ここでは、自己注射の流れや保管時のポイントなどを詳しく紹介します。
自己注射の基本手順
医師は患者さんの生活状況に合わせて、自己注射による治療を提案する場合があり、患者さん自身が注射を行うことで通院回数を減らし、負担を軽減できるメリットがあります。
自己注射の流れ
- 手指をしっかり洗浄して清潔に保つ
- 注射部位(お腹や太ももなど)の皮膚をアルコール綿で消毒する
- ペン型やシリンジ型のアダリムマブを、医師の指示どおりの角度で皮下注射する
- 注射後、止血用のガーゼなどで軽くおさえて様子を確認する
慣れるまで不安を感じるかもしれませんが、医療スタッフが手順を詳しく説明しますので、わからない点はその都度確認してください。
保管温度の重要性
アダリムマブは生物学的製剤のため、保管温度に注意が必要で、冷蔵庫(2℃〜8℃)で保管しなければなりません。高温や直射日光を避けることはもちろん、冷凍も避けることが望ましいです。
保管にあたって注意したいポイント
| 注意ポイント | 内容 |
|---|---|
| 温度管理 | 原則として2〜8℃の冷蔵庫に保管する |
| 冷凍の回避 | 凍結すると薬の効果が弱まる可能性がある |
| 開封後の使用目安 | 使用直前まで冷蔵庫に入れ、取り出したらすぐに打つ |
| 持ち運びの際 | クーラーバッグなどを利用し、温度変化を最小限に抑える |
アダリムマブの効果を十分に引き出すためには、正しい温度帯での保管が大切で、庫内奥の安定した場所に保管するとよいでしょう。
注射部位とローテーション
同じ部位に連続して注射すると、皮膚が硬くなったり炎症を起こしたりしやすくなりるので、患者さんは部位をローテーションしながら注射することで、皮膚ダメージを緩和できます。
- 腹部の左右
- 太ももの外側
- 上腕部の外側(自己注射が難しい場合は医療従事者に依頼するケースもある)
特定の部位だけに偏らないようにする工夫が必要です。
日常生活で意識したい点
アダリムマブを使用中は、注射のタイミングや皮膚のコンディションなど、細かい点に気を配ることが重要です。
気を付ける生活習慣
- 注射前後はアルコール類の摂取を控えめにする
- 体調に変化を感じたら、早めに医師に相談する
- 感染症状(発熱・倦怠感など)が出た場合は使用を中断するか医師に確認する
- 定期的に血液検査などを受け、内臓機能や免疫バランスを確認する
これらを守ることで、安全かつ効果的に治療を進めやすくなります。
適応対象となる患者さん
アダリムマブ(ヒュミラ)は尋常性乾癬や膿疱性乾癬といった皮膚疾患だけでなく、リウマチやクローン病、潰瘍性大腸炎など幅広い自己免疫疾患にも用いられます。
対象となりやすい皮膚疾患
皮膚科クリニックでアダリムマブを検討する場合、以下のような疾患を抱える方に選択されやすいです。
- 尋常性乾癬(かんせん)
- 膿疱性乾癬
- 関節症性乾癬
- 重症のアトピー性皮膚炎(ただし、適応症例は医師が判断)
このような疾患は炎症が長期化しているケースが多いので、従来の外用薬や内服薬だけでは十分な効果が得られにくい場合があり、アダリムマブで症状のコントロールを狙うことで、生活の質を向上しやすくなります。
病歴や既往症との関係
医師はアダリムマブを処方するにあたって、患者さんの病歴や既往症を慎重に確認し、肺結核や肝炎ウイルスなどの既感染歴がある方は注意が必要で、再燃を防ぐために投与前に検査を実施します。
考慮する要因
- 結核や肝炎ウイルスへの感染リスク
- 中枢神経疾患や悪性腫瘍の有無
- 免疫力が低下するほかの薬剤使用状況
- 過去の薬物療法や効果の有無
病歴や既往症によっては、他の治療薬との併用や投与スケジュールを調整することがあります。
主な注意点
| チェック項目 | 具体的な内容 |
|---|---|
| 感染症の既往 | 結核・B型肝炎・C型肝炎の検査結果など |
| 中枢神経系の疾患 | 多発性硬化症や神経性の難病の有無 |
| 悪性腫瘍の既往 | がん治療歴や現在の経過観察の状況 |
| 他の生物学的製剤 | 他の抗TNF-α製剤やIL-17阻害薬の使用歴 |
重症度と治療の優先度
乾癬は軽度の場合、外用薬や光線療法などで十分にコントロールできることがあり、アダリムマブは中度から重度の乾癬、あるいは関節症を伴う乾癬など、症状が強く日常生活に支障が大きい方を中心に検討されます。
医師はPASIスコア(乾癬の重症度を評価する指標)などを参考にしながら、アダリムマブの開始を判断します。診察時に希望や不安をしっかり伝えることで、より納得感のある治療選択につながります。
アダリムマブ(ヒュミラ)の治療期間
アダリムマブ(ヒュミラ)は炎症を抑えることに特化した薬剤ですが、治療期間は患者さんの症状や体質によって大きく異なり、短期間で劇的に改善する人もいれば、長期的に使用して安定状態を保つケースもあります。
治療開始時期と初期反応
医師は症状の重症度が高いと判断した場合、できるだけ早い段階でアダリムマブを導入することがあります。初期のうちは、効き目の様子を観察しながら投与間隔の設定や他の薬剤との組み合わせを検討することが大切です。
アダリムマブの投与スケジュール(乾癬の場合)
| 投与週数 | 投与の目安 |
|---|---|
| 第0週 | 1回目の投与(医療機関で開始) |
| 第1週 | 2回目の投与 |
| 第2週以降 | 2週ごとの投与(自己注射または通院) |
早い人では2週〜4週ほどで症状の軽減を実感する場合もあり、赤みが薄くなったり鱗屑が剥がれやすくなったりすると報告されています。ただし、効果の出方には個人差があるため、焦らずに経過を追うことが大切です。
中長期的な継続治療
慢性的な乾癬や膿疱性乾癬では、症状が落ち着いても再燃するリスクがあるため、ある程度の期間にわたって定期的にアダリムマブを使用し、炎症をコントロールすることが多いです。
治療の継続が検討される場面
- 症状が改善しているかどうか
- 副作用や感染症のリスクはコントロールできているか
- 他の治療薬や日常生活の工夫とのバランス
医師と相談しながら投与スケジュールを調整し、段階的に投与間隔を伸ばすこともあれば、症状がぶり返しそうな気配があれば早めに再度投与を行うこともあります。
治療終了のタイミング
アダリムマブの使用を完全に終わりにするかどうかは、症状の程度やリスク評価によって決まり、軽快した状態が長期間続き、再燃の兆しが見られなければ治療を中止することも可能です。
ただし、自己判断で中止すると急に症状が悪化するケースがあります。医師の指示なしに投与を止めるのは避けましょう。
治療の終了や継続の目安
- 連続して数か月以上、皮膚症状が安定している
- 血液検査の炎症反応や免疫バランスに大きな異常がない
- 社会生活を問題なく営めている状態が続いている
医師は上記を参考にしつつ、患者さんの希望も踏まえて最終的な判断を行います。
アダリムマブ(ヒュミラ)の副作用やデメリット
アダリムマブ(ヒュミラ)は高い炎症抑制効果がある一方で、他の薬剤と同様に副作用やデメリットがあります。ここでは、代表的な副作用や対処法、治療の継続を検討するうえで注意すべきリスクについて解説します。
感染症リスクの増加
アダリムマブはTNF-αを抑えることで炎症を和らげますが、同時に免疫機能が低下しやすくなり、感染症にかかりやすくなる可能性が指摘されています。特に結核や肺炎など、重症化のリスクが高い感染症には注意が必要です。
免疫低下による感染症のリスク
| 感染症の例 | 注意ポイント |
|---|---|
| 結核 | 潜在性結核を発症させるリスクがある |
| 肺炎 | 呼吸器系の症状が出たらすぐ受診が望ましい |
| 帯状疱疹 | ヘルペスウイルスが再活性化しやすくなる |
| 日和見感染症 | 免疫が弱った状態でかかる特殊な感染症 |
このような感染症を予防するために、医師は投与前に結核や肝炎ウイルスの有無をチェックし、使用中も定期的に血液検査などを行います。体調に不安を感じたときは放置せず、早めに受診することが大切です。
アレルギー反応
薬物アレルギーによって、発疹やかゆみ、重症例ではアナフィラキシーショックなどを起こす可能性があります。アダリムマブによる重度のアレルギーは稀とされますが、症状が出た場合はすぐに医療機関を受診することが重要です。
注意が必要な症状
- 全身の発疹や強いかゆみ
- 呼吸困難、のどの腫れ
- めまい、意識の混濁
重いアレルギーが疑われる場合は、別の治療薬への切り替えも選択肢になります。
アダリムマブ(ヒュミラ)で効果がなかった場合
アダリムマブ(ヒュミラ)を使用しても個人差や疾患の性質により、期待通りに症状が改善しなかったり、途中で効果が頭打ちになってしまったりする場合があります。
効果不足の原因を探る
効果が得られない場合、医師は以下のポイントをチェックしながら原因を探ります。
- 投与スケジュールや用量は適切か
- ほかの要因(別の感染症やホルモンバランス)が影響していないか
- 長期使用で抗体ができ、薬の作用が減弱していないか
詳しい血液検査や画像検査、他の専門科との連携などを通じて原因を特定し、対策を立てることが大切です。
他の生物学的製剤への切り替え
TNF-α阻害薬はアダリムマブ以外にもいくつかあり、IL-17やIL-23などをターゲットとする新しい治療薬も複数あります。効果が見られない場合や、副作用で継続が難しい場合は、別の生物学的製剤への切り替えを検討します。
切り替えにあたっては次の表のように、ターゲットとなる炎症分子や投与頻度、効果の持続期間などを比較することがあります。
| 製剤の種類 | ターゲット | 投与頻度 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 抗TNF-α製剤 | TNF-α | 2週~4週 | 炎症抑制効果が高い |
| 抗IL-17製剤 | IL-17 | 2週~4週 | 乾癬患者に有効性が高い |
| 抗IL-23製剤 | IL-23 | 4週~12週 | 投与間隔が長めの場合もある |
併用療法の検討
外用薬や光線療法、内服薬との併用によって効果を高める方法もあり、単独では十分な結果を得られなかった場合に、皮膚の状態をトータルで改善するために複数の治療を組み合わせることが選択肢になります。
医師と相談しながら、できるだけ負担が少なく効果が見込める方法を模索していくことが重要です。
他の治療薬との併用禁忌
アダリムマブ(ヒュミラ)は強力な免疫抑制作用を持つため、他の治療薬と併用すると副作用や重複効果によるリスクが高まる可能性があります。
他の生物学的製剤との重複使用
他の抗TNF-α製剤や抗IL-17製剤、抗IL-23製剤などを同時に使用することは推奨されていません。効果が強くなりすぎるだけでなく、感染症などの副作用リスクも高まります。
重複投与を避けたい主な製剤
- インフリキシマブ(抗TNF-α)
- エタネルセプト(抗TNF-α)
- セクキヌマブ(抗IL-17)
- イキセキズマブ(抗IL-17)
併用は原則として行わず、効果が不十分な場合には先に使用していた生物学的製剤を中止し、十分な休薬期間を置いてから新しい製剤に切り替えます。
免疫抑制薬との併用
ステロイド薬や免疫抑制薬(メトトレキサートなど)を用いている患者さんがアダリムマブを追加するケースはありますが、用量や使用期間には注意が必要です。
過度な免疫抑制状態になると感染症のリスクが一気に高まるため、医師は血液検査や問診で安全性を確認しながら併用の可否を判断します。
主な併用療法
| 併用療法 | メリット | リスク |
|---|---|---|
| アダリムマブ+ステロイド | 急性増悪時の症状コントロールが速い | 免疫低下や副作用の増強に注意 |
| アダリムマブ+メトトレキサート | 慢性期の炎症制御に相乗効果が期待できる | 肝障害や血液異常に注意が必要 |
ワクチン接種とのタイミング
生ワクチン(BCGや麻疹など)の接種とアダリムマブの併用には注意が必要で、免疫が抑えられている状態で生ワクチンを接種すると、感染症のリスクが高まる可能性があります。
死菌や不活化ワクチンの場合でも、副反応が出やすくなるので、ワクチンを受ける計画があるときは、事前に医師に相談しましょう。
服用中のサプリメント
健康サプリメントや漢方薬なども、身体に何らかの影響を与えている可能性があります。重大な相互作用を引き起こす例は少ないとされますが、念のため医師にはサプリメントの種類を伝え、問題の有無を確認しておくことが安心です。
アダリムマブ(ヒュミラ)の保険適用と薬価について
以下に記載している治療費(医療費)は目安であり、実際の費用は症状や治療内容、保険適用否により大幅に上回ることがございます。当院では料金に関する以下説明の不備や相違について、一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。
保険適用の範囲
尋常性乾癬、膿疱性乾癬、関節症性乾癬などの重症度が一定以上と認められる場合、アダリムマブは健康保険の適用対象になり、保険適用の可否は医師の診断と保険の審査基準に基づき決定します。
- 乾癬の重症度(PASIスコアなど)
- 既存の治療が無効または効果不十分な事実
- 他の治療手段ではコントロールが困難と判断
クリニックで診察を受け、医師と相談することで保険適用の対象かどうかが明確になります。
薬価と自己負担額
アダリムマブ(ヒュミラ)の薬価は種類や製剤量によって異なりますが、一例として「ヒュミラ皮下注40mgペン1本あたり約94,640円」という価格設定がされています(時期や改定により変動)。
| 自己負担割合 | 1本あたりの自己負担額 | 2本使用時の自己負担額 |
|---|---|---|
| 3割負担 | 約28,392円 | 約56,784円 |
| 2割負担 | 約18,928円 | 約37,856円 |
| 1割負担 | 約9,464円 | 約18,928円 |
通常、乾癬治療では2週ごとの注射が標準的で、月に2回の注射を行うと、3割負担の方は1か月あたり56,000円前後の負担です。
高額療養費制度の活用
アダリムマブは高額医療の部類に入るため、所定の条件を満たせば高額療養費制度を適用できます。自己負担額が一定の上限を超えた場合、超過分が払い戻される制度です。
所得や年齢によって上限額が異なるため、加入している健康保険組合や市町村窓口で詳しい情報を入手しましょう。
以上
参考文献
Traczewski P, Rudnicka L. Adalimumab in dermatology. British journal of clinical pharmacology. 2008 Nov;66(5):618-25.
Scheinfeld N. Adalimumab (HumiraTM): a brief review for dermatologists. Journal of dermatological treatment. 2004 Jan 1;15(6):348-52.
Graves JE, Nunley K, Heffernan MP. Off-label uses of biologics in dermatology: rituximab, omalizumab, infliximab, etanercept, adalimumab, efalizumab, and alefacept (part 2 of 2). Journal of the American Academy of Dermatology. 2007 Jan 1;56(1):e55-79.
Patel T, Gordon KB. Adalimumab: efficacy and safety in psoriasis and rheumatoid arthritis. Dermatologic therapy. 2004 Oct;17(5):427-31.
Alexis AF, Strober BE. Off-label dermatologic uses of anti-TNF-a therapies. Journal of cutaneous medicine and surgery. 2005 Dec;9:296-302.
Blanco R, Martínez-Taboada VM, Villa I, González-Vela MC, Fernández-Llaca H, Agudo M, González-López MA. Long-term successful adalimumab therapy in severe hidradenitis suppurativa. Archives of dermatology. 2009 May 1;145(5):580-4.
Kerbleski JF, Gottlieb AB. Dermatological complications and safety of anti-TNF treatments. Gut. 2009 Aug 1;58(8):1033-9.
Strober B, Crowley J, Langley RG, Gordon K, Menter A, Leonardi C, Arikan D, Valdecantos WC. Systematic review of the real‐world evidence of adalimumab safety in psoriasis registries. Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology. 2018 Dec;32(12):2126-33.
Kim ES, Garnock-Jones KP, Keam SJ. Adalimumab: a review in hidradenitis suppurativa. American journal of clinical dermatology. 2016 Oct;17(5):545-52.
Yiu ZZ, Mason KJ, Hampton PJ, Reynolds NJ, Smith CH, Lunt M, Griffiths CE, Warren RB, BADBIR Study Group. Drug survival of adalimumab, ustekinumab and secukinumab in patients with psoriasis: a prospective cohort study from the British Association of Dermatologists Biologics and Immunomodulators Register (BADBIR). British Journal of Dermatology. 2020 Aug 1;183(2):294-302.