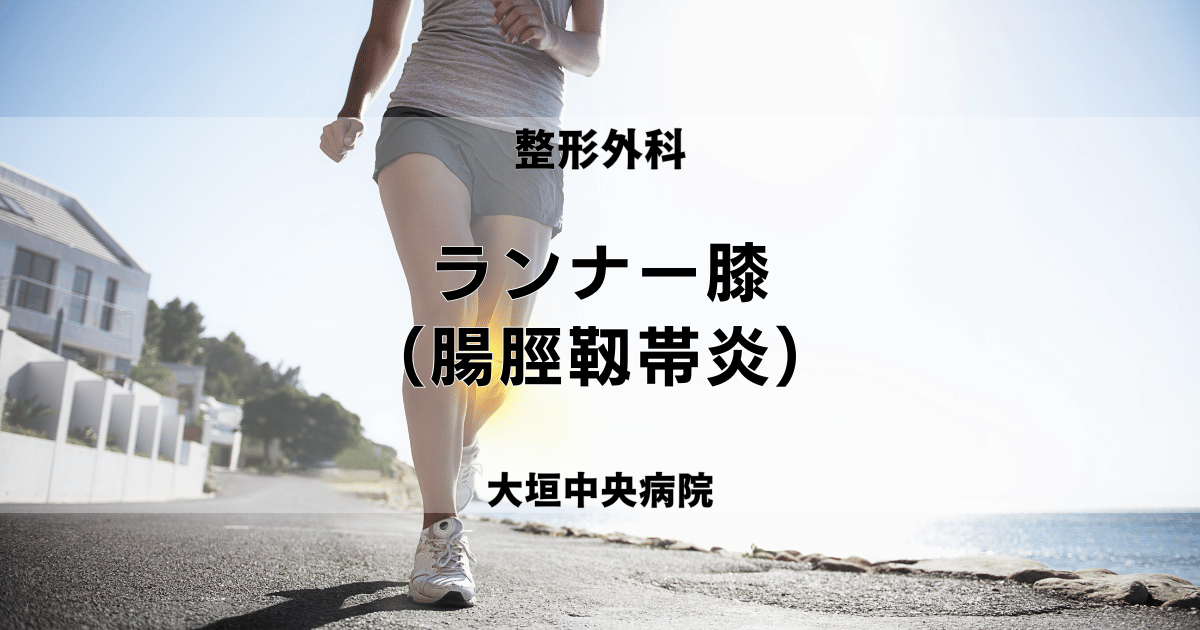ランナー膝(腸脛靱帯炎)(Iliotibial Band Syndrome:ITBS, Runner’s Knee)とは、ランニングやウォーキングなどの膝を反復して動かす運動で生じやすい、膝外側に痛みが生じるオーバーユース障害の総称です。
腸脛靱帯という太ももの外側を走る組織が、膝の外側の骨と摩擦を起こして炎症や痛みが発生します。運動を始めたばかりの方から長距離走を続けている方まで、幅広いランナーが悩まされやすい症状です。
腸脛靱帯炎だけで、ランニング障害全体の約10%を占めるというデータもあります。
放置すると痛みでトレーニングが中断してしまうケースもあるため、原因や対策を早めに知ることが大切です。
この記事の執筆者

臼井 大記(うすい だいき)
日本整形外科学会認定専門医
医療社団法人豊正会大垣中央病院 整形外科・麻酔科 担当医師
2009年に帝京大学医学部医学科卒業後、厚生中央病院に勤務。東京医大病院麻酔科に入局後、カンボジアSun International Clinicに従事し、ノースウェスタン大学にて学位取得(修士)。帰国後、岐阜大学附属病院、高山赤十字病院、岐阜総合医療センター、岐阜赤十字病院で整形外科医として勤務。2023年4月より大垣中央病院に入職、整形外科・麻酔科の担当医を務める。
ランナー膝(腸脛靱帯炎)の病型
ランナー膝(腸脛靱帯炎, ITBS)は症状の程度によって分類されます。
Lindenbergによる分類では、4段階に区分されています。
| 分類 | 特徴 |
|---|---|
| グレード1(軽度) | 痛みはランニング後にのみ出現し、距離やスピードに影響はない。 |
| グレード2(中等度) | 痛みがランニング中にも発生するが、まだ走行距離や速度に制限を及ぼすほどではない。 |
| グレード3(やや重度) | ランニング中に痛みが生じ、走行距離や速度に制限がかかる(痛みのためペースダウンや途中停止を要する)。 |
| グレード4(重度) | 痛みが強くランニング自体が不可能な状態。 |
この分類は症状出現のタイミングとスポーツ継続の可否による一例であり、他にも急性期(発症直後の炎症が強い時期)か慢性期(長期化し肥厚や瘢痕変化を伴う時期)かで分ける見方もあります。
また、片脚性か両脚性かという分類もあります。
ランナー膝(腸脛靭帯炎)は通常片脚に発症しますが、稀に両膝に起こる場合もあり、同時に両側発症したものを両側性ITBSと呼びます。
一般にはLindenbergによる分類が臨床的に有用で、症状が進行すると痛みの出現時期が早まり最終的には安静時にも支障を来す状態に至ります。
ランナー膝(腸脛靱帯炎)の症状
ランナー膝(腸脛靱帯炎, ITBS)の症状は個人差が大きいですが、主に膝の外側(大腿骨外側顆付近)に痛みや違和感を覚えるのが特徴です。
運動中だけでなく、日常生活の動作にも影響する場合があります。
ランニングや階段の昇降を続けるうちに痛みが増すようなら、ランナー膝を疑って早めに対処する必要があります。
| 症状の特徴 | 状況 | 疑われる段階 |
|---|---|---|
| 走り始めや走行中の膝外側痛 | ウォーミングアップが不十分なときなど | 軽度〜中程度 |
| 膝外側の圧痛 | 指で押すと痛む、湿布を貼るとしみるなど | 中程度〜重度 |
| 階段や坂道での痛み | 下半身に体重をかける動作全般 | 中程度〜重度 |
| 膝の曲げ伸ばしでの引っかかり感 | 外側部分でこすれるような違和感 | 中程度〜重度 |
走り始めや一定時間経過後に出現する痛み
走り始めの数分後または一定距離を走ったころに、膝の外側に痛みを感じるパターンがよく見られます。ウォーミングアップが不十分だったり、腸脛靱帯の柔軟性が低下していたりすると痛みの出現が早まりやすいです。
膝外側の深部で熱感や刺すような痛みが生じるケースもあります。
初期の痛みはランニングなど運動をし終えた後に鈍い痛みや灼熱感として現れ、走行距離が長いほど出現しやすくなります。
症状が進行すると運動中にも痛みを感じるようになり、さらに悪化すれば運動を中止せざるを得ない鋭い痛みに変わります。
膝外側を押すと出る圧痛
膝を伸ばした状態で膝外側(大腿骨のでっぱりから2~3cm上)を軽く押すと、はっきりした痛みを感じる場合があります。
炎症が進むと、この圧痛が強くなり、普段の動きでも気になるようになります。圧痛は他の膝障害でも見られますが、ランナー膝の場合は側面に集中するケースが多いです。
階段昇降での痛み
ランナー膝という名前から、走る場面でのみ痛みが出ると考えがちですが、階段の上り下りや坂道の昇降でも痛みを訴える方が多いです。
膝を曲げ伸ばししながら体重をかける動作で腸脛靱帯に負荷がかかるため、ランニングと同様に負荷が膝外側に集中します。
痛みは膝が約30°屈曲したときに最も強く感じられるケースが多く、ちょうど膝が曲がった状態で荷重がかかる局面で鋭い痛みが走るときがあります。
膝の曲げ伸ばしに伴う引っかかり感
腸脛靱帯が硬くなると、膝の曲げ伸ばしの際に外側にピリッと引っかかる感覚が出るときがあります。これは腸脛靱帯と大腿骨外側顆がこすれ合って生じる症状です。
強い炎症があると、引っかかり感だけでなく鋭い痛みに変化し、日常動作がスムーズに行えなくなるケースもあります。
- ランニング途中に膝外側がピリピリする
- 押すと痛みがはっきりわかる
- 階段や坂道で痛みが増す
- 膝を動かすと外側が引っかかる感覚がある
症状が続くときは、腸脛靱帯炎の可能性があるため、専門家や医療機関に相談してください。
ランナー膝(腸脛靱帯炎)の原因
ランナー膝(腸脛靱帯炎, ITBS)の原因は、主に腸脛靱帯の過度な摩擦と炎症です。
運動フォームやランニング量だけでなく、身体の柔軟性や筋力バランスなど多くの要因が関係します。根本的な原因を探って適切な対策をとると、症状の悪化を防げて、再発リスクを減らせます。
発生メカニズム
ランナー膝の発症メカニズムについては摩擦説(腸脛靭帯と骨の摩擦による滑膜包炎)と圧迫説(腸脛靭帯下面の高度に神経分布した脂肪組織の圧迫による痛み)の2つの説があります。
近年は後者の圧迫説も支持されており、摩擦そのものよりも腸脛靭帯と骨に挟まれる脂肪組織の炎症・肥厚による圧迫痛が主体ではないかとも言われます。
この観点では、単純なストレッチや過度なフォームローリングで無理に腸脛靭帯を押し伸ばすのはかえって脂肪組織を圧迫し痛みを悪化させる可能性も示唆されています。
ただし依然としてはっきりした結論は出ておらず、原因除去には包括的な取り組み(筋力強化、フォーム改善、炎症管理など)が必要とされています。
| 原因 | 説明 | 対応策 |
|---|---|---|
| オーバーユース | トレーニング過多や休息不足で腸脛靱帯に負担がかかる | 休息日を設定し、週単位の走行距離を徐々に調整する |
| 筋力バランスの乱れ | 特定の筋肉だけが強く、他が弱いため膝に偏った負担がかかる | 下半身全体の筋トレやフォームを意識したエクササイズ |
| 柔軟性不足 | 腸脛靱帯や周辺筋肉の硬さが原因で負荷が集中しやすい | ランニング前後のストレッチ、日常的な柔軟体操 |
| 不適切なランニングフォーム | 足の着地やシューズの選択が原因で衝撃が外側に集中する | フォーム改善、専門家とのシューズフィッティング |
オーバーユース(使いすぎ)
特に長距離ランナーやトレーニング頻度が高い人に多い繰り返しの摩擦、圧迫が主原因です。
走行距離や走行頻度を急激に増やすと、腸脛靱帯に大きな負荷がかかり続けてしまいます。
ランニングでは膝が約30°屈曲した時に腸脛靭帯が大腿骨外側上顆に擦れる「インピンジメントゾーン」に入るとされ、この屈伸の反復により腸脛靭帯と骨の間の滑液包や脂肪組織が炎症・肥厚を起こすと考えられます。
また休息日を十分に取らずにトレーニングを積む場合、炎症や痛みが発生しやすくなります。
筋力バランスの乱れ
大腿四頭筋やハムストリングス、臀部の筋肉など、下半身の筋力バランスが崩れると、歩行やランニングの際に膝関節へ不自然な負担がかかります。
中殿筋の弱さは、膝の外側に負担をとくに集中させる原因になりやすいです。筋力トレーニングを行うときは、下半身全体をまんべんなく鍛える工夫が重要になります。
柔軟性不足
腸脛靱帯の硬さや太ももの裏・表の筋肉が硬い場合、腸脛靱帯に余計な張力がかかりやすいです。その結果、走行中に膝外側で過度な摩擦が生じ、痛みへつながります。
日常的にストレッチを行い、柔軟性を保つと予防につながります。
不適切なランニングフォームやシューズ
足の着地が極端に外側や内側に偏るフォーム、過剰な回外や回内などの走り方は、膝外側への負担を増やしやすいです。
また、クッション性が足りないシューズやサイズの合わないシューズを使うと、足底からの衝撃が適切に吸収されないため、腸脛靱帯へのストレスが蓄積しやすくなります。
路面にも注意が必要で、偏ったコース(トラックのカーブばかりや、道路の端ばかりなど)を走るのもリスク要因です。
- トレーニング量を急に増やす
- 休息を十分に取らない
- 下半身の筋力が偏っている
- ストレッチ不足
- シューズが自分の足に合っていない
- 着地の衝撃が大きい
このような要因が重なると、ランナー膝のリスクが上がります。自己判断だけでなく、フォームチェックやシューズ選びを専門家に相談すると良いでしょう。
ランナー膝(腸脛靱帯炎)の検査・チェック方法
自分がランナー膝(腸脛靱帯炎, ITBS)かどうかを確かめるには、医療機関での診察や検査が重要です。
専門家の目で診断を受けると、適切な治療方針や再発予防策を立てやすくなります。自己判断だけで痛みを我慢していると症状が悪化する可能性があるため、早めの受診を考えましょう。
問診と触診
まず、いつから痛みが始まったのか、どのような運動を行っているのかを詳しく聞き取ります。その後、膝外側を触ったり膝を曲げ伸ばししながら痛みの程度や部位を確認します。
この段階でランナー膝が疑われたら、さらに画像検査で状態を詳細に把握します。
画像検査(レントゲンやMRIなど)
| 検査名 | 目的 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
| レントゲン | 骨の状態や変形を確認 | 短時間で撮影可能、費用が比較的安い | 軟部組織の詳細はわかりにくい |
| MRI | 軟部組織の炎症や損傷を確認 | 腸脛靱帯や周辺筋肉・靱帯の状態がわかりやすい | 費用が高い、時間がかかる |
レントゲン検査では骨の状態を確認し、他の膝障害(半月板損傷や変形性膝関節症など)の有無を調べます。
腸脛靱帯そのものの炎症や組織の変化をより詳しく見るためにMRIを用いるケースもあります。
炎症の程度が高い場合は、MRIによって周辺組織の腫れや筋肉との摩擦状況を把握できます。
臨床徒手検査
徒手検査としてNoble法とOber法があります。
Noble法
Nobleテストでは仰向けの患者さんの膝を90度屈曲位から徐々に伸展させつつ、術者が膝の外側上顆を指で強く圧迫します。
膝が約30度屈曲位になったところで患者に膝外側の痛みが生じれば陽性で、これはその角度で腸脛靭帯が骨に擦れているのを示唆します。
Ober法
Oberテストは腸脛靭帯の緊張の強さ(拘縮)の評価に用います。
患者さんの健側※1を下にした横向きに寝かせ、膝を直角に曲げた状態で股関節を他動的に最大外転・後方伸展します。
※1健側:障害のない側の身体。この場合は痛みや違和感のない側を下に、ある側(患側)を上にして横向きに寝る。
その後、膝を保持したままゆっくり股関節を自然に下ろそうとしたとき、腸脛靭帯が硬いと腿が水平より下に十分に降りず浮いたままになります(陽性所見)。この際に膝外側部に痛みが生じても陽性と判定されます。
これらのテストにより腸脛靭帯の摩擦痛か他の膝外側痛かを鑑別します。
加えてRenneテスト(立位片脚荷重で膝を屈伸し30度付近で痛み発現)も有用です。
また、片脚スクワット動作で膝が内側に入る(ニーイン)などの代償動作がないか観察し、股関節筋力やアライメント※2の評価も行います。
※2アライメント:骨や関節の正しい位置関係や並び方。
ランニングフォームの分析
専門のスポーツクリニックやトレーナーのもとで、ランニングフォームを撮影・解析するのも効果的です。
膝の角度や足の着地位置、上半身のバランスなどを総合的にチェックし、腸脛靱帯に負担をかけているポイントを洗い出します。
その結果をもとにフォームを改善すると、再発防止につながります。
全体的な検査の流れ
- 問診と触診で痛みの原因を絞り込む
- レントゲンで骨の異常を除外
- MRIで腸脛靱帯の炎症を詳細に把握
- 臨床テストで腸脛靱帯の張りをチェック
- フォーム分析で動作の改善点を探る
このような流れで診断を進めると、ランナー膝かどうかを正確に判断できます。
ランナー膝(腸脛靱帯炎)の治療方法と治療薬、リハビリテーション、治療期間
ランナー膝(腸脛靱帯炎, ITBS)の治療では、炎症を抑えながら再発を防ぐためのリハビリや筋力バランスの改善が大切です。
症状の程度や個々の生活スタイルに合わせて、さまざまな方法を組み合わせます。
保存療法(安静・アイシング・テーピングなど)
軽度から中程度の症状であれば、まずは保存療法が第一選択になります。
炎症がある場合は安静を優先し、痛みがある部位をアイシングします。テーピングやサポーターを使用し、腸脛靱帯にかかる負荷を軽減します。
- 安静と休養
- アイスパックによるアイシング
- テーピングまたはサポーター
- 軽いストレッチとマッサージ
これにより、痛みの悪化を防ぎながら身体を動かせるようになります。
数週間~2ヶ月程度の保存療法で大半は回復に向かいますが、症状が長引く場合でも6ヶ月ほど継続すれば約9割は良好な結果が得られる見込みです。
投薬(消炎鎮痛薬など)
痛みや炎症が強い場合は、医師が消炎鎮痛薬や筋弛緩薬を処方するケースがあります。飲み薬のほか、軟膏や貼り薬による局所的な治療法もあります。
痛みがある程度抑えられるためリハビリテーションを進めやすくなる一方、薬の効果に頼りすぎず根本原因の改善も同時に図ることが重要です。
物理療法やリハビリテーション
専門の施設やクリニックでは、超音波や電気刺激を使った物理療法、または理学療法士の指導のもとでリハビリを行います。
腸脛靱帯や下半身の筋肉を柔軟にし、筋力バランスを整えるエクササイズを実施すると、再発のリスクを低減できます。
具体的なリハビリ内容としては、臀筋や大腿四頭筋、ハムストリングスの強化運動が含まれます。
リハビリテーションでよく行うエクササイズ
| エクササイズ | 目的 | ポイント |
|---|---|---|
| スクワット | 大腿四頭筋と臀筋の強化 | 膝が内側に入らないように姿勢を維持する |
| ブリッジ | 臀筋と体幹の安定性向上 | 骨盤を左右にぶらさず持ち上げる |
| ヒップアブダクション | 中臀筋の強化 | 横向きで足を持ち上げ、腰を回さない |
| ハムストリングスストレッチ | 太ももの裏の柔軟性アップ | ゆっくり伸ばし反動をつけない |
手術が検討されるケースと治療期間の目安
保存療法やリハビリテーションを続けても症状が改善しない場合や、重度の炎症が起きている場合は、手術を検討するときがあります。
ただし、実際には手術を行うケースは少なく、多くの人は保存的な治療で改善が期待できます。
治療期間は軽度であれば数週間から数か月、重度の場合は半年程度かかる場合もあります。
リハビリの進捗状況や生活スタイルによっても大きく変化するため、担当医や理学療法士とよく相談しましょう。
- 保存療法で痛みを緩和する
- 投薬で炎症を抑えてリハビリを進める
- 物理療法やエクササイズで再発予防を図る
- 改善が乏しい場合は手術も検討する
このような工程を経て、症状の軽減と再発防止に向かって治療を行います。
薬の副作用や治療のデメリット
治療に用いる薬や治療法には、それぞれメリットがある一方で副作用やデメリットも存在します。
安全に治療を進めるには、デメリットを理解しつつ、正しい方法とタイミングで行いましょう。
- NSAIDsなどの薬は副作用に注意しながら使用する
- ステロイド注射は局所的には効果が高いが慎重に判断する
- 手術には感染や麻酔リスクなどが伴う
- 安静が長引くと筋力低下やストレスが生じる
消炎鎮痛薬の副作用
一般的に処方される非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)は、胃腸障害や腎機能への影響を起こす可能性があります。
長期間の服用は症状の軽減に効果的であっても、消化器系への負担が大きくなる場合があるので注意が必要です。医師が処方した用量を守り、必要以上の長期連用は避けてください。
ステロイド注射のリスク
強い痛みに対して、ステロイドの局所注射を行う場合がありますが、注射部位の組織が弱くなったり、感染リスクが上がるおそれがあります。
また、ステロイド注射に頼りすぎると、本来必要なリハビリやフォーム改善が後回しになるリスクがあるため、他の治療法と併用してバランスを取るのが基本です。
治療薬の主な副作用・デメリット
| 治療薬 | 副作用・デメリット | 補足 |
|---|---|---|
| NSAIDs(飲み薬) | 胃痛、胃粘膜障害、腎機能への影響など | 長期連用は避ける |
| NSAIDs(外用薬) | 皮膚のかぶれ、かゆみ | 直接貼る箇所に注意 |
| ステロイド注射 | 組織が弱くなる、感染リスク上昇 | 連続的な注射は慎重に検討 |
| 筋弛緩薬 | 眠気、だるさ、意識低下 | 運転や機械操作に注意 |
手術によるリスク
ランナー膝に対する手術はまれですが、実施するときには麻酔によるリスクや術後感染のリスクが存在します。
術後はリハビリ期間が必要になり、運動復帰までに時間がかかる可能性があります。手術を検討する際は、保存療法の効果や日常生活の影響度合いなどを総合的に判断して決定するケースが多いです。
運動を制限するために起こるデメリット
保存療法や安静が必要な期間が続くと、筋力や体力が落ちやすくなります。ランニングやスポーツを習慣にしている方にとって、運動制限は精神的ストレスに繋がりやすいです。
ただし、痛みをこらえて続けると症状が長引くリスクもあるため、主治医や理学療法士の助言を参考に無理のない範囲で運動を継続すると良いでしょう。
保険適用と治療費
以下に記載している治療費(医療費)は目安であり、実際の費用は症状や治療内容、保険適用否により大幅に上回ることがございます。当院では料金に関する以下説明の不備や相違について、一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。
ランナー膝(腸脛靱帯炎, ITBS)の治療は、一般的な医療保険の適用範囲に含まれるケースが多いです。ただし、保険の種類や施術内容によって自己負担金が変わる場合があります。
受診前に概算の費用を確認しておくと、治療を受ける際の不安が軽減します。
保険適用の範囲
整形外科クリニックやスポーツクリニックでの診察やリハビリテーション、投薬などは、健康保険が適用されるのが一般的です。
物理療法(電気治療や超音波など)や注射も保険が適用される場合があります。
一方、健康保険が使えない自由診療のリハビリやフォーム指導、トレーナーによるパーソナルトレーニングなどは自己負担となるところがほとんどです。
治療費の目安
実際の治療費は症状の程度や通院回数、検査内容、施設の料金設定により異なります。
初診の場合、診察とレントゲン検査だけなら自己負担が3割の場合で1,500円〜3,000円程度になります。MRI検査を追加すると、さらに1,000円〜3,000円程度かかります。
リハビリや物理療法を受ける場合、1回あたり数百円〜1,000円程度の自己負担が目安です。
| 治療内容 | 保険適用の有無 | 自己負担の目安(3割負担) |
|---|---|---|
| 初診・レントゲン検査 | あり | 約1,500円〜3,000円 |
| MRI検査 | あり | 約1,000円〜3,000円 |
| 物理療法(電気治療など) | あり | 1回あたり数百円〜1,000円程度 |
| ステロイド注射 | あり | 数百円〜1,500円程度 |
| 自由診療のリハビリ・フォーム指導 | なし | 1回数千円〜(施設・内容による) |
自由診療との違い
保険適用で行えるリハビリや治療には時間や内容に一定の制限があるケースが多いです。
一方、自由診療のリハビリやパーソナルトレーニングでは、より個別性の高いプログラムを受けられる場合もありますが、すべて実費となるため負担が増える可能性があります。
治療費に関して不明な点があれば、受診前に医療機関に問い合わせると安心です。
ランニングやウォーキングなどの運動を続けたい方は、早期に原因を探って適切なケアを行うのが重要になります。
痛みがあるときは我慢しすぎず、専門家による診察と治療を検討してください。
以上
参考文献
RUBIN, Benjamin D.; COLLINS, H. Royer. Runner’s knee. The Physician and Sportsmedicine, 1980, 8.6: 47-58.
JAMES, Stan L. Running injuries to the knee. JAAOS-Journal of the American Academy of Orthopaedic Surgeons, 1995, 3.6: 309-318.
FREDERICSON, Michael, et al. Hip abductor weakness in distance runners with iliotibial band syndrome. Clinical Journal of Sport Medicine, 2000, 10.3: 169-175.
FAIRCLOUGH, John, et al. The functional anatomy of the iliotibial band during flexion and extension of the knee: implications for understanding iliotibial band syndrome. Journal of anatomy, 2006, 208.3: 309-316.
HADEED, Andrew; TAPSCOTT, David C. Iliotibial band friction syndrome. 2019.
FREDERICSON, Michael; WOLF, Chuck. Iliotibial band syndrome in runners: innovations in treatment. Sports Medicine, 2005, 35: 451-459.
STRAUSS, Eric J., et al. Iliotibial band syndrome: evaluation and management. JAAOS-Journal of the American Academy of Orthopaedic Surgeons, 2011, 19.12: 728-736.
FERBER, Reed, et al. Competitive female runners with a history of iliotibial band syndrome demonstrate atypical hip and knee kinematics. journal of orthopaedic & sports physical therapy, 2010, 40.2: 52-58.
HOLMES, James C.; PRUITT, Andrew L.; WHALEN, Nina J. Iliotibial band syndrome in cyclists. The American journal of sports medicine, 1993, 21.3: 419-424.
NOBLE, Clive A. Iliotibial band friction syndrome in runners. The American journal of sports medicine, 1980, 8.4: 232-234.