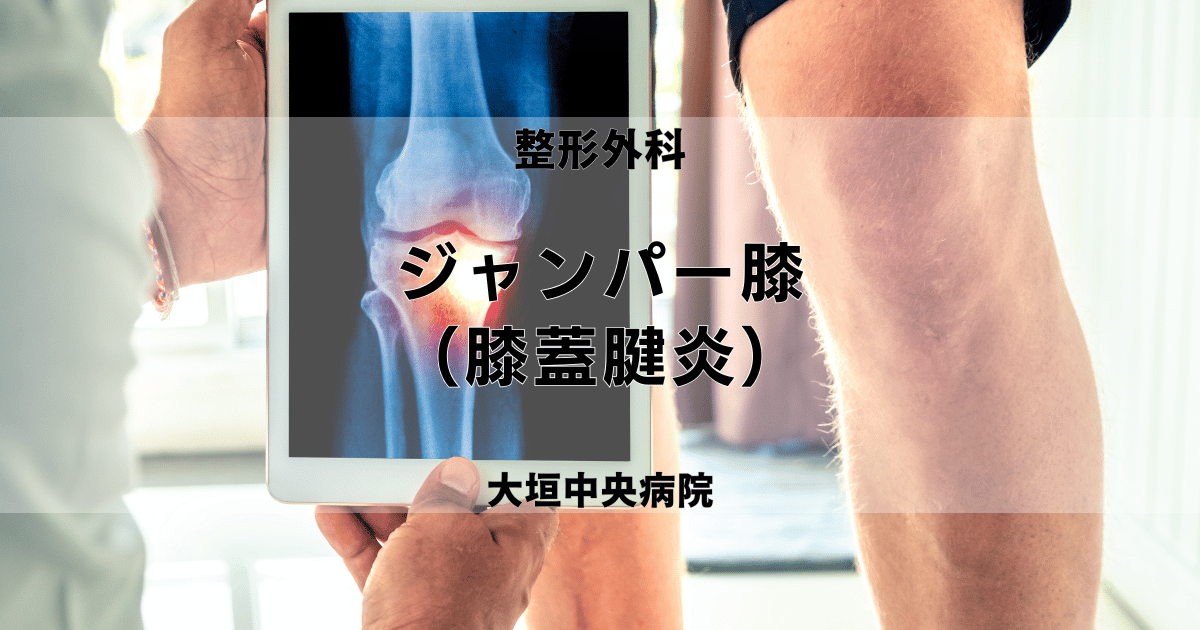ジャンパー膝(Jumper’s knee, Patellar tendinopathy)とは、膝蓋骨下端の膝蓋腱(しつがいけん)付着部に生じる使いすぎによる腱障害です。
バスケットボールやバレーボールなど、ジャンプ動作が多い競技で起こりやすいです。ただ、スポーツ以外でも、膝への負荷が大きい作業や生活習慣が重なると発症します。
膝の痛みが長引く場合や、休息を取っても症状が改善しにくい場合は、専門的なケアと治療が必要です。
ジャンパー膝は英語で“Jumper’s Knee”とも呼ばれ、古くは「膝蓋腱炎(patellar tendinitis)」と表現されます。
しかし実際の病態は腱の変性を主体とする慢性の障害であり、炎症よりもコラーゲン線維の変性・断裂や血管増生(腱症 tendinosis)が認められます。
そのため近年では膝蓋腱障害と総称され、腱の治癒に長期間を要する難治性のオーバーユース傷害として位置づけられています。
この記事の執筆者

臼井 大記(うすい だいき)
日本整形外科学会認定専門医
医療社団法人豊正会大垣中央病院 整形外科・麻酔科 担当医師
2009年に帝京大学医学部医学科卒業後、厚生中央病院に勤務。東京医大病院麻酔科に入局後、カンボジアSun International Clinicに従事し、ノースウェスタン大学にて学位取得(修士)。帰国後、岐阜大学附属病院、高山赤十字病院、岐阜総合医療センター、岐阜赤十字病院で整形外科医として勤務。2023年4月より大垣中央病院に入職、整形外科・麻酔科の担当医を務める。
ジャンパー膝の病型
ジャンパー膝(膝蓋腱炎)は、その症状の程度により段階的に分類されます。Blazinaらの分類(1973年)では症状に応じて4段階に区分されます。
| ステージ分類 | 特徴 |
|---|---|
| Stage 1 | スポーツ活動後に痛みが現れるのみ |
| Stage 2 | 活動開始時に痛みがあるがウォーミングアップで軽快し反復や疲労で痛みが再発する |
| Stage 3 | 活動中も後も継続する顕著な痛みで競技継続が困難 |
| Stage 4 | 膝蓋腱の完全断裂 |
多くの場合はStage 1~3の慢性的な腱障害として経過し、Stage 4(腱断裂)に至るのは稀ですが、重度の変性が蓄積した腱では外傷契機に断裂が起こりえます。
病態面では慢性変性(腱症)が主であり、腱組織には粘液様変性、膠原線維の乱れ、小血管や神経の侵入(神経血管芽組織)が認められます。
炎症細胞浸潤は必ずしも顕著ではなく、従来の腱炎(tendinitis)という名称からイメージされる「急性炎症」とは異なる病態です。
このような慢性腱障害は一旦発症すると自然回復しにくく、慢性化・再発しやすい点が知られています(ある報告では約20%が再発・難治化する)。そのためジャンパー膝は慢性期の病態に合わせた治療が重要になります。
ジャンパー膝の症状
ジャンパー膝(膝蓋腱炎)は膝に鋭い痛みを伴う場合や、鈍い痛みを伴う場合など、多彩な症状があります。
膝蓋骨(ひざのお皿)の下にある膝蓋腱にトラブルが集中し、症状を放置すると腱の損傷が広がる可能性があります。
- 膝蓋骨下部の鋭い痛み
- 運動後に増す鈍い痛み
- 膝蓋腱周辺の腫れや熱感
- 突っ張り感やひっかかり感
- 日常動作への影響(階段昇降など)
膝のトラブルが続くと他の関節や筋肉をかばう動作が増え、二次的な故障を招く場合があります。少しでも気になる症状があれば、医師や理学療法士の診察・相談を受けると回復のチャンスを高めやすいです。
典型的な痛みのパターン
代表的なのは、ジャンプ直後や着地時に膝の膝蓋骨下端付近が痛むケースです。また、走り出しや急な方向転換など、膝に瞬発的な力を込めるときにも痛みを訴える人が多いです。
痛みは運動の後半になるほど強まることが多く、休息時や翌朝に特にひどくなる傾向があります。
腫れや熱感
患部の炎症によって腫れが生じる場合があります。触れると熱っぽく感じるケースも多く、この状態が長く続くほど慢性化しやすくなります。
腫れがあると、膝を曲げ伸ばしするだけでも苦痛になる人が多いです。
違和感や突っ張り感
膝蓋腱付近に突っ張り感を訴えるケースもあります。走り始めやジャンプの準備動作で引っかかるような感覚になり、スポーツ動作に支障が出る場合があります。
突っ張り感や違和感の段階でケアを行えば、痛みの悪化を防ぎやすいです。
動作の制限
膝の伸展時に強い痛みがあるため、着地時の衝撃をしっかり受け止められず、身体バランスをくずす人もいます。
痛みが進むと、階段の昇降も難しくなり、普段の移動さえ億劫になるときがあります。特に、着地の動作、ダッシュの開始、階段昇降、深くしゃがむ動作で膝前面の鋭い痛みを訴えます。
また、長時間座って膝を曲げていると症状が増悪する症状がみられる場合があります。
症状の変化と注意ポイント
| 症状の進行度 | 痛みのタイミング | 注意ポイント | 対応策 |
|---|---|---|---|
| 軽度 | 運動後や翌朝に軽い痛みを感じる | 放置すると慢性化につながりやすい | 早めの休息、ストレッチ、アイシング |
| 中度 | 運動中、日常生活でも痛みを感じる | 膝の使い方を修正しないと悪化しやすい | 装具の利用、筋力強化、スポーツドクターの受診 |
| 重度 | 常時痛みを感じ、動作が制限される | 膝以外への負担が増加 | 集中的なリハビリ、場合によっては手術 |
ジャンパー膝の原因
ジャンパー膝(膝蓋腱炎)は典型的なオーバーユース(使いすぎ)障害であり、その主因は繰り返しの跳躍動作による膝蓋腱への過度な負荷蓄積です。
特に着地の瞬間などに膝が曲がった状態で大腿四頭筋が急激に収縮(伸張性収縮)する際、膝蓋骨下端の腱付着部に強大な張力がかかり、腱組織の微細な損傷が繰り返されます。
実際、バレーボール選手では、競技歴が長くジャンプ回数の多い選手ほど膝蓋腱に構造変化や痛みを抱える率が高いことが報告されています。
他にも、膝の構造や身体の使い方、練習環境など、複数の要素が重なって発症し、悪化へつながります。
- ジャンプやダッシュの頻度が極端に多い
- 大腿四頭筋やハムストリングスの筋力不足
- ストレッチ不足による柔軟性の欠如
- フォームや着地動作に問題がある
- 過密スケジュールで休息が少ない
- コンクリートなど硬いコートでのプレー
過度なジャンプ動作
バスケットボールやバレーボールのように、着地や飛び上がりを頻繁に行う競技は、膝蓋腱に大きな負荷をかけます。
ジャンプ力やスピードを高めようと練習を繰り返すと、腱の炎症がとくに起きやすくなります。同じ動作を何度も繰り返すと、休む間もなく膝蓋腱が酷使され、微小断裂が徐々に蓄積するのが原因です。
練習や試合の頻度・強度が高いほどリスク上昇は顕著で、ある前向き研究ではバレーボール選手において週あたりの試合数や練習時間が多いほど将来ジャンパー膝を発症する確率が有意に高まると示されています。
筋力や柔軟性の不足
太ももの前面にある大腿四頭筋の筋力や、ハムストリングス、大腿部周辺の柔軟性が乏しいと、衝撃を吸収しきれず膝蓋腱が過剰に伸展・収縮を強いられます。
筋バランスの偏りによっても膝への負担が増加し、ジャンパー膝を引き起こす一因になります。
実際、ジャンパー膝患者では健常者に比べハムストリングスの柔軟性や足関節の背屈可動域が有意に小さいという報告があり、それらの要因が膝伸展機構への負荷増大に寄与している可能性があります。
また下肢のアライメント※1異常も膝蓋腱へのストレス分布を変化させ、発症要因となりえます。
※1アライメント:間接や骨の並びや位置関係。下肢のアライメント異常の例として、膝蓋骨の位置異常や下腿の回旋異常、偏平足などが挙げられる。
着地動作や走法の問題
ジャンプやランニングの際のフォームが崩れていると、膝に集中する負荷が増す可能性があります。
足を前方に突き出すような走り方や、深く曲げすぎる着地動作を続けると、膝蓋腱へのストレスがとくに大きくなります。
休息の不足
休息やクールダウンが不十分な状態で激しい運動を続けると、腱組織の回復が追いつきません。
コンディションが整わないまま試合や練習に臨むことが繰り返されると、膝蓋腱の炎症が慢性化しやすくなります。
原因と対策の関係
| 原因 | 具体例 | 対策 |
|---|---|---|
| 過度なジャンプ動作 | 高頻度のジャンプ練習、アタック練習など | 練習メニューの見直し、休息の確保 |
| 筋力・柔軟性の不足 | 太ももや股関節周辺の筋力不足、ストレッチ不足 | 筋力トレーニング、ストレッチ、ウォームアップの徹底 |
| フォームの乱れ | 膝が内側に入るジャンプ、足を突き出す走り方など | 動画分析、コーチや理学療法士によるフォーム指導 |
| 過密スケジュール | 大会直前の連日の猛練習、短い休息など | 練習量の調整、積極的なアイシング、睡眠時間の確保 |
膝への負担を減らすためには、根本的な原因の見直しとトレーニングメニューの改善が大切です。なかでも、筋力向上やフォーム改善を行いながら、膝へのストレスを抑える取り組みが重要となります。
ジャンパー膝の検査・チェック方法
痛みの原因が膝蓋腱の炎症によるものなのか、あるいは他の部位の損傷によるものなのかを明確にするために、医師や理学療法士がさまざまなチェックを行います。
しっかりとした検査を行うと、治療方針を正しく決めやすくなります。
| 検査方法 | 特徴 | 得られる情報 |
|---|---|---|
| 問診・視診 | 痛みの経緯を知る、患部の見た目を確認 | 症状の原因、痛みの強さ、患部の外観的異常 |
| 触診・圧迫テスト | 正確な痛みの位置、炎症の有無を感じ取る | 膝蓋腱の炎症部位、腱のコンディションの把握 |
| X線検査 | 骨の変形や配列の異常を確認 | 骨に由来する痛みの可能性の検討 |
| MRI検査 | 軟部組織や腱の状態を精密にチェック | 腱の炎症範囲、断裂の有無、周辺組織のダメージ |
| 超音波検査 | リアルタイムで腱の厚みや損傷を観察可能 | 血流量や腱の変性状態、断裂の有無の即時確認 |
検査の結果を総合して、医師がジャンパー膝と確定診断したり、ほかの膝疾患との鑑別を行ったりします。診断を受けた後は、早期に具体的な治療方針とリハビリ計画を立てるのが大切です。
問診と視診
医師がまず患者の症状や痛みの経過、運動習慣、既往歴などを確認します。
痛みの場所や強さを詳しく聞き取り、膝蓋腱に負荷が集まっているかどうかの大まかな見当をつけます。視診では、膝の腫れや変形、熱感の有無を確認します。
触診と膝蓋腱圧迫テスト
膝のお皿の下部を軽く触れて、痛みの程度や場所を特定します。膝を伸展させて膝蓋腱を指で押さえて痛みが増す場合、炎症や断裂が疑われます。
圧迫テストを行いながら屈伸すると、炎症が顕著な個所をさらに確認できます。
画像検査(X線、MRI、超音波)
骨の変形を確認したい場合はX線撮影を行い、腱の損傷や炎症範囲を詳細に把握したい場合はMRI検査を実施するケースが多いです。
超音波検査は腱の厚みや断裂の有無をリアルタイムで確認しやすく、スポーツクリニックでも広く活用されています。
X線
多くの場合、異常所見がみられませんが、慢性例では膝蓋骨下端に骨棘(こっきょく:骨が棘状に変形)が形成されているケースがあります。
また、骨折や骨端症(若年者のSinding-Larsen-Johansson病)などの骨病変との鑑別に有用です。
超音波検査(エコー)
腱組織をその場で評価できる有用な手段で、ジャンパー膝では膝蓋腱の肥厚、不均一なエコーパターン(低エコー領域)、石灰化の有無などを観察します。
ドップラー超音波を用いると腱内や付着部における血流シグナルの増加をとくにとらえやすく、これは慢性腱症に特徴的な所見です
MRI
膝蓋腱の状態をより詳細に評価するために有用です。MRIでは正常の膝蓋腱はT1強調像で均一な低信号を示し、厚みも7mm未満ですが、ジャンパー膝では近位腱の肥厚と信号強度の増加が特徴的です。
具体的には膝蓋骨下端寄りの腱内にT1で低信号、T2系で高信号の変化が認められ、腱内の微小断裂や浮腫を反映します。
機能テスト
大腿四頭筋やハムストリングスの筋力測定、膝周辺の柔軟性テストなどを行い、膝に負担を与えている原因を探ります。
片脚スクワットや片脚ジャンプなどを通して、バランス能力や筋力の偏りもチェックします。
ジャンパー膝の治療方法と治療薬、リハビリテーション、治療期間
ジャンパー膝(膝蓋腱炎)の治療は、患部の炎症を抑え、腱の損傷を回復させる、そして再発を防ぐための筋力強化やフォーム矯正を組み合わせるのがポイントとなります。
治療期間は症状の度合いによって異なりますが、焦らずにリハビリを行う姿勢が大切です。
保存療法
ジャンパー膝の治療は、保存療法が基本となります。腱の負荷を減らすために運動量を調整し、患部の安静を確保します。
アイシングや痛み止めの内服薬、炎症を鎮める外用薬などを活用しながら、悪化を防ぎます。
膝蓋腱をサポートするためにテーピングやサポーターを使用する場合もあります。
よく用いられる治療薬(内服薬・外用薬)
| 薬の種類 | 用途 | 投与・使用の形態 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| NSAIDs(非ステロイド性消炎薬) | 炎症や痛みを軽減 | 内服薬、塗り薬、貼り薬など | 長期使用で胃腸障害のリスクが高まることがある |
| 抗炎症外用薬 | 炎症部位に直接作用 | 軟膏、クリーム、パッチなど | 皮膚かぶれやかゆみが出る場合がある |
| 筋弛緩薬 | 筋肉の緊張をほぐす | 内服薬 | 眠気や倦怠感を訴える人がいることに注意 |
内服薬や外用薬は症状を緩和するために用います。痛みがひどいときは、一時的に消炎鎮痛剤を使用するケースもあります。
ただし、治療薬を使い続ける場合は、胃腸や皮膚などへの影響にも注意が必要です。
物理療法・リハビリテーション
物理療法としては、温熱療法や超音波治療、低周波治療などが役立ちます。これらは血行を促進したり筋肉の緊張をほぐしたりする目的で行います。
理学療法士の指導のもと、ストレッチや筋力強化を段階的に行い、膝への負荷をコントロールしながら再発を予防していきます。
リハビリテーションの目標
ジャンパー膝のリハビリテーションは、痛みの管理と腱・筋機能の回復を両立させるのが目標です。
基本的な取り組みはアスリートであっても一般患者であっても共通ですが、競技者の場合は競技スケジュールやパフォーマンス維持の観点も考慮した特別な配慮が必要です。
リハビリの基本的な流れ
一般的なリハビリ手順としては、まず痛みが強い急性期には負荷軽減と鎮痛(アイシングや電気療法など)を行い、痛みが落ち着き次第可動域訓練と等尺性収縮エクササイズから開始します。
等尺性運動(例:軽い膝屈曲角度での膝押し伸ばしを静止して5~10秒保持する訓練)は腱に大きな動的負荷をかけずに筋力維持・鎮痛効果を得られるため、初期リハビリに有用です。
次に、痛みが許容できる範囲でエキセントリック運動(膝をゆっくり曲げながら負荷をかける運動)を導入し、腱と筋の強化を図ります。
典型例なトレーニングのスクワットのほか、レッグプレスやランジなど種目は様々ですが、とにかく膝蓋腱に十分な張力がかかる運動を段階的に行うのが重要です。
筋力がついてきたら重錘を用いたレジスタンストレーニング(レッグエクステンションやスクワットで高負荷・低回数のトレーニングなど)も加え、腱・筋に適応を促します。
リハビリ終盤では、ジャンプ動作に耐えうるようプライオメトリック(反復跳躍)トレーニングやアジリティトレーニングを取り入れ、競技特性に合わせた動きの中で痛みなく力を発揮できるかを確認します。
最終的にフルスプリントや最大跳躍を行っても痛みが再発しないのを確認して競技復帰となります。
アスリート向けのリハビリ
アスリート向けのリハビリ戦略では、単に休ませるのではなく痛みと付き合いながら競技練習を続行するための工夫が重視されます。
例えば、痛みが閾値以下であればジャンプ練習を続け、痛みが増悪するようならメニューを軽減するといったペインモニターモデルを採用します。
具体的にはVAS(視覚的アナログ尺度)で痛みが10中3~4以下であれば許容範囲とし、それを超える痛みが出たら練習内容を調整するといった指標を設けます。
さらに、練習内容を細分化して膝腱への負荷度をスコア化し、週内での高負荷メニューの配分を管理するといった洗練された方法も提案されています。
またアスリートの場合、競技パフォーマンス維持も重要であるため、膝に負担をかけない範囲での筋力トレーニング(例えば上半身や体幹の強化)や、有酸素トレーニング(エアロバイクや水中ランニング等)で全身のコンディションを維持する取り組みも並行して行われます。
競技復帰のタイミングはシーズンオフに合わせるなど計画的に調整され、メンタル面のサポートも含め包括的なリハビリが提供されます。
一般患者向けのリハビリ
一般患者向けのリハビリでは、日常生活での痛みの解消と再発防止が目標となります。
まず日常で痛みを誘発する動作(階段の昇降や長時間の正座など)を極力避けつつ、上記と同様のストレッチや筋トレを処方します。
痛みが引いてきたらウォーキングや軽いジョギング程度の全身運動を開始し、膝周囲の筋持久力を高めます。
一般の方でも痛みが長期化すると歩行や趣味活動に支障が出るため、アスリートと同じく数ヶ月にわたる計画的な理学療法が重要です。
痛みが再燃した際の対処法(アイシングや休息の取り方)や、自宅でできるストレッチ・筋トレ方法を指導し、患者さんにセルフケア能力を高めてもらいます。
場合によっては理学療法士による家庭訪問指導などを行い、リハビリ継続のサポートをするケースもあります。
リハビリテーション全般として、症状が改善するペースには個人差があります。
VISA-Pスコア※2などを参考に客観的に機能回復度合いを評価しつつ、無理のない範囲で復帰を目指すのが大切です。
※2VISA-Pスコア:膝蓋腱障害の患者さんから症状を報告してもらう自己評価式の指標。0~から100点で評価、点数が高いほど症状が軽い。
仮に6か月以上リハビリを行っても改善が得られない場合には、手術療法など次の段階を検討するサインと考えられます。
注射治療や手術
保存療法で十分な効果が得られない場合や、腱の断裂が進んでいる場合は、ステロイド注射やヒアルロン酸注射などを行う場合があります。
腱に大きな損傷が生じているケースでは手術を検討する場合もあり、手術後のリハビリも慎重に進める必要があります。
ジャンパー膝に対する手術法としては、膝蓋腱の病変部デブリードマン(清掃術)と腱の一部切離術(テノトミー)が代表的です。
治療期間の目安
軽度であれば2~3週間程度の安静とリハビリで症状が落ち着く人もいます。
中度から重度の場合は数か月以上かかるケースもあり、再発を防ぐためにはさらに長期的なサポートやリハビリ計画が必要となります。
症状レベル別の治療と期間の目安
| 症状レベル | 治療法 | 回復までの目安期間 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 軽度 | 保存療法(NSAIDs、サポーター、物理療法)、リハビリ軽度 | 2~3週間程度で症状が落ち着く場合あるが、数ヶ月以上かかる人もいる | 運動量の早期調整が重要 |
| 中度 | 保存療法(痛み止め、外用薬、物理療法、リハビリ) | 1~3か月程度 | ストレッチや筋力強化を丁寧に継続 |
| 重度 | 保存療法+注射、手術の検討 | 3~6か月以上になる例が多い | 手術後のリハビリ期間を含め長期にわたるケアが必要 |
焦りは禁物であり、痛みが引いたあとも継続的にリハビリを行うのが大切です。
軽度でも適切なケアを怠ると重症化しやすいので、医師や理学療法士の指導のもと正しいケア続けましょう。
薬の副作用や治療のデメリット
ジャンパー膝(膝蓋腱炎)の治療には薬物療法や注射治療などが用いられますが、効果と同時に副作用やデメリットを理解しておくことが重要です。
また、手術には入院や長期リハビリが必要になるなどの負担があります。
NSAIDsなどの内服薬の副作用
NSAIDs(非ステロイド性消炎鎮痛薬)は炎症や痛みを和らげるためにしばしば使用します。
ただし、長期にわたる服用や過剰摂取によって、胃腸障害(胃痛・胸やけ・胃潰瘍など)、肝機能障害、腎機能障害などが起こる場合があります。医師の指示を守って用量や期間を管理しましょう。
ステロイド注射のデメリット
ステロイド注射は炎症や痛みを強力に抑える反面、腱や軟骨組織への影響や、注射箇所の感染リスクなどのデメリットがあります。
多用すると腱自体の回復力を損なう恐れがあるため、医師が慎重に使用を検討します。
手術のリスクと回復期間
手術を行う場合、術後の痛みや感染症リスク、手術自体の合併症などを考慮する必要があります。
入院やリハビリ期間が長引くと、競技復帰や社会復帰に時間がかかる点がデメリットです。スポーツ選手にとっては、競技の練習再開時期の遅れが精神的な負担にもなります。
治療での注意点
痛みを感じにくくなると、つい運動を再開したくなるものですが、腱の回復には時間が必要です。
また、薬の副作用による体調不良が出た場合は早めに医師に相談してください。
対症療法だけでなく、原因となるトレーニング習慣やフォームを改善しないと再発リスクが高まりますので、今までのトレーニングやフォームを見直すきっかけにすると良いでしょう。
薬や治療のメリット・デメリット
| 治療法 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| NSAIDs内服 | 痛みや炎症を抑え、日常生活が楽になる | 胃腸障害、肝臓や腎臓への負担 |
| ステロイド注射 | 痛みを強力に抑制 | 腱への悪影響、感染リスク、過度の繰り返しで回復力を損なう恐れ |
| 手術 | 根本的な腱損傷を修復 | 入院や長期リハビリが必要、合併症リスク |
| 物理療法・リハビリ | 筋力向上、柔軟性向上、再発予防に役立つ | 時間と継続的な努力が必要 |
焦って運動に復帰すると、治療効果を台無しにする可能性があります。医師や理学療法士の指示を守り、無理のない範囲で行動しましょう。
保険適用と治療費
以下に記載している治療費(医療費)は目安であり、実際の費用は症状や治療内容、保険適用否により大幅に上回ることがございます。当院では料金に関する以下説明の不備や相違について、一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。
ジャンパー膝(膝蓋腱炎)の治療では、保存療法、リハビリ、注射治療、場合によっては手術など、さまざまな選択肢があります。
日本の医療保険制度では、整形外科で診療を受ける場合、健康保険が適用になるケースが多いです。治療費は受ける治療の内容や病院の設備、保険の種類によって異なります。
保険適用の範囲
一般的に、医師による診察料、処方された薬の費用、理学療法士によるリハビリテーションなどは健康保険の適用対象です。
基本的に、ステロイド注射やヒアルロン酸注射も適用範囲です。
ただし、自由診療(PRP療法や体外衝撃波治療など)や一部の特殊なリハビリプログラムなど保険の適用外になる項目もあるため、事前に医師やスタッフに確認すると安心です。
- 初診料・再診料
- X線検査、MRI検査、超音波検査(病院やクリニックで行われる場合)
- リハビリテーション(理学療法、物理療法)
- 薬の処方(内服薬、外用薬)
- ステロイド注射やヒアルロン酸注射
治療費の目安
具体的な金額は治療内容や通院回数、保険の自己負担割合(3割負担、2割負担、1割負担など)によって変わります。
例えば、初診料や検査費用、リハビリ費用が含まれる通院1回あたりの費用は、3割負担の場合でおおむね3,000円~8,000円程度になるケースが多いです。
複数の検査や注射などを実施した場合や、保険外サービスを受ける場合には追加費用が発生します。
| 治療の種類 | 3割負担時の費用 | 備考 |
|---|---|---|
| 初診・再診+物理療法+リハビリ | 3,000円~5,000円程度 | 検査内容が多いと費用は増加 |
| X線、MRI、超音波検査を追加する場合 | 4,000円~8,000円程度 | 病院の設備や検査項目で変動 |
| ステロイド注射やヒアルロン酸注射を実施 | 1,000円~2,000円程度追加 | 治療内容や回数によって変わる |
| 手術(入院治療含む) | 数万円~数十万円 | 手術の内容、入院日数、個室利用などで大きく変動 |
通院回数が増えると、当然費用もかさむ傾向があります。手術が必要なケースでは、入院費用や術後リハビリ費用も考慮しましょう。
高額療養費制度※3の活用が可能な場合もありますので、該当する際は確認しておくと安心です。
※3高額療養費制度:1ヶ月あたりの医療費の上限額が決められていて、超過分が払い戻しされる制度。上限額は収入や年齢により異なる。
自由診療の場合
高次医療機関やスポーツ整形外科などで、特殊な治療を受ける場合、自由診療の扱いとなり、全額自己負担になるときがあります。
治療費が高額になる場合があるため、事前の説明や見積もりが重要です。
治療費と治療内容や受診タイミングの関係
ジャンパー膝の治療費は、症状の重症度や治療内容によって大きく差が生じます。
保険適用の範囲内で治療を受けると一定の負担で済む方が多いですが、自由診療などに頼る場合は自己負担額が増える点に留意してください。
早期発見・早期治療を行うと費用負担も軽減しやすくなるため、気になる膝の痛みがあるときは早めに医療機関で相談しましょう。
以上
参考文献
BLAZINA, Martin E., et al. Jumper’s knee. Orthopedic Clinics of North America, 1973, 4.3: 665-678.
FREDBERG, Ulrich; BOLVIG, L. Jumper’s knee: review of the literature. Scandinavian journal of medicine & science in sports, 1999, 9.2: 66-73.
FERRETTI, Andrea, et al. Jumper’s knee. The American journal of sports medicine, 1983, 11.2: 58-62.
TIEMESSEN, Ivo JH, et al. Risk factors for developing jumper’s knee in sport and occupation: a review. BMC research notes, 2009, 2: 1-6.
LIAN, Østein B.; ENGEBRETSEN, Lars; BAHR, Roald. Prevalence of jumper’s knee among elite athletes from different sports: a cross-sectional study. The American journal of sports medicine, 2005, 33.4: 561-567.
FRITSCHY, Daniel; DE GAUTARD, René. Jumper’s knee and ultrasonography. The American journal of sports medicine, 1988, 16.6: 637-640.
VISNES, Håvard; AANDAHL, Hans Åge; BAHR, Roald. Jumper’s knee paradox—jumping ability is a risk factor for developing jumper’s knee: a 5-year prospective study. British journal of sports medicine, 2013, 47.8: 503-507.
FERRETTI, Andrea, et al. The natural history of jumper’s knee: patellar or quadriceps tendonitis. International orthopaedics, 1985, 8: 239-242.
KETTUNEN, Jyrki A., et al. Long-term prognosis for Jumper’s knee in male athletes: prospective follow-up study. The American journal of sports medicine, 2002, 30.5: 689-692.
FERRETTI, Andrea, et al. Jumper’s knee: an epidemiological study of volleyball players. The physician and sportsmedicine, 1984, 12.10: 97-106.