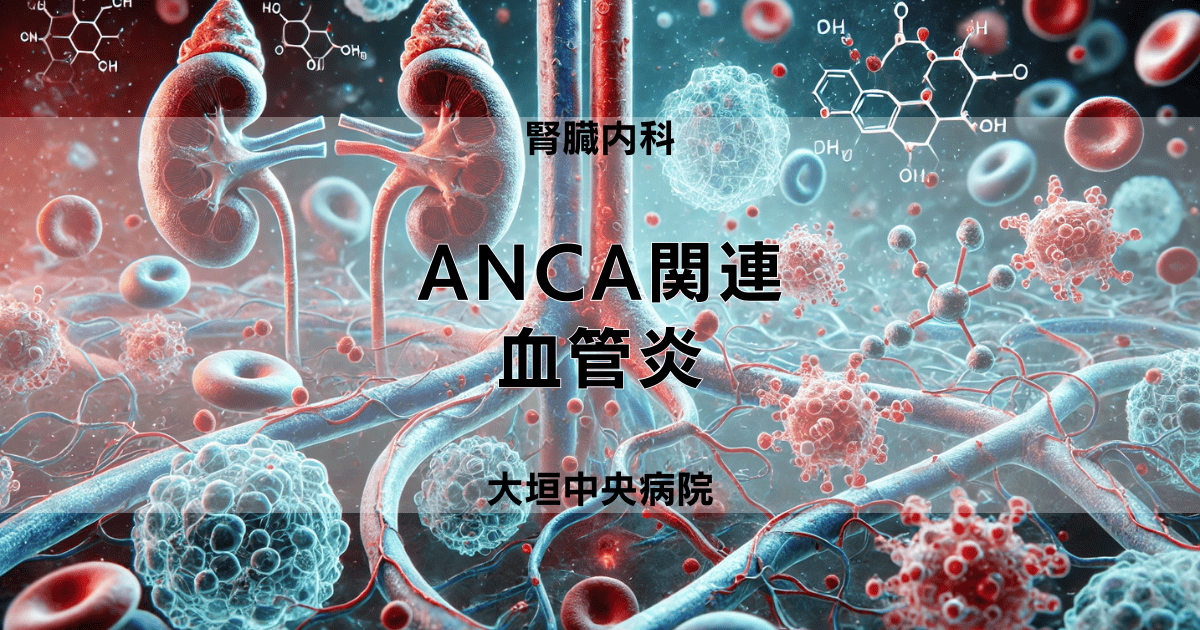ANCA関連血管炎とは、全身の小〜中サイズの血管に炎症が生じる自己免疫性疾患の総称であり、主に抗好中球細胞質抗体(ANCA)が関与していると考えられています。
腎臓や肺などの臓器を中心に症状が現れやすく、体調不良が続くのに原因がわからず不安を感じる方も多いです。
病気の全体像や具体的な症状、検査の流れ、治療方法、そしてかかる費用などを詳しく知ることで、治療を受けるかどうか迷っている方が納得できる情報を得られます。
ANCA関連血管炎の病型
ANCA関連血管炎は、代表的な疾患として顕微鏡的多発血管炎、肉芽腫性多発血管炎、好酸球性多発血管炎(かつてはチャーグ・ストラウス症候群と呼ばれたもの)などがあり、全身の多岐にわたる組織や臓器に障害を及ぼす可能性があります。
このカテゴリーに属する疾患は、いずれもANCA(抗好中球細胞質抗体)の存在や、それに伴う炎症反応が特徴です。
顕微鏡的多発血管炎(MPA)の特徴
顕微鏡的多発血管炎は、全身の小型血管を中心に炎症が生じる病型であり、腎臓や肺、皮膚、神経など、さまざまな臓器に影響を及ぼす可能性があります。
腎障害と肺障害が顕著に出るケースが多いとされ、放置すると腎機能の低下や呼吸器系の異常などにつながるリスクがあります。
腎生検を実施すると糸球体に壊死性の変化が確認されることが多いため、そうした組織学的所見は診断において大切です。
顕微鏡的多発血管炎の主な臓器症状と傾向
| 主な影響臓器 | 具体的症状 | 病気の進行にともなう影響 |
|---|---|---|
| 腎臓 | 尿蛋白、血尿、腎機能低下 | 透析が必要になるほど悪化するケースがある |
| 肺 | 呼吸困難、肺出血、咳、倦怠感 | 重度の呼吸不全に至る可能性がある |
| 皮膚 | 皮疹、皮下出血 | かゆみや潰瘍につながることがある |
| 神経 | 四肢のしびれ、感覚障害、筋力低下 | 生活の質を著しく低下させる場合がある |
肉芽腫性多発血管炎(GPA)の特徴
かつてウェゲナー肉芽腫症と呼ばれていた肉芽腫性多発血管炎は、肺や気道、鼻などの上気道領域に病変を形成しやすい病型です。
慢性的な副鼻腔炎や血性鼻汁、鼻の痛みが続く場合、GPAを疑う必要があり、さらに肺の結節や空洞性病変、腎機能障害など、全身に多様な症状を起こします。病理学的には肉芽腫を伴う炎症反応が特徴となります。
呼吸器症状で来院する方が多いため、肺のX線検査やCT検査で異常所見が認められたときに初めて、血液検査を含む詳しい検査を行ってANCA関連血管炎を疑うケースが少なくありません。
肉芽腫性多発血管炎で認められやすい初期症状
- 長引く鼻づまりと慢性的な副鼻腔炎
- 血性鼻水や鼻出血
- 肺の結節病変に伴う呼吸困難
- 腎機能低下に伴う血尿や浮腫
呼吸器・腎症状が並行して進む場合もあり、診断の遅れが症状の悪化につながるリスクを高めます。
好酸球性多発血管炎(EGPA)の特徴
好酸球性多発血管炎(EGPA)は、好酸球増加を伴う血管炎として知られ、気管支喘息やアレルギー性鼻炎との関連が深い点が特徴的です。気道のアレルギー症状が数年単位で先行し、その後に好酸球の増加を伴う血管炎が発症します。
呼吸困難や喘鳴に加えて、皮膚症状や末梢神経の障害など、症状が多岐にわたる点がほかのANCA関連血管炎とは異なる部分です。
また、好酸球の異常増殖が確認された場合は、好酸球性多発血管炎のみならず、寄生虫感染や血液腫瘍など他の原因も視野に入れつつ、注意深く鑑別が行われます。
EGPAとアレルギー性疾患の因果関係は明確に解明されたわけではありませんが、同時に存在するケースが多いです。
ANCA陽性と陰性のバリエーション
ANCA関連血管炎ではANCAが検出されることが多いですが、必ずしもすべての症例で陽性になるわけではありません。
顕微鏡的多発血管炎や肉芽腫性多発血管炎の多くは、PR3-ANCA(C-ANCA)またはMPO-ANCA(P-ANCA)が高率に陽性を示しますが、好酸球性多発血管炎の一部ではANCA陰性の症例もあります。
ANCA陰性の症例でも明確な臨床症状や組織学所見がANCA関連血管炎を示すことがあるため、血液検査だけでなく複合的な視点で診断を確定する必要があります。
ANCA関連血管炎の主な病型とANCA陽性率の目安
| 病型 | 主なANCAタイプ | ANCA陽性の頻度 | 症状の特長 |
|---|---|---|---|
| 顕微鏡的多発血管炎(MPA) | MPO-ANCAが多い | 約70〜80% | 腎・肺障害が多い |
| 肉芽腫性多発血管炎(GPA) | PR3-ANCAが多い | 約80〜90% | 肉芽腫形成、上気道・肺障害が多い |
| 好酸球性多発血管炎(EGPA) | MPO-ANCAが多い | 約40〜50%(陰性も多い) | 好酸球増多、喘息症状が多い |
症状
ANCA関連血管炎は、全身性の疾患であるため、ほぼあらゆる臓器系統に症状が生じる可能性があり、症状の現れ方は個人差が大きく、初期の段階では、倦怠感や微熱、体重減少などの非特異的な体調不良が続きます。
進行するにつれ、腎臓や呼吸器系、皮膚、神経など、多岐にわたる臓器症状が合わさり、生活の質に大きな影響を与えます。
全身症状
多くの方が、初期段階で全身の倦怠感や微熱、食欲不振、夜間の発汗といった体のだるさを感じます。
風邪やインフルエンザのような感染症を疑うことが多く、とくに明確な特徴がないまま数週間から数カ月続く場合はANCA関連血管炎を考慮する必要があります。
急激に症状が進むより、じわじわと体調不良が長引いていく印象を受けるケースが多いです。
初期段階に見られやすい全身症状
- 微熱が続く
- 倦怠感や疲労感が取れない
- 食欲が低下する
- 体重が減少傾向にある
腎臓の症状
ANCA関連血管炎では、腎障害が中核的な問題になることが少なくありません。特に顕微鏡的多発血管炎や肉芽腫性多発血管炎では、腎機能への影響が顕著に出ることがあります。
血尿や尿蛋白が初期の段階で見つかる場合もあれば、症状に気づかず進行してしまい、明らかな腎不全の兆候が出るまで異常に気づかないケースもあり、むくみや高血圧が見られるようになったら、腎障害を疑うことが重要です。
腎障害が疑われるサイン
| サイン | 具体的な観察事項 | 考えられる腎機能への影響 |
|---|---|---|
| 尿の色や泡立ちの変化 | 尿が濃い褐色・赤色、泡立ちが多い | 血尿・尿蛋白による腎炎の可能性 |
| むくみ | 顔や下肢などに浮腫が出る | ネフローゼ症候群や腎不全の進行 |
| 高血圧 | 血圧が急に高くなる | 腎機能障害の悪化 |
| 倦怠感や貧血傾向 | 体力の低下、動悸を感じることが多い | エリスロポエチン産生低下による貧血 |
呼吸器の症状
呼吸器への影響は非常に多彩であり、慢性的な咳や息切れ、肺出血や喀血を伴うケースがあり、肉芽腫性多発血管炎では、副鼻腔炎や中耳炎など上気道炎症が長く続き、鼻血や血性の鼻水が出るケースも多いです。
呼吸器症状は気管支喘息など他の疾患と見分けがつきにくいため、詳細な検査が必要で、特にANCA関連血管炎による肺出血は重症化しやすく、血痰に気づいた段階で医療機関を受診してください。
呼吸器症状に関してよくある疑問点
- 喘鳴(ゼーゼーという呼吸音)は喘息とどのように見分けるか
- 持続する副鼻腔炎は単なる慢性副鼻腔炎ではないのか
- 血痰や喀血が出た場合にどの程度急いで受診したほうがいいか
- 胸部X線やCT検査でどのような異常所見が出やすいか
皮膚や神経の症状
皮膚の症状としては、斑点状の発疹や紫斑、潰瘍などが挙げられ、これらは炎症によって血管が傷害されることで起きる出血斑や壊死性変化によるものです。
また、神経系では多発単神経炎が起こりやすく、四肢のしびれ、筋力低下、感覚鈍麻などが進行していく場合があります。中枢神経系への影響は少ないとされますが、全身状態の悪化に伴い中枢神経症状が出ないわけではありません。
神経症状の進行具合と日常生活への影響
| 神経症状の度合い | 具体的な症状 | 日常生活への影響 |
|---|---|---|
| 軽度(しびれ程度) | 足先や手先のピリピリ感 | 歩行や細かい作業にやや支障が出る |
| 中程度(感覚障害や痛み) | しびれに加え、強い痛みを伴う | 歩行や道具操作が難しくなる |
| 重度(筋力低下など) | 筋力の著しい低下や重度の痛み | 自力歩行や日常生活動作が困難になる |
ANCA関連血管炎の原因
ANCA関連血管炎は自己免疫疾患の一種であり、体内の免疫システムが何らかの異常を起こし、自分自身の血管を攻撃してしまうことが原因です。
免疫異常が起こるメカニズムは複雑で、単一の因子ではなく、遺伝的素因や環境要因、感染症などの複数の要素が絡み合っていると考えられます。
免疫システムの誤作動
正常な免疫システムは、細菌やウイルスなどの外来異物を察知し、体を守る働きをしますが、ANCA関連血管炎では、抗好中球細胞質抗体(ANCA)が好中球を刺激し、血管内皮を傷つける方向に働いてしまうと推測されています。
好中球が過剰に活性化すると、血管の炎症を引き起こし、その部分に組織の壊死や損傷が起こると考えられています。
ANCA関連血管炎の免疫異常に関して取りざたされるポイント
- ANCAが好中球を活性化して血管を障害する
- サイトカインやケモカインのバランス異常が持続する
- 炎症性物質が局所的に留まり、組織を攻撃する
遺伝的素因
遺伝性の疾患とは言い切れませんが、家族歴や特定の遺伝子多型が関与している可能性があり、HLA(ヒト白血球抗原)タイプとの関連が示唆されており、特定のHLAタイプを持つ人がANCA関連血管炎を発症しやすいという報告もあります。
ただし、全体的にみて決定打とは言えず、遺伝因子だけが原因ではありません。
遺伝的要素の関与を示唆する研究知見
| 研究報告の概要 | 主な内容 | 結論のまとめ |
|---|---|---|
| 特定のHLAタイプとの関連 | B細胞やT細胞の機能異常を増強する可能性 | 発症リスクを高める因子の1つと考えられる |
| 親族内で同様の血管炎が報告された症例 | 家族間で同じ病型が出現した事例が少数報告あり | 遺伝的素因が関係している可能性がある |
| 倍数の遺伝子多型を調べた疫学調査 | 免疫調節に関わる分子の発現レベルが影響を与える | 複合的な要因と相まって発症に至る |
環境要因
タバコ、感染症、薬剤など、さまざまな環境要因がANCA産生を誘導するきっかけになると考える研究もあり、例えば、上気道感染症をきっかけに免疫バランスが崩れ、その後にANCAが産生されて病状が進行するケースがあります。
とはいえ、生活習慣や環境を変えるだけで発症を完全に防げるわけではなく、いろいろな要因が組み合わさっている点が複雑です。
不明な部分も多い複合要因
現在の医学的知見では、ANCA関連血管炎に至るメカニズムを完全に解明できておらず、原因が複数にわたる複合的な要素が大きいとされています。
遺伝と環境、免疫異常が絡み合って引き起こされる疾患と考えるのが現状であり、「これを避ければ絶対に発症を予防できる」というものはないので、症状の兆候を早期にとらえて検査を受けることが重要です。
考えられる複合要因
- もともとの免疫バランスに乱れが生じやすい体質
- 何らかの感染症やストレスで免疫バランスが崩れる
- 好中球が誤って自己組織を攻撃するような抗体が産生される
- 炎症が繰り返されることで血管炎が慢性化する
ANCA関連血管炎の検査・チェック方法
ANCA関連血管炎の疑いがある場合、最初に行うのは血液検査で、ANCAの有無や腎機能、炎症の程度などを調べますが、最終的な確定診断にあたっては、画像検査や組織の生検も組み合わせて判断することが多いです。
腎生検であれば、腎臓の糸球体に壊死性病変があるかどうかを調べ、顕微鏡下での異常所見を確認します。
血液検査
血液検査では、ANCA(MPO-ANCA、PR3-ANCA)の有無や量を調べることが核となります。
また、免疫グロブリンや補体の変動、一般的な炎症マーカー(CRP、赤沈など)や腎機能(クレアチニン、BUN)を同時にチェックし、全身状態の把握を行います。
ANCAが陽性であっても、必ずANCA関連血管炎というわけではなく、他の病気でも陽性になる可能性があるため、総合的な判断が必要です。
血液検査項目
| 検査項目 | 目的・意義 | 判定の目安 |
|---|---|---|
| MPO-ANCA | 好中球細胞質の酵素に対する自己抗体の測定 | 基準値以上の場合は、MPAやEGPAを疑う |
| PR3-ANCA | 好中球細胞質の蛋白質に対する自己抗体の測定 | 基準値以上の場合は、GPAを疑う |
| CRP | 炎症反応の指標 | 高値の場合、体内で強い炎症を伴う可能性が高い |
| BUN、クレアチニン | 腎機能評価 | 上昇している場合、腎障害が進行している可能性がある |
| 血球算定 | 白血球数、好酸球数、貧血の有無などを調べる | EGPAでは好酸球数が増えるケースが多い |
画像検査
肺や副鼻腔、その他の臓器の病変をチェックするために、胸部X線撮影やCT検査、MRI検査などが行われます。
肉芽腫性多発血管炎では、肺に結節や空洞がみられることが多く、好酸球性多発血管炎では肺浸潤影が広範囲に確認されるケースもあります。
また、鼻や副鼻腔など、上気道粘膜のびらんやポリープ形成なども画像検査で確認することで、病型の推定に有用です。
生検
生検は、実際に組織の一部を採取し、顕微鏡で観察することによって血管の炎症や壊死の程度、肉芽腫形成の有無などを確認するために行います。
腎生検、肺生検、鼻粘膜生検などが代表例で、腎生検が診断確定のうえで最も重要になるケースが多いです。ただし、生検は侵襲的検査であり、合併症や出血リスクがあるため、患者の状態を見極めたうえで判断されます。
他の疾患との鑑別
類似した症状を示す疾患として、全身性エリテマトーデス(SLE)やリウマチ性疾患、血管炎症候群などが考えられ、鑑別を行う上でも、ANCAのパターンや生検所見、画像検査の結果を総合的に見て診断を付けることが求められます。
複数の診療科にわたって検査を受け、専門家による評価が大切です。
ANCA関連血管炎の主な鑑別疾患と着目すべきポイント
- SLE:抗核抗体や免疫複合体による炎症が主たる機序
- 顕微鏡的多発血管炎との混在:中にはオーバーラップ症候群のように併発が疑われる例もあり
- 関節リウマチ:リウマトイド因子や関節症状が主体だが、血管炎症状を併発することもある
治療方法と治療薬について
ANCA関連血管炎の治療は、主に免疫抑制療法が中心となり、ステロイド(副腎皮質ステロイド)や免疫抑制薬を使い、炎症を抑制しながら臓器障害の進行を防ぎます。
近年では、生物学的製剤も選択肢の1つになりつつあり、重症度や病型に合わせて治療方法が組み合わされます。
ステロイド療法
プレドニゾロンなどのステロイド薬が用いられ、初期治療や再燃時の寛解導入に役立ち、ステロイドは強力な抗炎症作用を持ち、急性期の炎症を素早く抑えることが期待できます。
腎障害や肺出血など重篤な合併症がある場合は、点滴パルス療法(大量ステロイド投与)を短期間実施して、炎症を一気に鎮静化させる場合もあります。
ただし、副作用が出やすい点に注意が必要で、投与量や期間を医師が慎重に調整することが重要です。
ステロイドを使用する際の留意点
- 血糖値が上昇しやすいため、糖尿病の既往がある場合は要注意
- 感染症にかかりやすくなるため、風邪や肺炎などに十分注意
- 長期使用時には骨粗しょう症や消化性潰瘍にも気を配る
免疫抑制薬
ステロイドと併用することで、ステロイドの用量を減らしながら寛解を維持しやすくする目的で使われるのが免疫抑制薬で、代表的なものにシクロホスファミドやメトトレキサート、アザチオプリンなどがあります。
シクロホスファミドは導入療法として効果が高く、重症例や再燃を繰り返すケースにおいて使用し、メトトレキサートは、比較的軽症例や維持療法に使われることが多いです。
代表的な免疫抑制薬の特徴
| 薬剤名 | 主な特徴 | 注意すべき副作用 |
|---|---|---|
| シクロホスファミド | 強力な免疫抑制効果がある | 骨髄抑制、出血性膀胱炎、脱毛など |
| メトトレキサート | 維持療法や軽症〜中等症で用いられることが多い | 肝機能障害、口内炎、間質性肺炎など |
| アザチオプリン | 比較的作用が穏やかで維持療法に使われる | 骨髄抑制、感染症リスクの増大など |
生物学的製剤
リツキシマブなどの生物学的製剤は、B細胞を標的として免疫反応をコントロールすることで、ANCA関連血管炎の活動性を抑えることを狙う薬です。
生物学的製剤は費用が高額になる場合もありますが、ステロイドや従来の免疫抑制薬だけではコントロールが難しいケースにおいて治療の選択肢となります。
一般的には、ステロイドやシクロホスファミドに代替あるいは併用して使うシーンが想定されます。
補助療法
高血圧のコントロールや、感染予防のための抗菌薬投与、骨粗しょう症予防のためのビタミンDやカルシウムの補給など、複数のサポート療法を組み合わせることが大切です。
特にステロイドを大量・長期にわたって使うケースでは、感染リスクと骨粗しょう症対策が非常に重要になります。
ANCA関連血管炎の治療戦略
| 治療段階 | 治療目標 | 主な治療法 |
|---|---|---|
| 寛解導入期 | 炎症を迅速に抑制し、臓器障害を最小限にする | ステロイドパルス療法、シクロホスファミド、リツキシマブ |
| 寛解維持期 | 再燃を抑え、ステロイド量を可能な限り減量 | メトトレキサート、アザチオプリン、生物学的製剤など |
| 合併症・副作用対策 | 治療に伴うリスクを低減し、生活の質を保つ | 感染予防、骨密度低下予防、高血圧管理など |
ANCA関連血管炎の治療期間
ANCA関連血管炎は、治療によって一時的に症状が落ち着いても再燃するリスクがあり、長期にわたって経過観察と治療を継続する必要があります。
個人差が大きいため、一概に「何年」という目安を示すことは難しいですが、少なくとも数カ月〜数年単位での治療計画を立てることが多いです。
急性期の治療期間
急性期にはステロイドの高用量投与やシクロホスファミドによる導入療法を行い、要する期間は数週から数カ月におよぶ場合があります。
炎症のコントロールが確認された後、維持療法にシフトします。重症度が高いほど急性期の治療に時間を要し、入退院を繰り返すケースもあります。
急性期治療の実際の流れ
- ステロイドパルス療法を3日〜1週間程度施行し、以後経口ステロイドに切り替える
- 必要に応じて免疫抑制薬を導入し、炎症と臓器障害の程度を観察する
- 重症肺出血や腎不全などの場合は、ICUでの管理が必要になることもある
寛解維持期
寛解維持期には、ステロイドの減量や免疫抑制薬の種類変更などを通じて、副作用のリスクをできるだけ抑えながら再燃を防ぐことが目標です。
この時期が最も長く、数年にわたることもあり、定期的に血液検査や画像検査、尿検査を行い、ANCA値の上昇や炎症反応の悪化がないかをチェックします。
寛解維持期の治療
| 治療ステージ | 期間の目安 | 主な管理のポイント |
|---|---|---|
| 寛解導入後~1年 | 6カ月〜1年程度 | ステロイド減量のペースを決定、免疫抑制薬の副作用をチェック |
| 1~2年目 | 1年〜2年程度 | 定期的なANCA測定、再燃兆候の早期発見 |
| 2~5年目 | 2年〜5年程度 | 長期的なQOL維持、定期検査と副作用対策 |
個別差と長期フォロー
ANCA関連血管炎の再燃リスクは個別に異なるため、長い方では5年以上、時には10年以上にわたって治療とフォローが続く場合があります。
特に腎障害が著しいケースでは、慢性腎不全に移行するリスクもあり、その管理も合わせて行う必要があります。
再燃が疑われる初期段階で適切に対応すれば重症化を回避できるので、自己判断で通院や薬を中止するのは避け、医師の指示に従うことが大切です。
副作用や治療のデメリットについて
ANCA関連血管炎の治療薬の多くは、強力な免疫抑制作用を持つものです。そのため、病気の進行を抑制する一方で、薬にともなう副作用や感染リスクの増大など、治療のデメリットも理解しておく必要があります。
ステロイドの副作用
ステロイドは急性期の症状コントロールに必須の薬ですが、副作用として糖尿病、骨粗しょう症、精神面への影響などが挙げられ、血糖値の上昇が顕著な場合は、内分泌科の受診が必要になることもあります。
また、長期服用により骨がもろくなり、骨折のリスクが高まります。さらに、不眠やイライラ感、うつ傾向など、精神面にも悪影響が及ぶことがある点にも注意が必要です。
免疫抑制薬の副作用
シクロホスファミドやメトトレキサート、アザチオプリンなどの免疫抑制薬は、白血球や赤血球が減少しやすくなり、貧血や感染症が起こりやすくなります。
シクロホスファミドは強力な薬であり、脱毛や吐き気、出血性膀胱炎などが起こる可能性があります。メトトレキサートでも口内炎や肝機能障害、間質性肺炎などを発症するリスクがあるため、定期的な血液検査とモニタリングが大切です。
免疫抑制薬の使用時に注意すべき点
- 血液検査で白血球数や肝機能を定期チェックする
- 体調不良を感じたらすぐ医師に相談して薬剤調整を行う
- 妊娠・授乳を計画する場合は事前に主治医へ相談する
生物学的製剤のリスク
リツキシマブなどの生物学的製剤はB細胞を標的としているため、効果は高い一方で細菌やウイルスへの抵抗力が低下しやすくなり、また、投与後に重篤なアレルギー反応(インフュージョンリアクション)が起こることもあります。
投与時には医療機関で状態観察を行い、異常を認めた場合には速やかに対処する体制を整えることが必要です。
生物学的製剤における考慮事項
| 製剤名 | 主な標的 | 注意点 | 使用メリット |
|---|---|---|---|
| リツキシマブ | B細胞表面分子CD20 | 投与時のアレルギー反応、感染症リスク増 | ステロイド減量が期待できる |
ANCA関連血管炎の保険適用と治療費
以下に記載している治療費(医療費)は目安であり、実際の費用は症状や治療内容、保険適用否により大幅に上回ることがございます。当院では料金に関する以下説明の不備や相違について、一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。
ステロイド薬と免疫抑制薬の費用
ステロイド(経口薬)の費用は比較的安価ですが、長期的に服用するため、総額としては積み重なっていきます。
免疫抑制薬も種類によって費用に差があるものの、シクロホスファミドやメトトレキサートなどは保険適用下で処方できるため、月数千円から数万円程度で収まるケースが多いです。
3割負担を想定したおおよその月額費用目安
- 経口ステロイド:数千円〜1万円程度
- シクロホスファミド内服:数千円〜1万円台
- メトトレキサート:数千円〜1万円程度
生物学的製剤の費用
リツキシマブなど生物学的製剤の費用は高額になりやすく、1回の点滴で薬剤費が数万円から十数万円にのぼり、3割負担でも1回あたり数万円以上になる場合があるため、年間で数十万円の出費になるケースもあります。
ただし、病状や他の薬との組み合わせ、投与間隔によって大きく変わるため、一概に金額を断定することは難しいです。
生物学的製剤の投与頻度と費用
| 製剤名 | 1回の薬剤費(保険適用後3割負担目安) | 投与間隔 | 年間推定費用(目安) |
|---|---|---|---|
| リツキシマブ | 3〜5万円程度 | 数週〜数カ月おき | 数十万円〜100万円前後 |
検査費用
血液検査や尿検査、画像検査などは定期的に行う必要があり、1回あたり数千円から1万円程度かかり、腎生検や入院での検査を実施する場合は、さらに費用がかさむことも想定されます。
合併症や病状の変化に合わせて追加の検査が必要な場合は、その分の費用が上乗せされます。
入院費用
急性期や重症期に入院治療が必要となった場合、短期間の集中治療で済むケースもあれば、腎不全や重度の肺出血などで長期入院になることもあるため、費用は数万円から数十万円以上におよびます。
以上
参考文献
Ozaki S. ANCA-associated vasculitis: diagnostic therapeutic strategy. Allergology International. 2007 Jan 1;56(2):87-96.
Shimojima Y, Kishida D, Ichikawa T, Kida T, Yajima N, Omura S, Nakagomi D, Abe Y, Kadoya M, Takizawa N, Nomura A. Hypertrophic pachymeningitis in ANCA-associated vasculitis: a cross-sectional and multi-institutional study in Japan (J-CANVAS). Arthritis Research & Therapy. 2022 Aug 23;24(1):204.
Ozaki S, Atsumi T, Hayashi T, Ishizu A, Kobayashi S, Kumagai S, Kurihara Y, Kurokawa MS, Makino H, Nagafuchi H, Nakabayashi K. Severity-based treatment for Japanese patients with MPO-ANCA-associated vasculitis: the JMAAV study. Modern rheumatology. 2012 Jun 1;22(3):394-404.
Tsuchiya N. Genetics of ANCA-associated vasculitis in Japan: a role for HLA-DRB1* 09: 01 haplotype. Clinical and experimental nephrology. 2013 Oct;17:628-30.
Harigai M, Nagasaka K, Amano K, Bando M, Dobashi H, Kawakami T, Kishibe K, Murakawa Y, Usui J, Wada T, Tanaka E. 2017 Clinical practice guidelines of the Japan Research Committee of the Ministry of Health, Labour, and Welfare for Intractable Vasculitis for the management of ANCA-associated vasculitis. Modern Rheumatology. 2019 Jan 2;29(1):20-30.
Yamagata K, Usui J, Saito C, Yamaguchi N, Hirayama K, Mase K, Kobayashi M, Koyama A, Sugiyama H, Nitta K, Wada T. ANCA-associated systemic vasculitis in Japan: clinical features and prognostic changes. Clinical and experimental nephrology. 2012 Aug;16:580-8.
Fujimoto S, Uezono S, Hisanaga S, Fukudome K, Kobayashi S, Suzuki K, Hashimoto H, Nakao H, Nunoi H. Incidence of ANCA-associated primary renal vasculitis in the Miyazaki Prefecture: the first population-based, retrospective, epidemiologic survey in Japan. Clinical Journal of the American Society of Nephrology. 2006 Sep 1;1(5):1016-22.
Kitching AR, Anders HJ, Basu N, Brouwer E, Gordon J, Jayne DR, Kullman J, Lyons PA, Merkel PA, Savage CO, Specks U. ANCA-associated vasculitis. Nature reviews Disease primers. 2020 Aug 27;6(1):71.
Yates M, Watts R. ANCA-associated vasculitis. Clinical Medicine. 2017 Feb 1;17(1):60-4.
Jayne DR, Merkel PA, Schall TJ, Bekker P. Avacopan for the treatment of ANCA-associated vasculitis. New England Journal of Medicine. 2021 Feb 18;384(7):599-609.