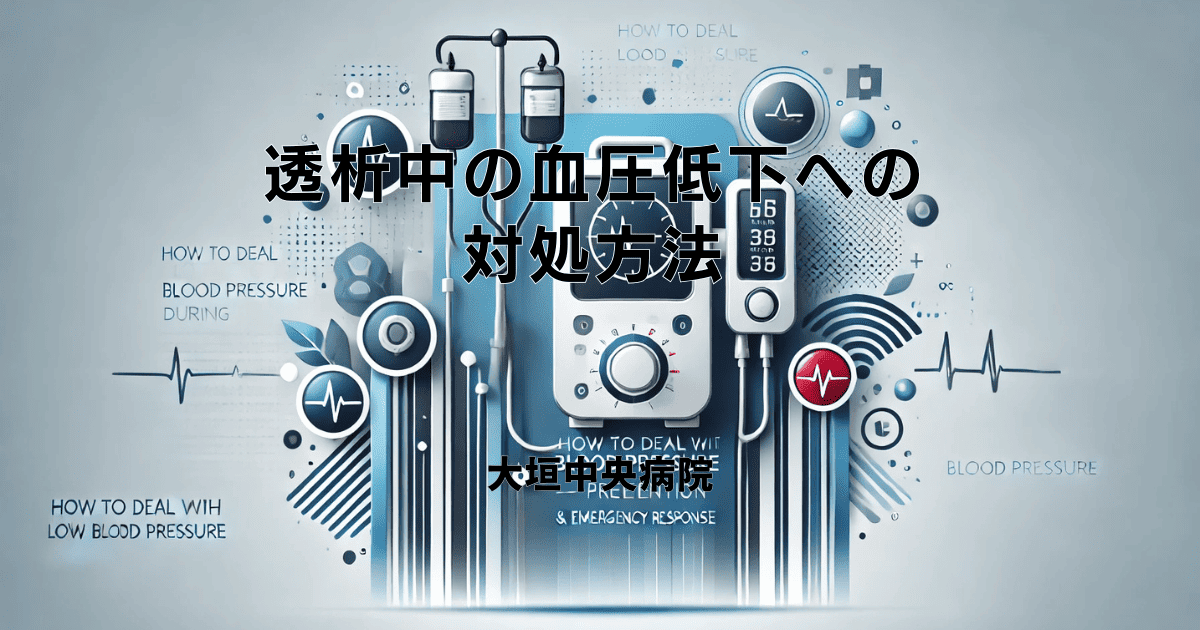透析治療では血液をきれいにするために体外循環を行いますが、その過程で血圧が低下しやすくなる場面があります。血圧低下は患者の体調に大きな影響を与え、めまいや失神などの症状につながることもあります。
この状況を未然に防ぎ、万一の際には迅速に対応することが大切です。今回は、透析中に起こりうる血圧低下の仕組みや原因、具体的な対処方法、日常生活での注意点などを幅広くまとめました。
体への負担を軽減し、安心して透析を受けられるようにするための情報をお伝えします。
透析時の血圧低下とは何か
透析中の血圧低下は体外循環中に血液量のバランスが崩れることなどが原因で起こりやすい状態です。血圧低下が顕著になると、めまいや失神だけでなく、重篤な循環不全を引き起こす可能性もあります。
まずはその基本的な仕組みと、どのような症状が見られるのかを理解することが重要です。
どうして血圧が下がるのか
透析では血液を体外に出し、透析装置を介して老廃物や水分を除去しながら血液を体内に戻します。血圧が下がる主な原因としては下記のようなメカニズムが考えられます。
- 大量の除水による循環血液量の減少
- 透析による血管拡張や交感神経活動の低下
- 透析中の急激な電解質変動による循環動態の乱れ
- 体内温度の変化に伴う血管の反応
透析血圧低下を防ぐためには、これらのメカニズムを押さえたうえで、除水量や透析条件を調整することが欠かせません。
原因とメカニズム
血圧低下の原因をもう少し具体的に挙げると、除水速度が早い場合や、患者ごとに心臓機能や血管弾力性の違いがある点などが見過ごせません。心臓のポンプ機能が弱いと、循環血液量が少しでも減ったときに十分な血圧を保てなくなります。
また、透析液の温度が低いと血管が収縮しやすく、逆に高いと血管が拡張しやすくなるので、温度設定も血圧に影響を与えます。
血圧低下の主な要因一覧
| 要因 | 内容 |
|---|---|
| 大量の除水 | 短時間で過剰に水分を除去すると循環血液量が急激に減少する |
| 交感神経の活性低下 | 透析により体液バランスが変化し、自律神経の働きが乱れる |
| 心臓のポンプ機能低下 | 心不全などがあると血圧が維持しづらくなる |
| 血管抵抗の低下 | 血管拡張による血管抵抗の低下で血圧が下がる |
| 透析条件・温度の影響 | 透析液の温度やナトリウム濃度の設定によって血管の反応が変わる |
透析血圧低下の主な症状
血圧が下がると、めまいや頭痛、倦怠感などの症状がみられる場合があります。重症の場合は失神や意識障害に至り、対応が遅れると循環不全を引き起こすリスクも考えられます。
透析中に以下の症状が出現した場合は、速やかに看護師や医師に伝えることが大切です。
- めまい、ふらつき
- 頭痛、吐き気
- 発汗や寒気
- 顔面の蒼白、動悸
- 意識がもうろうとする
リスクの高い方の特徴
すべての透析患者が同じように血圧低下を起こすわけではありません。以下の特徴を持つ方は特に注意が必要となります。
- 高齢者で循環調節機能が低下している
- 心疾患(心不全や冠動脈疾患など)を合併している
- 透析治療歴が短く、まだ身体が適応していない
- 体重変動が大きく、除水量が大きくなりやすい
- 自律神経障害を有しており、血圧調節が乱れやすい
これらのリスク要因を把握しながら治療を進めると、血圧低下の発生率を抑えやすくなります。
透析治療中の血圧低下における一般的な予防策
血圧低下を未然に防ぐためには、透析前後の体重管理や除水量の調整が欠かせません。また、適切な水分・栄養摂取も血圧維持に大きく影響します。この章では、透析時の血圧を保ちやすくするための基本的な対策を解説します。
血液除水量の調整
透析時には体内の余分な水分を除去しますが、その除水速度が過度に早いと血圧低下を誘発しやすくなります。除水速度を適正に設定し、患者の体重や体調に合わせて細かく調整することが予防の第一歩です。
大量除水になりがちな方は、短時間で一気に除水するのではなく、回数を増やして負担を分散する方法などが検討されます。
適切な除水設定のポイント一覧
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ドライウェイト | 個々の適正体重を明確にし、それに向けて除水量を計算する |
| 除水速度 | 患者の血圧安定度や心機能に応じてゆるやかに設定する |
| モニタリング | 透析中の血圧や脈拍、体液量の変化を随時確認し、柔軟に対応する |
体重管理
体重の急激な増加は透析時に大量の除水が必要になるため、透析血圧低下につながりやすくなります。透析間の体重増加を抑えることで、血圧の急降下を防止しやすくなります。
以下のような点を普段の生活で注意すると、体重増加をコントロールしやすくなります。
- 水分摂取量を適度に管理する
- 塩分を控えて過剰な水分保持を防ぐ
- 定期的な体重測定で変動を早期に把握する
透析前後の体重変化が大きいと感じた場合は、医師や管理栄養士に相談すると良いでしょう。
- こまめな記録をつける
- 1日の摂取水分量を可視化する
- 外食時の塩分量にも配慮する
食事や水分摂取の注意
塩分を摂りすぎると喉が渇き、水分を多く摂取しやすくなります。水分を過剰摂取すると、透析で短時間に大量の除水が必要となり血圧が下がりやすくなるため、適度な塩分制限は重要です。
タンパク質やカリウム、リンなどの栄養素バランスも含めて、医師や管理栄養士と相談しながら食生活を整えてください。
運動や生活習慣
日々の運動は血管を丈夫にし、血圧変動に対する体の調節力を養う面があります。無理のない範囲でウォーキングや軽めの体操を取り入れるなど、継続しやすい運動を選ぶと良いでしょう。
生活リズムを安定させることも血圧維持には大切です。
血圧低下による具体的症状と対処法
透析中に血圧が下がると、頭痛やめまい、倦怠感などが見られます。症状の現れ方は個人差があり、一見軽症に見えても重い疾患へ進行するケースも考えられます。症状別に対処法を理解しておくと、いざというときに落ち着いて対応できます。
対処の基本は早期発見と速やかな医療スタッフへの連絡です。自分自身の体の変化に注意を向け、症状を感じたら遠慮なく報告してください。
頭痛やめまい
透析中に脳への血流が不足すると、頭痛やめまいが生じることがあります。体を動かしたときに症状が強くなる場合は特に要注意です。頭痛が続く場合は、除水速度の見直しや、安静にして血圧を安定させるなどの対応が必要になります。
めまい対策の一覧
| 対策 | 内容 |
|---|---|
| 安静を保つ | 座位や臥位で少し休むことで血流を脳へ安定的に送りやすくする |
| 水分補給 | 適量の塩分や水分を補給し、循環血液量を補う |
| 除水速度の調整 | 急激な除水を避け、徐々に水分を引くようにする |
| 深呼吸 | 呼吸を整えることで自律神経を落ち着かせ、血圧変動を緩やかにする |
吐き気と倦怠感
吐き気や倦怠感は血圧低下だけでなく、電解質バランスの乱れによっても引き起こされます。まずは透析条件を調整し、急激な変化を避けることが大切です。
血圧が一時的に下がっている場合は頭を低くして足を高くした姿勢をとるといった対処も考えられます。
失神や意識障害
失神や意識障害は重度の血圧低下を示すサインです。このような症状が出た場合は透析を一時中断し、補液や酸素投与など緊急対応を行います。
血圧低下が長引くと臓器への酸素供給が不十分になり、深刻な合併症につながるおそれがあります。
- 失神時はすぐに医療スタッフへ声をかける
- 頭部への外傷がないか確認
- 意識が戻った後も安静を保ち、血圧を定期的に測定
循環不全への対応
循環不全を起こすと、心臓や脳などの重要臓器に十分な血液が行き渡らなくなります。早期の診断と治療が必要であり、医師や看護師による点滴や薬物投与の判断が下される場合もあります。
定期的に血圧を測定し、循環不全につながる前の段階で適切に処置を行うことが大切です。
- 循環動態を安定化する薬剤の使用
- 酸素供給の確保
- 血液検査で電解質や血球成分をチェックし、異常があれば速やかに補正
緊急時の初期対応方法
透析中に血圧が急激に下がったときは、一刻を争う対応が必要となる場合があります。実際には病院の医療スタッフが主体となって対処しますが、患者自身も基本的な流れを理解しておくと安心につながります。
この章では緊急時の主な初期対応を解説します。
血圧測定とポジショニング
血圧が下がったと感じたら、まずは血圧測定を行い、実際の数値を把握することが重要です。その際、頭を低く足を高くする姿勢(いわゆるショックポジション)を取ることで、重力を利用して脳への血流を助ける対応が行われます。
急激な体位変換はかえって症状を悪化させることもあるため、医療スタッフの指示を仰ぎながら安全にポジションを調整してください。
初期対応の要点一覧
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 血圧測定 | 可能な限り速やかに実測値を確認し、基準値との比較を行う |
| ポジショニング | 頭部を低く、下肢を高くする姿勢を取ると脳への血流量を補いやすくなる |
| 周囲への声かけ | 異変を感じたら早めにスタッフや家族に伝え、協力を求める |
| 心電図や脈拍測定 | 必要に応じて心電図や脈拍などを測定し、重症度を判断する |
透析条件の変更
血圧の低下が顕著な場合、透析スタッフは除水速度の緩和や透析液の温度設定などを変更します。生体情報モニターを参照しながら、症状の程度に応じて必要な対策を迅速に行います。
患者自身は無理に体を動かす必要はなく、安静を保ちながら状況を医療スタッフにしっかり伝えることが大切です。
補液や生理食塩水の活用
急に血圧が下がったときには、生理食塩水やアルブミン製剤などの補液を行って循環血液量を増やし、血圧を回復させる方法があります。
投与量は医師の判断によって決められ、過度の補液は心臓に負担をかける可能性もあるため、慎重なコントロールが求められます。
- 生理食塩水やブドウ糖液の投与
- 高ナトリウム透析液の一時的な使用
- 血圧を保つ薬剤の追加投与
緊急搬送が必要なケース
低血圧が持続して心不全や意識障害の兆候が強くなった場合、循環器科などの専門施設への緊急搬送が検討されます。症状が改善しない、もしくは悪化傾向が見られるときは速やかな判断が必要です。
救急車による搬送や集中治療室での管理が想定されることもあります。
透析後血圧低下対処と日常で気をつけたいポイント
透析が終わった直後でも血圧が下がり続けたり、少し遅れてから血圧低下が起きたりする場合があります。この状態を放置すると、日常生活にも支障を来す恐れがあります。
透析後血圧低下対処をしっかり行い、普段から注意点を押さえておくと安定した生活を営むうえで役立ちます。
透析後に起きやすい状態
透析後は、体から急激に水分や老廃物を除去した影響が残っていることがあり、以下のような状態になりやすいです。
- 血液量の低下による低血圧持続
- 脱力感や倦怠感
- 体液バランスの乱れによるむくみやけいれん
透析後に注意が必要な状態一覧
| 状態 | 対象となる症状 |
|---|---|
| 低血圧持続 | めまい、ふらつき、失神のリスク |
| 血糖値変動 | 糖尿病を合併している場合には低血糖や高血糖に注意 |
| 脱力感 | 筋肉の疲労や電解質異常で動きが悪くなる |
| 食欲低下 | 吐き気や食欲不振、栄養不足による体調不良 |
透析後血圧低下対処の具体策
透析直後に血圧を測定し、基準値より明らかに低い場合はしばらく休息を取ることが大切です。また、必要に応じて補液を行うことや、食事を摂ることで血液循環を安定させる方法があります。
過度な動作は避け、ゆっくりと体を慣らしてから立ち上がるようにすると、起立性低血圧を防ぎやすくなります。
自宅で観察すべき症状
病院での透析が終わった後、自宅に帰ってからの様子も重要です。体調が急変する場合もあるため、以下のような症状に注意してください。
- 夜間のめまいや吐き気
- 足や手の異常なむくみ
- 普段と比べて極端に疲れやすい
- 頻脈や不整脈を感じる
必要があれば透析後血圧低下対処に詳しい主治医へ連絡し、受診の判断を仰ぎましょう。
- 血圧計を使って定期的に測定
- 前後の体重差や食事内容の記録
- 水分摂取量を過不足なく管理
定期的な受診の重要性
透析前後の血圧変動が大きい人ほど、こまめな受診と検査が欠かせません。診察の際に血液検査や心電図などを行い、必要に応じて透析条件の調整や薬剤の変更を検討します。
異常を早期に察知し、合併症を回避するための連携を取り続けることが安心な透析生活の基盤となります。
予防を補助する生活習慣とサポート
血圧低下を予防する取り組みは透析中だけにとどまりません。普段の生活で適切な栄養バランスや水分管理を意識することで、透析時の血圧変動も緩やかになりやすいです。
家族や医療スタッフとの連携も含めて、総合的に取り組む姿勢が重要です。
塩分制限と栄養バランス
腎機能が低下している方にとって塩分過多は水分貯留を引き起こしやすく、透析時の負担を大きくします。塩分制限によって血圧コントロールが行いやすくなるだけでなく、心血管リスクの低減にもつながると考えられます。
タンパク質やカリウム、リンなどの栄養素も含めて、管理栄養士のサポートを受けることが有益です。
食事面で意識したい要素一覧
| 要素 | ポイント |
|---|---|
| 塩分 | 1日あたりの摂取目標を決め、食事全体でバランスを取る |
| カリウム | 野菜や果物の摂り方を調整し、過剰摂取を避ける |
| タンパク質 | 必要量を満たしながらも腎機能に負担がかからない範囲を考える |
| エネルギー | 適度なカロリー摂取で体力を維持し、やせすぎにも注意 |
こまめな水分補給のコツ
透析患者は水分制限が必要になる場合がありますが、まったく摂らないわけにもいきません。必要量を把握したうえで、少しずつこまめに摂取することで、体液バランスを維持しやすくなります。
飲料の種類や温度を工夫して、無理のない範囲で摂取量を調整してください。
- カフェイン入り飲料の過剰摂取は避ける
- 自分専用の水筒などで摂取量を見える化
- 砂糖や塩分の入った飲み物に注意
ストレスと睡眠
ストレスや睡眠不足は自律神経の乱れにつながり、血圧の調節を難しくします。透析に伴う体の負担や生活リズムの乱れがストレス要因となる場合も多いため、適度な休養やリラクゼーション法を取り入れることが大切です。
血圧管理のための協力体制
自分ひとりで生活習慣を管理するのは難しい場面も出てきます。家族や医療スタッフの協力を得ながら、食事管理や定期的な血圧測定をサポートしてもらうと継続しやすくなります。
特に高齢者や合併症を持つ方は、通院時だけでなく、日常生活全般のフォロー体制を整えておくと安心です。
血圧低下を防ぐために医療機関で行う取り組み
病院やクリニックでは、患者が安全に透析を受けられるよう多角的な配慮を行っています。血圧低下を防ぐためのモニタリングや透析条件の細かい調整など、医療者が行っている取り組みを知ることで患者自身の理解も深まります。
医師や看護師が行うモニタリング
透析中は定期的に血圧や脈拍、呼吸数、体温、酸素飽和度などをモニタリングします。異常が見られた場合はすぐに除水量の変更や透析条件を見直し、症状の進行を抑えるように工夫しています。
患者側も体調の変化を申し出ることで、医療スタッフとの情報共有が円滑に進みます。
主なモニタリング項目一覧
| 項目 | 意味 |
|---|---|
| 血圧 | 低下が続く場合は除水量調整や補液などの対策が必要になる |
| 心拍数 | 不整脈の有無や循環状態を知る手がかり |
| 酸素飽和度 | 酸素の取り込み状態を把握し、必要に応じて酸素投与を検討 |
| 呼吸数・体温 | 全身状態の変化を捉えるための基本的なバイタルサイン |
透析装置や技術の工夫
近年では透析装置が高機能化し、血圧低下を抑えるためのさまざまな機能を備えています。例えば、透析液の温度制御やナトリウム濃度の調整、除水速度の自動制御などが挙げられます。
患者の体調をリアルタイムで観察しながら機械的にフィードバックするシステムも活用され、急激な変動を抑えやすくなっています。
透析条件の適切な調整
透析時間や除水量の設定は患者の腎機能や心機能、体重増加量などを考慮して個別に決めます。医療スタッフは透析中の血圧変動を見ながら微調整し、余裕を持った水分除去を行うように心がけています。
過度に水分を引きすぎると血圧が下がるリスクが高まるため、バランスを取ることが重要です。
- 透析時間を延ばして除水速度を緩やかにする
- 医療スタッフによる声掛けで患者の体調変化を常に確認
- 電解質バランスを見ながら透析液の設定を柔軟に変更
緊急対応の訓練
病院内では、急激な血圧低下や心停止などの緊急事態に備えた訓練が定期的に行われます。医師や看護師だけでなく、臨床工学技士や薬剤師など関連職種が連携し、迅速な救命処置を実施できる体制を整えています。
患者からの情報提供と職員間の情報共有がスムーズに進むよう、職員間でのコミュニケーションも重視しています。
チーム連携における役割一覧
| 職種 | 主な役割 |
|---|---|
| 医師 | 診断、治療方針の決定、必要な薬剤や検査を指示 |
| 看護師 | バイタルサインの観察、日常的なケア、患者とのコミュニケーション |
| 臨床工学技士 | 透析装置の管理・調整、機器トラブルの対処 |
| 薬剤師 | 薬の調剤と服薬指導、相互作用の確認 |
よくある質問
透析を受ける方やそのご家族が気にかけることの中には、血圧低下に関する疑問が多々含まれています。よく寄せられる質問とその対応のポイントをまとめました。安心して透析治療に臨むための参考にしていただければと思います。
- 血圧が下がりやすい人は透析時に何を注意すべきか
-
心臓や血管の状態が万全でない方や、高齢で自律神経が乱れやすい方は特に注意が必要です。除水量を少しずつ設定してもらいながら、透析中は医療スタッフとこまめにコミュニケーションを取ってください。
めまいや頭痛を感じ始めた段階で早めに声をかけることで重篤化を防げます。体重増加に気を配り、透析間の過剰な水分摂取を避けることも大切です。
- 血圧を上げる食事はあるのか
-
急激に血圧を上げる食品を探すより、普段からバランスの良い食事を心がけるほうが結果として血圧の安定につながりやすいです。
塩分は一時的に血圧を上げることがありますが、長期的には水分過多になりやすく透析時の負担が大きくなるため注意が必要です。
管理栄養士の指導を受けながら自分に合った食事を続けると、長期的な血圧コントロールの面でメリットがあります。
- 自宅血圧管理と透析の関係
-
透析の有無にかかわらず、血圧は日々変動します。自宅で朝晩に定期的に測定し、その値を記録して透析日に医療スタッフと共有すると、より精密な評価と透析条件の調整につながります。
夜間や早朝に極端な血圧変化が見られる場合は、透析後血圧低下対処の観点からも追加の検査や生活習慣の見直しが必要となることがあります。
- 血圧低下を繰り返す時の相談窓口
-
繰り返し血圧が下がる方は、主治医や看護師に相談して透析治療の内容を見直すことが第一です。場合によっては循環器科など他科との連携で検査を受け、心臓の状態や血管の状態を確認することもあります。
生活習慣や食事内容を含めて総合的に診断し、対策を立てるために病院やクリニックの地域連携窓口を活用する方法も考えられます。
以上
透析センター(人工透析) | 大垣中央病院(医療法人社団豊正会 )
参考文献
REEVES, Patrick B.; MC CAUSLAND, Finnian R. Mechanisms, clinical implications, and treatment of intradialytic hypotension. Clinical journal of the American Society of Nephrology, 2018, 13.8: 1297-1303.
KANBAY, Mehmet, et al. An update review of intradialytic hypotension: concept, risk factors, clinical implications and management. Clinical Kidney Journal, 2020, 13.6: 981-993.
HAMRAHIAN, Seyed Mehrdad, et al. Prevention of intradialytic hypotension in hemodialysis patients: Current challenges and future prospects. International Journal of Nephrology and Renovascular Disease, 2023, 173-181.
PALMER, Biff F.; HENRICH, William L. Recent advances in the prevention and management of intradialytic hypotension. Journal of the American Society of Nephrology, 2008, 19.1: 8-11.
CHOU, Jason A.; KALANTAR‐ZADEH, Kamyar; MATHEW, Anna T. A brief review of intradialytic hypotension with a focus on survival. In: Seminars in dialysis. 2017. p. 473-480.
SULOWICZ, W.; RADZISZEWSKI, A. Pathogenesis and treatment of dialysis hypotension. Kidney International, 2006, 70: S36-S39.
BRADSHAW, Wendi. Intradialytic hypotension: a literature review. Renal Society of Australasia Journal, 2014, 10.1: 22-29.
MCINTYRE, Christopher W.; SALERNO, Fabio R. Diagnosis and treatment of intradialytic hypotension in maintenance hemodialysis patients. Clinical Journal of the American Society of Nephrology, 2018, 13.3: 486-489.
SARS, Benedict; VAN DER SANDE, Frank M.; KOOMAN, Jeroen P. Intradialytic hypotension: mechanisms and outcome. Blood purification, 2020, 49.1-2: 158-167.
ASSIMON, Magdalene M.; FLYTHE, Jennifer E. Definitions of intradialytic hypotension. In: Seminars in dialysis. 2017. p. 464-472.