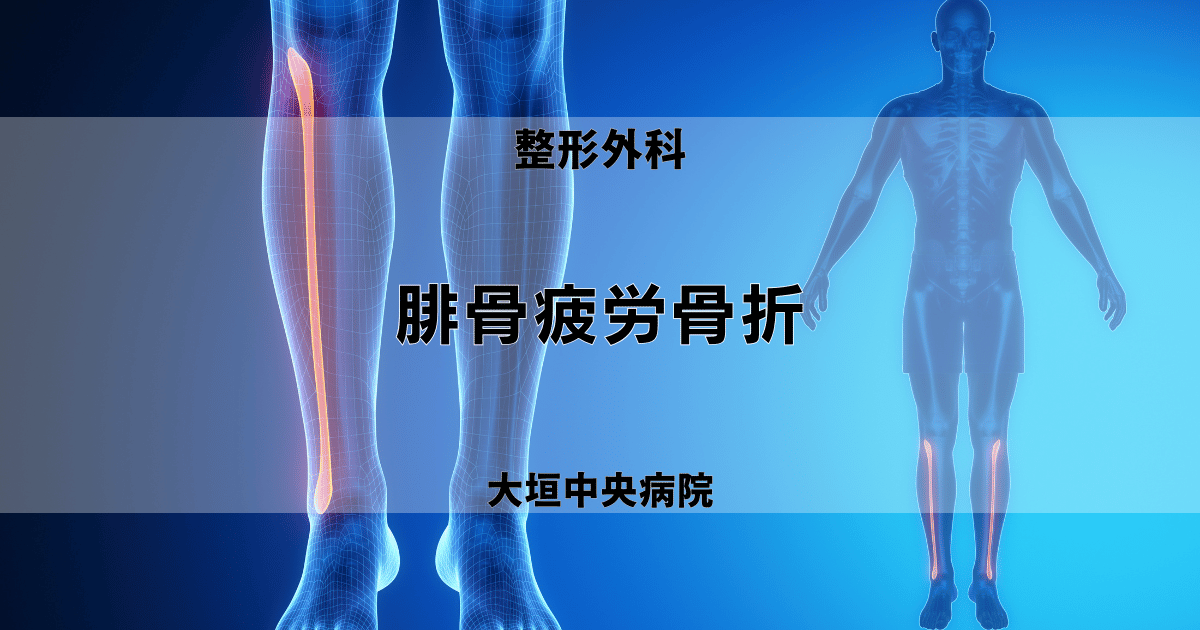腓骨疲労骨折(ひこつひろうこっせつ)(Fibular stress fracture)とは、足首から膝にかけての外側にある腓骨に繰り返し負荷がかかり、骨修復が追いつかず骨にわずかなヒビが入る状態です。
マラソンや長距離走などのスポーツ、長時間の歩行、立ち仕事などが原因で発症します。
痛みを放置すると症状が悪化し、競技や仕事に大きな支障をきたすおそれがあるため、早めの検査と治療が欠かせません。
この記事の執筆者

臼井 大記(うすい だいき)
日本整形外科学会認定専門医
医療社団法人豊正会大垣中央病院 整形外科・麻酔科 担当医師
2009年に帝京大学医学部医学科卒業後、厚生中央病院に勤務。東京医大病院麻酔科に入局後、カンボジアSun International Clinicに従事し、ノースウェスタン大学にて学位取得(修士)。帰国後、岐阜大学附属病院、高山赤十字病院、岐阜総合医療センター、岐阜赤十字病院で整形外科医として勤務。2023年4月より大垣中央病院に入職、整形外科・麻酔科の担当医を務める。
腓骨疲労骨折の病型
腓骨疲労骨折(ひこつひろうこっせつ)は、骨に大きな外力が加わる「骨折」とは異なり、繰り返しの負荷によって微小な損傷が蓄積して起こります。
明確な国際統一の分類はありませんが、部位や骨折の程度、骨の状態(MRI所見など)で臨床的に分類・評価されるケースが多いです。
部位による分類
- 腓骨近位部(膝周辺に近い部分)
- 腓骨遠位部(足首に近い部分)
- 腓骨中央部(近位部と遠位部の中間域)
一般的に疲労骨折は下腿(脛骨・腓骨)の中央〜遠位部に起こりやすいとされています。
骨折の程度による分類(グレード分類)
疲労骨折の場合は、MRI所見で骨髄浮腫(骨の中のむくみ)や骨皮質の連続性の乱れなどを評価し、Grade 1〜4に分けるケースが一般的です。
グレードが上がるほど症状や治癒期間が長期化しやすく、治療も厳重な固定などが必要となる場合があります。
- Grade 1:骨膜炎など、骨折線は明らかではないが痛みとMRIでの変化がある
- Grade 2:骨折線は見られないが、より強い骨髄浮腫(炎症像)がある
- Grade 3:骨折線が一部確認できる
- Grade 4:骨折線がはっきり確認でき、骨皮質にも連続性の乱れが明瞭にある
腓骨疲労骨折の症状
腓骨疲労骨折(ひこつひろうこっせつ)の症状は、初期段階では軽度の違和感を覚える程度です。
しかし、痛みを自覚しつつも運動を続ける人が多く、気づかないまま進行してしまうケースも少なくありません。
初期段階の症状
- ランニング時に下腿外側に軽い鋭い痛みがある
- 歩行時に小さな痛みがあるが、休むと消える
- 階段の上り下りで少し違和感を覚える
- 足首を回したときにピリッとくる痛みを感じる
足首から膝にかけて軽い痛みや違和感がある場合、腓骨への負荷が蓄積しているおそれがあるため、早めに運動量を調整し、整形外科で相談することが大切です。
中期から後期にかけての症状
- 運動開始時や運動後だけではなく、安静時や夜間も鈍痛が続く
- 歩行やランニング時に鋭い痛みを感じ、運動を制限する必要がある
- 外部から腓骨部分を押すと激痛が走る
- 腓骨付近の腫れや軽い熱感がある
疲労骨折が進行すると、痛みがはっきりとわかるようになり、運動や日常生活が困難となる場合があります。
骨折の亀裂が大きくなっている可能性が高いため、専門的な検査が必要です。
痛み以外の症状
- ふくらはぎの外側の筋肉が硬くなり、触れるとごわつく
- 足首周りの可動域がやや狭くなる
- ランニングフォームや歩くときの姿勢が崩れる
- 足の裏の接地バランスが乱れる
腓骨疲労骨折の主な症状は痛みですが、筋肉や可動域の変化、姿勢の崩れなど、身体にさまざまな変化が現れる場合もあります。
腓骨疲労骨折の原因
腓骨疲労骨折(ひこつひろうこっせつ)は、日常生活や運動習慣のなかで、足に繰り返し負荷がかかって生じます。
運動習慣と負荷の増加
日常的にスポーツをしている人は、疲労骨折のリスクが高まるため注意が必要です。
とくに、下腿部に負荷が集中する運動を短期間に増やしすぎた場合、腓骨に大きな負担がかかります。
【腓骨に負荷をかけやすいスポーツ例】
- 長距離走(マラソン、トライアスロン、駅伝など)
- バスケットボールやバレーボールなどのジャンプ系競技
- サッカーなどサイドステップを多用するスポーツ
- ダンスやエアロビクスなど繰り返し足首を使う運動
骨は適度な負荷を受けると強くなる性質がありますが、一気に負荷が増えると修復が追いつかず、疲労骨折へと発展しやすくなります。
体の使い方の癖
走り方や歩き方の癖は、腓骨に局所的に強いストレスをかける原因となります。歩行やランニング時に、足を外側や内側にひねって着地する癖がある方は注意が必要です。
また、古い靴を使い続けている場合や、サイズが足に合っていない場合も、腓骨疲労骨折の発症リスクを高めます。
筋肉の疲労や柔軟性の低下
筋肉や腱の柔軟性が低下していると、衝撃を吸収しきれず骨に直接ダメージが及びやすくなります。
また、筋力が低下している状態では、下腿周りをしっかり支えられず腓骨に余分な負荷がかかりかねません。
とくに以下のような状況が続くとリスクが高まります。
- ウォーミングアップやクールダウンを十分に行わない
- 連日ハードな練習をして睡眠不足のまま続ける
- 長期間休みなしでトレーニングを行い、筋疲労がたまる
- 急に激しい運動を始めて筋力不足のまま負荷をかける
外傷歴やバイオメカニクスの問題
以前のケガの影響や、先天的・後天的なアライメント(下肢の骨配列)異常があると、腓骨に負荷がかかる場合があります。
とくに、O脚やX脚で膝や足首の角度に偏りがあると、腓骨に負荷が集中しやすくなります。
また、足裏のアーチ崩れ(偏平足やハイアーチ)も、腓骨疲労骨折のリスクを高める要因です。足裏に均等に体重が乗らず、腓骨周辺にストレスがかかりやすくなります。
骨密度や栄養状態
骨密度が低い人ほど、骨折のリスクが高まります。とくに若年層や高齢者、女性アスリートで月経異常がある場合は注意が必要です。
栄養バランスが崩れていると、骨の回復力が落ち、疲労骨折を起こしやすくなります。
【骨密度を低下させる主な原因】
- カルシウムやビタミンD、タンパク質の摂取不足
- 極端なダイエットによるエネルギー不足
- ホルモンバランスの乱れ
腓骨疲労骨折の検査・チェック方法
腓骨疲労骨折(ひこつひろうこっせつ)の早期発見には、専門的な検査が欠かせません。触診と問診に加えて、レントゲンやMRIなどの画像検査を行います。
触診と問診
触診や問診を通じて、痛みの部位や程度、発症時期、普段の運動習慣などを細かく確認します。
腓骨を軽く圧迫したときに痛みが走ったり、特定の姿勢で激痛が出たりする場合は疲労骨折を疑います。
【主な問診内容】
- いつから痛みが始まったか
- どのタイミングや動作で痛みが強くなるか
- 運動や生活習慣に変化はあったか
- 以前に同じ部位を痛めたことがあるか
画像検査
画像検査では、初期にレントゲン検査を行い、必要に応じてMRIや骨シンチグラフィー、CTなどを追加します。
| 検査方法 | 特徴 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
| レントゲン | 一般的なX線撮影 | ・簡便でコストが比較的安価 ・ある程度進行した段階では、骨膜の反応や骨折線を確認可能 | 疲労骨折の初期段階では骨折線が写らない場合がある |
| MRI | 磁気を利用して断面画像を撮影 | ・軟部組織や早期骨変化を確認可能 ・疲労骨折の初期段階の診断に有用 | ・検査費用が高め ・検査時間が長い |
| 骨シンチグラフィー | 放射性医薬品を用いて骨の代謝を撮影 | 疲労骨折か否かの判別がしやすい | ・被ばくのリスクが懸念される ・検査設備が限られる ・MRIよりも局所的診断精度が低い |
| CT | X線で断層撮影を行い、3D画像を構成 | ・骨の形状を立体的に把握できる ・骨折線を正確に描出するのに役立つ | ・被ばく量がやや多い ・費用が高め |
セルフチェック方法
自分でも、ある程度は腓骨疲労骨折の可能性をチェックできます。ただし、痛みが続く場合は専門医の診断を受けることが大切です。
【セルフチェックのポイント】
- 腓骨の外側を軽く押して痛みがあるかを確かめる
- 片足立ちでバランスをとるときに外側に痛みが出るかを確認する
- 足首をゆっくり回したときに特定の方向で痛みが走るかを見る
- 朝起きたときや運動後に、下腿外側の鈍痛や張りを感じるかをチェックする
腓骨疲労骨折の治療方法と治療薬、リハビリテーション、治療期間
腓骨疲労骨折(ひこつひろうこっせつ)の治療は、骨折の程度や患者さんのライフスタイル、競技レベルなどに応じて異なります。
基本的には保存的治療で骨癒合を目指しますが、骨折の進行度によっては手術が必要です。
回復には時間がかかるものの、段階的にリハビリテーションを行うことで再発リスクを下げられます。
保存療法
| 保存療法の種類 | 説明 |
|---|---|
| 免荷、荷重制限 | 痛みが強い場合は、松葉杖などを用いて腓骨の負担を減らす |
| ギプスや装具での固定 | ・骨折部位を安定させ、痛みや骨への刺激を減らす ・脛骨の疲労骨折に比べて、ギプスによる完全固定が必要になるケースは少ない |
| サポーターやテーピングの利用 | 動きを完全に制限せず、ある程度の活動を可能にする |
| 痛み止めの内服薬や外用薬 | NSAIDs(非ステロイド性抗炎症薬)や消炎鎮痛外用薬などを使って痛みを軽減する |
| 安静と運動療法 | 患部に大きな負荷をかけない範囲で筋力維持のトレーニングを行う |
保存療法では、痛みが出ている段階で負荷を減らし、骨が修復するのを待ちながら筋力維持と柔軟性向上を図ります。
骨の連続性が途絶え、変形や転位を伴うようなケース(重症度が非常に高い場合)を除いては、手術となるケースはまれです。
保存療法で使うことが多い治療薬
| 薬の種類 | 例 | 主な作用 |
|---|---|---|
| NSAIDs(非ステロイド性抗炎症薬) | ロキソプロフェン、イブプロフェンなど | 炎症と痛みの軽減 |
| 消炎鎮痛外用薬 | 湿布やゲル、クリームなど | 患部への直接アプローチ |
| ビタミン剤 | ビタミンD、ビタミンCなど | 骨代謝や組織修復をサポート |
手術療法
腓骨疲労骨折ではまれですが、骨折線が大きく広がっている場合や骨癒合が期待しにくい場合、再発を繰り返している場合は手術を検討します。
手術では骨折部位に金属製のプレートやスクリューを固定し、安定性を高めます。術後は固定具によるサポートとともにリハビリテーションを行い、徐々に負荷を増やすことが重要です。
手術後は痛みの軽減が期待できますが、固定具の抜去手術が必要な場合があります。
また、傷口の感染症リスクや固定不良などの合併症にも注意しなければなりません。
リハビリテーションの流れ
リハビリテーションは骨折が判明した直後から始めます。痛みがある期間も、患部以外の部位や軽いストレッチなど、できることはたくさんあります。
| 急性期(骨折判明後~痛みが強い期間) | ・患部の安静確保 ・アイシングや軽い筋収縮運動(患部以外の筋力維持を目的) ・消炎鎮痛剤の使用など |
|---|---|
| 回復期(痛みがやや落ち着いてきたころ) | ・サポーターや装具をつけながら軽い負荷をかける ・関節可動域訓練、筋力強化トレーニング ・バランストレーニング |
| 最終期(痛みがほとんどない状態) | ・スポーツ復帰に向けた専門的トレーニング ・運動量を徐々に増やし、再発防止のフォーム指導 ・インソールやシューズ選びの見直し |
治療期間の目安
| 回復ステージ | 期間の目安 | 内容 |
|---|---|---|
| 安静~固定期間 | 2~4週間 | 痛みの軽減、患部保護、安静と軽い運動 |
| 軽負荷のリハビリ期 | 4~8週間 | 関節可動域拡大、低負荷トレーニング |
| 徐々に負荷を増加させる時期 | 8~12週間 | 競技復帰の準備、フォーム改善 |
| スポーツ復帰・日常復帰 | 12週以降~ | 正常な動作や競技パフォーマンスの回復 |
腓骨疲労骨折の治療期間には個人差がありますが、6~12週間程度が目安です。
アスリートの方の場合、完全にもとの競技レベルへ復帰するには、それ以上の時間が必要な場合もあります。
痛みが完全になくなっても、骨の強度が十分に回復していない可能性があるため、医師や理学療法士の判断に従ってリハビリテーションを進めていきましょう。
薬の副作用や治療のデメリット
腓骨疲労骨折(ひこつひろうこっせつ)の治療法には、それぞれ副作用やデメリットもあります。
薬の副作用
- 胃腸障害:NSAIDsを長期間服用すると、胃粘膜を刺激して胃痛や胃もたれ、胃潰瘍のリスクが上がる
- 腎臓への負担:高齢者や腎機能が低下している人は、腎臓に負担がかかる可能性がある
- アレルギー反応:皮膚の発疹やかゆみ、呼吸困難などを引き起こすケースがまれにある
腓骨疲労骨折の痛みを和らげるために痛み止めや消炎鎮痛薬(NSAIDs)を使用すると、胃腸や腎臓に負担をかけるおそれがあるため、自己判断で薬を長期使用しないよう注意してください。
医師や薬剤師から示された用法・用量を守り、何らかの異常を感じたらすぐに医療機関へ相談しましょう。
長期固定・安静による筋力低下
ギプスや装具などで長期固定を行う場合、患部だけではなく全身の筋力や柔軟性が低下しやすくなります。
また、血行不良が起こり、関節の動きの制限されるケースも少なくありません。
とくに、下半身を使わない期間が続くと、筋力が落ちてしまい、リハビリテーションが長引くおそれがあります。
手術療法のリスク
- 麻酔のリスク:全身麻酔や局所麻酔に伴うアレルギー反応や合併症
- 感染症:手術部位の細菌感染、術後管理が不十分な場合に悪化する
- 再手術の可能性:金属プレートやスクリューが外れた場合や、うまく骨癒合しなかった場合リスト
手術療法には、麻酔のアレルギー反応や手術部位の感染などのリスクが伴います。
また、手術方法や術後の固定方法によっては、再手術が必要となるケースもあるため、慎重に判断する必要があります。
手術のデメリット
| デメリット | 具体例 | 対処策 |
|---|---|---|
| 麻酔や手術そのもののリスク | 麻酔事故、血栓症、出血、神経損傷など | 術前検査を十分に行い慎重に判断する |
| リハビリ期間の延長 | 傷口の治癒が遅れるなどで回復が遅くなる | 医師や理学療法士の指示を守る |
| 固定具の不具合 | 金属製プレートやスクリューのゆるみ | 定期的に画像検査でチェック |
保険適用と治療費
以下に記載している治療費(医療費)は目安であり、実際の費用は症状や治療内容、保険適用否により大幅に上回ることがございます。当院では料金に関する以下説明の不備や相違について、一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。
腓骨疲労骨折(ひこつひろうこっせつ)の検査や治療は、多くのケースで保険が適用されます。
| 治療内容 | 保険適用の有無 | 自己負担割合 | 代表的な費用の目安 |
|---|---|---|---|
| レントゲン検査 | あり | 約3割 | 1,000~2,000円/1部位 |
| MRI検査 | あり | 約3割 | 5,000~10,000円 |
| 保存療法(装具) | あり | 約3割 | 装具代として1万~2万円前後 |
| 手術療法 | あり | 約3割 | 手術費+入院費で数万~数十万円 |
費用はあくまで目安であり、症状や治療内容、自己負担割合により実際の金額は異なるため、各医療機関にお問い合わせください。
画像検査の費用目安(3割負担)
- レントゲン検査:1部位あたり約1,000~2,000円
- MRI検査:1回あたり約5,000~10,000円
- CT検査:1回あたり約3,000~6,000円
- 骨シンチグラフィー:1回あたり約5,000~10,000円
施設ごとに検査機器や検査項目が異なるため、実際の費用は前後します。
保存療法の費用目安(3割負担)
保存療法の場合、主に装具やサポーター、薬代、リハビリの費用がかかります。
- 診察・装具費:数千円~数万円(足首固定用の装具は、保険が適用されれば自己負担1万~2万円ほどになる場合もある)
- リハビリ費:1回あたり数百円
- 薬代:NSAIDsなどを2週間分処方された場合、数百円~1,000円ほど
手術療法の費用目安(3割負担)
手術療法では入院費や手術費がかかるため、保存療法よりも総額が大きくなる傾向があります。
- 入院費(1日あたり):食事代含めて約5,000~15,000円
- 手術費:金属固定の場合で約10万~30円(自己負担は3割で高額療養費の対象になる場合もある)
- 術後のリハビリ費:1回あたり数百円
高額療養費制度の活用
長期入院や手術などで1カ月の医療費負担が高額になった場合は、高額療養費制度の活用によって経済的負担を軽減できる可能性があります。
所得や家族構成によって自己負担の限度額が異なるため、医療費がかさむ場合は事前に制度を確認してください。
以上
参考文献
SANDERLIN, Brent W.; RASPA, Robert F. Common stress fractures. American family physician, 2003, 68.8: 1527-1532.
ORAVA, S. Stress fractures. British journal of sports medicine, 1980, 14.1: 40.
BURROWS, H. Jackson. Fatigue fractures of the fibula. The Journal of Bone & Joint Surgery British Volume, 1948, 30.2: 266-279.
SCRANTON JR, PIERCE E.; MCMASTER, JAMES H.; KELLY, EDWARD. Dynamic fibular function: a new concept. Clinical Orthopaedics and Related Research (1976-2007), 1976, 118: 76-81.
HONG, Seoung Hwan; CHU, In Tak. Stress fracture of the proximal fibula in military recruits. Clinics in orthopedic surgery, 2009, 1.3: 161-164.
WOODS, Michael, et al. Magnetic resonance imaging findings in patients with fibular stress injuries. Skeletal radiology, 2008, 37: 835-841.
EMERY, Sanford E., et al. Tibial stress fracture after a graft has been obtained from the fibula. A report of five cases. JBJS, 1996, 78.8: 1248-51.
GILL, J. Brian, et al. Comparison of manual and gravity stress radiographs for the evaluation of supination-external rotation fibular fractures. JBJS, 2007, 89.5: 994-999.
SHERBONDY, Paul S.; SEBASTIANELLI, Wayne J. Stress fractures of the medial malleolus and distal fibula. Clinics in sports medicine, 2006, 25.1: 129-137.
EGOL, Kenneth A., et al. Ankle stress test for predicting the need for surgical fixation of isolated fibular fractures. JBJS, 2004, 86.11: 2393-2398.
BODEN, Barry P.; OSBAHR, Daryl C.; JIMENEZ, Carlos. Low-risk stress fractures. The American journal of sports medicine, 2001, 29.1: 100-111.