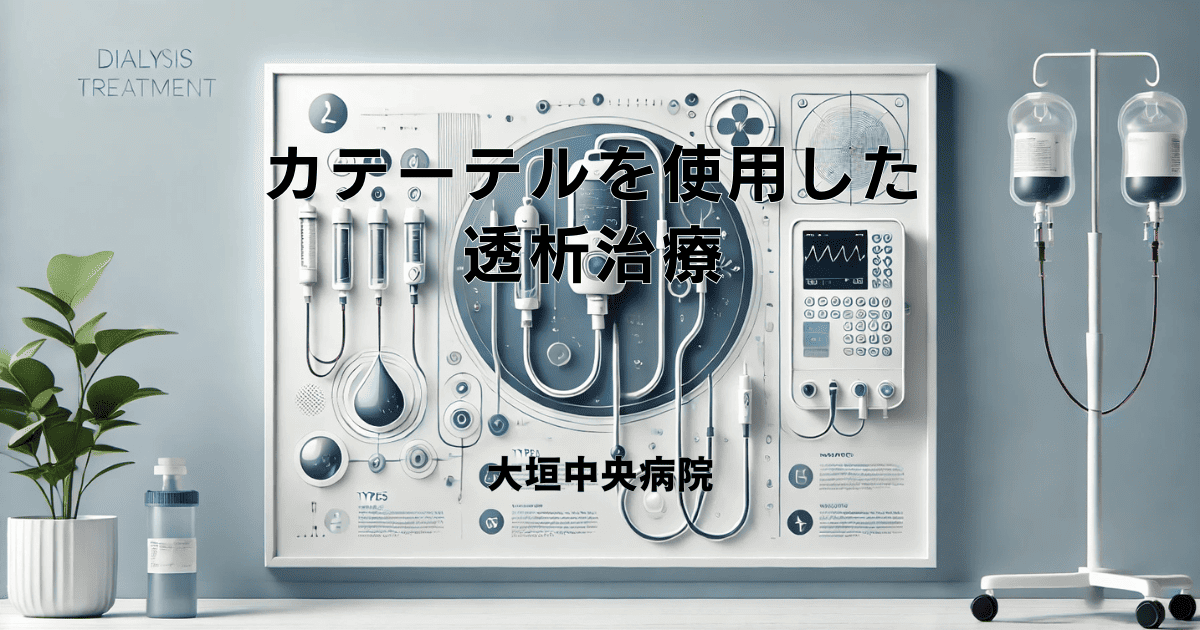透析治療では血液を体外に導き、余分な水分や老廃物を除去します。その際、静脈へチューブを入れる方法を選択する場面があります。血管の状態によっては透析カテーテルを挿入して透析を行うこともあります。
カテーテルを使うときには適切な管理が重要です。血管への挿入方法、材質の違い、合併症を防ぐための清潔保持など、注意すべきポイントが多くあります。
治療を受ける方が安心して透析に臨むためにも、正しい知識を知ることが大切です。
この記事ではカテーテル挿入部位を含む具体的な方法やカテーテル種類の解説、日常生活での留意点などをわかりやすく紹介します。
カテーテルを利用した透析治療の概要
透析には大きく分けて血液透析と腹膜透析がありますが、血液透析を行う際に必要になる血管ルートの1つとして、透析カテーテルを用いる方法があります。通常、内シャント(AVF)を作成して血液透析を行うことが多いです。
しかし血管の状態が十分でない場合や、緊急透析の必要があるケースではカテーテルを選択します。治療効果を高めるためにも、カテーテル利用の特徴や管理方法について理解しておくことが重要です。
透析治療におけるカテーテルの役割
カテーテルは血液を体外に導き出し、透析装置へ運ぶためのチューブです。シャントを作成するまでの一時的な手段として使う場合もあれば、長期間にわたって使用することもあります。
柔軟性を持つ素材で作られたものが多く、身体への負担がなるべく軽減されるように工夫されています。
カテーテルの基本構造
カテーテルの管には血液が流れる通路が2本以上備わっています。透析装置へ血液を送る管と、浄化された血液を戻す管に分かれます。
素材にはポリウレタンやシリコンが使われ、使用期間や挿入部位に応じて形状や太さが異なります。
透析とカテーテルの関係
血液透析では十分な血液量を確保しながら、血液を速やかに装置へ導き出し、透析後に体内へ戻します。
シャントに比べるとカテーテルは感染リスクや血管合併症のリスクが上がる傾向があり、また長期的に利用する場合に詰まりが起こりやすいといった問題が生じる可能性があります。
一方で緊急時にはすぐ対応できるメリットもあるため、患者の状況に合わせて選択されます。
カテーテルとシャントの主な違い
| 項目 | カテーテル | シャント(AVF) |
|---|---|---|
| 透析開始までの期間 | 挿入後すぐに可能 | 作成後2~4週間の成熟期間が必要 |
| 感染リスク | やや高い | 比較的低め |
| 使用期間 | 短期~長期(種類による) | 半永久的 |
| メンテナンスの頻度 | 定期的な交換や管理が必要 | 比較的長期間維持できる |
| 血管状態への依存度 | 血管状態が悪くても対応できる場合有 | 血管の良好な状態が必要 |
カテーテル挿入部位の選択の重要性
カテーテル挿入部位は治療効果と合併症のリスクを左右するため、医療者が慎重に決定します。
中心静脈、例えば内頸静脈や鎖骨下静脈、大腿静脈などが候補になりますが、それぞれの血管が持つ特徴や患者の身体状況によって適切な部位を選択します。
血管の選択と合併症のリスク
中心静脈にカテーテルを入れる場合、血管穿刺そのものによる合併症のリスクがあります。気胸や血胸などの可能性がありますが、医師が超音波ガイドなどを用いて丁寧に挿入することでリスクを抑えます。
周術期には血栓形成や感染を最小限にとどめるための管理も重要になります。
カテーテル挿入部位ごとの特徴
内頸静脈にカテーテルを挿入すると血流が良好で、透析効率が期待できます。大腿静脈は挿入しやすい一方で、局所感染や日常的な動作によるトラブルのリスクが比較的高いといわれます。
鎖骨下静脈は挿入時の合併症が比較的多いとされますが、固定しやすく安定しやすいメリットがあります。
カテーテル種類に応じた適用範囲
カテーテルには短期用や長期用など、さまざまな種類があります。短期用は急性期の透析やシャント作成までのつなぎとして使う場合が多いです。
長期用は移植までの期間やシャントが作りにくい場合に用いることが多く、材質や構造がより安定性を重視して設計されています。
挿入部位と特徴の対比
| 挿入部位 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 内頸静脈 | 血流量が大きく透析効率が良い | 首元にあるため日常生活での負担を感じることがある |
| 鎖骨下静脈 | 埋め込みやすく固定が安定しやすい | 穿刺時に気胸などのリスクが比較的高い |
| 大腿静脈 | 手技が簡便で緊急挿入しやすい | 歩行や座位での摩擦に注意しないと感染リスクが上がる |
透析カテーテルの種類~短期用と長期用
透析カテーテルには大まかに分けて短期用と長期用があります。カテーテル種類の選択は治療期間や目的、患者の血管状態など多角的な視点で行います。
誤った選択や管理は合併症につながる可能性があるため、慎重な判断と専門的な評価が必要です。
短期用カテーテル
緊急透析が必要な場合、またはシャントが完成するまでのつなぎとして短期用カテーテルを使います。大腿静脈や内頸静脈など、太い静脈に挿入しやすいものを選ぶケースが多いです。
取り扱いが比較的簡易である一方、感染や血栓のリスクがあるため、こまめな観察や管理が必要です。
長期用カテーテル
シャント作成が困難な場合、あるいは移植までの長期間にわたって血液透析を行うときには長期用カテーテルを選択します。カフ付きカテーテルと呼ばれる、皮下組織と癒合して固定性を高める装置が付いている製品が多いです。
このカフ部分が外部からの細菌侵入を抑える機能をもつと考えられます。
それぞれのメリットとデメリット
短期用は手技的な負担が少なく、必要に応じて速やかに挿入と抜去ができる利点がありますが、管自体が細菌感染や血栓によって詰まりを起こしやすいという弱点があります。
長期用は安定的に透析を続けやすい半面、抜去時にはある程度の時間と手術操作が必要になります。透析カテーテルの特徴を十分に理解し、医療スタッフと相談したうえで選ぶことが大切です。
短期用と長期用の比較
| 種類 | 使用期間 | 主な使用目的 | メンテナンス頻度 |
|---|---|---|---|
| 短期用 | 数日~数週間 | 緊急透析や一時的な透析 | 頻繁な観察や交換が必要 |
| 長期用 | 数か月~数年 | シャント作成困難時や長期治療 | 定期的な評価と交換が必要 |
カテーテル挿入時の流れと注意点
カテーテル挿入には手技的な技術が求められますが、患者にとっても体位保持などの協力が必要です。安全かつ円滑に治療を行うために、事前の説明や検査、患者本人の理解が大切です。
挿入前の準備
血管超音波検査などで挿入可能な血管を評価し、患者の凝固機能や感染症の有無を調べます。必要に応じて抗生物質の投与や血液検査を行い、血管出血のリスクを把握したうえでカテーテルを用意します。
患者には処置の流れや必要とされる安静時間などを説明し、精神的な安心感を得てもらうよう配慮します。
手技の流れ
消毒を徹底し、局所麻酔を行ったうえで血管を穿刺します。穿刺針を使ってガイドワイヤーを挿入し、その上からカテーテルを血管内に入れる方法が一般的です。
ガイドワイヤーが血管内でどう動いているかを透視や超音波で確認し、位置を調整します。適切な深さや向きになるように挿入を終えたら、縫合などで固定し、血液透析が行えるかどうかテストを実施します。
カテーテル挿入後に観察する点
血液透析中の血流量が十分に保たれているか、カテーテル周囲に出血や皮下出血がないか、感染の兆候がないかなどを観察します。異常があれば早期に対処し、必要に応じてカテーテルの再挿入や位置調整を検討します。
患者には挿入部位の痛みや腫れ、発熱などの症状が出た場合にすぐ報告してもらうよう促します。
挿入時に着目するポイント
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 血管の状態 | 静脈の太さ、走行、周囲組織との位置関係などを評価 |
| 感染リスク管理 | 消毒の徹底、清潔操作、周辺環境の維持 |
| 挿入後の固定 | カテーテルが外れないように医療用テープや縫合などで固定 |
| 患者の体調変化 | 血圧、脈拍、呼吸状態、痛みの強さなど全身状態を定期的に確認 |
| 位置確認 | 挿入後にエックス線や超音波を使って先端位置をチェック |
透析カテーテル管理のポイント
透析カテーテルを長期にわたって使用する場合、管理の質が治療成績に直結します。感染や閉塞といった合併症を防ぐためのポイントを理解して、医療者と患者が協力してケアを行うことが重要です。
カテーテル周囲の清潔保持
清潔さを保つために、挿入部位のドレッシング交換が必要になります。ガーゼや透明ドレッシング材を用いて傷口を保護し、湿潤環境を過度に作らないようにします。
交換は数日おきに行うことが多いですが、出血や浸出液がある場合には早めに交換します。患者にも入浴やシャワーの方法などを伝え、挿入部位を清潔に保つための指導を行います。
感染防止策
カテーテル管理において最も気をつけるべき点は感染予防です。医療従事者は手袋の着脱や手指衛生を徹底し、カテーテルに触れる際は手指の洗浄と消毒を繰り返します。
透析後やドレッシング交換後にはカテーテル接続部のアルコール消毒を行い、常に無菌操作を維持します。
- 毎回の手洗いと手指消毒
- 清潔な器具の使用
- 交換時の無菌操作徹底
- カテーテル接続部の消毒
カテーテルの定期的なチェック
カテーテルの先端位置がずれていないか、血流が滞らないかを定期的に確認します。医師や看護師は血液透析の前後や途中でカテーテルから血液が問題なく出入りするかを評価し、閉塞の兆候に早期対応します。
外部から見える部分の劣化や亀裂がないかも観察して、必要なら交換を検討します。
管理に関連する主なチェック項目
| チェック項目 | 具体的な確認内容 |
|---|---|
| カテーテル挿入部位 | 発赤、腫脹、分泌物、痛み、出血の有無 |
| 接続部・チューブの状態 | 亀裂、リーク、変色、接合部の緩み |
| 血液回路の流量 | 血液ポンプを回したときに十分な流量が得られるか |
| 抵抗感の有無 | 押し引きしたときの抵抗や詰まり感 |
| 患者の自覚症状 | 発熱、悪寒、倦怠感、局所痛など |
カテーテルの合併症と対処法
カテーテルを使用することで発生しうる代表的な合併症として、血流障害、感染症、機械的トラブルなどがあります。これらを早い段階で察知し、適切な対処を行うことが患者の安全に直結します。
血流障害
血栓やフィブリンシースによって血管内の流れが阻害され、透析効率が低下する場合があります。カテーテル先端の閉塞が疑われる場合は、生理食塩水や抗凝固薬の注入などの処置を行うことがあります。
改善が見られない場合はカテーテルの交換を検討します。
感染症
カテーテル周辺部の赤みや痛み、排膿、発熱などが認められる場合は感染を疑います。表在性の感染であれば局所ケアと抗生物質投与で対応しますが、血流感染に進展して全身症状が出ている場合にはカテーテル抜去が必要になることもあります。
感染症の早期発見と迅速な治療が大切です。
機械的トラブル
カテーテルの破損やねじれ、接続部の緩みなどによる血液漏れや脱血不良が起こる可能性があります。
小さな亀裂でも血液透析中に重大なトラブルにつながるため、使用前後の点検を欠かさず行い、問題があればすみやかに交換や修理を検討します。
- ねじれや折れ曲がりがないか確認
- 接続部分にぐらつきや漏れがないか点検
- カテーテル固定テープのずれやゆるみのチェック
合併症が疑われる場合の対応
| 症状・兆候 | 可能性のある原因 | 一般的な対策 |
|---|---|---|
| カテーテル先端から血液が出ない | 血栓、フィブリンシースの形成など | 生理食塩水や抗凝固薬での洗浄、再挿入検討 |
| 挿入部位が赤く腫れて痛い | 局所感染、カテーテル刺入部炎 | 抗生物質投与、抜去、創部処置など |
| カテーテルからの液漏れ | 亀裂、接続部ゆるみ、機械的破損 | カテーテル交換、修理対応 |
| 発熱、悪寒、全身倦怠感 | 血流感染 | 抗生物質投与、カテーテル抜去検討 |
生活上の注意点とセルフケア
カテーテルを留置した状態で日常生活を送るにあたり、患者が気をつけるべき点を理解することが透析の継続において大切です。医療スタッフと連携し、トラブルを未然に防ぐための習慣づくりを行います。
入浴や運動時の注意
カテーテル挿入部位を濡らさないように、シャワーや入浴時には防水カバーを使用するなどの注意が必要です。感染リスクを避けるため、湯船に長く浸かることは医療スタッフと相談して判断することが多いです。
適度な運動は健康維持に役立ちますが、カテーテルが大きく動揺するほどの激しい運動は避けたほうがよい場合があります。
カテーテルを安定させる工夫
装着部分に負荷がかからないよう、患者自身が日常生活で気をつける必要があります。衣類がカテーテルに擦れすぎないようにしたり、寝返りを打つ際に痛みを伴わない枕の高さを探るなど、細かな工夫がトラブル予防につながります。
マジックテープや専用バンドでホースを固定する方法を提案されることもあります。
生活面で取り入れたい工夫
| 項目 | 実践例 |
|---|---|
| カバーの使用 | 保護フィルムや専用カバーで挿入部位を保護 |
| 衣服の選択 | ゆったりとした服を着用し、擦れや引っかかりを軽減 |
| 就寝時の姿勢 | カテーテル側を下にしないよう枕やクッションを活用 |
| 運動時のサポート | 医療者と相談して適度な運動負荷を選択し、過度な動きを避ける |
| 定期的な点検 | 自宅でもカテーテル周辺を毎日目視確認 |
日常生活での確認事項
- 挿入部位の発赤や腫れ
- カテーテル固定部分のずれや汚染
- 体温の変化や寒気
- カテーテル挿入部位周囲の痛みや違和感
こういった変化を見つけた場合には、放置せずに医療機関へ連絡して指示を仰ぐことが重要です。日頃のセルフケアと定期通院の双方を大切にし、安全に透析治療を続けていきましょう。
よくある質問
- カテーテル挿入後の痛みが続くときはどうすればよいでしょうか?
-
挿入後しばらく軽い痛みを感じる方は多いです。しかし強い痛みや腫脹、発赤などが伴う場合はトラブルの兆候かもしれません。我慢せずに医療者へ相談し、必要に応じた処置を早めに検討してください。
- 日常生活でシャワーをするときにカテーテルを濡らしてしまった場合は?
-
透析カテーテル周囲が濡れてしまったときには、消毒をして清潔なドレッシング材に交換することが望ましいです。感染が心配な場合は医療者に報告し、必要な対応を相談してください。
- カテーテルが抜けかけたように感じたらどうすればいいですか?
-
カテーテル固定が弱まったり、位置がズレたりすると血液透析が困難になるだけでなく、感染リスクも高まります。固定を試みる前に、まずは医療機関へ連絡し、専門的な処置を受けることを推奨します。
- カテーテル挿入部位がかゆくなる原因はなんでしょうか?
-
ドレッシング材のかぶれや皮膚の乾燥によってかゆみが生じる場合があります。適切なケアを行い、それでも続く場合には感染症やアレルギー反応の可能性もあるため医療者に相談してください。
以上
透析センター(人工透析) | 大垣中央病院(医療法人社団豊正会 )
参考文献
EL KHUDARI, Husameddin, et al. Hemodialysis catheters: update on types, outcomes, designs and complications. In: Seminars in interventional radiology. Thieme Medical Publishers, Inc., 2022. p. 090-102.
TREROTOLA, Scott O. Hemodialysis catheter placement and management. Radiology, 2000, 215.3: 651-658.
WANG, Kai, et al. Epidemiology of haemodialysis catheter complications: a survey of 865 dialysis patients from 14 haemodialysis centres in Henan province in China. BMJ open, 2015, 5.11: e007136.
PEPPELENBOSCH, Arnoud, et al. Peritoneal dialysis catheter placement technique and complications. NDT plus, 2008, 1.suppl_4: iv23-iv28.
NAPALKOV, Pavel, et al. Incidence of catheter-related complications in patients with central venous or hemodialysis catheters: a health care claims database analysis. BMC cardiovascular disorders, 2013, 13: 1-10.
BESARAB, Anatole; PANDEY, Rahul. Catheter management in hemodialysis patients: delivering adequate flow. Clinical Journal of the American Society of Nephrology, 2011, 6.1: 227-234.
KAIRAITIS, Lukas K.; GOTTLIEB, Thomas. Outcome and complications of temporary haemodialysis catheters. Nephrology, dialysis, transplantation: official publication of the European Dialysis and Transplant Association-European Renal Association, 1999, 14.7: 1710-1714.
PREMUZIC, Vedran, et al. Complications of Permanent Hemodialysis Catheter Placement; Need for Better Pre‐Implantation Algorithm?. Therapeutic apheresis and dialysis, 2016, 20.4: 394-399.
HAGEN, Sander M., et al. A systematic review and meta-analysis of the influence of peritoneal dialysis catheter type on complication rate and catheter survival. Kidney International, 2014, 85.4: 920-932.
GALLIENI, Maurizio, et al. Optimization of dialysis catheter function. The Journal of Vascular Access, 2016, 17.1_suppl: S42-S46.