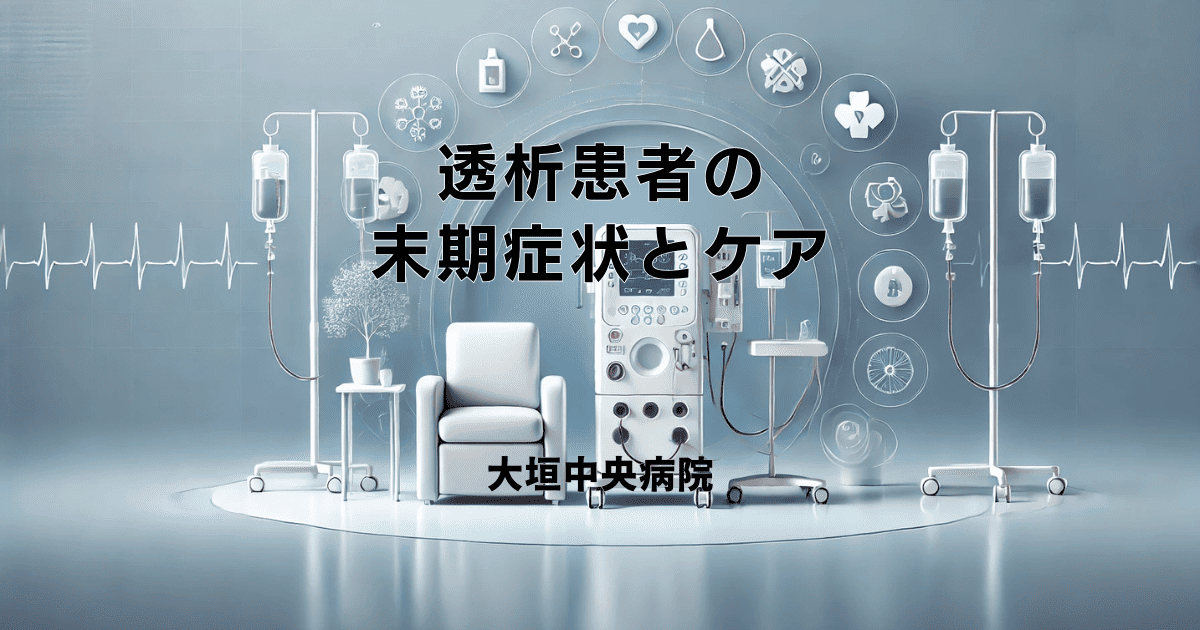近年、人工透析を受ける方が増え続け、腎不全と向き合う期間が長くなる傾向があります。
治療法が進歩している一方で、長期にわたり透析を行う方が最終的に迎える状態は、本人はもちろん、支える家族や医療者にとっても負担が大きいと感じやすいものです。
身体の変化や心の揺れにどう向き合えばいいのか、透析患者末期症状にはどのような特徴があるのか、そして透析患者の最後を迎える場面で必要となるケアとは何かを理解することが重要です。
本記事では、総合病院の視点から、医療者や家族が押さえておきたいポイントを解説します。
透析と腎不全の理解
透析を受ける方の末期状態を考えるには、透析そのものの仕組みと腎不全が進行していく過程を十分に理解することが大切です。
腎臓の機能を代替するために行う透析ですが、その背景には複雑な病態の変化が存在し、様々な判断が求められます。この段階での理解が、その後のケアや判断に役立ちます。
透析の基本的な仕組み
腎臓は血液をろ過して老廃物や余分な水分を排出し、体内の電解質バランスを保つ器官です。これが十分に機能しなくなると腎不全に至り、人工的に血液を浄化する必要があります。
一般的には血液透析と腹膜透析がありますが、多くの方は血液透析を選択することが多いです。血液透析では血液を体外に導き、ダイアライザと呼ばれる装置を使って老廃物や余分な水分を除去し、清浄化した血液を身体に戻します。
透析治療の概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 血液透析 | 体外循環で血液をろ過し、不要な物質を除去したうえで血液を体内に戻す |
| 腹膜透析 | 腹膜をろ過膜として利用し、透析液と血液の間で物質交換を行う |
| 透析時間 | 血液透析の場合、週3回で1回あたり4~5時間ほど行うことが多い |
| 合併症対策 | 透析時の血圧低下や血液透析シャント感染症予防などが重要になる |
透析の種類や回数、時間は患者の全身状態や合併症によって調整します。透析患者末期症状が見えてきた段階では、治療内容を見直すことも選択肢に含まれます。
末期腎不全が進行するしくみ
末期腎不全になると腎臓は機能を大幅に失い、水分や老廃物、電解質の調整ができません。そのため身体に老廃物が蓄積し、意識障害や心臓への負担が増大する状態に至ります。
血液透析で一定の老廃物を取り除いたとしても、腎臓自体の機能が回復するわけではないので、さらに病状が進行して合併症が増えることもあります。
腎不全に伴う主な合併症
| 合併症 | 特徴 |
|---|---|
| 心不全 | 血液量や電解質の異常による心臓への負担増加 |
| 高カリウム血症 | 腎臓でのカリウム排泄低下により、重度になると不整脈のリスクが高まる |
| 体液貯留 | むくみや肺水腫などの呼吸苦を引き起こすこともある |
| 低栄養・貧血 | 食事制限や食欲低下による栄養不足、および腎臓機能低下による造血能の低下 |
末期の状態では複数の合併症が重なり、症状が複雑化します。早めに医療者へ相談し、適切な対策を取ることが望ましいです。
透析中止の考え方
人工透析を受けている方の中には、病状の進行や生活の質の問題、あるいは本人の意思により透析中止という選択肢を検討する場面があります。
透析を中止すると老廃物や水分が排出されなくなるため、身体に大きな負担がかかり、比較的短期間で生命予後が厳しくなる可能性が高いです。
しかし、長引く透析治療に伴う苦痛や合併症の増加などを総合的に判断して、中止や緩和ケアへ移行するケースもあります。
家族や医療チームは、本人がどのような生活や最終的な時間を望んでいるかを確認して、最善と考えられる対応策を検討します。透析患者の最後を迎える方法は一律ではなく、それぞれの人生観や病状、家族の状況などを踏まえて判断が必要です。
透析患者末期症状の特徴
透析患者末期症状には、身体的にも精神的にも顕著な変化が現れることがあります。合併症による負担に加えて、体力や気力の低下に伴う日常の困難が増すため、本人や家族が混乱を感じる場合も少なくありません。
どのような症状が出やすいかを把握しておくと、早期に対処できるきっかけになります。
体力低下と食欲不振
末期になると持続的な疲労感や著しい食欲不振が目立ちます。透析の治療スケジュール自体が体力を消耗させることもあり、あらゆる活動が億劫になる方が多いです。食事摂取量が減ると栄養状態が悪化し、さらなる体力低下に拍車がかかります。
こうした状態に対しては口当たりの良い食品に切り替えたり、少量で高カロリーの食事を工夫したりする方法が考えられます。
食事を工夫する考え方
- 一度にたくさん食べるより、少量を複数回に分ける
- 温かいものと冷たいものを組み合わせ、食欲を刺激する
- 水分制限がある場合も食事の味付けを調整して楽しみを維持する
- プロテイン補助食品や医師推奨のサプリメントを取り入れる
体力低下を補うには、生活全体のバランスを整えながら、身体に負担の少ない運動を取り入れるなどの方法も選択肢になります。
皮膚や粘膜の症状
末期には皮膚が乾燥しやすくなったり、かゆみが強まったりするケースがあります。これは体内のリンや尿素が十分に排出されないことで発生しやすいと考えられます。
また、口腔内や消化管の粘膜も弱りやすく、口内炎や歯肉炎などのリスクも増加します。皮膚の清潔と保湿、粘膜への丁寧なケアを続けることである程度の軽減が見込まれます。
皮膚・粘膜ケアの主な方法
| ケアの種類 | 内容 |
|---|---|
| 保湿剤の使用 | 入浴後や洗浄後に保湿クリームなどを塗る |
| 温度・湿度管理 | 部屋の空調や加湿器で乾燥を防ぎ、汗などによる不快感も軽減 |
| 口腔ケア | こまめなうがいや唾液の分泌を促すケア、歯科受診での定期的チェック |
| 下着や寝具 | 肌触りの良い素材を選ぶことで皮膚への摩擦を減らし、かゆみを緩和する |
かゆみが強い場合は医師に相談し、飲み薬や塗り薬などを検討することも選択肢になります。
精神面の変化
長期間にわたる人工透析や頻繁な通院による生活の制限は、精神的な負担となりやすいです。末期に近づくにつれ、自身の体調悪化や将来への不安が強まることで、抑うつ状態やイライラ感の増大につながることもあります。
また、透析患者末期症状が顕著になると意思疎通やコミュニケーションが難しくなる場合があります。
周囲が変化に早めに気づいて声をかけたり、医療者や専門カウンセラーと連携して対策を講じることが大切です。透析患者の最後に向き合う時期は本人の気持ちを尊重しつつ、必要に応じた精神面のサポートを考える機会にもなります。
体調管理と合併症への対応
透析患者末期症状が深刻化すると、医療チームと連携して体調管理を行い、さまざまな合併症に対処する必要があります。血液検査や血圧管理など、日常のチェックを怠ると体調悪化を見逃す恐れがあるため、定期的な確認が重要です。
高血圧や心不全の管理
腎不全が進行すると塩分や水分の制限が強くなり、高血圧や心不全のリスクが高まります。透析を行っていても完全に血圧をコントロールできない場合があり、心臓への負担が増えて呼吸困難や倦怠感を生じやすくなることがあります。
血圧が高いとさらに腎臓の機能に負荷がかかる悪循環にも陥りやすいため、適度な血圧管理が欠かせません。
心臓を守るための留意点
- 塩分を控え、水分摂取量を厳密に確認する
- 体重増加の推移をこまめに記録し、急激な変化があれば主治医に報告する
- 安静にしがちな時期でも体位変換や軽い運動で血行を促す
- 意欲の低下が見られるときは、血圧管理の計測タイミングを工夫して負担を減らす
心不全が悪化すると息苦しさやむくみなどの症状が増え、末期にはQOL(生活の質)が大きく損なわれることがあります。本人の希望を踏まえつつ、医療チームと連携して管理すると良いでしょう。
感染症予防の具体的ポイント
透析患者は免疫力が低下しやすいため、感染症にかかりやすい状況にあります。特に透析シャント部位の感染、尿路感染、肺炎などのリスクが高まります。
高齢の方や体力が低い方は感染すると重症化する恐れがあるので、普段からこまめにリスクを減らす行動が必要です。
感染対策の具体例
| 対策 | 詳細 |
|---|---|
| シャント部位の清潔管理 | 透析後の止血が十分に行われているか確認し、軽度の赤みや熱感があれば速やかに受診する |
| 手洗い・うがい | 帰宅後や食事前など定期的に行い、外出先でのマスク着用も検討する |
| ワクチン接種 | インフルエンザや肺炎球菌ワクチンなど、医師と相談しながら可能な範囲で接種する |
| 口腔ケア | 口の中の細菌が肺炎などにつながることもあるため、歯科医との連携を図る |
細やかな注意を続けるのは大変ですが、本人や家族が協力しながら継続していくことが体調維持に役立ちます。
血液検査の読み方と注意点
定期的に行う血液検査は、末期の透析患者においても重要な指標です。電解質(ナトリウム、カリウム、リンなど)や尿素窒素、クレアチニンの値が高くなると、腎臓の機能低下や透析の効果不足を示す場合があります。
また、ヘモグロビン値の低下は貧血を反映するので、造血ホルモン製剤や鉄剤の投与などを検討することになります。
血液検査で注目すべき代表的項目
| 項目 | 意味・注意点 |
|---|---|
| BUN (尿素窒素) | 腎機能低下やタンパク質の代謝状態を示す |
| Cre (クレアチニン) | 腎臓のろ過機能の指標 |
| K (カリウム) | 高値の場合、不整脈や心停止のリスクが高まる |
| Hb (ヘモグロビン) | 貧血の程度を把握する数値で、エリスロポエチン製剤の使用に関わる |
これらの数値を定期的に追うことで、体調悪化の兆候を早期にキャッチできる可能性があります。
透析患者末期症状の緩和ケア
透析患者末期症状が進行すると、身体の苦痛を緩和し、生活の質をできる限り維持する緩和ケアが大きな課題となります。痛みだけでなく、呼吸困難や不眠、心の問題などさまざまな苦痛が重なることも多く、包括的な対処が望まれます。
痛みや苦しみを軽減する方法
末期の透析患者は、骨や筋肉の痛み、むくみに伴う張りなどを訴えることがあります。鎮痛薬の使用やマッサージ、体位調整などの方法を組み合わせながら、本人の状態に合った軽減策を探すことが大切です。
痛みがあると寝返りや移動が難しくなるため、褥瘡のリスクも高まります。
ケアチームで共有したいアプローチ
- 痛みの程度を数値化し、医師や看護師に随時報告する
- マッサージや温熱療法、クッションなどで負担を和らげる
- 身体介助の頻度を増やし、負担を軽減する
- 鎮痛薬は副作用を意識しながら使用し、効果をこまめに評価する
緩和ケアの対象となる症状は痛みだけではありません。吐き気や不安感、睡眠障害などが生じることもあるため、複数の側面を同時にチェックする必要があります。
終末期の呼吸ケア
呼吸困難や痰の処理など、呼吸に関わる症状が重なると非常に苦痛を感じやすくなります。特に心不全や体液バランスの乱れがある方は、呼吸が浅くなりがちで、安眠を妨げる原因にもなります。
呼吸補助のために酸素投与を行うケースもありますが、末期状態での酸素療法は患者の安楽を第一に考えて使い方を検討することが多いです。
痰が絡む場合には、吸引や体位の工夫で気道を確保します。呼吸を楽にするためには上半身をやや起こし、寝具を調整して横隔膜の動きを確保しやすくする方法も選ばれます。
呼吸を楽にするための取り組み
| 方法 | 内容 |
|---|---|
| 体位調整 | 背中や腰にクッションを当ててやや前かがみに近い姿勢にする |
| 吸引のタイミング調整 | 本人の苦しそうな時に合わせて適宜痰を吸引し、呼吸を確保する |
| 酸素投与 | 酸素流量を調整し、過度な負担をかけない範囲で行う |
| 加湿器の活用 | 気道を乾燥させないよう湿度を保ち、痰が絡みにくい環境をつくる |
呼吸に関連するケアは看護師や医師だけでなく、家族が日常的にサポートする部分も多いです。
心理的支援の重要性
末期に近づくと「自分の人生はあとどれくらいなのか」「透析患者の最後はどうなるのか」といった不安に苛まれる方もいます。精神的に落ち込みやすい時期に適切な声かけや専門家への相談を行うことで、気持ちの負担が和らぐことがあります。
医療ソーシャルワーカーや心理カウンセラーがいる場合は早めに依頼し、患者本人と家族をサポートしてもらうのが望ましいです。
苦痛や不安が大きいとき、医師や看護師だけで解決しきれないこともあります。多職種が協力して視点を増やすことで、心のケアを充実させることができます。
家族が知っておきたい透析患者の最後の過ごし方
透析患者末期症状がはっきりしてくると、家族にとっては「これからどのように支えればいいのか」が大きなテーマになります。本人の気持ちを尊重するのはもちろんですが、家族自身の心身の健康や負担にも目を向ける必要があります。
どのような形で最期を迎えるのか考えながら、適切なサポートを続けることが大切です。
日常生活でのサポート
在宅での看取りを希望する方もいれば、入院を選ぶ方もいます。いずれにしても本人の生活空間をより快適に維持するため、環境整備やコミュニケーションの工夫が求められます。
小さな変化を見逃さないためにも、体温や血圧、食事量などの記録をこまめに取りながら、気になった点はすぐに医療者へ相談すると良いでしょう。
家族が主に行いやすい支援
- 寝室やリビングなど、動線を短くして移動を楽にする
- トイレや浴室には手すりや滑り止めを設置して安全性を高める
- 食事の時間や献立を一緒に考え、摂取できるものを工夫する
- 本人が会いたい人ややりたいことなどを確認し、可能な範囲で調整を行う
家族が全てを背負いすぎると疲弊しやすいため、訪問看護や介護サービスなどを積極的に活用することも検討が必要です。
コミュニケーションを大切にする工夫
透析患者末期症状が進むと、本人の体力が落ちて言葉を発するのが大変になることもあります。そのようなときこそ、気軽に話しかけて様子をうかがう姿勢が大事です。
声をかけても反応が薄い場合でも、目を合わせたり手を握ったりするだけで安心感を与えられることがあります。
心をつなげるコミュニケーション例
| 取り組み | 具体的内容 |
|---|---|
| 言葉のシンプル化 | 長い質問や説明より、短い言葉で話しかける |
| 非言語的アプローチ | 手を握る、背中をさするなど、身体接触で気持ちを伝える |
| 好きな音楽の活用 | 昔から親しんだ音楽やラジオを流し、リラックスできる環境をつくる |
| メモや写真の使用 | 大切な用件や思い出は文章や写真で示し、忘れやすい部分を補う |
本人が伝えたいことを十分に言葉にできない状況でも、家族が寄り添っていることが伝わると心の安定につながります。
医療チームとの連携
透析医療だけでなく、腎臓内科、循環器内科、緩和ケアチームなど、必要に応じて様々な診療科が関わってきます。情報を共有しながら、症状の緩和や合併症の管理を進めることが不可欠です。
わからないことや不安な点は遠慮せず、医師や看護師、ソーシャルワーカーに相談すると良いでしょう。
家族が主治医との面談に同席し、本人が言いにくいことを代弁したり、退院後の支援体制を一緒に考えたりすることも重要な役割です。病院や地域の福祉資源を活用しながら、最善と思われる環境を整えることを検討してみてください。
意思決定と緩和ケアチームの役割
透析患者末期症状が進行していくにつれ、治療やケアの方向性について大きな決断を迫られる場面が増えます。本人と家族だけで判断するのが難しい場合、緩和ケアチームを含む医療者のサポートを得ることが支えとなります。
透析継続か中止か
透析患者の最後を考えるとき、治療を継続するか中止するかは非常に重大な問題です。継続すれば余命は延びる可能性がありますが、苦痛や通院負担が増すかもしれません。
中止すれば、終末期の負担を軽減できる可能性はありますが、生命予後は短くなることが予想されます。
本人の意向や生活の質をどう考えるか、家族の思いや倫理的な観点をどう折り合わせるかは簡単ではありません。病状や今後の見通しを主治医や緩和ケア医と一緒に整理し、複数の選択肢を比較検討する姿勢が求められます。
透析継続・中止を検討するときの視点
- 本人の意志が明確に示されているか
- 合併症の程度や生活の質にどの程度影響があるか
- 家族や介護者のサポート体制がどの程度整っているか
- 医療者が提供できるケアの選択肢と本人の希望が合致しているか
いずれの選択肢を選んでも後悔が残る場合がありますが、可能な限り多角的に考慮し、本人が望む形に近づくよう調整することが大切です。
看取りに向けた体制づくり
在宅か病院か、あるいは緩和ケア病棟かなど、どの場所で看取りを行うかによって必要な準備は変わります。住み慣れた自宅を希望する場合は、訪問看護や介護サービス、在宅医療がどの程度利用できるかを早めに調べておくことが重要です。
病院で看取る場合は、緩和ケア病棟や一般病棟で対応することになります。
どの選択をしても、痛みや不安などをできる限りコントロールし、穏やかに過ごせるような体制づくりが望まれます。家族や周囲の負担を軽減するためにも、医療者との早期連携がカギになります。
看取り場所ごとの特徴
| 場所 | 特徴 |
|---|---|
| 自宅 | 馴染みのある環境で過ごせるが、家族の負担が増えやすい |
| 病院一般病棟 | 症状が急変したときに対応しやすいが、個室や面会時間などの制約がある場合がある |
| 緩和ケア病棟 | 痛みや苦痛のコントロールを重視した医療体制があるが、病床数に限りがあることが多い |
早めに看取り場所を検討することで、心の準備をしながら必要な手続きを済ませることができます。
医療者と家族の連携
本人が言葉で意思を表明できなくなったとき、家族がその意思を推測して医療者に伝える場面が出てきます。食事の取り方や鎮痛剤の使用、延命措置の有無など、多くの判断が必要です。
家族だけで結論を出せないときは、医師や看護師、緩和ケアチーム、ソーシャルワーカーなどと話し合いながら進めることが望ましいです。
十分に連携を図ることで、本人の苦痛を和らげたり、家族の負担感を軽減したりすることができるはずです。必要に応じて各専門職の助力を仰ぎ、情報を集めて総合的に判断することが大切といえます。
総合病院で受けられるサポートの具体例
総合病院には様々な診療科と専門スタッフがそろっており、透析患者末期症状に対して多面的な支援が可能です。
体調管理だけでなく、精神的ケアや家族支援なども連携して行うことで、最後の期間をより安心して過ごせるように整備されています。
各診療科との連携
腎臓内科だけでなく、循環器内科、呼吸器内科、消化器内科など、複数の診療科が連携を取り合うことで、合併症への的確なアプローチができるようになります。
透析シャントの管理が必要な場合には血管外科が関わることもありますし、感染症が疑われるときには感染症科や微生物検査室と協力して迅速に対応します。
総合病院での連携イメージ
| 診療科 | 主な役割 |
|---|---|
| 腎臓内科 | 透析管理や腎機能評価、電解質バランスのコントロール |
| 循環器内科 | 心不全や血圧管理、不整脈の評価と治療 |
| 呼吸器内科 | 呼吸困難、肺感染症、呼吸リハビリテーションなどの対応 |
| 血管外科 | 透析シャントの作成や合併症の処置 |
| 感染症科 | 発熱や感染症の疑いがある場合の原因究明と治療方針 |
| 緩和ケアチーム | 痛みや呼吸困難などの苦痛緩和、精神的サポート、家族支援などの総合的ケア |
このような多職種連携によって、各分野での専門性を活かしたケアを組み合わせることができます。
入院や在宅医療との組み合わせ
透析患者末期症状が進行すると、通院が難しくなるケースもあります。そうした場合、入院治療や在宅医療を組み合わせることで、本人の状態に合わせた柔軟な対応が可能になります。
入院中は医療スタッフがこまめに状態を確認し、症状コントロールや合併症対応を行います。状態が安定すれば在宅に切り替え、訪問看護や訪問診療を利用して必要な治療やケアを継続することもできます。
ただし、自宅での療養には一定の生活環境や介護力が必要です。早めに病院のソーシャルワーカーなどに相談し、各種制度や地域の福祉サービスについて情報収集しておくことが望まれます。
在宅医療を利用するときに確認したい項目
- 在宅透析を実施できる環境(設備・水質管理など)
- 訪問看護やヘルパーの利用可能な時間帯と回数
- 緊急時の相談先や駆けつけが可能な医療機関の確保
- 介護保険サービスや福祉用具の導入状況
これらを整えておくと、安心して在宅ケアを行える可能性が高まります。
チーム医療の重要性
透析患者末期症状は多彩かつ個人差が大きいため、一人の医療者や家族だけで抱え込むと負担が大きくなりがちです。
そこで、医師、看護師、薬剤師、管理栄養士、リハビリテーションスタッフ、ソーシャルワーカーなど、様々な専門職が協力するチーム医療が力を発揮します。
患者本人や家族が望む生活や看取りの形に近づけるため、各領域の知識と技術を持ち寄ることが重要です。
相談先を一元化できる窓口を設けている病院もあり、家族が質問や相談をしやすい仕組みを整えているケースもあります。医療者の間でこまめに情報共有が行われている総合病院であれば、より安心して治療やケアに専念できます。
まとめと総合病院への受診を考える意義
透析患者末期症状は身体的負担も心の負担も大きく、患者本人だけでなく家族や支援者のサポート体制を見直す局面となります。
痛みや呼吸困難などの症状管理はもちろん、意思決定に迷いやすい場面もあるため、腎臓内科や緩和ケアチームを含む多職種との連携が欠かせません。
透析患者の最後をどう迎えるかは、一人ひとり状況や価値観が異なるため、その方に合った形を一緒に模索していく姿勢が大切です。
総合病院では、多くの診療科や専門家が集まり、スムーズなチーム医療を提供しやすい利点があります。何か不安や疑問があれば一度受診し、適切な検査や相談を行うことで、今後の展開を考える手がかりを得ることができます。
ご本人やご家族が抱えている悩みを遠慮なく伝え、各専門職の力を借りながら納得のいく方法を見つけてください。
以上
透析センター(人工透析) | 大垣中央病院(医療法人社団豊正会 )
参考文献
O’CONNOR, Nina R.; KUMAR, Pallavi. Conservative management of end-stage renal disease without dialysis: a systematic review. Journal of palliative medicine, 2012, 15.2: 228-235.
WEISBORD, Steven D., et al. Symptom burden, quality of life, advance care planning and the potential value of palliative care in severely ill haemodialysis patients. Nephrology Dialysis Transplantation, 2003, 18.7: 1345-1352.
MURTAGH, Fliss EM; ADDINGTON-HALL, Julia; HIGGINSON, Irene J. The prevalence of symptoms in end-stage renal disease: a systematic review. Advances in chronic kidney disease, 2007, 14.1: 82-99.
VALDERRÁBANO, Fernando; JOFRE, Rosa; LÓPEZ-GÓMEZ, Juan M. Quality of life in end-stage renal disease patients. American Journal of Kidney Diseases, 2001, 38.3: 443-464.
BROWN, Mark A., et al. CKD in elderly patients managed without dialysis: survival, symptoms, and quality of life. Clinical journal of the American Society of Nephrology, 2015, 10.2: 260-268.
ABDEL-KADER, Khaled; UNRUH, Mark L.; WEISBORD, Steven D. Symptom burden, depression, and quality of life in chronic and end-stage kidney disease. Clinical Journal of the American society of Nephrology, 2009, 4.6: 1057-1064.
KIMMEL, Paul L.; PATEL, Samir S. Quality of life in patients with chronic kidney disease: focus on end-stage renal disease treated with hemodialysis. In: Seminars in nephrology. WB Saunders, 2006. p. 68-79.
WEISBORD, Steven D., et al. Development of a symptom assessment instrument for chronic hemodialysis patients: the Dialysis Symptom Index. Journal of pain and symptom management, 2004, 27.3: 226-240.
EVANS, Roger W., et al. The quality of life of patients with end-stage renal disease. New England journal of medicine, 1985, 312.9: 553-559.
GOH, Zhong Sheng; GRIVA, Konstadina. Anxiety and depression in patients with end-stage renal disease: impact and management challenges–a narrative review. International journal of nephrology and renovascular disease, 2018, 93-102.