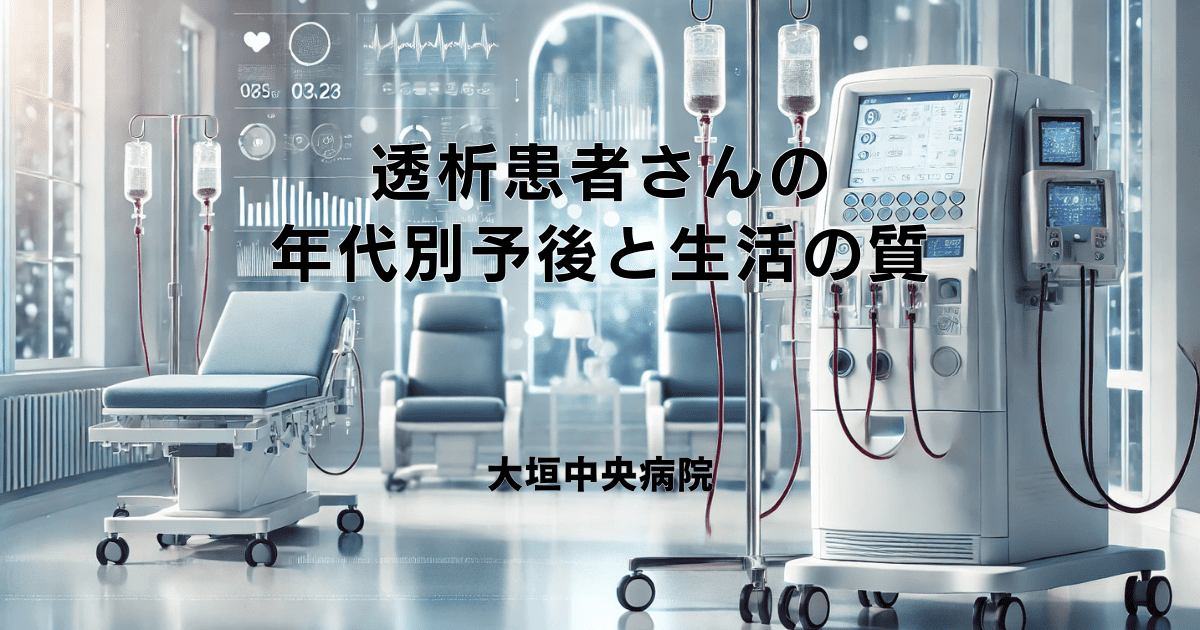透析治療に関心をお持ちの方や、すでに透析を始めている方が気になるのは年齢ごとの予後や暮らし方の違いではないでしょうか。年齢によって体力や合併症のリスク、社会的な状況などが異なるため、適切な情報を得ることが重要です。
この記事では、各年代に多い特徴や人工透析余命30代から80代までの傾向、生活の質向上を目指すために意識したいポイントを、公開されている統計データをもとにまとめました。
多くの方が気にかけるデータや話題を取り上げ、幅広い年代の方にとって有用な情報を提供します。
透析治療の概要
透析とは、腎臓の機能が大きく低下した場合に体内の老廃物や余分な水分を取り除く手段として行う治療です。腎機能が低下している方にとって、血液を浄化する機能を補うために人工的な装置を利用することが、健康状態を保つうえで大切です。
血液透析と腹膜透析の2種類があり、それぞれの方法にメリットと注意点があります。
透析という言葉だけで大きな負担をイメージする方もいらっしゃるかもしれませんが、正しい知識を身につけることで治療と日常生活を調和させやすくなります。
透析の基礎と必要性
腎不全が進行すると、体内の老廃物や過剰な水分を排出できなくなり、高血圧や心臓への負担などを生じます。人工的に不要な物質を取り除く透析は、こうした合併症を抑える役割を担います。
特に末期腎不全では透析が生命維持に直結し、受けるかどうかで予後が大きく異なります。透析をすることで安定した体調を保てる可能性がある一方、週に数回の通院や治療時間など、生活スタイルへの影響も少なくありません。
透析導入のタイミングは一般的にGFR(糸球体濾過量)の低下や症状の度合いをもとに医師が判断し、適切な時期を見極めます。
透析における主な種類
代表的な手法としては、血液透析と腹膜透析が挙げられます。血液透析では、血液を体外に出してダイアライザーという専用フィルターに通し、余分な水分や老廃物を除去して再び体内に戻します。
腹膜透析では、腹膜をフィルターとして利用し、透析液を一定時間おなかの中に入れて老廃物を吸着させる方法です。血液透析は医療機関へ通院して行うことが多く、1回あたり数時間かかります。
腹膜透析は自宅でも実施できる一方で、自己管理の負担が大きくなる場合があります。どちらを選ぶかは生活環境や体の状態、希望などを総合的に考慮して決定します。
症状やリスクの主な特徴
透析が必要になる段階では、尿量の減少やむくみ、倦怠感などが強くなり、体が余分な老廃物を排出できない状況になっています。
そのため、高カリウム血症や高リン血症など、血液中の電解質バランスが崩れることで心臓や血管への負担が増え、重篤な合併症へつながるリスクが高まります。
透析治療によって症状を改善しやすくなる一方、透析を長年継続することで特有の合併症(透析アミロイドーシスなど)を招くリスクもあるため、年齢や体調に応じたケアが必要です。
透析治療における主なメリット・デメリット
| 項目 | 血液透析 | 腹膜透析 |
|---|---|---|
| 主な実施場所 | 病院や透析施設 | 自宅 |
| 治療頻度 | 週3回程度、1回4~5時間ほど | 1日に複数回交換 or 1日1回機械を使用(就寝時など) |
| メリット | ・医療スタッフが管理を行うので安心感がある | ・自宅で治療でき、通院の負担が少ない |
| デメリット | ・通院の手間、時間の拘束 | ・自己管理の負担、感染リスクの管理が必要 |
| 生活への影響 | ・透析日に合わせたスケジュール調整が必要 | ・日常的に交換や機械操作を行うため時間配分が大切 |
年代別の人工透析を受ける患者数と背景
腎臓病が進行した結果として導入される透析ですが、患者さんの年齢によって抱える背景は異なります。若年層は仕事や育児などの活動が活発で、透析に割く時間や費用の問題で悩むケースが多くみられます。
一方で高齢者は合併症のリスクが高まり、血管や心機能の脆弱化などへ配慮する必要があります。年齢ごとの特徴を把握することで、自身の状況に合った治療やサポートが得やすくなるかもしれません。
30代から40代の患者背景
30代から40代で透析を受ける方は、働き盛りや子育て世代にあたることが多く、仕事との両立や家庭での役割分担に課題を感じることがあります。
慢性腎臓病の原因としては糖尿病や高血圧などの生活習慣病がある一方、若年性の腎不全や遺伝的な疾患も含まれます。この年代の方は仕事を持っていることが多く、治療のスケジュール調整が難しくなるケースがあります。
身体的には比較的体力があるため、症状の進行が急激にならない限りは生活の質を保ちやすい面もあります。ただし、ストレスや不規則な生活習慣が腎機能悪化につながるおそれがあるため、継続的に健康管理を行う必要があります。
50代から60代の患者背景
50代から60代は、糖尿病性腎症や高血圧性腎硬化症などで人工透析を導入する方が特に多い年代です。働き方の見直しや定年退職前後のライフステージの変化など、社会的にも大きな転換期となります。
多忙な中で生活習慣が乱れやすく、腎機能の低下を早める可能性があります。透析を導入すると通院や治療時間が必要になりますが、比較的柔軟に時間を調整できる場合もあります。
この年代は心血管系の病気のリスクが高いことも特徴で、食事や運動に気を配りながら、血圧管理や血糖値管理を徹底することが欠かせません。
70代から80代以上の患者背景
高齢化が進むにつれて、70代から80代以上の透析患者も増加傾向にあります。加齢に伴って動脈硬化が進行しやすく、心血管疾患や脳血管疾患のリスクが高まるため、総合的な健康管理が必要となります。
血液透析では血圧の変動や血管アクセスの問題が起こりやすくなるため、きめ細やかな医療的ケアが求められます。
一方、自宅で行う腹膜透析は手技の煩雑さが高齢者に負担となる場合もあり、家族のサポート体制の有無が重要になることがあります。
透析導入患者の年齢分布(概算)
| 年代 | 主な原因疾患(例) | 人数の増加傾向 |
|---|---|---|
| 30~40代 | 糖尿病性腎症、慢性糸球体腎炎など | ゆるやかに増加 |
| 50~60代 | 高血圧性腎硬化症、糖尿病性腎症など | 高齢化に伴い増加 |
| 70~80代 | 動脈硬化、心血管合併症を伴う腎不全など | 急速に増加傾向 |
年代別に注意したいポイント
- 30代~40代:仕事や育児との両立、ストレス管理
- 50代~60代:糖尿病や高血圧の厳重な管理、生活リズムの見直し
- 70代~80代以上:合併症への対策、介護体制や家族の支援
年代別の統計データが示す予後の特徴
人工透析を受けるときに、気になるのが余命に関する情報です。実際には個人差や基礎疾患の状態によって大きく異なりますが、一般的な統計を参照すると、おおまかな傾向を把握できます。
たとえば、若い年代ほど合併症が少なく、体力的な余力があるため、長期間にわたって透析を継続できる可能性があります。
一方で、高齢者は合併症が重なりやすく、透析による負担も大きくなるため、緊急入院や治療法の選択が制限されることがあります。
人工透析余命30代から40代の傾向
人工透析余命30代から40代は、数十年にわたる長期透析が可能なことが少なくありません。
透析歴が長期化すると骨ミネラル代謝異常や心血管リスクが高まるものの、適切な管理を行い、かつ合併症の早期発見と対処を徹底すれば比較的安定した状態を維持できるケースが多いです。
若い段階から透析導入となった場合は、社会生活を続けながら治療を継続し、職場環境や家庭環境に配慮したサポートを得ることが重要になってきます。
医療機関と連携しながら個別の治療スケジュールを組むなどして、身体への負担を軽減しながらの透析生活を目指す方が多いです。
人工透析余命50代から60代の傾向
人工透析余命50代から60代は、生活習慣病が原因となる方が多いため、合併症の有無が予後に大きく影響します。
糖尿病性腎症を患っている場合、血糖コントロールを適切に行わないと神経障害や網膜症などを同時に抱えてしまい、全身状態が悪化しやすくなります。
高血圧が原因となる場合にも、動脈硬化が進むことで心筋梗塞や脳卒中といった合併症を誘発しやすいです。
ただし、定期的な通院と、血圧・血糖値を含めた健康管理を欠かさず行うことで、透析を続けながらも10年以上の長期生存を保つ事例も少なくありません。
定年退職後のライフプランを見直しながら、無理のない範囲で運動や食事療法を続けるなど、焦らず自分のペースで健康管理を続けることがポイントです。
人工透析余命70代から80代の傾向
人工透析余命70代から80代は、合併症の多さと体力の低下が重なることで、若年層に比べると短くなる傾向があります。心臓や血管への負荷が大きく、慢性心不全や脳梗塞などのリスクが高いため、定期的な検査や早期治療が欠かせません。
一方で、透析技術が進歩したことで高齢でも導入可能なケースが増えており、通院が厳しい場合に腹膜透析を検討する選択肢もあります。
個人差が大きいため、「必ずしも年齢が上がるほど厳しい」というわけではなく、適切に合併症を管理すれば安定した状態を保てる方もいます。
介護サービスの利用や家族の協力を得ながら、生活の質の維持につなげる取り組みが大切です。
年代別予後の目安(透析歴5年以上の報告例から)
| 年代 | 主な合併症リスク | 長期生存の目安(あくまで統計的) |
|---|---|---|
| 30~40代 | 骨密度低下、貧血など | 20年~30年の生存例もあり |
| 50~60代 | 糖尿病・高血圧による心疾患 | 10年~20年ほど |
| 70~80代 | 心不全、脳卒中 | 数年~10年ほど |
生活の質を向上するためのポイント
透析を続けながら生活する場合、ただ長く生きるだけでなく、日常の活動を楽しむための工夫が求められます。
食事制限や通院のスケジュール調整など、生活に大きな変化が生じるため、積極的に情報を取り入れ、モチベーションを維持していくことが大切です。
年齢や病状に合わせた管理を行いながら、心理的なサポートや適度な運動などを取り入れると、より前向きな生活スタイルを確立しやすくなります。
食事管理と栄養バランス
透析ではカリウムやリンの制限が必要になる場合が多く、食事のレパートリーを狭めてしまうことがあります。
しかし、制限を守りつつも楽しめる料理や、栄養バランスに配慮したレシピを工夫することで満足感を得られます。特に高齢者ほど食欲が低下しがちなので、適切なタンパク質摂取や水分管理を意識したいところです。
管理栄養士のサポートを受けたり、腎臓病食に対応した宅配サービスを利用したりすると、負担軽減につながるケースもあります。
運動習慣と体力維持
運動は心肺機能の維持や血液循環の改善を促し、透析患者の体調管理に役立ちます。年齢や体調に応じて無理のない運動を継続することが重要です。
ウォーキングや軽い筋力トレーニングなど、医師と相談しながら取り入れる方が多いです。筋肉量が減少すると基礎代謝が落ち、糖尿病や心血管系のリスクが高まりやすくなるため、適度な運動は健康維持にとって意味が大きいです。
ただし、血圧の急激な変動を起こさないようこまめに体調をチェックし、透析後は特に休息を取りながら取り組む必要があります。
精神面の安定とサポート体制
透析を長期間続けていると、治療への不安や疲労、将来への心配などで精神的に落ち込みやすくなる方がいます。そうしたときに、カウンセリングや医療ソーシャルワーカーとの面談を通じて悩みを共有することが役立ちます。
また、家族や友人、同じ透析を受ける仲間と話す機会を増やすことで、孤立感を軽減できます。特に高齢の方や一人暮らしの方にとって、周囲とのコミュニケーションや定期的な見守りは大きな支えになります。
生活の質向上のために大切な点
- 自分に合った食事制限を無理なく継続
- 運動と休息のバランスを保つ
- カウンセリングや医療スタッフへの相談
- 家族や周囲との協力体制を築く
透析患者が意識したい栄養素と目安
| 栄養素 | 役割と注意点 | 摂取の目安(個人差あり) |
|---|---|---|
| タンパク質 | 筋肉維持や免疫力維持に役立つ | 透析状況や体重によって調整 |
| カリウム | 高値になると心臓に影響を及ぼす | 野菜や果物の摂取量を制限 |
| リン | 骨や血管に蓄積してトラブルを起こしやすい | 加工食品などの摂取を抑制 |
| ナトリウム | 高血圧を促進する恐れがある | 塩分制限を意識 |
| 水分 | 体に水分が溜まり血圧変動やむくみを引き起こす | 1日の制限量を守る |
合併症のリスクと対処法
透析を受けていると、腎機能以外の部分にもさまざまな影響が及びます。特に長期透析患者では、心血管疾患や感染症、骨や関節のトラブルなどが頻出しやすく、細心の注意が必要です。
合併症の予防や早期対処を心がけることで、透析による負担を減らし、より快適な日常生活を送りやすくなります。医師やコメディカルスタッフとの定期的なフォローアップが欠かせません。
心血管疾患への注意
心臓や血管の合併症は、人工透析余命60代や人工透析余命70代の方にとって特に大きなリスクとなります。透析は血液量や血圧に影響を与えるため、心臓に負担をかける場合があります。
動脈硬化が進んでいると、透析時の血液除水などでさらに血管障害を招く恐れもあるでしょう。血圧管理や不整脈の早期発見に努め、食事制限や運動、薬物療法などを組み合わせて心臓を守ることが大事です。
感染症リスクと対策
透析患者は免疫力が低下しがちなうえ、血液透析では血管アクセス(シャントやカテーテル)を介して細菌感染が起こる可能性があります。
腹膜透析の場合もカテーテルからの感染に注意が必要です。医療施設での感染予防対策だけでなく、患者自身が日常生活で手洗いや傷口の管理を徹底することが大切です。
インフルエンザや肺炎など一般的な感染症に対してもワクチン接種を検討し、重症化を防ぐ取り組みが求められます。
骨・関節トラブルの予防
長期透析を受けると、ミネラル代謝の乱れによって骨がもろくなる骨粗鬆症や関節の痛みを引き起こす透析アミロイドーシスなどが生じやすくなります。
特に人工透析余命40代や人工透析余命50代で長期間透析を続ける方が増えるにつれ、こうしたトラブルへの備えが必要性を増しています。
カルシウムやリンのコントロール、適度な運動や骨量測定の定期的な実施などを通じて、リスクを減らす工夫が求められます。
主な合併症と対処法の例
| 合併症 | 症状や特徴 | 主な対処法 |
|---|---|---|
| 心不全 | 息切れ、疲労感、むくみなど | 血圧管理、利尿薬の使用、循環器科との連携 |
| 感染症(シャント感染等) | 発熱、患部の腫れや痛み、膿の排出など | 手指衛生、抗生物質の投与、カテーテルの交換 |
| 骨粗鬆症 | 骨折リスクの増加、骨痛など | カルシウム・リン管理、骨密度検査、ビタミンD補給 |
| 透析アミロイドーシス | 関節の変形、疼痛、腱鞘炎など | 透析効率の向上、薬物療法、適切な運動療法 |
透析を受けながら働く・生活する工夫
透析治療を受けながらも、職場や家庭での役割を果たし、趣味や外出を楽しむ生活を送りたいと望む方は少なくありません。
とくに人工透析余命30代から40代の方には仕事や子育ての両立が大きなテーマとなり、高齢の方も介護や家事をこなしながら通院する事例が多く存在します。
自分のライフスタイルと治療をバランスよく組み合わせるためには、環境調整や制度の活用など、具体的な工夫が必要です。
仕事と治療を両立するためのコツ
就業中の方であれば、透析治療に伴う通院日や治療時間を踏まえて、勤務時間や休暇取得のスケジュールを調整する必要があります。
雇用形態や職種によっては在宅勤務や時短制度を利用できる場合もあり、事前に会社と相談しておくことで、負担を減らせるかもしれません。
急な体調不良や合併症の症状などに備えるためにも、同僚や上司に透析についての基本的な理解を得ておくと安心感が高まります。
日常生活を快適にするためのアイデア
通院や食事制限など、透析特有の制約が生じやすい中でも、普段の生活が過度に制限されないように工夫を重ねることが大切です。
調理の際は一度湯通しするなどしてカリウムを減らしたり、外食時は塩分量を意識してメニューを選んだりすることで制限のストレスを軽減できます。
出かける際には、透析後の疲れに配慮したゆったりめの行動計画を立てると、外出の機会を楽しみやすくなるでしょう。携帯用の血圧計や水分管理アプリなどを活用することで、体調をこまめにチェックする方も増えています。
社会福祉制度や経済的支援
透析に要する費用は、医療保険や高額療養費制度を使うことで自己負担を抑えることができます。働いている方であれば傷病手当金や障害年金などの給付金を検討できる場合もあり、経済的な安心材料となるかもしれません。
自治体によっては交通費の助成や医療費助成があるため、自分が住んでいる地域の制度を調べる意義は大きいです。透析にかかる費用負担を減らすことで、治療を継続しながら安定した暮らしを続ける余裕が生まれます。
生活しやすくするためのヒント
- 会社や学校とスケジュール相談し、柔軟な働き方を模索する
- 外出先でも血圧や体調をチェックする習慣をつける
- 調理方法の工夫でカリウムやリンを減らす
- 高額療養費制度や障害年金の仕組みを確認
透析患者が活用しやすい支援制度の例
| 制度・サービス | 内容 | 留意点 |
|---|---|---|
| 高額療養費制度 | 医療費が一定額を超えた場合に負担軽減 | 所得や年齢により自己負担額が異なる |
| 障害年金 | 働くことが難しい場合に年金を受給できる | 納付実績や障害認定基準による |
| 就労支援サービス | ハローワークや就労移行支援事業所など | 自分に合った就労形態を相談できる |
| 介護保険サービス | 訪問介護やデイサービスを利用できる | 要介護認定が必要、高齢者対象(原則65歳以上) |
透析患者と家族のコミュニケーションとサポート
透析治療を受ける本人だけでなく、家族にも心身の負担がかかることがあります。特に高齢の親を介護している場合や、若い世代の親が透析治療を行っている場合など、関わる家族の状況によってサポートの形はさまざまです。
気になることを率直に話し合い、役割分担を明確にしながら進めると、生活や心身の負担が和らぎやすくなります。
家族や周囲との情報共有
透析の仕組みや注意点を家族と共有しておくと、日常生活でのサポートがスムーズになります。とくに食事制限や水分制限が必要な場合、家族が同じメニューを工夫して一緒に取り組んでくれると心強いです。
家族にとっても、どのようなときに緊急対応が必要なのか、症状の変化を見分けるポイントなどを把握しておくと安心感が高まるでしょう。
本人が疲れて調理できないときや通院に同行してほしいときに、互いに助け合える体制を整えることが重要です。
医療スタッフとの連携
主治医や看護師、管理栄養士などは、透析治療に関する専門知識を持った頼もしいパートナーです。
小さな疑問や不安も遠慮せずに相談することで、症状の変化を早めに察知したり、ライフスタイルに合わせたアドバイスをもらえたりします。
高齢者や合併症を多く抱える方ほど、多職種が連携して情報を共有しながらケアプランを作成することが欠かせません。
家族が同席して相談を受けたり、定期的に面談の時間を設定してもらったりすると、医療者とのコミュニケーションが円滑になります。
一人ひとりの選択肢を尊重する意義
透析を始めるタイミングや治療方法、生活スタイルなどは人それぞれです。本人が大切にしたい価値観やライフプランを考慮しながら、家族としてサポートするのが望ましい姿といえます。
高齢者の場合、延命よりも生活の質を重視したいケースがあれば、その希望を理解して医療スタッフと共に調整することが必要かもしれません。
逆に若年層の場合は、長期的な人生設計に基づいて働き方や家庭計画を見直す場面も出てきます。どの年代においても、本人の気持ちに寄り添ったサポートこそが大きな支えになっていくでしょう。
家族との情報共有をスムーズにするコツ
| 方法 | メリット | 注意点 |
|---|---|---|
| 共有アプリやノート | 通院日程や体調を一元管理 | 個人情報の取り扱いに注意 |
| こまめなミーティング | お互いの状況を理解しやすい | 時間の調整が必要、頻度を決めておく |
| 医療スタッフを交えた面談 | 正確な情報交換が可能 | 事前予約が必要で、家族全員の予定を合わせる必要がある |
透析治療と長期的な展望
透析を始めると長期的な治療となり、体力面だけでなく精神面、経済面など複合的な課題が生じます。しかし、適切なケアや周囲のサポートを得ながら生活リズムを整えていけば、趣味や仕事を続けながら充実した日常を送ることも十分可能です。
人工透析余命80代を迎えても安定した状態で生活している方はたくさんいます。実際にどのように過ごすかは、自分と家族、そして医療スタッフとの話し合いによって作り上げられるものです。
定期的な評価と治療方針の見直し
透析を続ける中では、体の状態やライフステージの変化に合わせて治療内容を見直すタイミングが出てきます。例えば、血液透析から腹膜透析に切り替える方や、逆に自己管理の負担が大きいと感じて血液透析へ変更する方もいます。
また、透析頻度や除水量の調節によって、体力的・経済的負担を軽減するケースもあります。
主治医との定期的な面談や検査をもとに、「今の自分に合う治療スタイルは何か」を考え続けることで、より納得感のある療養生活を送りやすくなります。
個人に合わせた生活習慣の調整
食事や運動、休養のバランスは年代や病状、個人の嗜好によって変わります。若年層であれば外出や旅行の機会が多く、食事制限が難しくなる局面があるかもしれません。
一方、高齢者は外出頻度が低い反面、体力維持のために短時間の運動を習慣化することが必要です。透析中は水分制限も大きな課題となりやすいため、個々のライフスタイルに合わせて具体的な方法を検討しましょう。
医療スタッフや栄養士、リハビリ専門職の意見を集めながら、少しずつ無理のない調整を行うことが重要です。
受診を検討する方へのメッセージ
腎臓病が進行して人工透析を検討するときは、不安や戸惑いを感じるのが自然です。しかし、透析を導入している方の多くは自分のペースで日常を営み、時には旅行や趣味を楽しむなど前向きに暮らしています。
年代別に課題が異なるものの、適切な情報や支援を得れば、透析を続けながら質の高い生活を目指すことは十分可能です。
自覚症状が少ないうちから定期検査を受け、腎機能の低下が疑われる場合には早めに受診すると、治療の選択肢が広がる傾向があります。心配があるときは遠慮なく医療機関を頼ってください。
健康維持に向けての実践アイデア
- こまめな血液検査や腎機能検査で変化を早期に捉える
- 専門医や専門スタッフのいる施設を活用する
- 家庭でできるリラクゼーション法(深呼吸、マッサージなど)
- 信頼できる情報源で透析に関する最新の情報を得る
主な指標と適切な検査頻度の目安
| 指標 | 意味 | 検査頻度の例 |
|---|---|---|
| eGFR | 腎機能の推定値 | 年に2~4回程度 |
| 血清クレアチニン | 腎臓のろ過機能を反映 | 定期的にチェックする |
| ヘモグロビン | 貧血の指標 | 月1回~2回程度 |
| カリウム | 心機能への影響が大きい | 状態に応じて定期的に測定 |
| リン・カルシウム | 骨代謝への影響が大きい | 1~3カ月に1回程度 |
以上
参考文献
ABDEL-KADER, Khaled, et al. Individual quality of life in chronic kidney disease: influence of age and dialysis modality. Clinical Journal of the American Society of Nephrology, 2009, 4.4: 711-718.
PAGELS, Agneta A., et al. Health-related quality of life in different stages of chronic kidney disease and at initiation of dialysis treatment. Health and quality of life outcomes, 2012, 10: 1-11.
DA SILVA-GANE, Maria, et al. Quality of life and survival in patients with advanced kidney failure managed conservatively or by dialysis. Clinical Journal of the American Society of Nephrology, 2012, 7.12: 2002-2009.
BROWN, Mark A., et al. CKD in elderly patients managed without dialysis: survival, symptoms, and quality of life. Clinical Journal of the American Society of Nephrology, 2015, 10.2: 260-268.
FRUCTUOSO, M., et al. Quality of life in chronic kidney disease. Nefrología (English Edition), 2011, 31.1: 91-96.
KEFALE, Belayneh, et al. Quality of life and its predictors among patients with chronic kidney disease: A hospital-based cross sectional study. PloS one, 2019, 14.2: e0212184.
CRUZ, Maria Carolina, et al. Quality of life in patients with chronic kidney disease. Clinics, 2011, 66.6: 991-995.
LAMPING, Donna L., et al. Clinical outcomes, quality of life, and costs in the North Thames Dialysis Study of elderly people on dialysis: a prospective cohort study. The Lancet, 2000, 356.9241: 1543-1550.
FUKUHARA, Shunichi, et al. Health-related quality of life among dialysis patients on three continents: the Dialysis Outcomes and Practice Patterns Study. Kidney international, 2003, 64.5: 1903-1910.
NORTH THAMES DIALYSIS STUDY (NTDS) GROUP. Clinical outcomes and quality of life in elderly patients on peritoneal dialysis versus hemodialysis. Peritoneal Dialysis International, 2002, 22.4: 463-470.