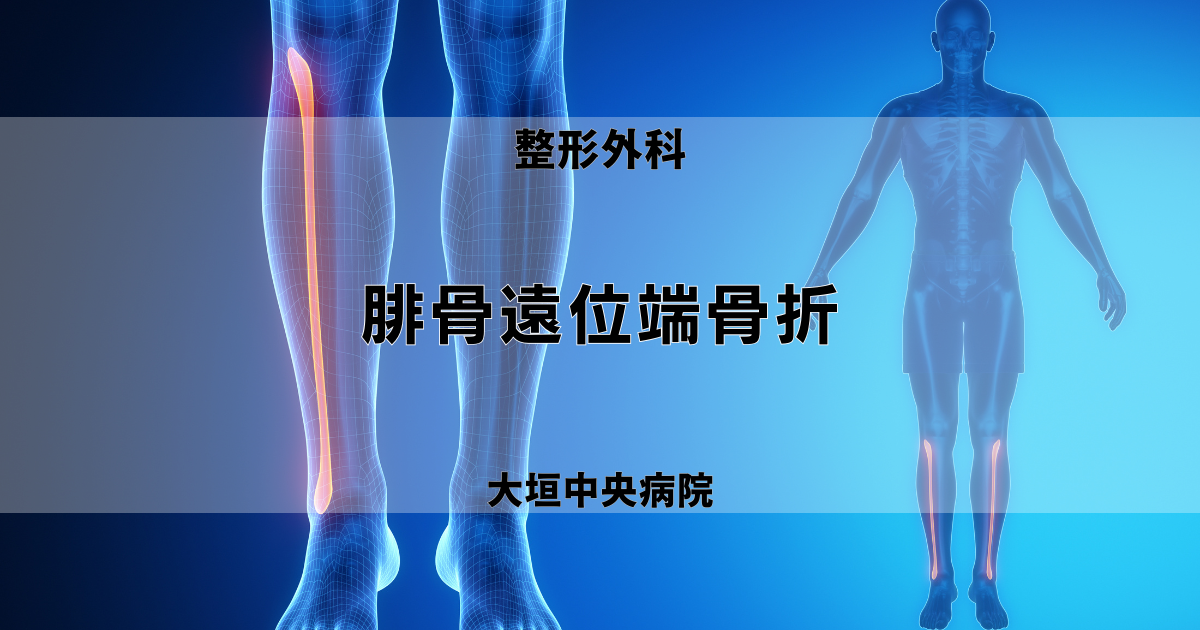腓骨遠位端骨折(distal fibular fractures)は、足首の外側にある腓骨(ひこつ)の下部分が折れたり損傷したりする外傷です。
スポーツや突発的な事故などで、足首が急に捻じれてしまう際に発生するケースが多いほか、足首への急な負荷も腓骨遠位端骨折の原因になりえます。
主な症状は、痛みや腫れ、歩きにくさなどですが、重症の際には手術が必要となる場合もあります。
この記事の執筆者

臼井 大記(うすい だいき)
日本整形外科学会認定専門医
医療社団法人豊正会大垣中央病院 整形外科・麻酔科 担当医師
2009年に帝京大学医学部医学科卒業後、厚生中央病院に勤務。東京医大病院麻酔科に入局後、カンボジアSun International Clinicに従事し、ノースウェスタン大学にて学位取得(修士)。帰国後、岐阜大学附属病院、高山赤十字病院、岐阜総合医療センター、岐阜赤十字病院で整形外科医として勤務。2023年4月より大垣中央病院に入職、整形外科・麻酔科の担当医を務める。
腓骨遠位端骨折の病型
腓骨遠位端骨折の病型を分ける際には、腓骨遠位端の骨折線の位置から3つのタイプに分類する「ウェーバー分類(Danis-Weber Classification)」を使用します。
足関節の構造と腓骨遠位端骨折
足関節は単体で存在しているわけでなく、脛骨、腓骨、距骨と呼ばれる骨の集合体によって形成されています。
そして、足首周辺には、足首を支える3つの靱帯群が存在しています。
具体的には、足首の内側は三角靱帯、外側は外側靭帯(前距腓靱帯、踵腓靱帯、後距腓靱帯)、脛骨遠位と腓骨遠位を連結する部分はシンデスモーシスという靱帯が足首の骨を支えています。
腓骨遠位端骨折は、足首を構成している腓骨部分が骨折してしまうことをいいます。
ウェーバーA型骨折の特徴
腓骨遠位の骨折線がシンデスモーシスの高さより下にあるタイプの骨折です。
通常、このタイプの骨折は骨折した部分が動きにくく、骨の位置を保ちやすいため、保存療法が可能なケースが多いです。
ウェーバーA型骨折は、X線とCTスキャンで診断できます。
ウェーバーB型骨折の特徴
シンデスモーシスと同じ高さに骨折線が存在するタイプの骨折です。
この部分は足首の回転機能を担っている部分であるため、治療の際には骨折部位を正しい位置に戻し、固定する処置がとられます。
骨折の原因としても、無理な足首の回転にともなう損傷や骨折によるケースが多いです。
ウェーバーB型骨折は、靭帯損傷(三角靭帯やシンデスモーシス)が頻発して見られる点も特異な特徴として挙げられます。
三角靭帯の深部に断裂があると、距骨が身体の外側に移動したり距骨が傾斜したりといった問題が生じるのですが、理学所見で内側に圧痛があっても三角靭帯断裂の正確な予測にはならないため、慎重に診断を進めていく必要があります。
ウェーバーC型骨折の特徴
C型骨折は、シンデスモーシスよりも膝側に位置する部分に骨折線が存在するタイプです。ウェーバーC型骨折は、足関節の安定感にはあまり影響しません。
しかし、油断は禁物で、骨折部分が広範囲に及ぶ際や複雑な骨折をしている疑いがある場合には注意が必要です。こちらの病型も、足首が内側および外側に回転した際に起こりやすいものです。
他に、腓骨骨折に関連する足関節外傷には以下のものがあります。
メゾヌーブ損傷
回内―外旋損傷※1によって生じる不安定な足関節の損傷です。
腓骨近位部骨折とシンデスモーシスおよび三角靭帯損傷を組み合わせた損傷を指し、足首の内くるぶし部分にある内果部分の骨折を伴うものと伴わないものがあります。
通常、手術治療が選択されます。
※1回内―外旋損傷:足部が回内(内側に捻れる)し、同時に外旋(外側に捻れる)力が加わる際に発生する外傷。
ボスワース骨折-脱臼
腓骨が後方に脱臼するまれなタイプの足関節骨折です。
脛骨後縁※2が、腓骨骨片が元に戻るのを妨げるため、腓骨を元の位置に戻し固定する手術治療が必要となります。
※2脛骨後縁:すねの骨である脛骨の後ろ側にある縁(ふち)。
腓骨遠位端骨折の症状
腓骨遠位端骨折の主な症状には、足首の疼痛や腫れ、皮膚の変色や歩きにくさなどが挙げられます。
足首の疼痛と腫れ
足首の疼痛と腫れは最も起こりやすい症状です。腓骨遠位端骨折を患ったほとんどの方に、疼痛や腫れが見られます。
特に足首の外側部分が強烈に痛むケースが多く、足を踏みしめた際や動かした際に痛みは強く感じやすいです。
疼痛が起こっているということは周辺組織に炎症が起こっているとも考えられ、その場合、炎症にともなう組織の腫れも見られます。
皮膚の変色と触診時の圧痛
骨折すると、周辺の皮膚に内出血が起こり皮膚の変色が見られますが、腓骨遠位端骨折も例外ではありません。
一般的には、骨折部位の皮膚に紫色や青色の斑点が出現し、時間の経過とともに内出血が治癒していくと黄色や緑色へと変化していきます。
また、診断時には患部を触って骨折部位を確認する触診を行いますが、患部を触ると強い痛みを感じる“圧痛”をともなう場合があります。
歩きにくさ、関節の動きにくさ
腓骨遠位端骨折は足首に関する骨折であるため、痛みのために足関節を動かしにくくなるほか、歩きにくい、歩けなくなるなどの症状が見られます。
骨折場所や骨折の範囲にもよりますが、重度の骨折の場合は、足を床につけるだけでも強い痛みを感じるかもしれません。
関節は複数の骨と靭帯が組み合わさって機能している部分であるため、たとえ小さな骨折だったとしても、構造的なバランスが失われて歩行が不安定になってしまいます。
腓骨遠位端骨折の原因
腓骨遠位端骨折の根本的な原因は腓骨の骨折ですが、骨折に至る原因については、突発的な外傷・足首の無理な回転・疲労骨折等が挙げられます。
直接的な外力による骨折
高所からの転落、スポーツ時の衝突といった急な外力は、腓骨遠位端骨折で最もよく見られる原因です。
足関節部分に衝撃時の力が集中し、腓骨部分が力に耐えきれずに骨折してしまうために起こります。
外力による骨折では、骨だけでなく靭帯や軟部組織などの周囲にまで損傷が及んでいるケースも珍しくありません。
捻転力による骨折
足首に過度な回転がかかってしまう際に起こる骨折です。
例えば、サッカーやバスケットボールのプレー中に急な方向転換をしてしまい足首に負担がかかってしまった際、階段を踏み外して足首を捻ってしまった際などに起こりやすいです。
関節の可動域を越えてしまうほどに力が加わってしまうと起こります。
捻転力による骨折は、力が加わる方向に合わせて特徴的な損傷形態が見られるため、骨折型からどのような力が加わったかを推定することができます。
最も一般的なのは回内-外旋による損傷で、約60%を占めています。
疲労骨折によるもの
疲労骨折とは、小さな損傷が治りきる前に新しい損傷が加わることで骨の構造が弱くなってしまい、ついに骨折してしまうような状態を指します。
長距離ランナーやバレエダンサーなど、繰り返し足首を酷使するようなスポーツを行う方に多くみられるタイプの骨折です。
また、骨粗しょう症の方も関節部分の骨も脆くなっているため、腓骨遠位端骨折をおこす可能性があります。
腓骨遠位端骨折の検査・チェック方法
腓骨遠位端骨折の診断には、問診や触診、画像検査、可動域テストなどが用いられます。
検査は単体で行う場合もあれば、複数を組み合わせて行う場合もあります。
問診、視診、触診
問診では、どのような状況で関節を痛めるに至ったのか、痛みや症状の性質、歩行の様子などを詳しく尋ねます。また、受傷前の運動レベルや普段の活動、機能的目標についても確認します。
視診で確認する主な点は、足首の外観や腫れの具合、皮膚の色味などです。
触診では、痛みを感じる部分の確認、骨の変形、関節部分の不安定性を確認します。重度の腓骨遠位端骨折の場合には、ピロン骨折※3やコンパートメント症候群※4の可能性が疑われます。
※3ピロン骨折:脛骨におこる複雑な骨折。
※4コンパートメント症候群:筋肉や神経が圧迫され、血流が阻害される状態。
画像診断
腓骨遠位端骨折の確定診断には、画像検査が必ず必要です。通常ではまず、X線検査から行います。X線は、足首の前後方向、側面方向、そして必要に応じて斜め方向から撮影します。
骨折線の有無、ずれの程度、関節面の状態などを細かく見ていきます。場合によっては、関節の安定性を評価するためにgravity testや外旋ストレスをかけて撮影することもあります。
より精密な画像検査が必要だと判断された場合には、CTスキャンを用います。CTスキャンは、立体的に骨折部分を見られるほか、損傷の際に生じた細かな骨片を見つける点でも役に立ちます。
重度の腓骨遠位端骨折で靭帯や軟骨にまで損傷が及んでいる可能性があると判断した場合には、MRI撮影が行われます。
機能評価
機能評価では、関節の可動域のチェックや筋力テストなどの検査を行い、より詳細に患者様の容体を分析します。
| 機能評価 | 詳細 |
|---|---|
| 関節可動域(ROM)測定 | 足首の動きを評価 |
| 筋力テスト | 周囲の筋肉の強さや神経学的な問題の有無を確認 |
| 歩行分析 | 歩き方、足首にかかる負担を評価 |
腓骨遠位端骨折の治療方法と治療薬、リハビリテーション
腓骨遠位端骨折の治療は、保存療法と手術療法を骨折の状態に応じて選択し、薬物療法とリハビリテーションを組み合わせて行います。
保存療法
保存療法は、足関節が比較的安定している場合に選択されます。ギブスや装具を用いて骨折部分を固定し、自然に骨を治癒させていく治療方法です。
侵襲性の低い治療であるため手術による副作用やリスクを避けられるメリットがありますが、固定期間が長くなってしまう側面があります。
手術療法
骨の状態が不安定であったり関節面にまで及んでいたりする際には、手術療法が選択されます。
軟部組織の腫れが強い場合や開放骨折の場合などには、第一段階として、不安定な足関節骨折を一時的に固定するために創外固定を行います。
具体的には、創外固定器※5という器具を用い、足関節を正常な位置に固定し、軟部組織が落ち着くのを待ちます。
その後、軟部組織の腫れが引いて安全に閉鎖できるようになれば、第二段階として足関節の手術を行えるようになります。
※5創外固定器:金属製のピンやスクリューを骨に直接挿入し、体の外側にあるフレームで連結することで骨折部位を固定できるというもの。
薬物療法
腓骨遠位端骨折における薬物療法は、鎮痛や骨形成を促進する目的で用いられます。
| 薬剤の種類 | 目的 |
|---|---|
| NSAIDs(非ステロイド性抗炎症薬) | 炎症と疼痛の軽減 |
| ビスホスホネート | 骨密度の増加 |
骨形成を促進する薬剤は、特に高齢の方や骨粗鬆症(こつそしょうしょう)の患者様の骨癒合に有効です。
リハビリテーション
早期からのリハビリテーションは、関節拘縮(かんせつこうしゅく:関節の動きが制限されること)の予防と機能回復に役立つとされています。
リハビリテーションプログラムは、骨折の治療段階に応じて少しずつ負荷を強めていくよう進められます。
| リハビリ段階 | 内容 |
|---|---|
| 初期 | 関節可動域訓練、等尺性筋力トレーニング※6 |
| 中期 | 荷重訓練、バランス訓練 |
| 後期 | 日常生活動作練習、スポーツ特異的トレーニング |
※6等尺性筋力トレーニング:関節を動かさずに筋肉に力を入れるトレーニング
薬の副作用や治療のデメリット
腓骨遠位端骨折の治療には保存療法と手術療法がありますが、双方にデメリットが存在します。
保存療法のリスク
保存療法ではギブスや装具を用いての固定が主な治療となりますが、長期の固定で患部の自由が拘束されてしまうデメリットがあります。
長期間の固定は身動きがとりにくいだけでなく、筋萎縮や関節拘縮のリスクが生じる点にも注意が必要です。
また、ギブスや装具の装着により皮膚がかぶれ痒みや湿疹が生じるといったトラブルが考えられるほか、血流が悪くなってしまうと深部静脈血栓症(DVT)のリスク上昇といった弊害も考えられます。
手術療法のリスク
手術療法は骨折部位を直接固定できるため、より早期の機能回復が期待できるメリットがありますが、手術特有のリスクも存在します。
| 手術療法で考えられるリスク | 詳細 |
|---|---|
| 感染症 | 治癒の遅れや疼痛、腫れの可能性。骨髄炎に発展してしまうケースも。 |
| 神経損傷 | 足首の曲げ伸ばしの困難さや感覚異常が残る可能性。 |
| 血管損傷 | 術後の出血や血流障害につながる可能性。 |
リハビリテーションのリスク
リハビリテーションでは、骨折の治癒状況に応じてだんだんと負荷を上げていき、通常通りの動きができるような道を辿っていくのが理想です。
しかし、早期のうちに負荷をかけすぎてしまうと骨折部分が再度ずれてしまったり、骨を固定している器具が破損してしまったりする恐れがあります。
逆に負荷が不十分になると、関節拘縮や筋力低下のリスクが上がってしまう恐れがあります。
骨の状態を確認しながら、バランスのよい負荷をかけていかなければいけません。
保険適用と治療費
以下に記載している治療費(医療費)は目安であり、実際の費用は症状や治療内容、保険適用否により大幅に上回ることがございます。当院では料金に関する以下説明の不備や相違について、一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。
腓骨遠位端骨折の治療では健康保険が適用できるため、患者様の自己負担額は通常3割となります。
ただし、治療方法や入院期間によって総額は変動します。
保存療法の費用の目安
保存療法を選択した場合、主な費用はギプス固定や装具の費用です。
3割負担で計算すると、ギブスの固定に3000円~5000円程度、装具を用いる場合は1~3万円が目安です。
ここに、X線検査や定期的な診察費用が追加されます。
手術療法の費用の目安
手術療法を選択する場合、手術料・麻酔料・入院費・術後のリハビリテーション費用がかかります。
手術方法によって費用は大きく異なるものの相場としては3割負担で20~40万円程度が目安となります。
リハビリテーション費用の目安
リハビリテーションも保険適用内で利用でき、1回の自己負担額は3割負担で500円~1000円程度です。
例えば、週3回のリハビリテーションを1ヶ月かけて行う場合、リハビリにかかる総額は3割負担で6000円~1万2000円程度、3ヶ月かけてリハビリを行う場合は1万8000円~3万6000円程度かかる計算になります。
以上
参考文献
Takao M, Uchio Y, Naito K, Fukazawa I, Kakimaru T, Ochi M. Diagnosis and treatment of combined intra-articular disorders in acute distal fibular fractures. Journal of Trauma and Acute Care Surgery. 2004 Dec 1;57(6):1303-7.
Jain S, Haughton BA, Brew C. Intramedullary fixation of distal fibular fractures: a systematic review of clinical and functional outcomes. Journal of Orthopaedics and Traumatology. 2014 Dec;15:245-54.
Schepers T, Van Lieshout EM, De Vries MR, Van der Elst M. Increased rates of wound complications with locking plates in distal fibular fractures. Injury. 2011 Oct 1;42(10):1125-9.
Bonnevialle P, Lafosse JM, Pidhorz L, Poichotte A, Asencio G, Dujardin F, of Orthopaedics TF. Distal leg fractures: How critical is the fibular fracture and its fixation?. Orthopaedics & Traumatology: Surgery & Research. 2010 Oct 1;96(6):667-73.
Tas DB, Smeeing DP, Emmink BL, Govaert GA, Hietbrink F, Leenen LP, Houwert RM. Intramedullary fixation versus plate fixation of distal fibular fractures: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials and observational studies. The Journal of Foot and Ankle Surgery. 2019 Jan 1;58(1):119-26.
Luong K, Huchital MJ, Saleh AM, Subik M. Management of distal fibular fractures with minimally invasive technique: a systematic review. The Journal of Foot and Ankle Surgery. 2021 Jan 1;60(1):114-20.
Mitchell JJ, Bailey JR, Bozzio AE, Fader RR, Mauffrey C. Fixation of distal fibula fractures: an update. Foot & ankle international. 2014 Dec;35(12):1367-75.
Marvan J, Horak Z, Vilimek M, Horny L, Kachlik D, Baca W. Fixation of distal fibular fractures: a biomechanical study of plate fixation techniques. Acta of Bioengineering and Biomechanics. 2017;19(1).
Canton G, Sborgia A, Maritan G, Fattori R, Roman F, Tomic M, Morandi MM, Murena L. Fibula fractures management. World journal of orthopedics. 2021 May 5;12(5):254.
Schaffer JJ, Manoli 2nd A. The antiglide plate for distal fibular fixation. A biomechanical comparison with fixation with a lateral plate. JBJS. 1987 Apr 1;69(4):596-604.