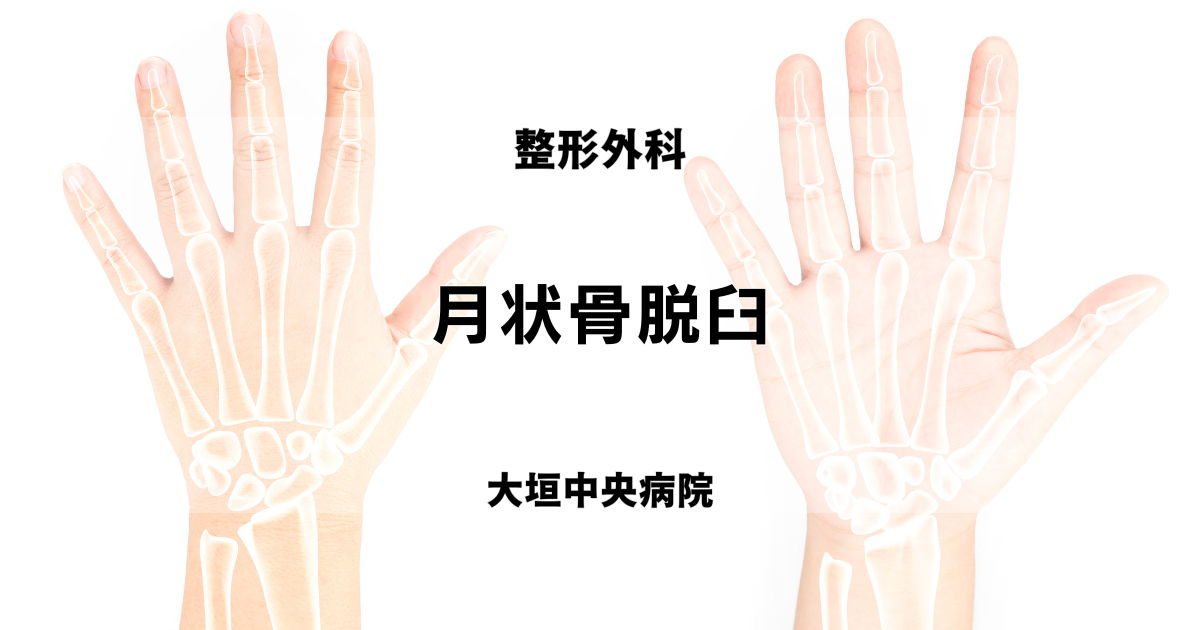月状骨脱臼(げつじょうこつだっきゅう. lunate dislocations)とは、私たちの手首を形作る8個の手根骨のうちの一つである月状骨が、事故や転倒などの強い外力によって、本来あるべき位置から前方または後方へと逸脱してしまう深刻な外傷性の疾患です。
日常生活やスポーツ活動中に手首に強い衝撃が加わった際、あるいは不意の転倒で手をつくような状況下で発生するケースが多く、耐え難い激痛が走り、手首の可動域が著しく制限されるようになります。
放置してしまうと手首の永続的な機能障害や慢性的な疼痛を引き起こす可能性があるため、早期発見と医療機関での診断が非常に重要です。
発症する可能性が特に高いのは、若年層のスポーツ活動中や交通事故の際、また高所からの転落などの事故の際で、腫脹や変形、激痛といった特徴的な症状を伴うケースが多いです。
この記事の執筆者

臼井 大記(うすい だいき)
日本整形外科学会認定専門医
医療社団法人豊正会大垣中央病院 整形外科・麻酔科 担当医師
2009年に帝京大学医学部医学科卒業後、厚生中央病院に勤務。東京医大病院麻酔科に入局後、カンボジアSun International Clinicに従事し、ノースウェスタン大学にて学位取得(修士)。帰国後、岐阜大学附属病院、高山赤十字病院、岐阜総合医療センター、岐阜赤十字病院で整形外科医として勤務。2023年4月より大垣中央病院に入職、整形外科・麻酔科の担当医を務める。
月状骨脱臼の病型
月状骨脱臼(げつじょうこつだっきゅう)は解剖学的な位置関係から掌側脱臼、背側脱臼、そして月状骨周囲脱臼の3つの主要な病型に分類できます。
解剖学的特徴からみた病型分類の意義
手根骨の中でも特異な位置づけにある月状骨は、複雑な解剖学的構造と生体力学的特性を持つため、その脱臼形態も多様な様相を呈します。
解剖学的な位置関係と周囲の靭帯構造の破綻パターンによって、脱臼の形態が大きく異なることから、的確な病型分類が診断の基盤となります。
月状骨がもともとの位置にあり、舟状骨・三角骨・遠位主根列が一塊となって脱臼するのが月状骨周囲脱臼で、月状骨のみが掌側や背側(ごく稀)に脱臼するのが月状骨脱臼です。手根骨間の複雑な靭帯構造が破綻するため、手関節全体の生体力学的特性に大きな影響を及ぼします。
このような複雑な病態を呈する月状骨周囲脱臼においては、個々の症例における解剖学的破綻のパターンの詳細な把握が欠かせません。
手関節の機能解剖学的な理解に基づいた病型分類は、その後の治療方針の決定において極めて大きな意義を持つものと考えられます。
月状骨脱臼の症状
月状骨脱臼(げつじょうこつだっきゅう)の症状は、手首の激痛や腫脹、可動域制限から始まり、進行すると手根管症候群様の神経症状や、手指の巧緻運動障害まで引き起こす重篤な外傷性疾患であり、早期発見と正しい対応が必要不可欠な状態といえます。
初期症状の特徴
| 初期症状 | 特徴的な所見 |
| 疼痛 | 手首背側の強い痛み |
|---|---|
| 腫脹 | 手首背側の腫れ |
| 可動域制限 | 屈曲・伸展制限 |
| 圧痛 | 手根骨部の圧痛 |
受傷直後から手首の背側(甲側)に著明な腫脹が出現し、同部位に強い圧痛を伴う人が多く、激しい痛みのために手首をほとんど動かせない状態となってしまいます。
手首を曲げる動作や回転させる動きに著しい制限が生じ、日常生活における基本的な手の使用にも困難をきたすようになり、この状態を放置してしまうと症状が徐々に進行していく傾向にあります。
神経症状について
月状骨の脱臼により手根管内で正中神経が圧迫され、手のしびれや感覚障害が出現する場合があり、特に親指から中指にかけての領域でしびれ感や痛みを強く感じる人が多いといった特徴があります。
夜間になると症状が悪化する傾向があり、これは就寝時の手首の位置や圧迫により神経への刺激が増強される点に起因していると考えられています。
手指の巧緻運動障害も顕著に現れ、物をつまむ動作や細かい作業に著しい支障をきたすようになり、進行性に症状が悪化していく可能性が指摘されています。
進行性の症状変化
症状は受傷直後から、時間の経過とともに変化していきます。
初期(受傷直後)
- 手首の激痛
- 著明な腫脹
- 手首の可動域制限
亜急性期(数日後)
- 手指のしびれ
- 感覚障害
- 把持力低下
慢性期(数週間後)
- 手根管症候群様症状
- 手指の巧緻運動障害
- 慢性疼痛
随伴症状と合併症
| 随伴症状 | 関連する解剖学的構造物 |
| 靭帯損傷 | 月状骨周囲靭帯 |
|---|---|
| 骨配列異常 | 舟状骨・有頭骨 |
| 関節包損傷 | 手根中央関節包 |
| 軟部組織損傷 | 手根管内組織 |
月状骨脱臼に伴い、手関節周囲の靭帯損傷や周囲の手根骨の配列異常が発生する場合があり、これらの随伴症状は長期的な機能障害につながる重要な要素となっています。
手関節周囲の複雑な解剖学的構造により、一度発生した脱臼は周囲組織にも大きな影響を及ぼし、特に靭帯損傷や関節包損傷は慢性的な不安定性の原因となるケースが多いとされています。
重症度評価の指標
腫脹の程度や疼痛の強さ、神経症状の有無などから総合的に判断される重症度は、その後の経過に大きく影響を与える要素です。
手指の感覚障害や運動障害の範囲、程度によって神経損傷の程度を評価でき、これらの所見は経時的な症状の変化を把握する上で大切な指標となります。
定期的な経過観察により症状の進行や改善を評価していくと、より正確な状態把握が可能となり、長期的な予後の推測にも役立つものとされています。
月状骨脱臼の原因
月状骨脱臼(げつじょうこつだっきゅう)は、手関節に対する強い外力や捻り、そして手をついた際の衝撃によって引き起こされる外傷性の疾患であり、手根骨間の靭帯損傷を伴って発生します。
月状骨の解剖学的特徴と受傷機序
手は複雑な解剖学的構造を持ち、8個の手根骨が互いに精緻な配列を保ちながら、靭帯によって強固に結合されている特徴があります。
この繊細な構造において、月状骨はその名が示すように、三日月形の半月状骨です。近位端は凸状で、橈骨遠位端の凹状の月状小面と関節します。遠位端の関節面は凹状で、手根骨と関節を形成します。
月状骨は、橈側では舟状骨に、尺側では三角骨に接しており、それぞれ舟状靱帯および月状三角靱帯によって連結しており、月状骨は、前腕と手指をつなぐ中心的な要として機能しています。
手をついた際に手関節に加わる強い衝撃は、この複雑な構造に対して破壊的な力を及ぼすときがあり、特に手関節が極端な背屈位や掌屈位にある状態での受傷が多く見られます。
病態としてはMayfieldの説が有名です。これは、手関節過伸展損傷の時に、舟状月状骨間靱帯損傷、月状骨遠位脱臼、月状三角骨間靱帯の順に断裂がすすむといった経過を指します。
外傷の発生状況と力学的要因
- 転倒時に手をつく際の急激な衝撃
- ラケットやバットによる直達外力
- 格闘技での受け身の失敗
- 球技での壁や地面への衝突
- 手関節の過度な捻り動作
月状骨脱臼を引き起こす外力の作用方向と大きさは、日常生活における様々な状況で発生する不可欠な検討事項です。
交通事故や転落事故などの高エネルギー外傷では、手関節に対して複雑な方向から強い外力が加わるため、靭帯装置の破綻と月状骨の位置異常が引き起こされます。
職業性要因と環境因子
| 職業性要因 | 関連する作業内容 |
| 重量物取扱 | 荷物の積み下ろし |
|---|---|
| 工具使用 | 振動工具操作 |
| 手首捻り | 組立作業 |
| 反復動作 | キーボード作業 |
産業現場における重量物の取り扱いや工具の使用など、職業に関連した反復性の外力も、月状骨脱臼の発生要因として認識されています。
解剖学的素因と個体要因
手関節の解剖学的な個人差や靭帯の緩みなどの素因的要素も、月状骨脱臼の発生に関与していると示唆されています。
先天的な靭帯の脆弱性や手根骨の形態異常を持つ人においては、比較的軽微な外力でも脱臼が発生する可能性が高まると臨床的な観察から明らかになっています。
生体力学的観点からの分析
手関節に作用する外力の方向と大きさは、月状骨周囲の靭帯系に対して複雑な応力を発生させ、その結果として様々な損傷パターンが起きます。
手関節の背屈あるいは掌屈が極端な位置にある状態で外力が加わった際には、靭帯系に対して過度な緊張が生じ、これが月状骨の脱臼を引き起こす直接的な原因です。
このような複雑な発生機序を理解することは、予防医学的な観点からも大切な意味を持つものと考えられます。手関節の解剖学的特徴と外力が作用した際の生体力学的な応答についての理解を深めると、より効果的な予防策の立案につなげやすいです。
月状骨脱臼の検査・チェック方法
月状骨脱臼(げつじょうこつだっきゅう)の的確な診断には、詳細な身体所見の確認と複数の画像検査による総合的な評価が必要不可欠です。
初診時の基本的な診察手順
| 身体所見項目 | 確認するポイント |
| 視診 | 手関節背側の腫脹状態 |
|---|---|
| 触診 | 圧痛の部位と程度 |
| 可動域 | 掌屈・背屈の制限 |
| 神経症状 | しびれの有無と範囲 |
手関節の外傷を訴えて来院された患者さまに対しては、まず視診と触診による丁寧な身体所見の確認から診察を開始します。
腫脹の程度や変形の有無、圧痛点の位置などを細かく確認すると、月状骨脱臼の可能性を探れます。手関節背側の腫脹が顕著で、手根管付近に明確な圧痛を認めるケースがあり、これらの所見は月状骨脱臼を示唆する重要な手がかりとなります。
手関節の可動域検査も欠かせない確認事項となっているため、掌屈と背屈の制限の程度を特に注意深く観察していきます。月状骨脱臼では、通常の可動域と比較して著しい制限が見られるケースが多く、この所見は診断の一助となります。
画像診断による詳細な評価
身体所見の次のステップとして、複数の画像検査による客観的な評価を進めていきます。
単純X線検査では、手関節の側面像において月状骨の位置異常を確認でき、これは月状骨脱臼の診断において最も基本的かつ有用な情報源となりますが、25%の症例で見逃しが発生するともいわれています。
X線検査
X線写真は、前後面、側面、斜位、舟状骨など複数の方向で撮影しますが、いくつかの典型的なX線異常が認められます。
前後像では、舟状月状骨間隔が3mm以上異常に広がっている場合(すなわち、Terry Thomas徴候)は、舟状月状靱帯損傷を示すときがあります。
さらに、正常な手根ライン(Gilulaライン)の消失は、手根損傷を疑うべきです。2番目の円弧は舟状骨、月状骨、および三角骨の遠位縁と一致し、最後の円弧は主根骨と有鉤骨の近位縁の合流点をなぞります。月状骨は回転すると三角形に見えるときがあり、これは「ピース・オブ・パイ徴候」として知られています。
側方X線写真では、橈骨遠位端の関節面、月状骨、帽状骨、および第3中手骨軸を形成する結線があるかどうかを判定する必要があります。このアライメントが崩れていれば、手根不安定症またはアライメント異常を疑うべきです。
さらに、側面像では月状骨の掌側転位に伴い、古典的に記載されている「こぼれたティーカップの徴候」が認められるケースがあります。
CT・MRI検査
CTやMRIなどの精密検査では、月状骨周囲の軟部組織の状態や他の手根骨との位置関係をより詳しく把握可能です。
CTでは三次元的な骨の位置関係を特に明確に捉えられ、手術の計画を立てる際にも非常に参考になります。
特殊検査による詳細な評価
| 画像検査の種類 | 評価できる内容 |
| 単純X線検査 | 骨の位置関係、変形の有無 |
|---|---|
| CT検査 | 三次元的な骨の位置関係 |
| MRI検査 | 軟部組織の状態評価 |
| 関節造影検査 | 靭帯損傷の詳細な評価 |
関節造影検査は、月状骨周囲の靭帯損傷の程度を評価する際に実施する検査です。造影剤の漏出パターンを観察し、どの靭帯が損傷しているのかを特定できるため、より正確な病態の把握につながります。
関節鏡検査では直接的に関節内を観察でき、靭帯や軟骨の損傷状態を詳細に確認できます。検査によって得られた情報をもとに、治療方針を決定していきます。
神経学的検査の実施手順
- Tinel徴候:手根管部の叩打による正中神経領域のしびれの誘発
- Phalen test:手関節最大屈曲位での正中神経症状の出現
- 母指球筋力検査:母指の対立運動の筋力低下の有無
- 感覚検査:正中神経支配領域の知覚異常の確認
- 2点識別覚検査:感覚障害の程度の定量的評価
神経学的検査は、手根管症候群の合併の有無を確認するために実施する検査です。
経時的な評価の意義
初期評価で得られた所見は、その後の経過観察において基準値として使用できます。定期的に同様の検査を実施し、客観的な改善度を評価していくと、より質の高い医療を提供できます。
可動域や神経症状の変化は、予後を判断する上で特に貴重な情報源となる場合が多いため、継続的な評価が望ましいと考えられます。
手関節の状態を正確に把握するためには、これらの検査を組み合わせた総合的な判断が求められます。また、年齢や活動性、職業などの背景因子も考慮に入れながら、個々の状況に応じた評価が大切です。
月状骨脱臼の治療方法と治療薬、リハビリテーション、治療期間
月状骨脱臼(げつじょうこつだっきゅう)の治療においては、まず手関節の位置を本来あるべき場所に戻す整復術を行い、その後しっかりと固定する手技が基本です。
また治療過程では痛みを抑える薬を使用し、手首の機能を段階的に回復させるリハビリテーションを組み合わせて手関節の働きを元の状態に近づけるのが目標です。
初期治療と整復の意義
| 治療方法 | 選択基準 |
| 非観血的整復 | 受傷後早期・軽度損傷 |
|---|---|
| 観血的整復 | 陳旧例・重度損傷 |
手関節が本来の機能を取り戻すためには、できるだけ早い段階で脱臼した月状骨を正しい位置に戻す治療から始まります。
月状骨を正しい位置に戻す方法には、外から力を加えて整復する非観血的整復と、手術によって直接月状骨を整復する観血的整復といった二つの方法があり、担当する整形外科医が損傷の具合や症状が出てからどのくらい時間が経過しているかなどを総合的に判断して、どちらの方法を選択するかを決定していきます。
ただし、非手術的治療が最終的に管理される方法として選択されるケースはまれです。
非観血的整復を試みても月状骨が正しい位置に戻らないような状況では、手術室で全身麻酔をかけた上で、切開を加えて直接月状骨を見ながら整復を行う観血的整復術を実施します。この手術では、切れてしまった靭帯を修復したり、骨をつなぎ合わせたりする手技も同時に行う場合があります。
手術治療
急性期(8週間未満)の月状骨脱臼、月状骨周囲脱臼の管理は、一般に手術が適応となります。手術管理の目標は、整復の確認、靭帯の修復/再建、関連骨折の固定を可能にすることです。
手術は掌側、背側、または掌側と背側を組み合わせた方法と手根管開放術を組み合わせて行います。
手術治療が必要といった点では医師のなかで意見の一致が得られていますが、外科的治療は依然として論争が多いです。いくつかの研究で同等の治療成績が示されているため、アプローチの選択は外科医の好みに大きく左右されます。
慢性月状骨脱臼や見逃し損傷は、観血的整復および内固定術(ORIF)を試みるか、舟状骨切除および固定術、近位列切除、手関節全置換術などの救命処置で治療するときがあります。
薬物療法による疼痛制御
月状骨脱臼の治療初期には強い痛みを伴う人が多いため、非ステロイド性抗炎症薬を中心とした薬物療法を行っていきます。
これらの薬剤には、炎症を抑える効果と痛みを和らげる効果があり、手関節の腫れを軽減させながら痛みをコントロールできます。
痛みの強さや腫れの程度に応じて飲み薬や塗り薬を組み合わせながら処方していき、患部の状態が改善してくるに従って、徐々に薬の使用量を調整していくのが一般的です。
段階的なリハビリテーション戦略
- 関節可動域訓練
- 手関節筋力強化エクササイズ
- 把持動作トレーニング
- 日常生活動作練習
- スポーツ動作練習
手関節の固定期間が終わったら、理学療法士の指導のもとでリハビリテーションを開始していきます。
治療期間と経過観察
| 期間 | 実施内容 |
| 1-2週間 | 固定・消炎 |
|---|---|
| 2-4週間 | 可動域訓練 |
| 4-8週間 | 筋力訓練 |
| 8-12週間 | 応用動作 |
月状骨脱臼の治療には一定の時間がかかりますが、その期間は損傷の重症度によって大きく変わってきます。軽度な損傷であれば比較的早期に回復するケースもありますが、重度な損傷の場合は長期的な治療とリハビリテーションが必要となる場合があります。
治療は整形外科医を中心として、理学療法士やその他の医療スタッフがチームとなって患者さまの回復をサポートしていきます。
それぞれの専門家が連携を取りながら、患者さまの状態に合わせて治療内容を微調整し、最終的には手関節の機能を可能な限り回復させることを目指していきます。
初期段階
治療の初期段階である固定期間中には、定期的にX線検査を行って月状骨が正しい位置に保たれているかどうかを確認していきます。この時期の経過観察は特に入念に行う必要があります。
リハビリテーションの経過観察
リハビリテーションを進めていく際には、担当する医師や理学療法士が患部の状態を細かくチェックしながら、一つ一つの動作や訓練の強度を細かく調整していきます。
手首を使う動作は日常生活の中で非常に多く、かつ繊細な動きを必要とするため、焦らずじっくりと時間をかけてリハビリテーションを進めていくのが大切です。
治療の進行に合わせて、手関節の状態を定期的に診察し、必要に応じてリハビリテーションの内容を変更したり、投薬内容を調整したりしていきます。
また、X線検査やCT検査などの画像診断を行いながら、骨や関節の状態を詳しく確認していきます。
薬の副作用や治療のデメリット
月状骨脱臼(げつじょうこつだっきゅう)に対する手術的治療および保存的治療には、関節拘縮や骨萎縮、神経障害などの様々な副作用やデメリットが伴う可能性があり、慎重な経過観察が不可欠となります。
手術療法における合併症
- 外傷後関節炎:56%
- 関節可動域低下:68~80%
- 握力:健側の70%
- CRPS(複合性局所疼痛症候群):20%
手術的アプローチを選択した際には、術後の関節可動域制限が発生するケースがあります。これは手術による組織の修復過程で、関節周囲に癒着が生じることに起因するものと考えられます。
手術創部の治癒過程においては、創傷治癒遅延や感染のリスクも無視できません。高齢の方や糖尿病などの基礎疾患をお持ちの人は、創傷治癒に特に時間がかかりやすいです。
神経血管系への影響
手術操作に伴う神経損傷は、重要な合併症の一つとして認識されています。正中神経や橈骨神経などの主要な神経が手術部位の近傍を走行しているため、これらの神経に一時的な障害が生じる事例も報告されています。
手術による血管の圧迫や損傷により末梢循環不全を引き起こす場合があり、この状態が継続すると手指の腫脹や皮膚温の低下などの症状が出現するケースもあります。
骨・関節への長期的影響
- 関節症性変化の進行
- 手根骨の圧潰
- 骨密度の低下
- 関節可動域の永続的制限
- 手根管症候群の発症
- 腱組織の癒着
手術後の長期的な問題として、関節症性変化の進行や手根骨の圧潰などの合併症に注意が必要です。
固定期間中の筋力低下
| 固定による影響 | 回復までの期間 |
| 前腕筋力低下 | 2-3ヶ月 |
|---|---|
| 手指筋力低下 | 1-2ヶ月 |
| 関節拘縮 | 3-4ヶ月 |
| 握力低下 | 2-4ヶ月 |
ギプス固定や装具による保護は手術後の回復に必須ですが、長期の固定は一部の人で筋力低下を招きます。前腕部の筋力低下は特に顕著となりやすく、握力の低下にも影響を及ぼします。
保存療法における問題点
保存療法を選択した際には、完全な整復位が得られないと将来的に変形性関節症へ進展するリスクが存在します。また、長期の外固定による関節拘縮や筋委縮なども懸念されるところです。
保存療法では骨や軟部組織の修復過程において不安定性が残存するときがあり、これにより慢性的な疼痛や違和感が持続する可能性があります。このような状態が続くと、二次的な機能障害を引き起こす例も少なくありません。
リハビリテーション期間中の課題
術後のリハビリテーション期間中には、関節可動域の改善と筋力回復のバランスを取るのが大切です。過度な運動負荷は組織の修復を阻害する一方で、運動量が不足すると関節拘縮のリスクが高まります。
さらに、手関節周囲の腱組織に癒着が生じるとスムーズな手指の動きが阻害される人もいて、手指の巧緻運動に支障をきたすケースもあります。
手術後の経過観察においては、これらの副作用やデメリットに細心の注意を払いながら、それぞれの状態に応じた対応を行ってくのが重要です。
保険適用と治療費
以下に記載している治療費(医療費)は目安であり、実際の費用は症状や治療内容、保険適用否により大幅に上回ることがございます。当院では料金に関する以下説明の不備や相違について、一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。
月状骨脱臼(げつじょうこつだっきゅう)の治療には健康保険が適用され、3割負担の場合、手術を含む入院治療で概ね15万円から25万円程度の自己負担となります。
手術費用の内訳
| 手術費用項目 | 3割負担額 |
| 観血的整復術 | 6-8万円 |
|---|---|
| 靭帯修復術 | 7-9万円 |
| 関節固定術 | 8-10万円 |
| 骨接合術 | 7-9万円 |
手術費用は術式により異なりますが、健康保険が適用されるため、患者様の負担は抑えられています。手術室使用料や麻酔料なども保険適用の対象です。
入院時の費用
- 入院基本料
- 食事療養費
- 術前検査費用
- 投薬料
- リハビリテーション料
- 病衣料
入院期間中に必要となる主な費用項目には、投薬量や病衣料なども含まれます。
外来診療における費用
| 外来診療項目 | 3割負担額 |
| X線撮影 | 1500-2000円 |
|---|---|
| MRI検査 | 5000-7000円 |
| CT検査 | 4000-6000円 |
| 装具作成 | 3000-5000円 |
費用はあくまでも目安であり、詳しい治療内容や治療費については各医療機関にお問い合わせください。
以上
参考文献
Israel D, Delclaux S, André A, Aprédoaei C, Rongières M, Bonnevialle P, Mansat P. Peri-lunate dislocation and fracture-dislocation of the wrist: Retrospective evaluation of 65 cases. Orthopaedics & Traumatology: Surgery & Research. 2016 May 1;102(3):351-5.
Garner M, Rudran B, Khan A, Tang Q, Mathew P. Lunate dislocations: anatomy, diagnosis and management. British Journal of Hospital Medicine. 2021 Jul 2;82(7):1-0.
ADKISON J. Treatment of acute lunate and perilunate dislocations. Clinical Orthopaedics and Related Research (1976-2007). 1982 Apr 1;164:199-207.
Goodman AD, Harris AP, Gil JA, Park J, Raducha J, Got CJ. Evaluation, management, and outcomes of lunate and perilunate dislocations. Orthopedics. 2019 Jan 1;42(1):e1-6.
Pai SN, Kumar MM. Isolated lunate dislocation. BMJ Case Reports. 2022;15(3).
Campbell RD, Lance EM, Yeoh CB. Lunate and perilunar dislocations. The Journal of Bone & Joint Surgery British Volume. 1964 Feb 1;46(1):55-72.
Scalcione LR, Gimber LH, Ho AM, Johnston SS, Sheppard JE, Taljanovic MS. Spectrum of carpal dislocations and fracture-dislocations: imaging and management. American Journal of Roentgenology. 2014 Sep;203(3):541-50.
Trumble T, Verheyden J. Treatment of isolated perilunate and lunate dislocations with combined dorsal and volar approach and intraosseous cerclage wire. The Journal of hand surgery. 2004 May 1;29(3):412-7.
Stanbury SJ, Elfar JC. Perilunate dislocation and perilunate fracture-dislocation. JAAOS-Journal of the American Academy of Orthopaedic Surgeons. 2011 Sep 1;19(9):554-62.
Tucker A, Marley W, Ruiz A. Radiological signs of a true lunate dislocation. Case Reports. 2013 Apr 23;2013:bcr2013009446.