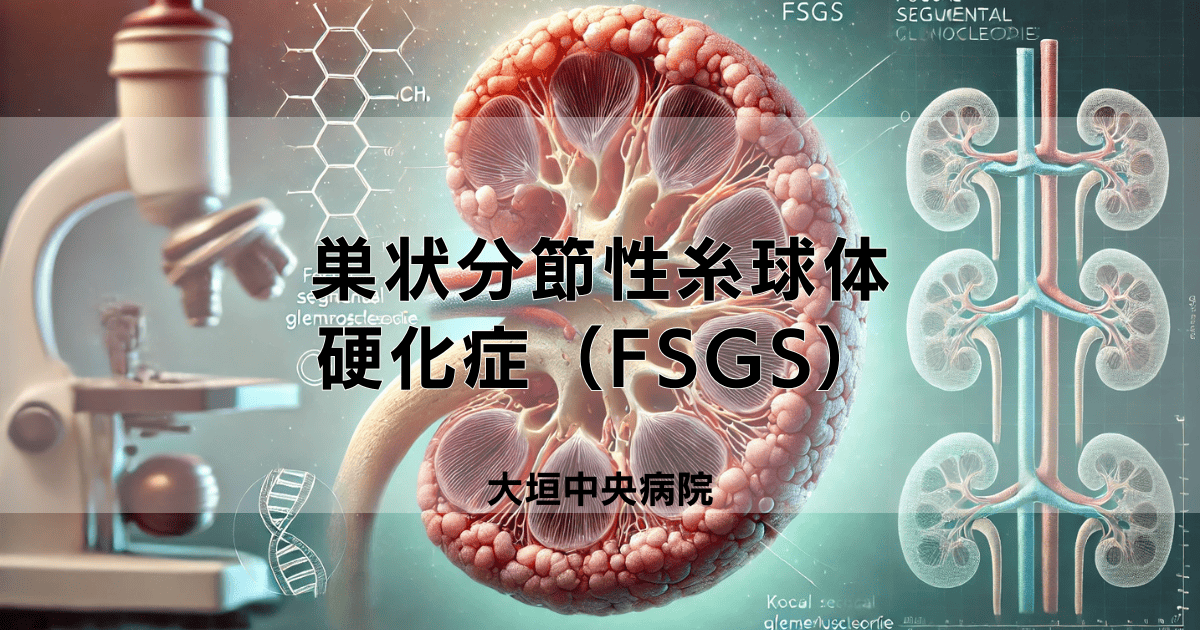巣状分節性糸球体硬化症(FSGS)とは、糸球体の一部(巣状)かつ部分的(分節性)に硬化や損傷が生じる腎疾患で、たんぱく尿や腎機能の低下などを起こします。
さまざまな原因から生じる一次性、または高血圧や肥満、ウイルス感染などが関与する二次性に分類されます。
初期において特有の自覚症状が乏しいため受診が遅れやすく、慢性腎不全へ移行したり、ネフローゼ症候群を発症したりして日常生活に大きく影響を及ぼすリスクがあることから、早期発見と治療が大切です。
病型
糸球体は腎臓内に無数に存在し、血液をろ過して老廃物や不要な水分を尿へと排出する重要な単位として機能しますが、FSGSでは、糸球体が部分的に硬化し機能が損なわれることで腎臓全体のろ過能力が低下し、たんぱく尿や腎機能障害へとつながります。
一次性FSGSと二次性FSGS
FSGSは一次性・二次性の大きな分け方が知られ、原因がはっきりせず自己免疫や遺伝子変異などが関与すると推測されるものを一次性、または原発性FSGSと呼びます。
一方、高血圧や肥満、ウイルス感染症など別の疾患や要因が存在していて、結果としてFSGSが生じたものは二次性FSGSです。
- 一次性FSGS:自己免疫的背景や遺伝子異常が示唆されるが、詳細なメカニズムは個々の患者で異なる
- 二次性FSGS:慢性的な高血圧や肥満、HIV感染などがきっかけとなり腎臓に負担がかかり、糸球体の一部が硬化する
一次性と二次性FSGS
| 分類 | 原因・背景 | 治療方針 |
|---|---|---|
| 一次性(原発性) | 自己免疫反応、遺伝子変異など不明要因 | 免疫抑制療法、ステロイドなどを主に |
| 二次性 | 高血圧・肥満・ウイルス感染(HIVなど)など | 原因疾患の管理を含めた総合的治療 |
病理像による分類
FSGSという呼称は、「巣状・分節性・糸球体・硬化」という病理的特徴を示します。
病理検査によって、糸球体全体ではなくいくつかの糸球体やその部分だけが選択的に硬化病変を起こしていることが確認されるため、特徴的な形態からFSGSと呼ばれるのです。
- 「巣状」とは、すべての糸球体ではなく、一部の糸球体だけに変性・硬化が見られること
- 「分節性」とは、1つの糸球体の中でも一部の領域だけが硬化すること
病態の多様性
同じFSGSといえども、患者さんによって症状の強さや進行度合いは異なり、ネフローゼ症候群のように大量のたんぱく尿が出るケースもあれば、比較的軽度で長期間症状が緩やかに進むケースもあります。
初期から腎機能低下の進行が速いタイプも存在し、治療方針を判断する上で、病理組織の解析や原因究明が重要です。
病態の多様性を示す例
- 一部の患者はネフローゼ症候群を急激に発症し、大量たんぱく尿や浮腫が目立つ
- 少量のたんぱく尿だけで軽度腎機能低下が続き、数年後に進行する例
- 二次性FSGSでは原因疾患(例:肥満、高血圧)をコントロールすると進行が止まる例
疾患ステージと腎不全リスク
FSGSが進むにつれて糸球体の硬化範囲が広がり、正常な糸球体の数が減少すれば腎不全に至るリスクが高まり、末期腎不全に移行した場合には人工透析や腎移植の検討が必要になる場合があるため、定期的な腎機能評価が欠かせません。
- ステージの概念:GFR(糸球体ろ過率)がどの程度保たれているかで重症度を判断
- 早期介入で腎不全リスクを抑え、透析回避の可能性を高める
巣状分節性糸球体硬化症(FSGS)の症状
FSGSは腎臓のろ過機能が障害されることで、さまざまな症状が現れますが、初期にはほとんど症状がなく、健康診断の尿検査でたんぱく尿を指摘されることで初めて気づくケースも少なくありません。
たんぱく尿
糸球体が硬化し機能が低下すると、血液中のたんぱく質が尿中に漏れ出すようになり、これが「たんぱく尿」で、FSGSの主な兆候の1つです。
尿が泡立ちやすくなる、あるいは健康診断の尿検査で「+」以上が出るといった形で発覚します。
- 定量的にみると、1日当たり0.5g~3.5g程度のたんぱく尿が出ることもある
- ネフローゼ症候群レベル(1日3.5g以上)まで達する例もあり、浮腫や低アルブミン血症を伴うことがある
浮腫(むくみ)
たんぱく質が尿から失われ、血中のアルブミンが低下すると、体内に水分が保持できず浮腫が生じやすくなり、下肢のむくみだけでなく、眼の周りや顔などに症状が出て、特に朝起床時のまぶたの腫れや、夕方になると足首周辺がひどくむくみます。
浮腫の主な特徴
| 部位 | 症状の例 |
|---|---|
| 下肢(足首やすね) | むくみで靴がきつくなる |
| 眼瞼(まぶた) | 朝起きた時に特にわかりやすい腫れ |
| 全身 | 進行すると腹水や胸水の貯留を伴う場合も |
血尿・高血圧
FSGSでは血尿がみられる場合もありますが、軽度な顕微鏡的血尿にとどまり、肉眼的には確認しにくいことが多く、また、腎臓の機能障害が進むと、体内の水分バランスやナトリウム排泄が乱れ、高血圧が生じやすくなります。
高血圧がさらに腎障害を悪化させる悪循環を引き起こすことも少なくありません。
高血圧に関連した症状
- 頭痛や肩こり、めまい
- 動悸や息切れが起こりやすい
- 収縮期血圧が140mmHg以上になるなど血圧が上がる
腎機能低下に伴う全身症状
FSGSが進行してGFRが低下すると、慢性腎臓病(CKD)のステージが進み、尿毒症状のような倦怠感や食欲不振が現れる場合があります。
最終的には透析が必要となるリスクもあるため、疲れやすい、集中力の低下などを自覚したら早期に医療機関で検査を受けることが大切です。
- 尿毒素が溜まると吐き気やだるさが強まる
- 皮膚のかゆみや口臭などが生じるケースも
- 末期には体内の毒素を排泄できなくなり、透析や腎移植が検討される段階に進む
巣状分節性糸球体硬化症(FSGS)の原因
FSGSの原因は、多岐にわたり一次性(原発性)・二次性(続発性)に大別され、一次性FSGSは詳細なメカニズムが完全には解明されていない部分がありますが、遺伝子変異や自己免疫的な要因が示唆されています。
一方、二次性FSGSでは、高血圧や肥満、ウイルス感染など明確な別疾患が引き金となって腎臓を傷害するケースが多いです。
一次性FSGS(原発性)
一次性FSGSは、特定の自己免疫や血中の未解明タンパク質による糸球体上皮細胞への障害、遺伝子変異による糸球体の構造欠陥などを原因として発症します。
- 遺伝的要因:一部の患者でポドシンやネフリンなどの遺伝子異常が確認される
- 血中因子:スリット膜を障害する不明因子が存在するという報告もあり、移植腎でも再発する場合がある
- 免疫調節の異常:ステロイドなど免疫抑制薬で改善することがあるため、自己免疫の関与が示唆される
一次性FSGSの主な原因仮説
| 要因 | 仮説・説明 |
|---|---|
| 遺伝子変異 | ポドシン、アルファアクトニン4などの変異 |
| 不明蛋白質(循環因子) | 血液中に存在しポドサイトを障害する因子 |
| 自己免疫学的異常 | リンパ球やサイトカインが糸球体を攻撃する可能性 |
二次性FSGS(続発性)
高血圧や肥満といった生活習慣病、またはHIV感染などのウイルス感染が腎臓への負担を増やし、糸球体が局所的に硬化していくタイプを二次性FSGSと呼びます。
- 高血圧:持続的に腎血管へ高い圧力がかかり、糸球体の微小な損傷が蓄積
- 肥満:体重過多で腎血漿流量やろ過量が増大し、糸球体が過負荷状態になる
- ウイルス感染(HIV、パルボウイルスB19など):直接腎組織を障害したり免疫変調を引き起こしたりする
- 合併疾患(鎌状赤血球症、ドラッグの使用など)でも二次性FSGSが生じる場合がある
二次性FSGSの代表的な要因
- 慢性高血圧下での糸球体過負荷
- 重度肥満(BMI30以上)に伴う腎代謝ストレス
- HIV関連腎症(HIVAN)などの感染症による腎障害
- 一部の薬物(ヘロイン、インターフェロンなど)が腎機能に影響を及ぼす
メカニズムの共通点
一次性・二次性を問わず、糸球体のポドサイト(上皮細胞)や基底膜に負担がかかることでスリット膜が壊れ、たんぱく質が漏れ出すというメカニズムが共通していて、ポドサイト障害が最終的に瘢痕化や硬化を招き、FSGSとして確認されます。
検査・チェック方法
FSGSは症状が出にくいことが多く、検査によってはじめて発見されるケースがあり、ここでは、主に臨床で行われる検査やチェック方法を通じてFSGSを正確に診断するプロセスを解説します。
尿検査(たんぱく尿、尿沈渣)
FSGSはたんぱく尿が主徴であり、尿検査によって定性および定量的な評価を行います。
- 尿定性検査:早朝尿などでたんぱく+以上が持続すれば詳細検査へ
- 24時間尿たんぱく量:1日当たり0.5g以上だと腎障害を疑う
- 尿沈渣:赤血球円柱がみられるケースもある
尿検査で得られる主な情報
| 検査項目 | 意味 |
|---|---|
| 尿定性(リボテストなど) | +以上の場合、腎疾患を追加チェック |
| 24時間尿たんぱく量 | タンパク漏出の総量を評価し、ネフローゼかどうかを判断 |
血液検査(腎機能、電解質、免疫学的検査)
FSGSの診断には、腎機能(クレアチニン、推算GFR)、電解質(Na、Kなど)のバランス、自己抗体や補体価の検査なども重要です。
他に考えられる糸球体疾患との鑑別や二次性の要因(HIV感染など)を確認するための検査も行われます。
- クレアチニンやBUNの上昇度合いから腎機能低下の程度を把握
- 免疫学的検査(ANA、ANCAなど)で他の自己免疫疾患を除外
- 感染症スクリーニング(HIV、HBVなど)で二次性FSGSを検索
FSGS診断に関わる血液検査項目
- 血清クレアチニン(sCr)
- eGFR(推算糸球体ろ過量)
- 総蛋白・アルブミン
- HIV抗体、B型肝炎ウイルスマーカーなど
画像検査(超音波、CT、MRI)
腎臓の大きさや形態、他の腎疾患を併発していないかをチェックする目的で、超音波検査やCT、MRIなどが行われることがあり、二次性FSGSを疑う場合には、腎血流の状態や腎臓周囲の構造変化を評価することが有用です。
- 超音波検査で腎臓のサイズを把握し、萎縮や腫瘍の有無を確認
- CTやMRIで内部構造をより詳細に可視化
画像検査で把握可能な情報
| 検査法 | 主な目的 |
|---|---|
| 腹部超音波 | 腎の大きさ・表面状態、腎結石・腫瘍の有無を確認 |
| CT/MRI | 腎の構造・血流・周囲臓器との関係を詳細に評価 |
腎生検による確定診断
FSGSを確定診断するうえで最も重要なのは腎生検です。
腎生検では、局所麻酔下で専用の針を使い腎臓の組織を少量採取し、光学顕微鏡や免疫染色を用いて糸球体の構造変化や硬化病変の有無、広がりなどを直接確認します。
- 巣状・分節性の硬化があるかどうかが確認できる
- 病理診断でFSGSの病型や活動性、瘢痕化程度を把握して治療方針を決める
腎生検のメリット
- 病因や活動性を直接判定でき、ステロイド治療などの方針が明確になる
- 他の類似糸球体疾患(膜性腎症や微小変化型ネフローゼなど)との鑑別が可能
巣状分節性糸球体硬化症(FSGS)の治療方法と治療薬について
FSGSの治療は、原因や病型、進行度に応じてさまざまなアプローチが取られ、一次性FSGSの多くはステロイド療法を中心とした免疫抑制治療が主体となり、二次性FSGSでは原因疾患のコントロールや生活習慣改善が並行して行われます。
ステロイド治療
一次性FSGSに対して最も一般的に用いられるのがステロイド(プレドニゾロンなど)による免疫抑制療法で、糸球体上皮細胞の障害を抑え、炎症や免疫反応を抑える効果が期待されます。
- 高用量ステロイドを一定期間投与し、改善があれば漸減していく
- ステロイド抵抗性の症例もあり、反応が悪い場合はほかの免疫抑制剤を検討
ステロイド治療の概要
| 投与計画 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 初期高用量 | 炎症を迅速に抑え、たんぱく尿減少を狙う | 副作用(満月様顔貌、糖尿病悪化など) |
| 漸減・維持療法 | 再発を防ぐ、長期管理 | 長期使用で骨粗鬆症リスクなどが上昇 |
免疫抑制剤の併用
ステロイドだけでは効果が不十分、または副作用が強い場合、シクロスポリンやタクロリムス、ミコフェノール酸モフェチルなどの免疫抑制剤を併用することがあり、T細胞やB細胞など免疫系を調整し、糸球体の障害を抑制する狙いがあります。
免疫抑制剤の例
- シクロスポリン:カルシニューリン阻害薬でステロイド抵抗性FSGSに用いられる
- タクロリムス:同様にカルシニューリンを阻害し、免疫を抑える
- ミコフェノール酸モフェチル:リンパ球の増殖を抑える作用があり、補助的に使用される
二次性FSGSの治療(原因疾患のコントロール)
高血圧や肥満が原因となっているケースでは、原因をコントロールすることが治療の柱となります。
高血圧に対してはACE阻害薬やARBなどを用い、腎保護作用を期待しながら血圧を適正に保ち、肥満が関与する場合には体重コントロールや生活習慣の改善が欠かせません。
- HIV感染によるFSGSでは、抗レトロウイルス療法によってウイルス量を抑える
- 糖尿病が背景にある場合は血糖コントロールを徹底する
二次性FSGSへの対応
- 高血圧管理:ACE阻害薬、ARBを使い、腎保護と血圧コントロールを両立
- 体重管理:有酸素運動や食事療法でBMIを下げ、腎負荷を減らす
- 感染症管理:HIVなどの抗ウイルス療法を適切に行う
血漿交換療法・LDLアフェレーシス
ステロイド抵抗性や難治性のFSGSに対し、血漿交換やLDLアフェレーシスが行われる場合もあり、血液中の自己抗体や有害物質を除去し、糸球体への障害因子を減らす狙いがあります。
ただし、適応や効果は症例によって異なり、専門施設での判断が必要です。
血漿交換・LDLアフェレーシスの概要
| 手法 | 作用 | 適応 |
|---|---|---|
| 血漿交換療法 | 血漿を機械的に置換し、自己抗体や炎症メディエーターを除去 | ステロイド抵抗性など特殊例 |
| LDLアフェレーシス | LDLコレステロールや炎症性物質を吸着除去 | 難治性ネフローゼなどで検討 |
巣状分節性糸球体硬化症(FSGS)の治療期間
FSGSの治療期間は、一次性(原発性)か二次性(続発性)か、そして病状の進み具合やステロイドなどに対する反応性によって大きく異なります。
ステロイド治療のスケジュール
一次性FSGSに対しては、まずステロイド高用量療法を一定期間行い、効果が認められれば徐々に用量を減らしていくことが一般的です。
- 初期治療:1~3か月程度、高用量ステロイドを毎日投与(体重1kgあたり0.5~1.0mgなど)
- 維持療法:症状・検査値を見ながら数か月~1年程度、用量を減らし再燃を防ぐ
- 再発・抵抗例:免疫抑制剤併用や血漿交換などを検討
ステロイド治療の流れ
| 期間 | 内容 |
|---|---|
| 初期(約1~3か月) | 高用量ステロイドでたんぱく尿の寛解を目指す |
| 中期(約3~6か月) | 徐々に減量し、再燃がないかを確認する |
| 維持(1年程度) | 低用量維持または徐々に中止を検討 |
二次性FSGSの管理期間
二次性FSGSの場合は、原因疾患をコントロールする限り腎機能低下の進行を抑えられる可能性があるので、高血圧や肥満を改善するための生活習慣管理、抗ウイルス療法などを長期にわたって継続する必要があります。
- 高血圧の管理:生涯にわたり血圧コントロールが不可欠
- 肥満関連:体重管理とリバウンド対策が重要
- HIV感染:抗レトロウイルス療法を継続しながら腎機能を定期的にチェック
二次性FSGS管理期間
- 急激に改善することは少なく、半年~1年以上かけて緩やかに腎機能が安定
- 生活習慣の改善を怠ると再び糸球体への負担がかかり再発リスク上昇
- 原因疾患がコントロール不能な場合、透析や移植を視野に入れる場合も
難治性や再発例
FSGSは再発やステロイド抵抗性が比較的多い疾患の1つとされ、寛解と再燃を繰り返しながら長期にわたり治療を続ける例があります。
- ステロイドや免疫抑制剤を中止した後にたんぱく尿が再び増加
- 腎移植後に移植腎でFSGSが再発する場合がある
難治性FSGSの治療経過
| 状況 | 治療ステップ |
|---|---|
| ステロイド抵抗性 | カルシニューリン阻害薬(シクロスポリンなど)を追加 |
| 再燃の反復 | 再度ステロイド増量+他の免疫抑制剤との併用検討 |
| 腎不全進行 | 透析導入、腎移植、血漿交換などの選択を検討 |
治療終了・寛解の判断
一次性FSGSのうち、ステロイドや免疫抑制療法で寛解に至り、半年以上たんぱく尿が出現しない状態が続けば、治療を中止または維持量を低く抑える選択肢が出てきますが、経過観察で再びたんぱく尿が増えたり血清アルブミンが低下すれば早めに受診し、再度治療を検討します。
- 寛解が続いている間も年に数回の血液・尿検査は推奨
- 完全寛解後5年以上経過すれば再発リスクは低めと考えられる
巣状分節性糸球体硬化症(FSGS)薬の副作用や治療のデメリットについて
FSGSの治療薬は多くが免疫抑制作用を持つため、さまざまな副作用リスクが伴います。
ステロイドの副作用
ステロイド(プレドニゾロンなど)はFSGS治療の主軸になりやすい一方で、副作用も多岐にわたります。
- 満月様顔貌(ムーンフェイス)、体重増加
- 糖尿病の悪化や新規発症
- 骨粗鬆症
- 易感染性
ステロイドの主な副作用と対策
| 副作用 | 対策 |
|---|---|
| 骨粗鬆症 | カルシウムやビタミンD摂取、運動 |
| 高血糖 | 血糖管理、栄養士の指導 |
| 感染症リスク | マスク着用、うがい手洗い徹底 |
| 精神症状 | ストレスマネジメント、カウンセリング活用 |
免疫抑制剤(シクロスポリン、タクロリムスなど)の副作用
カルシニューリン阻害薬であるシクロスポリンやタクロリムスは、ステロイド抵抗性FSGSや再発例などで併用されることが多いですが、腎障害や高血圧、神経毒性などの副作用には注意が必要です。
- シクロスポリン:歯肉増殖、毛髪多毛なども報告
- タクロリムス:血糖値が上がりやすい、手指振戦など神経症状がみられる
免疫抑制剤の特有副作用
- カルシニューリン阻害薬誘発性腎障害:投与量や血中濃度の管理が必要
- 体毛の増加(シクロスポリン)、手指振戦(タクロリムス)
- 感染症リスク上昇
長期治療のストレスとQOL
FSGSの治療は長期に及ぶ場合が多く、定期的な通院や検査、食事管理などがストレスになる可能性があり、また、ステロイドによる体型変化や感染症リスクへの不安など、患者の日常生活や生活の質に大きな影響を及ぼすことがあります。
- 外見的な変化(ムーンフェイス、体重増加)を気にする心理的負担
- 職場や家庭で治療スケジュールを優先せざるを得ない負担
- 副作用や再燃リスクへの常時不安感
巣状分節性糸球体硬化症(FSGS)の保険適用と治療費
以下に記載している治療費(医療費)は目安であり、実際の費用は症状や治療内容、保険適用否により大幅に上回ることがございます。当院では料金に関する以下説明の不備や相違について、一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。
腎生検や検査の費用
腎生検は入院または短期入院で行われることが多く、検体の病理検査も合わせて、数万円台の費用になるケースが一般的です。
- 1~2泊の入院費(部屋代など)
- 病理検査のコスト
- 血液検査や尿検査など追加の検査費用
腎生検入院時の費用
| 項目 | 自己負担目安(円) |
|---|---|
| 入院費(1~2泊) | 10,000~20,000程度 |
| 病理検査 | 10,000程度 |
| その他検査(血液検査など) | 数千円~1万円程度 |
薬物療法の費用
治療には、ステロイドや免疫抑制剤などを使用します。
- ステロイド:月1,000~2,000円程度の自己負担
- シクロスポリンなど免疫抑制剤:月3,000~8,000円程度の自己負担
- 高血圧治療薬や利尿薬などを併用する場合、その分が追加
外来通院と検査費用
FSGSでは定期的に血液検査や尿検査、時には超音波検査などを行い、腎機能とたんぱく尿の変化をモニタリングします。
- 血液検査(腎機能、免疫学的指標、薬物血中濃度測定など)
- 尿検査(定量たんぱく検査)
外来通院時の費用目安
| 内容 | 自己負担目安(円) |
|---|---|
| 血液検査+尿検査 | 2,000~3,000 |
| 追加免疫検査(抗体価など) | 1,000~2,000 |
| 超音波検査 | 1,000~2,000 |
以上
参考文献
Rosenberg AZ, Kopp JB. Focal segmental glomerulosclerosis. Clinical Journal of the American Society of Nephrology. 2017 Mar 1;12(3):502-17.
D’Agati VD, Kaskel FJ, Falk RJ. Focal segmental glomerulosclerosis. New England Journal of Medicine. 2011 Dec 22;365(25):2398-411.
Fogo AB. Causes and pathogenesis of focal segmental glomerulosclerosis. Nature Reviews Nephrology. 2015 Feb;11(2):76-87.
Korbet SM. Primary focal segmental glomerulosclerosis. Journal of the American Society of Nephrology. 1998 Jul 1;9(7):1333-40.
D’Agati V. Pathologic classification of focal segmental glomerulosclerosis. InSeminars in nephrology 2003 Mar 1 (Vol. 23, No. 2, pp. 117-134). WB Saunders.
Shabaka A, Tato Ribera A, Fernández-Juárez G. Focal segmental glomerulosclerosis: state-of-the-art and clinical perspective. Nephron. 2020 Jul 28;144(9):413-27.
D D’Agati V, Fogo AB, Bruijn JA, Jennette JC. Pathologic classification of focal segmental glomerulosclerosis: a working proposal. American journal of kidney diseases. 2004 Feb 1;43(2):368-82.
Kitiyakara C, Kopp JB, Eggers P. Trends in the epidemiology of focal segmental glomerulosclerosis. InSeminars in nephrology 2003 Mar 1 (Vol. 23, No. 2, pp. 172-182). WB Saunders.
Jefferson JA, Shankland SJ. The pathogenesis of focal segmental glomerulosclerosis. Advances in chronic kidney disease. 2014 Sep 1;21(5):408-16.
Korbet SM. Treatment of primary focal segmental glomerulosclerosis. Kidney international. 2002 Dec 1;62(6):2301-10.