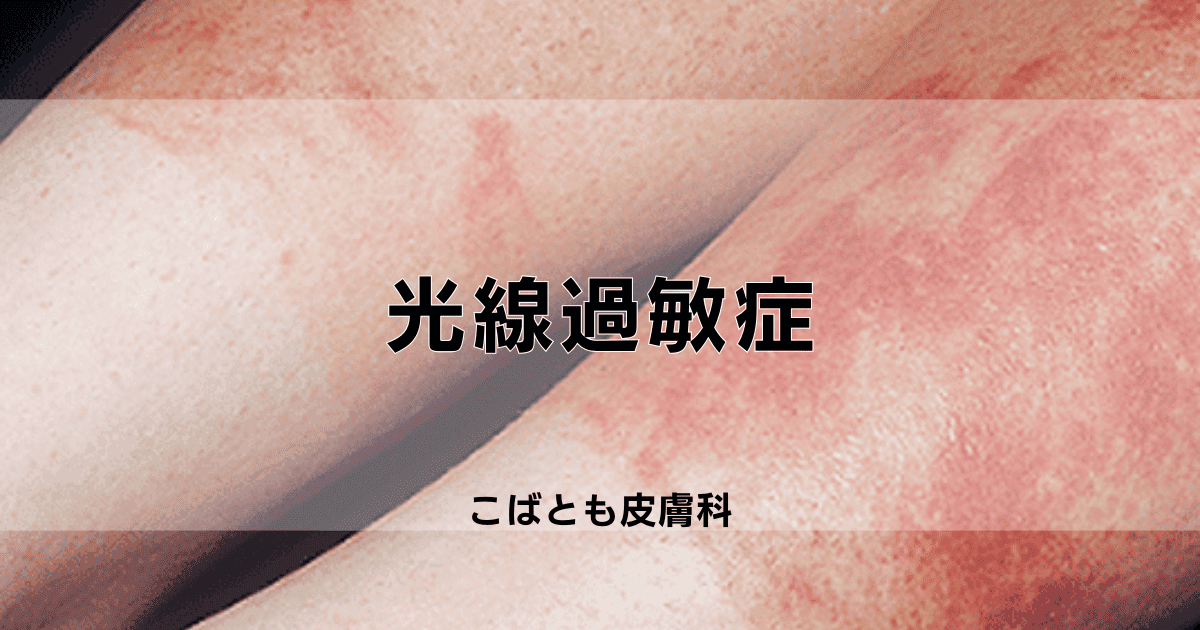光線過敏症(photosensitivity)とは、紫外線などの光線に対して皮膚が通常以上の強い反応を示し、発赤や腫れ、水疱、かゆみなどの症状を起こす皮膚疾患です。
この疾患は、直射日光への暴露だけでなく、日焼け止めや化粧品に含まれる特定の成分との相互作用によっても発症する可能性があり、症状の重症度は個人差があります。
遺伝的素因や自己免疫疾患との関連が指摘されているほか、特定の薬剤の服用が光線過敏症を誘発することもあり、近年では室内照明のLEDや電子機器の画面から放出される青色光による症状の報告も増加しています。
この記事の執筆者

小林 智子(こばやし ともこ)
日本皮膚科学会認定皮膚科専門医・医学博士
こばとも皮膚科院長
2010年に日本医科大学卒業後、名古屋大学医学部皮膚科入局。同大学大学院博士課程修了後、アメリカノースウェスタン大学にて、ポストマスターフェローとして臨床研究に従事。帰国後、同志社大学生命医科学部アンチエイジングリサーチセンターにて、糖化と肌について研究を行う。専門は一般皮膚科、アレルギー、抗加齢、美容皮膚科。雑誌を中心にメディアにも多数出演。著書に『皮膚科医が実践している 極上肌のつくり方』(彩図社)など。
こばとも皮膚科関連医療機関
光線過敏症の症状
光線過敏症は、太陽光線に過剰に反応して発症する皮膚障害で、主な症状として日光に当たった部位に発赤、かゆみ、水疱などの皮膚炎症が現れます。
光線過敏症の主要な皮膚症状
光線過敏症の皮膚症状は、日光への暴露から数時間以内に発現することが多く、症状の強さは紫外線の強度や暴露時間によって大きく変化し、夏季の強い日差しの下では、わずか数分の暴露でも激しい皮膚反応が生じます。
日光に当たった皮膚表面では、まず軽度の熱感とチクチクした痛みを感じ始め、その後徐々に発赤や腫れが進行していき、初期症状は通常の日焼けよりも早期に現れ、より強い炎症反応を伴うことが特徴的です。
皮膚の表面に現れる症状は、一般的な日焼けとは異なり、短時間の日光暴露でも激しい反応を示すことがあり、顔面や手背などの露出部位では、鮮やかな紅斑や小水疱の形成が見られます。
| 症状の種類 | 特徴的な皮膚の変化 | 発現までの時間 |
|---|---|---|
| 即時型反応 | 発赤、熱感、痛み | 数分~数時間 |
| 遅延型反応 | 水疱、丘疹、痒み | 24~48時間後 |
皮膚表面に現れる発疹は日焼けよりも鮮やかな赤色を呈し、境界がはっきりとした不規則な形状となり、さらに症状が進行すると、皮膚の表面が粗造になったり、小さな水疱が多発したりすることもあります。
全身に及ぶ症状と随伴症状
光線過敏症が進行すると、皮膚症状だけでなく、全身にさまざまな影響を及ぼすことがあり、重症例では、強い倦怠感や関節痛、発熱などの全身症状が現れることもあります。
また、日光暴露後、数時間から数日かけて、頭痛や倦怠感、微熱などの全身症状が生じることがあり、症状は日光暴露を避けることで徐々に改善していきますが、完全な回復までには一定の時間が必要です。
全身性の症状
- 疲労感や脱力感
- 微熱(37.5度前後)
- 関節の痛みや筋肉痛
- 消化器症状(吐き気など)
重度の場合には、皮膚症状が顔面全体に広がり、まぶたの腫れや口唇の腫脹など、顔貌の変化をもたらすことがあります。
症状の部位による特徴
露出部位である顔面、首、手背などでは、症状がより顕著に現れ、皮膚の状態が著しく変化し、日常的に日光に曝される部位では、慢性的な炎症反応により、皮膚の肥厚や色素沈着などの二次的な変化が生じることもあります。
| 発症部位 | 主な症状 | 特徴的な性質 |
|---|---|---|
| 顔面 | 紅斑、腫脹 | 対称性の発赤 |
| 手背 | 水疱、痒み | 持続性の炎症 |
| 首筋 | 色素沈着 | 境界明瞭 |
衣服で覆われていない部分に症状が集中し、衣服との境界線がはっきりと確認できることも、本症の診断における参考になり、この特徴的な症状分布は、日光暴露との関連を強く示唆する重要な所見です。
季節や時間帯による症状の変化
紫外線の強度が増す春から夏にかけては症状が増悪しやすく、日中の10時から14時の間は注意が必要で、この時間帯は紫外線の強度が最も強くなるため、短時間の暴露でも激しい症状が誘発されます。
季節による症状の変化
- 春~夏 症状が顕著
- 秋~冬 症状が軽減
- 曇天時 症状が緩和
- 晴天時 症状が悪化
室内にいても窓ガラスを通して入ってくる紫外線により、軽度の症状が引き起こされることもあり、UVAは窓ガラスを透過しやすいため、室内であっても窓際での長時間の作業には注意が必要です。
光線過敏症の症状は、一度発症すると数日から数週間持続し、その間は日光暴露を避けることで症状の悪化を防ぐことができ、特に急性期には完全に遮光することが症状の改善につながります。
皮膚症状は、通常、数時間から数日で徐々に改善していきますが、繰り返しの日光暴露により症状が遷延化することもあり、慢性的な経過をたどる場合には、長期的な紫外線対策が重要です。
光線過敏症の原因
光線過敏症は、遺伝的要因や薬剤の影響、自己免疫疾患など、様々な要因が複雑に絡み合って起こります。
光線過敏症の基本的なメカニズム
紫外線による光線過敏症の発症には、体内の光感作物質が重要な役割を果たしており、この物質が紫外線のエネルギーを吸収することで活性酸素が発生し、周囲の組織に炎症反応を起こすことが分かっています。
また、光感作物質の生成には、遺伝的な要因だけでなく、環境因子や生活習慣が深く関与していることが明らかになってきました。
特に注目すべきは、一部の医薬品や化粧品に含まれる成分が光感作物質として作用する可能性があることです。
| 光感作物質のタイプ | 主な発生源 | リスク要因 |
|---|---|---|
| 内因性物質 | 体内で生成 | 遺伝的素因 |
| 外因性物質 | 医薬品・化粧品 | 環境要因 |
| 複合型 | 両方の組み合わせ | 複合的要因 |
遺伝的要因による光線過敏症
遺伝的な光線過敏症は、DNA修復機能に関与する遺伝子の変異によって起こされることが多く、紫外線によって損傷を受けたDNAの修復が適切に行われないために症状が現れます。
関連のある遺伝性疾患として、色素性乾皮症やコケイン症候群などが挙げられ、生まれつき紫外線に対する感受性が著しく高いです。
- 色素性乾皮症関連遺伝子
- DNA修復遺伝子群
- 光感受性調節遺伝子
- メラニン産生関連遺伝子
- 免疫応答遺伝子
薬剤性光線過敏症のメカニズム
薬剤性光線過敏症は、服用している薬剤自体が光感作物質として作用するケースと、薬剤が体内で代謝される過程で光感作物質に変化するケースの大きく二つのパターンに分類できます。
抗生物質や降圧薬、非ステロイド性抗炎症薬などの一般的な医薬品でも、光線過敏症を起こすことが分かっています。
| 薬剤分類 | 代表的な成分 | 光線過敏性リスク |
|---|---|---|
| 抗生物質 | テトラサイクリン系 | 中~高 |
| 降圧薬 | カルシウム拮抗薬 | 中程度 |
| 抗炎症薬 | ケトプロフェン | 高 |
| 利尿薬 | サイアザイド系 | 低~中 |
環境因子と光線過敏症
環境要因による光線過敏症の発症には、大気汚染物質や化学物質への曝露が深く関与しており、工業地域や都市部での発症リスクが高く、また、地球温暖化による紫外線量の増加や、オゾン層の破壊による有害紫外線の増加なども、光線過敏症の発症リスクを高める要因です。
- 大気汚染物質
- 化学物質
- 紫外線量の変化
- オゾン層の状態
- 気候変動の影響
都市部における光化学スモッグの発生は、大気中の光感作物質の濃度を上昇させ、光線過敏症の発症リスクを著しく高めることが最新の研究で明らかになってきました。
室内環境においても、LED照明やデジタルデバイスから放出される青色光が、特定の光線過敏症の症状を誘発する可能性があることが報告されており、現代の生活様式そのものが新たなリスク要因となっていることが分かってきています。
光線過敏症の検査・チェック方法
光線過敏症の診断には、詳細な問診と視診による臨床診断に加え、光パッチテストや光誘発試験などの特殊検査による確定診断が必要です。
初診時の問診と視診による臨床診断
問診では患者さんの症状の経過や特徴、日光暴露との関連性について詳しくお聞きし、皮膚症状が出現するまでの時間や症状の持続期間、季節性の有無などを確認します。
視診による皮膚の観察では、症状の分布パターンや皮疹の形態、色調の変化などを詳細に観察し、露光部と非露光部での症状の違いに注目しながら、光線過敏症に特徴的な所見を調べることが大切です。
| 問診項目 | 確認内容 | 診断的意義 |
|---|---|---|
| 発症時期 | 季節性・時間帯 | 光線との関連性 |
| 症状経過 | 持続時間・程度 | 重症度評価 |
| 部位分布 | 露光部・非露光部 | 原因特定 |
光パッチテストによる原因物質の特定
光パッチテストは、疑わしい物質を皮膚に貼付し、人工的な紫外線を照射することで、光線過敏症の原因となる物質を特定する検査方法であり、詳細な診断には不可欠な検査です。
検査では背部に複数の物質を貼付し、48時間後に貼付物質を除去して人工紫外線を照射し、その後の皮膚反応を経時的に観察します。
テスト実施前の注意事項
- 検査2週間前からステロイド外用薬の使用中止
- 検査1週間前から日光浴を控える
- 服用中の薬剤の確認
- 既往歴の確認
光パッチテストの結果は、照射部位の発赤や腫脹、水疱形成などの皮膚反応の程度を総合的に評価し、原因物質の特定に役立てていきます。
光誘発試験による症状の再現性確認
光誘発試験は、人工的な紫外線を用いて症状を再現し、どの波長の光線に反応するかを確認する検査であり、診断の確実性を高めるために実施します。
| 検査項目 | 観察ポイント | 判定基準 |
|---|---|---|
| UVA照射 | 即時反応 | 30分以内の反応 |
| UVB照射 | 遅延反応 | 24時間後の変化 |
| 可視光線 | 持続性 | 1週間の経過 |
検査では、まず少量の光線から開始し、徐々に照射量を増やしながら皮膚の反応を観察していき、最小紅斑量(MED)を測定することで、光線感受性を定量的に評価することが可能です。
血液検査による全身状態の評価
光線過敏症の診断では、血液検査を通じて全身の状態を評価することも大切で、抗核抗体や補体価、ポルフィリン代謝産物など、光線過敏症に関連する様々な項目を測定し、全身性疾患との関連性を確認します。
血液検査での確認項目
- 一般的な血液検査(血算・生化学)
- 免疫学的検査(抗核抗体など)
- ポルフィリン代謝産物
- ビタミンB群
- 肝機能検査
検査結果の解釈には臨床症状との関連性を慎重に評価し、総合的な判断を行うことで、より正確な診断につなげます。
光線過敏症の治療法と治療薬について
光線過敏症の治療には、原因となる光感作物質の除去や紫外線防御、炎症抑制のための外用薬・内服薬による治療が必要です。
外用薬による治療の基本
皮膚の炎症反応を抑制するステロイド外用薬は、光線過敏症の治療において中心的な役割を果たしており、症状の重症度に応じて強さの異なる薬剤を使い分けることで、より効果的な治療効果を得られます。
急性期の強い炎症症状に対しては、強力な抗炎症作用を持つストロングクラス以上のステロイド外用薬を使用することで、速やかな症状の改善が期待できます。
また、ステロイド外用薬の長期使用による副作用を防ぐため、症状の改善に応じて徐々に弱いクラスの薬剤に切り替えていく方法が一般的です。
| ステロイド外用薬のクラス | 主な使用場面 | 使用期間の目安 |
|---|---|---|
| ストロングクラス | 急性期の強い炎症 | 2-4週間 |
| ミディアムクラス | 中等度の炎症 | 4-8週間 |
| マイルドクラス | 軽症例・維持療法 | 8週間以上 |
内服薬治療のアプローチ
重症例や広範囲に症状が及ぶ場合には、内服抗ヒスタミン薬や内服ステロイド薬による全身治療が重要となり、薬剤は体内での免疫反応を抑制することで症状の改善を図ります。
抗ヒスタミン薬には、第一世代と第二世代があり、眠気などの副作用が少ない第二世代の薬剤を中心に使用することで、日常生活への影響を最小限に抑えながら治療を進めることが可能です。
- H1受容体拮抗薬
- 免疫抑制薬
- 副腎皮質ステロイド
- 抗アレルギー薬
- 光線防御内服薬
光線防御製剤による予防的治療
外用の日焼け止め剤は、紫外線を物理的にブロックする酸化チタンや酸化亜鉛などの無機系成分と、化学的に吸収する有機系成分を組み合わせることで、より効果的な紫外線防御効果を発揮します。
| 紫外線防御成分 | 作用機序 | 特徴 |
|---|---|---|
| 酸化チタン | 物理的遮断 | 低刺激性 |
| 酸化亜鉛 | 物理的遮断 | 広域スペクトル |
| オクチノキサート | 化学的吸収 | UVB対応 |
| アボベンゾン | 化学的吸収 | UVA対応 |
特殊な治療法と最新の治療アプローチ
近年注目されている光線過敏症の新しい治療法として、免疫調節薬による治療や、特殊な波長の光を用いた光線療法があり、従来の治療法で効果が得られない症例に対する新たな選択肢です。
免疫調節薬による治療は、体内の免疫反応を直接的にコントロールすることで、光線過敏症の根本的な原因に対するアプローチが可能となります。
- 免疫調節薬治療
- 光線療法
- 生物学的製剤
- 遺伝子治療
- 幹細胞治療
また、最新の研究では、特定の波長の光を用いた光線療法が、一部の光線過敏症患者さんの症状改善に効果を示すことが報告されており、従来の薬物療法と組み合わせることで、より高い治療効果が期待できます。
生物学的製剤による治療も、重症例や従来の治療法で効果が不十分な症例に対する新たな治療選択肢として注目を集めており、自己免疫疾患に関連した光線過敏症での有効性が報告されてきました。
薬の副作用や治療のデメリットについて
光線過敏症の治療では、ステロイド外用薬や免疫抑制薬、光線療法などの各種治療法において、それぞれ特有の副作用やリスクがあります。
ステロイド外用薬の長期使用による副作用
ステロイド外用薬の長期使用では、皮膚の萎縮やステロイド皮膚症などの局所的な副作用が出現することがあり、特に顔面など皮膚の薄い部位での使用には慎重な経過観察が重要です。
皮膚萎縮が進行すると、皮膚が薄くなって血管が透けて見えるようになり、さらに外傷を受けやすくなります。
| 副作用の種類 | 主な症状 | 好発部位 |
|---|---|---|
| 皮膚萎縮 | 皮膚の菲薄化 | 顔面・関節部 |
| 毛細血管拡張 | 血管透見 | 頬部・鼻周囲 |
| 多毛 | 軟毛増生 | 頬部・額部 |
長期使用による皮膚バリア機能の低下は、外的刺激に対する皮膚の抵抗力を弱め、さらなる皮膚トラブルを引き起こすことがあるので注意が必要です。
免疫抑制薬による全身性の副作用
免疫抑制薬による治療では、感染症のリスク増加や腎機能への影響など、全身性の副作用に注意を払う必要があり、定期的な血液検査による経過観察が欠かせません。
免疫抑制薬の主な副作用
- 感染症リスクの上昇
- 消化器症状(悪心・嘔吐)
- 腎機能障害
- 高血圧
免疫機能の低下により、通常では問題とならない程度の細菌やウイルスによっても感染症を発症しやすくなることから、日常生活における感染予防対策にも十分な注意が必要となります。
光線療法に伴うリスクと注意点
光線療法では、治療に用いる紫外線による急性および慢性の皮膚障害が起こる可能性があり、特に長期的な治療では皮膚の光老化や色素沈着などの副作用があります。
| 治療期間 | 主なリスク | 対策のポイント |
|---|---|---|
| 短期 | 紅斑・水疱 | 照射量調整 |
| 中期 | 色素沈着 | 遮光対策 |
| 長期 | 光老化 | 定期的な経過観察 |
光線療法の副作用は、照射量や照射回数によって異なり、特に初期治療では慎重な光量調整と頻回な経過観察が大切です。
抗ヒスタミン薬による日常生活への影響
抗ヒスタミン薬の使用では、眠気や口渇、めまいなどの副作用が現れ、日常生活や仕事に支障をきたす可能性があります。
抗ヒスタミン薬の一般的な副作用
- 強い眠気
- 口渇感
- 集中力低下
- 便秘傾向
第一世代の抗ヒスタミン薬では、特に眠気の副作用が強く出現することから、自動車の運転や機械の操作には十分な注意が必要で、第二世代の抗ヒスタミン薬でも、個人差はありますが、眠気などの中枢神経系への影響が完全には避けられないことがあります。
抗ヒスタミン薬による口渇は、歯科的な問題を引き起こす可能性もあり、より丁寧な口腔ケアが必要です。
保険適用と治療費
以下に記載している治療費(医療費)は目安であり、実際の費用は症状や治療内容、保険適用否により大幅に上回ることがございます。当院では料金に関する以下説明の不備や相違について、一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。
外用薬による治療の基本
皮膚の炎症反応を抑制するステロイド外用薬は、症状の重症度に応じて強さの異なる薬剤を使い分けることで、より効果的な治療効果を得られます。
| ステロイド外用薬のクラス | 主な使用場面 | 1本あたりの費用目安(3割負担) |
|---|---|---|
| ストロングクラス | 急性期の強い炎症 | 1,500-2,000円 |
| ミディアムクラス | 中等度の炎症 | 800-1,500円 |
| マイルドクラス | 軽症例・維持療法 | 400-800円 |
内服薬治療のアプローチと費用
重症例や広範囲に症状が及ぶ場合には、内服抗ヒスタミン薬や内服ステロイド薬による全身治療が必要です。
- H1受容体拮抗薬(1日あたり100-300円)
- 免疫抑制薬(1日あたり200-1,000円)
- 副腎皮質ステロイド(1日あたり100-500円)
- 抗アレルギー薬(1日あたり100-400円)
- 光線防御内服薬(1日あたり200-600円)
特殊な治療法と最新の治療アプローチ
- 免疫調節薬治療(1クール30,000-100,000円)
- 光線療法(1回5,000-15,000円)
- 生物学的製剤(1回50,000-150,000円)
- 遺伝子治療(要相談)
- 幹細胞治療(要相談)
以上
参考文献
Morison WL. Photosensitivity. New England Journal of Medicine. 2004 Mar 11;350(11):1111-7.
Millard TP, Hawk JL. Photosensitivity disorders: cause, effect and management. American journal of clinical dermatology. 2002 Jun;3:239-46.
Covanis A, Stodieck SR, Wilkins AJ. Treatment of photosensitivity. Epilepsia. 2004 Jan;45:40-5.
Harding GF, Edson A, Jeavons PM. Persistence of photosensitivity. Epilepsia. 1997 Jun;38(6):663-9.
Jeavons PM, Bishop A, Harding GF. The prognosis of photosensitivity. Epilepsia. 1986 Oct;27(5):569-75.
Roelandts R. The diagnosis of photosensitivity. Archives of dermatology. 2000 Sep 1;136(9):1152-7.
Harber LC, Baer RL. Pathogenic mechanisms of drug-induced photosensitivity. Journal of Investigative Dermatology. 1972 Jun 1;58(6):327-42.
Moore DE. Drug-induced cutaneous photosensitivity: incidence, mechanism, prevention and management. Drug safety. 2002 Apr;25:345-72.
Lankerani L, Baron ED. Photosensitivity to exogenous agents. Journal of cutaneous medicine and surgery. 2004 Dec;8:424-31.
Epstein JH, Wintroub BU. Photosensitivity due to drugs. Drugs. 1985 Jul;30(1):42-57.