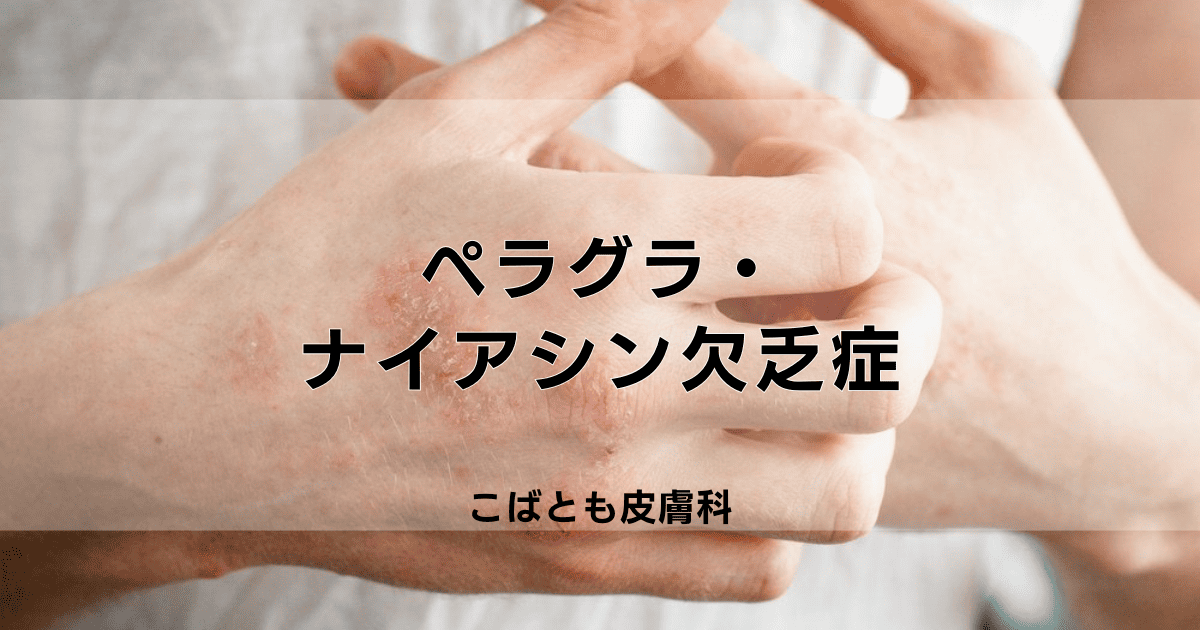ペラグラ・ナイアシン欠乏症(pellagra)とは、体内で重要な役割を果たすビタミンB3(ナイアシン)が著しく不足することで発症する代謝異常症であり、重篤な場合は生命に関わる可能性がある疾患です。
本疾患の特徴的な症状として、露光部位に現れる進行性の皮膚炎、持続する下痢症状、さらには重度の認知機能障害が挙げられ、医学的には「3D」(皮膚炎、下痢、認知症)という特徴的な症候群として知られています。
発症メカニズムとしては、トリプトファンからナイアシンへの変換経路の障害や、慢性的な栄養摂取不足、あるいは消化管での吸収障害などが主な原因です。
この記事の執筆者

小林 智子(こばやし ともこ)
日本皮膚科学会認定皮膚科専門医・医学博士
こばとも皮膚科院長
2010年に日本医科大学卒業後、名古屋大学医学部皮膚科入局。同大学大学院博士課程修了後、アメリカノースウェスタン大学にて、ポストマスターフェローとして臨床研究に従事。帰国後、同志社大学生命医科学部アンチエイジングリサーチセンターにて、糖化と肌について研究を行う。専門は一般皮膚科、アレルギー、抗加齢、美容皮膚科。雑誌を中心にメディアにも多数出演。著書に『皮膚科医が実践している 極上肌のつくり方』(彩図社)など。
こばとも皮膚科関連医療機関
ペラグラ・ナイアシン欠乏症の症状
ペラグラ・ナイアシン欠乏症は、皮膚炎、下痢、認知機能障害が主要な症状です。
主要な3大症状とその特徴
皮膚炎、下痢、認知機能障害は、ペラグラ・ナイアシン欠乏症における代表的な3大症状として知られており、症状は段階的に進行していきます。
| 症状名 | 初期症状 | 進行期症状 |
|---|---|---|
| 皮膚炎 | 軽度の発赤 | 水疱形成、色素沈着 |
| 下痢 | 軽度の腹痛 | 重度の水様性下痢 |
| 認知機能障害 | 集中力低下 | 意識障害、錯乱 |
皮膚症状は日光にさらされる部位に見られ、首から胸部にかけての領域や手背部、足背部などに好発し、皮膚の変化は、初期には軽度の発赤や灼熱感から始まり、進行すると水疱形成や色素沈着、さらには皮膚の肥厚化や落屑へと変化していくことが特徴的です。
消化器系の症状と特徴
消化器系の症状は、ペラグラ・ナイアシン欠乏症における重要な診断指標の一つで、以下のような症状が段階的に現れます。
- 食欲不振や悪心が初期症状
- 腹部不快感や軽度の腹痛が持続的に続く
- 水様性の下痢が頻繁に起こる
- 腸管粘膜の炎症により栄養吸収が障害される
- 体重減少が進行性に進む
消化器症状の進行は、全身状態の悪化に直接的に影響を及ぼすため、早期からの症状把握が診断において非常に大切です。
精神神経症状の進行と特徴
精神神経症状は、ペラグラ・ナイアシン欠乏症の進行において重大な影響を及ぼす症状群として認識されており、発現パターンには特徴的な経過が見られます。
| 段階 | 精神症状 | 神経症状 |
|---|---|---|
| 初期 | 不安感、抑うつ | 頭痛、めまい |
| 中期 | 不眠、焦燥感 | 振戦、協調運動障害 |
| 後期 | 幻覚、妄想 | 痙攣、意識障害 |
精神症状は、初期には軽度の不安感や抑うつ傾向として現れ、徐々に不眠や焦燥感といった症状へと進展していき、神経症状は頭痛やめまいといった軽度なものから始まり、進行すると振戦や協調運動障害、さらには痙攣や意識障害といった重篤な症状へと発展します。
全身症状と生理学的変化
全身症状は、ペラグラ・ナイアシン欠乏症の進行に伴って様々な形で現れます。
- 全身倦怠感や易疲労感が持続的に続く
- 筋力低下や筋肉痛が徐々に進行
- 体重減少が進行性に見られる
- 貧血症状が出現する
- 電解質バランスの乱れが生じる
生理学的な変化としては、ナイアシンが関与する様々な代謝経路の障害により、細胞レベルでのエネルギー産生が低下し、それに伴って全身の機能障害が進行します。
このような全身症状は、単独では非特異的な症状として見過ごされやすいですが、他の特徴的な症状と組み合わせて評価することで、診断の精度を高めることが可能です。
自律神経症状としては発汗異常や体温調節障害、血圧の変動といった症状が生じることがあり、また、粘膜症状として、口内炎や舌炎、口角炎といった症状が見られます。
ペラグラ・ナイアシン欠乏症の原因
ペラグラ・ナイアシン欠乏症は、必須栄養素であるナイアシン(ビタミンB3)の重度な欠乏状態や、その前駆体であるトリプトファンの代謝異常によって起こります。
栄養素の不足による発症メカニズム
ナイアシンは体内で重要な補酵素として機能し、細胞のエネルギー代謝や神経伝達物質の合成に不可欠です。
体内のナイアシン量が不足する背景には、主に食事からの摂取不足と、アミノ酸の一種であるトリプトファンからナイアシンへの変換障害という二つの大きな要因があります。
慢性的な栄養不良や極端な食事制限による直接的なナイアシン摂取量の低下は、発展途上国における主要な発症原因となっており、公衆衛生上の重大な課題です。
| 要因 | 具体的な状況 | リスク度 |
|---|---|---|
| 食事性 | トウモロコシ中心の食事 | 高 |
| 代謝性 | トリプトファン変換障害 | 中 |
| 吸収障害 | 消化管疾患 | 中 |
| 薬剤性 | 特定の薬剤による影響 | 低 |
代謝異常によるナイアシン欠乏のメカニズム
トリプトファンからナイアシンへの変換経路における代謝異常は、遺伝的要因や他の栄養素の不足によって起こされることがあり、代謝障害は体内でのナイアシン供給を著しく低下させることがあります。
消化管における吸収障害は、炎症性腸疾患や慢性的なアルコール摂取による腸管機能の低下によって起き、十分な量のナイアシンを摂取しても体内での利用が制限されます。
- 遺伝的要因による代謝異常
- 消化管疾患による吸収障害
- アルコール依存による栄養素吸収低下
- 薬剤性の代謝障害
- ホルモンバランスの乱れ
環境因子とリスク要因
社会経済的な要因や生活環境の変化は、ペラグラ発症のリスクを大きく左右する環境因子で、食料へのアクセスが制限される状況下では発症リスクが顕著に上昇します。
| リスク要因 | 影響度 | 予防可能性 |
|---|---|---|
| 貧困 | 極めて高 | 中 |
| 食料不足 | 高 | 中 |
| 環境変化 | 中 | 低 |
| 社会的孤立 | 中 | 高 |
予防的観点からの原因究明
栄養学的な観点からは、食事内容の多様性確保とバランスの取れた栄養摂取が発症予防の基本となりますが、実現するためには社会的なサポートシステムの構築が大切です。
- 食事内容の偏り
- 栄養知識の不足
- 社会的支援の欠如
- 経済的困窮
- 医療アクセスの制限
個人の生活習慣や食習慣の改善だけでなく、社会全体での栄養教育の充実と、誰もが必要な栄養素を摂取できる環境づくりが疾病予防において不可欠です。
ペラグラ・ナイアシン欠乏症の検査・チェック方法
ペラグラ・ナイアシン欠乏症の診断には、特徴的な臨床症状の確認に加え、血液検査によるナイアシン代謝産物の測定や尿中代謝物質の分析など、複数の検査方法を組み合わせた総合的な評価が重要です。
問診と視診による臨床診断
問診では患者さんの生活習慣や食事内容、症状の経過などを詳しく聴取することから始まり、日光暴露部位の皮膚症状と消化器症状、精神神経症状の有無について慎重に確認します。
| 確認項目 | 診察のポイント | 臨床的意義 |
|---|---|---|
| 皮膚症状 | 日光露出部位の変化 | 典型的な皮疹の確認 |
| 消化器症状 | 下痢の持続期間 | 栄養吸収障害の評価 |
| 精神症状 | 認知機能の変化 | 中枢神経障害の程度 |
視診による皮膚症状の評価では、特徴的な症状である日光暴露部位の対称性の紅斑や色素沈着、落屑などの有無を丁寧に確認していくことが大切です。
また、口腔内の状態についても詳細な観察が必要で、舌炎や口内炎の有無、粘膜の状態などを綿密にチェックすることで、栄養状態の評価にも役立ちます。
血液検査による生化学的評価
血液検査では、ナイアシンの代謝産物である尿中N1メチルニコチンアミドやN1メチル2ピリドン5カルボキサミドの測定が診断において大切な指標です。
- 血清ナイアシン濃度の測定
- トリプトファン代謝産物の分析
- ビタミンB群の血中濃度を確認
- 血清アルブミン値を測定
- 電解質バランスをチェック
血液検査の結果は、栄養状態の客観的な評価に不可欠な情報を提供するだけでなく、他の代謝異常症との鑑別診断にも重要な役割を果たします。
尿検査と代謝産物分析
尿検査では、ナイアシンの主要な代謝産物を定量的に測定することで、体内のナイアシン欠乏状態を評価できます。
| 検査項目 | 測定方法 | 基準値 |
|---|---|---|
| N1-メチルニコチンアミド | HPLC法 | 17.5-45.3 μmol/日 |
| 2-ピリドン | 蛍光法 | 20.8-41.2 μmol/日 |
24時間蓄尿検査を実施することで、より正確なナイアシン代謝状態の評価が可能となり、診断精度の向上につながり、また、尿中のトリプトファン代謝産物の分析も補助的な診断指標として活用されます。
栄養状態評価と身体測定
栄養状態の評価では、体重や体組成の変化、筋力の測定など、複数の指標を組み合わせた総合的なアプローチが重要です。
- 体重の継時的な変化を記録
- 上腕筋囲や皮下脂肪厚を測定
- 握力などの筋力テストを実施
- 基礎代謝率の評価
- 体組成分析を実施
身体測定の結果は、栄養状態の客観的な評価指標として活用されるだけでなく、治療効果のモニタリングにも重要な情報を提供します。
鑑別診断のための追加検査
鑑別診断においては、類似した症状を呈する他の疾患との区別を明確にするため、追加の検査を実施することがあります。
皮膚症状については、光線過敏症や接触性皮膚炎などとの鑑別が必要となることがあり、皮膚生検や光線過敏試験などの専門的な検査を追加することもあります。
消化器症状については、感染性腸炎や炎症性腸疾患との鑑別が重要となり、便培養検査や内視鏡検査などを実施することで、より確実な診断が可能です。
精神神経症状については、うつ病や認知症などの精神疾患との鑑別が求められることがあり、神経学的検査や認知機能検査などを追加することで、診断の確実性を高められます。
ペラグラ・ナイアシン欠乏症の治療法と治療薬について
ペラグラ・ナイアシン欠乏症の治療には、ニコチン酸(ナイアシン)またはニコチン酸アミドの経口投与を主体とし、重症例では入院管理下での静脈内投与を行います。
治療薬の種類と投与方法
ナイアシン製剤の投与は、患者の症状の重症度や全身状態に応じて投与経路や用量を慎重に選択する必要があり、急性期の重症例では迅速な改善を目指して静脈内投与を積極的に検討します。
経口投与では、ニコチン酸製剤を1日あたり300〜500mgの用量で開始し、症状の改善に応じて漸減していくことで、副作用の発現リスクを最小限に抑えることが可能です。
| 投与経路 | 初期投与量 | 維持投与量 | 投与期間 |
|---|---|---|---|
| 経口 | 300-500mg/日 | 100-300mg/日 | 2-4週間 |
| 静脈内 | 500-1000mg/日 | 250-500mg/日 | 1-2週間 |
| 筋肉内 | 400-800mg/日 | 200-400mg/日 | 1-2週間 |
重症度別の治療戦略
重症例においては、急性期の集中的な治療が不可欠で、入院管理下での静脈内投与により速やかな血中濃度の上昇を図ることで、神経症状や皮膚症状の早期改善を目指します。
中等症から軽症例では、外来での経口投与を基本としながら、定期的な経過観察を行い、症状の改善度に応じて投与量の調整を行っていきます。
- ニコチン酸ナトリウム注射液(重症例)
- ニコチン酸アミド錠(中等症)
- ニコチン酸製剤(軽症例)
- 複合ビタミンB群製剤(補助療法)
- 高単位ビタミンB3含有製剤(予防投与)
治療効果の判定と経過観理
皮膚症状は治療開始後24〜48時間以内に改善傾向を示し始め、神経症状の改善には数日から数週間を要することがあるため、症状の種類に応じた経過観察期間の設定が必要です。
治療効果の判定には、臨床症状の改善度と血中ナイアシン濃度の測定を組み合わせて総合的に評価を行い、治療方針の微調整に活用していきます。
- 皮膚症状の改善度評価
- 神経学的所見の変化
- 消化器症状の推移
- 血中ナイアシン濃度
- 一般状態の改善度
薬の副作用や治療のデメリットについて
ペラグラ・ナイアシン欠乏症の治療においては、ナイアシン補充療法や栄養療法による様々な副作用が生じる可能性があり、高用量投与時には肝機能障害や血糖値の変動などの重大な合併症に注意が必要です。
ナイアシン補充療法における副作用
ナイアシンの経口投与や静脈内投与では、投与量や投与方法によって様々な副作用が現れることがあり、特に治療開始初期には慎重なモニタリングが大切です。
| 投与方法 | 初期副作用 | 長期副作用 |
|---|---|---|
| 経口投与 | 皮膚紅潮、悪心 | 肝機能障害、胃潰瘍 |
| 静脈内投与 | 血圧低下、頭痛 | 電解質異常、腎機能障害 |
高用量のナイアシン投与では、皮膚の紅潮や灼熱感といった一過性の症状が高頻度で出現することがあり、症状は投与開始後30分から1時間程度で最も強く現れます。
胃腸症状としては、悪心や嘔吐、腹痛などが多く見られ、症状は食後投与や投与量の調整によって軽減できることもありますが、完全な予防は困難です。
肝機能への影響と対策
肝機能への影響は、ナイアシン治療における最も注意すべき副作用の一つで、定期的な肝機能検査によるモニタリングが欠かせません。
- 肝酵素値の上昇が観察されることがある
- 黄疸が出現する事例も報告
- 肝機能障害は用量依存的に増加
- 慢性的な肝障害のリスク
- 既存の肝疾患がある場合は特に注意が必要
肝機能障害の発現機序については、ナイアシンの代謝過程で生じる中間代謝産物が肝細胞に直接的な影響を及ぼすことが、複数の研究から示唆されています。
血糖値と代謝への影響
血糖値の変動は、ナイアシン治療中に比較的頻繁に観察される副作用の一つで、糖尿病の既往がある患者さんでは慎重な管理が必要です。
| 投与期間 | 血糖への影響 | 代謝への影響 |
|---|---|---|
| 短期 | 血糖上昇 | インスリン感受性低下 |
| 中期 | 耐糖能異常 | 脂質代謝変動 |
| 長期 | 糖尿病リスク上昇 | 代謝性アシドーシス |
血糖値の変動メカニズムについては、ナイアシンがインスリン感受性に影響を与えることや、肝臓での糖新生を促進する作用があることが、実験的研究から明らかになってきました。
代謝への影響は複雑で、脂質代謝の変動や電解質バランスの乱れなども引き起こす可能性があり、変化は患者さんの全身状態に大きな影響を与えます。
腎機能と電解質バランスへの影響
腎機能への影響は、高用量投与や長期投与の際に注意が必要な副作用で、以下のような症状や異常が生じることがあります。
- 尿量の変化が観察
- 電解質バランスの乱れが生じやすい
- 腎機能マーカーの上昇
- 浮腫が出現
- 高尿酸血症のリスクが増加
電解質バランスの変動は、ナトリウムやカリウム、マグネシウムなどの値に影響を及ぼすことがあり、不整脈などの重篤な合併症につながる可能性があります。
腎機能障害のリスクは、既存の腎疾患がある患者さんや高齢者において高くなる傾向があり、定期的な腎機能検査と電解質のモニタリングが不可欠です。
保険適用と治療費
以下に記載している治療費(医療費)は目安であり、実際の費用は症状や治療内容、保険適用否により大幅に上回ることがございます。当院では料金に関する以下説明の不備や相違について、一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。
外来診療における治療費
外来での治療では、定期的な診察と検査、投薬を組み合わせた包括的な医療を行います。
| 診療内容 | 自己負担額(3割負担の場合) |
|---|---|
| 血液検査 | 2,000〜4,000円 |
| 尿検査 | 800〜1,500円 |
| ナイアシン製剤(2週間分) | 3,000〜6,000円 |
| 皮膚生検 | 5,000〜8,000円 |
入院治療における費用
重症例では入院加療が必要となり、治療室使用料や注射薬、点滴などの費用が加算されます。
- 個室使用料(1日) 12,000〜20,000円
- 2人部屋使用料(1日) 8,000〜15,000円
- 特別療養環境費 5,000〜10,000円
検査・処置に関わる費用
定期的な血液検査や尿検査に加え、画像診断や特殊検査も実施します。
| 検査項目 | 費用(保険適用後) | 実施頻度 |
|---|---|---|
| 一般血液検査 | 2,500円 | 週1回 |
| 生化学検査 | 3,500円 | 2週間毎 |
| 皮膚生検 | 7,500円 | 必要時 |
| 画像診断 | 5,000円 | 必要時 |
投薬治療における費用
ナイアシン製剤を中心とした薬物療法では、症状の重症度に応じて投与量や投与期間を調整することが大切です。
- ナイアシン注射液(1回) 1,500〜3,000円
- ナイアシン錠剤(1日分) 200〜500円
- ビタミンB群製剤(1日分) 300〜800円
- 外用薬(1本) 2,000〜4,000円
以上
参考文献
Karthikeyan K, Thappa DM. Pellagra and skin. International journal of dermatology. 2002 Aug 1;41(8).
Wan P, Moat S, Anstey AJ. Pellagra: a review with emphasis on photosensitivity. British Journal of Dermatology. 2011 Jun 1;164(6):1188-200.
Hegyi J, Schwartz RA, Hegyi V. Pellagra: dermatitis, dementia, and diarrhea. International journal of dermatology. 2004 Jan;43(1):1-5.
Piqué-Duran E, Pérez-Cejudo JA, Cameselle D, Palacios-Llopis S, García-Vázquez O. Pellagra: a clinical, histopathological, and epidemiological study of 7 cases. Actas Dermo-Sifiliográficas (English Edition). 2012 Jan 1;103(1):51-8.
Crook MA. The importance of recognizing pellagra (niacin deficiency) as it still occurs. Nutrition. 2014 Jun 1;30(6):729.
Seal AJ, Creeke PI, Dibari F, Cheung E, Kyroussis E, Semedo P, van den Briel T. Low and deficient niacin status and pellagra are endemic in postwar Angola. The American journal of clinical nutrition. 2007 Jan 1;85(1):218-24.
Malfait P, Moren A, Dillon JC, Brodel A, Begkoyian G, Etchegorry MG, Malenga G, Hakewill P. An outbreak of pellagra related to changes in dietary niacin among Mozambican refugees in Malawi. International Journal of Epidemiology. 1993 Jun 1;22(3):504-11.
DesGroseilliers JP, Shiffman NJ. Pellagra. Canadian Medical Association Journal. 1976 Oct 10;115(8):768.
Li R, Yu K, Wang Q, Wang L, Mao J, Qian J. Pellagra secondary to medication and alcoholism: a case report and review of the literature. Nutrition in Clinical Practice. 2016 Dec;31(6):785-9.
Castiello RJ, Lynch PJ. Pellagra and the carcinoid syndrome. Archives of Dermatology. 1972 Apr 1;105(4):574-7.