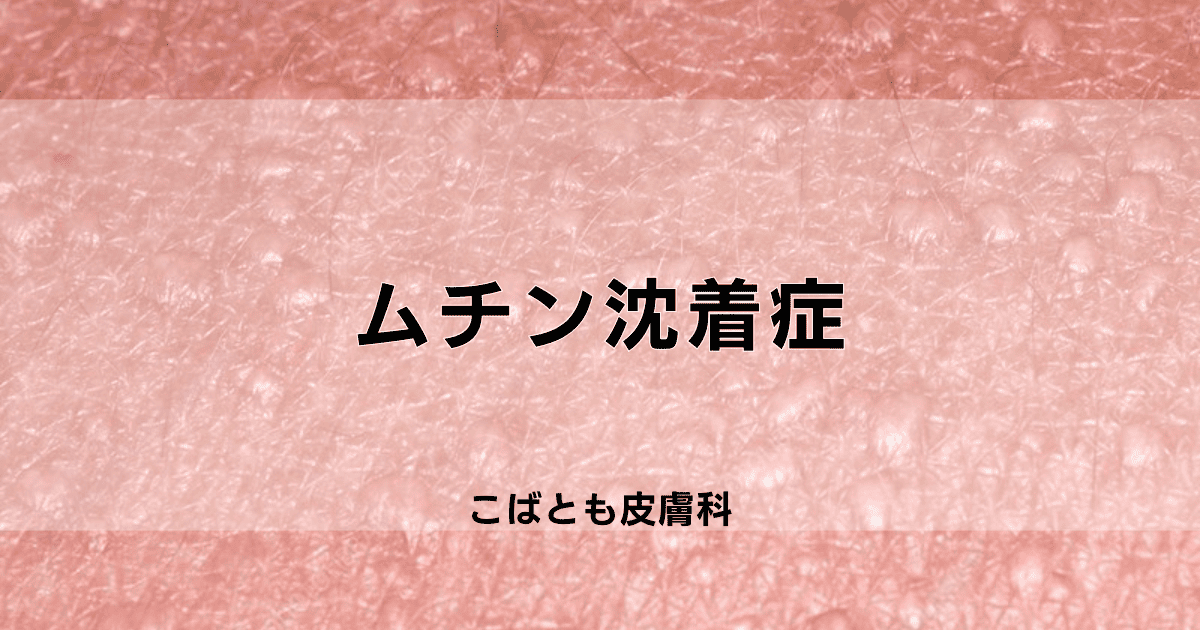ムチン沈着症(mucinosis)とは、真皮層における粘液様物質ムチンの異常蓄積を特徴とする代謝性皮膚疾患であり、遺伝的要因や自己免疫疾患との関連が指摘されています。
この疾患では、真皮層のコラーゲン線維間隙にムチンが過剰に産生・蓄積され、皮膚の柔軟化や浮腫性変化、時には丘疹や結節の形成などの特徴的な臨床症状を呈します。
この記事の執筆者

小林 智子(こばやし ともこ)
日本皮膚科学会認定皮膚科専門医・医学博士
こばとも皮膚科院長
2010年に日本医科大学卒業後、名古屋大学医学部皮膚科入局。同大学大学院博士課程修了後、アメリカノースウェスタン大学にて、ポストマスターフェローとして臨床研究に従事。帰国後、同志社大学生命医科学部アンチエイジングリサーチセンターにて、糖化と肌について研究を行う。専門は一般皮膚科、アレルギー、抗加齢、美容皮膚科。雑誌を中心にメディアにも多数出演。著書に『皮膚科医が実践している 極上肌のつくり方』(彩図社)など。
こばとも皮膚科関連医療機関
ムチン沈着症の症状
ムチン沈着症では、皮膚や関節周囲の組織にムチンと呼ばれる物質が過剰に蓄積することにより、様々な皮膚症状や関節の違和感が現れます。
皮膚における主要な症状
皮膚症状は、ムチン沈着症における最も特徴的な臨床所見で、患者さんの多くが初期段階で症状に気付くことがあり、特に顔面部や手足の露出部位での症状が目立ちます。
顔面や手足の皮膚においては、浮腫性の腫れや硬結が形成され、進行に伴って皮膚表面が徐々に肥厚していき、変化は対称性に出現することが特徴的です。
皮膚の触診では、特徴的なゴム様の弾力性を持った硬さを確認でき、この所見はムチン沈着症の診断における重要な手がかりとなります。
| 好発部位 | 初期症状 | 進行期症状 |
|---|---|---|
| 顔面 | 軽度の浮腫 | 丘疹形成 |
| 四肢 | 皮膚硬化 | 紅斑出現 |
| 体幹 | 色素沈着 | 皮膚肥厚 |
皮膚の色調変化については、初期では淡い紅斑として始まり、時間の経過とともに褐色調の色素沈着へと変化していき、変化は特に日光暴露部位でより顕著です。
関節周囲における症状
関節周囲の症状については、手指や手首、足首などの可動部位において違和感や不快感を感じ、症状は朝方により強く自覚されます。
関節周囲の組織にムチンが沈着することで、関節の可動域が制限され、日常生活における細かい動作に支障をきたすようになり、手指を使う精密な作業や長時間の歩行時に症状が増悪します。
- 手指関節の腫脹と硬化
- 手首の可動域制限
- 足首周囲の浮腫性変化
- 肘関節の違和感
- 膝関節周囲の硬結
全身症状と随伴症状
ムチン沈着症の進行に伴い、全身のさまざまな部位で症状が現れ、患者さんの体調に影響を及ぼすことがあり、症状は季節や気候の変化によって変動することが特徴的です。
全身倦怠感や易疲労感といった非特異的な症状も見られることがあり、日内変動を伴うい、特に午前中から昼過ぎにかけて症状が強くなります。
| 症状の種類 | 特徴的な所見 | 出現頻度 |
|---|---|---|
| 全身症状 | 倦怠感 | 高頻度 |
| 皮膚症状 | 浮腫性変化 | 必発 |
| 関節症状 | 可動域制限 | 中等度 |
体温調節機能への影響により、発汗異常や体温調節障害が現れることもあり、気温の変化が大きい季節の変わり目には注意が必要です。
症状の進行パターン
ムチン沈着症の症状は、緩やかな経過をたどりながら進行し、進行速度や症状の現れ方には個人差があります。
- 初期 軽度の皮膚症状
- 進行期 関節症状の出現
- 安定期 症状の固定化
- 変動期 症状の増悪と改善
- 晩期 全身症状の顕在化
皮膚症状は、初期には局所的な変化として始まりますが、時間の経過とともに徐々に範囲が拡大していき、皮膚の硬化や肥厚が顕著となる部位では、外観的な変化として認識されやすくなります。
進行速度には個人差が認められますが、環境因子や生活習慣の影響を受けやすく、外的因子は、紫外線暴露や寒冷刺激などです。
関節症状については、初期には軽度の違和感として自覚されることが多く、進行に伴って徐々に明確な症状として認識され、手指や手首など、細かい動作を必要とする部位での症状が目立つようになります。
ただし、皮膚症状と関節症状は必ずしも並行して進行するわけではなく、それぞれが独立したペースで進行します。
ムチン沈着症の原因
ムチン沈着症は、遺伝的要因、自己免疫疾患、内分泌異常などの複合的な要因により、真皮層でのムチン産生と分解のバランスが崩れることで発症します。
遺伝的要因と発症メカニズム
遺伝子の変異や多型性は、ムチン代謝に関与する様々な酵素の機能異常を引き起こし、発症リスクを顕著に高めることが、近年の分子生物学的研究により明らかになってました。
特に注目すべきは、ムチン型糖鎖の生合成に関与するGALNT3遺伝子の変異が、細胞外マトリックスにおけるムチンの代謝異常を引き起こす可能性が高いという点です。
また、細胞表面の糖タンパク質形成に重要な役割を果たすMUC1遺伝子の機能異常は、ムチンの産生過程における重大な障害を起こすことが、複数の研究で報告されています。
さらに、ヒアルロン酸結合タンパク2をコードするHABP2遺伝子の変異は、ムチンの分解経路に著しい影響を及ぼし、ムチンの過剰蓄積を起こす原因となります。
| 遺伝子タイプ | 関連する酵素 | 影響する代謝経路 |
|---|---|---|
| GALNT3 | N-アセチルガラクトサミン転移酵素 | ムチン型糖鎖の生合成 |
| MUC1 | ムチン1 | 細胞表面の糖タンパク質形成 |
| HABP2 | ヒアルロン酸結合タンパク2 | ムチン分解経路 |
自己免疫疾患との関連性
全身性エリテマトーデスやシェーグレン症候群などの自己免疫疾患を有する患者さんにおいて、ムチン沈着症の発症リスクが著しく上昇します。
自己免疫疾患では、免疫系の異常な活性化により産生される自己抗体や炎症性サイトカインが、真皮層におけるムチンの代謝バランスを大きく崩すことが分かっています。
- 全身性エリテマトーデス
- 甲状腺機能亢進症
- 関節リウマチ
- 強皮症
- シェーグレン症候群
内分泌系の影響
内分泌系の変調は、細胞外マトリックスの代謝に重大な影響を及ぼし、ムチン沈着症の発症メカニズムにおいて重要な役割を果たします。
甲状腺ホルモンの異常はグリコサミノグリカンの代謝に影響を与え、粘液水腫様の組織変化を引き起こす可能性があります。
また、性ホルモンバランスの乱れは、コラーゲン合成過程に影響を及ぼし、真皮層における異常なムチン沈着を促進する要因です。
さらに、成長ホルモンの分泌異常は、プロテオグリカンの産生に影響を与え、組織の肥厚や異常な水分貯留を起こすことがあることも判明しています。
| ホルモン | 影響を受ける代謝経路 | 関連する症状 |
|---|---|---|
| 甲状腺ホルモン | グリコサミノグリカン代謝 | 粘液水腫 |
| 性ホルモン | コラーゲン合成 | 皮膚変化 |
| 成長ホルモン | プロテオグリカン産生 | 組織肥厚 |
環境因子の関与
環境因子もまた、ムチン沈着症の発症や進行に重要な影響を及ぼすことが明らかになってきました。
紫外線暴露は、真皮層におけるムチンの代謝異常を起こす重要な環境要因で、また、特定の薬剤の使用は、細胞外マトリックスの代謝バランスを崩す可能性があり、ムチン沈着症の発症リスクを高める要因となります。
さらに、持続的なストレス状態は、内分泌系や免疫系の機能に影響を与え、間接的にムチンの代謝異常を起こす可能性があることも分かってきています。
- 紫外線暴露
- 特定の薬剤使用
- ストレス
- 感染症
- 外傷
ムチン沈着症の検査・チェック方法
ムチン沈着症の診断には、問診と視診による臨床所見の確認に加え、皮膚生検による病理組織学的検査が不可欠です。
初診時の問診・視診
初診時の問診では、発症時期や症状の進行経過、家族歴、既往歴などの詳細な情報収集を行い、自己免疫疾患や内分泌疾患の有無について慎重に確認することが重要です。
視診による皮膚所見の評価では、病変部の広がり、隆起の程度、色調変化などを詳細に観察し、デジタルカメラによる経時的な記録も併せて実施していきます。
病変部の触診では、皮膚の硬さや弾力性、圧痛の有無などを丁寧に確認し、健常部との比較による評価を行います。
| 問診項目 | 確認内容 | 関連する病態 |
|---|---|---|
| 発症時期 | 急性/慢性経過 | 病型分類 |
| 家族歴 | 遺伝的要因 | 遺伝性素因 |
| 既往歴 | 基礎疾患 | 続発性変化 |
皮膚生検による病理検査
皮膚生検における組織採取では、病変部位の選択が診断精度を左右する重要な要素となるため、最も典型的な臨床所見を示す部位を慎重に選定します。
採取した組織検体では、ヘマトキシリン・エオジン染色による組織構造の評価に加え、アルシアンブルー染色やコロイド鉄染色による特殊染色を実施することで、ムチン沈着の程度をより正確に判定できます。
- 膠原線維の配列異常の有無
- 炎症細胞浸潤の程度
- 血管周囲の変化
- 表皮の二次的変化
- 付属器の状態
免疫学的検査による精査
血液検査における自己抗体の測定では、抗核抗体を中心とした膠原病関連自己抗体のスクリーニングを行い、基礎疾患としての自己免疫疾患の有無を評価します。
補体価の測定では、CH50やC3、C4などの補体成分を定量することで、免疫複合体による補体消費の程度を判定し、疾患活動性の指標としても活用します。
免疫グロブリン分画の解析では、IgG、IgA、IgMなどの免疫グロブリンクラス別の定量を行い、体液性免疫応答の状態を詳細に評価することが可能です。
| 検査項目 | 測定意義 | 基準値範囲 |
|---|---|---|
| 抗核抗体 | 自己免疫評価 | 40倍未満 |
| CH50 | 補体活性 | 30-45U/mL |
| IgG | 免疫状態 | 870-1700mg/dL |
画像診断による評価
超音波検査では、高周波プローブを用いることで皮膚の各層構造を詳細に観察でき、真皮層の肥厚度や低エコー域の広がりを定量的に評価できます。
カラードップラー機能を活用することで、病変部における血流の変化や血管新生の状態を視覚化し、炎症活動性の指標として活用できます。
また、MRI検査では、特にT2強調画像でムチン沈着部位が高信号を示すことから、病変の深さや範囲を正確に把握することができ、経過観察における客観的な指標としても有用です。
- 超音波検査による皮膚厚の測定
- 深部組織の浮腫性変化の評価
- 血流評価によるドップラー所見
- 軟部組織の性状変化
- 関節周囲の変化
ムチン沈着症の治療法と治療薬について
ムチン沈着症の治療においては、ステロイド薬による内服治療を基本とし、症状の程度に応じて免疫抑制薬や生物学的製剤を併用します。
内服治療の基本アプローチ
内服治療では、副腎皮質ステロイド薬が第一選択薬として使用され、症状の重症度に応じて投与量を調整しながら、免疫系の異常な反応を抑制することで、ムチンの過剰な産生を抑制することが重要です。
プレドニゾロンなどの経口ステロイド薬による治療では、30mg/日程度から開始し、症状の改善に応じて徐々に減量していくことで、副作用のリスクを最小限に抑えながら治療効果を最大限に引き出せます。
| 薬剤分類 | 一般名 | 標準投与量 |
|---|---|---|
| ステロイド薬 | プレドニゾロン | 30-60mg/日 |
| 免疫抑制薬 | メトトレキサート | 6-8mg/週 |
| 生物学的製剤 | リツキシマブ | 1000mg/回 |
免疫抑制薬との併用療法では、メトトレキサートやアザチオプリンなどを使用することで、ステロイド薬の減量を図りながら、長期的な疾患活動性のコントロールを目指します。
局所治療のオプション
皮膚症状に対する局所療法として、ステロイド外用薬やタクロリムス軟膏などの免疫抑制外用薬を使用することで、皮膚の炎症や腫脹を効果的に抑制します。
- 強力ステロイド外用薬
- 中等度ステロイド外用薬
- タクロリムス軟膏
- ヒアルロン酸製剤
- ビタミンE含有軟膏
生物学的製剤による治療
従来の治療法で十分な効果が得られない場合には、生物学的製剤による治療を検討することがあり、使用されるのは、リツキシマブやベリムマブなどです。
| 投与方法 | 投与間隔 | 期待される効果 |
|---|---|---|
| 点滴静注 | 2週間毎 | 免疫抑制 |
| 皮下注射 | 4週間毎 | 炎症抑制 |
| 筋肉注射 | 8週間毎 | 症状緩和 |
生物学的製剤による治療では、定期的な血液検査やモニタリングを行いながら、感染症などの副作用に十分な注意を払う必要があり、投与開始前には結核などの感染症スクリーニングを実施します。
合併症への対応と治療効果のモニタリング
ムチン沈着症の治療においては、合併症の予防と早期発見が大切であり、定期的な血液検査や画像検査を通じて、治療効果と副作用の両面からモニタリングを行います。
- 血液検査による炎症マーカーの確認
- 画像検査による病変の評価
- 副作用モニタリング
- 感染症スクリーニング
- 骨密度測定
治療効果の判定には、皮膚症状の改善度や関節症状の変化、血液検査での炎症マーカーの推移など、複数の指標を組み合わせて総合的に評価を行うことで、より正確な治療効果の判定が可能です。
薬の副作用や治療のデメリットについて
ムチン沈着症の治療では、免疫抑制薬や副腎皮質ステロイド薬などの使用に伴い、骨粗鬆症、感染症リスクの上昇、内分泌系への影響など、様々な副作用やリスクが生じます。
免疫抑制薬による副作用
免疫抑制薬の長期使用は、生体の免疫機能に広範な影響を及ぼし、感染症に対する抵抗力の低下が顕著に現れることが多いです。
また、骨髄抑制による血球減少は、重篤な合併症を引き起こす可能性があり、好中球減少症は日和見感染のリスクを著しく高めます。
腎機能への影響も看過できない問題であり、特にカルシニューリン阻害薬の使用では、腎血流量の低下や糸球体濾過率の減少が生じます。
| 免疫抑制薬 | 主な副作用 | 発現頻度 |
|---|---|---|
| シクロスポリン | 腎機能障害 | 15-30% |
| タクロリムス | 高血圧 | 20-40% |
| ミコフェノール酸 | 消化器症状 | 30-50% |
ステロイド治療関連の合併症
副腎皮質ステロイド薬の全身投与では、糖代謝異常や骨代謝への影響が特に問題となり、二次性の糖尿病や骨粗鬆症の発症リスクが上昇します。
長期使用における副腎機能抑制は、ホルモンバランスの崩れを引き起こし、体重増加や満月様顔貌などのクッシング症候群様症状を呈することがあります。
また、創傷治癒の遅延や皮膚の脆弱化は、日常生活における外傷リスクを高める要因です。
- 骨密度低下と骨折リスクの上昇
- 白内障や緑内障の発症リスク
- 消化性潰瘍の発症
- 高血圧や電解質異常
- 精神症状(不眠、興奮など)
局所療法による皮膚への影響
外用ステロイド薬の長期使用は、皮膚萎縮や毛細血管拡張などの局所的な副作用を起こし、顔面や関節部周囲での使用では注意が必要です。
光線療法においては、急性期の症状として紅斑や水疱形成が生じる可能性があり、長期的には光老化や色素沈着のリスクが上昇します。
| 局所療法 | 短期的副作用 | 長期的副作用 |
|---|---|---|
| 外用ステロイド | 毛細血管拡張 | 皮膚萎縮 |
| 光線療法 | 紅斑・水疱 | 光老化 |
| 局所免疫調節薬 | 灼熱感 | 色素沈着 |
生物学的製剤による全身性の影響
生物学的製剤の使用では、投与部位反応や過敏症反応などの即時型の副作用に加え、長期的な免疫系への影響が懸念されます。
TNF阻害薬の使用では、結核などの日和見感染症や悪性腫瘍の発症リスクが上昇する可能性があることが、明らかになってきました。
自己抗体の産生誘導は、新たな自己免疫疾患の発症につながる可能性があり、特にループス様症候群の発症には注意が必要です。
- B型肝炎ウイルスの再活性化
- 脱髄性疾患の誘発
- 間質性肺炎の発症
- 注射部位反応
- 過敏症反応
保険適用と治療費
以下に記載している治療費(医療費)は目安であり、実際の費用は症状や治療内容、保険適用否により大幅に上回ることがございます。当院では料金に関する以下説明の不備や相違について、一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。
外来診療における保険診療費
外来診療では、定期的な診察と血液検査が基本となり、症状の経過観察と治療効果の確認を行います。
| 診療内容 | 自己負担額(3割負担の場合) | 治療頻度 |
|---|---|---|
| 血液検査 | 3,000円~5,000円 | 月1回 |
| 画像検査 | 5,000円~10,000円 | 3ヶ月毎 |
| 内服薬処方 | 8,000円~15,000円 | 月1回 |
薬物療法にかかる費用
ステロイド薬による治療では、安価な薬剤から開始することが多いです。
免疫抑制剤や生物学的製剤を使用する場合は、治療費が高額となります。
| 薬剤種類 | 月額自己負担(3割負担) | 投与期間 |
|---|---|---|
| ステロイド薬 | 5,000円~10,000円 | 3~6ヶ月 |
| 免疫抑制剤 | 15,000円~30,000円 | 6~12ヶ月 |
| 生物学的製剤 | 50,000円~100,000円 | 必要期間 |
検査費用の内訳
定期的な血液検査は、治療効果のモニタリングに重要で、画像検査は、症状の進行度や治療効果の判定に必要です。
- 一般血液検査 3,000円~5,000円
- 免疫系検査 8,000円~12,000円
- 生化学検査 4,000円~7,000円
- MRI検査 15,000円~25,000円
- 超音波検査 5,000円~8,000円
以上
参考文献
Rongioletti F. Lichen myxedematosus (papular mucinosis): new concepts and perspectives for an old disease. InSeminars in cutaneous medicine and surgery 2006 Jun 1 (Vol. 25, No. 2, pp. 100-104).
Rongioletti F, Rebora A. Updated classification of papular mucinosis, lichen myxedematosus, and scleromyxedema. Journal of the American Academy of Dermatology. 2001 Feb 1;44(2):273-81.
Gibson LE, Muller SA, Leiferman KM, Peters MS. Follicular mucinosis: clinical and histopathologic study. Journal of the American Academy of Dermatology. 1989 Mar 1;20(3):441-6.
Emmerson RW. Follicular mucinosis a study of 47 patients. British Journal of Dermatology. 1969 Jun 1;81(6):395-413.
Thareja S, Paghdal K, Lien MH, Fenske NA. Reticular erythematous mucinosis–a review. International Journal of Dermatology. 2012 Aug;51(8):903-9.
MEHREGAN DA, GIBSON LE, MULLER SA. Follicular mucinosis: histopathologic review of 33 cases. InMayo Clinic Proceedings 1991 Apr 1 (Vol. 66, No. 4, pp. 387-390). Elsevier.
Buchner A, Merrell PW, Leider AS, Hansen LS. Oral focal mucinosis. International journal of oral and maxillofacial surgery. 1990 Dec 1;19(6):337-40.
Del Pozo J, Almagro M, Martínez W, Yebra‐Pimentel MT, García‐Silva J, Peña‐Penabad C, Fonseca E. Dermatomyositis and mucinosis. International journal of dermatology. 2001 Feb;40(2):120-4.
JOHNSON WC, HELWIG EB. Cutaneous focal mucinosis: a clinicopathological and histochemical study. Archives of Dermatology. 1966 Jan 1;93(1):13-20.
Khalil J, Kurban M, Abbas O. Follicular mucinosis: a review. International Journal of Dermatology. 2021 Feb;60(2):159-65.