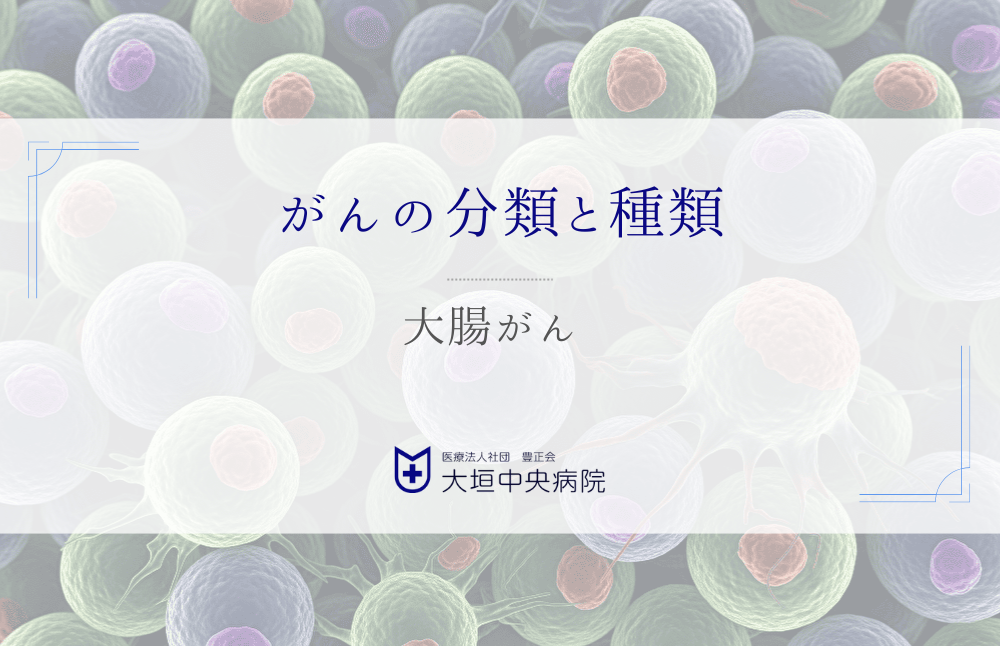大腸がんは、日本人にとって非常に身近ながんの一つです。しかし、多くの場合は早期に発見し、適切な治療を受けることで克服を目指せます。
この記事では、大腸がんの基本的な知識から、見逃してはならない症状、効果的な検査方法、そして治療の選択肢まで、患者さんとそのご家族が知っておくべき重要な情報を網羅的に解説します。
正しい知識を持つことが、不安を和らげ、前向きに治療と向き合うための第一歩となります。
大腸がんとは何か – 部位別の特徴と発生の仕組み
大腸がんは、消化管の最終部分である大腸(結腸と直腸)に発生するがんです。その発生には生活習慣が深く関わっており、日本の食生活の欧米化に伴い増加傾向にあります。
大腸のどの部位にがんが発生するかによって、その性質や症状の現れ方が異なるため、基本的な構造とがんの発生について理解することが重要です。
大腸の構造と働き
大腸は全長約1.5~2メートルの管状の臓器で、主に水分や電解質を吸収し、便を形成して体外へ排出する役割を担っています。
大腸は、結腸と直腸に大きく分けられ、結腸はさらに盲腸、上行結腸、横行結腸、下行結腸、S状結腸に区分されます。
大腸の部位ごとの役割
| 部位 | 主な役割 | 特徴 |
|---|---|---|
| 結腸 | 水分・ミネラルの吸収、便の形成 | 大腸の大部分を占める。がんが発生する頻度が最も高い。 |
| 直腸 | 便を一時的に溜める | 骨盤内にあり、周囲に重要な神経や臓器が密集している。 |
がんが発生する主な原因
大腸がんの発生原因は一つではありませんが、多くは生活習慣と遺伝的な要因が複雑に絡み合って発症すると考えられています。特に、食生活の乱れや運動不足が大きなリスク要因となります。
大腸ポリープとがんの関係
大腸がんの多くは、まず「ポリープ」と呼ばれる良性の腫瘍(腺腫)として発生します。このポリープが長期間放置されることで、その一部ががん化し、徐々に大きくなっていくと考えられています。
すべてのポリープががんになるわけではありませんが、がんになる可能性のあるポリープを早期に発見し切除することが、大腸がんの予防につながります。
発症リスクを高める要因
大腸がんの発症リスクを高める要因として、以下のようなものが知られています。これらの要因を複数持つ場合は、より注意が必要です。
- 赤肉(牛、豚、羊など)や加工肉(ハム、ソーセージなど)の過剰摂取
- 野菜や果物の摂取不足
- 肥満
- 運動不足
- 過度な飲酒と喫煙
症状を見逃すな – 早期発見につながる重要なサイン
大腸がんは、初期の段階では自覚症状がほとんどないことが多く、症状が現れたときにはすでに進行しているケースも少なくありません。
だからこそ、体に現れるささいな変化に気づき、早期発見につなげることが極めて大切です。
注意すべき初期の症状
がんがまだ小さい初期の段階でも、いくつかのサインが現れることがあります。これらの症状は他の病気でも見られるため、自己判断せずに専門医に相談することが重要です。
血便や便通の変化
最も代表的な症状が血便です。便に血が混じる、便の表面に血が付着する、排便後にトイレットペーパーに血が付くといった症状があります。
痔(じ)と間違えやすいですが、大腸がんの重要なサインである可能性があります。また、下痢と便秘を繰り返す、便が細くなる、残便感があるといった便通の異常も注意すべき症状です。
腹部の不快感
お腹が張る感じ(腹部膨満感)や、持続的な腹痛も症状の一つです。これらの症状は日常的に経験しやすいため見過ごされがちですが、長く続く場合は注意が必要です。
進行によって現れる症状
がんが進行すると、よりはっきりとした症状が現れるようになります。これらの症状は、がんが大きくなることで引き起こされたり、他の臓器へ転移したりすることで生じます。
貧血、体重減少、倦怠感
がんからの持続的な出血により、気づかないうちに貧血が進行することがあります。めまいや立ちくらみ、動悸、息切れなどが貧血のサインです。
また、特別な理由がないのに体重が減少したり、強い疲労感や倦怠感が続いたりする場合も、がんが進行している可能性があります。
症状の比較
| 項目 | 初期に見られる症状 | 進行期に見られる症状 |
|---|---|---|
| 排便関連 | 血便、便通異常(下痢・便秘)、残便感 | 便が極端に細くなる、強い腹痛 |
| 全身症状 | ほとんどない | 原因不明の貧血、体重減少、倦怠感 |
| 腹部症状 | 腹部の張り、軽い腹痛 | しこりを感じる、腸閉塞による激しい痛み |
検診で命を守る – 効果的な検査方法と受診のタイミング
症状がない早期の段階で大腸がんを発見するために、定期的な検診が非常に有効です。
検診によってがんやがんになる前のポリープを発見し、適切な治療につなげることで、大腸がんによる死亡リスクを大幅に減らすことができます。
大腸がん検診の目的と対象
大腸がん検診の最大の目的は、自覚症状のない早期がんやポリープを発見することです。特に、発症リスクが高まり始める40歳以上の方は、定期的に検診を受けることが推奨されます。
検診を受けるべき人
一般的に、40歳になったら男女ともに大腸がん検診の対象となります。自治体や職場の健康診断で受ける機会があります。
また、家族に大腸がんになった人がいる場合や、炎症性腸疾患などの持病がある場合は、より若いうちから、より頻繁な検査が必要になることがありますので、医師に相談してください。
検診で用いる検査の種類
大腸がん検診は、まず簡易的な検査でリスクのある人を見つけ出し、必要な場合に精密検査を行うという流れが一般的です。
便潜血検査
便潜血検査は、便に混じった目に見えない微量の血液を検出する検査です。自宅で2日間にわたって便を採取し、提出するだけで済むため、身体的な負担が少ないのが特徴です。
この検査で「陽性」と判定された場合は、出血の原因を特定するために精密検査を受ける必要があります。陽性だからといって必ずしもがんというわけではありませんが、精密検査を必ず受けることが重要です。
精密検査としての内視鏡検査
精密検査として最も一般的に行われるのが大腸内視鏡検査です。肛門から内視鏡(カメラ)を挿入し、大腸の内部を直接観察します。
この検査では、がんやポリープを直接目で見て確認できるだけでなく、疑わしい組織を採取して病理診断を行ったり、小さなポリープであればその場で切除したりすることも可能です。
これが、内視鏡検査が「診断」と「治療」を兼ね備えた優れた検査方法といわれる理由です。
各検査方法の比較
| 検査方法 | 目的 | 特徴 |
|---|---|---|
| 便潜血検査 | 一次検診(スクリーニング) | 身体的負担が少ない。がんやポリープからの出血を検出。 |
| 大腸内視鏡検査 | 精密検査・診断・治療 | 大腸全体を直接観察。組織採取やポリープ切除が可能。 |
| 注腸X線検査 | 精密検査 | 肛門からバリウムと空気を注入しX線撮影。内視鏡が困難な場合に選択。 |
大腸がんの進行度 – ステージ分類と予後への影響
大腸がんの治療方針を決定し、今後の見通し(予後)を予測する上で、がんの進行度を正確に把握することが不可欠です。
この進行度は「ステージ」として分類され、がんの広がり具合を示します。
ステージ分類の考え方
ステージは、がんがどのくらい深く大腸の壁に食い込んでいるか(壁深達度)、リンパ節への転移があるか、肝臓や肺など他の臓器への遠隔転移があるかの3つの要素を組み合わせて決定します。
壁深達度・リンパ節転移・遠隔転移
大腸の壁は内側から粘膜、粘膜下層、固有筋層、漿膜下層、漿膜という層構造になっています。
がんが粘膜内にとどまっているごく早期の状態から、壁を突き破って周囲の臓器にまで及ぶ進行した状態まで、その深さで進行度が変わります。
また、リンパ管を通ってリンパ節へ転移したり、血管を通って遠くの臓器へ転移したりすると、より進行したステージと判断します。
ステージごとの状態
ステージは0からIVまでの5段階に分けられ、数字が大きくなるほどがんが進行していることを意味します。このステージ分類は、治療法を選択する際の最も重要な指標となります。
ステージ分類の概要
| ステージ | がんの広がり | 一般的な状態 |
|---|---|---|
| 0 | がんが粘膜内にとどまる | ごく早期のがん。転移の可能性はほとんどない。 |
| I | がんが固有筋層までにとどまる | リンパ節への転移はない。 |
| II | がんが固有筋層を越えて広がる | リンパ節への転移はないが、周囲に広がっている。 |
| III | リンパ節への転移がある | 壁深達度に関わらず、リンパ節転移がある状態。 |
| IV | 遠隔転移がある | 肝臓、肺、腹膜など大腸から離れた臓器に転移している。 |
ステージと生存率の関係
がんの治療成績を示す指標として「5年相対生存率」が用いられます。これは、がんと診断された人が5年後に生存している割合が、日本人全体で同じ性別・年齢の人と比べてどのくらいかを示す数値です。
ステージが早いほど生存率は高く、早期発見の重要性がここからもわかります。
ステージ別の5年相対生存率の目安
| ステージ | 5年相対生存率(結腸がん) | 5年相対生存率(直腸がん) |
|---|---|---|
| I | 90%以上 | 90%以上 |
| II | 約85% | 約80% |
| III | 約75% | 約70% |
| IV | 約20% | 約20% |
※この数値はあくまで平均的なデータであり、個々の患者さんの状態によって異なります。
治療選択肢の理解 – 手術・化学療法・放射線療法の実際
大腸がんの治療は、がんの進行度(ステージ)や体の状態、患者さん本人の希望などを総合的に考慮して決定します。
治療の柱となるのは、内視鏡治療、手術、薬物療法(化学療法)、放射線療法の4つで、これらを単独または組み合わせて行います。
ステージに応じた治療の基本方針
治療法は、がんがどのくらい広がっているかによって大きく異なります。
早期のがんであれば体への負担が少ない内視鏡治療で根治を目指せますが、進行している場合は手術や薬物療法など、より集学的な治療が必要となります。
内視鏡による治療
がんが粘膜内または粘膜下層の浅い部分にとどまっているステージ0やステージIの一部では、内視鏡を使ってがんを切除する治療が可能です。
お腹を切る必要がなく、体への負担が非常に少ないという大きな利点があります。
ポリープや早期がんの切除
内視鏡の先端から出したスネアという輪状のワイヤーをポリープやがんにかけて締め付け、高周波電流を流して焼き切ります。
切除した組織は回収し、病理検査で詳しく調べて、がんが完全に取りきれているか、追加の治療が必要かなどを判断します。
手術(外科治療)
内視鏡治療の対象とならない、より進行した大腸がんに対する標準的な治療法が手術です。がんのある腸管と、転移の可能性がある周囲のリンパ節を一緒に切除します。
- 開腹手術: お腹を大きく切開して行う従来からの手術方法です。
- 腹腔鏡手術: お腹に数か所の小さな穴を開け、そこからカメラや手術器具を挿入して行う手術です。傷が小さく、術後の痛みが少なく、回復が早いという利点があります。
薬物療法(化学療法)
薬物療法は、抗がん剤などの薬を使ってがん細胞を攻撃する治療法です。手術で取りきれないほど進行した場合や、遠隔転移がある場合、また手術後の再発を予防する目的で行います。
抗がん剤治療の目的と種類
抗がん剤治療は、がんの進行を抑えたり、症状を和らげたりすることを目的とします。
また、手術で目に見えるがんをすべて取り除いた後でも、微小ながん細胞が残っている可能性がある場合に、再発のリスクを減らすために行う「補助化学療法」も重要です。
近年では、がん細胞の特定の分子だけを狙い撃ちする「分子標的薬」や、自身の免疫力を利用してがんを攻撃する「免疫チェックポイント阻害薬」なども登場し、治療の選択肢が広がっています。
放射線療法
放射線療法は、高エネルギーのX線をがん細胞に照射して破壊する治療法です。
特に骨盤内の狭い場所にある直腸がんの治療で、手術前や手術後の補助的な治療として、あるいは手術が難しい場合の中心的な治療として重要な役割を果たします。
主な治療法の概要
| 治療法 | 主な対象ステージ | 目的 |
|---|---|---|
| 内視鏡治療 | 0、Iの一部 | がんの根治(切除) |
| 手術 | I、II、III、IVの一部 | がんの根治(切除)、症状緩和 |
| 薬物療法 | III、IV、再発時 | 再発予防、延命、症状緩和 |
| 放射線療法 | 直腸がん(II、III、IV)、再発時 | 再発予防、手術の補助、症状緩和 |
予防可能ながん – 生活習慣改善で発症リスクを下げる方法
大腸がんは、生活習慣と深い関わりがあるがんの一つです。つまり、日々の生活を見直すことで、その発症リスクを下げることが可能です。
がんになってから治療することも大切ですが、まずはがんにならないための「予防」を意識することが重要です。
食生活で気をつけること
毎日の食事は、大腸の健康に直接影響を与えます。バランスの取れた食事を心がけ、リスクを高める食品を避け、リスクを下げる食品を積極的に取り入れましょう。
リスクをコントロールする食事の工夫
| 項目 | 推奨されること | 避けるべきこと |
|---|---|---|
| 食品 | 食物繊維(野菜、果物、きのこ、海藻)、発酵食品 | 赤肉・加工肉の過剰摂取、高脂肪食 |
| 調理法 | 蒸す、茹でる | 焦げるまで焼く、揚げる |
運動を取り入れる効果
定期的な運動は、腸の動きを活発にし、便通を改善する効果があります。また、肥満の予防・解消にもつながり、大腸がんのリスクを低下させることが多くの研究で示されています。
推奨される運動習慣
激しい運動である必要はありません。ウォーキングや軽いジョギング、水泳など、自分が楽しめる有酸素運動を、週に合計60分程度行うことを目標に始めてみましょう。
日常生活の中で、エレベーターを階段に変えるなど、少しでも体を動かす意識を持つことが大切です。
その他の生活習慣の見直し
食事や運動以外にも、禁煙や節酒が大腸がんの予防につながります。喫煙は多くのがんのリスク要因であり、アルコールの過剰摂取も大腸がんのリスクを高めることがわかっています。
統計から読み解く大腸がんの現状 – 日本における発症率と生存率
大腸がんが現在どのような状況にあるのかを客観的なデータで理解することは、病気と向き合う上で助けとなります。
ここでは、日本における大腸がんの罹患率(新たにがんと診断される人の割合)や生存率に関する統計データを見ていきます。
日本人の大腸がん罹患状況
国立がん研究センターの最新の統計によると、大腸がんは日本人のがんの中で罹患数が最も多い部位の一つです。
特に高齢になるほど罹患率は高くなる傾向があり、食生活の欧米化などを背景に、今後もこの傾向は続くと予測されています。
年代別・男女別の罹患率
男女ともに40歳代から罹患率が増加し始め、年齢とともに上昇します。性別で見ると、男性の方が女性よりも罹患率が高い傾向にあります。
これは、男性の方が喫煙や飲酒の習慣を持つ人が多いことなどが一因と考えられています。
生存率の動向
大腸がんは、早期に発見すれば治癒率が非常に高いがんです。治療技術の進歩により、全体の5年相対生存率は年々向上しています。
しかし、進行度によって生存率が大きく異なるため、やはり定期的な検診による早期発見が鍵となります。
部位別の5年相対生存率
| 部位 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|
| 結腸がん | 約72% | 約71% |
| 直腸がん | 約69% | 約68% |
※このデータは全部位・全ステージを含んだ平均値です。
治療後の生活 – 経過観察と再発防止のための取り組み
大腸がんの治療が終わった後も、再発や新たな合併症が起こらないかを確認するために、定期的な検査と診察(経過観察)を続けることが非常に重要です。
また、再発のリスクを少しでも減らすために、日常生活でのセルフケアにも取り組みましょう。
治療後の定期的な検査
治療後の経過観察の目的は、万が一の再発を早期に発見することです。再発した場合でも、早く見つけることができれば、再び治療してコントロールできる可能性が高まります。
経過観察のスケジュール例
検査の頻度や内容は、がんのステージや治療法によって異なりますが、一般的には治療後5年間は定期的に行います。以下は一般的なスケジュールの一例です。
- 診察・血液検査(腫瘍マーカー): 1~3ヶ月に1回から始まり、徐々に間隔をあけていく
- CT検査(胸部・腹部): 6ヶ月~1年に1回
- 大腸内視鏡検査: 治療後1年を目安に行い、その後は医師の指示に従う
再発への備え
大腸がんの再発は、多くが治療後5年以内に起こります。特に最初の2~3年が最も注意が必要な期間です。
再発は、もとのがんがあった場所の近くで起こる「局所再発」と、肝臓や肺など離れた臓器に起こる「遠隔転移」があります。
注意すべき再発のサイン
持続する腹痛、血便、便通の変化、原因不明の体重減少、長引く咳や血痰、体の特定の場所の痛みなど、治療前と同じような症状や、これまでになかった症状が現れた場合は、次の診察を待たずに早めに主治医に相談してください。
日常生活のセルフケア
治療後も、再発予防のために生活習慣を整えることが大切です。特に、直腸がんの手術で人工肛門(ストーマ)を造設した場合は、その管理方法を学び、上手に付き合っていく必要があります。
専門の看護師(皮膚・排泄ケア認定看護師)から指導を受け、サポートを得ることができます。
よくある質問
- ポリープはすべて切除する必要があるのですか?
-
すべてのポリープががんになるわけではありません。
しかし、内視鏡検査で見ただけでは良性か悪性(がん)か、あるいは将来がんになる可能性があるタイプ(腺腫)かを完全に判断することは困難です。
そのため、ある程度の大きさ以上のポリープや、がんが疑われる形状のポリープは、診断と予防を兼ねて切除することが一般的です。
- 血便が出たら必ず大腸がんですか?
-
いいえ、必ずしもそうではありません。血便の原因として最も多いのは痔(いぼ痔や切れ痔)です。その他、大腸炎などの病気でも出血することがあります。
しかし、大腸がんの重要なサインである可能性も否定できないため、自己判断は禁物です。血便に気づいたら、まずは消化器科や肛門科を受診して原因を調べることが大切です。
- 大腸内視鏡検査は痛いですか?
-
痛みの感じ方には個人差があります。腸の長さや曲がり具合、癒着の有無などによって、検査中にお腹が張ったり、痛みを感じたりすることがあります。
多くの医療機関では、患者さんの苦痛を和らげるために、鎮静剤や鎮痛剤を使用して、うとうとと眠っているような状態で検査を受けることができます。
不安な方は、事前に医療機関に相談してください。
- 家族に大腸がんの人がいると、自分もなりますか?
-
家族、特に親子や兄弟姉妹に大腸がんになった人がいる場合、いない人と比べて発症リスクが2~3倍高くなるといわれています。
これは、似たような生活習慣を送っていることや、遺伝的な要因が関係していると考えられます。
特に「家族性大腸腺腫症」や「リンチ症候群」といった遺伝性の病気の場合は、非常に高い確率で大腸がんを発症します。
血縁者に大腸がんの既往歴がある方は、通常より早い年齢から定期的な内視鏡検査を受けることが推奨されます。
- 抗がん剤治療の副作用はどのようなものがありますか?
-
抗がん剤の種類によって副作用は異なりますが、一般的には吐き気、嘔吐、食欲不振、口内炎、下痢、脱毛、倦怠感、白血球や血小板の減少による感染しやすさや出血しやすさ、手足のしびれなどが現れることがあります。
最近では、副作用を軽減するための支持療法も進歩しており、多くの副作用はコントロール可能です。
治療前に医師や薬剤師から詳しい説明を受け、つらい症状があれば我慢せずに伝えることが重要です。
大腸がんの転移先として最も多い臓器の一つが肝臓です。がんという病気は、一つの臓器だけでなく、体全体の問題として捉える必要があります。
肝臓がんは「沈黙の臓器」と呼ばれる肝臓に発生するため、症状が出にくく発見が遅れがちです。
大腸がんについて理解を深めた今、関連性の高い肝臓がんについても正しい知識を持つことは、あなたとあなたの大切な家族の健康を守るために非常に有益です。
次の記事で、肝臓がんの原因、症状、そして治療法について詳しく学んでみましょう。
参考文献
KANTH, Priyanka; INADOMI, John M. Screening and prevention of colorectal cancer. Bmj, 2021, 374.
LADABAUM, Uri, et al. Strategies for colorectal cancer screening. Gastroenterology, 2020, 158.2: 418-432.
BHAT, Shivaram K.; EAST, James E. Colorectal cancer: prevention and early diagnosis. Medicine, 2015, 43.6: 295-298.
KEUM, NaNa; GIOVANNUCCI, Edward. Global burden of colorectal cancer: emerging trends, risk factors and prevention strategies. Nature reviews Gastroenterology & hepatology, 2019, 16.12: 713-732.
MARSHALL, James R. Prevention of colorectal cancer: diet, chemoprevention, and lifestyle. Gastroenterology clinics of North America, 2008, 37.1: 73-82.
BINEFA, Gemma, et al. Colorectal cancer: from prevention to personalized medicine. World journal of gastroenterology: WJG, 2014, 20.22: 6786.
CHAN, Andrew T.; GIOVANNUCCI, Edward L. Primary prevention of colorectal cancer. Gastroenterology, 2010, 138.6: 2029-2043. e10.
LÓPEZ, Pedro J. Tárraga; ALBERO, Juan Solera; RODRÍGUEZ-MONTES, José Antonio. Primary and secondary prevention of colorectal cancer. Clinical Medicine Insights: Gastroenterology, 2014, 7: CGast. S14039.
ARAN, Veronica, et al. Colorectal cancer: epidemiology, disease mechanisms and interventions to reduce onset and mortality. Clinical colorectal cancer, 2016, 15.3: 195-203.
WILKINS, Thad; MCMECHAN, Danielle; TALUKDER, Asif. Colorectal cancer screening and prevention. American family physician, 2018, 97.10: 658-665.