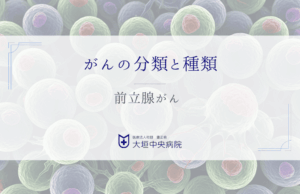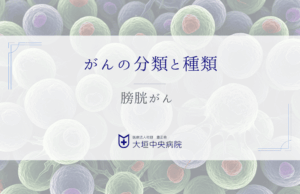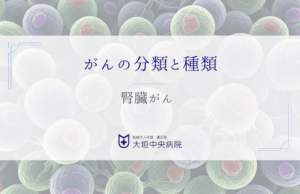精巣がんは、他のがんと比較して20代から30代の若い男性に多く見られるという特徴があります。
しかし、このがんは早期に発見し、適切な治療を行えば、非常に高い確率で治癒を目指せる「治るがん」の代表格です。
この記事では、精巣がんの基本的な知識から、自分でできるセルフチェックの方法、具体的な治療法、そして治療後の生活に至るまで、がんと向き合う患者さんやご家族が抱えるであろう疑問や不安に寄り添いながら、分かりやすく解説します。
精巣がんという病気を正しく理解し、前向きに治療に取り組むための一助となれば幸いです。
精巣がんの特徴 – 20代から30代に多い理由
精巣がんは、男性の精巣(睾丸)に発生する悪性腫瘍です。他のがんが高齢者に多いのに対し、精巣がんは思春期以降の若い世代、特に20代から30代の男性に発症のピークが見られます。
罹患率は10万人に1人程度と比較的稀ながんですが、若年男性にとっては最もかかりやすい固形がんの一つであり、決して他人事ではありません。
この年代は学業、就職、結婚など人生の重要な時期と重なるため、病気への理解と適切な対応がとりわけ重要になります。
若い世代を襲うがん
精巣がんは、まさにこれから社会で活躍しようとする若い世代にとって大きな試練となり得ます。しかし、その特性を理解することで、過度に恐れる必要はないことも分かります。
20代から30代が発症のピーク
精巣がんの好発年齢は、20代後半から30代前半です。
乳幼児期と思春期、そして60歳以降にも小さなピークがありますが、AYA世代(Adolescent and Young Adult:思春期・若年成人)と呼ばれる15歳から39歳での発症が際立って多いのが特徴です。
この年代の男性が精巣の異変に気づいた場合、精巣がんの可能性を念頭に置く必要があります。
なぜ若い世代に多いのか
精巣がんの多くは「胚細胞腫瘍」に分類されます。これは、精子のもとになる「胚細胞」ががん化するものです。胚細胞は、胎児がお母さんのお腹の中にいる間に作られます。
この胎生期の細胞に異常が生じ、それが精巣内に留まっていたものが、思春期以降に男性ホルモンの影響など何らかのきっかけでがん化すると考えられています。
そのため、細胞分裂が活発な若い世代に発症が集中するのです。
精巣がんの発生部位と基本的な性質
精巣は、男性ホルモン(テストステロン)と精子を作る重要な臓器です。精巣がんは、この臓器の根幹をなす細胞から発生します。
精子を作る細胞から発生
精巣の内部は、大部分が精子を産生する精細管で満たされています。精巣がんの95%以上は、この精細管の内側にある胚細胞から発生する胚細胞腫瘍です。
そのため、治療によって妊孕性(妊娠させる能力)に影響が出ることがあり、将来の家族計画についても考える必要があります。
比較的早く進行するが治療への反応性が良い
精巣がんは、がん細胞の増殖が速く、リンパ節や肺などの他の臓器に転移しやすい性質を持っています。
しかし、その一方で、化学療法(抗がん剤治療)や放射線治療に対する感受性が非常に高く、これらの治療が劇的に効きやすいという大きな特徴があります。
たとえ発見時に転移がある進行したステージであっても、標準的な治療によって根治を目指せる可能性が高いのです。
セルフチェックで見つかる精巣がんのサイン
精巣がんは、体の表面に近い臓器に発生するため、自分で触って異常を発見できる可能性がある数少ないがんの一つです。
早期発見が、より体に負担の少ない治療につながり、高い治癒率をさらに高める鍵となります。日頃から自分の体の状態に関心を持ち、定期的なセルフチェックを習慣にすることが大切です。
自覚できる初期症状
精巣がんの最も代表的な初期症状は、精巣のしこりや腫れです。多くの場合、痛みや発熱を伴わないため、気づいても放置してしまいがちです。
「痛みなし」の「しこり」や「腫れ」に注意
精巣がんのサインとして最も多いのが、痛みを感じない硬いしこりです。精巣全体がごつごつと硬くなったり、片方の精巣が明らかに腫れて大きくなったりします。
通常、精巣は左右の大きさが完全に同じではありませんが、「以前と比べて明らかに大きくなった」「硬い塊が触れる」といった変化があれば注意が必要です。
痛みがないからといって安心せず、まずは専門医に相談してください。
精巣の硬さの変化や重い感じ
しこりや腫れ以外にも、精巣の硬さが以前と変わったり、片方の陰嚢(いんのう)にずっしりとした重みや不快感を感じたりすることもあります。
まれに、内出血を起こして急な痛みや腫れとして発症することもありますが、基本的には「痛みなし」の変化が特徴的な初期症状です。
セルフチェックの具体的な方法
月に一度で構いませんので、入浴後など皮膚が柔らかくなっているリラックスした状態で行うことをお勧めします。
両方の精巣を丁寧に触診し、普段の状態を覚えておくことが異常の早期発見につながります。
精巣の正常な状態と異常なサインの比較
以下の表を参考に、ご自身の精巣の状態を確認してみてください。
| 項目 | 正常な状態 | 注意すべきサイン |
| 硬さ | 均一で弾力がある(ゆで卵の白身程度) | 硬いしこりがある、石のように硬い |
| 大きさ | 左右で多少違うことはある | 片方だけが明らかに腫れ、大きくなっている |
| 表面 | なめらかでつるつるしている | 表面がでこぼこしている、いびつな形 |
異常を感じたらすぐに泌尿器科へ
セルフチェックで少しでも「おかしいな」と感じる点があれば、ためらわずに泌尿器科を受診してください。精巣の病気は、がん以外にも精巣上体炎や精索静脈瘤など様々です。
専門医による診察で正確な診断を受けることが重要です。受診をためらう気持ちは分かりますが、精巣がんは進行が速い場合があるため、早期の行動があなたの未来を守ります。
精巣がんの種類と腫瘍マーカーの意味
精巣がんと診断された後、治療方針を決定する上で重要になるのが、がんの「組織型(種類)」と「腫瘍マーカー」の値です。
精巣がんは、大きく分けて「セミノーマ」と「非セミノーマ」の2種類があり、それぞれ性質や治療法が異なります。腫瘍マーカーは、がんの勢いや治療効果を測るための重要な指標となります。
精巣がんの組織型分類
手術で摘出した精巣の組織を顕微鏡で詳しく調べる病理診断によって、がんのタイプを確定します。この分類が、その後の治療法を選択する上で最初の分かれ道となります。
セミノーマ(精上皮腫)
セミノーマは精巣がんの約60%を占め、比較的進行がゆっくりしているという特徴があります。放射線治療が非常によく効くタイプで、20代よりも30代から40代に多く見られます。
転移している場合でも、化学療法や放射線治療によって高い治療効果が期待できます。
非セミノー-マ(非精上皮腫)
非セミノーマは、セミノーマ以外の精巣がんの総称で、胎児性がん、卵黄嚢腫瘍、絨毛がん、奇形腫といった複数の組織型が混在していることが多くあります。
セミノーマに比べて進行が速く、転移しやすい傾向がありますが、こちらも化学療法への感受性が高く、多くのケースで治癒を目指せます。
セミノーマと非セミノーマの主な違い
| 特徴 | セミノーマ | 非セミノーマ |
| 発生頻度 | 精巣がんの約60% | 精巣がんの約40% |
| 進行速度 | 比較的ゆっくり | 速い傾向がある |
| 治療感受性 | 放射線・化学療法が著効 | 化学療法が治療の中心 |
診断と治療方針決定に役立つ腫瘍マーカー
腫瘍マーカーとは、がん細胞が作り出す特殊な物質のことで、血液検査で測定します。精巣がんは、この腫瘍マーカーが診断や治療効果の判定に非常に役立つという特徴があります。
腫瘍マーカーとは何か
がんが存在すると体内で特定の物質が増加することがあり、これを腫瘍マーカーと呼びます。精巣がんでは、AFP、hCG、LDHという3つのマーカーが重要です。
これらの値は、がんの種類を推定したり、体内にどれだけのがんがあるかを推測したり、さらには治療が効いているかどうかの判断材料として使われます。
主要な腫瘍マーカー(AFP, hCG, LDH)
これらのマーカーは、手術前の診断補助、手術後の再発モニタリング、化学療法中の効果判定など、あらゆる場面で測定します。
精巣がんの主要な腫瘍マーカー
| マーカー名 | 正常値の目安 | どのタイプで上昇しやすいか |
| AFP | 10.0 ng/mL以下 | 非セミノーマ(特に卵黄嚢腫瘍) |
| hCG | 2.5 mIU/mL未満 | セミノーマ、非セミノーマ(特に絨毛がん) |
| LDH | 124~222 IU/L | セミノーマ、非セミノーマ(腫瘍量に相関) |
純粋なセミノーマではAFPが上昇することはありません。もしAFPが高い場合は、非セミノーマの成分が混じっていると判断し、非セミノーマに準じた治療を行います。
診断から治療開始までの迅速な流れ
精巣に異常を感じて泌尿器科を受診してから、診断が確定し、治療が始まるまでの流れは非常に迅速です。
これは、精巣がんが比較的速く進行する場合があるため、時間を無駄にせず、速やかに病状を正確に把握し、最適な治療へとつなげる必要があるからです。
泌尿器科での診察と初期検査
まずは専門医による問診と身体診察から始まります。いつから、どのような症状があるのかを詳しく伝えましょう。
問診と触診
医師が精巣やその周辺を直接触って、しこりの有無、大きさ、硬さ、痛みがあるかなどを確認します。この触診は診断において非常に重要な情報となります。
超音波(エコー)検査
触診で異常が疑われた場合、次に行うのが超音波検査です。これは、精巣に超音波を当てて、その内部の様子を画像で確認する検査です。痛みはなく、体に負担もかかりません。
この検査で、しこりが精巣内部にあるのか、液体が溜まっているだけなのか、そして悪性腫瘍が疑われるか、など多くのことが分かります。
精巣がんを確定させる検査
超音波検査で精巣がんが強く疑われた場合、病気の広がり(ステージ)を調べるための検査に進みます。
血液検査による腫瘍マーカーの測定
前述したAFP、hCG、LDHといった腫瘍マーカーを血液検査で測定します。これらのマーカーの値は、診断の補助だけでなく、治療方針の決定や治療効果の判定にも重要な役割を果たします。
CT検査による転移の確認
精巣がんは、後腹膜(お腹の背中側)のリンパ節や、肺、肝臓などの遠隔臓器に転移しやすい性質があります。
そのため、胸部から骨盤部にかけてのCT検査を行い、がんが精巣以外の場所に広がっていないかを確認します。この検査結果が、病期(ステージ)を決定する上で最も重要な情報となります。
ステージ(病期)の確定
ここまでの検査結果を総合的に判断し、がんの進行度を示すステージを決定します。ステージは、その後の治療方針を決めるための最も重要な指標です。
ステージⅠ、Ⅱ、Ⅲの定義
精巣がんのステージは、主にがんの広がりによって分類されます。
- ステージI期がんが精巣内にとどまっており、転移がない状態。
- ステージII期腹部の後腹膜リンパ節に転移が見られる状態。
- ステージIII期後腹膜リンパ節を越えて、肺や肝臓、脳、骨などの遠隔臓器や、頸部・鎖骨上窩のリンパ節にまで転移が広がっている状態。
精巣がんのステージ分類(簡略版)
| ステージ | がんの広がり |
| I期 | がんは精巣内にとどまる |
| II期 | 後腹膜リンパ節に転移がある |
| III期 | 肺などの遠隔臓器に転移がある |
これらの診断がおおよそ1週間から2週間という短期間で行われ、速やかに最初の治療である手術へと進むのが一般的な流れです。
精巣がんの高い治癒率を支える治療体系
精巣がんは、たとえ進行した状態で見つかっても、確立された治療体系によって高い治癒率を誇ります。その治療の根幹をなすのが、手術、化学療法、そして放射線治療です。
これらを、がんの組織型(セミノーマか非セミノーマか)とステージ(病期)に応じて適切に組み合わせることで、最大の治療効果を目指します。
治療の基本方針
精巣がんの治療は、まず原因となっている精巣を摘出することから始まります。
その後の追加治療については、手術で得られた病理診断の結果と、CT検査などで判明したステージに基づいて慎重に決定します。
まずは高位精巣摘除術
精巣がんが疑われた場合、診断と治療を兼ねて、がんのある側の精巣を摘出する手術(高位精巣摘除術)を第一に行います。
これは、ほぼすべての精巣がん患者に対して行う標準的な初期治療です。
病理診断とステージに基づいた追加治療
手術で摘出した組織を詳しく調べ(病理診断)、がんの正確な種類を確定します。この病理結果と、CT検査で判明しているステージを基に、手術後の追加治療が必要かどうかを判断します。
ステージIであれば経過観察で済むこともありますし、ステージが進んでいれば化学療法や放射線治療を行います。
手術(高位精巣摘除術)
精巣がんの手術は、一般的な精巣の手術とは少し異なる方法で行います。
なぜこの手術方法なのか
「高位」とは、足の付け根(鼠径部)の部分を指します。皮膚を数センチ切開し、そこから精巣につながる血管や精管をまとめて縛ってから、精巣を摘出します。
陰嚢を直接切開しないのは、がん細胞が周囲に散らばってしまうリスクを避けるためです。この手術は、正確な病理診断を下すためにも重要な意味を持ちます。
手術後の体の変化について
片方の精巣を摘出しても、もう片方の精巣が正常に機能していれば、男性ホルモンの分泌や性機能(勃起・射精)に影響が出ることはほとんどありません。
外見が気になる場合は、シリコン製の人工睾丸(精巣プロステーシス)を挿入することも可能です。
ステージに応じた治療の選択
手術後の治療は、ステージによって大きく異なります。
ステージごとの主な治療法
- ステージI がんが精巣内にとどまっている初期段階です。セミノーマ、非セミノーマともに、基本的には手術のみで治療が完了し、その後は定期的な検査で再発がないかを確認する「経過観察」が中心となります。ただし、非セミノーマで再発リスクが高いと判断された場合には、予防的に化学療法を1〜2コース行うこともあります。
- ステージII 後腹膜リンパ節への転移がある状態です。セミノーマの場合は放射線治療または化学療法を、非セミノーマの場合は化学療法を行います。
- ステージIII 遠隔転移がある状態です。セミノーマ、非セミノーマともに、治療の主体は化学療法となります。複数の抗がん剤を組み合わせた多剤併用化学療法を複数回行い、全身のがん細胞を叩きます。
化学療法が効きやすい理由と治療成績
精巣がん治療の大きな特徴は、化学療法(抗がん剤治療)が非常によく効くことです。たとえ肺などに転移がある進行したステージIIIであっても、化学療法によって完治を目指すことが可能です。
この高い効果は、精巣がん細胞が持つ特有の性質と、シスプラチンという優れた抗がん剤の登場によってもたらされました。
精巣がん細胞の特性
なぜ精巣がんには化学療法が効きやすいのでしょうか。その理由は、がん細胞の成り立ちと性質にあります。
細胞分裂が活発であること
化学療法で使われる抗がん剤の多くは、細胞が分裂して増殖する際に作用して、その働きを邪魔することで効果を発揮します。精巣がんの元となる胚細胞は、もともと活発に分裂・増殖する能力を持っています。
その性質を受け継いだ精巣がん細胞もまた分裂スピードが速いため、抗がん剤の格好の標的となるのです。
プラチナ製剤(シスプラチン)への高い感受性
1970年代に登場した「シスプラチン」というプラチナを含む抗がん剤が、精巣がんの治療成績を劇的に向上させました。
精巣がん細胞は、このシスプラチンに対して特に感受性が高く、DNAの複製を強力に阻害されて死滅しやすいという性質を持っています。
シスプラチンを中心とした多剤併用療法の確立が、精巣がんを「治るがん」へと変えた最大の要因と言えます。
標準的な化学療法
現在、世界の標準治療として確立されているのが、3種類の抗がん剤を組み合わせるBEP療法です。
BEP療法(ブレオマイシン、エトポシド、シスプラチン)
BEP療法は、ブレオマイシン(B)、エトポシド(E)、シスプラチン(P)の3剤を組み合わせた治療法です。通常、3週間を1クールとして、これを3~4クール繰り返します。
転移がある精巣がんの治療の基本であり、この治療によって多くの患者さんが治癒に至ります。
BEP療法の概要
| 薬剤名 | 主な役割 | 注意すべき副作用 |
| シスプラチン | がん細胞のDNAを破壊する | 吐き気・嘔吐、腎機能障害、聴力低下、しびれ |
| エトポシド | 細胞分裂を阻害する | 骨髄抑制(白血球減少など)、脱毛、吐き気 |
| ブレオマイシン | がん細胞の増殖を抑制する | 間質性肺炎・肺線維症、発熱、皮膚症状 |
治療成績と治癒率
確立された化学療法により、精巣がん全体の5年生存率は95%を超えています。これは、すべてのがんの中でも極めて高い数値です。
転移があっても治癒を目指せる
最も重要な点は、転移がある進行がんであっても、治癒を十分に目指せることです。
ステージIIやステージIIIの患者さんでも、標準的な化学療法を受けることで、70~80%以上の確率で治癒が期待できます。
これは、他のがんではなかなか見られない、精巣がん治療の大きな希望です。
ステージ別の5年生存率
ステージごとの5年生存率は以下のようになっており、早期であるほど治癒率はさらに高くなります。
| ステージ | 5年生存率の目安 |
| I期 | ほぼ100% |
| II期 | 約95% |
| III期 | 約70-80% |
この優れた治療成績こそが、精巣がんが「治る可能性の高いがん」と呼ばれる所以です。
治療後の経過観察と再発リスクの管理
精巣がんの初期治療が無事に終了しても、それで終わりではありません。治療後の「経過観察」は、完治を目指す上で治療そのものと同じくらい重要です。
経過観察の主な目的は、万が一再発した場合でも、できるだけ早い段階で発見し、迅速に次の治療を開始することにあります。
再発は治療終了後2年以内に起こることが多いため、この期間は特に注意深いフォローアップが必要です。
定期的な検査の重要性
治療後の生活に戻ると、つい病院から足が遠のいてしまうこともあるかもしれません。しかし、決められたスケジュールに沿って定期的に検査を受けることが、長期的な安心につながります。
再発の早期発見が目標
精巣がんの再発は、血液中の腫瘍マーカーの上昇や、CT画像での新たな転移巣の出現によって見つかることがほとんどです。
自覚症状が出てからでは、病気が進行してしまっている可能性があります。症状がないうちから定期的に検査を行うことで、再発を早期に捉え、より効果的な治療につなげることができます。
検査のスケジュールと内容
経過観察のスケジュールは、がんの組織型(セミノーマか非セミノーマか)や最初のステージによって異なります。
一般的には、問診、身体診察、腫瘍マーカーを調べる血液検査、そして胸部から骨盤部までのCT検査を組み合わせて行います。
経過観察の一般的なスケジュール例(セミノーマ ステージI)
| 期間 | 診察・腫瘍マーカー | CT検査 |
| 治療後1-2年目 | 3-6ヶ月ごと | 6-12ヶ月ごと |
| 治療後3-5年目 | 6-12ヶ月ごと | 1-2年ごと |
| 治療後6年目以降 | 年1回 | 必要に応じて |
このスケジュールはあくまで一例であり、個々の患者さんの状態に応じて主治医が判断します。
治療後5年を過ぎると再発のリスクは大幅に減少しますが、10年以上の長期的なフォローアップが推奨されています。
再発した場合の治療
万が一、経過観察中に再発が見つかった場合でも、治療の選択肢は残されています。精巣がんは、再発した場合でも根治を目指せる可能性があるがんです。
再発部位と状況に応じた治療選択
再発が見つかった場合、その部位や広がり、過去の治療内容などを考慮して、次の治療方針を決定します。
初回治療で化学療法を行っていなかった場合は、まず標準的な化学療法(BEP療法など)を行います。
救済化学療法や大量化学療法
すでに標準的な化学療法を受けた後に再発した場合には、「救済化学療法」と呼ばれる、初回とは異なる種類の抗がん剤を使った治療を行います。
それでも効果が不十分な場合には、より強力な「大量化学療法」と「自家末梢血幹細胞移植」を組み合わせた治療を行うこともあります。
これは、体に大きな負担がかかる治療ですが、難治性の再発精巣がんに対する有効な治療法の一つです。
妊孕性温存 – 将来の家族計画のために
精巣がんは20代、30代という、これから結婚や子育てを考える年代の男性に多いがんです。
そのため、がんの治療と同時に、将来子どもを持つ可能性(妊孕性)をいかにして守るかという問題に直面します。
治療を開始する前に、妊孕性温存について主治医とよく話し合い、正しい情報を得ておくことが非常に重要です。
治療が妊孕性に与える影響
精巣がんの治療は、妊孕性に様々な影響を与える可能性があります。
化学療法や放射線治療による影響
精子を作る機能(造精機能)は、化学療法や放射線治療によってダメージを受けやすいです。特に複数の抗がん剤を使用する化学療法では、一時的あるいは永久的に精子が作られなくなる可能性があります。
また、後腹膜リンパ節への放射線治療は、精子を作る細胞に影響を与えることがあります。
手術そのものの影響は少ない
片方の精巣を摘出する手術(高位精巣摘除術)だけでは、もう片方の精巣が正常であれば、妊孕性に大きな影響はありません。
ただし、もともと精巣がんの患者さんは、がんでない方の精巣の機能も低下している場合があることが知られています。
精子凍結保存(Sperm Banking)
将来子どもを持つことを望む場合、最も確実な妊孕性温存の方法が、治療開始前の精子凍結保存です。
治療開始前に行うことが重要
化学療法や放射線治療が始まってしまうと、精子の質が低下したり、精子自体が作られなくなったりする可能性があります。
そのため、精子凍結保存は、必ず初回の治療(手術や化学療法)が始まる前に行う必要があります。診断がついたら、できるだけ早く主治医に相談し、精子凍結保存を希望する旨を伝えましょう。
誰が対象になるのか
将来、子どもを持つことを希望するすべての精巣がん患者さんが対象となります。パートナーの有無にかかわらず、また未成年であっても、本人の意思と保護者の同意があれば可能です。
凍結保存の手順と費用
通常、医療機関でマスターベーションにより精液を採取し、特殊な処理を施した後に、マイナス196℃の液体窒素の中で半永久的に保存します。
精子凍結保存は公的医療保険が適用されない自費診療となりますが、自治体によっては助成金制度を設けている場合があります。
治療後の妊孕性の回復
化学療法を受けた後でも、造精機能が回復する可能性はあります。
回復の可能性と期間
化学療法の種類や量にもよりますが、治療終了後、約2~3年で造精機能が回復し始め、5年程度で多くの人が回復すると報告されています。
ただし、回復の程度には個人差が大きく、完全には元に戻らない場合もあります。そのため、やはり治療前の精子凍結保存が最も確実な選択肢となります。
パートナーとの話し合いの重要性
妊孕性の問題は、患者さん一人だけでなく、パートナーにとっても非常に重要な問題です。将来の家族計画について、二人でよく話し合い、お互いの気持ちを理解し合った上で、妊孕性温存の方法について決めていくことが大切です。
精巣がん克服後の社会復帰とフォローアップ
精巣がんの治療を乗り越えた後、多くの人が元の日常生活や社会生活へと戻っていきます。
しかし、がんという大きな病気を経験したことで、身体的な変化や心理的な課題、そして長期的な健康管理といった新たな側面に目を向ける必要が出てきます。
これらは「サバイバーシップ」と呼ばれ、がん治療後をより良く生きるための重要なテーマです。
身体的な変化への対応
治療によってもたらされる身体的な変化と、どう向き合っていくかを考えます。
精巣摘出後の外見(精巣プロステーシス)
片方の精巣を摘出することによる外見上の変化を気にする方もいます。
温泉やサウナなどで他人の目が気になる、左右のバランスが悪いと感じるなどの悩みに対しては、シリコン製の人工睾丸(精巣プロステーシス)を陰嚢内に埋め込む手術を受ける選択肢があります。
これは保険適用外ですが、見た目のコンプレックスを解消する一つの方法です。
男性ホルモンの変化
片方の精巣が正常に機能していれば、男性ホルモンの分泌が低下することはまれです。
しかし、両方の精巣を摘出した場合や、もともと機能が低下していた場合には、ホルモン補充療法が必要になることがあります。倦怠感や性欲の低下などの症状があれば、主治医に相談してください。
心理的なサポートとケア
がんと診断された衝撃、治療のつらさ、そして再発への不安は、心に大きな負担をかけます。
治療後の不安や悩みの共有
治療が終わっても、「またがんになるのではないか」という不安はすぐには消えません。
こうした気持ちを一人で抱え込まず、家族や友人、主治医や看護師、あるいは同じ経験をした患者会の仲間など、信頼できる人に話すことが大切です。
必要であれば、心理カウンセラーや精神科医といった専門家の助けを借りることも有効です。
がんサバイバーとしての生活
がんを克服した経験は、人生観を変えるほどの大きな出来事です。
この経験を乗り越えた自分を認め、新たな価値観を持って今後の人生を歩んでいくことが、真の意味での社会復帰につながります。
長期的な健康管理
精巣がんの治療は、数年後、数十年後に影響を及ぼす可能性があります。これを晩期合併症と呼び、生涯にわたる健康管理が重要になります。
二次がんのリスク
精巣がんの治療で用いた化学療法や放射線治療は、将来的に別のがん(二次がん)を引き起こすリスクをわずかに高める可能性があります。
特に白血病や固形がんのリスクが指摘されています。
心血管系への影響
シスプラチンを含む化学療法や胸部への放射線治療は、心臓や血管に影響を与え、将来的に心筋梗塞や高血圧などのリスクを高める可能性があります。
長期フォローアップで注意する点
- 反対側の精巣がんの発生
- 心血管疾患(高血圧、脂質異常症、糖尿病など)
- 腎機能障害
- 聴力低下
- 末梢神経障害(手足のしびれ)
これらのリスクに対応するため、定期的な健康診断を受け、禁煙やバランスの取れた食事、適度な運動といった健康的な生活習慣を心がけることが、がんを経験した後の人生を長く健康に過ごすために何よりも重要です。
よくある質問 (FAQ)
ここでは、精巣がんの患者さんやご家族からよく寄せられる質問にお答えします。
- 治療費はどのくらいかかりますか?
-
治療費は、行う治療内容(手術、化学療法、放射線治療など)や入院期間によって大きく異なります。
日本の公的医療保険制度には「高額療養費制度」があり、一個月の医療費の自己負担額が一定の上限を超えた場合、その超えた分が払い戻されます。
例えば、ステージIIIの化学療法で1ヶ月の医療費総額が100万円かかったとしても、一般的な所得の方であれば自己負担は9万円程度に収まります。
事前に「限度額適用認定証」を申請しておくと、窓口での支払いを自己負担限度額までに抑えることができます。詳しくは、病院の相談窓口やソーシャルワーカーにお尋ねください。
治療に関わる主な費用(目安)
項目 費用の目安(3割負担) 備考 高位精巣摘除術 10~15万円程度 入院日数や病院により変動します BEP療法(1クール) 15~25万円程度 高額療養費制度の対象となります 精子凍結保存 3~5万円(初回)+年間保管料 自費診療です。自治体の助成金を確認しましょう - 治療中、仕事や学校は続けられますか?
-
治療内容によります。高位精巣摘除術のみであれば、術後1~2週間程度の安静で、デスクワークなどであれば復帰が可能です。
しかし、化学療法を行う場合は、入院治療が必要となり、副作用(吐き気、倦怠感、白血球減少による感染リスクなど)もあるため、治療期間中は休職や休学をするのが一般的です。
体力や体調の回復には個人差がありますので、復帰のタイミングは主治医や職場の産業医、学校関係者とよく相談して決めることが大切です。
- 片方の精巣を摘出しても男性機能に問題はありませんか?
-
はい、ほとんどの場合、問題ありません。
もう片方の精巣が正常に機能していれば、男性ホルモン(テストステロン)の分泌は維持されるため、性欲がなくなったり、勃起障害(ED)が起きたりすることは基本的にありません。
射精機能も保たれます。ただし、後腹膜リンパ節郭清術という大きな手術を受けた場合には、射精障害が起こることがあります。
ご自身の治療が性機能にどのような影響を与える可能性があるか、事前に主治医に確認しておきましょう。
精巣がんと同様に、泌尿器科が専門とするがんの一つに「腎臓がん」があります。精巣がんが若年層に多いのに対し、腎臓がんは40代後半から70代の中高年層に多く見られます。
腎臓がんは、精巣がんと異なり、初期症状がほとんどなく、健康診断や人間ドックの腹部超音波検査などで偶然発見されるケースが多いのが特徴です。
がんは種類によって好発年齢や症状、発見のきっかけが大きく異なります。ご自身やご家族の年代に合わせて、注意すべきがんについて知っておくことは、健康を守る上で非常に重要です。
腎臓がんについて関心を持たれた方は、ぜひこちらの腎臓がんの解説記事もご覧になり、理解を深めてください。
以上
参考文献
CHOVANEC, M., et al. Long-term toxicity of cisplatin in germ-cell tumor survivors. Annals of Oncology, 2017, 28.11: 2670-2679.
FUNG, Chunkit, et al. Toxicities associated with cisplatin‐based chemotherapy and radiotherapy in long‐term testicular cancer survivors. Advances in urology, 2018, 2018.1: 8671832.
WONG, Jordan, et al. Long term toxicity of intracranial germ cell tumor treatment in adolescents and young adults. Journal of neuro-oncology, 2020, 149.3: 523-532.
TRAVIS, Lois B., et al. Adolescent and young adult germ cell tumors: epidemiology, genomics, treatment, and survivorship. Journal of Clinical Oncology, 2024, 42.6: 696-706.
CHOVANEC, Michal, et al. Late adverse effects and quality of life in survivors of testicular germ cell tumour. Nature Reviews Urology, 2021, 18.4: 227-245.
GIL, Thierry, et al. Testicular germ cell tumor: short and long-term side effects of treatment among survivors. Molecular and Clinical Oncology, 2016, 5.3: 258-264.
SHREM, Noa Shani, et al. Testicular cancer survivorship: long-term toxicity and management. Canadian Urological Association Journal, 2022, 16.8: 257.
SHAH, Rachana, et al. Is carboplatin-based chemotherapy as effective as cisplatin-based chemotherapy in the treatment of advanced-stage dysgerminoma in children, adolescents and young adults?. Gynecologic oncology, 2018, 150.2: 253-260.
STEIN, Kevin. The long term effects of cancer and cancer treatment: Research at the american cancer society. In: VI European Conference on Cured and Chronic Cancer Patients; Edisciences: Siracusa, Italy. 2016. p. 81.
FRAZIER, A. Lindsay, et al. Comparison of carboplatin versus cisplatin in the treatment of paediatric extracranial malignant germ cell tumours: a report of the Malignant Germ Cell International Consortium. European Journal of Cancer, 2018, 98: 30-37.
泌尿生殖器系がんに戻る