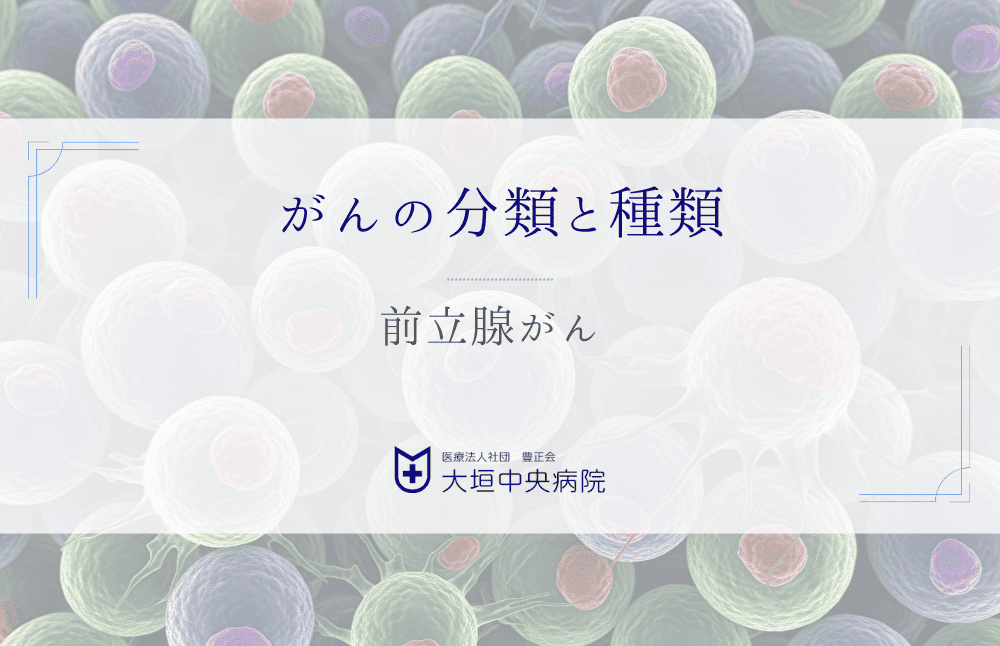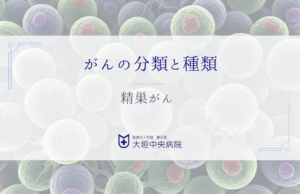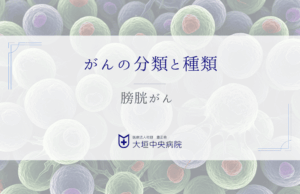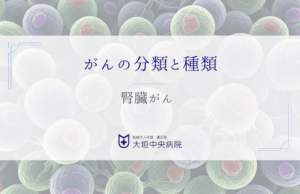50歳を過ぎた男性にとって、前立腺がんは決して他人事ではありません。日本の男性がかかるがんの中で最も罹患数が多く、その数は年々増加傾向にあります。
しかし、前立腺がんは早期に発見し、適切な対応をすれば、良好な経過を期待できるがんの一つです。
この記事では、前立腺がんが増えている背景から、早期発見の鍵となるPSA検査、進行度の見極め方、そして多様な治療の選択肢まで、皆さんが知っておくべき情報を網羅的に解説します。
前立腺がんはなぜ増えているのか – 高齢化社会との関係
近年、日本人男性の間で前立腺がんの診断を受ける人が著しく増えています。これは単に医療が進歩したからだけではなく、私たちの社会構造やライフスタイルの変化が深く関わっています。
その背景を理解することは、前立腺がんという病気と向き合う第一歩となります。
日本人男性における罹患率の増加
かつて欧米に比べて少ないとされていた日本の前立腺がんですが、現在では男性がかかるがんの中で最も多い部位となりました。
この急激な増加は、これから解説する高齢化と食生活の変化が大きく影響していると考えられています。
主な原因とリスク因子
前立腺がんの発生には、複数の要因が関わっていることが分かっています。明確な原因は特定されていませんが、いくつかの重要なリスク因子が指摘されています。
年齢と前立腺がんの関係
前立腺がんの最大のリスク因子は加齢です。50歳を過ぎた頃から罹患率が上昇し始め、高齢になるほどそのリスクは高まります。
高齢化が進む日本社会において、前立腺がんの患者数が増加するのは、ある意味で自然な現象ともいえます。
年代別の前立腺がん罹患リスク(人口10万人あたり)
| 年代 | 罹患率 |
| 40代 | 稀 |
| 50代 | 上昇し始める |
| 60代以降 | 急速に上昇 |
食生活の変化がもたらす影響
食生活の欧米化、特に動物性脂肪の摂取量増加が、前立腺がんのリスクを高める可能性が指摘されています。
脂肪分の多い食事がホルモンバランスに影響を与え、がんの発生や進行に関与するという説です。
このほか、家族歴も重要なリスク因子であり、近親者に前立腺がんの患者さんがいる場合、発症リスクが高まることが知られています。
PSA検査が変えた前立腺がんの早期発見
前立腺がんの治療成績が向上した背景には、PSA検査の普及があります。この簡単な血液検査によって、自覚症状が現れる前の非常に早い段階でがんの可能性を発見できるようになりました。
早期発見が、その後の治療選択の幅を広げ、良好な経過につながる鍵となります。
PSA検査とは何か
PSA(Prostate Specific Antigen:前立腺特異抗原)は、前立腺の腺細胞で作られるタンパク質で、主に精液中に分泌されます。
ごく微量が血液中にも存在し、その血中濃度を測定するのがPSA検査です。
前立腺がん細胞は正常な細胞よりも多くのPSAを産生するため、がんが存在すると血液中のPSA値が上昇する傾向があります。
PSA値が示すこと
PSA値は前立腺がんを発見するための重要な指標ですが、「PSA値が高い=前立腺がん」と直結するわけではありません。
前立腺肥大症や前立腺炎といった、がん以外の病気でもPSA値は上昇することがあります。そのため、検査結果の解釈には専門的な判断が必要です。
PSA値の基準値と対応の目安
| PSA値 (ng/mL) | 一般的な解釈 | 推奨される対応 |
| 0~4.0 | 基準値内 | 定期的な検診を継続 |
| 4.1~10.0 | グレーゾーン | 精密検査(生検など)を検討 |
| 10.1以上 | がんの疑いが強い | 速やかな精密検査が必要 |
※年齢によって基準値が異なる場合があります。
検査を受けるべきタイミングと頻度
一般的に、50歳になったら一度はPSA検査を受けることを推奨します。検査結果に問題がなければ、その後は1年から数年ごとの定期的な検査が望ましいでしょう。
ただし、近親者に前立腺がんの患者さんがいるなど、リスクが高いと考えられる場合は、40代からの検査開始を医師と相談することも重要です。
初期症状との関連性
前立腺がんの大きな特徴の一つに、初期の段階では自覚できる症状がほとんどないことが挙げられます。
排尿困難や頻尿といった症状が現れることもありますが、これらは加齢に伴う前立腺肥大症でも見られるため、がん特有の初期症状とは言えません。
症状がないから大丈夫と考えるのではなく、症状のない段階でPSA検査を受けることこそが、早期発見のために極めて重要です。
前立腺がんの進行速度と悪性度の見極め方
PSA検査でがんの疑いが生じ、その後の精密検査で前立腺がんと診断された場合、次に重要になるのは「がんがどのくらい広がっているか(ステージ)」と「がんの性質がおとなしいか、悪性度が高いか(グリソンスコア)」を正確に評価することです。
これらは治療方針を決定する上で最も重要な情報となります。
がんの進行度を示す「ステージ(病期)」
がんの広がり具合を示すステージは、がんが前立腺内にとどまっているか、周囲の組織や他の臓器にまで及んでいるかを示します。国際的な分類法である「TNM分類」を用いて評価します。
T分類(がんの広がり)
T分類は、がんが前立腺の中でどの程度広がっているかを示します。
がんが前立腺の被膜内にとどまっているか(T1, T2)、被膜を越えて周囲に広がっているか(T3)、膀胱や直腸などの隣接臓器に及んでいるか(T4)で分類します。
N分類(リンパ節転移)とM分類(遠隔転移)
N分類は骨盤内のリンパ節への転移の有無、M分類は骨や肺など、前立腺から離れた臓器への転移(遠隔転移)の有無を示します。
転移がある場合は、進行がんとして全身的な治療を検討する必要があります。
ステージ分類の概要
| ステージ | T分類 | N分類(リンパ節転移) | M分類(遠隔転移) |
| I, II | T1-T2 | なし | なし |
| III | T3 | なし | なし |
| IV | T4または転移あり | あり | あり |
がんの悪性度を測る「グリソンスコア」
グリソンスコアは、生検で採取した組織を顕微鏡で観察し、がん細胞の顔つき(組織学的異型度)を評価する指標です。
スコアは2から10までの数値で示され、数値が高いほどがんの悪性度が高く、増殖や転移をしやすい性質を持つことを意味します。
グリソンスコアと悪性度の関係
| グリソンスコア | 悪性度 | がんの性質 |
| 6以下 | 低い | おとなしく、進行がゆっくり |
| 7 | 中程度 | 注意深い経過観察または治療が必要 |
| 8~10 | 高い | 進行が速く、積極的な治療が必要 |
ステージと生存率の関係
前立腺がんの5年相対生存率は非常に高く、がん全体の中でも予後が良いとされています。
特に、がんが前立腺やその周辺に限局している段階で発見された場合の生存率はほぼ100%に近いのに対し、遠隔転移があるステージIVでは生存率が低下します。
このデータからも、いかに早期発見と、ステージや悪性度に応じた適切な治療選択が重要であるかがわかります。
【前立腺がんのステージ別5年相対生存率(目安)】 (全国がんセンター協議会等のデータより)
- ステージI〜III(転移なし):100%
- ※前立腺がんは進行が遅いため、早期発見・治療ができれば天寿を全うできる可能性が非常に高いがんです。
- ステージIV(遠隔転移あり): 約60〜70%
- ※転移があってもホルモン療法などが良く効くため、他のがんに比べて予後は比較的良好です。
生検から診断確定までのプロセスを理解する
PSA検査や直腸診、画像診断などで前立腺がんが疑われた場合、診断を確定するために前立腺生検を行います。これは、がんであるかどうかを最終的に判断するための重要な検査です。
不安を感じる方も多いと思いますが、どのような検査なのかを事前に理解しておくことで、落ち着いて臨むことができます。
前立腺生検が必要になるケース
PSA値が基準値を超えていたり、継続して上昇傾向にあったりする場合、あるいは直腸診でしこりを触れたり、MRI検査でがんを疑う所見が見られたりした場合に、生検を勧めます。
医師がこれらの情報を総合的に判断し、生検の必要性を決定します。
生検の具体的な方法
前立天生検は、細い針を使って前立腺の組織を複数箇所から採取する検査です。多くの場合、肛門から超音波(エコー)の器具を挿入し、前立腺の様子をモニターで確認しながら、狙いを定めて組織を採取します。
局所麻酔を行うため、強い痛みを感じることは少ないですが、検査後には一時的に血尿や血便が出ることがあります。
- 採取 前立腺の組織を10~20ヶ所程度採取
- 麻酔 局所麻酔または腰椎麻酔
- 時間 15分~30分程度
生検でわかること
採取した組織は病理医が顕微鏡で詳細に調べ、がん細胞の有無を判定します。がん細胞が見つかった場合には、その悪性度を示すグリソンスコアもこの時点で確定します。
生検は、前立腺がんの診断を確定させるためのゴールドスタンダード(最も信頼性の高い基準)となる検査です。
診断確定後の追加検査
生検でがんと診断された後は、がんの広がり(ステージ)を正確に把握するために、追加の画像検査を行うことが一般的です。
CT検査でリンパ節への転移を、骨シンチグラフィやMRI検査で骨への転移がないかを調べます。これらの検査結果とグリソンスコアを総合して、個々の患者さんに合った治療方針を立てていきます。
前立腺がんの治療選択 – 監視療法から手術・放射線まで
前立腺がんの治療法は一つではありません。がんの進行度や悪性度、患者さんの年齢や健康状態、そしてご自身の価値観やライフプランを考慮して、多様な選択肢の中から最も適した治療法を選んでいきます。
医師と十分に話し合い、納得のいく決定をすることが重要です。
治療方針を決める3つの要素
治療方針は、主に以下の3つの情報を基に総合的に判断します。
- がんの状態 ステージとグリソンスコア
- 患者さんの状態 年齢、合併症の有無、全身の健康状態
- 患者さんの希望 治療による体への負担や副作用、生活への影響に関する考え方
監視療法(アクティブサーベイランス)
発見されたがんが、グリソンスコアが6以下と悪性度が低く、ごく初期の段階である場合、すぐに積極的な治療を行わずに厳重な経過観察を行う「監視療法」という選択肢があります。
前立腺がんは進行がゆっくりなタイプも多いため、治療による副作用のリスクを避け、QOL(生活の質)を維持することを優先する方法です。
定期的にPSA検査や生検を行い、がんが進行する兆候が見られた時点で治療を開始します。
根治を目指す治療法
がんが前立腺内にとどまっている場合、根治を目指す治療として主に手術と放射線治療があります。どちらも高い治療効果が期待できますが、体への影響や副作用の現れ方に違いがあります。
手術(前立腺全摘除術)
がんを含んだ前立腺を精嚢と一緒にすべて摘出する治療法です。近年では、お腹に数カ所の小さな穴を開けて行うロボット支援手術が主流となっています。
カメラで患部を拡大して詳細に観察しながら、人間の手よりも精密な動きが可能なロボットアームを操作して手術を行います。
従来の開腹手術に比べて傷が小さく、出血量が少ない、術後の回復が早いといった利点があります。
放射線治療
高エネルギーのX線をがん細胞に照射して破壊する治療法です。
体の外から放射線を照射する「外部照射」と、放射線を放出する小さな線源を前立腺内に埋め込む「組織内照射(ブラキセラピー)」があります。
手術と同様に高い根治効果が期待でき、体を傷つけずに治療できるのが大きな利点です。
主な根治治療法の比較
| 治療法 | 対象となるがん | メリット | デメリット・副作用 |
| ロボット支援手術 | 限局がん | がんを物理的に摘出できる、術後の回復が早い | 尿失禁、性機能障害のリスク、麻酔のリスク |
| 放射線治療 | 限局がん、局所進行がん | 体への負担が少ない、入院期間が短い | 排尿・排便障害、性機能障害、二次がんのリスク |
| 監視療法 | 超早期・低リスクがん | 治療の副作用がない、QOLを維持できる | 定期検査が必要、がん進行への不安 |
治療による生活への影響と対処法
前立腺がんの治療は、がんを克服する上で非常に重要ですが、同時に生活の質(QOL)に影響を与える可能性のある副作用や後遺症を伴うことがあります。
どのような影響が起こりうるのかを事前に理解し、適切な対処法を知っておくことで、治療後の生活への不安を和らげることができます。
手術後の主な合併症
前立腺全摘除術で最も代表的な合併症が、尿失禁と性機能障害(ED)です。
これらは前立腺の近くにある尿道を締める筋肉(尿道括約筋)や、勃起に関わる神経が手術操作によってダメージを受けることで生じます。
尿失禁への対策
術後、多くの方で一時的に尿意を感じにくくなったり、くしゃみや咳などでお腹に力が入った際に尿が漏れたりする「腹圧性尿失禁」が起こります。
多くの場合、時間の経過とともに改善しますが、回復を早めるために骨盤底筋を鍛える体操が有効です。尿漏れパッドを使用することで、日常生活への影響を最小限に抑えることもできます。
- 骨盤底筋体操 肛門や尿道を意識的に締める・緩める運動を繰り返す
- 生活習慣 体重管理や便秘の解消も効果的
- 補助具 尿漏れパッドや専用下着の活用
性機能障害(ED)への向き合い方
勃起に関わる神経を温存する手術を行っても、性機能が完全に元通りになるまでには時間がかかったり、回復が難しかったりする場合があります。
これは非常にデリケートな問題であり、ご本人だけでなくパートナーの理解と協力も重要になります。現在では、内服薬による治療など、性機能の回復を助けるための様々な方法があります。
主治医や専門医に相談することが大切です。
放射線治療に伴う影響
放射線治療では、照射された放射線が前立腺だけでなく、隣接する膀胱や直腸にも影響を与えることがあります。
治療中や治療直後には、頻尿や排尿時痛、排便回数の増加や下痢といった急性期の副作用が見られることがありますが、これらは時間とともに軽快することがほとんどです。
まれに、治療後数ヶ月から数年経ってから、血尿や血便といった晩期の副作用が起こることもあります。
ホルモン療法が果たす役割と適応
ホルモン療法は、前立腺がんの治療において非常に重要な役割を担う薬物療法です。
手術や放射線治療のようにがんを直接取り除いたり叩いたりするのではなく、がんの成長を促す「エサ」を断つことで、がんの勢いを抑え、進行を遅らせることを目的とします。
ホルモン療法の仕組み
前立腺がんの多くは、男性ホルモン(アンドロゲン)を栄養源として増殖する性質を持っています。ホルモン療法は、この男性ホルモンの分泌や働きを抑えることで、がん細胞の増殖を抑制する治療法です。
注射薬や内服薬を用いて、体内の男性ホルモン濃度を去勢レベル(精巣を摘出したのと同程度の低いレベル)にまで低下させます。
ホルモン療法の適応となるケース
ホルモン療法は、主に以下のような状況で選択されます。
- 進行・転移がん骨やリンパ節など、前立腺から離れた場所に転移がある場合、全身に効果が及ぶホルモン療法が治療の中心となります。
- 局所進行がんがんが前立腺の被膜を越えて広がっている場合に、放射線治療と組み合わせて治療効果を高める目的で使用します。
- 再発した場合手術や放射線治療の後に再発(PSA再発)した場合にもホルモン療法を行います。
- 高齢や合併症高齢であったり、他の病気を持っていたりするために、手術や放射線治療といった体への負担が大きい治療が難しい場合の選択肢となります。
治療の副作用と長期的な管理
男性ホルモンを抑制するため、ホルモン療法には特有の副作用が現れます。
副作用の出方には個人差がありますが、どのようなものが起こりうるかを知り、適切に対処していくことがQOLの維持に繋がります。
ホルモン療法の主な副作用と対策
| 副作用の種類 | 主な症状 | 主な対策 |
| ホットフラッシュ | 顔のほてり、のぼせ、発汗 | 衣類の調整、漢方薬、一部の抗うつ薬 |
| 性機能関連 | 性欲低下、勃起障害(ED) | パートナーとの対話、カウンセリング |
| 骨への影響 | 骨密度の低下、骨粗しょう症、骨折リスク増 | 定期的な骨密度検査、ビタミンD・カルシウム摂取、運動 |
| その他 | 筋肉量の減少、体重増加、女性化乳房、倦怠感 | 定期的な運動、バランスの取れた食事、精神的ケア |
これらの副作用と上手く付き合いながら治療を継続していくことが大切です。気になる症状があれば、遠慮せずに主治医や看護師に相談しましょう。
前立腺がん治療後のQOL維持のポイント
前立腺がんの治療を乗り越えた後、多くの人が直面するのが「いかにして自分らしい生活を取り戻し、維持していくか」という課題です。
治療による身体的な変化だけでなく、精神的な側面も含めて、総合的にQOL(生活の質)を高めていく視点が重要になります。
再発への備えと精神的ケア
治療後、多くの方が「再発」に対する不安を抱えます。この不安と上手に付き合っていくためには、定期検査をきちんと受けて自分の体の状態を客観的に把握することが第一です。
また、不安を一人で抱え込まず、家族や友人、主治医に話したり、同じ経験を持つ患者会の仲間と気持ちを分かち合ったりすることも、大きな支えとなります。
食生活と運動の工夫
治療後の体力回復やQOL向上、さらには再発リスクの低減のために、バランスの取れた食事と適度な運動が推奨されます。
- 食事 特定の食品に偏るのではなく、野菜や果物を多く取り入れ、脂肪分の多い食事は控えめにするなど、バランスを意識することが大切です。
- 運動 ウォーキングや軽いジョギングなどの有酸素運動は、体力維持だけでなく、ホルモン療法による体重増加の抑制や気分のリフレッシュにも繋がります。無理のない範囲で継続しましょう。
パートナーシップと社会生活
尿失禁や性機能障害といった問題は、自信を喪失させ、パートナーとの関係に影響を与えることがあります。大切なのは、これらの変化について率直にパートナーと話し合うことです。
お互いの気持ちを理解し、支え合うことで、新たな関係性を築くことができます。また、仕事への復帰や社会活動への参加も、生活の張りを取り戻す上で重要な要素です。
必要であれば、職場の理解を得るための工夫も考えましょう。
定期検査とPSA値管理の重要性
前立腺がんの治療が終わった後も、医師との関係が終わるわけではありません。むしろ、ここからが長期的な健康管理の新たなスタートです。
治療後の経過を良好に保ち、万が一の再発を早期に発見するために、定期的な検査とPSA値の管理は極めて重要です。
治療後のPSA監視
治療後のPSA値は、がんの状態を示す最も重要なバロメーターです。
- 手術後 前立腺をすべて摘出しているため、PSA値は測定できないレベル(通常0.2 ng/mL未満)まで低下します。その後、PSA値が再び上昇してきた場合、「PSA再発」を疑い、追加の検査や治療を検討します。
- 放射線治療後 PSA値はゆっくりと時間をかけて低下します。最も低くなった値(ナディア値)から2.0 ng/mL以上の上昇が見られた場合に、再発の可能性を考えます。
検査の頻度と内容
治療後の検査スケジュールは、受けた治療法やがんのステージ、悪性度によって異なります。
一般的には、治療後2年間は3ヶ月ごと、その後5年までは半年ごと、それ以降は年1回といった頻度でPSA検査や診察を行います。必要に応じて、画像検査などを追加することもあります。
医師の指示に従い、忘れずに受診を継続することが大切です。
治療後の一般的な検査スケジュール(例)
| 期間 | 検査頻度 | 主な検査内容 |
| 治療後~2年 | 3ヶ月に1回 | 問診、PSA検査 |
| 3年~5年 | 6ヶ月に1回 | 問診、PSA検査 |
| 6年目以降 | 1年に1回 | 問診、PSA検査 |
長期的な健康管理の視点
前立腺がんの管理と同時に、全身の健康状態にも目を向けることがQOLの維持に繋がります。
特にホルモン療法を受けている場合は、骨粗しょう症やメタボリックシンドロームのリスクが高まるため、生活習慣病の予防・管理も重要です。
定期検査は、前立腺がんの再発チェックだけでなく、ご自身の総合的な健康を見直す良い機会と捉えましょう。
よくある質問
ここでは、前立腺がんに関して多くの方が抱く疑問についてお答えします。
- Q1 前立腺がんは遺伝しますか?
-
近親者(父親や兄弟)に前立腺がんの患者さんがいる場合、いない場合に比べて発症するリスクが2倍以上高くなると報告されており、遺伝的要因が関与すると考えられています。
リスクが高い方は、40代からのPSA検査を検討することをお勧めします。
- PSA値が高ければ必ずがんですか?
-
Aいいえ、必ずしもそうではありません。PSA値は前立腺肥大症や前立腺炎、加齢によっても上昇します。がんかどうかを確定させるためには、MRI検査や前立腺生検といった精密検査が必要です。
- 監視療法中にがんが進行したらどうなりますか?
-
監視療法の目的は、不要な治療を避けることにありますが、定期的な検査でがんの進行(PSA値の急な上昇や、生検結果での悪性度の上昇など)が確認された場合は、時期を逸することなく手術や放射線治療などの根治を目指す治療に切り替えます。
- ロボット支援手術は誰でも受けられますか?
-
がんが前立腺内にとどまっている限局がんの患者さんが主な対象となります。
ただし、過去に腹部の大きな手術を受けたことがある場合や、心臓や肺に重い病気がある場合は、適応とならないこともあります。
最終的には、医師が全身状態を評価して判断します。
- ホルモン療法はずっと続ける必要がありますか?
-
転移がある進行がんなどでは、基本的に治療を継続します。効果が続く限り続けますが、長期間続けると薬が効きにくくなること(去勢抵抗性)があります。
その場合は、別の種類のホルモン剤や化学療法など、次の治療法を検討します。また、放射線治療の補助療法として用いる場合は、2〜3年程度の期間限定で行うことが一般的です。
この記事では前立腺がんについて詳しく解説しましたが、男性特有のがんには「精巣がん(睾丸がん)」もあります。
精巣がんは、前立腺がんとは対照的に20代から30代の若い世代に多く見られるがんです。進行が速い一方で、早期に発見し治療すれば治癒率が非常に高いという特徴があります。
自分で触ってしこりを見つける「自己検診」が早期発見の最も有効な手段です。男性の健康を守るためには、年代に応じた異なるリスクを理解しておくことが重要です。
ご自身の、あるいはご家族の健康のために、精巣がんについても正しい知識を身につけておくことをお勧めします。
以上
参考文献
SHELKE, Abhay R.; MOHILE, Supriya G. Treating prostate cancer in elderly men: how does aging affect the outcome?. Current treatment options in oncology, 2011, 12.3: 263-275.
BECHIS, Seth K.; CARROLL, Peter R.; COOPERBERG, Matthew R. Impact of age at diagnosis on prostate cancer treatment and survival. Journal of Clinical Oncology, 2011, 29.2: 235-241.
DROZ, Jean‐Pierre, et al. Management of prostate cancer in older men: recommendations of a working group of the International Society of Geriatric Oncology. BJU international, 2010, 106.4: 462-469.
WONG, Yu-Ning, et al. Survival associated with treatment vs observation of localized prostate cancer in elderly men. Jama, 2006, 296.22: 2683-2693.
HALL, W. H., et al. The impact of age and comorbidity on survival outcomes and treatment patterns in prostate cancer. Prostate Cancer and Prostatic Diseases, 2005, 8.1: 22-30.
GOMELLA, Leonard G.; JOHANNES, James; TRABULSI, Edouard J. Current prostate cancer treatments: effect on quality of life. Urology, 2009, 73.5: S28-S35.
CLARK, Roderick; VESPRINI, Danny; NAROD, Steven A. The effect of age on prostate cancer survival. Cancers, 2022, 14.17: 4149.
ZELIADT, Steven B., et al. Why do men choose one treatment over another? A review of patient decision making for localized prostate cancer. Cancer: Interdisciplinary International Journal of the American Cancer Society, 2006, 106.9: 1865-1874.
LITWIN, Mark S.; TAN, Hung-Jui. The diagnosis and treatment of prostate cancer: a review. Jama, 2017, 317.24: 2532-2542.
TAYLOR, Lockwood G.; CANFIELD, Steven E.; DU, Xianglin L. Review of major adverse effects of androgen‐deprivation therapy in men with prostate cancer. Cancer, 2009, 115.11: 2388-2399.
泌尿生殖器系がんに戻る